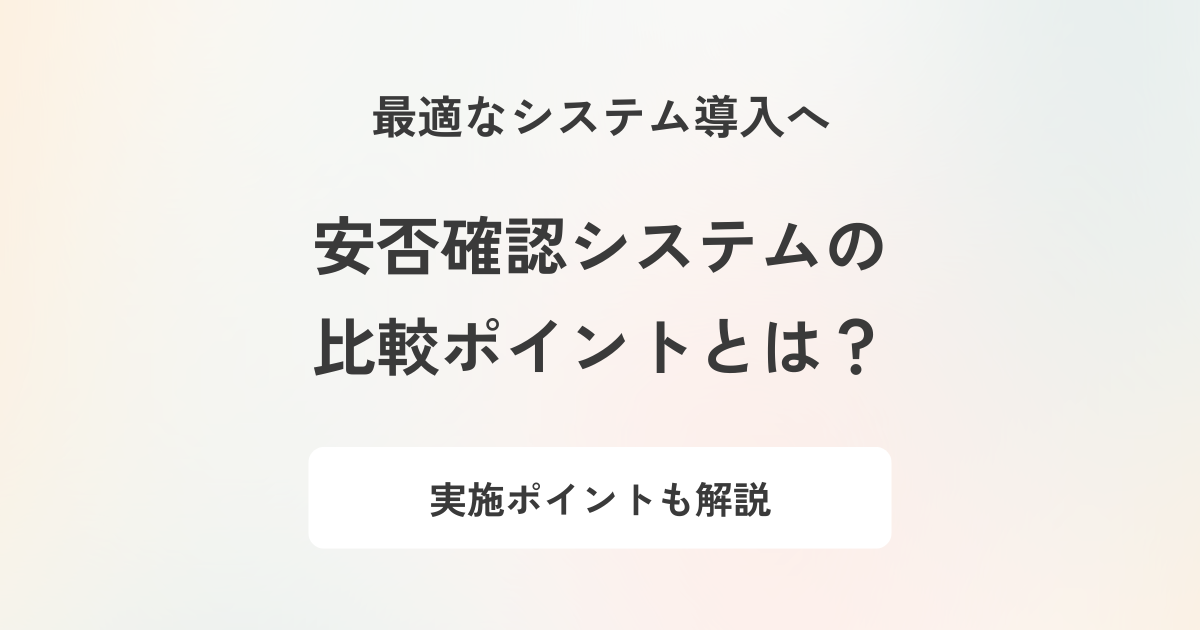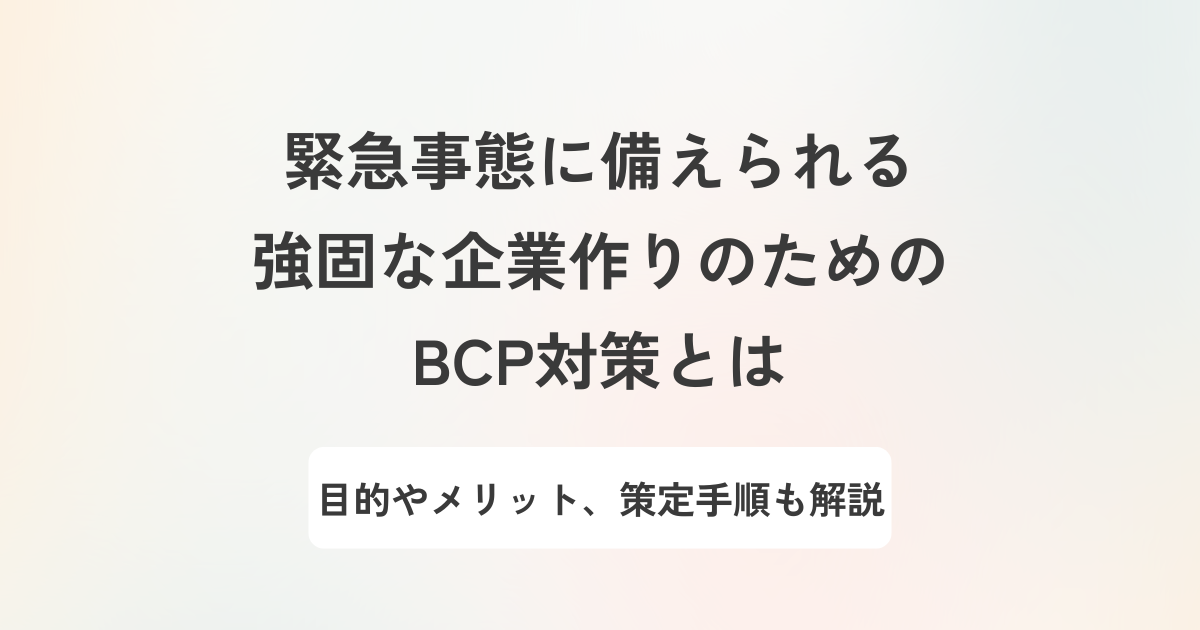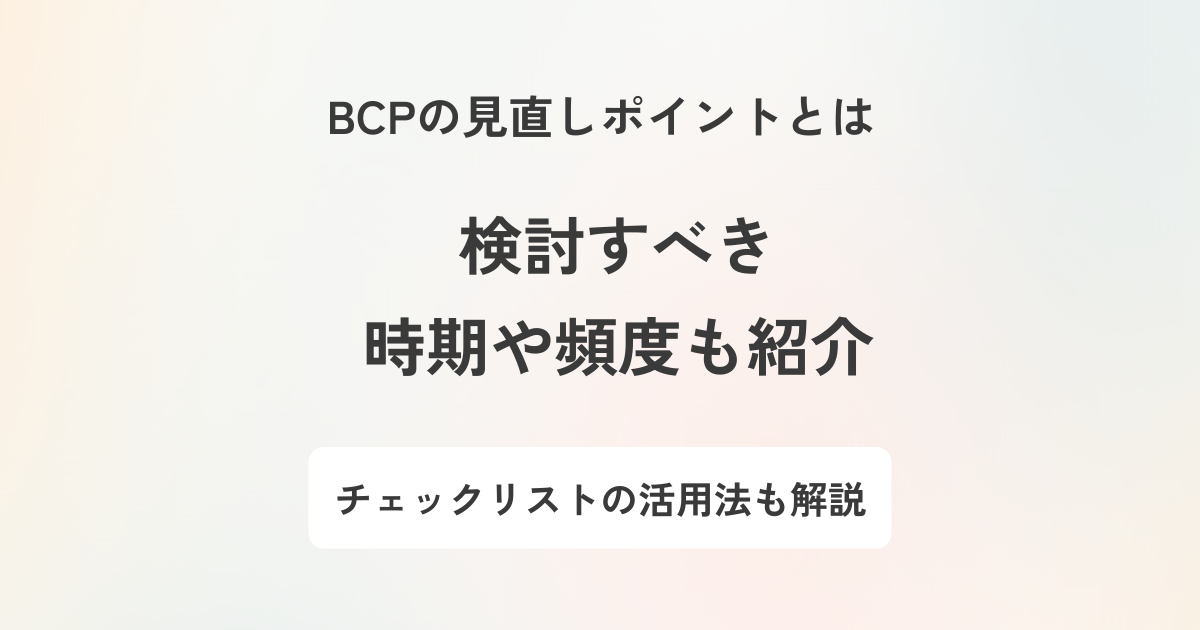緊急時でも安心!BCP備蓄品リストと準備やBCP対策のポイントを解説
大保颯大
BCP(事業継続計画)備蓄品リストとは、企業が自然災害や突発的な事故などの緊急事態が起こった場合、事業の継続性を確保し、早期に復旧させるためのものです。
備蓄品リストを作成し、備蓄品を準備しておくことで、自然災害などの緊急事態時にも企業の重要な業務の継続、早期復旧に繋がります。また、緊急時の対応をスムーズに進めることにも繋がります。
この記事では、BCPにおける備蓄品の重要性と、必要な備蓄品の種類や量について解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
BCP備蓄品の必要性
BCP(Business Continuity Planning:事業継続計画)とは、予期せぬ事態が発生した場合でも企業の事業を継続・早期復旧するための計画で、BCP対策の中でも、備蓄品は重要な役割を果たしています。
BCP備蓄品は、自然災害や突発的な事故など緊急事態が発生した場合に、従業員の安全を守ることはもちろん、業務の継続や早期復旧するために必要不可欠です。
自然災害や突発的な事故によって停電などが起こることでインフラが寸断されると、電気や水、食料などが不足する可能性があります。あらかじめ必要な物を備蓄品として用意しておくことで従業員の安全と健康を守れます。
そして、BCP備蓄品を用意することで緊急事態にもスムーズに対応でき、業務の継続、早期復旧できることにつながるのです。
東京都や関西のハンドブックでは、災害発生から3日間は応急対策期と呼ばれ、被救助者の救助・救出が優先される期間となっており、不要不急の外出は禁じられ、3日間の待機を推奨しています。
そのため、都市部の企業はBCPに「出社した従業員が3日間自社に待機する」ということを前提として組み込むべきであるとされています。
BCP備蓄品リストを作成し備蓄品を用意するメリット
BCP備蓄品リストを作成し用意することで得られる以下の3つのメリットを紹介します。
- 従業員の安全確保ができる
- 業務の継続や早期復旧ができる
- 企業としての評価がアップする
まず、従業員の安全確保ができるというメリットです。
緊急事態発生時、BCP対策によって安全に従業員が避難できる場所を確保でき、BCP備蓄品リストによって用意した食料や水、医薬品などを提供することで、従業員の健康状態を維持・サポートできます。
また、従業員の安全や健康を守ることを示せるため、従業員の企業への信頼やモチベーションがアップするメリットもあります。
次に、緊急事態時でも業務を中断させることなく、業務の継続や早期復旧ができるというメリットです。
緊急事態時には、システム停止やインフラの不足により、業務を停止させないといけなくなる可能性がありますが、BCP備蓄品を用意しておくことで、緊急事態でも用意しておいた物を使用し、業務を継続できます。また業務が停止してしまった場合にも、より速いスピードでの早期復旧を目指せるのです。
そして、企業としての評価アップというメリットも得られます。BCP対策に取り組んでいる姿勢や、緊急時に備えた準備が十分にしてあることで、従業員や取引先などからの評価、信頼が高まります。
BCP備蓄品リストによる2つのリスク軽減
BCP備蓄品リストを作成し、備蓄品を用意しておくことで軽減できる、以下の2つのリスクについても紹介します。
- 企業の倒産・業務縮小のリスクを軽減できる
- 法的責任・社会的責任の不履行のリスクを軽減できる
1つ目は企業の倒産・業務縮小のリスクの軽減です。緊急事態発生時に業務継続に必要な備蓄品が不足していれば、業務中断せざるを得ない状況になります。業務を中断してしまうと、利益の確保ができず損失が生まれることで倒産のリスクが上がったり、業務が縮小してしまったりする可能性があります。
事前にBCP備蓄品リストを作成し、業務を継続するために必要な物を用意しておくことで、企業の倒産・業務縮小のリスクを避けられるのです。
2つ目は、法的責任・社会的責任の不履行のリスクの軽減です。BCP対策や、BCP備蓄品を用意しておくことは努力義務とされていますが、緊急時に従業員の安全が確保されていなかった場合、法的責任や社会的責任を問われる可能性があります。
BCP備蓄品を作成して備蓄品を用意し、BCP対策を十分に行うことで法的責任や社会的責任を果たすことに繋がります。
BCP備蓄品リスト
ここでは、BCP備蓄品リストを作成する際に実際に必要なBCP備蓄品を紹介します。
具体的には、以下を用意しておくと良いでしょう。
- 3日分の食料と水
- 停電に備えるための電気グッズ
- 衛生用品・救急グッズ
- 情報収集グッズ
- 避難・安全グッズ
- 寝具・防寒グッズ
それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
3日分の食料と水
東京や関西の帰宅困難者ガイドブックに記載されているように、災害発生から3日間は「応急対策期」と呼ばれています。
応急対策期は、被救助者の救助・救出が優先される期間となっており、不要不急の外出が禁じられるため従業員は帰宅できません。
企業は施設内で従業員が安全に生活し、業務を遂行できるようにするため、応急対策期である3日間分の備蓄品を企業に留まる人数分で計算し用意する必要があります。
食料は1人あたり1日3食必要で、3日分で計9食となります。
緊急時は水道やガス、電気が止まることを想定して調理不要な食料を用意しましょう。
具体的には、以下がおすすめです。
- アルファ化米
- 缶詰パン
- 缶詰おかず
- レトルト食品
- クラッカー
- カップ麺 など
栄養に偏りが出ないよう、缶詰はおかずとして有用です。
上記の食料を、全部で9食×人数分用意する必要があります。
水は1人あたり1日3リットル必要で、3日分では計9リットルとなります。断水に備えて水の用意が必要です。
水を用意する際は、ペットボトル入りの飲料水が一般的で、通常の消費期限は2年程度となっています。備蓄向けのミネラルウォーターには、消費期限が5〜10年のものもあります。
全部で、9リットル×人数分の用意が必要です。
(参考:東京都帰宅困難者対策ハンドブック)
停電に備えるための電気グッズ
緊急時は長時間の停電になる可能性もあるため、生活や業務遂行に必要な電気グッズを用意しましょう。
インバーターエンジンガス発電機+以下を用意するのがおすすめです。
- 無停電電源装置(UPS)
- ポータブル電源(バッテリー式発電機)
無停電電源装置とは、停電や瞬時電圧低下などの電源障害が発生した際に、蓄電しておいたエネルギーを使って機器に電力を供給し続ける装置です。
無停電電源装置により、サーバーや業務PCを守れ、停電時などに瞬時に切り替わるため、データの破損を防げます。
内蔵バッテリーに電気を蓄えておき、外部の電気機器に給電できる持ち運び可能なバッテリーであるポータブル電源(バッテリー式発電機)は、ノートPCや通信機器の電力確保が可能です。
また、スマートフォンや業務PCの充電切れを防ぐため、1人1台モバイルバッテリーを用意しておくこともおすすめです。
衛生用品・救急グッズ
3日間でも、緊急時に待機する従業員が施設内で過ごせるようなオフィス環境を維持するためには、簡易トイレや簡易浴槽、歯ブラシ、生理用品などの衛生用品も必要不可欠です。
救急グッズは、以下を用意しましょう。
- 絆創膏
- 消毒液
- 包帯
- 体温計
- マスク
- 使い捨て手袋 など
医薬品も人によっては必要なため、常備薬として用意しておくことがおすすめです。鎮痛剤は頭痛・発熱時に、抗菌薬は切り傷や擦り傷の感染予防に使用します。
情報収集グッズ
緊急事態時には、正しい情報を素早く収集することが大切です。
取引先との連絡、連携、伝達、また災害や事故の発生場所、地震の震源地などの災害情報の収取や、従業員の安否確認には携帯電話やスマートフォンが必要になります。予備のバッテリーを複数用意し、電池切れや停電に備えましょう。
また、信頼性の高い情報を取得するために、ラジオやテレビのニュースの確認が大切ですが、停電によりテレビが使えない場合に備えて、ラジオの用意も必要です。
避難・安全グッズ
避難グッズとしては、非常持ち出し用袋・水に浮くリュックサック・消火器・避難誘導旗・地図・現金などを用意し、施設外に避難が必要になった場合にも備えておくことが大切です。
また、施設内でも自然災害時には二次災害を防ぐ必要があります。ヘルメットや軍手、非常用ライトなどの安全グッズも用意しておきましょう。
寝具・防寒グッズ
停電などによって空調が止まることに備えて、暖を取るための毛布やブランケットの用意がおすすめです。
また、3日間施設内に留まることを想定し、寝具の用意も必要です。
毛布は1人あたり1枚あたりが望ましいとされており、寝具は寝袋や簡易ベッドであるアウトドアベッド、また空気を入れて膨らませるエアーベッド・エアーマットなどを用意し快適に過ごせるようにしましょう。
BCP備蓄品リストの作成までにしておくこと3選
具体的なBCP備蓄品リストを作成するまでにするべきことは以下のとおりです。
- 災害など緊急時への対策の目的を明確にする
- 実際に使用する場面を想定し、必要量な備蓄量を計算する
- 緊急時を想定した訓練・備蓄品の見直しをする
それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
①災害など緊急時への対策の目的を明確にする
緊急時への対策の目的を明確にすることで、必要な備蓄品や連携方法を明確化させられます。
対策の目的を明確にするには、まず緊急時などの最悪の状況を想定し、全システムが止まり、インフラが止まった場合でも業務を継続できるようにするにはどんな課題があるのかを挙げます。
そして、挙げられた課題の最善の解決策を考え、対策に必要なBCP備蓄品を必要な数準備しておくことが大切です。
また、日頃からBCP対策について従業員に共有しておくことで、企業で一丸となって対策できることにも繋がります。
②実際に使用する場面を想定し、必要量な備蓄量を計算する
実際の緊急時に備蓄品を使用する場面を想定し、必要な備蓄量を計算しましょう。
実際に備蓄品を使用する場面を想定することで、どこに置けばいいのか、どれくらい必要なのかを明確に把握できます。
③緊急時を想定した訓練・備蓄品の見直しをする
緊急時を想定した訓練を行い、備蓄品を見直しましょう。
計画するだけでなく、緊急時を想定した訓練を行うことで実際に緊急事態が起きた場合にパニックになることを防ぎ、計画は本当にうまくいくのか、準備したBCP備蓄品は適切なのかなどを確かめることが必要です。
訓練を通してさらに必要な物や用意していた物の中での不要な物が明確になったり、連携方法の改善をしたりできます。
訓練を通して出てきた新たな課題をもとに、作成した備蓄品リストを見直し、改善することが大切です。
BCP備蓄品の保管ポイント
BCP備蓄品リストを作成しBCP備蓄品を用意した後は、保管しておかなければなりません。
BCP備蓄品を保管する上で大切なポイントを3つ紹介します。
- 備蓄品の保管場所
- ローリングストック法やフードバンクによる在庫管理
- 従業員・外部企業との協力体制を構築
それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
備蓄品の保管場所
火災や水害のリスクや倒壊の恐れがなく、緊急時でも業務ができる場所をBCP備蓄品の保管場所として選ぶようにしましょう。
災害などで特定の場所が利用できなくなる恐れもあるため、複数の場所で保管しておくことがおすすめです。
また保管場所を選ぶ際には、緊急時でも誰でも簡単にアクセスしやすく、清潔で高温多湿、直射日光を避けられる場所を選ぶことも大切です。
ローリングストック法やフードバンクによる在庫管理
ローリングストック法とは、賞味期限や使用期限が早いものから先に定期的に消費し、不足分を新たに買い足して備蓄する方法です。
フードバンクとは、まだ食べられるのに廃棄しなければならない食品を、食べ物に困っている場所へ届ける活動のことです。
BCP備蓄品の保管では、効率的な管理が重要になります。
効率的に備蓄品を管理するため、必要な備蓄の品目と量・賞味期限のリスト化し、古いものから手前に保管したり定期的に消費・フードバンクなどに寄付する日を設けたりすることが必要です。
従業員・外部企業との協力体制を構築
従業員や外部企業との協力体制を構築しておくことも大切です。
従業員にBCP対策の大切さやBCP備蓄品リストについて周知したり、研修を行ったりしておくことで、BCP備蓄品の保管についても体制を整えられ、緊急時には従業員一丸となって協力し安全を確保できることにつながるのです。
また、外部企業と連携しておき、ストックしてある物資や業務に使えるアイテムを緊急利用することも可能な場合があります。施設内に社員食堂などがある企業は、食料の緊急利用ができる場合もあります。
BCP対策の2つのポイント
BCP対策をする上で大切なポイントを2つ紹介します。
- 初動対応への対策・準備をする
- 国や自治体のガイドラインを活用する
それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
初動対応への対策・準備をする
初動対応への対策や準備を十分にしておくことが大切です。
BCP対策では、緊急時の初動対応がその後の業務継続に大きく関わってくるため、初動対応への対策を十分にしておき、スムーズに対応できるようにしましょう。
緊急時の初動対応の流れを以下にまとめました。
- 災害本部を設置する
- 従業員の安否確認、安全確保をする
- 情報収集をする
まず、緊急事態発生後の的確な業務継続への判断などを迅速に行えるようにするため、すぐに災害本部を設置します。そして、従業員の安否確認や安全確保、正確な情報収集を行い、緊急事態発生後の業務の方針を決定していくことになります。
初動対応への対策・準備では、誰がどの対応をするのか役割分担をし、実際の緊急時を想定して訓練をしておくことも大切です。緊急時の初動対応をスムーズに行い、業務を継続・早期復旧できるようにしましょう。
国や自治体のガイドラインを活用する
BCPの策定について、国や自治体からガイドラインが提供されています。
提供されている国や自治体のガイドラインを参考にすることで、法的な要件を満たせたり、よりBCP対策を強化したりできるのです。
提供されているBCPガイドラインの一部を以下にまとめました。
これらのガイドラインを活用し、BCP対策を強化しましょう。
企業のBCP対策強化には「安否確認サービス2」がおすすめ
今回は、BCP備蓄品リストについて解説しました。
BCP備蓄品リストは、自然災害や突発的な事故など緊急事態が発生した場合に、従業員の安全を守ることはもちろん、業務を継続、早期復旧するために必要不可欠です。
BCP備蓄品を用意しておくことで、従業員の安全確保や業務の継続・早期復旧をスムーズにおこなえます。
BCP備蓄品リストを作成するまでに、BCP対策の目的を明確にしたり緊急時を想定した訓練を行ったりすることが大切です。
企業のBCP対策強化には、トヨクモが提供している「安否確認サービス2」がおすすめです。
安否確認サービス2では、日本全国どこで大災害が発生しても確実に機能するよう設計されており、安否確認も自動化されています。
緊急時の連絡ツールを安否確認サービス2に統一することで、安否確認をスムーズにでき、初動対応にも迅速に移れるようになるのです。
安否確認サービス2は、機能制限なく30日間無料でお試しできます。何度でもお試しできる仕組みとなっており、初めて安否確認システムに触れる方でも体験しやすい内容です。
安否確認システム14製品を徹底比較!導入に失敗しない選び方も解説
また、緊急時に施設内にいる人数を想定して計算し、BCP備蓄品リストを作成することが大切で、想定される最大出社人数に予備を加えた人数で備蓄量を計算することが一般的です。