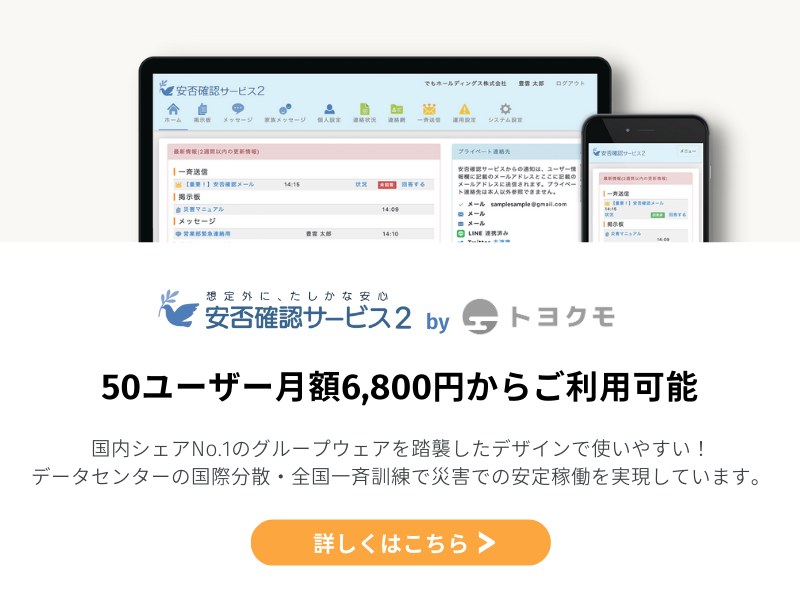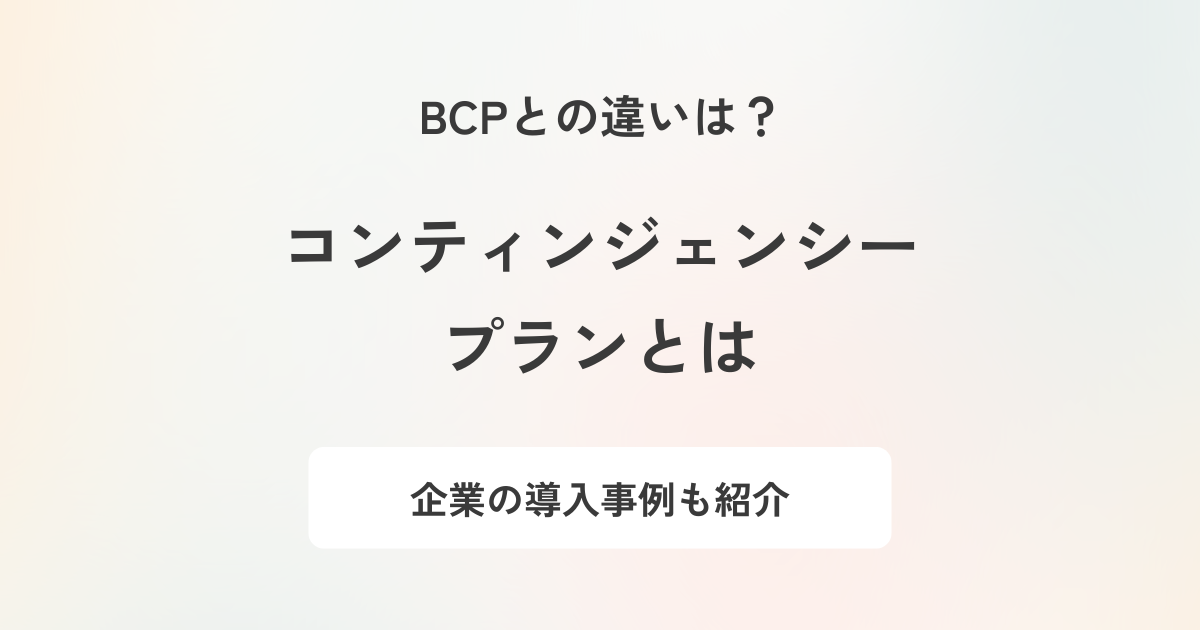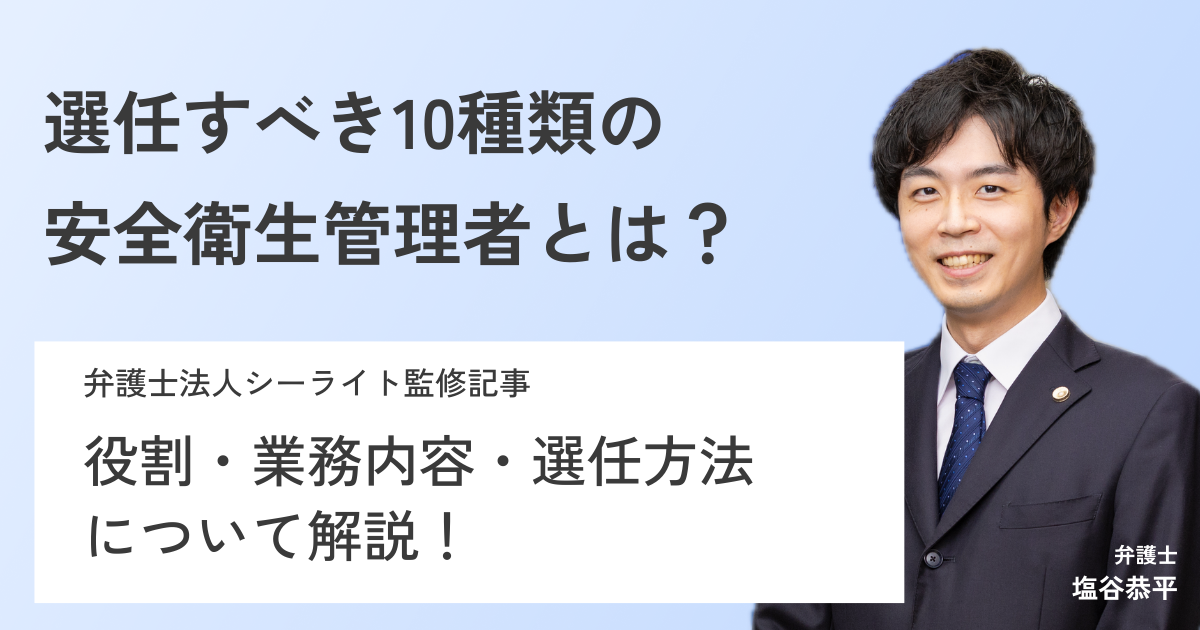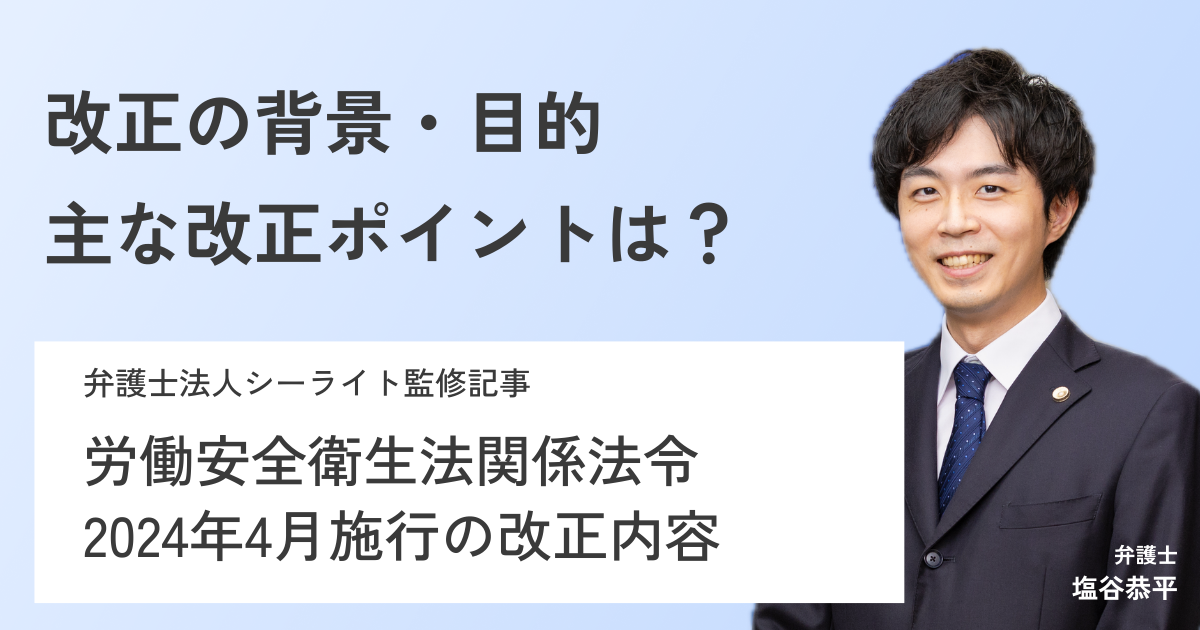弁護士が教える安全衛生委員会!設置要件や罰則、おすすめテーマも解説

塩谷 恭平(しおや きょうへい)
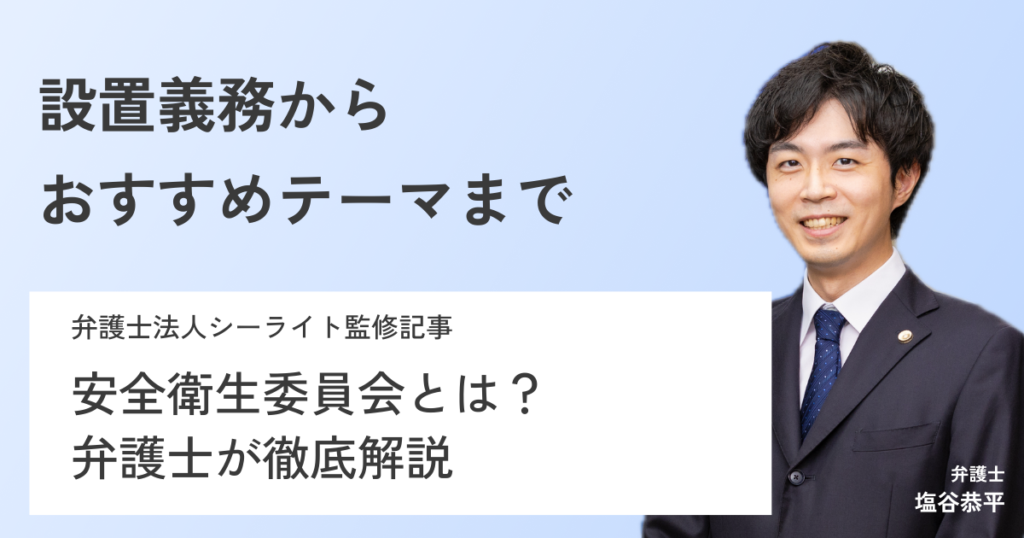
安全衛生委員会の設置は、労働者の安全と健康を守るために重要です。しかし、その設置要件や開催までの流れ等を正しく理解できている方は多くないのではないでしょうか。
この記事では、弁護士法人シーライト 弁護士の塩谷恭平が、安全衛生委員会の設置要件や構成メンバー、違反時の法的責任、そして開催までの流れと委員会で扱うおすすめのテーマ等を分かりやすく解説します。
当記事を参考にすることで、適切に委員会を設置・運営して安全で健康的な職場環境を構築する手助けとなればと思います。

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所 弁護士
弁護士法人シーライト藤沢法律事務所で、労働災害や企業からの労務相談を多数受任。弁護士として事件解決するだけでなく、労働災害や労務問題を起こさないリスクマネジメントの重要性を訴えることで、予防法務にも尽力している。法律的な説明であっても、できるだけ専門用語を使わずにわかりやすく説明を行う姿勢は、多くの企業の方から「わかりやすい」と好評。神奈川県弁護士会所属。
安否確認システムを選ぶなら、トヨクモの安否確認サービス2!
アプリ・メール・LINEで安否確認ができるほか、
ガラケーにも対応で世代を問わず使いやすいのが特徴です。
また初期費用0・リーズナブルな料金で導入できます。
下記のリンクから30日間無料お試し(自動課金一切ナシ、何度でもご利用可能)をお申し込みいただけます。
⇨安否確認サービス2を30日間無料でお試し
目次
安全衛生委員会とは?
まず、「安全衛生委員会」とは、事業場において「安全委員会」及び「衛生委員会」を設置しなければならない場合に、これらの代わりに設置することができる、上記の両委員会を統合した委員会のことをいいます。
委員会の種類としては、ほかに「安全委員会」と「衛生委員会」の2種類があります。
委員会の目的
委員会を設置する目的は、事業者と労働者が一体となって労働災害や健康障害の防止を実現することにあります。
労働災害や健康障害の防止に向けた取り組みは、事業者だけでなく労働者も一体となって取り組む必要があります。なぜなら、使用者側の視点だけでは、実際に働く労働者の労働環境のどのような点に問題があるかを把握しきれずに、実効性のある改善策を実施することが難しいからです。
そこで、労働災害や健康障害がより発生しやすいと考えられる一定の事業者に対しては、委員会の定期的な開催を通じて、労働災害や健康障害を防止するための基本となるべき対策等について、十分な調査審議をさせた上で、事業者に対して改善策等の意見を述べさせるために委員会の設置を義務付けることにしたのです。
委員会の法的根拠
労働安全衛生法(以下「法」といいます。)17条で「安全委員会」、18条で「衛生委員会」、19条で「安全衛生委員会」の設置について規定されています。
関連記事:弁護士が教える労働安全衛生法(安衛法)!重要ポイントと対応策、違反した場合の罰則を解説
これらの委員会については、設置を義務付けられる事業場の要件や調査審議する事項等に違いがあります。以下、詳しく解説いたします。
委員会の設置要件や構成メンバー等
委員会を設置する義務のある事業場
委員会については、労働安全衛生法施行令において、規模及び業種に応じて委員会を設置する義務がある事業場の種類が規定されています。
具体的には、以下の表のとおりです。
| 常時使用する労働者の数 | 業種 | |
|---|---|---|
| 安全委員会 | ①50人以上 | ・林業・鉱業・建設業・製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)・運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)・自動車整備業・機械修理業・清掃業 |
| ②100人以上 | ・上記①以外の製造業・上記①以外の運送業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・家具・建具・じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具・建具・じゅう器等小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業 | |
| 衛生委員会 | 50人以上 | 全ての業種が対象 |
※ 安全委員会と衛生委員会の両方を設置しなければならない場合は、これらの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することも可能です。
※ 上記の要件に当てはまらず委員会を設置する義務がない場合であっても、「委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」(労働安全衛生規則23条の2)という義務があります。
そのため、仮に委員会を設置していなくとも、労働者へのヒアリングやアンケート等を通じて労働者の意見を聴ける体制を整えておく必要があります。
委員会の構成メンバー
各委員会の具体的な構成メンバーについては、それぞれ法17条2項、18条2項、19条2項で定められています。
具体的には、以下の表のとおりです。なお、表中に出てくる「統括安全衛生管理者」、「安全管理者」、「衛生管理者」、「産業医」については、別記事にて詳しく解説しておりますので、こちらをご参照ください。
関連記事:企業必見!弁護士が10種の安全衛生管理者を徹底解説!役割、業務内容、選任方法まで
| 構成メンバー | |
|---|---|
安全委員会 | ①「統括安全衛生管理者」又は「統括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの」若しくは「これに準ずる者のうちから事業者が指名した者」(1人のみ) ②安全管理者のうちから事業者が指名した者 ③当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ※ 安全委員会の議長は、上記①の者が務めることになっています。※ 上記①の者以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにはその労働組合(労働組合がないときには労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名しなければなりません。 |
| 衛生委員会 | ①「統括安全衛生管理者」又は「統括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの」若しくは「これに準ずる者のうちから事業者が指名した者」(1人のみ) ②衛生管理者のうちから事業者が指名した者 ③産業医のうちから事業者が指名した者 ④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ※ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。 |
※ 安全衛生委員会の構成メンバーは、上記の安全委員会及び衛生委員会の構成メンバーを合わせた者になります。ただし、上記①の者は1人のみ選出可能です。
※ 上記①の者以外の委員の人数には上限はないため、事業場の状況に応じて事業者が人数を自由に増やしても構いません。
委員会の調査審議事項
各委員会では、それぞれ次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせることとされています。
調査審議する事項の具体的な内容は、以下の表のとおりです。
| 調査審議事項 | |
|---|---|
| 安全委員会 | ①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること ②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること ③上記①及び②のほか、下記を含む労働者の危険の防止に関する重要事項 ・安全に関する規程の作成に関すること ・法28条の2第1項又は57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること ・安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること ・安全教育の実施計画の作成に関すること ・厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること |
| 衛生委員会 | ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること ④上記①②③のほか、下記を含む労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 ・衛生に関する規程の作成に関すること ・法28条の2第1項又は57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること ・安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること ・衛生教育の実施計画の作成に関すること ・法57条の4第1項及び57条の5第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること ・法65条1項又は5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること ・定期に行われる健康診断、法66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること ・労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること ・長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること ・労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること ・厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること |
委員会の運営に関する義務
委員会の開催義務
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない(労働安全衛生規則23条1項)という委員会の開催義務があります。
労働者への周知義務
事業者には、委員会を開催する度に、遅滞なく、委員会における議事の概要を下記のいずれかの方法によって、労働者に周知させなければならない(労働安全衛生規則23条3項)という労働者への周知義務があります。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
議事録の記録及び保管義務
事業者は、委員会を開催する度に、下記事項を記録して、3年間保存しなければならない(労働安全衛生規則23条4項)という議事録の記録及び保管義務があります。
- 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
- 上記①のほか、委員会における議事で重要なもの
各種義務違反に対する罰則
事業者が、安全委員会・衛生委員会を設置する義務があるにもかかわらず、これらの委員会を設置しなかった場合には、50万円以下の罰金に処せられます(法120条1号)。
なお、安全衛生委員会については、安全委員会及び衛生委員会の代わりに設置する委員会のため、これらの委員会を設置していれば安全衛生委員会を設置する必要はありません。
他方で、委員会の開催義務・労働者への周知義務・議事録の記録及び保管義務については、違反した場合の罰則規定はありません。ただし、これらの義務が実施されていない場合には、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性がありますので、しっかりと行っておくべきです。
委員会の開催までの流れ
委員会設置義務の有無の確認
まず、上記の委員会の設置要件を参考に、委員会の設置義務があるか否かを確認します。設置義務の有無を判断するにあたっては、事業者ごとではなく、「事業場ごと」に判断する必要があります。
事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。
「引用:昭和47年9月18日発基第91号通達」
とされており、一つの事業場であるか否かは同一の場所にあるか離れた場所にあるかで決まることになります。そうすると、例えば、所在地が異なる本社ビルと工場を持っている事業者がいる場合には、原則として本社ビルと工場はそれぞれ別の事業場と判断される(=本社ビルと工場とでそれぞれ委員会の設置が必要になる可能性がある)ことに注意が必要です。
委員会規定の策定
委員会の設置が必要な場合には、委員会設置のため、調査審議事項や構成メンバー、任期等を定めた委員会規程の策定を行うのが良いと考えます。
法や労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則では、委員会規程の作成義務は特に定められてはいませんが、委員会の運営にあたって後で揉めることがないようにルールを明確に決めておくことをお勧めいたします。
なお、委員会規程については、東京労働局のホームページに作成例が掲載されており、ダウンロードが可能ですので、そちらをご参照ください。
委員の選出
上記の委員会の構成メンバーを参考に、委員会を構成する委員を選出します。
年間計画の策定
委員会は毎月1回以上開催することが義務付けられているため、委員会を開催する日程や調査審議する事項について計画を立て、年間計画を策定します。
年間計画の策定も特に義務とはされていませんが、委員会の円滑な運営のためにこちらも定めておくことをお勧めいたします。
委員会開催後のフィードバック
委員会開催後は、「委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容」等を議事録に記録して保存する義務があります。
講じた措置(=改善策)の結果どのように改善したのかについても定期的に振り返って、労働災害及び健康障害の防止のためにより良い労働環境を作っていきましょう。
【弁護士推奨】安全衛生委員会で扱うおすすめのテーマ
委員会で行うべき調査審議事項は、上記に挙げたとおりであり、これに沿ったテーマであれば委員会で取り扱っても問題ありません。
しかし、「どのようなテーマを調査審議すれば良いか分からない」という事業者もいらっしゃるかと思いますので、お勧めのテーマをいくつかピックアップいたします。委員会の運営にあたって参考にしていただければと思います。
特定の時季に関するテーマ
委員会は毎月1回以上開催する必要があるため、季節ごとに話題となりがちなテーマを選んでみることをお勧めいたします。
例えば、以下のようなテーマです。
- 新入社員の健康管理
- 地震や台風等の自然災害が起こった場合の安否確認方法
- 熱中症の予防と対策
- インフルエンザ等の感染症の予防と対策
関連記事:BCP策定に重要な従業員の安否確認方法とは?具体例を解説
災害時、従業員のLINEにも安否確認通知が届く!
⇨安否確認サービス2を30日間無料でお試し
日頃の業務に関するテーマ
委員会では、労働環境の改善のための意見を述べる場であるため、労働環境の改善につながるようなテーマを取り扱うことも効果的だと考えられます。
例えば、以下のようなテーマです。
- 事業場内で起きたヒヤリハット事例の振り返りと予防策
- 長時間労働の予防と対策
- 年次有給休暇の取得状況や福利厚生の利用状況の確認と促進
- テレワークによる健康障害の予防と対策
メンタルケアに関するテーマ
近年、仕事等に関して強いストレスを抱えてメンタルに不調をきたしてしまう労働者が増えています。
労働者の身体だけでなく、メンタル面についても健康を保てるような職場にするために、メンタルケアに関するテーマを取り上げてみてはいかがでしょうか。
例えば、以下のようなテーマです。
- 事業場内で起きたヒヤリハット事例の振り返りと予防策
- 長時間労働の予防と対策
- 年次有給休暇の取得状況や福利厚生の利用状況の確認と促進
- テレワークによる健康障害の予防と対策
安全衛生委員会の開催で安全で健康な職場環境を
上記のように、一定の規模・業種の事業場では、安全委員会や衛生委員会(または安全衛生委員会)の設置が必要となります。事業者としては、義務だから何となく設置するだけなく、労働者の労働災害や健康障害を防止するために、労働環境の問題点を洗い出したり、有効な改善策等を協議する場として、これらの委員会を積極的に活用していきましょう。
委員会の適切な運営を通じて労働環境が改善していけば、今いる労働者の生産性が上がるだけでなく、次世代の採用活動にもプラスとなり、事業の更なる発展へと繋がります。
もし各種委員会の設置・運営やその他の安全衛生管理体制についてご不安な点がある場合には、弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人シーライト藤沢法律事務所 弁護士
弁護士法人シーライト藤沢法律事務所で、労働災害や企業からの労務相談を多数受任。弁護士として事件解決するだけでなく、労働災害や労務問題を起こさないリスクマネジメントの重要性を訴えることで、予防法務にも尽力している。法律的な説明であっても、できるだけ専門用語を使わずにわかりやすく説明を行う姿勢は、多くの企業の方から「わかりやすい」と好評。神奈川県弁護士会所属。

執筆者:塩谷 恭平(しおや きょうへい)
弁護士法人シーライトで、労働災害や企業からの労務相談を多数受任。弁護士として事件解決するだけでなく、労働災害や労務問題を起こさないリスクマネジメントの重要性を訴えることで、予防法務にも尽力している。法律的な説明であっても、できるだけ専門用語を使わずにわかりやすく説明を行う姿勢は、多くの企業の方から「わかりやすい」と好評。神奈川県弁護士会所属。 プロフィール:http://cright.jp/lawyer/shioya.php