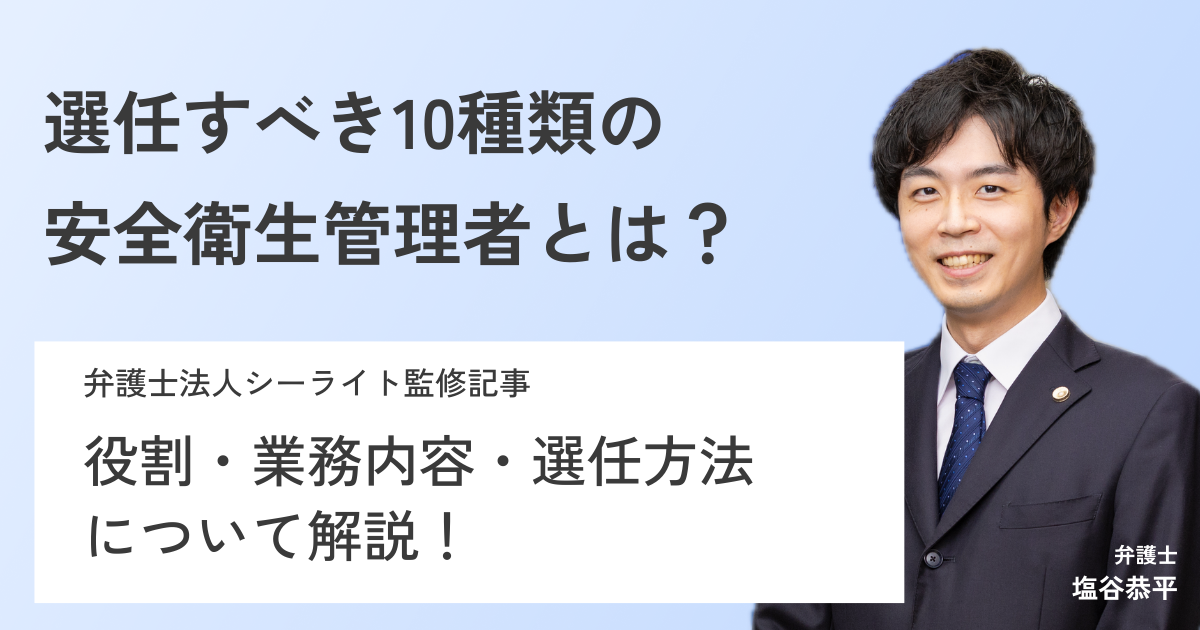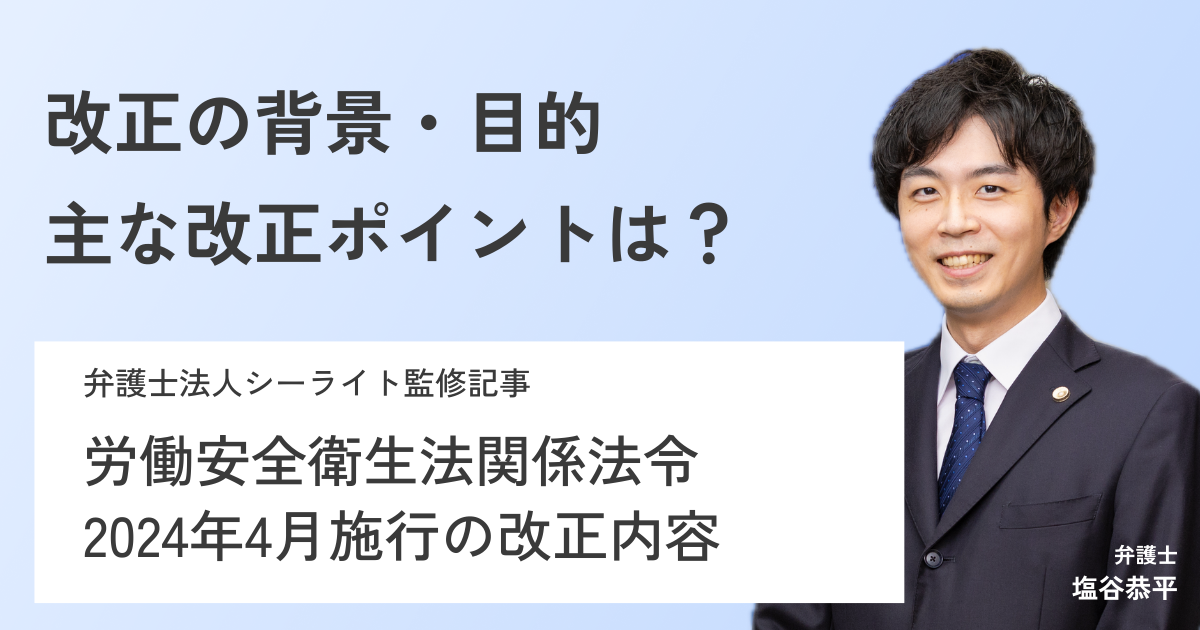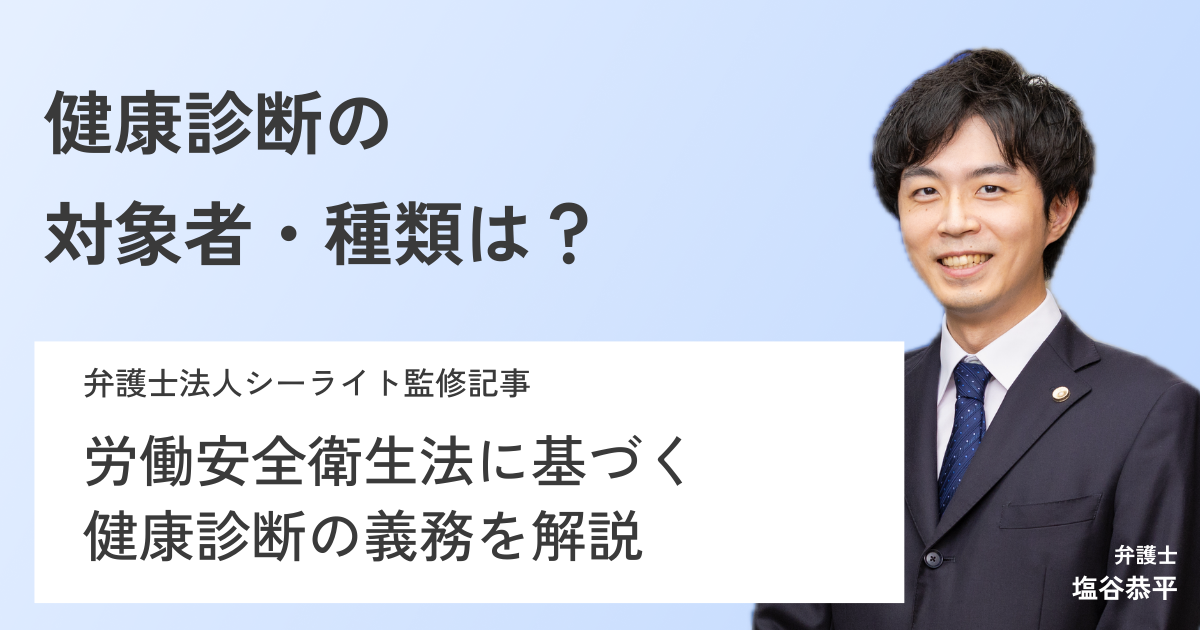【事例紹介】コンティンジェンシープランとは?策定の手順やBCPとの違いを解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
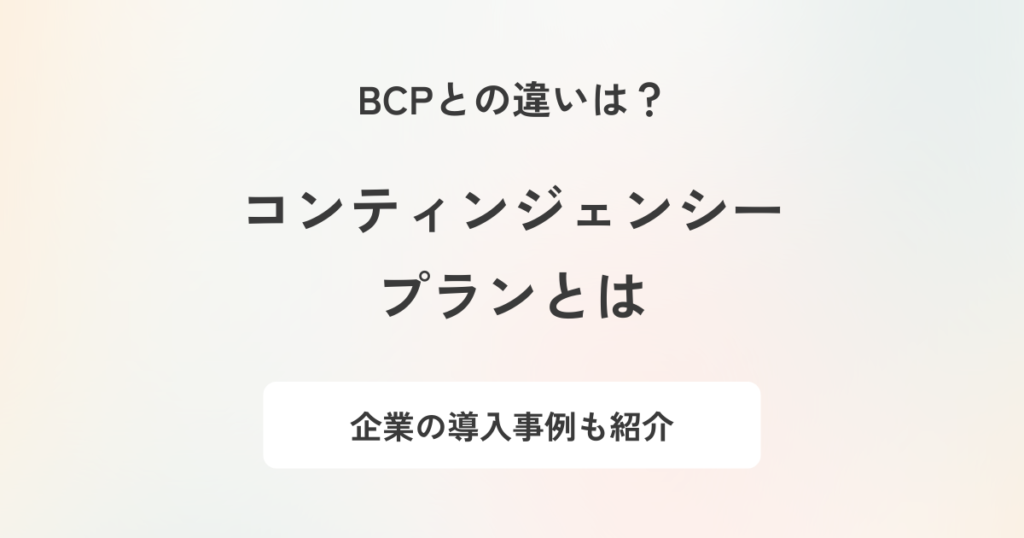
自然災害やサイバーテロなど、企業にとってのリスクは多様化しています。近年、こうしたリスクへの対策として注目を集めているのが「コンティンジェンシープラン」です。
本記事はコンティンジェンシープランの策定方法や、BCPとの違いについて解説します。
目次
コンティンジェンシープランとは
コンティンジェンシー(Contingency)とは「偶発」「不慮の事故」を表す単語です。つまり、不慮の事故に対応するための計画がコンティンジェンシープランと言えます。
ここからは、コンティンジェンシープランの具体的な定義、ならびにコンティンジェンシープランが注目されている理由について解説します。
コンティンジェンシープランは「緊急時対応計画」
コンティンジェンシープランは和訳すると「緊急時対応計画」です。自然災害やテロなどの緊急事態発生時、業務への被害を最小限にとどめ、早急に復旧するために策定されます。
自然災害やテロが発生すると、場合によっては、企業は一部の業務を停止しなければなりません。そこで、何から優先して対策するかをあらかじめ調べ、被害をできるだけ最小限にとどめる対策が必要です。これがコンティンジェンシープランなのです。
コンティンジェンシープランを定める目的
コンティンジェンシープランは、被害を最小限に抑えるために策定されます。緊急事態の発生時に対応が遅れると、被害が大きくなり、損失が膨らんでしまうおそれがあります。その損失を回避することが、コンティンジェンシープランを策定する目的です。
業務によっては、発生した被害が顧客や取引先へと連鎖的に広がるでしょう。そのため金融機関や公的機関では、コンティンジェンシープランの策定がとくに必要とされています。
コンティンジェンシープランが注目されている要因
コンティンジェンシープランへの関心は、近年高まっています。自然災害や新型コロナウイルス感染症のような、突発的な危機だけではありません。地政学リスクやサイバー攻撃、サプライチェーンの混乱など、多様化・複雑化する社会的リスクの存在があります。
企業や組織にとって、予測不能な事態に迅速かつ柔軟に対応する体制を整えることは、事業継続の鍵です。ここでは、コンティンジェンシープランが注目されている要因について詳しく解説します。
自然災害のリスク
日本は、地震や津波、台風といった自然災害が頻発するエリアです。災害は、企業の事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、企業にとって自然災害への対策は大きな課題です。被害を最小限に抑えるためにも、あらかじめ非常時の対応を定めたコンティンジェンシープランの整備が求められています。
グローバル・国際的なリスク
コンティンジェンシープランは、国内の危機対応だけでなく、国際的なリスクに備えるうえでも大切です。
グローバル市場で活動する日本企業にとっては、海外の政治不安や経済変動、パンデミックなど、国外で起きる事象が自社のビジネスに直接影響を与えることも少なくありません。柔軟に対応するためにも、危機対応計画の整備が重要視されています。
法令や規制の遵守
近年、日本を含む各国で法令や規制が厳しくなっており、企業には事業の継続性やリスク管理に対する明確な対応姿勢が求められています。
法的・社会的要請に応えるための手段として、コンティンジェンシープランの重要性は高いでしょう。緊急時の対応体制を整えることで、企業は外部からの信頼を確保できます。結果的に、企業の法令遵守と持続可能な経営につながります。
サプライチェーンの複雑化
グローバル化が進む中で、企業のサプライチェーンはより広範かつ複雑な構造になっています。部品や原材料の供給が滞った際には、生産の停止や納期の遅れといった深刻な影響が生じるリスクも高いでしょう。
こうした供給網の脆弱性に備えるためにも、コンティンジェンシープランは有効な手段です。サプライチェーン全体のリスク管理において、重要な役割をはたしています。
コンティンジェンシープランの策定方法
コンティンジェンシープランを一度策定すると、緊急事態時に従業員が安心できるマニュアルとして機能します。
優れたマニュアルを作成するために、コンティンジェンシープラン策定に必要な手順を以下で確認しましょう。
1. 策定の目的と方針の明確化
策定にあたって、コンティンジェンシープランを策定する目的を明確にする必要があります。「緊急時に被害を最小限に抑える」ことが大枠として共通していても、基本方針や具体的な目的は部署ごとに異なります。何をもって被害とするのか・何をもって復旧とするのかなど、メンバー同士で認識をすり合わせることが重要です。
その後の方向性を見失わないためにも、コンティンジェンシープランを策定する目的と方針を明確にしましょう。
2. 想定されるリスクを洗い出して把握
自然災害やテロなどあらゆる緊急事態が発生したときを想定し、各業務にどの程度のリスクが考えられるかを洗い出します。想定するリスクが偏るのを防ぐために、複数のメンバーでの検討が必要です。その後、業務の停止で起こりうるトラブル、損害額の大きさ、顧客や取引先に与える影響などから、復旧を優先すべき業務の順位を決めます。
想定した被害をもとに、人材や設備の見直しを行い、緊急時の具体的な対応を決定します。
3. 具体的な対応方法の検討
リスクの洗い出しが完了したあとは、緊急事態発生時の具体的なプランを検討します。ここで検討する内容は、緊急時に構築すべき業務体制と役割分担についてです。
緊急時には経営資源が確保できません。とくに自然災害発生時であればライフラインが停止する危険性もあります。通常の業務が遂行できない状況に備えて、代替案を決めておくといいでしょう。
こうして決定した具体的なプランを迅速に実行できるようにマニュアル化すれば、コンティンジェンシープランの策定は完了です。
4. 社員へのプランの周知
コンティンジェンシープランの策定が完了したら、従業員への周知を徹底しましょう。
従業員がコンティンジェンシープランの存在を認識していないと、緊急時の対応が遅れてしまいます。また、従業員各自がコンティンジェンシープランに目を通すだけでは、認識のずれが生じる可能性もあります。部署ごとに説明を交えた確認が重要です。
非常時に的確な対応ができるようコンティンジェンシープランを周知し、いつでも確認できる状態で管理しておきましょう。
5. 訓練を実施して見直しや改善
緊急時に慌てず行動するためには、コンティンジェンシープランの策定と従業員への周知だけでなく定期的な訓練も必要です。緊急事態を想定した訓練によって、万一の際、スムーズな対応や連携が取れるようにしておきましょう。
訓練では、コンティンジェンシープラン策定時に気付かなかった問題点を発見できる可能性があります。気付いたことや改善点を参加者同士で話し合い、コンティンジェンシープランの改善を随時行うことも必要です。
BCP(事業継続計画)との違いは?
コンティンジェンシープランと共通点が多く混同されやすい概念が、BCP(事業継続計画)です。どちらも企業が策定する緊急時における行動計画を指しますが、BCPとコンティンジェンシープランは異なります。ここからは、両者の違いについて解説します。
関連記事:BCP(事業継続計画)とは?専門家がわかりやすく解説
BCPは「事業の継続」を優先
BCP(事業継続計画)は、コンティンジェンシープランと類似している「緊急時に向けた計画」の一つですが、それぞれ近しい特徴を持っていることから、混同されがちです。
しかし、コンティンジェンシープランとBCPは同一の概念ではなく、以下のような違いがあります。
| コンティンジェンシープランとBCPの違い | |
| コンティンジェンシープラン | 各業務における緊急時の対応を決定する |
| BCP | 事業継続を目的として、各業務の復旧に優先順位を付ける |
コンティンジェンシープランは「緊急時の対応」に重点を置いた短期計画で、各業務での緊急時の対応を策定するものです。自然災害やテロなどの発生直後に実行される、緊急の対策マニュアルと言えます。
一方でBCPは「事業の継続」に重点を置いた中長期計画であり、各業務の復旧に優先順位をつけ、緊急事態下でも事業を継続するために策定するものです。こちらは緊急事態発生時だけでなく、その後のリスク回避や復旧までも見据えます。そのため、BCPで策定された計画のひとつとして、コンティンジェンシープランが含まれることもあります。
関連記事:【図解】BCP策定6つの手順|注意点をステップごとに解説
リスクを特定して対応する点は共通
かつては、コンティンジェンシープランは業務の停止によるリスクを考慮しない計画でした。コンティンジェンシープランが策定するのは、あくまで緊急事態発生時に従業員がどのように行動するのかの指針で、リスク計算までは行わなかったのです。
しかし近年はBCP同様、コンティンジェンシープランの策定でもリスクを洗い出す傾向にあります。そのため現在は、コンティンジェンシープランもBCPも「リスクを特定して対応策を検討する」点で共通しています。
リスクマネジメントとの違いは?
リスクマネジメントとコンティンジェンシープランは、どちらも組織の安定運営に欠かせない考え方です。しかし、目的と役割には明確な違いがあります。
リスクマネジメントは、将来的に発生し得るリスクを洗い出し、分析や評価したうえで、発生を未然に防ぐための戦略や方針を構築する手法です。
一方で、コンティンジェンシープランは、実際にリスクが発生した際にどのように対応するかという、緊急時の行動計画を定めることに重点を置いています。
リスクマネジメントは「起こさないための準備」であり、コンティンジェンシープランは「起きたときの備え」として機能する点に違いがあります。両者を適切に組み合わせることで、企業や組織はより強固なリスク対応体制を築くことが可能です。
コンティンジェンシープランの導入事例
緊急時のマニュアルであるコンティンジェンシープランは、企業でどのように扱われているのでしょうか。
日本の企業3社における、コンティンジェンシープランの導入事例をご紹介します。
日本取引所グループ
日本取引所グループは、1999年7月に「東証市場における売買に関するコンティンジェンシープラン」を策定しています。以来、数年おきに改正を繰り返しながら、緊急事態に備えています。
日本取引所グループの傘下には、東京証券取引所や大阪取引所があり、絶えず金融商品が売買されているのです。したがって緊急時に売買が停止してしまうと、投資家は甚大な影響を受けるでしょう。これを避けるため、システム障害や自然災害などのリスクを8つのケースに分類して想定し、それぞれのケースごとに細かなコンティンジェンシープランを策定しています。
ANA
ANA(全日本空輸)は、利用者を長時間にわたって機内で待たせた場合の対応策を公開しています。
お待たせ時間が2時間を超える前に飲食物を提供する、降機が可能な場合は案内する、などの対応策が盛り込まれたものです。
コンティンジェンシープランで実施するサービスを定めておくことで搭乗スタッフが対応しやすくなり、さらにプランを公開することで乗客が利用しやすい体制を構築しています。
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)では、グループ各社が独自にコンティンジェンシープランを策定しています。とくに「資金調達の著しい悪化により、子会社が必要資金を確保できない」といった、企業の存続に関わる深刻なリスクを対象に、対応策が考えられています。
MUFGが公表している「リスク管理」では、状況に応じて平時・懸念時・危惧時という、3つのステージが大切です。段階的に、対応を切り替える体制となっています。
リスクの管理プロセスとしては、定義・評価・コントロール・モニタリングの4段階が用意されており、発生し得るリスクに対して明確な判断基準と対応方針が示されています。危機発生時に、迅速かつ的確な行動が取れる仕組みです。
策定したコンティンジェンシープランはいつ見直す?
一度策定したコンティンジェンシープランも、状況の変化に応じて定期的な見直しが必要です。ここでは、見直しに適した3つのタイミングをご紹介します。
1.操業停止期間の前
お盆や年末年始といった長期休暇の前は、コンティンジェンシープランを見直す絶好のタイミングです。通常業務が一段落する時期であるため、冷静に災害対策や緊急時対応を再確認する余裕が生まれます。
この機会に、非常時の連絡手段が確実に機能するか、備蓄品の状態や量に問題がないか、重要な業務データがバックアップされているかなどを総点検しましょう。
従業員の安否確認の方法や、緊急参集の訓練内容もこのタイミングで再評価することが重要です。計画を最新の状況に合わせてアップデートすることで、いざというときの備えを、より確かなものにできます。
2.防災訓練
防災訓練は、実際の災害を想定した行動が確認できるため、コンティンジェンシープランの実効性を見直すのにおすすめです。
避難経路の把握や従業員の安否確認、初期消火や救護活動など、緊急対応手順を実践的に検証できる点が大きなメリットです。訓練で見つかった課題は、改善点として反映させることが求められます。
従業員が体験を通じて得た気付きや意見を取り入れることで、より現実に即した、実行可能なコンティンジェンシープランにブラッシュアップされます。こうした取り組みが、緊急時の迅速かつ的確な対応につながるでしょう。
3.災害・非常時
災害発生後、対応が終わった直後は、コンティンジェンシープランを抜本的に見直すのに、最適なタイミングです。実際の対応を経験することで、計画の有効性や課題が具体的に浮き彫りになります。
成功した点や改善が必要な部分を洗い出し、より実効性の高いプランへと再構築することが重要です。対応直後の記憶が新鮮なうちに関係者を集めて、詳細な振り返りをするとよいでしょう。
具体的には、「初動対応は円滑だったか」「情報伝達は迅速かつ正確に行われたか」「代替手段は適切に機能したか」などの項目を検証します。さらに、今後に備えた改善策を策定します。
コンティンジェンシープランが活用できる部署・部門
コンティンジェンシープランは、組織のさまざまな部署で活用が期待されます。ここでは、とくに重要な役割を担う部門について見ていきましょう。
総務・人事
総務・人事部門は、従業員の安全確保と継続的な組織運営を支える重要な役割を担います。コンティンジェンシープランの実行において、中心的な存在です。
災害や緊急事態発生時には、従業員の安否確認体制の構築や緊急連絡網の整備、避難誘導計画の策定などを担当します。非常時に備えた食料品や医薬品の備蓄、従業員の家族との連絡手段の確保も実施するのが特徴です。ほかにも休業補償制度の整備など、従業員を支援する体制も整える必要があります。
リスク管理
リスク管理部門は、コンティンジェンシープランの策定と運用において中心的な役割を果たします。リスクアセスメントを通じて、事業継続に影響を及ぼす可能性のあるリスクを特定し、その影響度を評価します。
具体的な業務は、緊急事態発生時の対応手順の作成や責任者の明確化、さらに代替手段の確保などです。策定したプランは定期的に見直し、必要に応じて改善することで、常に有効な対応体制を維持することが求められます。
施設・拠点管理
施設・拠点管理部門は、コンティンジェンシープランにおいて、事業継続のための物理的な基盤を支える役割です。災害時には、施設の安全点検や設備の緊急停止・復旧手順の確立、さらに代替施設の確保などが主な業務です。
建物の耐震補強や非常用電源の準備、通信設備のバックアップ体制の整備、防災設備の定期点検・更新なども実施します。物理的なリスクから組織を守り、安定した事業運営を支えることが求められる部門です。
コンティンジェンシープランについてよくある質問
コンティンジェンシープランに関して、よく寄せられる質問をまとめました。ここでは、疑問点やポイントをわかりやすく解説していきます。
そもそもコンティンジェンシーとはどういう意味ですか?
コンティンジェンシー(Contingency)とは、不確実な状況や、偶発的な出来事を指す言葉です。ビジネスの経営管理やITの現場でよく使われ、予測できないトラブルや事故に対応する考え方を表します。
リスクマネジメントがプロジェクトやチーム単位で行われることが多いのに対し、コンティンジェンシーは企業全体や事業単位など、より広範な範囲で対策を検討する際に用いられます。
コンティンジェンシープラン策定に関する資料はありますか?
コンティンジェンシープランの策定に関する資料は、金融情報システムセンター(FISC)が発行しています。資料には、システムリスクやオペレーショナルリスクに対するコンピュータセンターの対応方法や、営業店や本部機構の対策が詳細にまとめられています。
策定プロセスはわかりやすく記載されているため、金融機関以外の企業でも参考にできる内容です。詳細は、FISCの公式サイトで確認できます。
(引用:金融機関等におけるコンティンジェンシープラン(緊急時対応計画)策定のための手引書)
コンティンジェンシープランの注意点は何ですか?
コンティンジェンシープランは、策定が目的ではなく、実際に運用できるかどうかが重要です。策定に時間がかかる場合は、途中のプランを仮運用しながら、ブラッシュアップするのがよいでしょう。
実際の運用を通じて、新たな課題や改善点に気付くため、継続的な見直しが重要です。スタッフへの定期的な教育や訓練を実施し、計画を改善し続けることが求められます。
コンティンジェンシー理論とは何ですか?
コンティンジェンシー理論は、どのような状況でも完璧に対応できるリーダーシップは存在しないとする考え方のことです。別名「状況適合理論」とも呼ばれています。
近年、注目されており、リーダーの成果は本人の資質だけでなく、職場環境や人間関係などの外的要因が大きく影響すると考えるのが特徴です。コンティンジェンシー理論では、環境の変化に応じて、組織の管理方法も柔軟に変える必要があることを示しています。
コンティンジェンシー理論が生まれた背景はどのようなものですか?
コンティンジェンシー理論が登場する前は、優れたリーダーは生まれつき知性や行動力、責任感などの資質を持つとする「リーダーシップ資質論」が主流でした。
しかし、1960年代に技術や産業が高度化し組織のニーズが多様化すると、唯一最善のリーダーシップは通用しなくなりました。そのため、1964年に経営心理学者のフィドラーが「リーダーの適切なスタイルは状況によって変わる」とする、コンティンジェンシー理論を提唱します。
BCP策定にはトヨクモ『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用がおすすめ
『BCP策定支援サービス(ライト版)』は、自然災害や緊急事態に備えて、BCPを作成したい企業に最適なサービスです。日本の省庁ガイドラインや独自の事業環境を考慮し、各企業に合った計画を策定できます。
策定だけでなく、体制の維持も支援し、教育・訓練・演習、さらに監査まで幅広く対応できるのが魅力です。策定後も、継続的にサポートを受けられます。自社のBCPが実際に効果を発揮し、事業の安定につながるような支援を検討している方は、ぜひお試しください。
多様なリスクに備えて対策を
地震だけでなく台風や雪害など、近年は自然災害が頻発しています。また情報化の進む現代はサイバーテロが巧妙化し、過去にはサイバーテロによって業務が一時停止してしまった企業もありました。感染症による行動制限なども考慮すると、企業にとってリスクは多方面に存在しているでしょう。
緊急時に従業員の安全を守りながら事業を継続するために、コンティンジェンシープランやBCPの策定を行うなどの対策を取ることが大切です。
BCPを策定できていないなら、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用をご検討ください!
早ければ1ヵ月でBCP策定ができるため「仕事が忙しくて時間がない」や「策定方法がわからない」といった危機管理担当者にもおすすめです。下記のページから資料をダウンロードして、ぜひご検討ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。