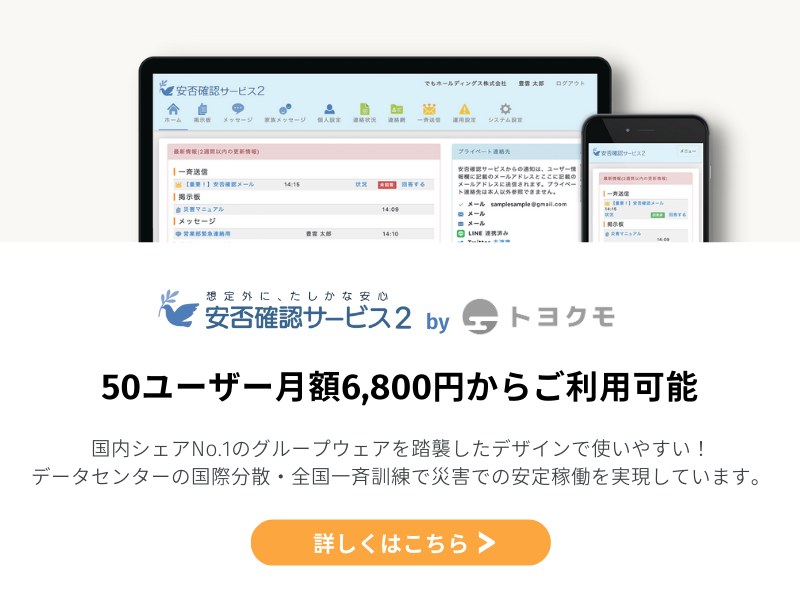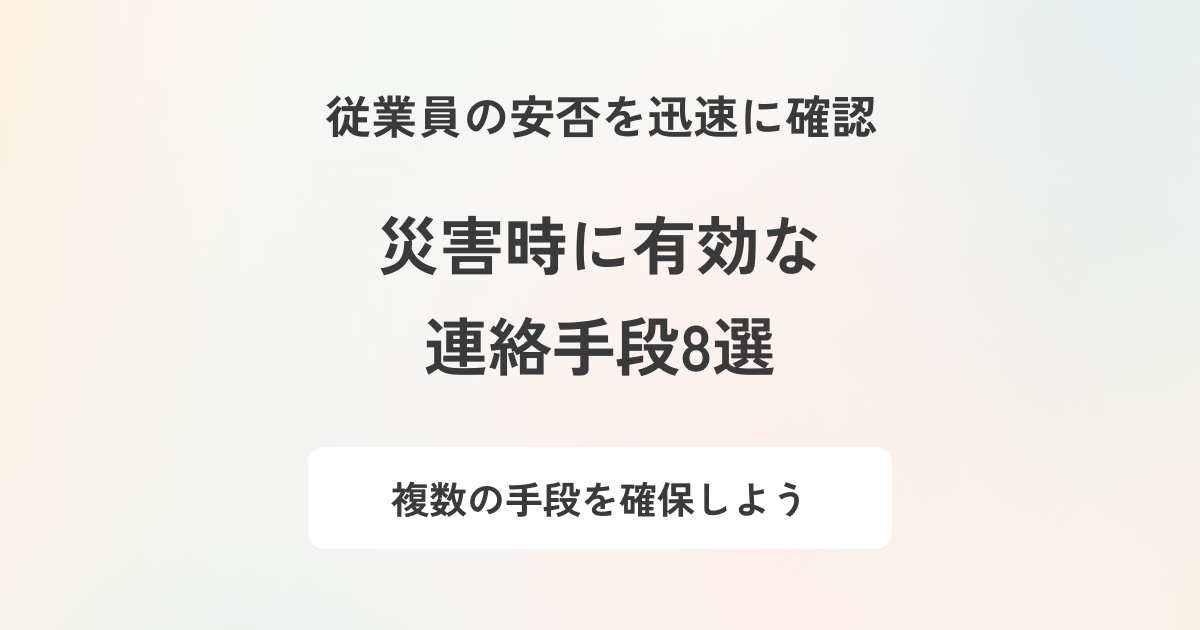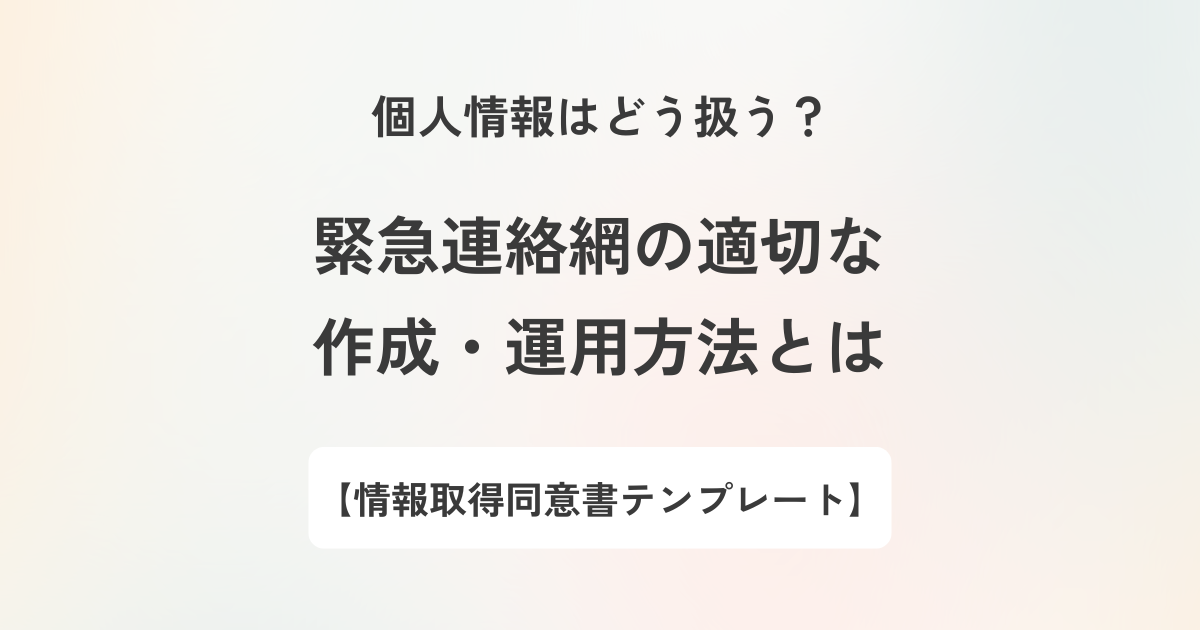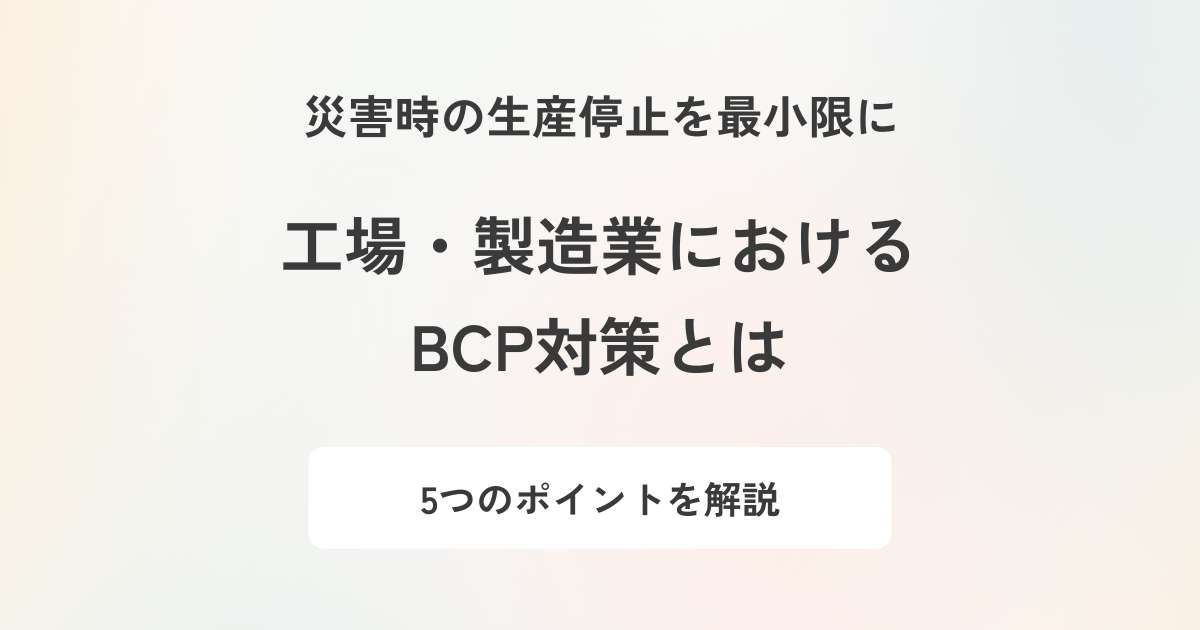BCP策定に重要な従業員の安否確認方法とは?具体例を解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
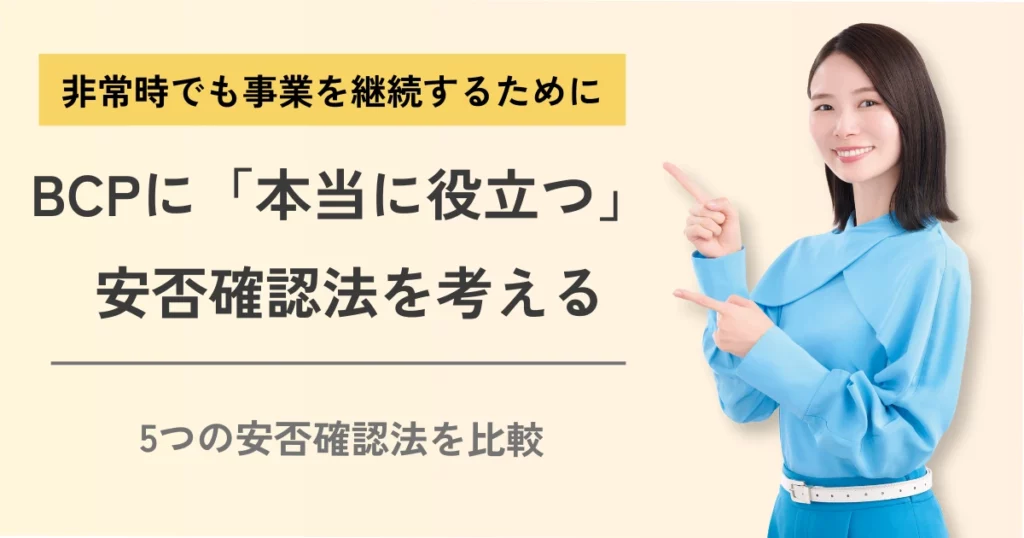
近年、地震をはじめとする自然災害が頻発しており、BCP策定の必要性を感じている企業は多いでしょう。緊急事態時に備えた準備を行っていると、企業の損害を最小限に抑えつつ事業継続ができます。なお、BCPを策定するうえで欠かせないのが従業員の安否確認です。緊急事態時に従業員の協力が得られないと、事業を継続するのは困難だからです。そのため、あらかじめ従業員の安否確認方法を決めておく必要があります。
そこでこの記事では、BCP策定における従業員の安否確認方法の具体例を紹介します。安否確認の方法を決める際のポイントも解説しているので、あわせて参考にしてください。

目次
そもそもBCPとは
BCP(事業継続計画)とは、地震やテロといった緊急事態が発生したとき、迅速な事業継続が行えるようにあらかじめ立てておく計画のことです。事前に緊急事態時の対応策を考えておくと、企業の損害を最小限に抑えながら事業を継続できます。
なお、BCP策定がまだできていない企業やBCPの見直しをしたい企業には、トヨクモ『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用がおすすめです。最短1ヵ月で策定できるため「時間がなくてBCPを策定できない」といった悩みを解決できます。
BCPコンサルティングは数十〜数百万円ほどするのが一般的ですが、BCP策定支援サービス(ライト版)であれば1ヵ月15万円(税抜)で提供できるのも魅力です。費用を抑えながらBCPを策定したい方は、ぜひご利用ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
BCP策定時に安否確認が重要な理由
企業にとって大切なのは、商品や資金だけではありません。事業に携わる従業員も企業にとっての非常に重要な資産です。特に緊急事態が発生したときは、事業を継続していくために従業員の協力が必要不可欠と言えるでしょう。
緊急事態時における安否確認は、従業員とその家族が無事であるかどうかを確認するだけではなく、業務を遂行できる従業員数を把握する役割も担っています。業務に携われる従業員を確保できれば、迅速な事業復旧も可能となるでしょう。
また、企業には従業員の安全や健康を守る義務があります。災害などのトラブルがあったときにすみやかに従業員の安全を確保・確認できる体制を整えておかなければいけません。
つまり、緊急事態時の安否確認は、従業員を守りつつ事業を継続していくうえで欠かせない重要な要素です。
従業員の安否確認方法の具体例
従業員の安否確認方法は、主に以下の5つがあります。
- メール
- 安否確認専用のアプリやサービス
- 災害時のみ利用できるサービス
- 連絡用アプリ
- SNS
それぞれの方法について解説します。
メール
従業員のメールアドレスを事前に集め、災害時にメールを送る方法です。この方法では、従業員のメールアドレスを一括で管理しておき、緊急事態が起きたときに1人ひとりに連絡をして状況把握を行う必要があります。
メールは平時から社員全体に対して行う注意喚起などの連絡にも使えるため、安否確認以外にも活用できるでしょう。
しかし、災害をはじめとする緊急事態時はメールサーバの利用者、利用数がともに爆発的に増えるため迅速なメールの送受信が難しくなります。
安否確認専用のアプリやサービス
安否確認専用のアプリやサービスは災害時を想定されているため、メールのように送受信しにくいといったトラブルを回避できます。従業員の安否確認を自動で行えるサービスもあり、担当者の負担を減らしながら状況把握ができるでしょう。
数ある安否確認専用アプリやサービスのなかでも特におすすめなのが、トヨクモが提供する『安否確認サービス2』です。気象庁の情報と連動して従業員の安否確認を自動で行えるほか、回答結果も自動で分析できるため迅速な状況把握が可能です。
安否確認だけでなく、その後のコミュニケーションにも活用できるのも大きな魅力でしょう。掲示板やメッセージ機能を活用すれば、事業継続に必要な会議や指示出しを迅速できるため、早期復旧に役立てられます。
また、安否確認サービス2では東日本大震災のような大災害を想定し、メインサーバをシンガポールに、バックアップサーバを米国と日本に置いています。このようにサーバを国際的に分散して置くことにより、リスクを軽減しています。さらに、アクセスの集中や災害が起きた場合は、自動的にサーバを拡張するシステムになっているため、いかなる事態となっても安定してサービスを利用できるでしょう。
災害時のみ利用できるサービス
通信各社が用意する緊急時用のサービスは、今までの災害時にも多くの方が利用しており、認知度の高いサービスです。しかし、個人での利用を前提として作られているため、大勢の従業員の安否確認やその後の指示などに使うのは不向きです。これらのサービスは、安否確認したい特定の人が数名だけいる場合に利用するといいでしょう。
連絡用アプリ
コミュニケーション機能に特化したアプリのなかには、災害時に利用できるものもあります。プライベートで使っている人も多いため既にIDを持っていたり、操作に慣れていたりする場合が多い連絡手段です。ただ、従業員の安否確認の回答結果を分析する機能などは備わっていないため、大人数の安否確認には不向きです。
なお、主な連絡用アプリは「LINE」と「Skype」があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
LINE
LINEは、東日本大震災の発生した2011年3月には開発途上のサービスでした。この震災を受け「緊急時にこそホットラインが必要だ」という思いからLINEには既読マークが取り入れられました。LINEの既読マークは相手が被災して返信すらできないときでも、メッセージが伝わったか否かを判断できるようにとつけられた機能です。
電話回線がつながっていなくても、インターネット回線がつながっていればLINEでのトーク(メッセージ)は可能です。緊急連絡網のグループを設定しておけば、非常時でも一斉に安否確認できます。
大規模災害時には自動で安否確認画面が出るので、そのときの状況を選択して「友だち」としてつながっているアカウントにメッセージを送信することも可能です。
Skype
無料通話ができるSkypeも災害時に有用です。電話回線ではなくインターネット回線を利用しているため、電話回線がつながりにくくなった場合でも、通話できるのが魅力です。
音声通話だけではなく、文章でのやり取りもできるため、落ち着いて通話ができない状況でもメッセージ機能を活用できます。
SNS
SNSを使った安否確認もできます。SNSは利用者が多く情報発信しやすいです。一方で、メッセージを見たかどうかなどの確認がしにくいというデメリットがあります。そのため、安否確認よりも事業継続に関する指示などの情報発信をしたい方におすすめです。
Twitterのつぶやきやメッセージなどの機能を使うと、従業員の安否確認を行えます。ただし、個別メッセージの送受信にはお互いのフォローが必要です。企業アカウントがあれば、従業員にメッセージを入れてもらうということもできます。
Twitterはインターネット回線を利用するため災害時にもつながりやすく、安否確認に使いやすいでしょう。また、首相官邸のアカウント(https://twitter.com/kantei_saigai)など政府や公共機関のアカウントをフォローしておくと、災害時の情報を迅速に収集できます。
facebookには「災害時情報センター」という機能があります。自然災害が発生した際、該当地域のユーザーに安否確認のメッセージが入ります。それに返信するとグループ内に安否確認が伝わる仕組みです。
BCP策定における安否確認方法を選ぶポイント
BCP策定における安否確認方法を選ぶ際のポイントは、以下の2つです。
- 安否確認だけではなくBCPに役立てられる方法を選ぶ
- 複数の安否確認方法を組み合わせる
それぞれのポイントについて解説します。
BCP策定における安否確認方法を選ぶポイント
BCPにおいては従業員の安否確認だけではなく、今後の事業継続について話し合える場は極めて重要です。災害をはじめとする緊急時は何が起こるか予測できないため、BCPを策定していたとしても災害発生時の経営陣、現場の管理者、従業員同士などのすみやかな話し合いは不可欠です。そのため、従業員の安否確認を行いつつ、事業継続について特定のメンバーで話し合える方法を用意しておくと迅速な初動が可能です。
複数の安否確認方法を組み合わせる
災害時をはじめとする安否確認方法は、複数用意しておくと安心です。あらゆる方法で安否確認を行えると従業員が返しやすい方法で返答できるほか、安否確認の通知が届かないといったトラブルを防ぎやすくなります。安否確認方法を一つに絞らないことによって、その場に応じた活用ができるでしょう。
BCP策定に有効な安否確認方法を決めておこう
BCPを策定するにあたって、従業員の安否確認方法を決めておくのは極めて重要です。迅速な安否確認ができると、早急な事業復旧も可能になるでしょう。安否確認方法はメールや連絡用アプリ、安否確認システムの活用などが挙げられます。今後の事業継続に役立てられる安否確認方法を選択し、迅速な対応を心がけてください。
なお、災害時の安否確認はトヨクモの『安否確認サービス2』の活用がおすすめです。従業員の迅速な安否確認を行いつつ、事業継続に必要な話し合いも行えます。BCP策定に役立てられる安否確認システムをお探しの方は、ぜひ利用をご検討ください。