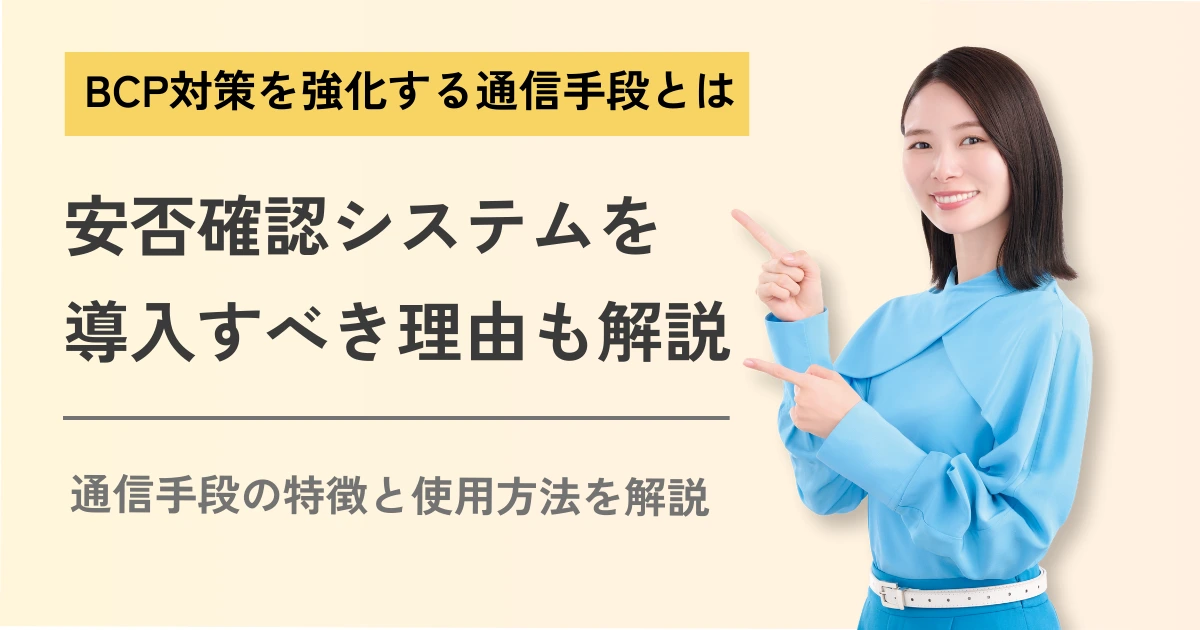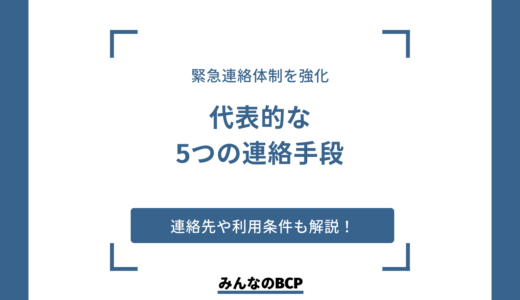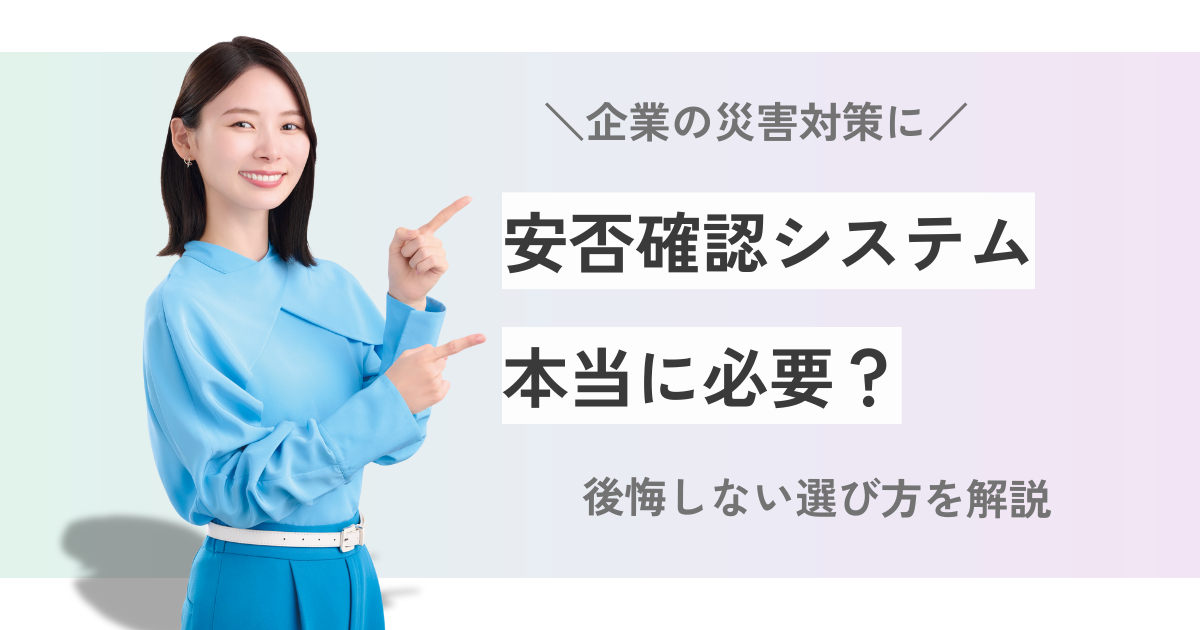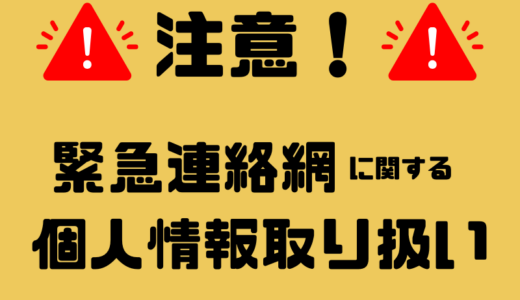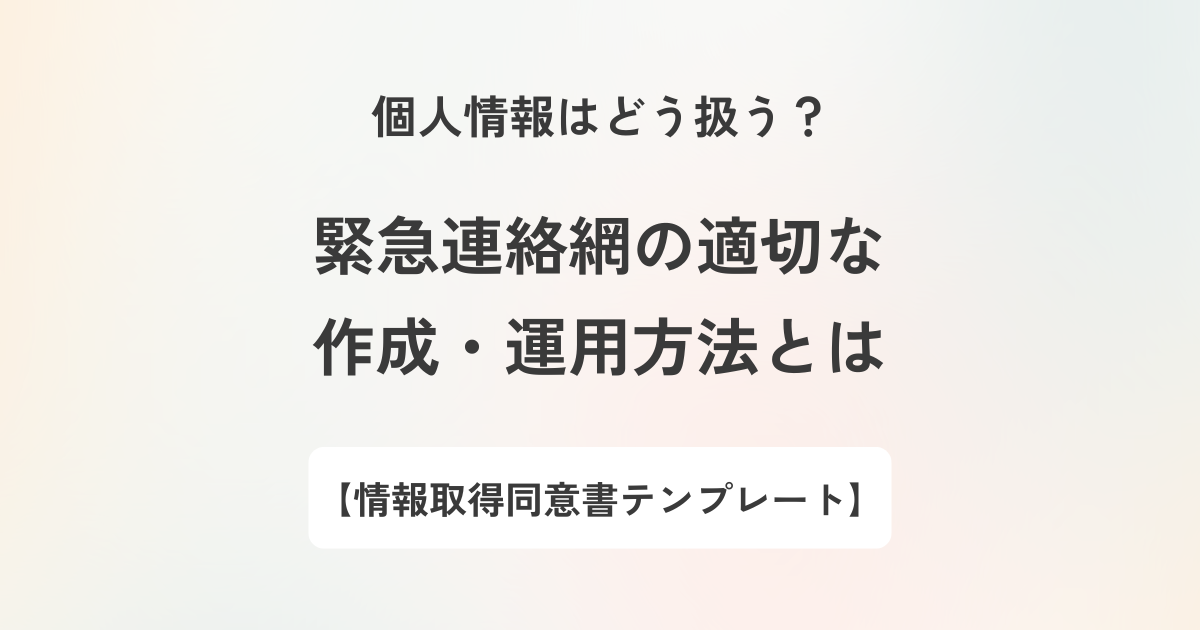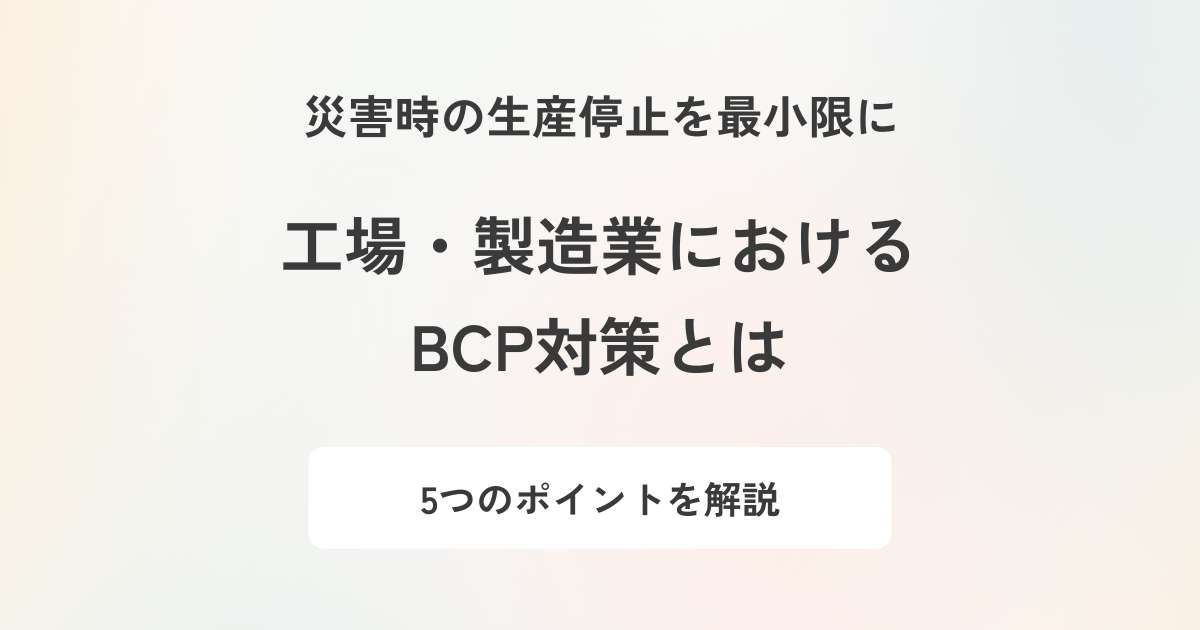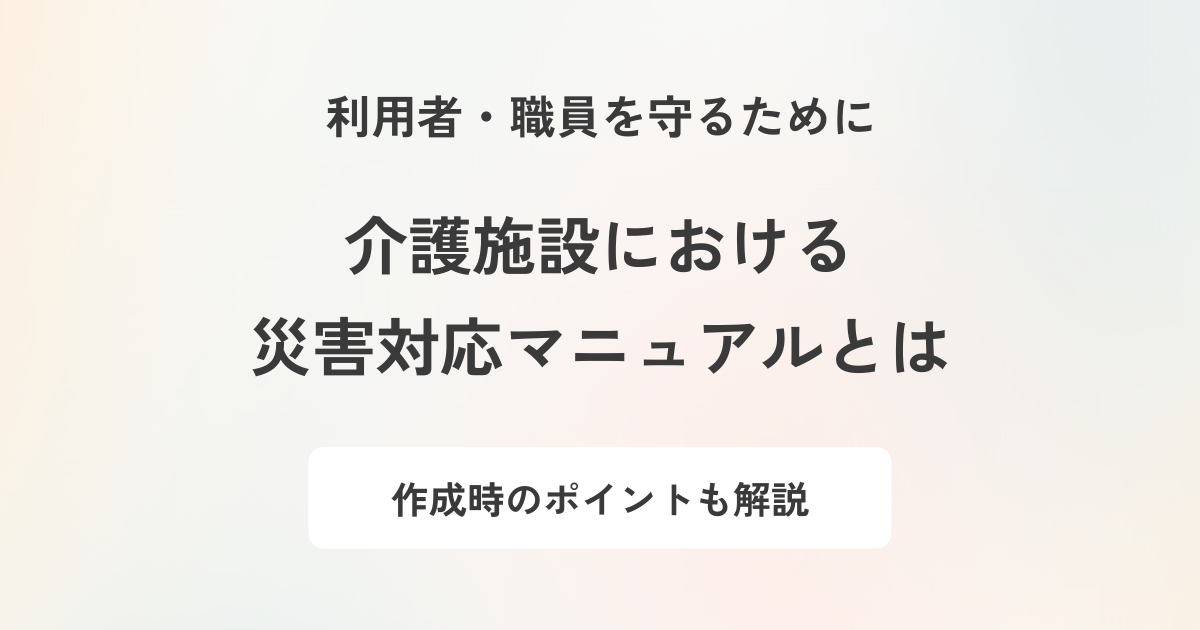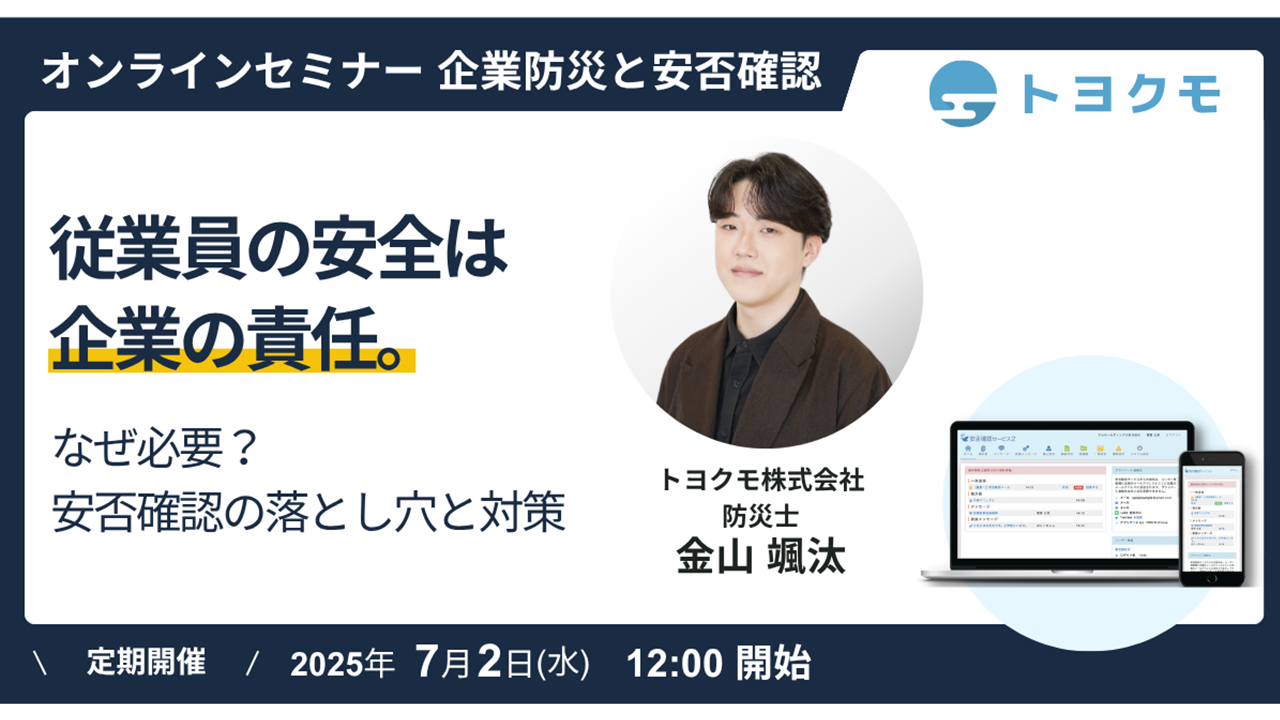災害時に有効な緊急連絡先や連絡手段8選!連絡先を扱う際の注意点も紹介

坂田 健太(さかた けんた)

自然災害や感染症の発生などが発生した際、従業員の無事を素早く確認できるよう、事前に従業員から緊急連絡先を聞いておく必要があります。ただし、緊急時は多くの方がメールや電話で連絡を取るため、複数の連絡手段を確保しておかなければなりません。
この記事では、緊急時に役立つ連絡手段や緊急連絡先を扱う際の注意点などに関して、紹介します。リスクマネジメントの強化に取り組んでいる方は、最後までご覧ください。
目次
災害時に有効な緊急連絡先や連絡手段8選
災害の際に役立つ緊急連絡先や連絡手段は以下の8つです。
- 災害用伝言ダイヤル(171)
- 災害用伝言板(Web171)
- iPhoneの緊急SOS
- IP電話
- SNS
- 衛星電話
- IP無線機
- 安否確認システム
個々の特徴や使い方などに関して紹介します。
災害用伝言ダイヤル(171)
災害用伝言ダイヤルとは、スマートフォンや公衆電話、NTTの災害用公衆電話などから利用可能な伝言サービスです。利用手順は以下のとおりです。
- 171にかける
- 録音を選ぶ
- 自宅の電話番号を市外局番から入力する
- 伝言を録音する
電話番号は、被災地域で連絡を取りたい方の電話番号を入力しても問題ありません。伝言の録音時間は1件あたり30秒以内、録音数は最大20件までです。
災害用伝言ダイヤルは相手の電話番号がわかれば、録音の登録・再生ができます。ただし、双方向のコミュニケーションは望めません。
複数人の安否確認を行う機能も搭載されておらず、個人向けの連絡手段といえるでしょう。
災害用伝言板(Web171)
災害用伝言板とはスマートフォンやノートPC、タブレットから伝言情報をテキストで登録できるサービスです。震度6弱以上の地震が発生した際はすぐに利用でき、震度5強以下の場合は電話の通信状況からNTTが利用可否を判断します。
伝言の登録件数は最大20件です。災害用伝言板でメッセージを残す際の手順は以下のとおりです。
- デバイスからWeb171へアクセスする
- 利用規約に同意する
- 電話番号を入力する
- 登録者とメッセージ内容を入力する
ただし、災害用伝言板は災害用伝言ダイヤルと同様、双方向のコミュニケーションは望めません。安否確認を効率化する機能も搭載しておらず、個人向けの連絡手段といえます。
iPhoneの緊急SOS
iPhoneに搭載されている「緊急SOS」機能を利用する方法です。緊急SOSとは外出先で被災した際、警察や救急など、事前に登録しておいた緊急連絡先へ自動的に連絡ができる機能です。
iPhoneの位置情報を利用し、自身が被災した場所や避難場所を知らせます。普段は位置情報をOFFにしていても、緊急連絡先へ連絡する際は自動的にONとなるため、常時位置情報をONにしておく必要はありません。
緊急SOSの設定方法は以下のとおりです。
- ヘルスケアアプリを開く
- プロフィール画像をタップする
- メディカルIDを選択する
- 緊急連絡先の該当項目に情報を入力する
登録した情報は後から編集が可能です。また、カバンやポケットにiPhoneを入れていると、誤作動が起きるおそれがあります。
誤作動が頻繁に起きる場合は、「サイドボタンを5回押して通報する」または「長押ししてから放して通報」など、設定条件を変更しておきましょう。
IP電話
IP電話とは、インターネット回線を利用して音声通話ができるサービスです。スマートフォンやPC、タブレットを利用して相手と通話をします。
IP電話は音声通話の際にインターネット回線を利用するため、基本的に配線工事は必要ありません。通話料も相手との距離を問わず一定の場合が多く、毎月の通信代も抑えられます。
また、文章や画像、動画を交えたコミュニケーションによって、被災状況や避難場所の様子を正確に伝えられる点も魅力です。
一方、通信品質はインターネット回線の影響を大きく受け、アクセス地点によっては速度遅延やノイズの混入などが発生します。
さらに、IP電話は位置情報が特定できないため、110番や119番などにかけられません。警察や救急を要請する際には、別のデバイスを使用する必要があります。
SNS
災害時にLINEやXを使って安否確認を行う方法です。LINEやXは、普段からコミュニケーションツールとして利用している方も多く、使い方に悩まされる可能性は低いでしょう。
LINEを業務に導入している場合、緊急時にグループトークを活用すると複数人の安否を素早く確認できます。
半面、誤送信による情報漏洩やプライバシーの侵害など、LINEを使用するリスクも考えなければなりません。緊急時の連絡手段として活用する際は、従業員からの同意が必要です。
また、Xはリアルタイムの情報を収集できる点がメリットです。ただし、Xを利用する際は、情報を正確に見極める能力が求められます。投稿内容が必ずしも正しい情報とは限らないためです。
フェイクニュースに惑わされないよう、Xで得た情報は1つの参考情報として捉えましょう。
衛星電話
衛星電話とは衛星電話専用の端末やスマートフォンを利用し、通信用の人工衛星と直接通信を交わすサービスです。
衛星電話は電波を受信できる範囲であれば、データ通信を交わせる点が特徴です。災害が発生した際、山間地や離島など、電波が届きにくい地域で働く従業員の安否も確認できます。
一方、屋内や都市部は障害物が多く、電波がつながりにくい可能性が高いです。屋内で安定して通信を行うには、屋内アンテナの設置が必要です。
また、使用頻度が少ない割に料金が高いため、資金力が豊富な企業向けの選択肢といえます。
IP無線機
IP無線機とは、携帯電話のインターネット回線を利用して音声通信を行う無線機です。従来の無線機と異なり、通信の際に基地局を経由しません。携帯電話のサービスエリア内であれば通信のやり取りが交わせるため、災害時でも従業員との連絡が取りやすいです。
グループ通話や全体通話など、複数の相手と同時にコミュニケーションが取れるため、安否確認を素早く終えられる点もメリットです。IP無線機の多くはGPS機能を搭載しており、管理者は従業員の避難場所を正確に把握できます。
また、IP無線機は利用する際、免許や登録申請が必要ありません。導入に必要な手続きも少なく、すぐに運用できます。資金力や企業規模を問わず、導入しやすい連絡手段といえるでしょう。
安否確認システム
安否確認システムとは自然災害や火災の発生時など、緊急時に従業員の安否を素早く確認できるシステムです。専用アプリやLINEなど、メールや電話以外の連絡手段に対応可能なシステムが多く、緊急時の連絡手段を確保できます。
サーバーの分散運用やネットワーク環境の冗長化など、強固な災害対策を講じているベンダーが多く、大規模災害の際も安定稼働を望めます。
また、安否確認メールの送信〜回答結果の集計まで、一連の作業をシステムに任せられるため、管理者が作業を行う必要はありません。管理者の負担軽減に加え、被災状況を問わず安否確認が行える体制を確立できます。
災害時の緊急連絡先・連絡手段に安否確認システムが適している5つの理由
安否確認システムを導入すべき理由には、以下5つの内容があげられます。
- 従業員との連絡手段を確保しやすい
- 大規模災害時もインターネット回線は機能している
- 従業員に安全確保を素早く促せる
- 安否確認を効率化できる
- 事業再開に向けた準備に移りやすい
理由を詳しく見ていきましょう。
従業員との連絡手段を確保しやすい
安否確認システムは専用アプリやLINEなど、複数の連絡手段に対応したシステムが多く、緊急時に従業員と連絡が取れる確率が高まります。自然災害や台風などが発生した際、企業は従業員の安否を素早く確認することが重要です。
労働基準法や労働安全衛生法にもとづき、企業は従業員の安全確保に努めなければなりません。ただし、緊急時の連絡手段が電話とメールだけの場合、従業員と連絡を取れない可能性が高まります。
大規模災害が発生した際は多くの方が家族や子ども、両親の安否を電話で確認するため、トラフィック量が大幅に増加します。トラフィック量とは、電話回線やネットワーク回線上で交わされるデータ量です。
東日本大震災の際、トラフィック量が通常時の50〜60倍以上まで増えました。トラフィック量が電話回線の容量を大幅に超えると、大手キャリアの各社が通信規制を設けるため、音声通話が通常のように利用できなくなります。
通信規制を設ける理由は、重要通信のスムーズなやりとりとネットワーク環境を維持するためです。実際、東日本大震災の際は、ドコモ・au・ソフトバンクで、70〜95%の音声通話が規制されていました。
また、メールもデータ通信量がサーバーのスペックを大幅に超えると、通信障害が頻繁に発生します。
上記の理由から緊急時の連絡手段には、複数の連絡手段に対応した安否確認システムの導入がおすすめです。
大規模災害時もインターネット回線は機能している
大規模災害が起きてもインターネット回線は機能している可能性が高く、安否確認システムの機能を通常時と同様に利用できます。
東日本大震災の際も、津波被害が極端に大きかった地域を除き、インターネット回線は機能していました。当時はXやLINE上で津波警報や避難の呼びかけが、盛んに投稿されていました。
東日本大震災後の調査で、津波被災地で通信サービスが利用できなくなった原因が、停電の影響が大きかったことが判明します。調査結果を受け、大手3大キャリアは停電対策の強化に取り組みました。
予備電源の長時間対応化、全国各地での大ゾーン基地局の整備などによって、停電が起きても安定して通信サービスが利用できる状態が整いました。予備電源で電力が確保できない場合に備えて、移動電源車の導入も進められています。
また、インターネット回線が利用できない場合に備えて、無料Wi-Fiサービス『00000JAPAN』が開発されました。
00000JAPANとは大規模災害が起きた際、キャリアの契約先を問わず認証不要でWi-Fiのアクセスポイントが利用できるサービスです。利用時間や回数の制限もありません。
停電対策の強化や00000JAPANサービスの開発によって、災害時も安否確認システムを使いやすい環境が整備されています。
従業員に安全確保を素早く促せる
気象庁と連携した安否確認システムを導入すると、自然災害が起きた際、従業員に避難と安全確保を促せます。事前に災害の種類や発生地域、規模など、安否確認メールを配信する条件を設定します。
条件に合致した地震や津波などが発生した場合、従業員の連絡先に安否確認メールと災害情報を自動で送信する仕組みです。
従業員に危険や避難の必要性を素早く通知できるため、命を確保できる確率が高まります。
安否確認を効率化できる
安否確認システムの導入によって、管理者の被災状況を問わず従業員の安否確認を効率的に進められます。安否確認システムの導入によって、安否確認メールの送信や回答結果集計、未回答者への再送信など、一連の作業を自動化できるためです。
事前にBCPを策定していた場合、災害後は管理者が中心になって従業員の安否確認を進めます。
ただし、自然災害の災害規模や発生頻度は予測不可能です。被災状況によっては、管理者が安否確認を進められないケースもあるでしょう。
安否確認システムを導入すると、管理者不在でも従業員の安否確認を素早く進められます。
事業再開に向けた準備に移りやすい
掲示板やメッセージ機能を実装した安否確認システムの導入によって、従業員とスムーズにコミュニケーションを交わせます。事前に策定したBCPの掲載もできるため、事業復旧に向けた流れや今後の作業内容を共有しやすくなります。
また、動画や画像の投稿にも対応しており、管理者は従業員の被災状況の正確な把握が可能です。安否確認メールに出社可否や家族の安否に関する設問を設けておくと、今後のスケジュールを立てやすいでしょう。
従業員の緊急連絡先管理にはトヨクモの『安否確認サービス2』がおすすめ
安否確認システムを導入すると、従業員の緊急連絡先をまとめて管理できます。トヨクモの提供する『安否確認サービス2』は、導入実績4,000社以上を誇る安否確認システムです。
緊急連絡先の登録に必要な作業は、従業員の個人設定にあるメモ欄を活用するだけです。緊急連絡先報告書の用意や従業員に記入を依頼する必要はありません。従業員の緊急連絡先はシステム上に一元管理されるため、個人情報を管理する手間を削減できます。
また、『安否確認サービス2』は気象庁と連携しており、地震や津波、特別警報が発生した際、緊急連絡先に安否確認メールと災害情報が送信される仕組みです。専用アプリやLINEなど、複数の連絡手段に対応しており、従業員の安否を素早く確認できます。
さらに、毎年防災の日にすべての契約企業を対象に、全国一斉訓練を実施しています。
全国一斉訓練とは、実際の災害時と同等の負荷をシステムに与え、システムが安定して稼働するかを確認する訓練です。
訓練結果が、トヨクモの導入するサービス品質保証制度(SLA)を下回ったことはありません。大規模災害が起きた際も安定稼働が期待できるでしょう。
緊急連絡先の管理工数削減や災害対策強化に取り組んでいる方は、『安否確認サービス2』の導入をご検討ください。
緊急連絡先の管理に『安否確認サービス2』が適している4つの理由
安否確認サービス2を導入すべき理由は以下の4つです。
- セキュリティ対策が充実している
- メールアドレスの有効性を定期的に確認している
- 管理者ごとにアクセス権限を制限できる
- 全体的にコストが安い
内容を一つひとつ見ていきましょう。
セキュリティ対策が充実している
『安否確認サービス2』はセキュリティレベルが高く、個人情報の流出リスクを最小限に抑えられます。メールアドレスの暗号化、ログインパスワードのハッシュ化によって、第三者は情報の中身を解読するのが困難な状態です。
システムへのログイン時には2段階認証を適用できるため、不正アクセスやなりすましの脅威を軽減できます。
定期的な脆弱性診断やログデータの取得など、他にもさまざまなセキュリティ対策を講じており、安心して利用できるでしょう。
また、『安否確認サービス2』は、大規模災害が起きてもシステムの安定稼働を望める点が特徴です。メインサーバーはシンガポールで運用しており、日本国内で大規模災害が起きても被害の影響を避けられます。
シンガポールは直近100年間で地震や津波の大規模な被害が記録されていません。電力供給も比較的安定しており、停電の心配が少ない点も魅力です。
メインサーバーはトラフィック量に応じて自動で拡張できるため、災害時にアクセスが急激に増えても、安定稼働が望めます。日本とアメリカでバックアップサーバーを運用しており、データ消失のリスクも心配する必要はありません。
メールアドレスの有効性を定期的に確認している
『安否確認サービス2』では定期的に自動メールを送信しており、登録した緊急連絡先の有効性を確認しています。緊急時に従業員と連絡が取れない事態を避けるためです。
また、迷惑メールと誤判定されないよう、無効なメールアドレスは配信対象から除外し、システムから送信するメールの信頼性向上に努めています。
管理者ごとにアクセス権限を制限できる
『安否確認サービス2』では料金プランを問わず、以下4種類の管理者を設定できます。
システム管理者:安否確認サービス2の管理を担当
危機管理責任者:安否確認サービス2の運用を担当
部門マネージャー:各部署の責任者
マネージャー:役員
管理者の分散や役割分担によって、緊急時の際も従業員とコミュニケーションが取りやすくなります。
上記のうちシステム管理者以外は、ユーザーや部署、管理者の追加は行えません。アクセス制限によって、内部不正やアクセス権の過大付与が原因での情報流出を避けられます。
全体的にコストが安い
『安否確認サービス2』は中小企業が利用しやすいよう、月額料金が比較的リーズナブルな価格に設定されています。仮に従業員が50人以下の場合、プレミアプランまでは月額1万円以下で利用できます。
初期費用や最低利用期間は発生しません。30日間の無料トライアルも用意されており、費用をかけずに機能性や操作性を確認できます。ミスマッチによる無駄な費用の支払いも避けられるため、はじめて安否確認システムを導入する方も安心できるでしょう。
企業における緊急連絡先の重要性
緊急連絡先は以下の非常事態が発生した際に役立ちます。
- 自然災害が発生した際
- 火災が発生した際
- 感染症が発生した際
- テロが発生した際
- 業務中の事故や急病
- 従業員が何日も無断欠席した際
上記以外でも、緊急連絡先は事業継続に関するトラブルが発生したときにも活用できます。従業員の緊急連絡先を把握しておくと、緊急事態が起きた際も迅速な初動対応につなげられます。
地震や津波、豪雨など、自然災害は被害規模や発生頻度が予測できません。最短での事業復旧や従業員の安全確保には、緊急連絡先の把握が不可欠です。
また、従業員によっては、入社時の履歴書に緊急連絡先を記入している場合があります。しかし、入社時から連絡先が変わっている可能性もあるため、定期的な確認が必要です。
従業員の緊急連絡先を取り扱う際の注意点
従業員の緊急連絡先を管理する際は、以下4点に注意しましょう。
- 従業員に利用目的を伝える
- 管理方法を検討する
- 個人情報保護や情報漏洩対策を行う
- 定期的に見直しを行う
トラブルを防ぐため、従業員の合意を取ってから取り組むことが重要です。
従業員に利用目的を伝える
従業員の緊急連絡先を集める際は、利用目的を周知する必要があります。個人情報の開示に抵抗を覚える従業員もいるでしょう。
「緊急連絡先をどのような場面で使用するか」「どのような方法で管理するのか」などを説明し、従業員から理解と同意を得ることが大切です。
事前に同意を得ておくと、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
管理方法を検討する
第三者に悪用されないよう、緊急連絡先は厳重に管理しなければなりません。緊急連絡先の管理方法はオフラインとオンライン、大きく2種類に分けられます。候補となる管理方法を以下の表にまとめました。
| オフライン | オンライン |
| ・印刷して部署ごとに保管・印刷して自宅に保管 | ・安否確認システム上に保管・オンラインストレージ上に保管・USBに保管 |
緊急連絡先は安否確認システムやオンラインストレージなどを活用し、電子データとして保管するのがおすすめです。紙書類で保管していると、洪水や津波で事業所が被災した際、書類が流されてしまう可能性が高まります。
個人情報保護や情報漏洩対策を行う
従業員の緊急連絡先が流出しないよう、個人情報保護や情報漏洩対策を強化します。仮に緊急連絡先が流出した場合、従業員からの信用低下やイメージダウンは避けられないでしょう。
個人情報の取り扱いに関して、国は以下のような基本ルールを設けています。
取得・利用:勝手に使わない
保管・管理:なくさない、漏らさない
提供:勝手に人に渡さない
開示請求などへの対応:問合せに対応する
(参考:「個人情報保護法」をわかりやすく解説 個人情報の取扱いルールとは? | 政府広報オンライン)
オンラインで保管する場合、パスワードの設定やセキュリティ対策ソフトの導入など、最低限のセキュリティ対策は必ず実施するよう求めています。
上記に加えて、アクセス制限や個人情報に関する研修の開催などを行い、内部不正の抑止力を高めましょう。
定期的に見直しを行う
従業員から集めた緊急連絡先は、定期的な見直しが必要です。結婚や転居などによって、住所や連絡先が以前と変わっているケースも少なくありません。
緊急時に連絡が取れない状況を防ぐため、毎年連絡先の変更有無を確認しましょう。また、緊急連絡先が変わった場合は、都度申告する体制を整備しておくことも重要です。
緊急時に備えて従業員の緊急連絡先を把握しておこう
従業員の緊急連絡先を把握しておくと、災害やトラブルが発生した際に従業員とスムーズにコミュニケーションが取れます。最短での事業再開や従業員の安全確保を実現するには、複数の連絡手段を確保しておく必要があります。
緊急時の連絡手段には、安否確認システムの活用がおすすめです。トヨクモの『安否確認サービス2』は、多くの企業に利用されている安否確認システムです。メモ欄を活用するだけで、従業員の緊急連絡先を把握できます。
また、複数の連絡手段への対応や強固な災害対策など、災害時の安定稼働が望める点も魅力です。
緊急連絡先の管理ツールをお探しの方は、『安否確認サービス2』の導入をご検討ください。