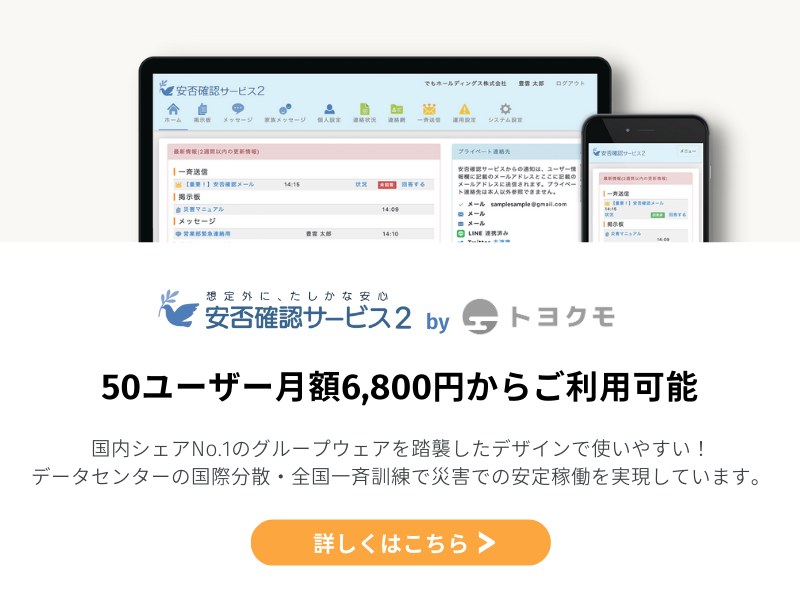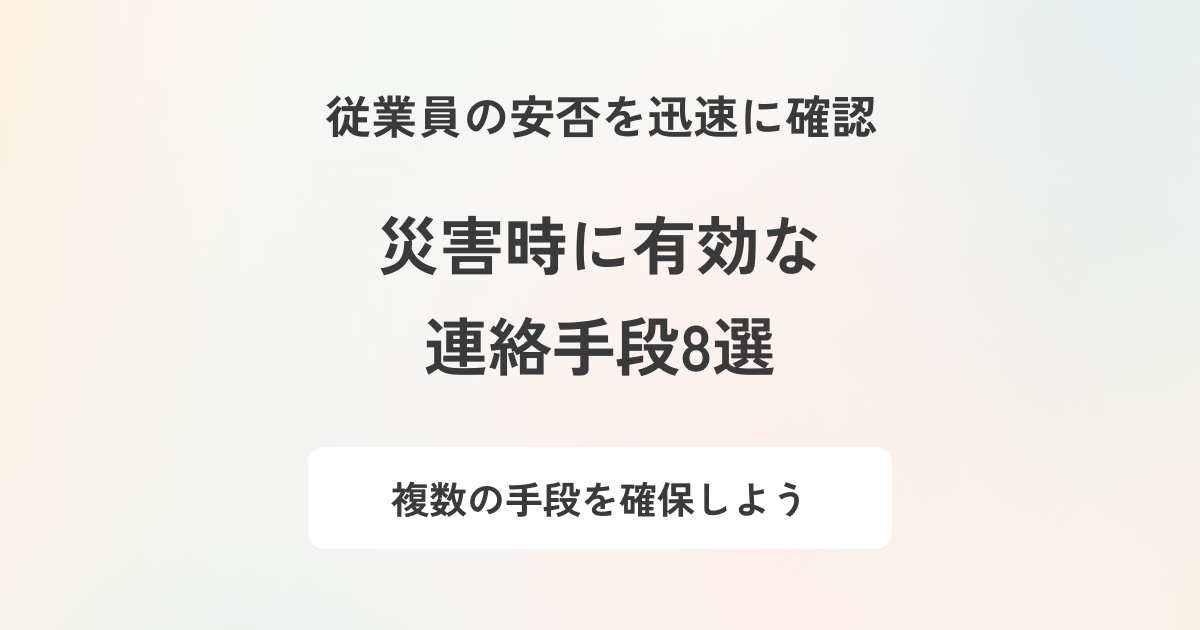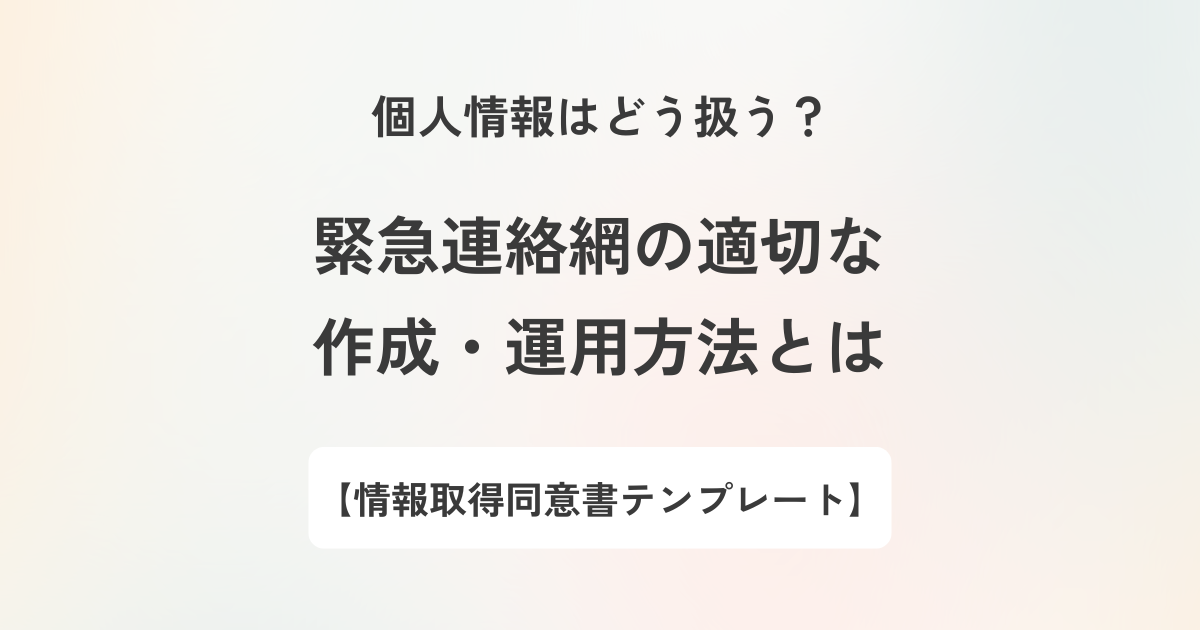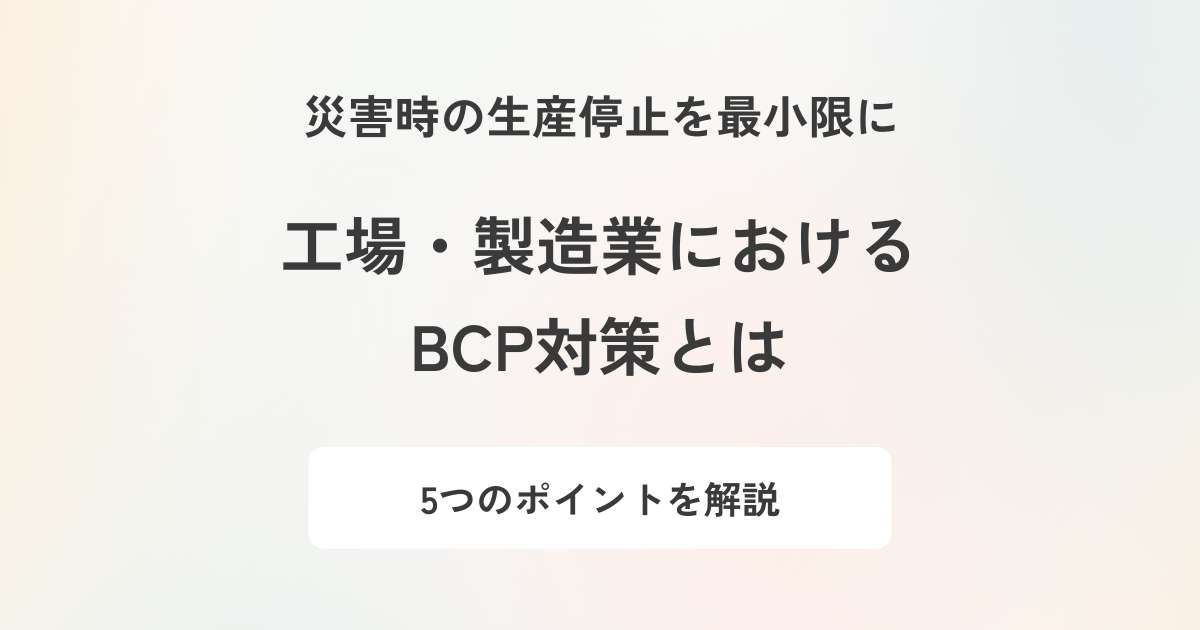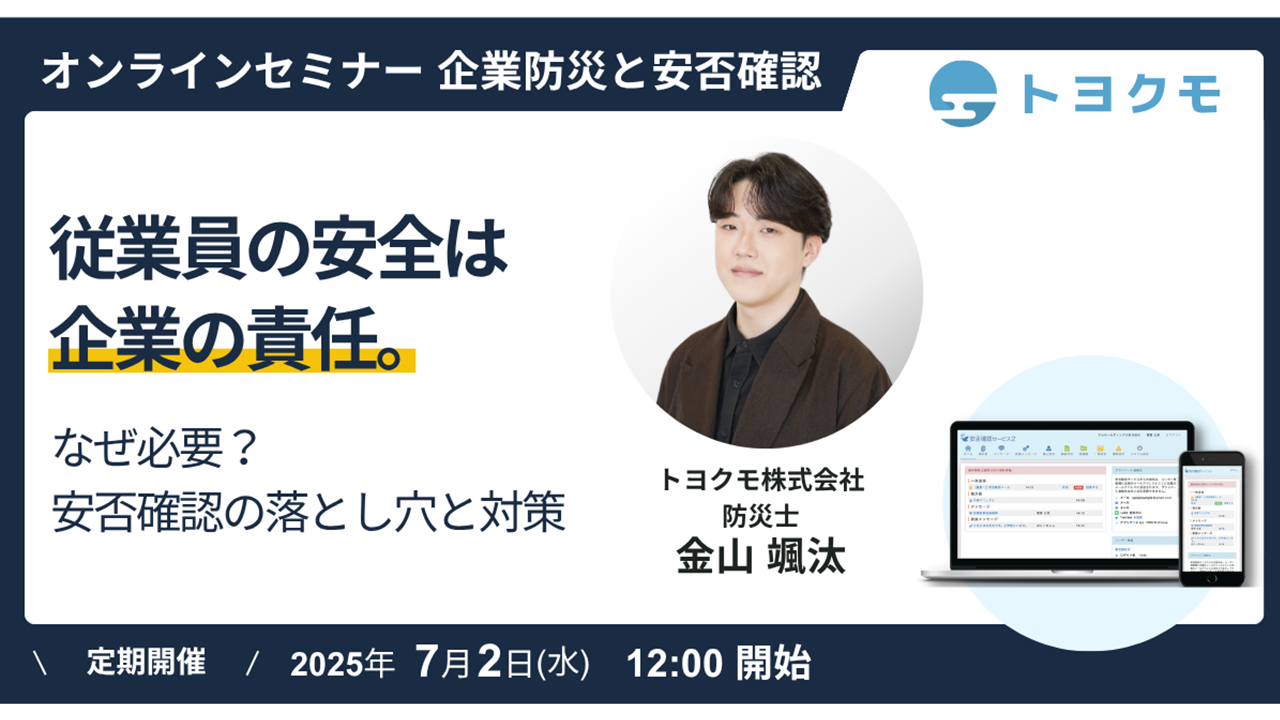サプライチェーンにおけるBCP対策の重要性|対策例や事例を紹介

遠藤 香大(えんどう こうだい)
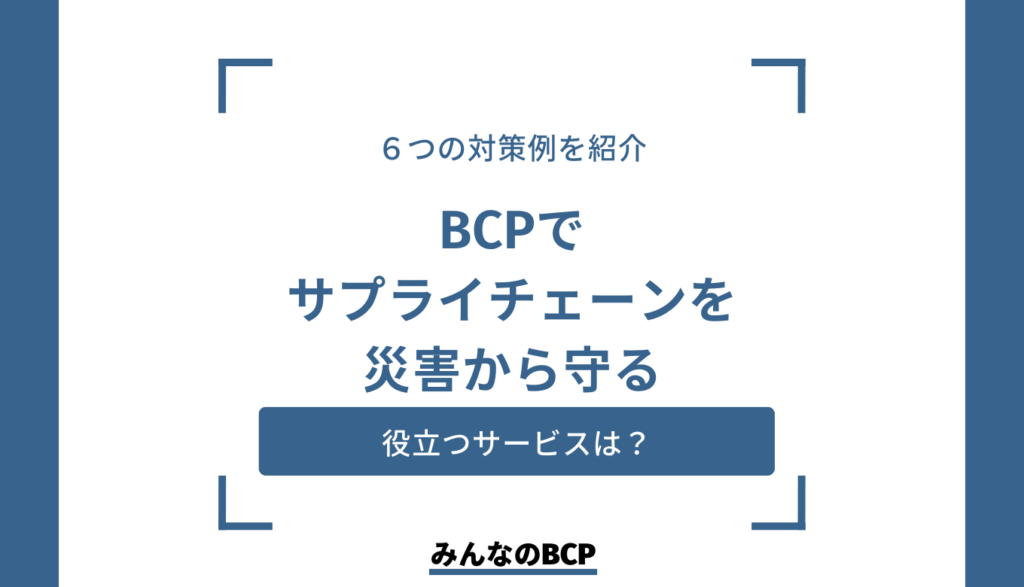
地震大国日本は、災害に備えてサプライチェーンを維持する取り組みが不可欠です。
サプライチェーンでは、一部のトラブルが全体に影響してしまうため、企業だけでなく地域経済や社会にも影響が広がります。
この記事では、サプライチェーンにおけるBCP対策の重要性や、災害などの緊急時にサプライチェーンを維持するための具体的な取り組みについて詳しく解説します。

目次
BCPとは
BCP(Business Continuity Planning)は、自然災害、テロ、システム障害などの緊急事態が発生した際に、企業が事業を継続するための計画です。予期せぬ危機が発生した場合に、企業が被る損失を最小限に抑えて、事業を継続、また事業を早期に復旧することを目的としています。
内閣府の「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によると、2023年における製造業を営む企業でBCPを策定している企業の割合は、58.3%です。年々上昇傾向にはあるものの、策定していない企業が多いのが現状です。
【BCP策定率】
| 2017年 | 2019年 | 2021年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 45.0% | 45.1% | 52.0% | 58.3% |
(参考:「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」)
BCPが普及しない理由
製造業でBCPが普及しにくい理由として、以下が考えられます。
- BCPの重要性や必要性が分からない
- BCP策定に必要なノウハウやスキルがない
- BCPを策定するための人手がない
BCPを策定したことがない場合、ノウハウやスキルがないため、どのように策定してよいか分からないでしょう。また、さまざまな事項を検討しなければならず、策定には多くの時間がかかります。そのため、BCPを策定できる人がいない、策定するための人手が足りないという理由でBCPが普及していないと考えられます。
自社でBCPを策定することが困難である場合には、コンサルティングサービスの利用がおすすめです。プロがBCPを代わりに策定してくれるため、自社にノウハウやスキルがなくてもBCPを策定できます。
トヨクモの「BCP策定支援サービス(ライト版)がおすすめ
トヨクモでは安価でBCPを策定できるサービス『BCP策定支援サービス(ライト版)』を提供しています。一般的なコンサルティングサービスでは数十万円〜数百万円の費用がかかりますが、BCP策定支援サービス(ライト版)ではより低価格で自社に合うBCPを策定できます。また、最短1ヶ月でBCPを策定できる点もおすすめのポイントです。
いつ発生するか分からない災害に備えて、できるだけ早くBCPを策定しておきましょう。ご興味がある方は、ぜひ以下からお問合わせください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
BCP導入の効果
あらかじめBCPを策定しておくと、自社の根幹となる事業を可視化できます。災害発生時に優先して復旧すべき事業が明らかとなり、経営面での被害を最小限に抑えることにつながります。
以下は、事業復旧に対するBCP導入効果のイメージです。
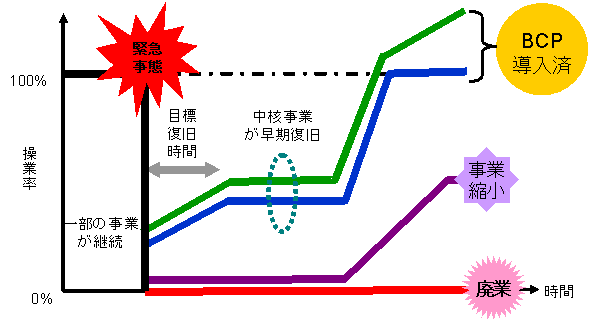
▲出典:中小企業BCP策定運用指針
上記グラフでは、BCPを導入している企業は中核事業を早期に復旧できます。一方、BCPを導入していない企業はなかなか中核事業を復旧できず、事業縮小や廃業に追い込まれていることがわかるでしょう。
緊急事態は突然発生するため、平常時からBCPを策定して緊急事態に備えておく必要があります。事業の縮小や従業員の解雇、廃業に追い込まれないためにも、BCPで中核事業を特定し、事業拠点や生産設備、仕入品調達などの代替策を用意しておきましょう。
(参考:中小企業BCP策定運用指針)
サプライチェーンにおける災害対策の重要性
企業を取り巻くリスクには、自然災害やウイルス感染、人為的リスクなどがありますが、特に近年は地震が頻発化しているため、災害対策を優先して行う必要があります。
大きな地震が発生すると、サプライチェーンの各段階で、さまざまな被害が発生する可能性があります。たとえば、工場や生産施設が被害を受けたり、物流の流れが途絶えたりといった影響が考えられます。
影響を受けるのは被災地周辺だけではありません。サプライチェーンの1つが被害を受けると、影響は他の部分にも波及します。生産や物流の流れが一部で途絶えると、企業は製品の供給ができなくなってしまい、顧客や取引先からの信用も失いかねません。
災害からサプライチェーンを守ることは、事業の継続性を確保し、リスクを軽減するために欠かせない大事な要素です。そのため、BCPの導入でサプライチェーンの災害対策を徹底し、リスク管理に努めましょう。
サプライチェーンを災害から守るBCP対策例6つ
災害からサプライチェーンを守る6つの手段を解説します。
- BCPを策定する
- 生産拠点を分散する
- 頑丈な流通網を確保する
- 災害時の生産体制を整える
- 災害時の需給バランスを想定したデータを蓄積する
- 競合他社との連携及び協定を結ぶ
BCPを策定する
BCPを策定することにより、サプライチェーンに潜んでいるリスクを特定し、それらの対応策を考え、災害に備えられます。災害発生時にも、事前に準備した対応策を迅速に実行すれば、リスクを軽減できるでしょう。
たとえば、代替品や代替手段の確保や、生産プロセスの変更などを行えば、サプライチェーンの各プロセスにおける被害を最小限に抑えることにつながります。
さらにBCPを策定しておくと、災害が発生しても、事業の継続が可能だと客観的に示すことができます。事業の継続性は、顧客や取引先との信頼関係を維持するためにも非常に重要です。
生産拠点を分散する
生産拠点を分散させることは、サプライチェーン全体を守る方法として有効です。地理的な条件が異なる地域や海外などに地域を分けて複数の生産拠点を配置しておけば、生産拠点全体が災害の影響を受けることを回避できます。
さらに、異なる地域で生産することによって、製品や生産量を販売地域に合わせて生産できます。
ただし、コストやリスク管理の観点から見ると、生産拠点を分散させるのは容易ではありません。それぞれの拠点での品質管理を統一する工夫や、製品の輸送や在庫管理などを適切に行うなどの対応が必要になります。
頑丈な流通網を確保する
頑丈な流通網を構築することは、災害時のサプライチェーンの継続性確保にとって重要です。サプライチェーン内の特定の地域で発生した災害によって、製品供給が途絶えるリスクを回避するなど、調達リスクを低減することにつながります。
また、流通網を整えておくと、物流拠点や輸送ルート、倉庫などの情報を集約し、サプライチェーン全体の状況が把握しやすくなります。災害が発生した際に、別の物流拠点を利用したり、代替輸送ルートを利用したりなど、迅速な対応が可能です。
災害時の生産体制を整える
災害が発生した場合、被災した生産拠点での生産が一時停止する可能性があります。このような事態に迅速に生産を再開できるよう、生産体制を整えておくことが重要です。
たとえば、停電などに備えて、非常用の電源を確保したり、電源をバックアップするシステムを導入したりなどの対策が考えられます。
さらに、代替生産ラインを整えておき、代替部品・材料を用意するなどの体制を整えておくことも、リスク回避のために必要です。サプライチェーンで部品や材料の供給が途絶えないよう、対策しておきましょう。
災害時の需給バランスを想定したデータを蓄積する
災害時にはどのような需要が高まり、どのような供給が必要となるかといった、需給バランスを想定したデータを蓄積しておくことも重要です。過去の災害時の需要動向や、地域ごとの需要特性などを分析し、需要予測データを蓄積することにより、需要の急増にも柔軟に対応できます。
データを蓄積するには、物流インフラの中断に備えて、在庫状況を正確に把握しておくことが大切です。日頃から在庫数、在庫場所、製品の消費期限などのデータをしっかり管理しておけば、需要変動への迅速な対応につながります。
競合他社との連携及び協定を結ぶ
サプライチェーンを守る取り組みとして、自社のグループ企業との連携はもちろん、競合他社との連携も検討する必要があります。競合他社との連携や協定によって、より強いサプライチェーンを構築することにつながるからです。たとえば、災害時には競合他社と製品や在庫、輸送手段を共有できるでしょう。
顧客や取引先への責任を果たし、信用を維持するためにも、平時から競合他社との連携を深める取り組みは欠かせません。
ただし、競合他社との協力には、情報共有や信頼関係の構築など、多くの課題があります。そのため、事前に十分な競技や調整を行い、信頼関係を築くことが重要です。
BCPの重要性がわかるサプライチェーンの事例
ここでは、BCPの重要性がわかるサプライチェーンの事例を紹介します。
トヨタ自動車
自動車は原材料の生産から製造の流れにおいて、いくつもの工場を通過して組み立てられます。
トヨタ自動車は震災により、北海道にある工場が操業できなくなったことにより、前後の工程を担う工場に影響が出てしまい、結果的に全国にあるすべての工場の操業をストップする事態となりました。自動車製造がストップすると、自動車販売の機会損失につながってしまいます。
2011年に発生した東日本大震災では、被害総額は約16兆9000億円にのぼると内閣府が推計しています。ここまで被害総額が大きくなった原因の1つには、サプライチェーンの分断が挙げられます。
東日本大震災での被害総額が大きい理由は、被災地域が多かったからだけではありません。企業が、部品などの供給拠点を多く持つようになったことや、他社に製造を委託していたことが挙げられます。
メーカーによっては、被災地以外の工場も操業できなくなり、結果的に被害総額が大きくなったと分析されているのです。
森永乳業
森永乳業では、災害による停電で工場や冷蔵設備が停止し、自家発電設備のない倉庫の冷蔵品を廃棄する事になりました。
北海道は日本の生乳生産率の半数以上を占める酪農拠点ですが、停電による冷蔵設備の停止の他、搾乳もままならない状態であったため、牛乳やバターなどの乳製品の供給に影響が出ることが懸念されています。
サプライチェーンBCPに役立つサービス
ここでは、サプライチェーンBCPに役立つサービスとして、以下の2種類のサービスを紹介します。
| 概要 | |
|---|---|
| 安否確認システム | 災害発生時などの緊急時に従業員に安否確認を行う。緊急対応できる人数を迅速に把握できるため、事業の早期復旧に役立つ |
| BCP策定サービス | コンサルタントがBCPを策定してくれる。自社に策定のノウハウがない場合や策定する余裕がない場合におすすめ |
安否確認サービス2
トヨクモの『安否確認サービス2』は、初期費用0円で始められる安否確認システムです。これまで4,000社以上で導入されており、サービス利用継続率は99.8%を誇ります。
災害が発生した際に登録したメールアドレスや専用アプリに自動で通知を送信します。オプションのLINE連携機能を利用すれば、LINEメッセージで通知を受け取ることも可能です。
また、安否確認の通知に未回答の従業員に対して、自動で通知を送信できる点も特徴です。一定時間が経過した際に自動で再送信されるため、未回答者の人数を最小限に抑えられます。
| 初期費用・解約費用(税抜) | 0円 |
| 月額費用(税抜) | ライト:6,800円/プレミア:8,800円/ファミリー:10,800円/エンタープライズ:14,800円 |
| 最低利用期間 | なし |
| 主な機能 | 外部システム連携/通知条件の設定/予行練習/自動一斉送信/回答結果の自動集計/家族の安否確認/災害以外のお知らせ送信ほか |
| 無料お試し | あり(30日間の無料お試し) |
BCP策定支援サービス(ライト版)
さまざまな企業がBCP策定サービスを提供していますが、費用を抑えたい場合にはトヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト)』がおすすめです。
一般的なBCP策定サービスは、数十万円〜数百万円と高額な費用が発生します。しかし、BCP策定支援サービス(ライト版)であればより安価に策定できるため、費用を大幅に削減することが可能です。また、BCPを策定するだけではなく、緊急時に活用しやすいポケットサイズのマニュアルも作成している点もおすすめのポイントです。
以下のリンクからBCP策定支援サービス(ライト版)に関する資料をダウンロードできます。興味がある方はぜひダウンロードしてください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
BCP策定は、災害時のリスクを最小限に抑える最適な対策
災害時のサプライチェーンを守る重要性をお伝えしました。サプライチェーンでは、一部のトラブルが全体に影響して、事業が中断するリスクがあります。
特に災害時はサプライチェーンの一部に支障が出るリスクがあります。災害はある日突然起こるため、普段からの対策が必要です。事前に災害時を想定した計画を立て、できる限りの対策を施しておきましょう。
災害時のサプライチェーンの維持に有効な手段が、BCPの策定です。BCPを策定することにより、サプライチェーンにおける重要な機能やプロセスを特定し、事業を維持する対策を講じることができます。まだBCPを策定していない場合には、コンサルティングサービスを活用するなどして、BCPを策定しましょう。
また、安否確認システムもBCP対策に有効です。災害時に自動で通知を送信し、緊急対応できる人数を迅速に把握できるため、すぐに次のアクションに移れます。費用を抑えて導入したい場合には、トヨクモの『安否確認サービス2』の導入を検討してみてはいかがでしょうか。