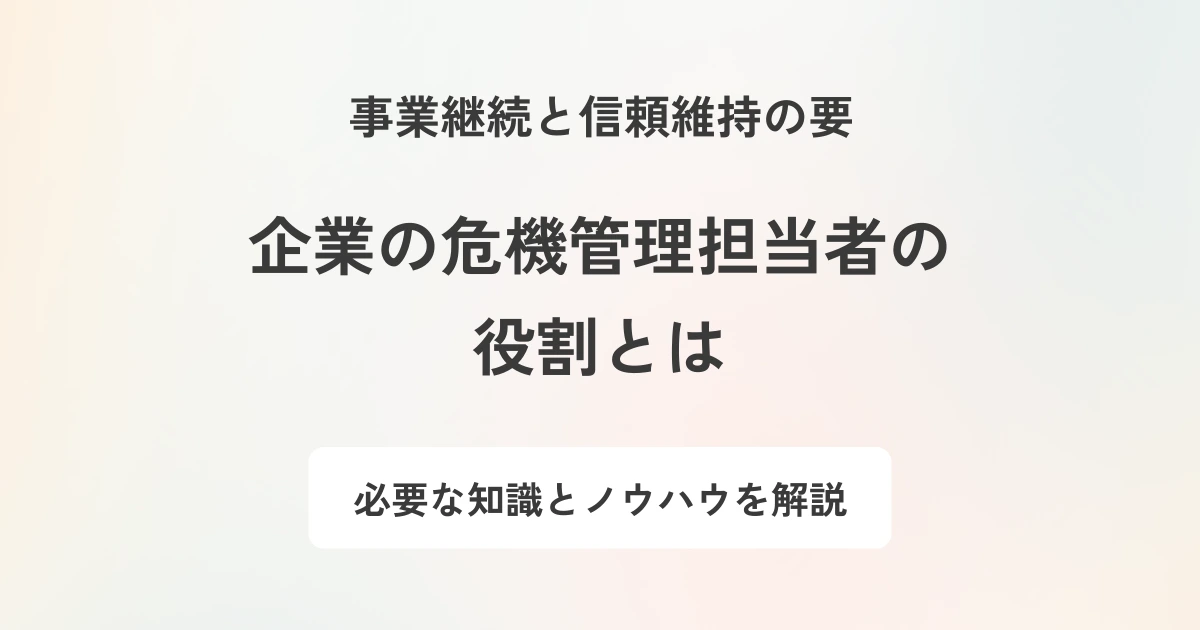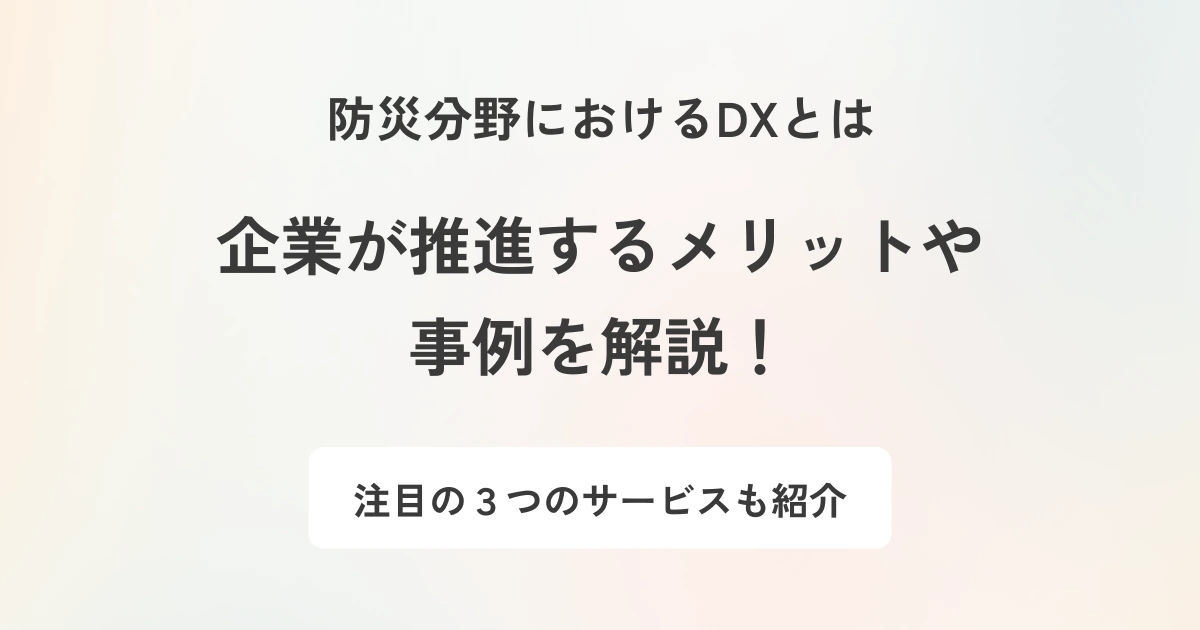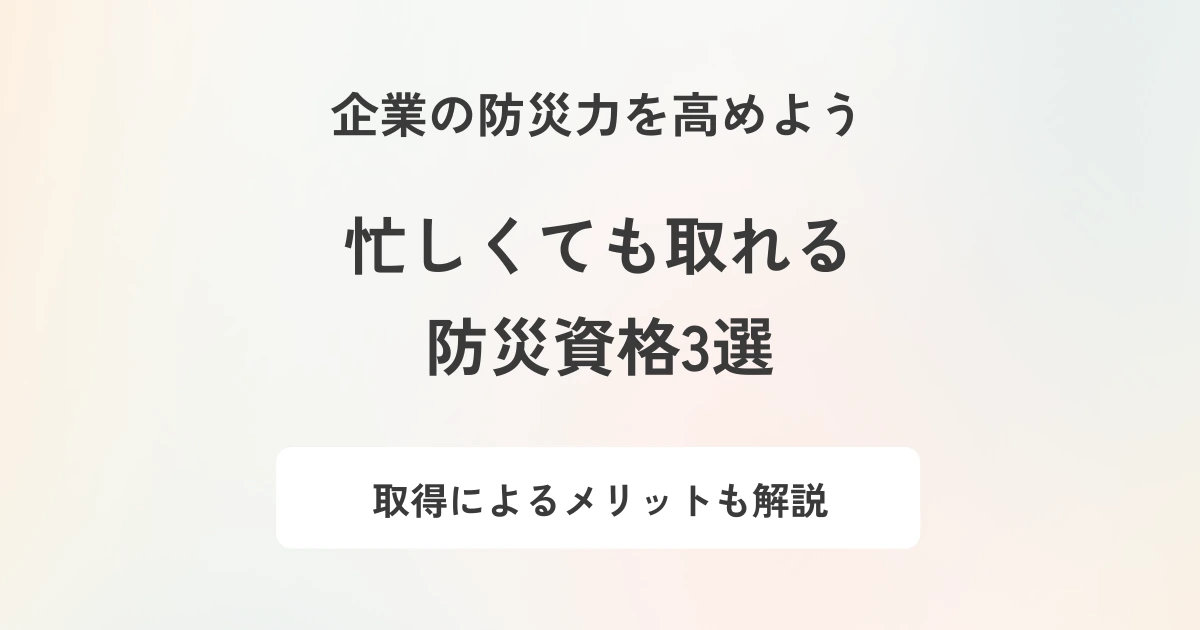企業の防災担当者になったら何をする?役割や情報収集の方法を紹介

トヨクモ防災タイムズ編集部
近年、地震や台風などの自然災害が頻発し、企業の防災対策はますます重要になっています。しかし、多くの防災担当者は「何をすればいいのか分からない」または「時間がない」といった悩みを抱えているでしょう。
本記事では、防災担当者になったら何をするべきかを解説し、求められるスキルや平時の役割、情報収集の方法までを紹介します。この記事を読めば、あなたも自信を持って防災対策に取り組めるはずです。

目次
防災担当者になったら何をすべきか
防災担当者になった場合、災害時に従業員と事業を守るための対策をとり、災害発生時には防災担当者が中心となり従業員を誘導することが必要です。
ここでは、防災担当者が行うべき具体的な内容を紹介します。
ハザードマップで災害リスクを把握
ハザードマップは、自然災害による被害予測を地図化したものを指します。防災担当者は、まず自社および周辺地域のハザードマップを入手し、想定される災害リスクをしっかりと把握しましょう。
ハザードマップには、浸水想定区域・土砂災害警戒区域・液状化危険度などが記載されており、これらの情報をもとに災害時の避難経路や避難場所、備蓄品の必要量などを検討する必要があります。ハザードマップは定期的に更新されるため、最新の情報を常に把握することが重要です。
社内の設備・備品を確認
自然災害だけでなく、社内で起こるリスクも把握しておくことが大切です。たとえば、廊下や通路に避難を阻害するものがあると、スムーズに逃げられません。大きな家具・什器については、地震に備えて固定しておく必要があります。
そのほかにも、実際に災害が起きたときを想定して、避難の妨げになるものがないかチェックしておくことが大切です。とくに、パソコンを多く利用しているオフィスでは、デスクトップPCやコピー機の転倒なども懸念されるので注意しましょう。
近隣の避難場所を確認
災害発生時、従業員や来訪者の安全を確保するため、近隣の避難場所を事前に確認しておくことは防災担当者の重要な役割です。避難場所は、災害の種類や規模に応じて適切に選定する必要があり、複数の避難場所を確保しておくことが望ましいでしょう。
避難場所までの経路や所要時間、収容人数や設備などを細かく確認し、従業員に周知しておきましょう。また、避難訓練を実施することにより、実際の災害時にスムーズな避難行動を促せます。
BCP(事業継続計画)の策定
BCP(事業継続計画)とは、災害などの緊急事態が発生した場合でも、企業が事業を継続・早期復旧するための計画です。防災担当者は、BCP策定の中心的な役割を担い、事業への影響を最小限に抑えるための対策を検討する必要があります。
BCPには、緊急時における従業員の安否確認や代替オフィスの確保、取引先との連携、情報システムのバックアップなどが含まれます。BCP策定後には定期的に見直し、訓練を実施して実効性を高めることが必要です。
防災担当者に求められるスキル
企業の防災担当者には、以下のようなスキルが求められる傾向です。
- コミュニケーション能力
- 情報収集能力
- リーダーシップ
- 防災関連の基本的な知識
災害発生時、関係機関や従業員との連携が不可欠であり、円滑な情報伝達や指示出しを行うためのコミュニケーション能力が求められます。災害に関する最新情報や防災技術、関連法令などを常に把握し、適切な対策を講じるための情報収集能力も必要です。
また、従業員の安全確保や事業継続のために、的確な判断と指示を行うリーダーシップも求められます。そのほか、防災に関する基本的な知識を身につけ、従業員や企業の事業継続を守ることも必要です。
防災担当者の平常時の役割
続いて、防災担当者の平常時の役割を見ていきましょう。
防災計画の策定
防災担当者は、企業の特性やリスクを考慮し、適切な防災計画を策定する必要があります。計画策定にあたっては、従業員の安全確保を中心に、事業継続や地域社会との連携など、多岐にわたる要素を検討しましょう。
また、計画は定期的に見直し、訓練を通じて改善を図ることが重要です。防災計画は、企業の規模や業種によって異なるため、専門家の意見を参考にしながら、自社に最適な計画を策定することが望ましいと考えられます。
防災訓練の企画・実施
防災訓練は、災害発生時に従業員が適切に行動できるよう、事前に準備するための重要な活動です。防災担当者は、訓練の目的・内容・参加者・日時などを明確にし、効果的な訓練を企画・実施するのが役割となります。
また、訓練後には必ず振り返りを行い、改善点を見つけることが重要です。訓練を通じて従業員の防災意識を高め、緊急時に冷静に行動できる体制を構築することも防災担当者の重要な役割の1つとなります。
防災用品の管理
防災用品は、災害発生時に従業員の安全を確保し、事業継続を支援するための重要な備品です。防災担当者は、必要な防災用品の種類・数量・保管場所・点検方法などを明確にし、適切に管理することが求められます。
防災用品には、食料・飲料水・救急用品・情報収集機器・ヘルメットなどが含まれます。備蓄品の保管場所は、災害時に安全にアクセスできる場所を選定し、定期的な点検と入れ替えを行いましょう。
従業員へのBCPの周知
BCPは、策定するだけでなく、従業員に周知を徹底することが重要です。従業員がBCPの内容を理解し、緊急時に適切な行動を取れるようにするため、研修や訓練などを通じて定期的に周知活動を行う必要があります。
周知すべき内容は、BCPの目的・緊急時の連絡体制・安否確認の方法・避難経路・役割分担など多岐にわたります。また、BCPは定期的に見直し、最新の情報に更新しましょう。更新された情報は速やかに従業員に周知し、理解を深めることが大切です。
防災担当者の災害発生時の役割
続いて、実際に災害が発生したときに行うべき行動を見ていきましょう。
安否確認
災害発生時、従業員の安否確認は最優先事項です。防災担当者は、事前に定めた安否確認システムや連絡網を活用し、迅速に従業員の安全を確認する必要があります。安否確認の結果は、速やかに経営陣や関係機関に報告し、必要な支援を行う体制を整えてもらいましょう。
また、安否不明者の捜索や救助活動にも協力し、従業員の安全確保に全力を尽くすことが求められます。安否確認は、従業員の家族への情報提供にもつながるため、正確かつ迅速な情報伝達が重要です。
避難誘導
災害発生時、従業員を安全な場所へ避難誘導することは、防災担当者の重要な役割の1つです。防災担当者は、事前に定めた避難経路や避難場所を把握し、従業員を落ち着いて誘導する必要があります。避難誘導中は、従業員の安全を確保するために、適切な指示や声かけを行い、混乱を防ぎましょう。
また、避難場所では従業員の安全確認や健康状態の把握を行い、必要な支援を提供しなければなりません。避難誘導は、従業員の命を守るために、冷静かつ迅速な判断と行動が求められます。従業員の不安を和らげるように配慮しましょう。
情報収集・伝達
正確な情報を迅速に収集し、関係者に伝達することは、防災担当者の重要な役割です。防災担当者は、気象情報や災害情報、避難情報など、多岐にわたる情報を収集しなければなりません。正確性を確認した上で、経営陣・従業員・関係機関に伝達しましょう。情報伝達手段は、電話やメール、SNSなど複数の手段を確保し、状況に応じて使い分けることが重要です。
また、誤った情報やデマの拡散を防ぐために、情報の出所や信頼性を確認することも忘れてはなりません。情報収集・伝達は、的確な状況判断と迅速な意思決定を支援するために、重要な役割を担います。
応急処置
負傷者への応急処置マニュアルを整備することは、防災担当者の役割です。防災担当者は、事前に応急処置の知識や技術を習得し、適切な処置を行えるようにしておきましょう。災害時に負傷者がいる場合は、状態に応じて、防災担当者が医療機関への搬送や医師の指示を仰ぐなど、適切な対応を取ることが求められます。
応急処置に必要な救急用品や医療機器を準備し、保管場所や使用方法を従業員に周知しておくことも重要です。いざというときに怪我人や病人を救うためには、防災担当者だけではなく、多くの従業員が応急処置の知識とスキルを持っている必要があります。救命活動の講習会の開催、応急処置マニュアルの配布なども効果的です。
防災担当者が知っておくべき情報の収集源
防災担当者が知っておくべき情報の収集源としては、以下のようなものが挙げられます。
- 政府広報オンライン
- 防災情報提供センター
- NHK そなえる 防災
- 各地域の自治体サイト
それぞれのサイトで得られる情報を詳しく紹介します。
政府広報オンライン
政府広報オンラインは、内閣府が運営するWebサイトであり、防災に関する正確かつ最新の情報を提供しています。災害の種類や対策、避難情報や支援制度など、防災担当者が知っておくべき情報が網羅的に掲載されているので、チェックしてみましょう。
また、ハザードマップや防災訓練の実施方法など、具体的な対策に役立つ情報も豊富に掲載されています。政府広報オンラインは信頼性の高い情報源として、防災担当者が常に参照すべきサイトの1つです。
防災情報提供センター
防災情報提供センターは、国土交通省が運営するWebサイトであり、リアルタイムの防災情報を提供しています。地震・津波・洪水・土砂災害など、さまざまな災害に関する情報が地図やグラフで分かりやすく表示されるのも特徴です。
また、過去の災害事例や防災に関する研究成果なども掲載されており、防災対策の参考になります。防災情報提供センターは、災害発生時の状況把握や情報収集に役立つサイトです。
NHK そなえる 防災
「NHK そなえる 防災」はNHKが運営し、防災に関するさまざまな情報を提供しているサイトです。災害の種類や対策、避難情報や防災グッズの選び方など、防災担当者が知っておくべき情報が分かりやすく解説されています。
また、災害発生時のニュースや情報番組も配信されており、リアルタイムの状況把握に役立ちます。信頼性の高い情報源として、防災担当者が常に参照すべきサイトの1つなので、ぜひチェックしておきましょう。
各地域の自治体サイト
各地域の自治体サイトは、地域の防災情報を把握するために重要な情報源です。ハザードマップ・避難場所・避難経路・防災訓練の情報など、地域に特化した情報が掲載されています。自社のオフィスがある地域のサイトなどを確認し、災害に備えましょう。
また、災害発生時の避難情報や支援制度なども提供されます。各地域の自治体サイトは、地域の防災担当者が常にチェックすべきです。こまめに情報は更新されるので、定期的に確認して災害に備えましょう。
BCPの策定・訓練実施で災害に備えよう
この記事では、防災担当者の役割や災害発生時の対応、情報の収集源、そしてBCPの重要性について解説しました。
防災担当者は、平時から防災計画の策定や防災訓練の企画・実施、防災用品の管理など、多岐にわたる業務を担います。また、災害発生時には、従業員の安否確認、避難誘導、情報収集・伝達、応急処置など、迅速かつ的確な対応が求められる役割です。
とくに、災害発生直後の従業員の安否確認は、その後の対応を左右する極めて重要な初動です。しかし、混乱した状況下において全従業員の安否を手作業で確認することは、防災担当者にとって大きな負担となるでしょう。
災害発生時、迅速に従業員の安否確認を行うなら、トヨクモの『安否確認サービス2』がおすすめです。地震発生時に自動で安否確認メールが一斉送信され、従業員は指定のURLから状況を回答するだけで安否確認が完了します。自動集計機能により、リアルタイムで従業員の状況を把握できるだけでなく、メッセージ機能を用いて特定のメンバー同士が連絡を取ることもできる便利なシステムです。防災担当者の業務を効率化し、緊急時にすぐに初動対応ができるようになるでしょう。
ぜひ、この機会に導入をご検討ください。