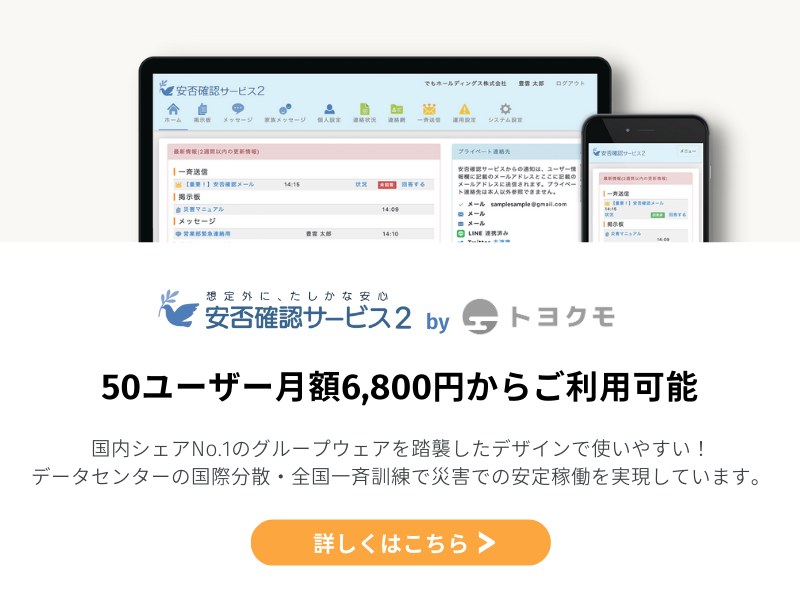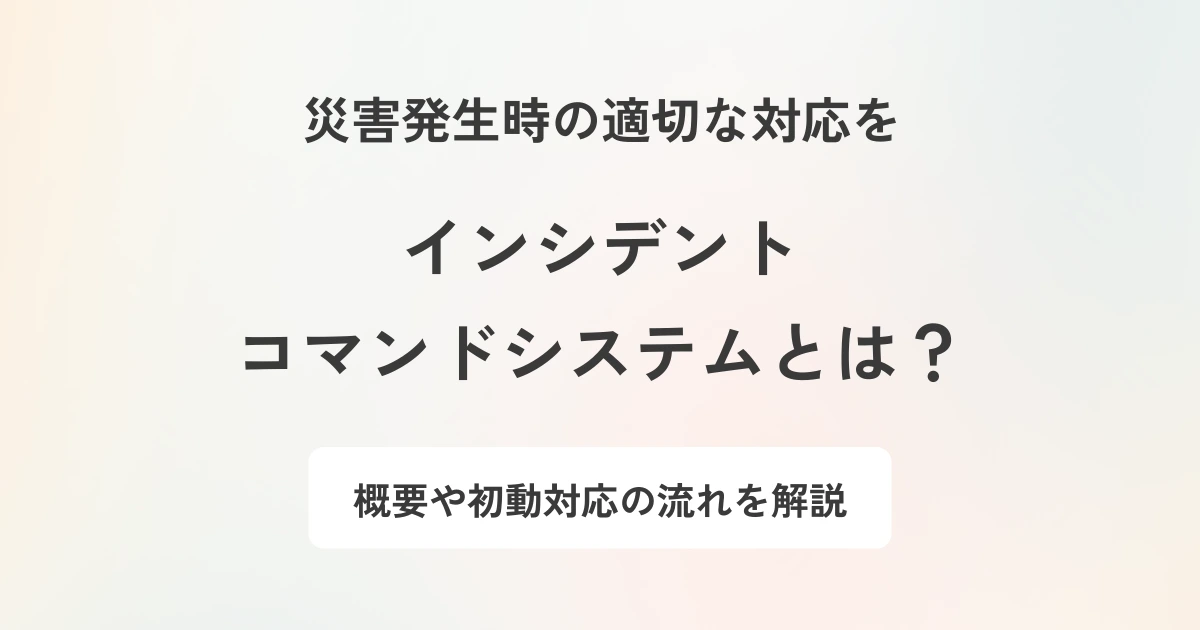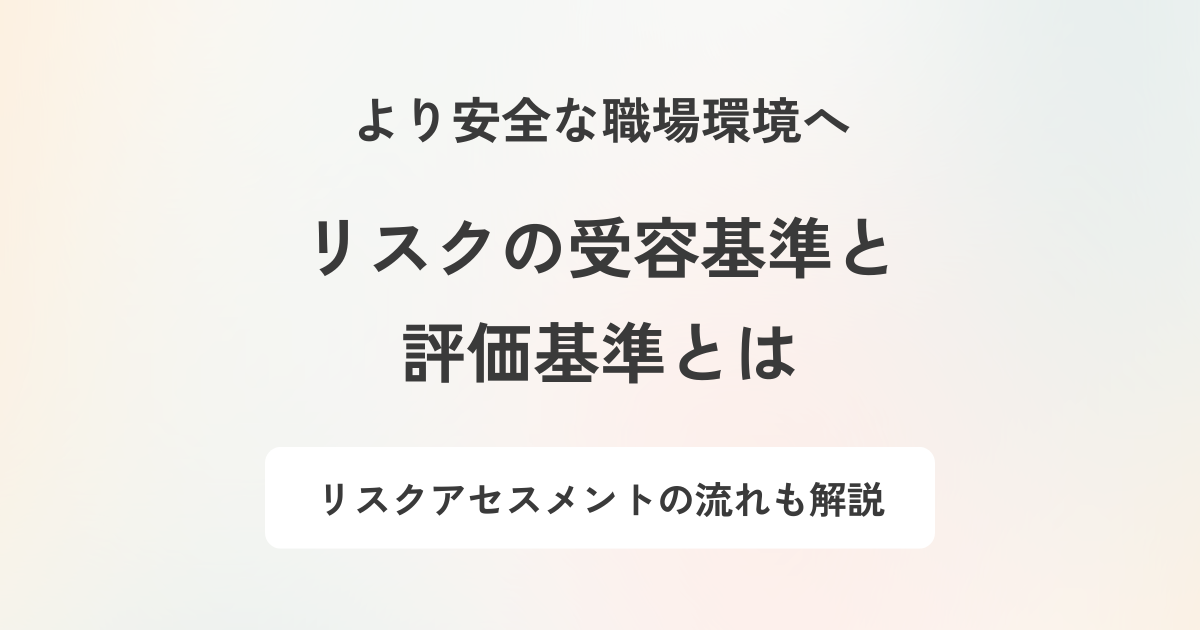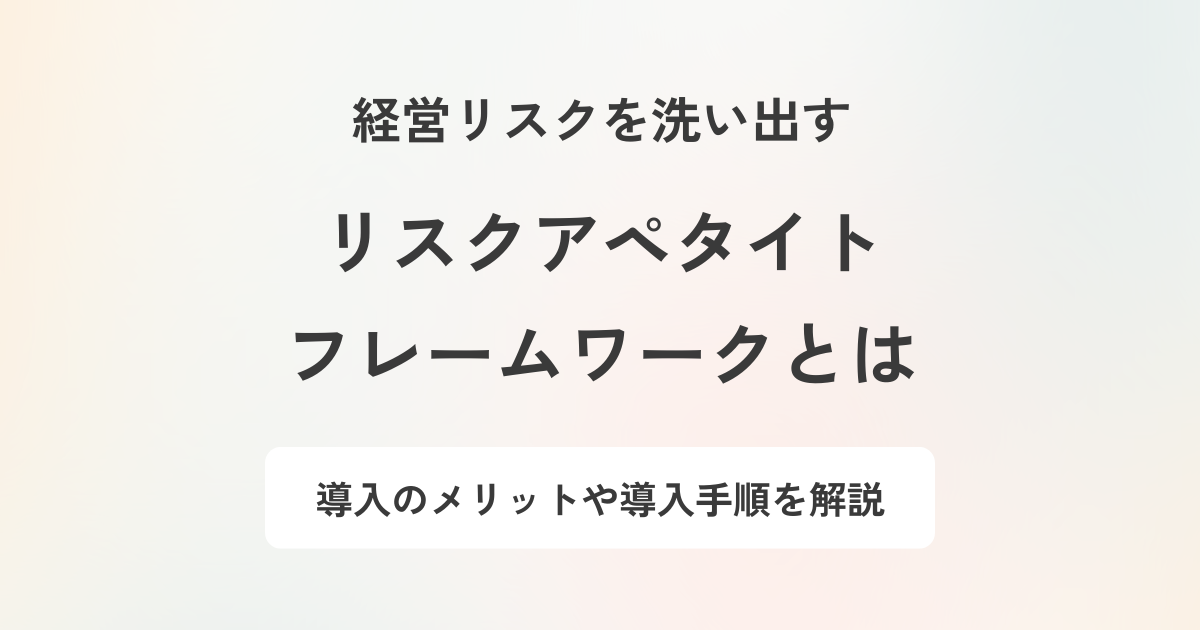CSR(企業の社会的責任)とは?取り組み例やメリットを紹介

遠藤 香大(えんどう こうだい)
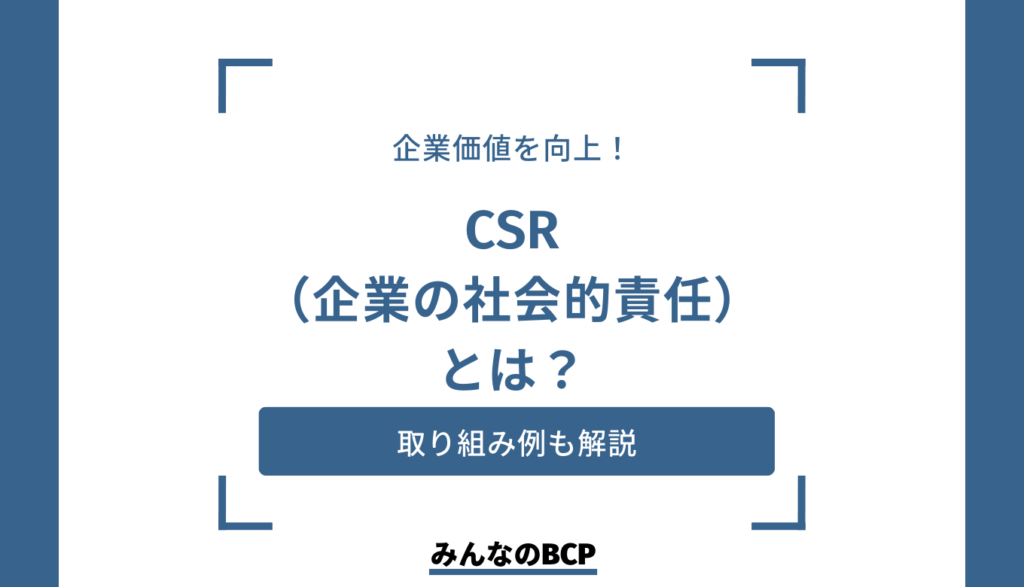
CSRとは、日本語で「企業の社会的責任」を意味する言葉です。CSRへの取り組みはさまざまなメリットをもたらします。しかし、取り組み方が分からないという人も多いでしょう。
重要なのは、CSRのメリットや方法を熟知しておくことです。この記事ではCSRに関して詳しく解説していきます。

兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。
目次
CSRとは
そもそもCSRとは一体何なのでしょう。
ここでは、CSRの概要について解説します。
CSRは「企業の社会的責任」のこと
CSRとは、企業が組織活動を行うにあたって担う社会的責任のことです。社会的責任の具体例としては、従業員・消費者・顧客・取引先・株主などへの責任、環境への配慮、地域社会への社会貢献などが挙げられます。
日本ではしばしば、ボランティア活動と混同されます。しかし、ボランティア活動とCSR活動は大きく異なるものです。ボランティア活動は報酬を目的としていません。一方で、CSR活動は利益追求の有無を問わないのです。
CSRに取り組む目的は、企業のブランディングです。かつて日本では、企業の独善的な行動や不祥事などについて、社会的な批判が強まる場面がしばしばありました。
たとえば1970年代に起こったオイルショックでは、便乗値上げや製品の買い占めなどによって、小売企業に対する批判的なムードが高まりました。
また、2000年代初頭にはバブル後の構造不況のなかで相次ぐ不祥事が問題となり、企業に対する信頼が著しく低下しました。
こうした経緯から、企業が消費者をはじめとした「社会」から信頼を得るための施策として、CSRの考え方が普及しました。
国際規格はISO26000
ISO26000とは、2010年11月1日にISO(国際標準化機構)が発行した国際規格です。ISO26000の目標は、持続可能な発展への貢献を最大化させることです。それと同時に、人権と多様性の尊重という重要な概念も含んでいます。
ISO 26000の特徴として、認証を意図しない手引き書(ガイダンス)である点や、あらゆる組織に役立つよう意図して作られている点などが挙げられます。したがって、ISO26000 は、ISO9001や ISO14001のように規格認証に用いるためのものではありません。
CSRが注目される理由
いまでは当たり前に普及しているCSRですが、注目され始めたのは2000年代です。2000年代前半にバブル後の構造不況のなかで、表示の偽装や意図的な異物混入など、食の安全性が問われる事件が多発しました。これがCSR普及のきっかけです。また近年では、企業活動に伴う環境破壊への批判は、世界的な問題として取り上げられるなど、一層激しさを増しています。
このような経緯からもわかるように、2000年代以降の消費者は、企業の誠意や責任を重視しています。こうした消費者意識の変化に対応すべく、CSRは注目されるようになったのです。
CSRの7つの原則
ISO26000はCSRに関する国際規格です。
企業がCSRに取り組むうえで、下のような原則が必要とされています。
- 説明責任
企業活動が社会に与える影響について、十分に説明する必要があります。
- 透明性
組織による意思決定や活動内容に対して、透明性を持つ必要があります。
- 倫理的な行動
公平性や誠実さなど、倫理観に基づいた行動が求められます。
- ステークホルダーの利害の尊重
株主だけでなく、多様なステークホルダー(利害関係者)に配慮した企業活動が求められます。
- 法の支配の尊重
自社に適用される自他国の法令を尊重し、遵守する必要があります。
- 人権の尊重
重要かつ普遍的である人権を尊重する必要があります。
CSRと「SDGs」との違い
CSRとSDGsもよく混合されますが、両者は全く異なる言葉です。
SDGsとは、Sustainable Development Goalsの略称で、「持続可能な開発目標」を意味します。2030年までに持続可能な経済活動を達成すべく定められた開発目標のことです。国や自治体など、さまざまな主体が取り組んでいます。
SDGsは決められた目標の達成を目的としているため、各主体の方針は似通っていることが特徴です。
一方CSRは、「企業の社会的責任」を意味します。
CSRの目的は、ステークホルダーをはじめとする社会から寄せられる声を聞き、期待を達成することで、ステークホルダーおよび社会からの信頼を獲得することです。
SDGsは国際会議で決定された世界共通の目標であるのに対して、CSRはステークホルダーなどからの要求に対して責任を果たす活動です。そのため、CSRのほうが活動内容を自由に選択でき、方針や取り組み内容にも大きな違いが生まれます。
企業がCSRに取り組むメリット
CSRについて理解はできても、CSRに取り組むメリットが分からない人もいるでしょう。
ここからは、CSRに取り組むメリットについて紹介します。
企業イメージが向上する
CSRを通して社会貢献することで、企業イメージを向上させることが可能です。
東京商工会議所が行った「企業の社会的責任」についてのアンケートによると、大企業の98.3%、中小企業の79.7%がCSR活動の目的として「企業イメージの向上」と回答しています。
企業イメージの向上によって、商品やサービスのイメージのみならず、商品やサービスへの安全性・信頼性も向上させられるでしょう。結果として市場競争力が高まり、利益向上につながると考えられます。
従業員の満足度が向上する
従業員の満足度向上も、CSR活動のメリットとして挙げられます。
自分の行動が社会貢献につながっているという意識は、自社で働くことのモチベーションの向上につながるためです。
東京商工会議所が行った「企業の社会的責任」についてのアンケートでは、大企業の72.9%、中小企業の52.9%がCSR活動に取り組む目的として「従業員の満足度の向上」と答えています。
また、従業員のモチベーションが上がることで、会社全体の雰囲気が明るくなり、求職者への印象も改善できるという副次的な効果も見込まれます。
コンプライアンスを意識できる
CSRに取り組むと、必然的に社内のコンプライアンスチェックにも関わります。そのためコンプライアンスチェックが徹底され、規律違反している業務の早期発見が可能となるでしょう。
早期発見によって迅速に修正できるため、自社の社会的評判が低下するリスクを防げます。
また、従業員が自身の行動を振り返ることで、不正や違反行為の抑止を期待できるでしょう。
CSRを強化する上でBCP(事業継続計画)対策を行うメリット
BCP対策を行うことは、CSRの強化につながります。
BCPとは、Business Continuity Planの略で、日本語では「事業継続計画」などと訳されます。自然災害やテロ、感染症などに対して、被害を最小に抑えるとともに、たとえ被害・影響が出てしまったとしても、適切な対応で速やかに事業活動を復旧・継続させることを目的とした計画です。
BCP対策を行うメリットは、ステークホルダーからの信頼を獲得できることです。BCP対策が完備されていると、自社が緊急事態において社会を支える存在であること、社員に対する責任を果たしていることが示せます。緊急事態への備えをステークホルダーにアピールできるでしょう。
関連記事:BCP(事業継続計画)とは?専門家がわかりやすく解説
CSRの取り組み例
ここではCSRの取り組み例をご紹介します。ここで紹介したものを、自社のCSRにぜひ取り入れてください。
職場環境の整備
個々の会社における労働慣行が積み重なり、社会全体における労働文化が形成されます。そのため、より働きがいのある職場環境を整備することで、社会全体の労働文化を改善できることが期待できます。
環境問題への取り組み
環境問題への取り組みも、代表的なCSR活動のひとつです。
企業は経済活動をしている以上、何らかの形で環境問題と関わっています。自社のオペレーションにおいて、環境問題の発生につながる行動の減少を意識しましょう。
また、サプライチェーンにおける環境・生物多様性保全活動を行うことも効果的な取り組みです。
環境問題への取り組み例は、省エネやCO2対策などが挙げられます。
たとえば、トヨタ自動車はCO2排出量の少ない自動車を積極的に開発していますが、これもCSRの一例です。同社はまた、緑化活動や教育活動などの社会貢献活動も行っています。
消費者課題の解消
消費者に危害が及ばないようにすること、消費者が環境破壊行為を行わないようにすることもまた、CSRの一環として重要です。
消費者課題に取り組むには、顧客満足度調査を実施したり、エコ製品の製造に取り組んだりするといいでしょう。
自社の強みを生かしたCSR活動を進めよう!
CSRとは、企業が社会的に果たさなければならない責任のことです。そして企業がCSRを果たすことは、信頼の向上、採用への好影響、法務リスクの減少など、多くのメリットをもたらします。
CSR活動に取り組みたいと考えた際は、今回ご紹介したCSRの7原則を考慮したうえで、自社の強みを活かすことが重要です。自社にマッチしたCSR活動の検討をぜひ、進めてみてください。
兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。