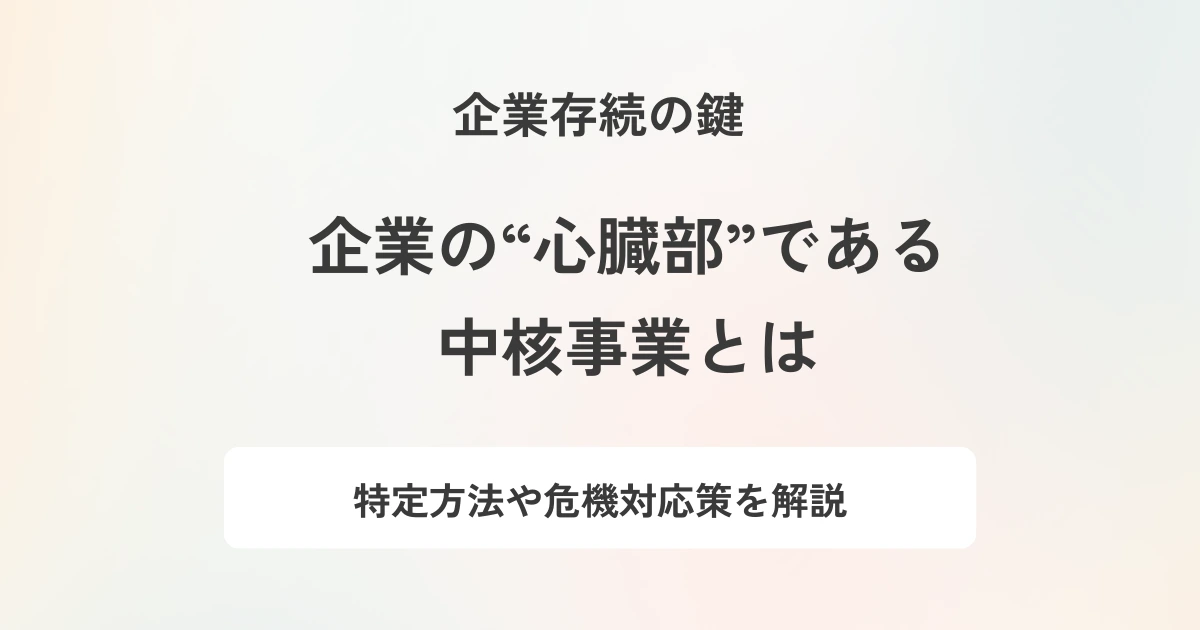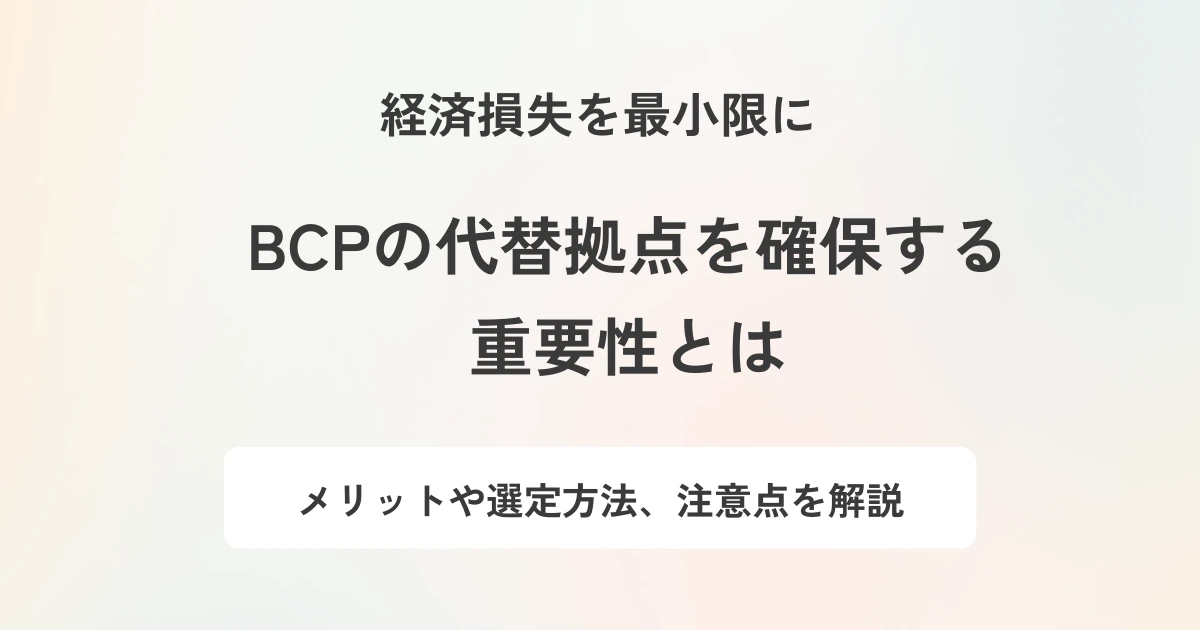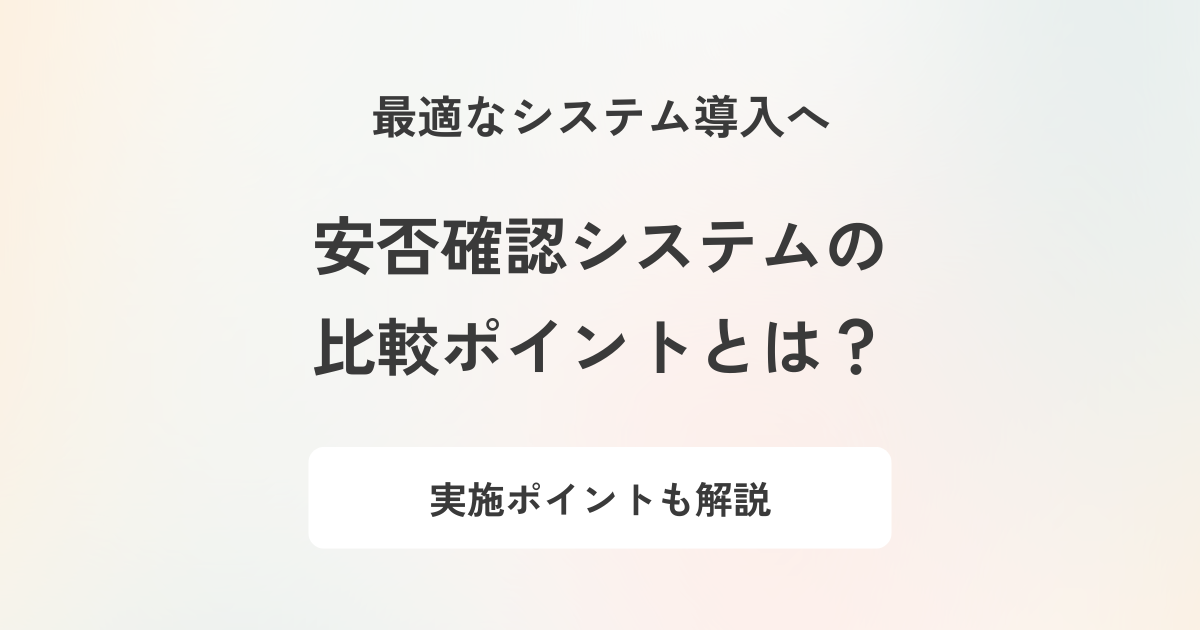【専門家が解説】BCP訓練とは?種類や事例、効果的に実施するポイントを紹介

福岡 幸二(ふくおか こうじ)
BCP訓練には机上訓練や緊急時通報訓練など、さまざまな種類があります。自社の課題や目的によって、訓練の種類を使い分けることが重要です。
この記事では、BCP&BCMコンサルティングの代表であり、マンダリンオリエンタル東京、沖縄科学技術大学院大学や九州大学などでBCM(事業継続マネジメント)の構築と運用、安全管理とリスク管理に携わってきた福岡 幸二氏が、BCP訓練の概要を解説します。
従業員の防災意識向上やリスクマネジメントの強化に取り組んでいる企業は、最後までご覧ください。
目次
BCP訓練とは
BCPとは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った言葉で「事業継続計画」のことです。自然災害などの緊急事態発生時に企業経営に関する被害を最小限に抑えながら、事業の早期復旧・継続を目指す計画を指します。
BCP訓練とは、有事に備えるため、あらかじめ定めたBCPに沿って行う訓練です。訓練を通してBCPの内容や重要性を全従業員に周知させ、BCPの効果を検証します。
自然災害などの緊急事態が発生した際、事業を存続させるためには経営陣や部門長が瞬時に状況を判断し、適切な指示をしなければなりません。しかし、緊急時は平常時とは異なる状況のなかで迅速に情報収集をしなければならず、冷静な判断や適切な行動を行うことは困難です。
そこで訓練を通してBCPの内容を把握し、緊急事態時に迅速な情報収集や冷静な判断、適切な行動ができるように備える必要があります。従業員にとってはBCP訓練を経験することで自分の役割が明確になり、必要な行動を把握しやすくなります。
また、BCP訓練を行うことでBCPそのものを検証でき、実現不可能だったり適切な行動が明記されていなかったりなど、計画の課題が見えてくるでしょう。よりよいBCPを作るため、実情に合わせて計画の内容を修正・更新することができます。
BCPについての詳しい内容は、以下の記事で解説しています。
2024年から介護事業者にはBCPの策定と訓練が義務化
2021年4月に施行された「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」により、介護事業者はBCP策定・BCP訓練の実施などが義務化されました。
介護事業者がBCP訓練を義務化された理由として、自然災害などの緊急事態発生時であっても介護やサービスを継続して提供できる体制の構築が求められる点があげられます。
2024年4月以降、すべての介護事業者においてBCPの策定が義務付けられており、策定していない事業所では業務継続計画未策定減算の対象となります。減算は「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡って計算されるため注意が必要です。
(参考:厚生労働省社会保障審議会「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」)
(参考:厚生労働省老健局「介護保険最新情報 Vol.1225 令和6年3月15日」)
BCPの策定と訓練を実施しなかった場合の罰則
2024年4月までに、自然災害または感染症に関するBCPを策定していない介護事業者に対しては、介護報酬の基本報酬額が減算されます。減算額は以下のとおりです。
- 介護施設・居住系サービスを提供:所定単位数の3%に相当する単位数を減算
- その他介護サービス:所定単位数の1%に相当する単位数を減算
ただし、BCPを策定していない場合でも、すぐに罰則が科されるわけではありません。2025年3月末まで1年間の経過措置が設けられているためです。
また、「感染症の予防およびまん延防止の基本方針」、「災害に関する具体的計画」のいずれも策定できていれば、BCPが未整備でも介護報酬の減算対象とはなりません。
さらに、訪問介護や居宅介護支援、福祉用具のレンタルサービスを提供する介護事業者についても、2025年3月末までの経過措置が設けられています。
経過措置期間内にBCPを策定し、介護報酬の減算を防止しましょう。
BCP訓練の目的
BCP訓練を定期的に行う目的は、以下3つの内容があげられます。
- 災害別の行動やBCPの内容を覚えるため
- BCPの内容改善に努めるため
- 従業員の防災意識を高めるため
内容を一つひとつ確認しましょう。
災害別の行動やBCPの内容を覚えるため
安全確保の手順や方法など、BCPの内容が充実していても、従業員が内容を覚えていない限り、被害の軽減は望めません。BCPの内容を理解して行動に移すには、被害を想定した訓練を繰り返し行うことが重要です。
また、自然災害と感染症の発生時には優先して取るべき行動が異なります。たとえば、地震が発生した場合、最優先にすべき行動は自身の安全を確保することです。
室内にいる場合は机や椅子の下など、物の落下を防げる場所に移動し、身の安全を確保します。外出中の場合はガラスや看板などでケガをしないよう、オフィスビルや安全な建物に入ります。
一方、感染症の患者が発生した際は、病原体と感染経路の遮断を最優先に行わなければなりません。感染者が増えないよう、患者の隔離に加えて、マスクや手袋などの着用が必要です。
両者の違いを想定してBCP訓練を実施すると、災害時に取るべき行動をイメージできるようになり、被害の軽減が望めるでしょう。
BCPの内容改善に努めるため
BCPは一度策定して終わりではありません。自社を取り巻く環境は常に変化しており、安定経営の継続には、あらゆるリスクに対して備えなければなりません。
仮に策定したBCPの内容を長期間見直さずに運用していた場合、新たなリスクに対応できない可能性が生じます。
また、BCP訓練には策定したBCPが機能するか、確認する目的もあります。多くの時間を割いてBCPの内容を見直したとしても、実際に訓練しない限り、機能するかはわかりません。
訓練の結果を通じて見直しと改善を繰り返し、BCPの完成度を高めましょう。
従業員の防災意識を高めるため
従業員の防災意識向上は、BCP訓練を行う大きな目的の1つです。普段から自然災害や感染症が発生した際の行動を意識して、生活を送っている従業員ばかりではありません。
被災の影響を軽減するには定期的にBCP訓練を行い、災害の種類に応じた行動を学んでおくことが重要です。
また、地震や津波、土砂災害などの自然災害は、いつ発生するか予測できません。防災意識が低いと、自然災害が発生した際に素早く行動を取るのが難しくなります。
避難場所や避難経路などを把握していないと、実際に災害が起きた際にパニックに陥る従業員も出てくるでしょう。
定期的にBCP訓練を実施すると、BCPの内容や災害時の行動に関する理解が深まり、落ち着いた対応が望めます。
BCP訓練の種類
BCP訓練には複数の種類があり、種類ごとに訓練内容が異なります。BCP訓練の種類は以下のとおりです。
- 机上訓練
- ワークショップ訓練
- ロールプレイング訓練
- バックアップデータの引き出し訓練
- 電話連絡網・緊急時通報診断
- 代替施設への移転・対応訓練
- 総合訓練
それぞれについて紹介します。
机上訓練
机上訓練は、机の上でBCP訓練をシミュレーションする訓練です。広い場所が不要で、比較的簡単に行えるのが特徴です。机上訓練の種類には、大きく分けてワークショップ訓練とロールプレイング訓練があります。
それぞれについて解説します。
ワークショップ訓練
ワークショップ訓練は、グループに分かれて与えられた想定について各自が議論をしながら対応を考える訓練です。
策定されたBCPに欠陥がないか、想定しきれていない部分はないかなど、ワークショップのテーマに従って討論します。そしてBCPへの理解を深め、緊急事態における課題とその解決方法について共有することが目的です。比較的初心者でも参加しやすい訓練で、緊急時という平時とは異なる状況で何が発生するのかを予測し対応する力を養うイメージトレーニングに近い形式で行います。
グループ内での決定事項は、ワークシートなどに記入して発表します。少人数でも開催できるうえ、詳細な訓練シナリオなどが必要ないことから、比較的取り組みやすい訓練です。意見交換・議論の過程でBCPの問題点などを発見し、BCPの修正や改善につなげることも可能でしょう。
ロールプレイング訓練
ロールプレイング訓練は、緊急時の想定をもとに各自が役割分担などをしたうえで、それぞれの役割に応じた柔軟な対応を考える訓練です。詳細な被害状況を設定したシナリオに沿ってBCP訓練を進めます。そのため、ロールプレイング訓練を行う前に災害の種類や規模、けが人や施設被害、ライフライン・交通機関の途絶など社内外の状況を細かに設定しましょう。
なお、ロールプレイング訓練には以下の2種類があります。
- シナリオ提示型
- シナリオブラインド型
シナリオ提示型は、シナリオのなかに何をすべきかの指針や対応があらかじめ記載されており、参加者はそれらを標準的な対応としながら各自の対応を検証します。一方、シナリオブラインド型は大まかなシナリオだけを提示し、各人が役割のなかで何をすべきかの指針や対応などをその場の判断で考えます。
どちらの訓練方法も双方向型のコミュニケーションが発生するため、運営側には高いコミュニケーション能力が求められます。さらに、訓練には運営側の入念な準備が求められるほか、ルールやタイムスケジュールの明確化が必要です。
また、訓練本番でも各グループの対応状況に応じたシナリオを付与したり、適切な対応ができないグループにはヒントを与えたりするなど、積極的な関与が求められます。
バックアップデータの引き出し訓練
BCP訓練の一環として、バックアップデータの引き出し訓練を実施しましょう。
災害発生時には電気やインターネットなどのインフラが故障・停止し、正常に機能しなくなる恐れがあります。多くの企業がデジタルデータを利用しているため、BCPの一環としてデータのバックアップを行っているでしょう。
そのため、平常時に稼働しているシステムに障害が発生した際、電気や通信などのインフラ設備の代替手段を瞬時に起動し、バックアップデータを取り出せるかどうかを検証する訓練も不可欠です。データの復旧に問題がないか、バックアップしたデータで事業を継続できるかどうかを確かめます。万が一、電子データが利用できない場合を想定して、紙ベースでの検証を行う訓練もあります。
また、データの引き出し訓練を機に、普段のバックアップ頻度やデータの保存先、管理体制などについて見直すといいでしょう。
電話連絡網・緊急時通報訓練
電話連絡網・緊急時通報訓練は、有事の際の情報伝達を速やかに行うのが目的の訓練です。
企業は災害や緊急事態が発生した際に、従業員の安否確認を迅速に行います。安否確認を行えば出社可能な従業員数の把握や出社可能時期の予測、優先度の高い業務についての事業継続体制づくりなどができます。
電話連絡網・緊急時通報訓練を実施すると緊急時の連絡手段が明らかになるうえ、スムーズな情報伝達が可能かどうかをチェックできるのがポイントです。たとえば、企業の電話連絡網に従業員の連絡先が登録してあっても、番号が変わっていれば緊急時に活用できません。こういったトラブルを未然に防ぐためにも、電話連絡網・緊急時通報訓練を通して情報伝達できる仕組みを構築します。
また、安否確認の専用システムを導入して、訓練を実施することもおすすめです。安否確認システムを導入すれば有事の場合の連絡をスムーズに行え、正確かつ迅速に安否確認を実施できます。
代替施設への移転・対応訓練
代替施設への移転・対応訓練とは、既存の施設が使用できなくなった場合にバックアップとしての代替施設に移動し、そこでBCPにもとづいた対応が可能かを検証する訓練です。
必要に応じて、倉庫が使えずに材料や商品などが保管できない、事業所が使えずに対応できないなどのケースについても想定して訓練を行いましょう。
総合訓練
総合訓練とは緊急事態となってBCPが発動されてから、対応が一段落つくまでの流れをすべて実施する訓練です。緊急事態発生直後から収束までを通して訓練を行うと、時間経過によって発生する課題や実施すべき対応がどのように移り変わっていくかを具体的にイメージできます。
また、自治体と合同で行う訓練もあります。自治体との合同訓練は、地域に存在するさまざまなステークホルダー(利害関係者)との連携を確認する機会にもなるでしょう。消防と協力して消防訓練をすれば、消防署から訓練の評価も得られます。
⇨企業が安否確認訓練を実施する目的は?具体的な手順とシナリオを紹介
【専門家が解説】短時間で効果的なBCP訓練を実施する際の手順
1回の訓練に十分な時間を確保できない企業、トップマネジメントの参加が難しい企業もあるでしょう。します。限られた時間で効果的にBCP訓練を実施するため、以下の流れに沿って訓練を進めます。
- 訓練の基本方針と計画を立てる
- 事前説明会を実施する
- 対策班ごとに訓練を実施する
- 総合訓練を実施する
- 火災発生を想定した訓練を実施する
- 振り返りと改善を行う
- 訓練内容を記録する
内容を一つひとつ確認しましょう。
1.訓練の基本方針と計画を立てる
そもそもBCPは、各対策班がそれぞれの役割を遂行することで、その目的を達成するものです。本訓練では、BCP発動時に各対策班がどのように行動するのかを実践的に確認するのが目的です。
基本方針や目的が定まったら、従業員へ周知しましょう。
BCP担当者は、各対策班の訓練内容と順番を決めます。たとえば、総務班は対策本部の設定・調整・進行を担当するため、優先的に訓練を実施します。
2. 事前説明会を実施する
訓練順が決まったら、BCP担当者が各対策班にBCP災害業務の説明会を行います。説明会では、各班の役割をBCP全体の流れと関連付けて解説し、所要時間は質疑応答を含めて約30分です。
3. 対策班ごとに訓練を実施する
説明会の終了後、1か月以内に各対策班ごとの訓練を行います。対策班リーダーが主体となり、実際にモノや人(負傷者の役割など)を使ってBCP本文のシナリオにもとづく訓練を行います。
- 訓練の所要時間は約30分。
- 訓練後、BCP担当者が問題点を指摘し、次回訓練の課題を設定。
- すべての対策班でこのプロセスを繰り返します。
4. 総合訓練を実施する
すべての対策班の訓練が終わったら、定期的に総合訓練を行います(最低でも年1回)。この訓練では、BCPに記載されたシナリオにもとづき、以下の対応を現場で実施します。
- 死傷者発生時の対応
- インフラ破壊時の対処
- 安否確認・負傷者対応・建物の安全調査
- 発災後、所定の時間に第1回対策本部会議を開催し、各班の対応状況を報告
- 報告内容にもとづき、対策本部が復旧工程表に示された次のステップを進める
所要時間は約45分。年度初めに日程を決め、毎年同じ時期に実施すると、トップマネジメントの参加もしやすくなります。
5. 火災発生を想定した訓練を実施する
地震後に火災が発生するケースを想定し、以下のような訓練を行います。
- 発火元の社員が初期消火を実施(消火器の使用・火災報知機の作動)
- 自衛消防隊や消防署への連絡・引き継ぎ
- 発火元の社員は訓練前に初期消火の方法や避難誘導をBCP担当者から学んでおく
- 防火スクリーン(防火シャッター)や防火扉が設置された建物では実際に使用して避難訓練を行う
訓練を単なる経験で終わらせないために、実際の操作を事前に学ぶことが重要です。
6. 振り返りと改善を行う
総合訓練の終了後は、消防署員を含む参加者やBCP担当者が集まり、BCPの遂行上の問題点を洗い出します。次回訓練に向けた改善策を検討し、より実践的な訓練へとつなげます。
7. 訓練内容を記録する
各対策班訓練や総合訓練の実施後は、訓練記録簿に詳細を記載します。この記録は、職場巡視や監査の際の資料として活用できます。
BCP訓練の事例8選
BCP訓練の種類を事例も交えながら8つ紹介します。
- イメージアップ教育訓練
- ウォークスルー訓練
- 情報システムのリストア訓練
- 総合実働訓練
- 情報伝達訓練
- 安否確認訓練
- 拠点立ち上げ訓練
- 図上訓練
それぞれの事例を参考に、BCP訓練を実施してください。
1.イメージアップ教育訓練
イメージアップ教育訓練とは、災害時における自分の行動をイメージアップして「わがこと意識」を向上させる訓練です。
訓練を実施する際に具体的な災害状況と課題を提示し、実施すべき災害対応について討議します。イメージアップ教育訓練では、イメージできた行動内容の数や行動解答例との比較をもとに評価が行われます。
イメージアップ教育訓練は災害時に必要な対応を学べたり、BCPのどの前提条件のもとに対応すべきかという発動条件を検討したりでき、緊急時の状況判断の難しさを実感できるのがポイントです。
実際、総務省が発表した事例によると、従業員の災害時における状況や行動すべき事項などを共有できました。その結果、緊急時への意識が高まり、必要な対応策などを検討しやすくなるでしょう。
(参考:総務省「ICT部門における業務継続計画 訓練事例集」)
2.ウォークスルー訓練
ウォークスルー訓練とは、実際に被災した場合を想定しながらBCPの読み合わせを行い、内容の矛盾点や課題を洗い出す訓練です。BCPを使用する状況についてイメージし合うことで、策定したBCPへの課題を発見できます。
総務省が発表した事例によると、ウォークスルー訓練によって策定していたBCPの行動手順に抜けや漏れが見つかり、最適な内容にブラッシュアップできました。さらに、ライフラインの被害状況によっては実行できない行動が見つかり、事前対策の検討を行っています。
つまり、ウォークスルー訓練を実践するとBCPの修正点や改善点が見つかり、よりよいBCPを策定できるでしょう。
(参考:総務省「ICT部門における業務継続計画 訓練事例集」)
3.情報システムのリストア訓練
情報システムのリストア(復旧・復元)訓練とは、緊急時におけるシステムの被害状況確認と復旧時間の短縮を目的に、情報システム部門が中心となって行う訓練です。この訓練では、設定された被害状況において、情報システムの被害状況と復旧手順の確認を行います。
実際、総務省が発表した事例によると情報システムの被害状況の確認手順やデータのリストア手順について、従業員への理解が深まりました。さらに、被害状況の確認手順は訓練結果を受けて、より実効性の高いものに改善しています。
(参考:総務省「ICT部門における業務継続計画 訓練事例集」)
4.総合実働訓練
総合実働訓練とは、実際の災害対応をともなう総合的な訓練です。
愛知県の加藤建設では、全従業員・各支社・地元住民などを対象に訓練を実施しています。南海トラフ巨大地震や大規模水害を想定し、対象となる人々が各々の役割を理解したうえで行動に移せるようにすることが目標です。訓練では非常用電源の運転訓練や衛星電話を利用した応援依頼なども行われるため、普段は触れない機器の扱い方を学習しています。
(参考:国⼟交通省 中部地⽅整備局「建設会社における災害時の事業継続⼒認定 BCP訓練事例集」)
5.情報伝達訓練
情報伝達訓練は情報伝達手段の確保や、被害や避難状況などの情報を正確かつ迅速に伝えることを目標に行う訓練です。
静岡県のグロージオでは、全社員や地域住民を対象に訓練を実施しています。大地震や台風、水害などを想定した情報伝達訓練をはじめとして、そのほか仮設トイレの設営や非常参集訓練なども並行して行っています。緊急事態時に復旧目標時間を短縮することや連絡先や安否確認情報に変更がないかを確認することが目的です。
(参考:国⼟交通省 中部地⽅整備局「建設会社における災害時の事業継続⼒認定 BCP訓練事例集」)
6.安否確認訓練
安否確認は、緊急時における初動対応のひとつです。緊急時は従業員1人ひとりの身の安全を確保しながら、企業としても対応要員を確保しなければいけません。いざという時に安否確認が滞りなく行えるように安否確認訓練を実施する必要があります。
静岡県の土屋建設では、定期的な防災訓練や教育を実施しています。災害時に対応できる能力の取得と従業員やその家族の安全確保を目的とした訓練です。
土屋建設では、年に一度の頻度で安否確認訓練を行うだけでなく、抜き打ちでも実施しています。SNSを連絡手段として活用する訓練を行っていましたが、安否確認システムを導入することで回答率が9割以上になるという成果が得られました。
通常の電話やメールでは、緊急時に「電話回線がつながらない」「メールがスムーズに送れない」などの問題が起こる可能性もあるからです。土屋建設の例にあるように確実に安否確認をしたい場合は、安否確認システムの導入を検討しましょう。
7.拠点立ち上げ訓練
自然災害などによって、普段使用している事務所や倉庫などが使用できない場合が想定されます。その場合、別の場所を「拠点」として立ち上げ、そこで災害対応をしながら事業継続を目指す必要があります。
このような拠点をスムーズに立ち上げるためには、災害発生前に具体的な手順を取り決めておくことが重要です。
鹿島建設では事業継続力を向上させるため、さまざまな事態を想定した実践的な訓練を実施しています。それらの訓練の1つに、関東支店が使用不可になったと想定し、茨城県に代替本部を立ち上げる訓練を行いました。日頃から具体的な被災状況を想定した訓練を行うことで、迅速な初動が可能になると考えています。
(参考:鹿島建設株式会社「首都直下地震を想定したBCP訓練を実施」)
8.図上訓練
図上訓練とは定められたテーマとシナリオに沿って、どのように対処するかを地図や企業の図面をもとにシミュレーションする訓練のことです。図上訓練では実際に対応行動は行わないものの、BCPの内容や手順をイメージして緊急時に行動できるように準備します。
介護施設などを運営する医療法人社団 洛和会では、図上訓練をより「簡単に」「短時間に」「楽しく」実施できるよう最短30分での訓練を実施しています。
通常の図上訓練は主に広域を対象とし、全体としての対策を検討するものです。しかし洛和会の図上訓練は施設内のみを対象として個人の行動を検討しており、従業員の負担を減らしながら防災意識と技術の向上に貢献しています。
(参考:内閣官房「383 介護施設が実施する災害図上訓練(DIG)」)
効果的なBCP訓練の実施に必要な4つのポイント
BCP訓練を成功させるには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- 従業員にBCP訓練の意味や目的を伝える
- シナリオは具体的に設定する
- 訓練内容を評価する
- BCP訓練は毎年1回以上実施する
それぞれについて解説します。
1.従業員にBCP訓練の意味や目的を伝える
従業員に訓練を実施する意味や目的を伝えておかなければ、BCP訓練を成功させるのは難しいです。緊急時は平時とは異なる状況となり、ゼロの状態から対応するのは難しく、あらゆる関係者との連携体制を構築することで困難な状況を乗り越えやすくします。
そのため、BCP訓練を通してどんな能力やスキルを養成する必要があるのか、使用するツールやシステムにどこまで習熟が必要かという点も、あわせて周知することが重要です。訓練の意味や目的を理解すれば効果が現れやすくなり、BCPの浸透にもつながります。
2.シナリオは具体的に設定する
シナリオとは災害発生から従業員の安否確認まで、対応すべき内容を時系列に沿って作成したものです。シナリオの完成度が高まるほど、本番を想定した訓練が行えるため、従業員のBCPへの理解や防災意識が高まります。
シナリオ作成の際は以下の内容を決めます。
- 災害の発生日時
- 災害発生による被害状況
- 当日確認すべき行動の内容や流れ
- 避難が数日間に及ぶ場合に確認すべき内容や流れ
最初から完成度の高いシナリオを作成できなかったとしても、問題ありません。BCP訓練の目的は実際の被害を想定し、BCPや災害時の行動に関して理解を深めることです。
訓練を積むほどイメージが描きやすくなるため、BCP訓練を繰り返し行い、シナリオの完成度を高めましょう。
また、シナリオのイメージがわかない場合、他社の事例を参考にするのも1つの方法です。以下で具体例を紹介します。
シナリオの具体例
地震が発生した際の一般企業と介護事業所の例を紹介します。一般企業の例は以下のとおりです。
| 事業場の概要 | ・電子部品のメーカーで、事業場は工場+営業所の構成 ・従業員数は総勢100人 |
| 訓練の想定状況 | ・平日の14:00頃に震度6強の地震が発生 ・事業場内には営業担当者5名を除く95人が働いていた状況 |
| 当日確認すべき行動の内容 | ・安否確認システムを利用し、従業員全員の安否を確認 ・営業担当者には被災状況を確認しながら、避難場所または自宅に行くよう指示 ・BCPの策定マニュアルに従い、指定の避難経路を使って避難場所へ避難 ・取引先へ被災状況を伝えるよう、管理者が指示するまでの流れを確認 ・火災や津波など、二次災害の有無を確認 ・負傷者対応や救急車手配の流れを確認 ・備蓄品の不足有無を確認 |
| 避難が数日間に及ぶ場合に確認すべき内容 | ・管理者または所属部署の上司から連絡が入るまで、避難場所や自宅で待機 ・納入実績が多いセンサーの生産復旧を優先的に取り組むよう組織内で共有 ・顧客に対して2ヵ月後の全面復旧を予定していることを連絡 ・一部の取引先が被災したため、代替会社から原材料を調達 |
発生日時や被害状況、当日の行動に関する内容が具体的なほど、効果的なBCP訓練が行えます。
一方、介護事業所向けのシナリオ例は以下になります。
| 事業場の概要 | ・3階建ての老人ホーム ・利用者は50名・事業所内の従業員数は総勢150人 ・シフト制で常に勤務している従業員は、約80名 |
| 訓練の想定状況 | ・平日の18:00頃に震度6強の地震が発生 ・施設内の一部で停電が発生 ・水は利用可能 ・通信状態は不安定だが、利用可能 |
| 当日確認すべき行動の内容や流れ | ・専用アプリを使って従業員の安否確認を実施 ・懐中電灯を使い、複数人で各フロアの利用者の安否を確認 ・利用者の無事や負傷者の有無などは、安否確認アプリの掲示板を利用して報告 ・利用者が負傷している場合は、救急箱を使って応急処置 ・施設内および施設周辺の被災状況を確認 ・従業員や利用者の家族へ連絡 ・備蓄品の不足有無を確認 |
| 避難が数日間に及ぶ場合に確認すべき内容 | ・道路や交通機関が問題なく利用できる場合は、従業員をシフトに沿って交代で勤務するよう指示 ・事業復旧の開始時期を取引先と利用者の家族へ連絡 ・利用者の家族へ利用者の体調を連絡 ・衛生用品を既存の取引先へ発注 ・施設内の損害状況を確認し、修理が必要な場合は業者へ連絡 |
医療サービスを提供する介護事業所の場合、どのサービスを優先して提供するか、事前に決めておくことが重要です。被災状況によっては従業員が十分に集まらないだけでなく、医療機器や設備が被災前と同じように使える保証もありません。
また、仮に従業員を確保できても事業の優先順位が曖昧な場合、従業員が判断に迷います。
シナリオ作成前に優先順位を明確化しておき、緊急時の対応力や訓練の有効性を高めましょう。
3.訓練内容を評価する
訓練後きちんと評価を行い、それを従業員に共有することも訓練を成功させるポイントのひとつです。
BCP訓練は従業員の行動や意思決定プロセスなどを記録したり、従業員1人ひとりに訓練後の自己評価などのフィードバックを収集したりすると評価をしやすいです。これにより、策定したBCPの課題や改善点が見えてくるでしょう。
また、従業員のBCPへの理解度や緊急時の対応の習熟度を把握することも重要です。数値評価できるような仕組みを用意してから訓練に臨むと効果的です。従業員と評価やフィードバックを共有し、課題や問題点を明らかにするとともに、解決策を模索するような訓練を目指しましょう。
4.BCP訓練は毎年1回以上実施する
BCP訓練は、年に1回以上実施するのが望ましいです。定期的な訓練を実施することで、万が一の場合にスムーズに対応できます。
とくに介護サービス事業者は年1回のBCP訓練が義務付けられており、入所系は年2回以上の訓練が必須です。それ以外の事業についても大規模な訓練は年1回、部門ごとの訓練は半年に1回程度を目安で行うと緊急時も安心です。
なお、企業によっては、BCP訓練を新入社員研修や社員研修・管理職研修で行うこともあります。社員研修で企業がBCPを重要視していることを伝えれば、全社員のBCPに対する意識向上につながるでしょう。
安否確認システムを導入して効果的なBCP訓練を実施
効果的なBCP訓練を実施するには、安否確認システムの導入が有効です。安否確認システムとは自然災害や感染症の発生などの緊急時に、従業員と素早く連絡が取れるシステムです。
メールや専用アプリ、LINEなど、複数の連絡手段に対応可能なシステムが多く、従業員との安否を素早く確認できます。BCP訓練の際は、安否確認メールを受け取った後を想定してシナリオを作成できるため、従業員は緊急時の行動に関して理解を深めやすいでしょう。
また、気象庁と連携している安否確認システムも多く、地震や津波などの災害情報を取得できます。取得した災害情報からいち早く従業員に避難や安全確保を呼びかけられるため、被害の影響の軽減も期待できます。
さらに、掲示板が使えると、従業員の無事や避難場所、出社可否など、スムーズな情報共有が可能です。策定したBCPや今後の流れの掲載にも対応しており、BCP訓練で事業復旧に向けた準備も確認できます。
安否確認システムの機能と特徴
安否確認システムの主な機能は以下のとおりです。
- 安否確認メールの自動配信
- 未回答者への再配信
- 従業員の家族の安否確認
- 回答結果の自動集計
- 災害情報の取得
- 掲示板
システムによっては上記に加えて、多言語表記や防災トリセツ、備蓄品管理などの機能も実装しています。
また、安否確認システムを提供する企業の多くは、大規模災害が発生した際の対策を強化しています。
データセンターの分散化やネットワーク環境の冗長化などによって、大規模災害が生じても安定稼働が望めるでしょう。
BCP訓練に関するよくある質問
BCP訓練に関するよくある質問について、以下で回答します。
BCP訓練の回数は決まっていますか?
介護事業者のみ決まっています。2024年から介護事業所に関しては年2回以上、BCP訓練の実施が義務付けられています。訓練の種類・内容に関する指定はありません。
ただし、人事異動や退職などにより管理者や人事担当者が変更する場合を想定し、BCP訓練を実施しておく必要があります。また、緊急時に素早く正確な行動が取れるよう、各担当者の役割を確認することを目的とした訓練も実施しておきましょう。
一方、一般企業に対するBCPの訓練回数は決まっていません。BCPの策定も介護事業者しか義務化されていないため、訓練回数についても規定はありません。
回数指定はないものの、従業員の防災意識を高めるため、介護事業所と同様に年2回ほどBCP訓練を実施しましょう。
ワークショップ型のBCP訓練は外部でも受けられますか?
コンサルティング会社や商工会議所など、さまざまな組織がワークショップ型のBCP訓練を開催しています。たとえば、コンサルティング会社によっては、中小企業限定で参加者を募集しているケースもあります。
ワークショップ訓練はBCPや防災に関する知識が乏しい場合でも、比較的参加しやすい訓練です。緻密なシナリオを作成する必要もないため、これからBCP対策を強化する企業にとっておすすめの訓練といえます。
BCP訓練開催のリソース・ノウハウに不安を抱えている企業は、外部企業が主催する訓練の利用も検討してみましょう。
災害時にはトヨクモが提供する『安否確認サービス2』の活用を!
地震・台風をはじめとする災害時には、トヨクモが提供する『安否確認サービス2』の活用がおすすめです。安否確認サービス2は、気象庁の情報と連動して安否確認連絡を一斉送信し、回答結果を自動集計できます。
さらに、『安否確認サービス2』を利用すると、9月1日(防災の日)に開催される一斉訓練に無料で参加できます。一斉訓練では実際の災害時に近い負荷をシステムに急激にかけ、安定稼働できるかどうかを確認しているのが特徴です。毎年確認することで、緊急時に稼働できないというリスクを軽減しています。
また、参加組織ごとの回答情報を集計した結果レポートでは、社内ユーザーの回答率の時間推移や訓練全体の平均回答時間などを確認できます。したがって一斉訓練を活用すると、自社の防災意識を高めやすくなるでしょう。
日頃からのBCP訓練で災害に備えよう
自然災害やパンデミックなどの緊急時に企業が生き残るためには、日頃から継続的にBCP訓練を行って全従業員がその内容を把握して適切な行動を取れるようにしておくことが大切です。最低でも年に1回以上のBCP訓練をして、万が一に備えましょう。
トヨクモの『安否確認サービス2』を活用した一斉訓練を実施すると、システムの操作手順や安否確認の流れ、その後のBCPまで幅広く見直せます。具体的なシナリオをあらじかじめ作成しておけば、緊急時に備えた訓練ができるはずです。
さらに、『安否確認サービス2』は初期費用がかからず、30日間の無料お試し期間を設けているのもおすすめポイントです。自社に適したシステムかどうかを見極めたうえで導入できます。緊急時に迅速な初動を可能にしつつ、BCP訓練を実施したい方は以下のフォームより無料体験をお試しください。
無料お試しは、何度でもご利用可能です。ぜひこの機会に安否確認システムを体験してください!
- 機能制限一切ナシ
- 何度でもご利用可能
- 初期設定サポート付き
- 自動課金一切ナシ

編集者:遠藤 香大(えんどう こうだい)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部に所属。RMCA認定BCPアドバイザー。2024年、トヨクモ株式会社に入社。『kintone連携サービス』のサポート業務を経て、現在はトヨクモが運営するメディア『トヨクモ防災タイムズ』運営メンバーとして編集・校正業務に携わる。海外での資源開発による災害・健康リスクや、企業のレピュテーションリスクに関する研究経験がある。本メディアでは労働安全衛生法の記事を中心に、BCPに関するさまざまな分野を担当。

執筆者:福岡 幸二(ふくおか こうじ)
BCP&BCMコンサルティング代表/元九州大学危機管理室 特任教授(博士) 神戸大学大学院海事科学研究科で博士号(海事科学)を取得。マンダリンオリエンタル東京、沖縄科学技術大学院大学、九州大学などで、地震・津波など自然災害や重大事故を含むBCM(事業継続マネジメント)を実装してきた実績を持つ。 2024年に起業しBCP&BCMコンサルティング代表として、大学や企業にカスタマイズされたBCM(事業継続マネジメント)およびSMS(安全管理システム)の構築を提供している。 国際海事機関(IMO)の分析官や事故調査官として国際的な活動も経験。著書に『Accident Prevention and Investigation: A Systematic Guide for Professionals, Educators, Researchers, and Students』(2025)、『Safer Seas: Systematic Accident Prevention』(2019年)があり、大学の実験室での事故防止策に関する論文をScientific Reports誌に発表するなど、現在国内外で活動し危機管理と安全管理を専門とする科学者兼実務家である。 プロフィール:https://bcp-bcmconsulting.com/about/