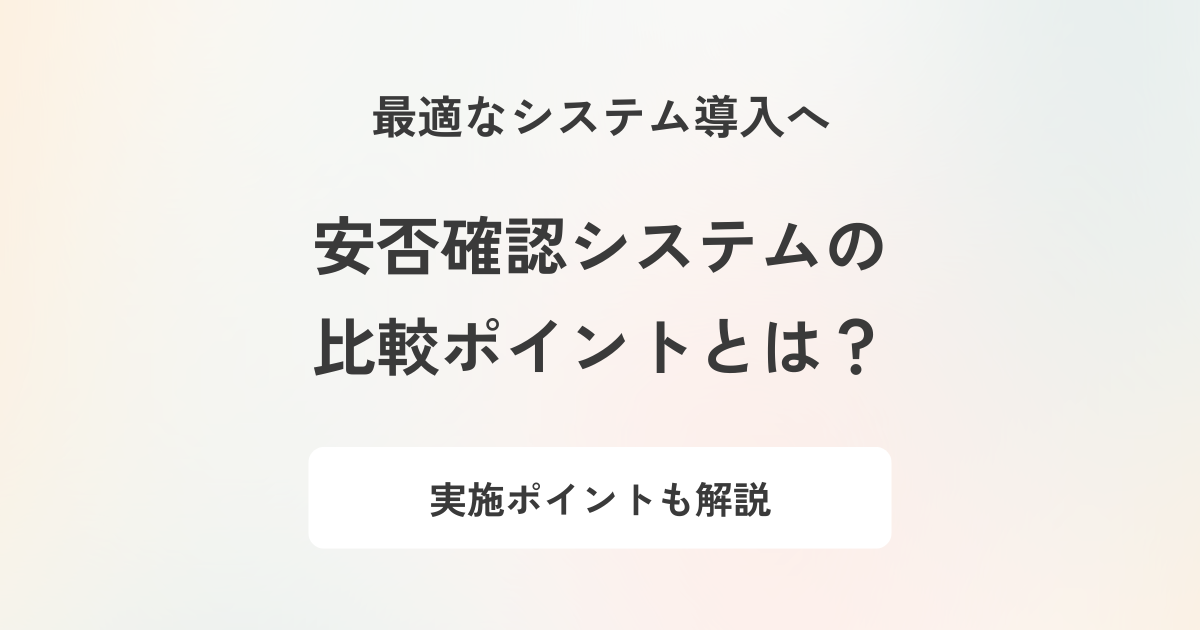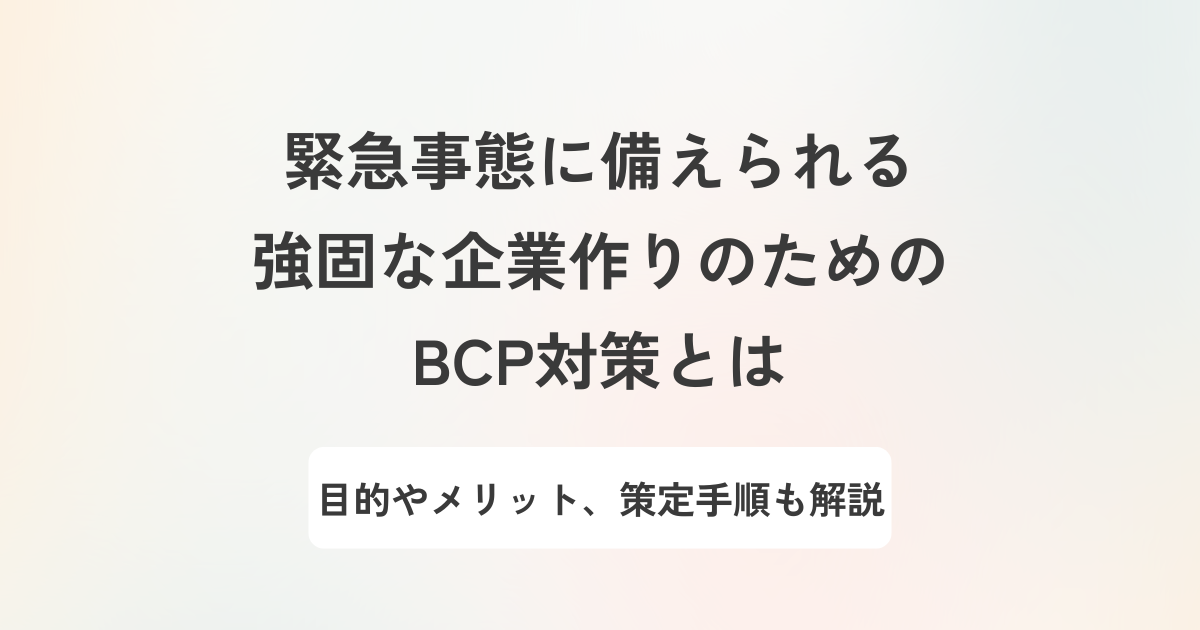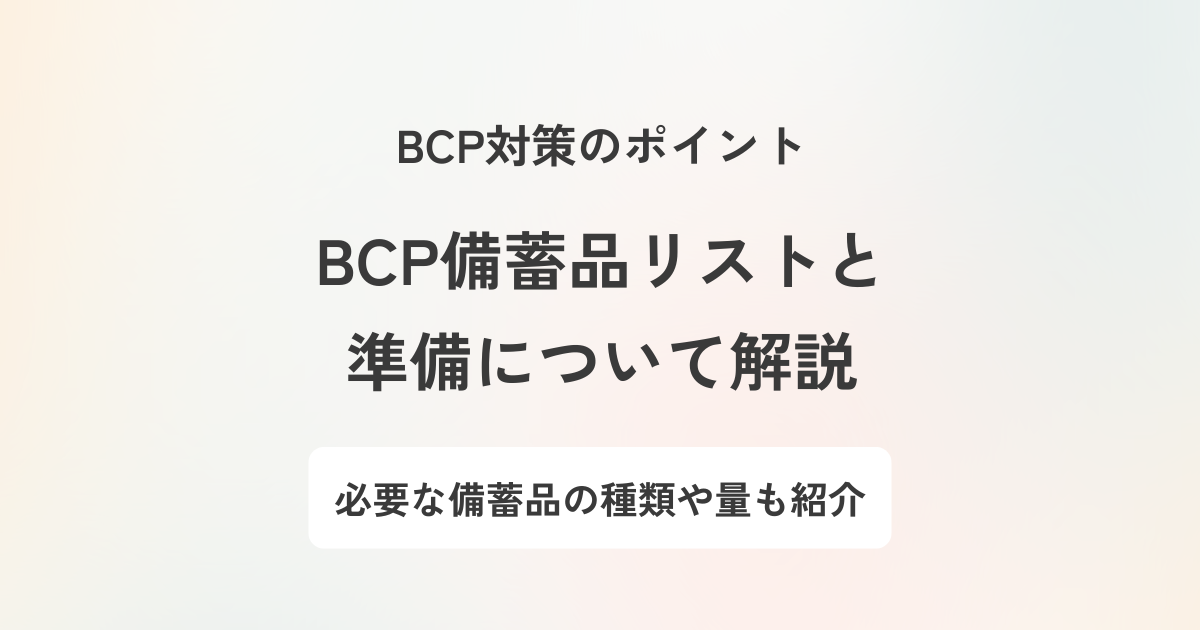BCPの見直しポイント6選!検討すべき時期や頻度も紹介
大保颯大
BCPは、自社の経営方針に変化があった際に見直しが必要です。BCPの策定から長期間内容を変更していない場合、新たなリスクに対応できる保証はありません。
しかしどのようなタイミングでBCPを見直すべきなのか、そしてどんなポイントを確認すればいいか分からず悩んでいるでしょう。
そこでこの記事では、BCPを見直すタイミングや見直す際のポイントなどを紹介します。リスクマネジメントの強化を推進中の方は、最後までご覧ください。
目次
BCPの見直しを検討すべき時期
BCPの見直しに適したタイミングは、下記4点です。
- 防災訓練を実施した場合
- 経営方針に変化が起きた場合
- 自社を取り巻く環境が変化した場合
- 組織体制を変更した場合
上記のタイミングで、見直すべき理由を詳しくみていきましょう。
防災訓練を実施した場合
防災訓練の直後は、BCPの見直しに適したタイミングの1つです。防災訓練では事前に策定したBCPの内容をもとに、安否確認や避難場所への移動など、災害発生後の行動を確認します。
防災訓練の重要な目的は、BCPの内容が機能しているか、有効性を確認することです。仮に機能していない内容が見つかった場合、早急に改善しなければなりません。
また、防災訓練には従業員の防災意識を高める効果も期待されています。完成度の高いBCPを策定しても、従業員に内容が浸透していない場合、緊急時に冷静な行動は取れないでしょう。
防災訓練のあとにBCPの見直しに取り組むことで、災害発生による被害軽減を図れます。
企業が安否確認訓練を行うべき理由とは?具体的な手順とシナリオを紹介
経営方針に変化が起きた場合
新商品・新サービスの開発、新事業立ち上げなど、事業内容や経営方針に変化が生じたタイミングも、BCPを見直すべき時期の1つです。
BCPの策定、または見直しから時間が経過している場合、新たなリスクに対応できない可能性があります。
新商品販売や新事業の運営を本格的に始める前に、既存のリスクの変化や新たなリスクの有無を確認しておきましょう。あらゆるリスクに備えることで、利益損失や事業失敗のリスクを軽減できます。
自社を取り巻く環境が変化した場合
大規模な自然災害や感染症の流行、法改正などが発生した際も、BCPを見直すべきタイミングです。
自然災害の発生や感染症の流行は、いつ起きるか予測できません。
事前の備えが不十分では、ヒトやモノ、カネなどの多くの経営資源を失う可能性が高まります。被災の影響や事業復旧までの時間を削減するには、あらゆるリスクに対して対策を講じておくことが重要です。
また、法改正の内容をBCPに反映しなければ、意図せず法律違反を招くおそれがあります。
組織体制が変更した場合
人事異動や配置転換によって、従業員の勤務地や連絡先が変わった場合も、BCPの見直しを検討すべきです。緊急事態の発生後に従業員と連絡が取れなければ、従業員の無事や避難場所などを確認できません。
従業員の安否がわからない状態が続くと、事業復旧に向けた準備も進められず、事業停止による損失額が膨らみます。
また、新卒採用や中途採用で多くの労働者を採用した際も、連絡先の登録や連絡網の見直しを実施しましょう。
BCPの見直しを進める際のポイント
BCPを見直す際は、以下6点を意識することが重要です。
- BCPの見直しにはチェックリストを活用
- 大規模地震発生時の対応の見直し
- 災害発生時の復旧目標を再設定
- 従業員との連絡手段増加を検討
- 課題の優先順位付けを実施
- 定期的な訓練の実施
上記の点を意識すると、有効性の高いBCPを策定できる可能性が高まります。
BCPの見直しにはチェックリストを活用
担当者がBCPの運用に慣れていない場合、どのような点を見直し、どのような状態であれば対策が十分なのか、わからない場合もあるでしょう。
BCP対策の内容を確認する際は、中小企業のチェックリストを活用するのがおすすめです。中小企業のチェックリストには、経営資源に関する設問が多数記載されており、BCP対策の充実度や課題を効率的に可視化できます。
チェックリストでは以下5つの内容に関する設問が用意されており、「はい」か「いいえ」で回答します。
- 人的資源(ヒト)
- 物的資源(モノ)
- 物的資源(資金)
- 物的資源(情報)
- 体制等
チェックリストの診断結果は以下の3段階です。
- 「はい」が16個以上:BCP対策が十分な状態
- 「はい」が3~15個:緊急時の備えはできているが、改善点が多い状態
- 「はい」が3個以下:災害が発生した場合、事業停止や倒産する可能性がある状態
各チェック項目について以下で解説しますので、「はい」が15個以下の場合は、改善点の把握と対策に努めましょう。
人的資源(ヒト)
人的資源とは事業場で働く従業員のことです。4つの経営資源のうち、モノや資金、情報は物的資源と表現されますが、人材に関しては人的資源と表現されます。
中小企業庁のチェックリストには人的資源に関して、以下の項目が記載されています。
緊急事態が発生した際、従業員の安全を確保するための災害対応計画を作成していますか?
就業時間中または勤務時間外に災害が発生した場合、従業員と連絡が取れますか?
出社できない従業員の代わりに業務を代行できる従業員を育成していますか?
避難訓練や初期救急、心肺蘇生法の訓練を定期的に実施していますか?
(引用:中小企業庁公式HP「1.3 BCP取組状況チェック」)
人的資源が不足すると通常業務に支障をきたし、商品やサービスを満足に提供できません。ITツールの導入やアウトソーシングの活用など、採用以外の方法で生産性を高める方法を考えましょう。
物的資源(モノ)
物的資源のモノとは、自社で保有する設備や備品全般を指します。モノに該当する主な資源を以下に記載しました。
- 事業所の建物
- 土地
- 社用車
- 机
- 椅子
- PC
- ソフトウェア
- システム
工場や倉庫を保有している場合、建物や生産ライン、フォークリフトなどの設備も資源に該当します。中小企業庁のチェックリストには物的資源に関して、以下の設問が記載されています。
事業所や工場は地震や風水害に耐えられますか?
事業所や工場内の設備は地震や風水害から保護されていますか?
事業所または拠点周辺に関する自然災害の脅威を把握していますか?
自社設備の流動化に関して把握し、内容を更新していますか?
事業停止に備えた代替手段を用意していますか?
主要な仕入先から資材が調達できない場合に備えて、調達先の多角化に励んでいますか?
(引用:中小企業庁公式HP「1.3 BCP取組状況チェック」)
災害によって多くのモノが不足した場合、災害前と同じように業務を遂行できません。
モノ不足に陥った場合は、通常業務を遂行する上で最低限必要な備品や設備を整理した上で、優先順位を付けましょう。
物的資源(資金)
物的資源の資金とは、会社存続に必要な運転資金のことです。資金には借入金や株式など、現金以外の資産も含まれます。
中小企業庁のチェックリストを活用してBCPを見直した場合、資金に関しては以下の設問が記載されています。
1ヶ月事業を停止した場合の損失額を把握していますか?
1ヶ月分の事業運転資金や資金繰りに関して把握していますか?
現在加入している災害保険の補償範囲に関して専門家に相談しましたか?
災害対策や事業復旧を目的とした融資制度を把握していますか?
(引用:中小企業庁公式HP「1.3 BCP取組状況チェック」)
資金に余裕がない場合、経営者が取れる選択肢は限られます。企業存続に向けた選択を優先せざるを得なくなり、場合によっては経営規模の縮小を検討しなければなりません。
金融機関からの融資や補助金の活用、クラウドファンディングなど、資金調達の手段を検討しておきしょう。
物的資源(情報)
物的資源の情報とは顧客情報や商品データ、自社の経営状況など、事業運営に必要な情報全般を指します。過去の販売データや市場ニーズの推移など、これまで培ってきたノウハウも含まれるため、今後事業を続けていくうえで重要な経営資源です。
中小企業庁のチェックリストを活用してBCPを見直した場合、情報に関しては以下の設問が記載されています。
情報のバックアップを取っていますか?
事業所以外の場所で情報のコピーまたはバックアップをしていますか?
緊急時に顧客や取引先に連絡する手段は確立されていますか?
業務システムが故障した場合の代替手段は確立されていますか?
(引用:中小企業庁公式HP「1.3 BCP取組状況チェック」)
従業員の持つ経験やノウハウも含めて、情報の保管には細心の注意を払いましょう。
体制等
体制等とは事業場内のルールや指示系統などが該当します。経営資源に該当しないものの、経営資源の有効活用やスムーズな業務遂行に欠かせない要素です。
中小企業庁のチェックリストを活用する場合、以下の設問に回答しながらBCPを見直します。
人的災害が発生した場合の影響を考えたことがありますか?
災害後にどの事業復旧を優先すべきか、考えたことがありますか?
経営者が不在の際に指揮を執る代替者が決まっていますか?
人的災害が発生した際、取引先と相互支援に関する内容を決めていますか?
(引用:中小企業庁公式HP「1.3 BCP取組状況チェック」)
緊急事態が発生しても冷静かつ素早い判断を下すためにも、緊急時の指揮系統や運営体制が確立されているか確認しましょう。
大規模地震発生時の対応の見直し
事業所内の危険箇所や備蓄品の保管場所の確認など、大規模地震の発生に備えた対策を強化する必要があります。
近年は能登半島地震や熊本地震など、地域を問わず大規模地震が多発しています。自社がいつ被災してもおかしくありません。
従業員の安全の確保や被害の軽減には、日頃から準備を進めることが重要です。地震発生後に素早く行動に移れるよう、以下の内容は従業員と共有しておきましょう。
- 災害発生に対する自社の方針
- 緊急時の連絡網や指示系統
- 避難経路や避難場所
- 従業員との連絡手段
- 災害情報を取得する手段
- 従業員が自宅に帰れない場合の対応
- 備蓄品の充実度
上記に加えて、近隣住民との情報共有や取引先との相互支援に関する体制を整えておくと、地域全体の防災力を強化できます。
災害発生時の復旧目標を再設定
被災後の事業復旧において、計画の実現性は極めて重要です。
復旧までの流れや期間、事業の優先順位が実態に即していない場合、BCPを見直して、実行可能な内容に修正しなければなりません。
たとえば従業員数や備蓄品の数に合わない目標を設定していると、復旧作業の際に従業員へ多大な負担がかかります。
従業員のモチベーション低下や離職者の発生を招き、被災前よりも人的資源が不足する恐れがあります。
従業員への負担に配慮しつつ短期間での事業再開を実現するため、以下の内容を再度見直しましょう。
- 事業停止の判断基準
- 事業再開の開始時期
- ライフラインが止まった場合の対策
- ライフラインが復旧するまでの時間
- 事業再開の優先順位
- 感染症患者が発生した場合の対応
- お風呂が利用できない場合の対応
被災した際は、出勤可能な従業員数や事業所の被災状況なども踏まえ、事業再開の時期を柔軟に変更する姿勢が求められます。
従業員との連絡手段増加を検討
緊急時の連絡手段がメールと電話のみの場合、LINEやSNSなど、連絡手段の拡充を検討しましょう。地震や津波などの大規模な自然災害が起きた場合、電話回線やインターネット回線のトラフィック量が通常の数十倍に増えます。
実際、東日本大震災が発生した際の電話回線では、トラフィック量が通常の50〜60倍に増えました。トラフィック量が回線の能力を超えると、速度遅延や通信障害が発生し、相手と長時間連絡が取れません。
仮に相手と連絡が取れたとしても、通信事業者による通信制限が設けられるため、スムーズなやり取りは望めないでしょう。
LINEやビジネスチャット、安否確認アプリなど、通信手段の選択肢を増やし、緊急時でも従業員と連絡が取れる体制を整えることが重要です。
課題の優先順位付けを実施
BCPの見直しによって可視化されたリスクは、基本的にすべて改善が必要です。しかし、人手不足や通常業務への影響を考慮すると、すべてのリスクに対応するのは難しいでしょう。
そのため、リスクが複数見つかった場合は優先順位付けを行い、優先度が高いものから対応策を考えます。優先順位を付ける際の判断基準は、自社の事業運営に対する影響力です。
たとえば、サプライチェーンの断絶による主要原材料の供給停止や、拠点の被災による事業継続の困難化などは、ビジネスモデルの転換を迫られる重大なリスクといえます。このようなリスクには、代替供給ルートの確保やリモートワーク環境の整備など、優先的に対策を検討すべきでしょう。
優先順位を付ける前に自社を取り巻くリスクを整理し、どのリスクが事業の根幹に影響を及ぼすかを明確にすることで、効率よく対策を講じやすいでしょう。
定期的な訓練の実施
最低でも1年に1回は防災訓練を実施しましょう。
定期的にBCPの内容を見直していたとしても、被害の発生を想定した実践的な訓練をしない限り、有効性は把握できません。防災訓練の定期的な実施することで、BCPの有効性や改善点を確認し、BCPをブラッシュアップしましょう。
また、従業員にBCPの内容や防災意識が浸透しなければ、緊急事態が起きた際に冷静な対応は望めません。避難経路や避難場所など、緊急事態が発生した際の行動を従業員が理解するためにも、定期的な訓練を実施しましょう。
BCPを見直す頻度
BCPを見直す頻度は、半年または年1回が目安です。なぜなら、法改正や社会情勢の変化、新たなリスクの発生などに対応するためです。
以前BCPを見直した時よりも、リスクの変化や施設の老朽化など、事業への影響が拡大している可能性も考えられます。
緊急事態が発生しても被害の軽減と最短での事業復旧ができるよう、定期的なBCPの見直しを行いましょう。
BCP対策の強化には安否確認システムの導入が有効
BCP対策の有効性を高めるには、定期的な見直しに加えて、安否確認システムの導入がおすすめです。安否確認システムとは、緊急事態が発生した際に従業員の無事を素早く確認できるシステムです。
メールやLINE、専用アプリなど、複数の連絡手段に対応したシステムが多く、災害後に従業員の安否や避難場所を確認できる可能性を高められます。
ネットワークの冗長化やデータセンターの分散化などを講じているシステムを選ぶと、大規模災害が起きても安定稼働が期待できるでしょう。
さらに、一部の安否確認システムでは気象庁と連動し、緊急地震速報や大雨警報などの災害情報を取得しています。システムに登録した連絡先に、安否確認通知と災害情報を自動で一斉送信する仕組みです。
従業員に危険性や避難の必要性を訴えられるため、被災する前に安全を確保できます。
BCP対策を見直してリスクへの備えを強化しよう
経営方針や自社の組織体制が変化したタイミングで、BCPの内容を見直しましょう。見直す頻度は、半年または1年に1回が目安になります。
定期的な見直しによって、既存リスクの変化や新しいリスクの発生にも素早く対応できる体制が整えられます。
また、安否確認システムの導入によって、BCPの有効性がさらに高まります。多くのシステムはメール・アプリなど複数の連絡手段に対応しており、大規模災害時に特定の通信手段が使えなくなっても、別の手段で安否確認を行うことができます。
ただし、はじめて安否確認システムを導入する場合、どのシステムを選ぶべきか、わからない方もいるでしょう。トヨクモの提供する「安否確認サービス2」は、導入企業数4,000社以上、リピート率99.8%を誇る安否確認システムです。
気象庁の「地震/津波/特別警報」との連動によって、災害発生後に安否確認の通知を登録した連絡先に自動で配信します。メールや専用アプリ、LINEでの回答に対応しており、従業員の安否を素早く確認できます。
また、安否確認サービス2を導入する際、初期費用は発生しません。最低利用期間も設定されておらず、1ヶ月単位でシステムの利用が可能です。
BCP対策の強化に向けて安否確認システムをお探しの方は、安否確認サービス2の導入をご検討ください。