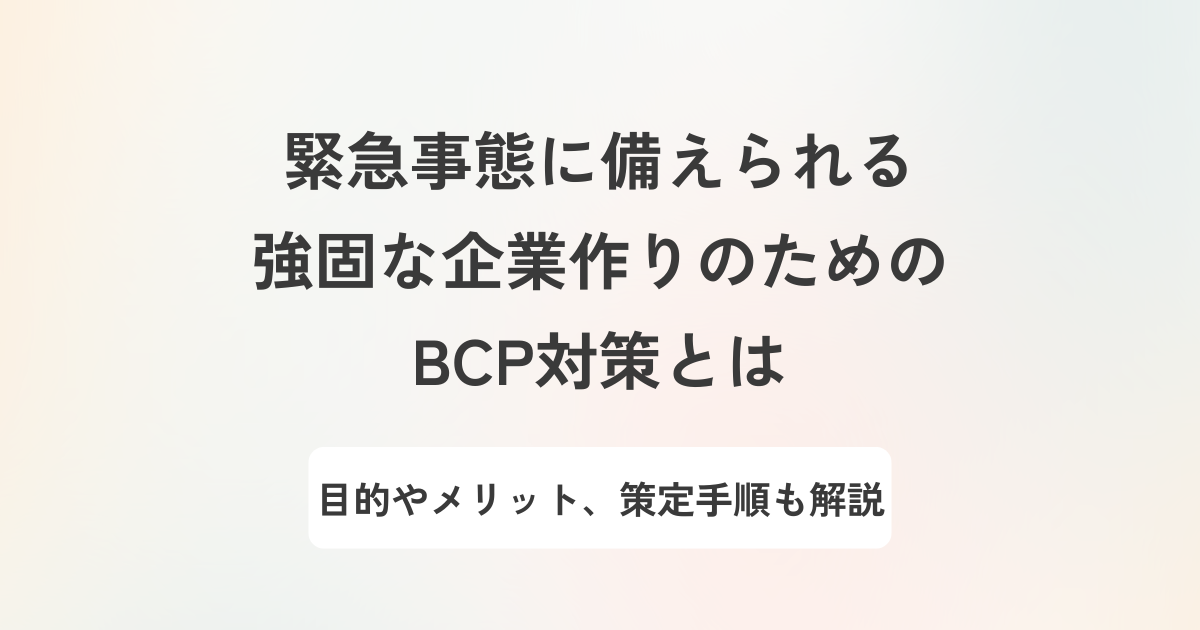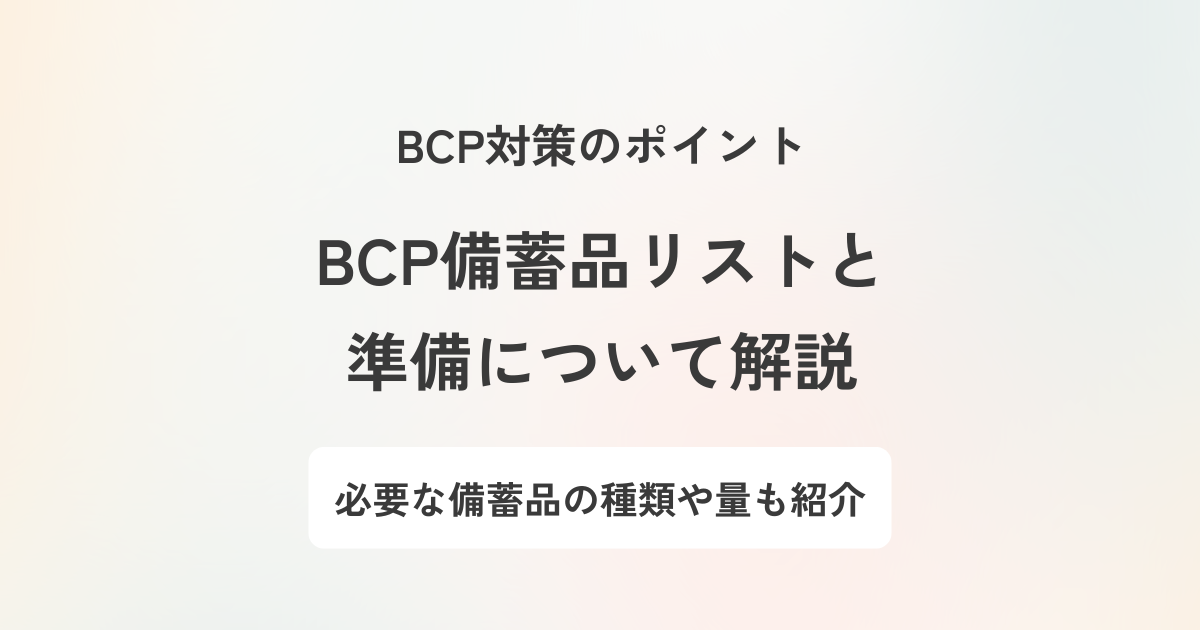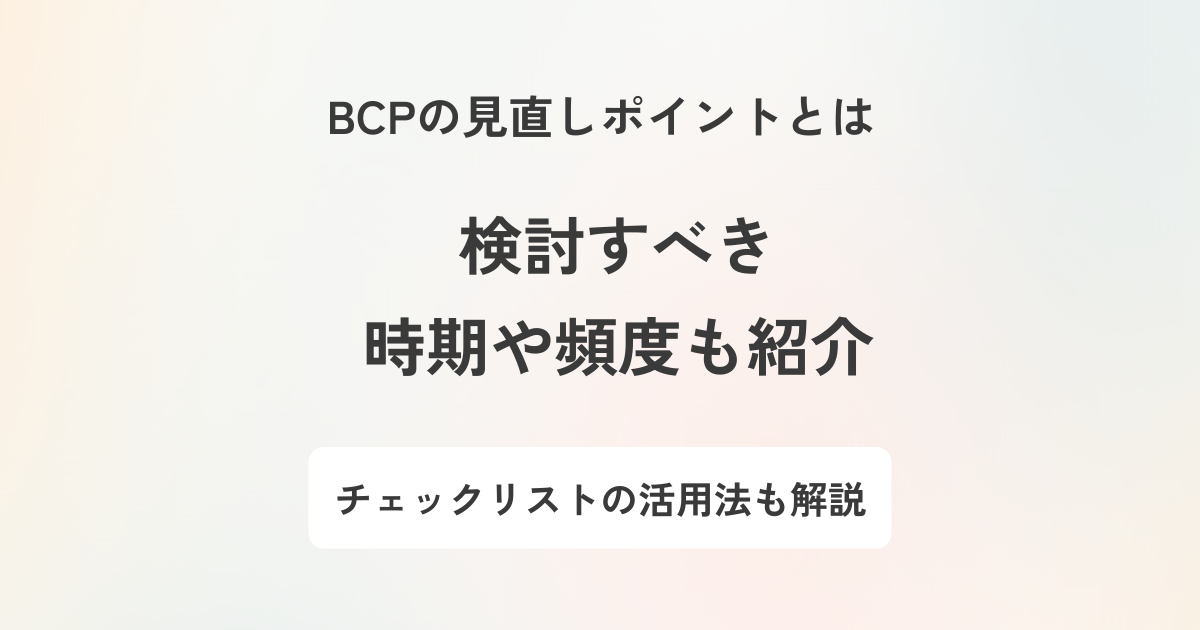安否確認システムを乗り換える際の比較ポイントとは?おすすめのシステムも紹介
大保颯大
既存システムの機能性に不満を覚えた場合、新たな安否確認システムへの乗り換えを検討しましょう。機能が不足していると、緊急時にスムーズに対応できない可能性が高まります。
この記事では、乗り換え時に比較すべきポイントやおすすめの安否確認システムなどを紹介します。安否確認システムの乗り換えを検討中の方は、最後までご覧ください。
目次
安否確認システムの乗り換えを検討すべきタイミング
既存システムが以下3つの内容に該当する場合、新しい安否確認システムの導入を検討しましょう。
- 機能性や操作性に不満を覚えたとき
- ランニングコストを下げたいとき
- 定期訓練で機能しなかったとき
機能性やコストパフォーマンスに不満を抱きながら使い続けると、さまざまなデメリットが生じます。
機能性や操作性に不満を覚えたとき
安否確認システムの機能性や操作性に不満を覚えた場合、新しいシステムへの乗り換えを検討しましょう。安否確認システムは従業員の安否を迅速に確認し、必要な対応を取るために利用するシステムです。
システムの乗り換えによって新たに使える機能が増えると、スムーズな情報共有や安否確認の効率化など、メリットが増えます。
たとえば、掲示板機能が使えるシステムを導入したとしましょう。従業員の出社可否や被害状況を正確に把握できるため、事業復旧に向けたスケジュールを立てやすくなります。
また、操作性に乏しいシステムを使っていると、一つひとつの作業に時間がかかり、安否確認に多くの時間を割かなければなりません。
使用中の安否確認システムについて「操作画面が見にくい」や「画面移行が遅い」など感じる場合は、乗り換えを検討すべきタイミングと言えます。
ランニングコストを下げたいとき
オンプレミス型の安否確認システムを利用している企業向けの内容です。ランニングコストが企業経営の負担になっている場合、クラウド型への乗り換えを検討しましょう。
クラウド型は一定の料金を支払う代わりに、メンテナンスやアップデートを自社で対応する必要がありません。安否確認システムを提供する企業側に対応を任せられるため、ランニングコストやシステム管理者の負担を軽減できます。
また、中小企業をターゲットにして月額料金を採用している安否確認システムも多く見られます。月額料金は従業員数に応じて変動し、たとえばユーザー数が100人の場合、月額料金が10,000円前後で利用できるシステムも少なくありません。
定期訓練で機能しなかったとき
従業員の防災意識向上やBCPの課題抽出のため、年1〜2回はBCP訓練を実施する必要があります。実践を想定して訓練を積まなければ、策定したBCPの理解が深まらず、状況に応じた判断や素早い行動は望めません。
実践に近い状況を想定したBCP訓練をおこなう上で、安否確認システムの存在が欠かせません。しかし、訓練の際に既存システムの機能性や操作性に不満を覚えた場合は、新しいシステムの導入を検討すべきです。
適切なシステムを導入しなければ、事前に定めたBCPが機能しないだけでなく、従業員の安否確認に多くの時間を要する可能性が高まります。
企業が安否確認訓練を実施する目的は?具体的な手順とシナリオを紹介
安否確認システムを乗り換える際の比較ポイント
新しい安否確認システムを選定する際は、以下7つのポイントを意識することが重要です。
- 機能数と料金のバランス
- 料金体系
- 取得可能な災害情報
- 操作性
- システムの安定性
- セキュリティ対策
- サポート体制
上記の内容を意識すると、自社の条件に見合うシステムを選べる確率が高まります。
機能数と料金のバランス
多機能型の安否確認システムを導入すると、さまざまな場面で活躍が見込めます。
たとえば、掲示板機能が実装された安否確認では、BCPマニュアルや今後の対応などを掲載できるため、事業復旧に向けて従業員とスムーズにコミュニケーションが取れます。
また、防災トリセツを利用できると、地震や津波などの災害に応じた避難方法や備えについて学習できます。災害日数や従業員数を想定して備蓄品を管理しておくと、被災時の影響を軽減できるでしょう。
半面、多機能型の安否確認システムは初期費用や月額費用が高めに設定されている傾向にあります。解決したい課題や必要な機能の優先順位づけをしておくと、予算内で機能性に優れたシステムを導入しやすくなるでしょう。
料金体系
安否確認システムの多くは、月額固定制の料金体系を採用しています。
月額固定制とは、利用できる機能と人数、月額料金があらかじめ決められたタイプです。ユーザー数の増加やオプションを利用しない限り、追加費用は発生しません。
また、毎月一定の料金を支払う仕組みのため、支出管理が楽になります。月額料金はユーザー数に応じて設定され、50人や100人などの区分で変動するケースもあります。
そのため、安否確認システムを選定する際は、自社の従業員数でどのくらいの金額が設定されているか比較しましょう。
取得可能な災害情報
気象庁と連携している安否確認システムを導入すれば、地震や津波などの災害情報が配信されます。ただし、システムによって取得できる災害情報の数は異なるため、事前に内容の確認が必要です。
主に取得できる災害情報を以下に記載しました。
- 地震
- 津波
- 警報や注意報
- 記録的短時間大雨情報
- 指定河川洪水予報
- 洪水
- 土砂災害
災害情報を多く取得できると、従業員に安全確保や避難を素早く促せます。
操作性
操作性に優れた安否確認システムを導入すると、回答結果の集計や被害状況の共有など、一つひとつの作業を効率的に進められます。特にクラウド型の安否確認システムを導入する場合、無料トライアルを利用して操作性を確認しましょう。
無料トライアルとは有料プランへの移行前、最大1ヶ月ほど安否確認システムを無料で利用できる制度です。多くのシステムで用意されている制度で、費用をかけずに操作画面や利用可能な機能などを試しながら、自社との相性を確認できます。
仮に導入を見送ったとしても、費用は発生しないためリスクはほとんどありません。まずは無料トライアルを利用し、操作性を確認した上で、有料プランの導入を検討しましょう。
システムの安定性
安否確認システムを選ぶ上で、システムの安定性は重要なポイントです。
本来、安否確認システムは緊急時に従業員や家族の無事を迅速に確認するために導入されます。しかし、システムの安定性が低い場合、大規模災害が起きた際に稼働しないおそれがあります。
万が一システムが稼働しなかった場合、導入コストに見合った効果が得られず、事業継続にも支障をきたしかねません。そのため、サーバーの分散化やネットワーク環境の冗長化など、強固な災害対策を講じているシステムを選びましょう。
また、複数のデータセンターが稼働している安否確認システムを選ぶと、大規模災害が起きてもデータ消失を避けられます。安定した運用が可能な安否確認システムを選ぶことで、緊急時の迅速な対応と企業のリスクマネジメントを強化しましょう。
セキュリティ対策
安否確認システムには従業員の氏名や連絡先など、個人情報を多く保存します。個人情報の流出を避けるには、強固なセキュリティ対策を講じているシステムを選ばなければなりません。
たとえば、データの暗号化や24時間体制でのサーバー監視など、サービスサイト上でセキュリティ対策の内容を確認しましょう。また、ISMSやプライバシーマークを取得した企業のシステムを選ぶのも有効です。
どちらも第三者機関が認定している規格で、簡単に取得できません。取得済みの企業は、一定水準以上の情報セキュリティ対策が講じられていると判断できます。
サポート体制
システムの導入から運用まで、手厚いサポートを受けられると、システムの乗り換えを安心して決断できます。特に使用したことのない安否確認システムを導入する場合、システムの操作方法や運用面で疑問が生じるケースも少なくありません。
そのため、チャットや電話、Web会議など、さまざまな手段で担当者と連絡が取れると、トラブルが起きても早期解決が望めるでしょう。
また、オンラインヘルプやマニュアルが充実していると、必要な情報を効率的に収集でき、問い合わせの手間が省けます。安否確認システム導入後のスムーズな運用を実現するためにも、サポート体制の充実度を事前に確認しましょう。
利用実績が多い安否確認システム5選
多くのユーザーに利用されている安否確認システムを5つ紹介します。
- 安否確認サービス2
- エマージェンシーコール
- オクレンジャー
- 安否確認システムANPIC
- セコム安否確認サービス
システムごとの特徴を紹介します。
安否確認サービス2
安否確認サービス2は、トヨクモ株式会社が提供する安否確認システムです。業種や企業規模を問わず多くのユーザーに利用されており、導入実績数は4,000社を突破しました。
安否確認サービス2では、すべての契約企業を対象に、毎年防災の日に全国一斉訓練を実施しています。防災訓練では実際の災害と同等の負荷をシステムに与え、安定して稼働するかを確認するのが目的です。
全国一斉訓練の詳細については、下記記事も参考にしてください。
これまでの訓練結果では、トヨクモが導入しているサービス品質保証制度(SLA)の基準を下回ったことがありません。そのため、安否確認システムの乗り換えを検討中の企業も、安心して決断しやすいでしょう。
また、防災訓練は単なるシステム検証にとどまらず、自社が策定したBCPの内容を確認する場としても活用できます。
サイト上には、防災訓練の日時と時間帯は公開されますが、開始時刻は事前に通知されません。突発的な災害時に近い状況下で訓練を実施でき、実践的な対応力を身につけられるでしょう。
また、訓練終了後は安否確認メールの回答率や回答時間などが記載されたレポートが送付されるため、現状の課題を把握し、今後の改善に役立てることが可能です。
安否確認サービス2は、BCPの強化や従業員の防災意識向上に取り組んでいる企業に、おすすめのシステムと言えます。
エマージェンシーコール
エマージェンシーコールとは、株式会社インフォコムが提供する安否確認システムです。多くのユーザーに利用されており、導入実績数は5,200社に達しました。エマージェンシーコールは、災害発生後に関する機能が充実したシステムです。
メールや専用アプリ、FAXなど、従業員との連絡手段が充実しているだけでなく、システム上には最大10個まで連絡先を登録できます。
従業員から回答を得られるまで最大100回まで安否確認メールを再配信するため、高確率で回答が望めるでしょう。回答結果は自動で集計されるため、管理者が対応する必要はありません。
また、同社は安否確認サービスを提供して30年の実績を誇ります。防災に関して豊富なノウハウを持ち、防災グッズや危機管理コンサルティングなど、幅広いサービスを展開しています。
防災対策全般やリスクマネジメントの強化を検討中の企業に、おすすめの安否確認システムと言えるでしょう。
オクレンジャー
オクレンジャーは株式会社パスカルが提供している安否確認システムです。医療機関や地方自治体、学校など、幅広い組織で導入されており、導入実績数は4,000社を突破しました。
オクレンジャーの特徴は、災害情報を多く取得できる点です。地震や津波情報の取得はサービス料金に含まれており、料金プランを問わず災害情報が自動的に配信されます。
オプションを利用すると、以下に関する災害情報の取得も可能です。
- 気象庁の注意報と警報、特別警報
- 記録的短時間大雨情報
- 土砂災害警戒情報
- 指定河川洪水予報
- 熱中症警戒アラート
自社が拠点を置く地域の気候や気象状況に応じて、必要な情報を選択しましょう。
また、自動翻訳機能が実装されており、掲示板や掲示板、スケジュールなどの多言語表記に対応しています。英語やスペイン語を中心に13か国語の表記に対応しているため、外国人の従業員を多数抱える企業にもおすすめの安否確認システムです。
安否確認システムANPIC
ANPICは、株式会社アバンセシステムが提供する安否確認システムです。ANPICはコストパフォーマンスに優れているため、国立大学に多数導入され、国立大学でのシェア率は40%を突破しました。
海外にサーバーを設置しており、国内で大規模災害が起きてもサーバーダウンを招く心配がいりません。
また、初期費用と月額料金がともに安く、ユーザー数が50名の場合は初期費用が25,000円、月額料金は5,130円です。
ANPICは、低コストで導入可能な安否確認システムを探している企業に、おすすめの安否確認システムです。
セコム安否確認サービス
セコム安否確認サービスは、セコムトラストシステムズ株式会社が提供する安否確認システムです。国内有数の導入実績を誇り、導入社数は約9,000社に達しました。
セコム安否確認サービスの特徴は、緊急事態が発生しても、従業員との連絡が取りやすい点です。
ドコモとau、ソフトバンクで安否確認システム専用の接続領域を確保しており、スマートフォンの機種を問わず高速通信が安定して望めます。複数のデータセンターが稼働しているため、システム上のデータを失う心配もいりません。
また、セコム安否確認サービスでは、専用チームが24時間365日体制で災害情報の取得に努めています。管理者に通知する前に情報の内容をチーム内でチェックしており、手間をかけずに正確な情報を集められます。
自社に適した安否確認システムへ乗り換えよう
安否確認システムの機能性やコストパフォーマンスに不満を覚えたら、新しいシステムへ乗り換えを検討すべきです。安否確認システムを乗り換える際は、さまざまな点に気を配らなければなりません。
ただし、安否確認システムの種類は多く、どのシステムを選べばいいか、わからない方もいるでしょう。
「安否確認サービス2」はリピート率99.8%、導入実績数4,000社以上を誇る安否確認システムです。災害情報の自動取得や安否確認メールの自動送信、回答結果の自動集計など、安否確認を効率化する機能を一通り実装しています。
掲示板やメッセージ機能も利用できるため、被害状況の報告や今後の対応についてスムーズにやり取りを交わせます。
また、安否確認サービス2は月額料金がリーズナブルに設定されています。初期費用や最低利用期間は発生せず、30日間の無料トライアルも用意されており、時間をかけて自社との相性を確認できるでしょう。
安否確認システムの乗り換えを検討中の方は、安否確認サービス2をぜひご利用ください。