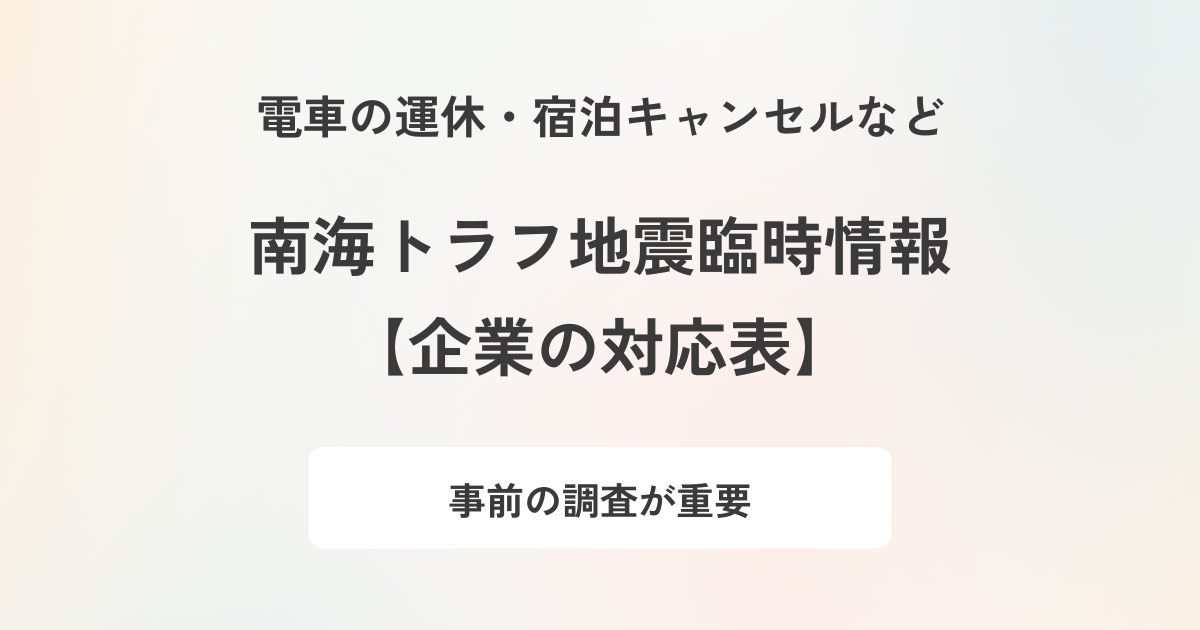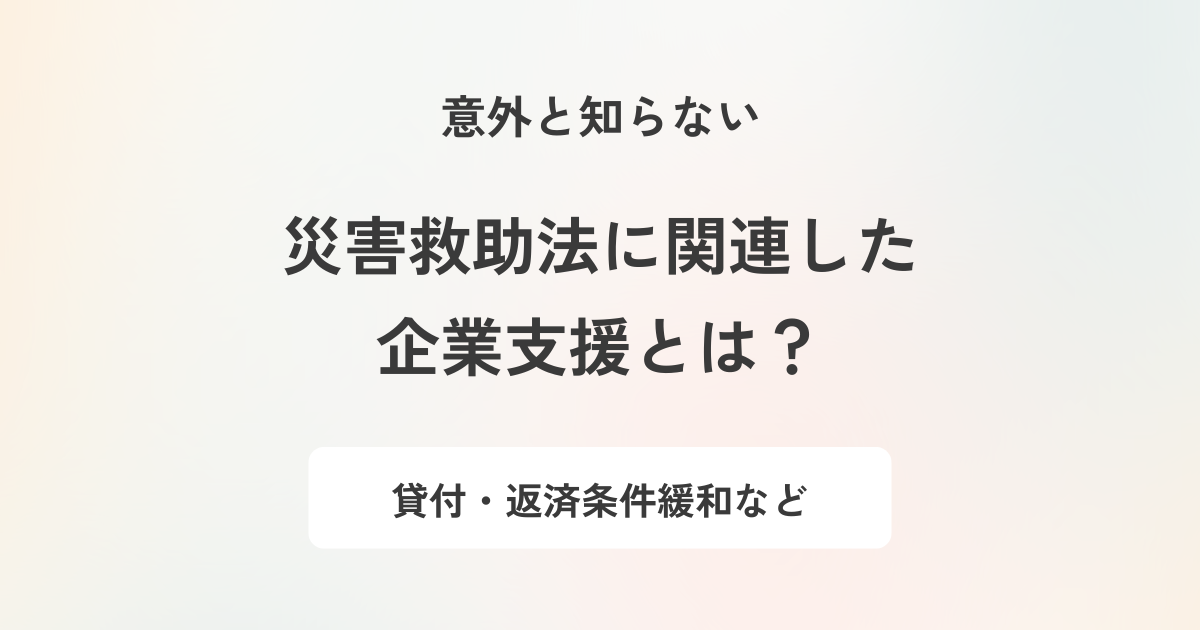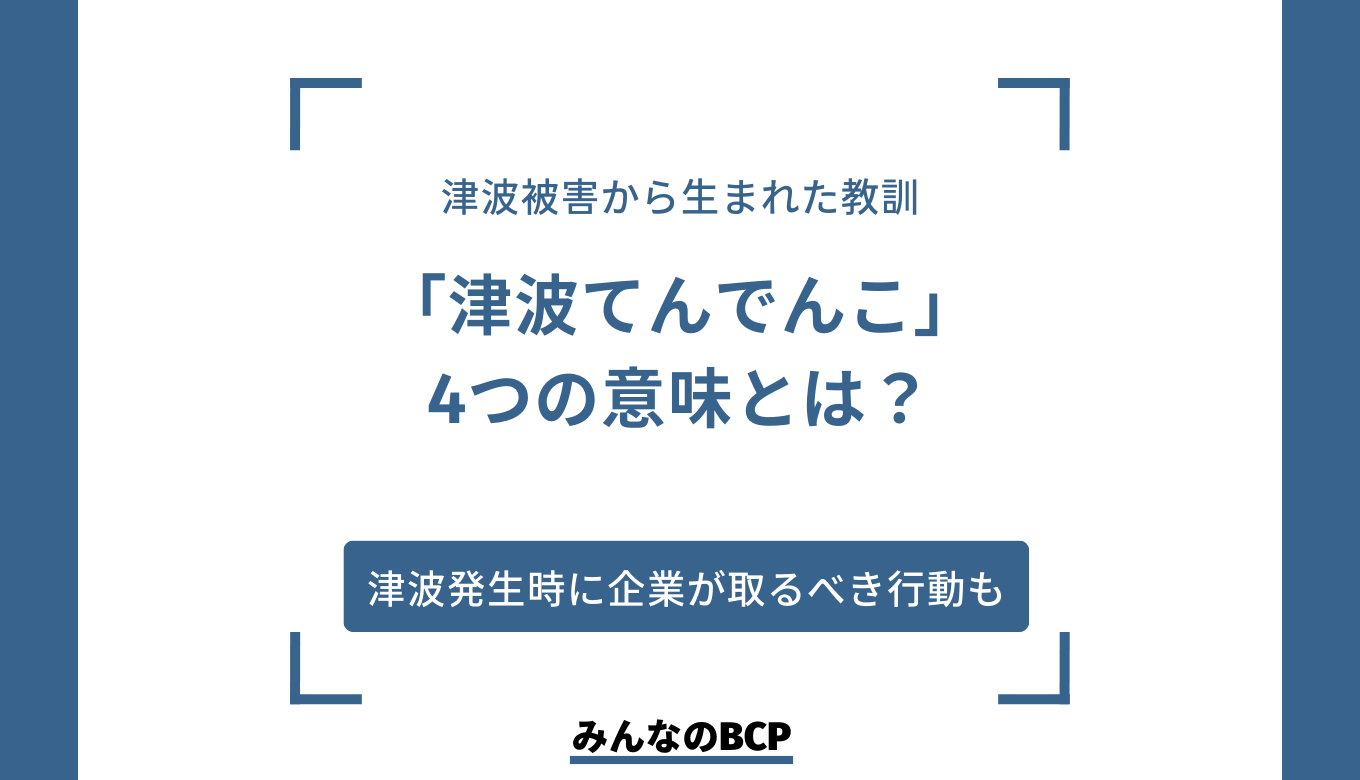【企業向け】地震発生時の安否確認を確実に! BCP担当者必見の完全ガイド
みんなのBCP編集部
大地震は、いつどこで起こるか予測できません。発生時、従業員の安全をいかに迅速に確認し、事業継続に向けた初動を的確に行えるかが、企業の存続を左右します。しかし、「安否確認体制は本当に十分か」「最適なシステムがわからない」といった不安の声はあとを絶ちません。本記事では、企業の経営層や防災・BCP担当者の皆様が抱える課題に応えるため、地震発生時の安否確認の重要性から、具体的な方法、システムの選び方、効果的な運用体制の構築まで、実践的な知見を網羅的に解説します。自社の防災力強化に向け、確かな一歩を踏み出しましょう。
目次
なぜ地震発生時の安否確認が企業にとって重要なのか?
地震発生後、まず最優先すべきは人命、すなわち従業員の安全確保です。安否確認は、そのためのもっとも基本的な活動と言えるでしょう。
事業継続と従業員の安全確保
従業員の無事が確認できて初めて、企業は次のステップ、つまり事業の復旧・継続へと進むことができます。安否確認は、単に状況を把握するだけでなく、支援が必要な従業員を特定し、企業としての責任を果たす上でも不可欠です。従業員とその家族の安心を守ることは、企業の社会的責任(CSR)でもあります。
BCP(事業継続計画)における安否確認の位置づけ
BCPとは、災害などの緊急事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または可能な限り短い期間で復旧させるための方針や体制、手順を示した計画のことです。このBCPを発動し、実行に移すためには、「どのくらいの従業員が出社・稼働可能なのか」を把握する必要があります。安否確認は、まさにBCPの初動における最重要プロセスなのです。
実施しないことのリスク(法的・信用的側面)
安否確認体制が不十分な場合、従業員の安全確保が遅れるだけでなく、事業復旧の遅延にも繋がります。これは従業員からの信頼を損なうだけでなく、企業としての安全配慮義務違反が問われる可能性も否定できません。結果として、企業全体の信用失墜や事業機会の損失といった、深刻なリスクに発展する可能性があります。
地震時の安否確認、基本の方法と手段を徹底比較
安否確認にはさまざまな方法があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社に合った方法を検討することが重要です。
電話連絡網
古くからある方法ですが、一人が繋がらないと次の人への連絡が滞る、担当者の負担が大きい、そして何より災害時には電話回線が輻輳(ふくそう)し繋がりにくくなるという大きなデメリットがあります。確実性に欠けるため、主要な手段としては推奨しにくいのが現状です。
メール・メーリングリスト
一斉に情報を送れる利点はありますが、従業員がメールを確認できる状況にあるか、そもそもメールサーバーが稼働しているか、といった不確実性があります。また、返信状況の集計や未返信者への再連絡は手作業となり、迅速な状況把握には課題が残ります。
SNS(LINE、Facebook等)
日常的に使われているため連絡しやすい面はありますが、プライベートなツールを業務連絡に使うことへの抵抗感や、情報セキュリティのリスク、既読機能だけでは安否の詳細が不明瞭、公式な情報管理が難しいなどの問題点があります。安否確認の主たる手段としては慎重な検討が必要です。
安否確認システム・アプリ
現在、多くの企業で導入が進んでいるのが専用の安否確認システムやアプリです。自動で安否確認通知を送信し、回答状況をリアルタイムで集計・可視化できます。災害時でも繋がりやすいよう設計されており、管理者の負担軽減と迅速・確実な安否確認に大きく貢献します。
その他(集合場所、伝言ダイヤル等)
地域の避難場所などを一時的な集合場所と定める、災害用伝言ダイヤル(171)の利用ルールを決めておく、といった方法も補助的な手段として考えられます。ただし、これらはシステム障害時の代替策や、補完的な位置づけとして捉えるのが適切でしょう。
自社に最適な安否確認システム・サービスの選び方
多くの安否確認システムの中から、自社に最適なものを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。導入してから後悔しないために、慎重に比較検討しましょう。
機能比較:自社のニーズを満たすか?(自動集計、連絡手段、多言語対応など)
比較すべき機能は多岐にわたります。主に、以下のような機能が挙げられます。
- 自動集計・レポート機能
- メール以外の連絡手段(アプリのプッシュ通知、SMSなど)
- GPSによる位置情報把握
- メッセージのテンプレート機能
- 外国人従業員のための多言語対応
- 家族の安否も登録できる機能
複数の製品を比較し、自社のニーズに合わせて必要な機能を洗い出すことが重要です。
費用対効果:コストと機能・サポートのバランスは?
費用体系はサービスによってさまざまです。初期導入費用、月額の基本料金(従業員数に応じた課金が多い)、オプション機能の費用などを確認しましょう。単純な価格だけでなく、機能やサポート内容を含めた費用対効果で判断することが大切です。
その他の選定基準:自社の状況にフィットするか?(規模、業種、連携、サポート)
従業員数や拠点数といった企業規模、業種特有のニーズ(たとえば、現場作業員が多いなど)、既存の人事システムなどとの連携の可否、導入時や運用時のサポート体制の手厚さなども重要な選定基準となります。トライアル(試用)期間があれば、実際に使ってみることをおすすめします。
クラウド型とオンプレミス型はどこが違う?
現在は、インターネット経由で利用するクラウド型(SaaS)が主流です。自社でサーバーを持つ必要がなく、導入・管理が比較的容易で、災害時にもベンダー側のインフラで稼働が期待できます。一方、オンプレミス型は自社管理下に置けるメリットがありますが、初期投資や維持管理の負担が大きくなります。多くの企業にとってクラウド型が有力な選択肢となるでしょう。
無料ツールと有料サービスの違い
無料のツールも存在しますが、機能制限、広告表示、サポート体制の不在、災害時の稼働保証がない、などの制約がある場合が多いです。企業の公式な安否確認手段としては、信頼性、機能性、サポート体制の整った有料サービスを検討するのが一般的です。これは従業員の安全を守るための投資と考えるべきでしょう。
以下の記事で、主要な安否確認システム14製品を比較・解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:【2025年】安否確認システム14製品を徹底比較!導入に失敗しない選び方も解説
実効性のある安否確認体制の構築と運用のポイント
優れたシステムを導入しても、それを使う体制が整っていなければ意味がありません。実効性のある運用体制を構築し、維持していくことが重要です。
BCPへの組み込み方:発動基準と連携プロセス
安否確認を単独の取り組みとせず、必ずBCP全体の中に明確に位置づけましょう。「震度いくつ以上で安否確認を発動する」といった具体的な発動基準や、安否確認の結果をどのように事業継続の判断(出社指示、在宅勤務指示など)に繋げるかのプロセスを定めておく必要があります。
具体的な運用フローとルール策定(誰が、いつ、何を、どのように)
「誰が」安否確認を発動し、「いつ」「どのような」メッセージを送り、「どのように」回答を集計し、未回答者に「どう」対応するのか、といった具体的なフローとルールを文書化し、関係者で共有することが不可欠です。曖昧な点をなくし、緊急時でも迷わず行動できるようにしましょう。
担当者・責任体制の明確化と多重化
安否確認の主担当者と副担当者を明確に任命します。災害時には担当者自身が被災する可能性もあるため、必ず複数の担当者を置き、権限を分散させておく(多重化)ことが極めて重要です。担当者不在時でも運用が滞らない体制を目指しましょう。
従業員への周知・教育(説明会、マニュアル配布)
なぜ安否確認が必要なのか、自社で導入しているシステムの使い方、緊急時にどのような連絡が来るのか、そしてどのように回答すればよいのかを、全従業員に周知徹底する必要があります。定期的な説明会の実施や、わかりやすいマニュアルの配布、ポータルサイトでの情報提供などが有効です。
定期的な訓練の重要性と効果的な実施方法
安否確認体制が形骸化しないためには、定期的な訓練が欠かせません。システムの操作に慣れるだけでなく、連絡先の情報が最新か、ルールに不明瞭な点はないかなどを確認するよい機会です。抜き打ち訓練や、さまざまな災害シナリオを想定した訓練を取り入れることで、より実践的な対応力を養うことができます。
関連記事:企業が安否確認訓練を実施する目的は?具体的な手順とシナリオを紹介
収集した安否情報の集計・分析と次のアクションへの連携
安否確認システムで集まった情報は、単に「無事かどうか」を確認するだけでなく、「誰が」「どこで」「どのような状況か」を迅速に把握し、必要な支援や次の指示に繋げるための重要なデータとなります。ダッシュボード機能などを活用し、経営層や対策本部が状況を即座に理解できるようにすることが求められます。
よくある問題と失敗しないための対策・他社事例
安否確認体制を運用する上では、さまざまな問題が発生しがちです。事前に想定される問題とその対策、そして他社の事例から学び、自社の体制をより強固なものにしましょう。
「連絡がつかない」「回答がない」場合の代替手段・対応
システムからの連絡に応答がない従業員に対して、どのように対応するかは事前に決めておくべき重要な事項です。再通知のルール、電話など別の手段での連絡、事前に同意を得た上での緊急連絡先への連絡など、複数の対応策を用意しておきましょう。
システム障害やインフラ遮断への備え
安否確認システム自体が利用できない、あるいは通信インフラが広範囲に途絶するといった最悪の事態も想定しておく必要があります。システムの冗長性(データセンターの分散など)を確認するとともに、衛星電話の配備や、オフラインでも確認できる代替連絡手段(事前に定めた集合場所など)を検討することも有効です。
従業員のITリテラシー差への配慮
スマートフォンやアプリの操作に不慣れな従業員がいることも考慮し、できるだけシンプルで直感的に操作できるシステムを選ぶことが望ましいです。丁寧なマニュアル作成や、個別のフォローアップ体制も検討しましょう。回答方法を複数用意することも有効な場合があります。
担当者負荷の軽減と運用の継続性確保
安否確認の運用は、担当者にとって大きな負担となる可能性があります。システムの自動化機能を最大限活用する、担当者を複数名体制にする、定期的に役割を見直すなど、属人化を防ぎ、持続可能な運用体制を築く工夫が必要です。
安否確認システム導入の成功事例:『安否確認サービス2』
トヨクモが提供する『安否確認サービス2』を導入し、安否確認体制の強化に成功した企業の事例をご紹介します。
株式会社スノーピークウェル 様
株式会社スノーピークウェル様は、令和6年能登半島地震を契機に安否確認体制の課題を再認識しました。ITに不慣れな従業員が多い、従来のメールや電話では安否確認が難しい、また家族への一斉連絡手段も不足しているという課題がありました。
こうした課題を受け、同社は「安否確認サービス2」を導入。操作が簡単でカテゴリー別の一斉連絡が可能な点、スマートフォンから回答状況を確認できる点、初期費用・解約費用が不要な点が決め手となりました。
導入後は安否確認訓練を実施し、平常時の情報共有にも活用。個人のITリテラシーに関係なく、簡単・確実に安否確認を実施できる体制を実現しました。
この事例の詳細はこちら:株式会社スノーピークウェル|安否確認の体制構築が、事業継続の鍵 令和6年能登半島地震で危機感を感じ、約1ヶ月でスピード導入
京都生活協同組合 様
京都生活協同組合(京都生協)様は、旧システムの操作性の悪さや人事情報の更新作業の煩雑さに課題を抱えていました。令和6年能登半島地震を機に、より迅速で確実な安否確認体制の必要性を実感し、『安否確認サービス2』を導入しました。
「人事システムとのAPI連携機能」を活用し、人事管理システムの従業員情報を自動で連携する体制を実現。情報更新作業の手間がなくなり、安否確認業務にかかる担当者の負荷を大幅に軽減しました。
また、直感的な操作性、使いやすさから職員からの問い合わせは激減し、安否確認訓練の回答率は95.1%に向上。LINE連携機能も活用し、非正規職員への情報共有もスムーズになりました。
この事例の詳細はこちら:京都生活協同組合|生成AIを活用してAPI連携。情報メンテナンスの手間が激減した
まとめ:従業員の安全と事業継続のためにいますぐ始めるべきこと
地震発生時の迅速かつ確実な安否確認は、従業員の生命と安全を守るための基本であり、事業継続を実現するための第一歩です。見てきたように、安否確認にはさまざまな方法がありますが、現代においては専用の安否確認システムの活用が非常に有効です。
しかし、もっとも重要なことは、単にシステムを導入することではありません。自社の実情に合った運用ルールを策定し、全従業員への周知と訓練を徹底し、形骸化させずに実効性のある運用体制を構築・維持し続けることです。
この記事を参考に、ぜひ自社の安否確認体制を今一度見直し、改善すべき点があれば、今日からでも具体的な行動を開始しましょう。それが、万が一の際に従業員と会社を守るための、もっとも確実な備えとなるはずです。