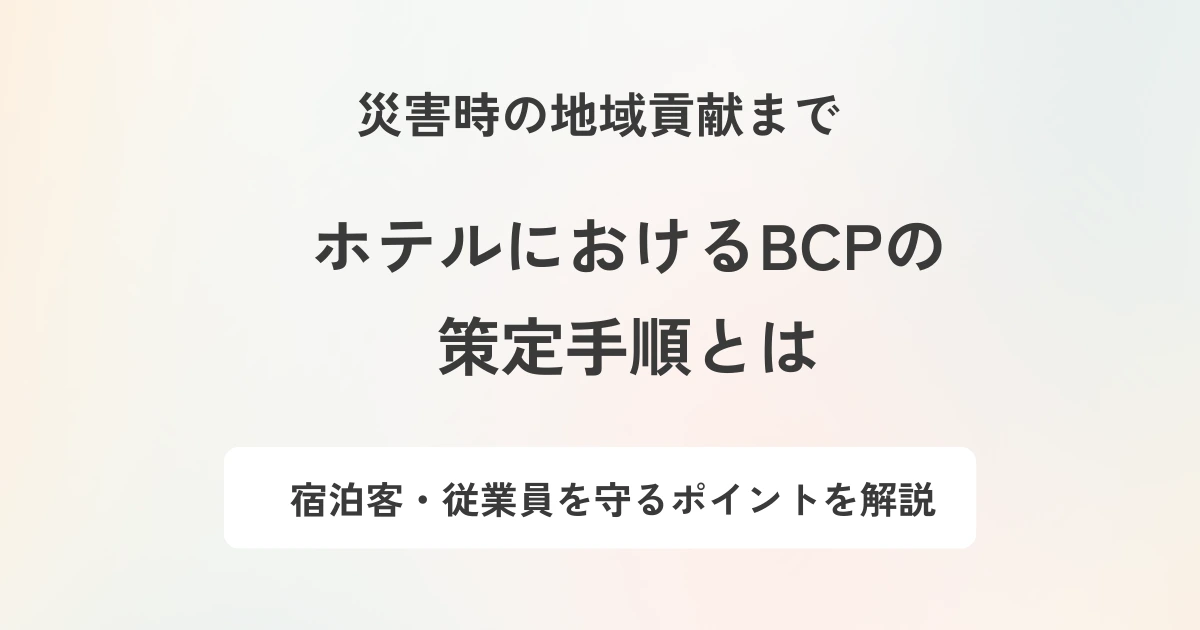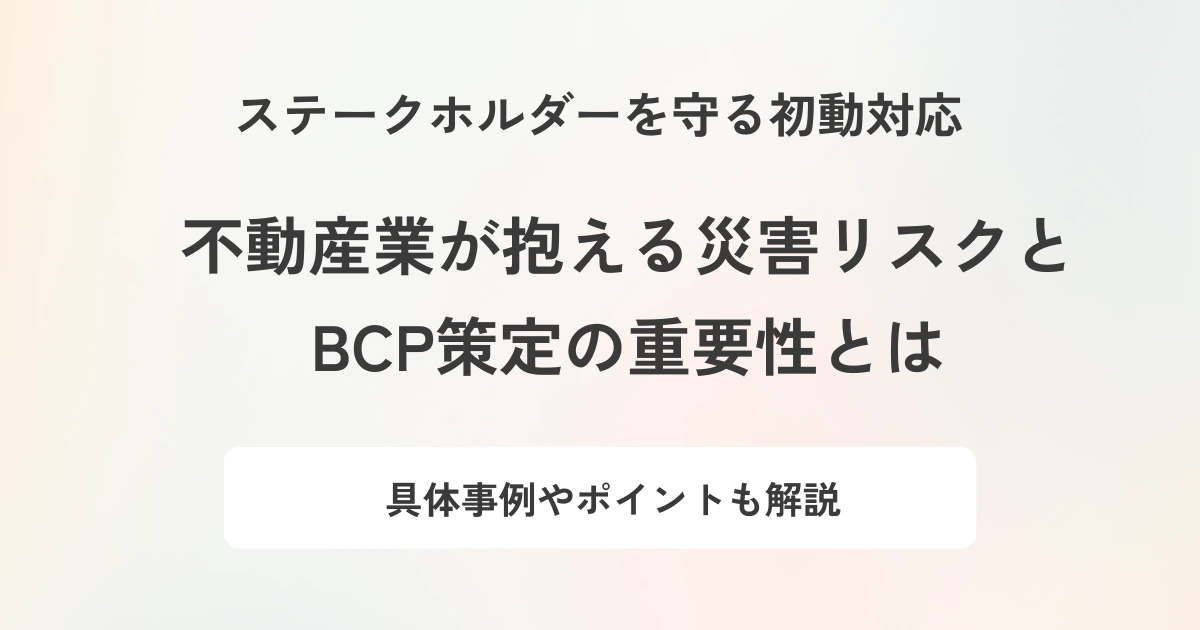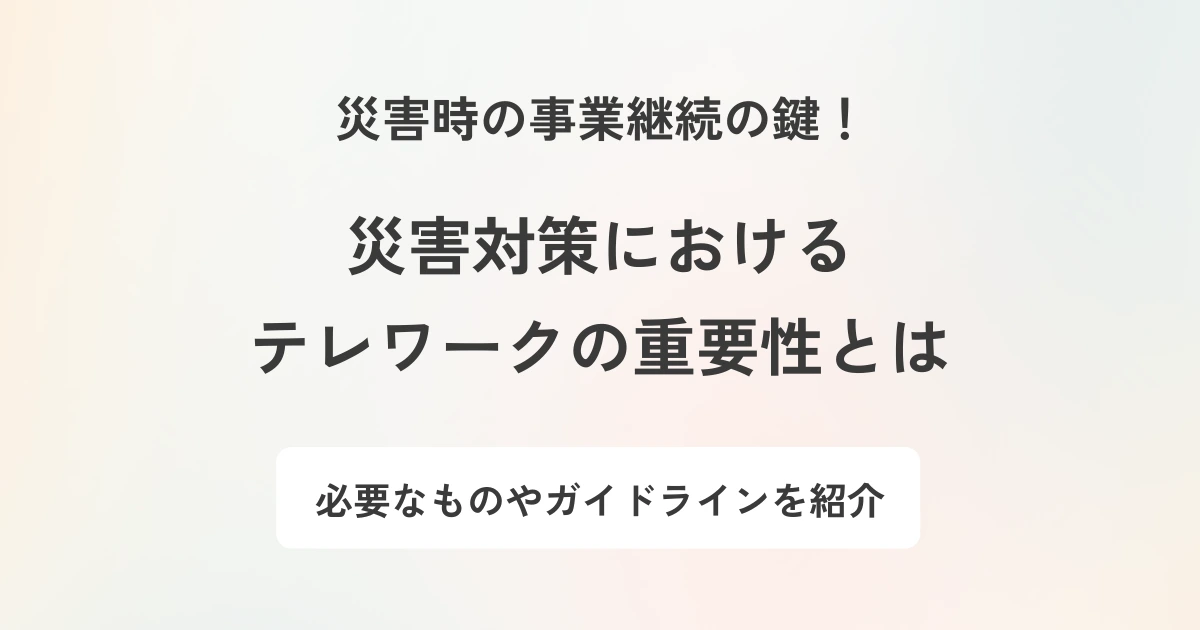飲食店に必要なBCP対策とは?具体例や策定の流れを解説

トヨクモ防災タイムズ編集部
飲食店においては、自然災害以外にも食中毒など多くのリスクがあります。そのため、BCPを作成して緊急時に備えなければなりません。
しかし、実際にBCPを策定するとなると、何をしてよいものか迷う担当者も多いはずです。
そこで、本記事では、飲食店におけるBCPの目的や災害別の例、平常時の取り組みを解説します。BCP策定に役立つサービスも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
飲食店におけるBCPの目的
飲食店におけるBCPの目的は、主に以下の3点です。
- 従業員と会社を守るため
- ステークホルダーからの信頼を獲得・維持するため
- 地域・顧客を守るため
以下で具体的な内容を紹介します。
従業員・会社を守る
まず第一に、従業員と会社を守ることが優先されます。緊急時でも従業員の安全を確保し、雇用を維持することが重要です。
また、店舗や設備などの資産を保護し、事業の中断を最小限に抑える必要があります。緊急時の対応手順を明確化することにより、従業員の不安を軽減できるほか、迅速な行動を促すことが可能です。
ステークホルダーからの信頼を得る
BCPを策定し、あらゆるステークホルダーから信頼を得ることも目的の1つです。
取引先や顧客に対して、災害時でも事業を継続する姿勢を示すことにより、信頼関係を維持・強化できます。地域社会への貢献を通じて、企業の社会的責任を果たすことも可能です。また、安全確保のための施策を策定していれば、従業員からの信頼も得やすくなります。
このようにBCPの策定と運用は、企業の信頼性や企業価値の向上につながります。
地域・顧客を守る
飲食店に関しては、従業員だけでなく地域や顧客を守ることも大切です。緊急時には、店内にいる顧客の安全を確保し、安全な帰宅を支援する必要があります。
また、災害時に食料や水などの生活必需品を提供すれば、地域住民の生活を支援することも可能です。さらに、被災地で営業を継続できれば、取引している地域の事業者や生産者の経済的な助けになり、地域経済の早期復旧にも貢献できます。
【災害別】飲食店におけるBCP対策例
飲食店におけるBCPは、災害の種類によって対策が異なります。ここでは、災害別のBCPの具体例と、とくに飲食店で注意すべき感染症対策について詳しく解説します。
地震
地震においては、以下のような対策が必要です。
- 調理器具や食器の落下防止対策
- 火災発生時の初期消火体制
- 顧客の避難誘導
- 代替食材の調達
大きな揺れに備えて、調理器具や食器の落下防止対策を行いましょう。また、飲食店では揺れによって火災が発生しやすいため、初期消火体制を整えることも大切です。営業中であれば、火を使っている可能性が高いため、燃え広がる前に消火できる体制を整えてください。
そのほかにも、顧客の避難誘導や安全の確保も必要です。避難経路を事前に確保・確認しておき、従業員が顧客をスムーズに案内できるようにしましょう。
地震発生時は地面や家屋の崩れにより物流網が滞り、通常時のように食材が入ってこない可能性があります。早期に営業を再開するためには、代替食材の調達も視野に入れるとよいでしょう。
火災
火災発生時には、以下のようなことが求められます。
- 初期消火設備の設置と点検
- 避難経路の確保
- 従業員の消火訓練
- 代替店舗の確保
被害を最小限にするには、初期消火に努めることが最も大切です。消火設備の位置確認や従業員の消火訓練を行い、シミュレーションをしておくとよいでしょう。事前に訓練をしておけば、万が一の際にも落ち着いて対応しやすくなります。
また、火災によって店舗などが燃えた場合は、代替店舗が必要になるケースもあります。被害が大きくなった場合も考慮しながら、BCP策定を進めましょう。
感染症
飲食店は、多くの人が集まる場所であり、感染症が広がりやすい環境です。そのため、感染症対策はBCPの中でもとくに重要となります。感染症が発生した際の主な対応は、以下のとおりです。
- 従業員の健康管理
- 店舗の消毒・換気
- 保健所との連携
まず第一に、従業員の健康管理を徹底し、感染拡大を防ぐ必要があります。店舗の衛生管理を徹底し、顧客に安全な食事を提供できる環境を整えることも大切です。保健所との連携を強化して最新情報を把握し、感染状況に応じて柔軟に営業形態を変更することも求められます。
感染症の発生後は信頼を取り戻すのが非常に難しくなるため、日頃から発生防止に努めなければなりません。万が一に感染症が発生した場合にもBCP策定を徹底して行い、早い段階で営業再開できるようにしましょう。
平常時の減災への取り組みも大切
飲食店におけるBCPでは、災害時の対策だけでなく、平常時の減災への取り組みも重要です。ここでは、飲食店でできる具体的な対策を紹介します。
ハザードマップの確認
常に災害に備えるためには、ハザードマップの確認が欠かせません。店舗周辺のハザードマップを確認し、地震・津波・洪水などのリスクを把握しましょう。発生する可能性のあるリスクが分かれば、対策も立てやすくなります。
避難場所や避難経路を従業員と共有し、定期的に確認することが大事です。情報は常に更新されていくため、定期的に確認・周知する必要があります。
大型什器の固定を実施する
飲食店には、大型の什器が多数設置されているケースがほとんどです。冷蔵庫・冷凍庫・食器棚などの大型什器を壁や床に固定し、転倒を防ぎましょう。大地震があった際、しっかりと固定されていれば怪我や事故を最小限に抑えられます。
もし、大きな什器が倒れてくると、二次被害につながる可能性もあるので、注意が必要です。固定する際は、什器のサイズや重量に合わせた固定器具を使ってください。
食器類の収納方法の見直しを行う
調理器具や食器なども、落下しないように収納方法を工夫しましょう。食器類は地震が起きると落下して割れ、避難経路を妨害する可能性があります。安全に避難するためにも、できるだけ落下しないようにします。
たとえば、食器棚の扉に耐震ラッチを付ければ、落下を防ぐことができます。重い食器は下の段へ収納したり、割れやすい食器は滑り止めの上に置いたりして、災害に備えましょう。
設備の安全点検を行う
飲食店では、電気・ガス・水道に関する多くの設備を使用しています。災害時は、これらの設備から二次災害が発生するケースが多いため、定期的な点検を実施してください。
とくに、厨房の火気設備やガス設備、電気設備などはこまめな安全点検が必要です。点検によって漏電やガス漏れなど、火災につながる危険性を早期に発見し、対処することができます。
また、消火器や火災報知機の設置場所の確認、使用方法に関する教育を定期的に行うことも大切です。消火器は実際に使う機会がかなり少ないため、災害時に備えて徹底した指導をしておく必要があります。
飲食店におけるBCP策定の流れ
飲食店におけるBCP策定の流れは、以下のとおりです。
- 基本方針の策定
- リスク分析
- 重要業務の特定
- 対策の検討
- 計画書の作成
- 訓練の実施と見直し
それぞれ詳しく見ていきましょう。
基本方針の策定
基本方針の策定では、BCP策定の目的や責任体制を明確にします。従業員と顧客の安全確保を最優先とするのはもちろん、地域社会への貢献を考慮する必要もあるでしょう。BCP策定の目的としては、事業の早期再開と継続を目指すことも挙げられます。
このステップでは「何のためにBCPを策定するのか」や「どのような状態を目指すのか」を明確にすることが大切です。たとえば、「顧客の安全・安心を最優先とし、食中毒や感染症発生時においても事業を早期に再開し、地域社会への影響を最小限に抑える」ことなどが挙げられます。
リスク分析
リスク分析では、地震・火災・水害・感染症など、想定されるリスクを洗い出すことが重要です。このとき、考えられるあらゆるリスクを網羅的に洗い出す必要があります。
たとえば、ハザードマップなどを参考に、地域特有のリスクを把握します。そのなかから、最も対処すべきリスクの特定を行いましょう。河川が近くにあるのであれば、氾濫による災害に備えた洪水対策に注力する必要があります。
重要業務の特定
重要業務の特定は事業活動において、中断した場合に事業継続に重大な影響を及ぼす業務を特定するステップです。
重要業務としては、食材の調達と管理や衛生面の管理などが挙げられます。とくに、災害時は食中毒が発生しやすいため、徹底した管理によって安心と安全を届けることが求められます。顧客や取引先の信頼を失わないためにも、しっかりと対策を検討することが重要です。
重要業務特定の際には、業務の依存関係も把握する必要があります。たとえば、ある業務が中断した場合、ほかの業務にどのような影響が出るかの分析をしておくことなどが挙げられます。
対策の検討
ここでは、特定された重要業務が中断した場合に、事業を早期に復旧・継続するための具体的な対策を検討します。
飲食店においては、地震発生時の代替調理場所の確保、非常用食材の備蓄、従業員への安否確認・参集方法の確立などを検討する必要があるでしょう。食中毒などが発生した際には、あわせて再発防止対策を検討することも重要です。
計画書の作成
計画書の作成では、これまでの内容を踏まえて実際にBCPを策定します。BCPは、事業継続のための具体的な手順や責任者を明確にし、組織全体で共有するための重要なツールとなります。BCP策定の際は、「誰が」「いつ」「何をすべきか」を明確に記述してください。
飲食店においては、たとえば地震発生時の初動対応、従業員の役割分担、顧客の避難誘導、設備の安全確認手順などを具体的に記述した計画書を作成します。
訓練の実施と見直し
最後に、作成した事業継続計画書に基づいて、実際に事業中断が発生した場合を想定した訓練を実施します。訓練を通じて、計画の実効性や課題を検証するだけでなく、改善につなげましょう。
また、訓練の目的と範囲を明確にし、訓練後には必ず結果を評価して課題や改善点を見つけることが重要です。たとえば、飲食店では食中毒発生を想定した顧客対応訓練、保健所への報告訓練などを実施することなどが挙げられます。
飲食店がBCPを策定する際のポイント
飲食店におけるBCP策定のポイントとしては、以下の3つが挙げられます。
- 従業員の安否確認を迅速に行う
- 一定数の従業員を確保する
- 地域との連携を図る
以下で詳しく見ていきましょう。
従業員の安否確認を迅速に行う
飲食店においては、パートやアルバイトなどさまざまな雇用形態の従業員がいます。パートやアルバイトは、正社員と比べて連絡手段が多様であり、安否確認が困難な場合があります。安否確認システムなどを導入し、迅速な安否確認を行うことが大切です。
安否確認システムは、従業員の安否情報をリアルタイムで把握し、緊急時の対応をスムーズなものにしてくれます。利用方法や連絡手段については、全従業員に周知を徹底しましょう。
一定数の従業員を確保する
多数の店舗を抱える飲食チェーンでは、営業再開時に十分な人員を確保する必要があります。従業員の安否確認と出勤可能状況の把握を迅速に行い、人員配置を最適化することも重要なポイントです。代替要員の確保や、近隣店舗からの応援体制を構築しておくとよいでしょう。
営業再開に向けて、従業員の安全と健康に配慮した勤務体制を構築する必要もあります。営業を再開したあとは、従業員の安全と健康に配慮した職場環境を維持し、従業員のモチベーションを維持することが大切です。
地域との連携を図る
飲食店においては、災害時に食べ物や水を提供する役割があります。災害時に地域住民へ食料を配布したり、炊き出しを行ったりするなど、地域貢献を意識した計画を策定しましょう。
また、地域との連携を図り、災害時の協力体制を構築しておく必要があります。食料や物資の供給、避難場所の共有など具体的な協力内容を検討することが大切です。地域社会における自社の役割を明確にし、地域との連携を深めましょう。
飲食店のBCP策定には『BCP策定支援サービス(ライト版)』がおすすめ
飲食店のBCP(事業継続計画)策定には、『BCP策定支援サービス(ライト版)』の利用がおすすめです。
BCP策定には専門知識が必要なほか、時間と手間がかかります。さらには、自社の状況に合わせた計画が難しいことも課題となるでしょう。
『BCP策定支援サービス(ライト版)』を利用すれば、専門知識がなくても自社に合ったBCPを短期間で策定できます。飲食店の実際の業務やリスクを考慮し、現実的な計画を立てることも可能です。
1ヶ月で15万円(税抜)とリーズナブルな価格設定となっており、少ない負担で利用できるのがメリットです。策定だけでなく、定期的な見直しにも適しています。
コストを抑えながら効果的なBCPを短期間で策定したい場合は、ぜひ導入をご検討ください。
BCPを策定し、災害に強い体制を整えよう
今回は、飲食店におけるBCP策定の目的や具体例を紹介しました。
飲食店のBCP策定は、会社や従業員を守るために欠かせません。また、ステークホルダーからの信頼を得たり、地域を守ったりする目的もあります。BCP策定の際には、災害の内容に合わせ、さまざまな対策を講じることが大切です。さらに、平常時の減災への取り組みも重要となります。
自社に合ったBCPを策定したい場合は、『BCP策定支援サービス(ライト版)』がおすすめです。飲食店が抱える課題に合わせ、適切なBCPを短期間で策定できます。
従業員の安否確認には『安否確認サービス2』の利用が便利
さらに、従業員の安否と被災状況を確認したい場合は、トヨクモが提供する『安否確認サービス2』もおすすめです。自動で安否確認のメッセージを送信できるため、災害発生時に迅速な安否確認ができます。そのあとの指示や情報共有も可能な掲示板やメッセージ機能を備えているため、事業の早期復旧にも役立つはずです。
たとえば、宿泊業や飲食サービス事業を展開する企業であるLEOCでは安否確認サービス2の導入により、26,000人に及ぶ従業員の安否確認を自動で一斉に行うことに成功しています。管理側の負担が軽減されただけでなく、夜間や休日に災害が発生しても迅速に対応できるようになりました。
詳しくは、以下の事例記事をご参照ください。
飲食店でBCP対策を行いたい場合、導入を検討してみてはいかがでしょうか。