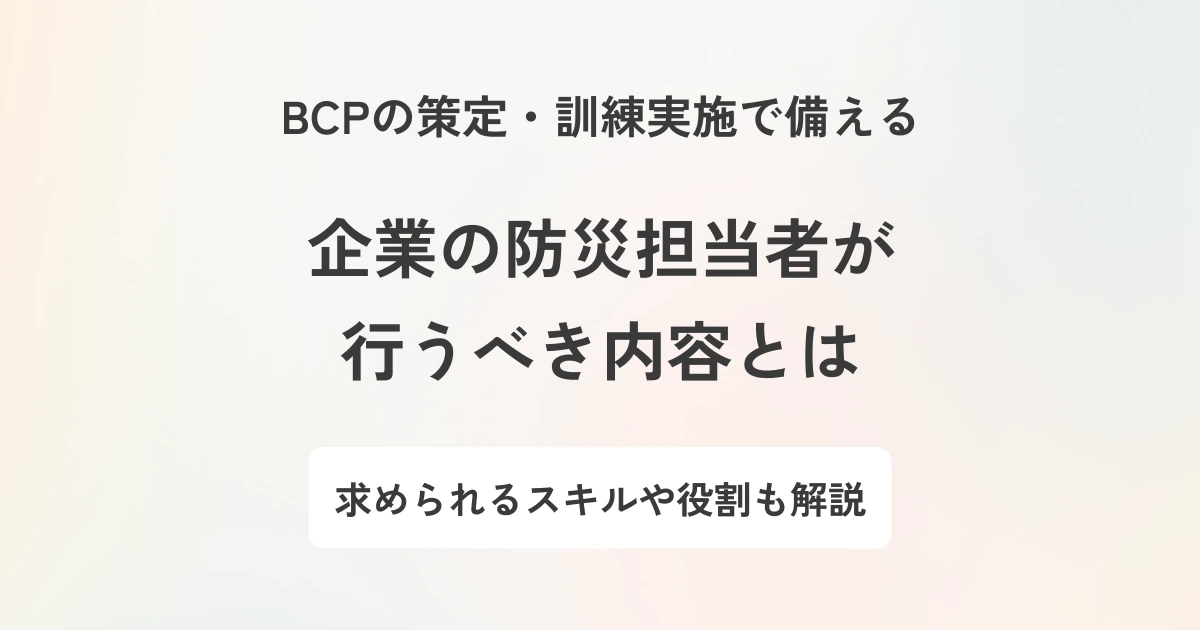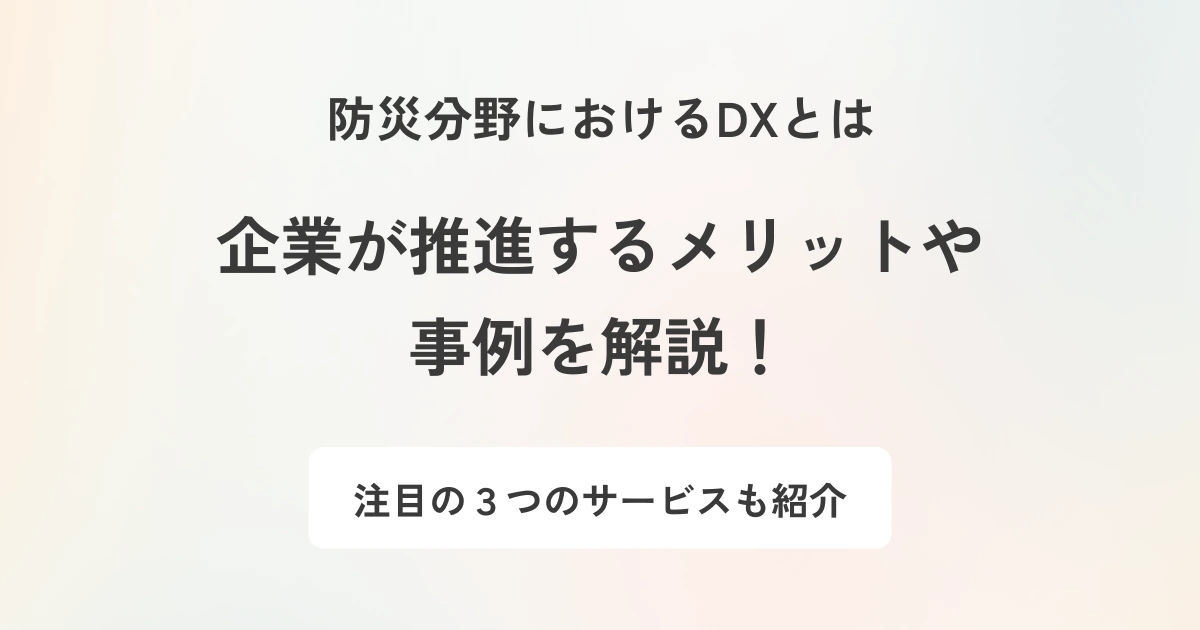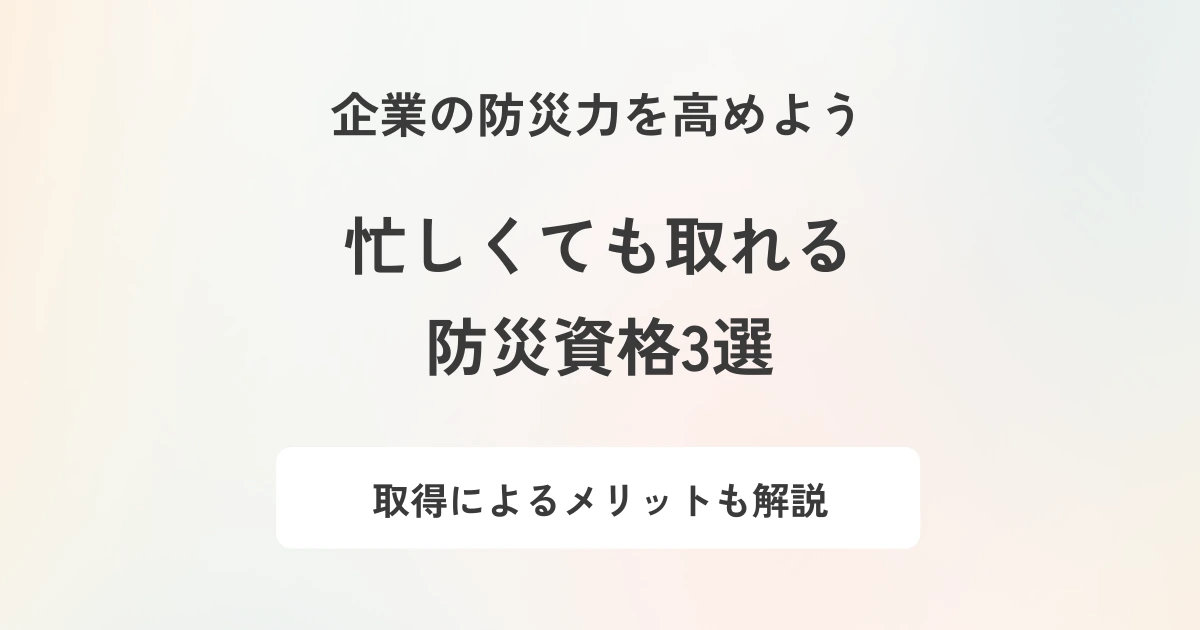危機管理担当者の役割とは?対策すべきリスクや危機管理のポイントを紹介

トヨクモ防災タイムズ編集部
企業にとって、危機管理は事業継続と信頼維持の要となります。しかし、何から始め、どのような対策を講じるべきか悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、企業の危機管理担当者が押さえておくべきリスクの種類と対策や、緊急時の対応手順、情報発信の方法など、危機管理に必要な知識とノウハウを体系的に解説します。新たに危機管理担当になった方や、これから危機管理体制の強化を図りたいと考えている経営者・ご担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次
危機管理担当とは
危機管理担当とは、企業や組織が遭遇する可能性のあるさまざまな危機を未然に防ぎ、発生時には被害を最小限に抑えるための責任者です。その役割は多岐にわたり、リスクの特定と評価や危機管理計画の策定、緊急時の対応、そして事後対応と評価などを行います。
優先順位を付けて速やかに対処することにより、被害を最小限に抑えると共に、従業員や企業を守ることが求められます。
さらに、危機発生後の事後対応も重要な役割です。原因究明や被害状況の把握、関係者へのケア、そして再発防止策の策定を通じて、組織の信頼回復と再発防止に努める必要があります。危機管理担当者は常に最新の情報を収集し、変化するリスクに対応するための知識とスキルを磨かなければなりません。
企業の危機管理担当者の概要と役割
企業の危機管理担当者は、組織が直面する可能性のある自然災害や事故、情報漏洩、風評被害などの危機から企業を守り、事業継続を確保するための専門家です。平時から緊急時、そして事後にかけて、多岐にわたる役割を担います。
平時における役割
平時における危機管理担当者の主な役割は、危機発生の予防と発生時の影響を最小限に抑えるための準備です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- リスクアセスメントの実施
- 危機管理計画の策定・見直し
- 危機管理体制の構築
- 従業員への教育・訓練
- 情報収集と分析
- 関係機関との連携
まずは、企業内外の潜在的なリスクを特定・分析・評価し、優先順位をつけます。続いて、特定されたリスクに対応するための具体的な計画を策定し、定期的に見直しながら改善を図りましょう。そのほかにも、情報伝達経路や役割分担などの危機管理体制の構築、従業員への周知や教育も必要です。
緊急時における役割
緊急時における危機管理担当者の主な役割は、被害の拡大防止と事業の早期復旧です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 初動対応の指揮
- 緊急対策本部の設置・運営
- 情報収集と共有
- 意思決定の支援
- 事業継続計画(BCP)の発動と実行
- 従業員と家族への支援
危機発生直後は、迅速かつ適切な初動対応を指揮し、被害状況の把握や従業員の安全確保、関係機関への連絡などを行いましょう。必要に応じて緊急対策本部を設置し、情報の集約、対策の検討、指示の伝達などを行うことも求められます。
迅速な情報収集と共有、収集した情報に基づいた意思決定の支援なども必要です。そのほか、BCPの発動と実行、家族への支援なども危機管理担当者が行います。
事後における役割
事後における危機管理担当者の主な役割は復旧と再発防止、そして教訓の活用です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 復旧活動の推進
- 被害状況の分析と評価
- 原因究明と再発防止策の策定
- BCPの見直しと改善
- 関係機関への報告
- 風評被害対策
復旧活動を推進することはもちろん、原因の究明と再発防止策の策定も欠かせません。同じことが起きないように努めるほか、次に緊急事態が起こった際に、さらに迅速に動けるようにBCPの見直しと改善を図るのも重要な役割です。
危機管理が必要なリスク
危機管理には、起こり得るリスクの把握が欠かせません。ここでは、危機管理が必要なリスクを紹介します。
自然災害
自然災害は、地震・津波・台風・豪雨など、予測が困難で甚大な被害をもたらす可能性のあるリスクです。これらの災害は、人命に関わるだけでなく、企業の事業継続や地域社会の機能にも深刻な影響を与えます。
危機管理においては、自然災害のリスクを適切に評価し、避難計画の策定や事業継続計画(BCP)の策定など、多岐にわたる対策を講じる必要があるでしょう。
また、地域社会との連携を強化し、災害発生時の情報共有や協力体制を構築することも重要です。自然災害は、その規模や種類によって対策が異なるため、地域特性や事業特性に応じた柔軟な対応が求められます。
事故
事故は、労働災害や交通事故、製品事故など、予期せぬ事態によって発生するリスクです。人命や財産に損害を与えるだけでなく、企業の社会的信用を失墜させる可能性もある大きなリスクのため、しっかりと対策を整えておく必要があります。危機管理においては、事故の発生原因を分析し、再発防止策を講じることが重要です。
また、事故発生時の対応手順を明確化し、関係者への適切な情報提供や支援を行う必要があります。事故の種類によっては、法的責任や賠償問題に発展する可能性もあるため、専門家と連携し、適切な対応を行うことが求められます。
情報漏洩
情報漏洩は、個人情報や企業秘密、顧客情報などが外部に漏洩するリスクです。近年では、サイバー攻撃の高度化や内部不正の増加により、情報漏洩のリスクは増大しています。情報漏洩は、企業の信頼を失墜させるだけでなく、法的責任や損害賠償問題に発展する可能性もあるので厳重な注意が必要です。
情報セキュリティ対策を強化するだけでなく、従業員のセキュリティ意識を高めることも重要となります。情報漏洩が発生した場合の対応手順を明確化し、混乱のないようにしましょう。対応が遅れるほど、被害も甚大になりやすいので、注意が必要です。
風評被害
風評被害は、根拠のない噂や誤った情報が拡散し、企業の社会的信用やブランドイメージを損なうリスクです。最近ではSNSの普及により、風評被害の拡散速度は加速しており、企業にとって大きな脅威となっています。
風評被害は売上減少や株価下落など、経済的な損失をもたらすだけでなく、従業員のモチベーション低下や離職にもつながる可能性があります。風評被害の発生源を特定し、正確な情報を迅速に発信することが重要です。また、風評被害の拡大を防ぐことも重要です。
危機管理のプロセス
危機管理のプロセスは、以下のとおりです。
- リスクアセスメント
- 計画策定
- 計画の実行
- 評価と見直し
正しい手順を踏み、さまざまなリスクに備えましょう。
1.リスクアセスメント
リスクアセスメントは、組織が直面する可能性のあるリスクを特定し、その影響度と発生確率を評価するプロセスです。このプロセスを通じて潜在的な脅威を把握し、優先的に対策を講じるべきリスクを明確にしましょう。
過去の事例を分析したり、専門家からのアドバイスを受けたりしながら、自社にとってリスクとなることをリストアップしてください。リスクアセスメントは、危機管理の出発点であり、その精度が後のプロセスに大きく影響を与えます。
2.計画策定
計画策定は、リスクアセスメントで特定されたリスクに対する具体的な対策を立案するプロセスです。この段階では、緊急時の対応手順や責任者の役割分担、情報共有の方法などを詳細に定めます。さまざまな意見を取り入れて、現実的かつ実行可能な計画を策定することが重要です。
策定した計画は従業員に周知し、実際の緊急時に計画通りに動けるように従業員の訓練を行います。
3.計画の実行
計画の実行は、策定された計画に基づいて、実際の危機発生時に対応するプロセスとなります。この段階では、迅速かつ正確な情報収集と状況把握が不可欠です。関係機関との連携を密にし、適切な指示を出すことが求められます。
また、訓練やシミュレーションを通じて、改善点を見つけることも重要です。計画の実行では、柔軟な対応が求められます。状況は常に変化するため、計画通りに進まない場合も想定されます。そのため、臨機応変に対応できる体制を構築しておくことが重要です。
4.評価と見直し
評価と見直しは危機対応の経験をもとに、計画や体制を改善するプロセスです。この段階では、対応の成果と課題を客観的に評価し、再発防止策や改善策を策定します。関係者からのフィードバックを収集し、多角的な視点から評価を行うことが重要です。
また、新たなリスクの出現や社会情勢の変化に合わせて、計画を定期的に見直す必要があります。評価と見直しを通じて、組織は危機管理能力を継続的に向上させられます。状況に合わせていつでもすぐに動き出せるよう、必ず定期的な見直しを行いましょう。
危機管理体制を構築する際のポイント
続いて、危機管理体制を構築する際のポイントを紹介します。
責任者を決める
危機管理体制の構築において、責任者の選定は極めて重要な要素です。責任者は、危機発生時の意思決定や関係機関との連携、情報発信など多岐にわたる役割を担います。そのため、責任者には、リーダーシップや判断力、コミュニケーション能力が求められるでしょう。
また、責任者は危機管理に関する専門知識や経験を有していることが望ましいと考えられます。責任者の選定にあたっては、組織の規模や事業内容、リスクの種類などを考慮し、最適な人材を選ぶことが必要です。責任者は危機管理体制の要として、組織全体の安全確保と事業継続に責任を持ちましょう。
役割分担を行う
緊急事態の発生時には、さまざまなタスクを迅速かつ効率的に遂行する必要があります。そのため、事前に役割分担を明確にしておくことが重要です。役割分担では、以下のように各担当者の役割と責任範囲を明確に定めましょう。
- 情報収集
- 状況把握
- 関係機関との連携
- 広報対応
- 被害状況の把握
- 復旧作業など
また、各担当者の連絡体制や代替要員も決めておくことにより、担当者が不在の場合でも対応が滞らないようにします。役割分担を明確にしておけば、危機発生時の混乱を最小限に抑え、迅速かつ適切な対応が可能となります。
情報共有のシステムを構築する
危機発生時には、正確な情報を迅速に関係者間で共有することが不可欠です。そのため、緊急連絡網や安否確認システムなどの情報共有のシステムを構築しておく必要があります。情報共有のシステムでは、緊急連絡網や情報共有ツール、情報共有のルールなどを整備しましょう。
また、情報共有のシステムは平時から運用し、定期的に訓練を行うことによって緊急時にもスムーズに機能するようにしておいてください。情報共有のシステムを構築することで、関係者間の連携を強化し、迅速かつ正確な意思決定を支援できます。
効率的に安否確認を行うには、トヨクモの『安否確認サービス2』の導入がおすすめです。災害時には、事前に登録した連絡先に自動で安否確認のメッセージが送られ、回答も自動で集計されるため、管理者は従業員の安否や初動対応にあたれる従業員をすぐに把握できます。
危機管理担当は再発防止策の策定も必要
危機管理担当は、再発防止策の策定も重要な任務の一つです。ここでは、再発防止策を策定する重要性とともに、具体的な内容を紹介します。
再発防止策を策定する重要性
危機管理担当者にとって再発防止策の策定は、単なる事後対応ではなく、組織の持続的な成長と信頼確保に必要なものです。災害や事故の発生後は原因を徹底的に分析し、同様の事態を二度と起こさないための具体的な対策を講じることにより、組織はより強固なものとなります。
再発防止策は、関係者からの信頼回復や組織の安全確保に加え、教訓の共有という3つの重要な目的を果たします。組織が再発防止に真摯に取り組む姿勢を示すことは、顧客・取引先・従業員など、関係者からの信頼回復につながります。再発防止策は将来の同様の危機発生を防ぎ、組織の安全性を高めることにもつながるでしょう。
具体的な内容
再発防止策の策定は、多岐にわたる側面からの検討が必要です。まず、危機発生の原因を徹底的に調査し、根本的な原因を特定します。これには、多角的な視点からの分析が不可欠です。
次に、特定された原因に基づき、具体的な対策を策定します。これには、システムの改善や教育・研修の実施、マニュアルの見直しなどが含まれます。
また、再発防止策の内容を関係者に適切に開示し、透明性を確保することも重要です。関係者からのフィードバックを収集し、再発防止策の改善に役立てることも忘れてはなりません。最後に再発防止策の効果を定期的に測定し、必要に応じて見直しを行います。
危機管理体制を強化してリスクに強い組織を目指そう
危機はいつ、どのような形で発生するか予測できません。しかし、危機発生後の対応次第で、被害を最小限に抑え、早期の復旧と事業継続を実現できます。そのためには、平時から危機管理体制を構築し、危機発生時には迅速かつ適切な対応を行うことが重要です。
また、BCP(事業継続計画)の策定は、多くの企業にとって喫緊の課題となります。専門家の知見を活用しながら効率的に策定を進めたい場合は、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』が便利です。1ヶ月15万円(税抜)と手頃な費用で利用でき、時間やコストをかけずにBCPを策定できます。