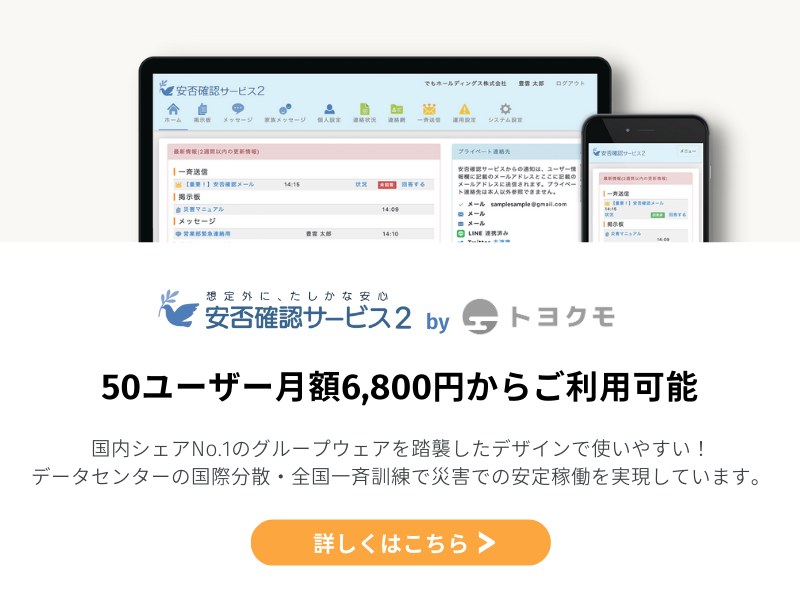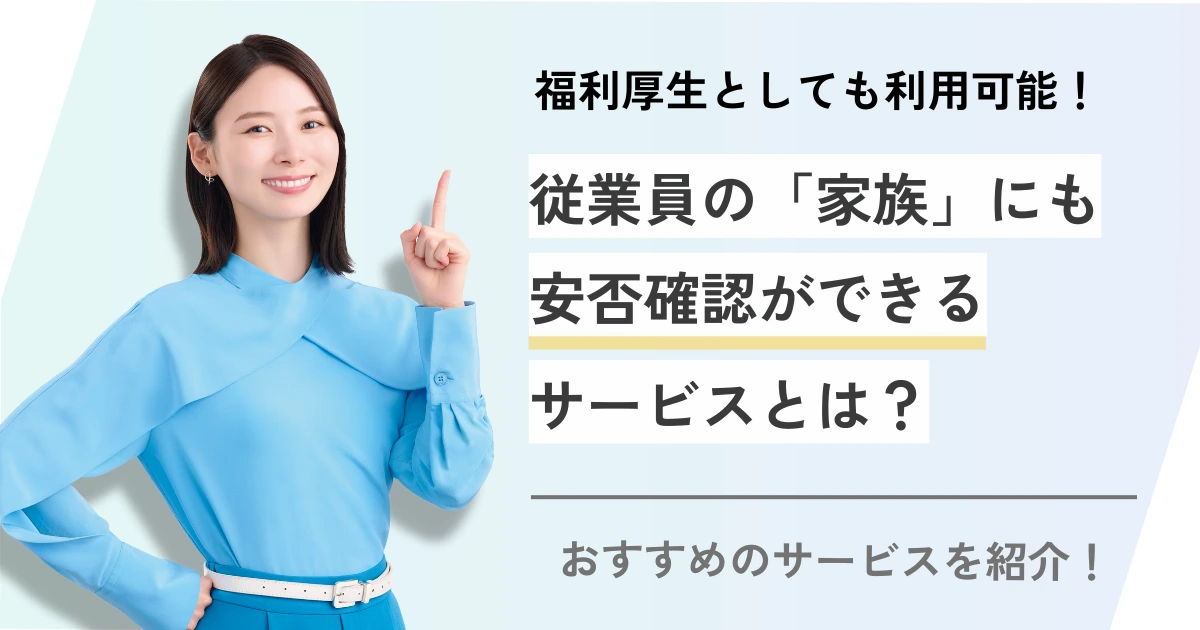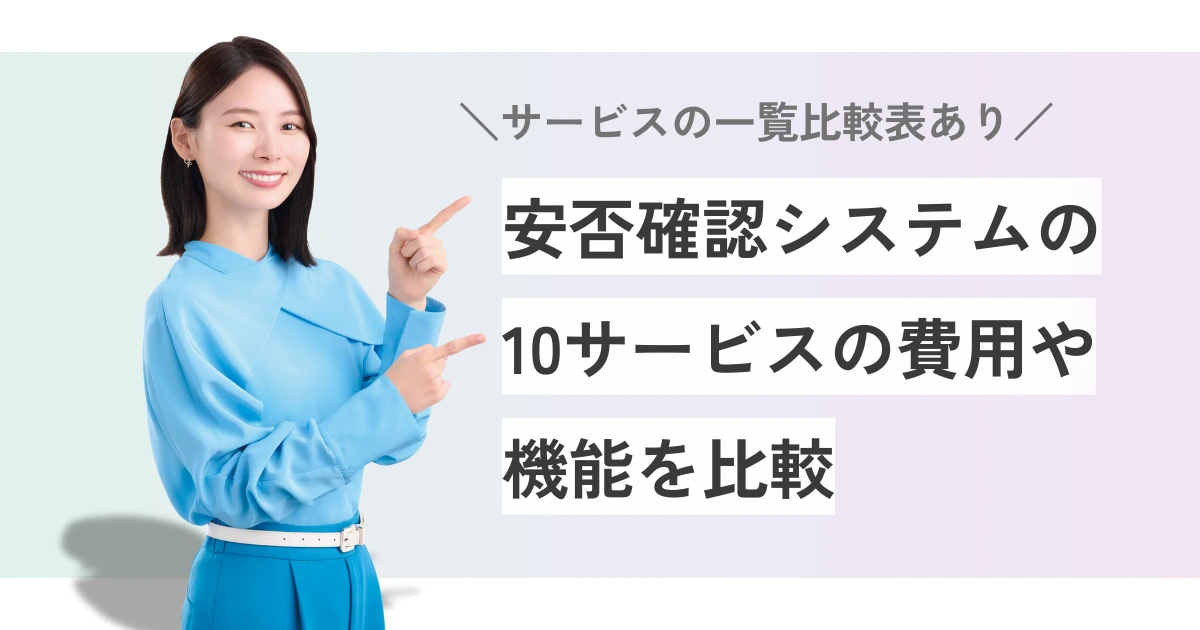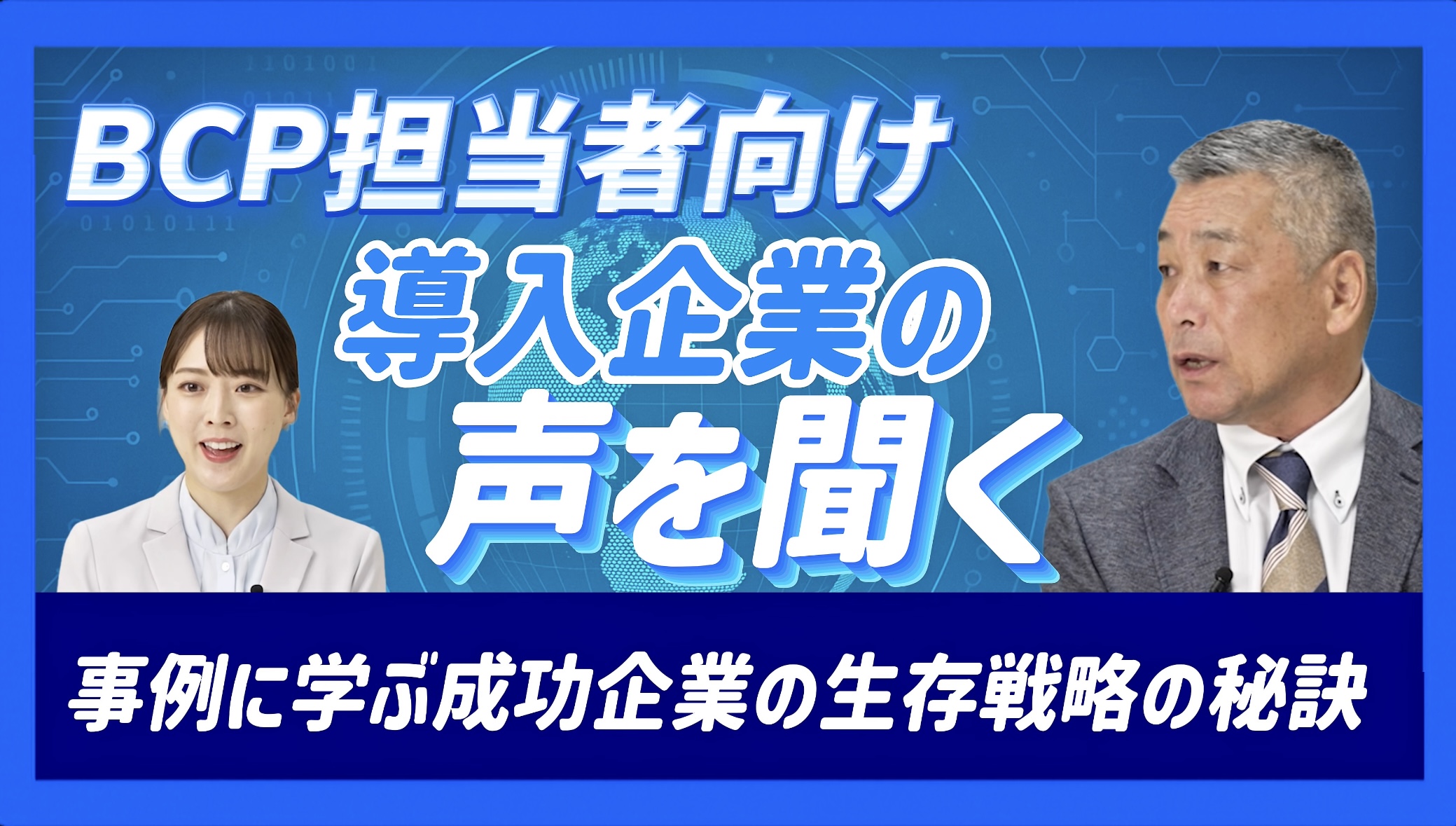BCP研修やセミナーを利用するメリットは?学べる内容や具体的な事例を解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
新型コロナウイルス感染拡大や大規模地震、ランサム攻撃による主要なサービスの一時停止など、企業にとって事業継続が難しい事態が頻発しています。緊急時に速やかな初動を可能にし、事業の早期復旧・継続を迅速化するためにはBCPの策定が欠かせません。緊急時を想定したBCPを策定していれば、混乱した状況下であっても次の一手が出しやすくなるでしょう。
とはいえ「BCPの策定方法などよく分からない」という企業担当者もいるかもしれません。本記事では、BCP策定に役立つ研修やセミナーを利用するメリットや学べる内容を紹介します。

兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。
BCPを策定できていないなら、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用をご検討ください!
早ければ1ヵ月でBCP策定ができるため「仕事が忙しくて時間がない」や「策定方法がわからない」といった危機管理担当者にもおすすめです。下記のページから資料をダウンロードして、ぜひご検討ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
目次
BCP研修とは
BCP研修・セミナーとは、BCPに関する情報を学べる研修です。BCPの理解を深めたり、緊急時の対応を見直したりでき、より実用性の高いBCPを策定できます。
また、BCP研修はその内容により対象が異なります。たとえばBCPの策定方法を学べる研修であれば危機管理担当者が受講し、緊急時の対応方法は従業員も受けるべきといえるでしょう。BCP研修を通じてBCPへの理解を深めることが緊急時の備えともなるでしょう。
日本は地震や感染症などの自然災害や突発的なトラブルが多く、事業継続にリスクを抱えています。これに備えるため、BCP(事業継続計画)研修の実施が重要です。
研修の対象者は、BCP策定を担当する社員や、既存の計画を見直したい人などが中心になります。研修の目的は、BCPへの理解を深め、実効性の高い計画を策定し、運用できるようにすることです。
また、研修を通じて、BCPの必要性を認識してもらうことも大切で、リスクに対して適切に対処できる力を養うことが求められます。
BCP研修やセミナーで学べる主な内容
BCP研修やセミナーで学べる主な内容は、以下のとおりです。
- BCPを策定する目的や必要性
- BCP全体の枠組み
- BCPの策定手順
- BCPの運用方法
- 防災意識
- 災害発生時に求められる対応
それぞれについて解説します。
BCPを策定する目的や必要性
BCPの策定目的や必要性を理解することは大変重要です。「なぜBCPを策定しなければいけないのか」を理解できると、策定する際のポイントが明確になるからです。BCPへの理解を深め、従業員1人ひとりが関心を持てるようにしましょう。
BCP全体の枠組み
BCP全体の枠組みを理解することも大切です。「BCPにはどのようなことが書かれているのか」などを理解すると、BCPの全体像を把握しやすくなります。また、多くの企業では事業計画や中長期経営計画と連動させてBCPを策定しています。BCPの枠組みを理解できると、事業継続への必要性も分かりやすいでしょう。
BCPの策定手順
BCPの策定目的や必要性が理解できても、具体的な策定手順が分からないと活用できません。そのため、研修やセミナーで策定手順を学び、自社に合ったBCPを策定します。研修やセミナーによって学べる内容は異なるものの、自社の事業計画や経営計画を参考にしながら演習できる場合もあります。研修やセミナーを通してBCP策定への理解を深め、実際に策定しましょう。
BCPの運用方法
研修やセミナーによっては、BCPの運用方法を学べます。BCPは策定して終わりではなく、実際に運用しながらより有効なものに改善していくことが重要です。たとえば、実際に災害が起きたとき、どのような手順でBCPを運用していくかを学べる研修もあるでしょう。運用方法を学ぶと、緊急時の組織体制を整える際にも役立ちます。
防災意識
BCP研修は、社内全体の防災意識を向上させる重要な機会です。とくに、全社員を対象とした研修では、防災意識の強化が欠かせません。
研修では、自社で策定されているBCPの内容を説明しつつ、社員同士がディスカッションする場を設けられます。研修を通じて、現状のBCP計画が適切かどうかを見直すことが重要です。
意見を交換しながら課題を洗い出し、必要な改善点を共有することで、より実効性のあるBCPの策定や運用につなげられます。
災害発生時に求められる対応
BCP研修では、防災意識の向上に加え、災害発生時に必要な対応について学ぶことが重要です。全社員を対象とした研修では、災害時の適切な行動を事前に習得することで、緊急時の対応力がつきます。
研修内容として、防災訓練も兼ねる場合、AEDの使用方法や心肺蘇生法、負傷者への応急処置、ライン設備の復旧手順、IT部門におけるサーバー復旧方法などを取り入れるとよいでしょう。これにより、実際の災害時にも落ち着いて対応できる体制を整えられます。
BCP研修やセミナーを利用するメリット
BCP研修やセミナーを利用するメリットは、主に以下の2つです。
- BCPへの理解を深められる
- 有効なBCPを策定できる
- 無料で参加できる研修が多くある
それぞれについて解説します。
BCPへの理解を深められる
BCP研修やセミナーを受けると、BCPへの理解を深められます。
トヨクモが運営する防災総研が実施した「自社のBCPに対する認識調査」によると、実際にBCPについて把握できている新入社員は17.5%しかいませんでした。
一方、BCPを担当する企業内での防災教育担当者へ向けたアンケートでは、全体の75.7%が自社のBCPについて「新入社員教育をした」と答えました。これらの結果からみると、BCPについての社内研修を実施しているにもかかわらず、受けた従業員には浸透していないということが分かります。
BCP研修やセミナーを利用すると、目的や構造といった枠組みから学べます。すると従業員のBCPに対する理解が深まりやすくなり、緊急時に備えられるでしょう。
有効なBCPを策定できる
研修やセミナーを受けると、有効なBCPを策定できます。先ほどの「自社のBCPに対する認識調査」では、「訓練の形骸化」や「災害を想定しきれているのか」という教育担当者の回答が目立ちました。東日本大震災以降もさまざまな大災害が発生しており、災害下においても事業を継続していくBCPの重要性が高まっている証拠です。しかし、他のプロジェクトのようにPDCAサイクルなどで見直すことができないため、BCP策定ではより実践的なものを作る必要があります。
BCP研修やセミナーを受けると、適切な運用ができているかどうかを判断できるようになります。こうした能力を身につけることで、日常業務に戻るまでのサービスの復旧過程や災害管理を網羅したBCPを策定できるようになるのです。
とくに研修やセミナーでは体系的にBCPについて学べるため、自社のBCPの問題点を解消したり、新しいBCPを策定したりする際の役に立つでしょう。
無料で参加できる研修が多くある
BCP研修の多くは無料で受講できるため、コストをかけずに企業の防災対策を強化できます。とくに、BCP策定が義務化されている介護事業者向けの研修は充実しており、実践的な内容を学べるものが多くあります。
また、Zoomなどのオンラインセミナーを活用すれば、時間や場所にとらわれずに受講でき、業務の合間を活用して学習することも可能です。無料であっても質の高い研修が多く、効果的にBCPの知識を習得できます。
BCP研修やセミナーのデメリット
BCP研修やセミナーにはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、下記の3つに分けて注意すべき点をまとめました。
- 実践時にギャップを感じる可能性がある
- 理解が深まるまでに時間がかかる
- 緊急性が低いため後回しになるおそれがある
とくにBCP研修で学んだ内容を、実践で活かせるかどうかは重要な課題です。あらかじめデメリットを把握しておけば、適切に対処できるようになるでしょう。
実践時にギャップを感じる可能性がある
BCP研修やセミナーで学んだ内容を実際に活用しようすると、想定外の問題が発生し、ギャップを感じる可能性があります。たとえば、策定時に決めた連絡手段や指揮系統が機能しないこともあるでしょう。
このように、BCP研修で学んだ内容が実践に活かされず、机上の空論に終わるリスクがあるため、最悪の状況を想定しながら実際の運用を行い、課題を洗い出すことが重要です。得られたフィードバックをもとにBCPの見直し、継続的な改善を重ねることで、より実効性のあるBCPを構築できます。
理解が深まるまでに時間がかかる
BCP研修は、事業継続計画の理解を深めるうえで重要ですが、学習に時間がかかる点がデメリットとして挙げられます。
無料で研修に参加できるからといって多くの時間を学習に割くと、通常の業務時間が減るおそれがあります。そのためBCP研修は取り入れつつも、業務への影響を最小限に抑える工夫が必要です。
たとえば、オンライン研修を活用したり、業務の合間に学べる環境を整えたりすることで、効率的に学習を進められるでしょう。
緊急性が低いため後回しになるおそれがある
BCP研修は企業にとって重要な取り組みですが、緊急性が低いため、日々の業務を優先し後回しにされることが少なくありません。
とはいえ、災害やトラブルが発生した際に適切に対応するためには、事前の学習が不可欠です。BCP研修の必要性を社内で共有し、従業員が積極的に参加しやすい環境を整えることが企業に求められます。
具体的には、研修のスケジュールを柔軟に設定したり、業務時間内に組み込んだりすることで、受講のハードルを下げるのがおすすめです。
BCP研修・セミナーの事例
ここではBCPの研修やセミナーの事例について紹介します。
BCP策定研修・セミナーの事例
BCP策定研修・セミナーは、以下のような流れで開催されることが一般的です。
【日程の参考例】
9:00〜9:10 イントロダクション
9:10〜9:30 BCPの概要・枠組みに関する座学
9:30〜12:00 ワークショップ(活動ルールの策定・ステークホルダー分析など)
12:00〜13:00 昼休憩
13:00〜15:30 ワークショップ(BCPの演習計画の策定など)
15:30〜16:30 BCPの策定
16:30〜17:00 クロージング
一般的なBCP研修ではイントロダクションがあり、BCPとはなにかやBCPの必要性について具体的な説明をします。BCP策定研修・セミナーでは枠組みを解説することが多く、緊急時対応の計画や安全確保のための初動、危機管理計画などBCPに必要な行動計画の種類や、事業の継続計画の概要などを取り上げます。
ワークショップ形式のセミナーでは災害発生直後の活動ルールを決め、ステークホルダー分析を行って災害時の組織編成について整理、実際の状況を想定した模擬研修・セミナーが展開されます。
また、災害時は企業内に対策本部を設置しBCPを進めていくことになりますが、その際の活動を決定するという研修もあります。
BCP策定をゴールとする研修では、ワークショップでBCPに関する感覚や経験をもとにBCPの演習計画を立ててみるなど、自発的な活動の練習をさせてくれる傾向があります。そして、最後に自社のBCPを策定して研修は終了になります。
BCP訓練手法に関する研修・セミナーの事例
BCP訓練手法に関する研修・セミナーは、以下のような流れで開催されることが一般的です。
【日程の参考例】
14:00〜14:10 イントロダクション
14:10〜15:20 訓練の必要性や実効性についての座学
15:20〜15:50 簡易評価についての座学
15:50〜16:40 ワークショップ(図上訓練・意思決定訓練など)
16:40〜17:20 訓練の評価と課題の改善手法の解説
17:20〜18:00 自社訓練計画の設計
訓練が形骸化している企業の場合、BCP訓練や評価を適切に行うことを目的とした研修・セミナーを選ぶのがおすすめです。
一般的なBCP訓練手法に関する研修・セミナーはイントロダクションから始まり、訓練の必要性についての座学があります。実効性について学んだ後、評価手法について学びます。BCP訓練に関する一連の知識を身につけた後で、ワークショップへと進むのが一般的です。
ワークショップでは図上訓練や意思決定訓練といった、災害時を想定した訓練手法などを実践します。ワークショップによって実際の訓練手法について体験したら、訓練の評価と課題の改善手法について学びます。
最後に、ワークショップの体験を生かして自社訓練計画の設計をすることが一般的です。
なお、BCPに関する研修・セミナーは目的やカリキュラムによって千差万別です。ここで挙げたBCPの研修やセミナーの事例も一例でしかありません。より実践的なBCPの研修やセミナーを受けたいのであれば、ワークショップの時間が設けられているものを選ぶとよいでしょう。
BCPの研修やセミナーを選ぶ際のポイント
BCP研修やセミナーを選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。
- 研修の目的を明確にする
- 研修期間や日程を確認する
- 企業の規模に合ったものを選ぶ
- どのようなスタイルで学習したいかを検討する
- BCPの理解度に合わせて選ぶ
それぞれについて解説します。
研修の目的を明確にする
まず、BCP研修の目的を明らかにしたうえで学ぶようにしましょう。研修やセミナーによっては目的が異なるため、自社が必要とする内容かどうかを調べる必要があります。「今何を知りたいか」「どうして研修を受けようと思ったのか」などを明確にしたうえで、受ける研修を選んでください。
研修期間や日程を確認する
研修やセミナーによって日程はさまざまで、1日に3〜4時間程度の内容を数日に分けて行うものや、前期・後期の2回に分けているものもあります。そのため、業務に支障が出ない範囲で受けられる研修・セミナーを選ぶといいでしょう。
しかし、研修期間が空きすぎると内容を忘れてしまうため、心配な方は1日で基礎からBCP策定まで行える研修がおすすめです。1日だけであれば、通常の業務への支障も少ないでしょう。
企業の規模に合ったものを選ぶ
企業の規模に合わせて、研修やセミナーを選ぶのもひとつです。たとえば商工会議所や商工会、中小企業組合などを主催者とする中小企業の集合研修を利用すると、中小企業に合った内容を学びやすいでしょう。
公的な機関が主催する研修やセミナーは多くの企業から担当者が出席するため、コストを抑えながら効率的なBCP策定ができます。
どのようなスタイルで学習したいかを検討する
BCP研修・セミナーを受ける際は、どのようなスタイルで学習したいかを検討しましょう。BCP研修・セミナーといっても実施方法はさまざまあり、代表的な例は以下のとおりです。
- 座学
- ワークショップ
- 動画学習
- オンライン講習
研修やセミナー会場に行くことが難しい場合は、オンラインを活用するのもひとつです。従業員それぞれが自分のペースで学べるのも魅力といえるでしょう。
BCPの理解度に合わせて選ぶ
BCPの理解度は人それぞれ異なるため、自分に合った研修を選ぶことが重要です。初心者、中級者、上級者の判断方法は、下記の指標を目安にしてください。
- 初心者:BCPの基本的な内容や記載事項を把握する
- 中級者:策定されたBCPが実際に機能するかを確認し、改善点を見つける
- 上級者:災害や緊急時を想定したシミュレーションを行い、柔軟な対応力を養う
自社の状況や個人の習熟度に応じて適切な研修を選び、効果的に学ぶことが大切です。
BCP研修のよくある疑問
そもそもBCP研修を自社で実施するにはどのようにすればいいのか、業種ごとにBCP研修の内容は変わるのかなど、さまざまな疑問が浮かぶ方もいるでしょう。BCP研修のよくある疑問を、Q&A形式でいくつか紹介します。
- BCP対策・研修は義務づけられている?
- 自社で実施できる?
- 業種ごとにBCP研修の内容は変わる?
- インターネットで見られるBCP研修の動画はある?
- BCP研修は年に何回実施すべき?
上記の5つに分けて解説するので、ぜひ参考にしてください。
BCP対策・研修は義務づけられている?
BCP対策や研修は、多くの企業において義務化されていません。そのため、とくに中小企業では十分に策定されていないケースが多くみられます。
しかし、2024年4月から介護施設など一部の業種ではBCPの策定が義務化されており、対応が求められています。
義務の有無にかかわらず、企業が災害や緊急事態に適切に対応するためには、リスクマネジメントの一環としてBCPを策定し、研修を実施することが重要です。事業継続のための備えとして、積極的に取り組むべきでしょう。
自社で実施できる?
BCP研修は自社で実施可能です。しかし効果的な策定と運用を実現するためには、専門的な知識や経験が求められます。
社外のサービスを活用し、BCP策定に関するノウハウをもつ専門家の意見を取り入れることで、より研修の効果を高められるでしょう。
とくに、実際にBCPを策定した経験をもつ講師が在籍するサービスを活用することで、より実践的で有益な知識を得られます。さらに、実際にBCP策定したことのある人から直接アドバイスを受けることも、具体的な対策を理解するうえで有効な方法です。
業種ごとにBCP研修の内容は変わる?
BCP研修は、業種に関係なく基本的な内容は共通しています。業種ごとに優先すべき項目や対応方法には違いがあるため、研修を実施する前に、業種ごとの特性に合った課題や対応策を社内で共有しておくことが重要です。
たとえば、生産部門では生産ラインの迅速な復旧が最優先事項となり、設備の早急な復旧が求められます。
ほかにも、デジタル部門ではシステムやサーバーの復旧が重要で、素早い対応が求められるなど、部門ごとのニーズに対応した準備が必要です。これにより、災害時に効率的で適切な対応ができるようになります。
インターネットで見られるBCP研修の動画はある?
BCP研修の動画を、インターネットから無料で視聴できるサイトはいくつか存在します。具体的には、下記の二つが挙げられます。
BCP研修の内容としては、BCPの基本的な作成手順やBCPを活用した訓練の実施方法、感染症や自然災害向けのBCPの作成方法などがあります。自社の足りない知識を、効果的に補うのがおすすめです。
BCP研修は年に何回実施すべき?
BCP研修は、業種や企業のリスク特性に応じて適切な頻度で実施することが重要です。
とくに介護や医療業界では年に2回以上、在宅系の場合は年に1回以上の実施が推奨されています。定期的に開催するもの以外に、新規採用や人事異動とあわせて実施することが望ましいといえます。
研修を実施する際には、参加者がどの部署や役職に属しているか、どのような役割を担っているかを考慮し、研修で学ぶべき内容を明確にすることが大切です。もし時間に制限がある場合は、研修の目的やテーマを絞り込んで、効率よく短時間で実施してもよいでしょう。
このように、組織に合った頻度と内容で実施することで、BCPの理解を深め、効果的に運用できる体制を整えられます。
BCPが普及しない理由・背景
中小企業を中心に、BCPが普及しない背景には以下のような理由が挙げられます。
- BCP策定の重要性・必要性を感じていない
- 法律で定められていない
- 人材・スキルが不足している
まず、BCPに関する情報や重要性が自治体や関連団体から、経営者や従業員に対して十分に周知されていないことが挙げられます。
とくに大規模な災害や予期しないトラブルを経験したことがない企業は、その重要性を実感しにくいという側面もあります。災害の実態やその対応方法について学ぶことが、BCPの必要性を理解する第一歩となるでしょう。
またBCP策定は、介護業界など一部の業種を除き、法律で義務づけられていません。そのため強制力が低く、BCPの重要性を感じていても実際に導入するまでに至らないことがあります。
ほかにもBCP策定するための人材確保やスキルの不足も大きな障害となります。とくに中小企業では、現在の業務に手が回らず、BCP策定に必要なリソースを割くことが難しい場合があるでしょう。
上記のようなケースでは、外部の専門サービスを活用することが非常に有効です。外部サービスを導入することで、社内のリソース不足を補い、適切なBCP策定につながります。
BCPの策定にはトヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』がおすすめ
「自社に合ったBCPを策定したい」「自社内でBCPを策定できる自信がない」などとお考えの方には、トヨクモが提供する『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用がおすすめです。
通常、BCPコンサルティングは数十〜数百万円ほどしますが、『BCP策定支援サービス(ライト版)』であれば1ヵ月15万円(税抜)で策定できます。また、最短1ヵ月で策定できるため、できるだけ手間をかけずにBCPを策定したい方にも向いています。
金銭的な負担を軽減ながら手軽にBCPを策定したい方は、ぜひトヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』の利用をご検討ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
BCP研修・セミナーを受けて理解を深めよう
災害は突発的に発生し、事業に多大な影響を及ぼす可能性があります。そうした際にBCPを策定していれば、円滑に通常業務に戻ることができ、事業への影響を最小限に抑えられます。しかし、実践的なBCPの策定や評価は難しく、企業担当者も頭を悩ませていることが少なくありません。
このような状況に置かれている企業担当者は外部で実施されている研修やセミナーを活用し、自社を災害や緊急事態から守る準備を進める必要があるでしょう。
なお、BCPの策定が難しいと感じる場合は、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』を活用するのがおすすめです。費用や手間を抑えながら策定できるため、BCPに多くの時間を割けない企業でも取り組みやすいでしょう。
兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。


編集者:坂田健太(さかた けんた)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部 プロモーショングループに所属。防災士。
企業の防災対策・BCP策定を支援するメディア「トヨクモ防災タイムズ」を運営。防災・BCPの専門家として、セミナー講師や専門メディアでの記事執筆も行う。
主な執筆記事に「BCPって何? ~中小企業の経営者が知っておくべき基礎知識~」「他人事では済まされない! BCP未策定が招く経営危機と、”備える”ことの真の価値とは?」(ともにニッキン ONLINE PREMIUM)などがある。