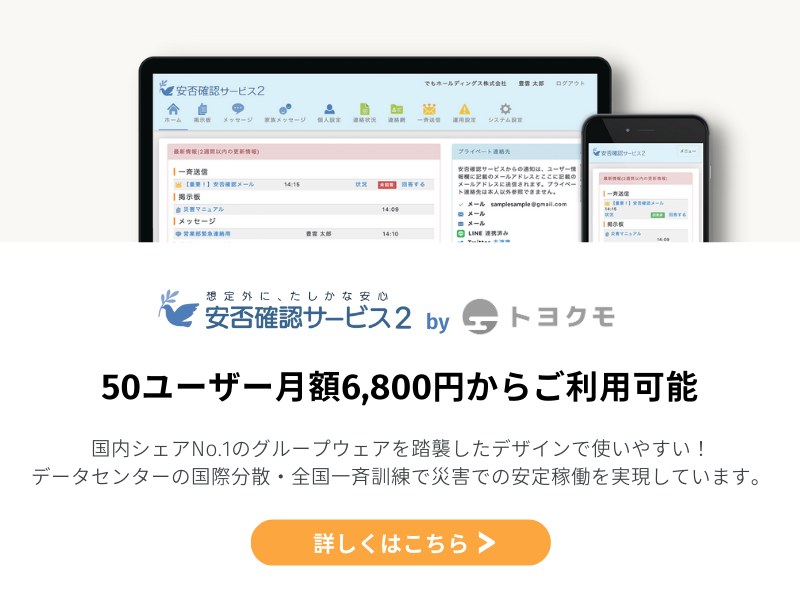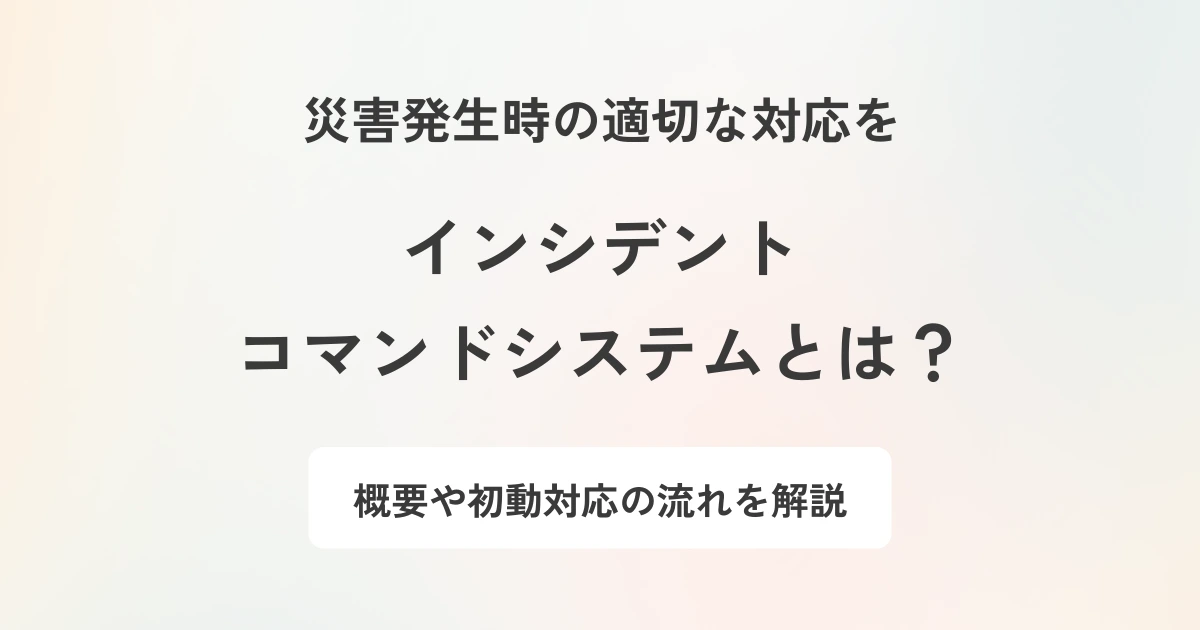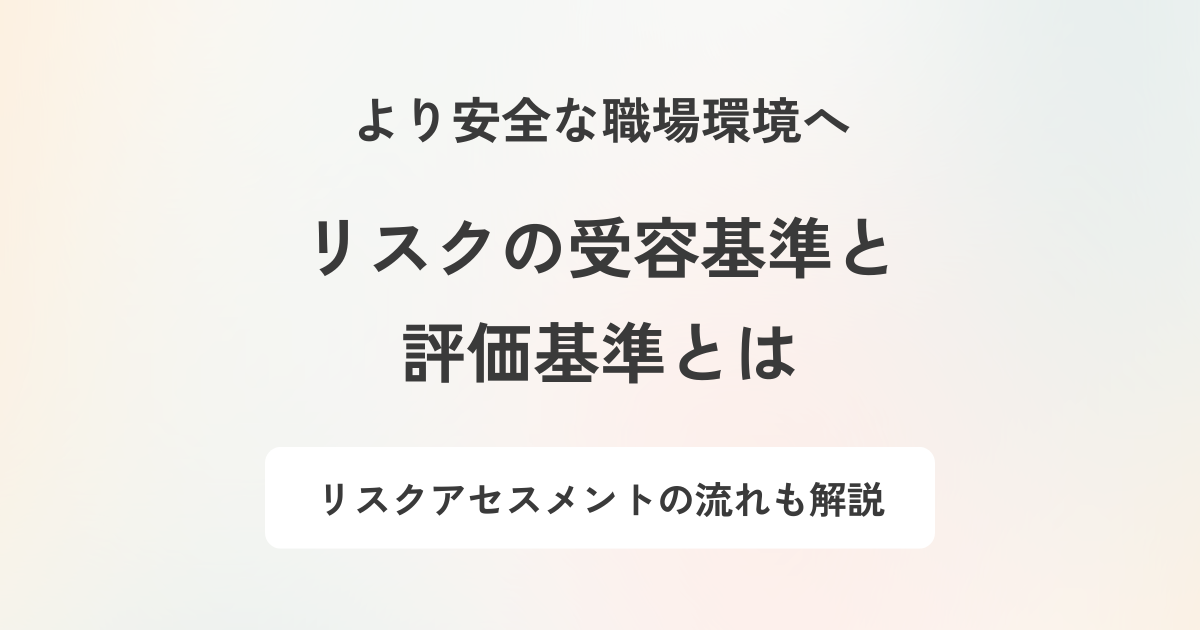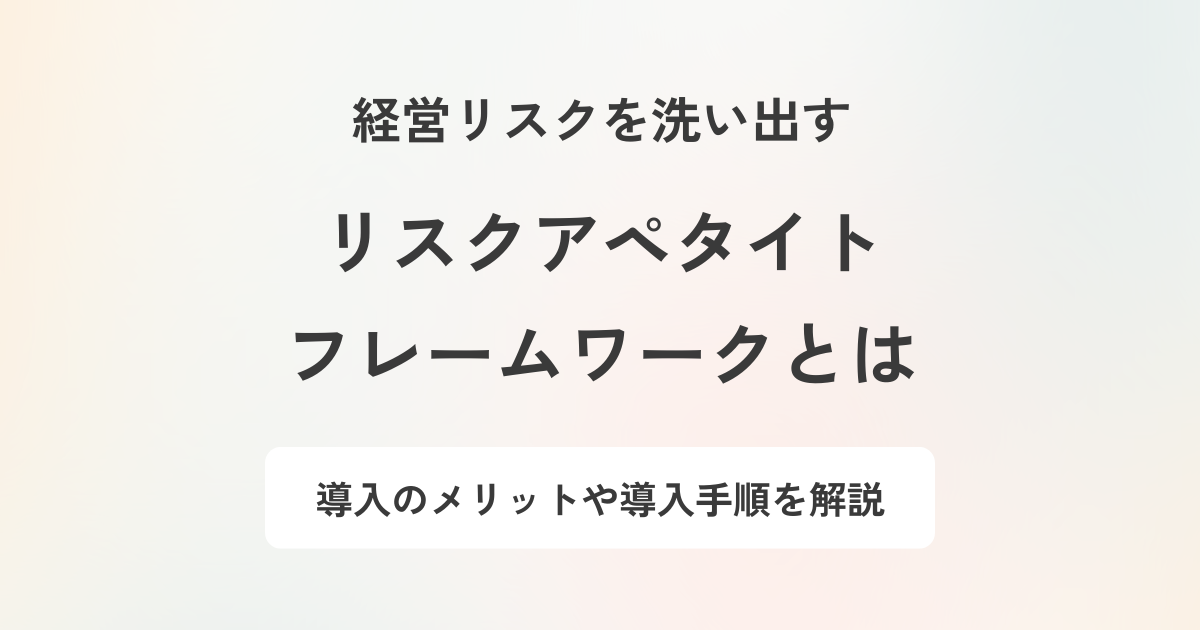介護現場におけるリスクマネジメントとは?目的や方法を解説

坂田 健太(さかた けんた)
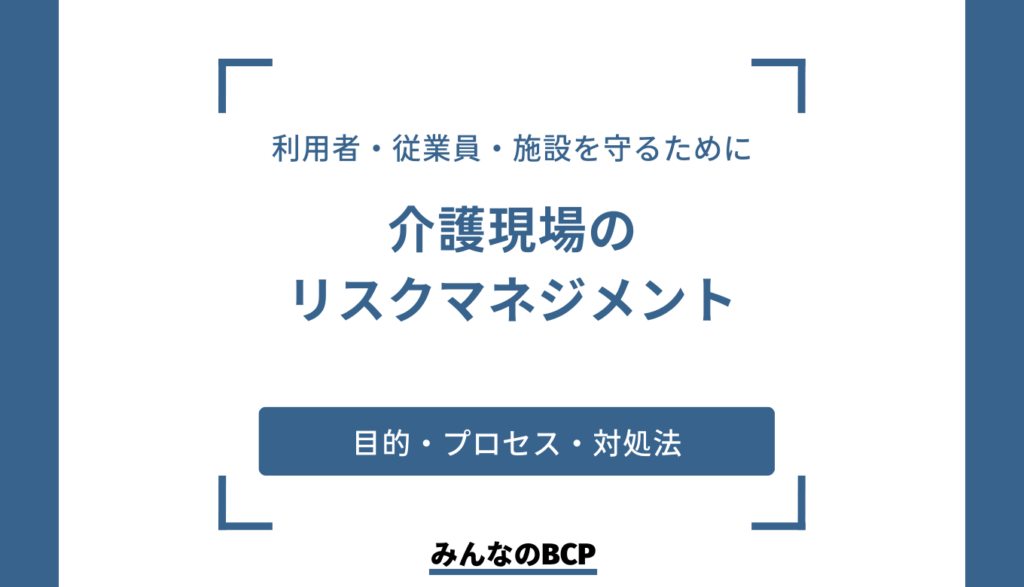
介護現場は高齢の方が多く集まっていることもあり、事故が起こりやすい環境です。すべての事故を未然に防ぐのは難しいですが、リスクマネジメントをしていれば、ある程度の危険性は回避できるはずです。
そこでこの記事では、介護におけるリスクマネジメントの目的と具体的な取り組み方法を解説します。事故が起こったときの対処法も紹介しているので、あわせて参考にしてください。

BCPを策定できていないなら、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用をご検討ください!
早ければ1ヵ月でBCP策定ができるため「仕事が忙しくて時間がない」や「策定方法がわからない」といった危機管理担当者にもおすすめです。下記のページから資料をダウンロードして、ぜひご検討ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
目次
介護におけるリスクマネジメントとは
介護におけるリスクマネジメントとは、現場で起こり得る事故の原因を分析して予防策を講じ、適切な管理を行うことです。リスクマネジメントを行えば重大な過失やトラブルを避けやすくなり、安全な施設運営が可能となります。ただし、事故のすべてを防ぐことは困難なため、万が一のための対応策も考えておく必要があるでしょう。
近年、介護現場のリスクマネジメントが重要視されるようになり、令和3年度の介護報酬改定では、リスクマネジメントの強化が反映されています。これまでもリスクマネジメントの指針の策定や事故発生時の報告、従業員の研修実施などは定められていたものの、改定によって安全対策担当者が義務付けられました。
介護現場の安全対策に対する対策は、安全管理体制加算という制度で評価されます。基準を満たしていない場合は、安全対策への評価が1日あたり5単位減算されることになっています(安全管理対策未実施減算)。
これらの背景から、介護現場では、早急なリスクマネジメント体制の見直しが求められていると言えるでしょう。
介護現場におけるリスクマネジメントの目的
介護におけるリスクマネジメントの主な目的は、以下のとおりです。
- 利用者の安全を守る
- 従業員が働きやすい環境を整える
- 訴訟を未然に防ぐ
それぞれの目的について解説します。
利用者の安全を守る
介護におけるリスクマネジメントは、利用者の安全を守るうえで欠かせない要素です。
介護サービスを利用するのは高齢者の方がほとんどであるため、身体的機能が低下しており、あらゆる事故が起こりやすいのが現状です。高齢者の事故は生命にも関わる重要なトラブルに発展する恐れがあることから、未然に事故を防ぐ必要があります。
従業員が働きやすい環境を整える
介護におけるリスクマネジメントは、従業員にとって働きやすい環境を整える役割もあります。介護事故が発生すると、利用者だけではなく、従業員も巻き込まれる可能性があるからです。また、重大な事故を経験すると、従業員に精神的なダメージが残るケースもあるため、未然に防ぐ必要があります。
なお、介護における事故の原因は、従業員個人によるものとは限りません。たとえば階段に手すりがついていないために、利用者が足を滑らせることなどが考えられます。
介護施設の設備を整えていれば、従業員もより安心して働けるでしょう。従業員によりよい職場を提供するためにも、介護現場のリスクマネジメントを重視してください。
訴訟を未然に防ぐ
介護におけるリスクマネジメントは、訴訟を未然に防ぐ意味もあります。
介護業界では事故による訴訟が頻発しており、施設の経営にも大きな影響を与えています。訴訟の内容によっては企業の倒産もあり得るため、できる限り回避したいと考えるはずです。
訴訟が発生すると、たとえ倒産を免れたとしても施設への信頼が失われ、利用者が減少する可能性があります。そのため、訴訟に発展しないように、事前の事故の対策が必要です。
介護における4つのリスクマネジメント方法
介護における具体的なリスクマネジメント方法は、以下のとおりです。
- 起こり得る事故はなにかを考える
- 想定される事故に対する予防策を考える
- 利用者の状況を把握する
- 従業員同士で情報共有・周知を徹底する
それぞれの方法について解説します。
1.起こり得る事故はなにかを考える
まず、介護現場で起こり得る事故にはどのようなものがあるかを考えましょう。具体的には、以下のような事例が想定できます。
| 考えられる事故の原因 | |
|---|---|
| 転倒 | ・トイレに行こうとした ・物を拾おうとした ・入浴中に足を滑らせた |
| 転落 | ・ベッドから落ちた ・トイレの便座から落ちた |
| 誤飲・誤薬 | ・水と洗剤を間違えた ・ほかの利用者の薬を飲もうとした |
介護現場では転倒や転落といった事故が起こりやすいため、原因を含めて起こりやすい事例を把握しておく必要があります。事故は介助中のみならず、利用者が1人のときにも起こり得るため、できるだけ多くの事例を洗い出してみましょう。
2.想定される事故に対する予防策を考える
次に起こり得る事故の予防策を考えます。先ほど挙げた事例を参考にしながら「どうすれば事故を未然に防げるか」や「事前に取るべき対策はないか」を検討します。
たとえばベッドから落ちる可能性がある利用者に対しては柵の利用を徹底したり、介助付きの移動を必須にしたりするのも有効な方法でしょう。起こり得る事故に対して事前に対策を行っておくと、事故の発生率を大幅に下げられます。
とはいえ、すべての事故を未然に防げるわけではありません。リスクマネジメントを行う際は「防げる事故」と「防ぎにくい事故」に分けたうえで、防げる事故から予防策を講じるのがおすすめです。
3.利用者の状況を把握する
介護におけるリスクマネジメントには、利用者の状況把握が欠かせません。利用者の心身状態などによって、事故の予防策に違いが生まれるからです。
歩行器の使用が必須の利用者がいれば、立ったり座ったりする際の事故防止策も必要となります。ほかにも飲んでいる薬や生活習慣、趣味などを把握していれば、起こり得る事故を想定しやすくなるでしょう。
なお、利用者の状況を把握する際は、過去の起こった事例を参考にするのも一つの方法です。たとえば入浴中に足を滑らせて転倒した利用者がいる施設では、その利用者の特徴などと照らし合わせながらリスクマネジメントするのもいいでしょう。過去の経験を参考にしつつ、事故の予防策を検討してください。
4.従業員同士で情報共有・周知を徹底する
事故の予防策がまとまったら、従業員同士で情報共有や周知徹底を行いましょう。
上層部で予防策について話し合い、今後の対応を取り決めたとしても、現場で働く従業員にその内容を周知させなければ意味がありません。そのため、予防策を立てたら、すべての従業員にその情報が伝わる仕組みを構築する必要があります。従業員が実際に行動できるように、事故防止マニュアルを作成するのもおすすめです。
介護現場で事故が起こったときの対処法
介護におけるリスクマネジメントを行っていても、すべての事故を未然に防ぐことはできません。そのため、万が一事故が発生した場合の対処法についても考えておく必要があります。具体的な対処法は以下のとおりです。
- 応急処置を行う
- 家族へ報告する
- 事故の調査を行う
- 関係機関へ連絡する
それぞれの方法について解説します。
応急処置を行う
実際に事故が起きた場合は、すぐに応急処置を行います。
事故が起きたときの状況を把握したうえで、必要に応じて止血したり人工呼吸を行ったりします。怪我の程度が重いようであれば、医師や看護師にも応援を依頼して状況に合わせた判断を行ってもらいましょう。利用者の送迎中に事故が起きた場合は、すぐさま管理者へ連絡して指示を仰ぎます。
家族へ報告する
事故が起きたときは、利用者の家族へ報告して心からの謝罪を行います。事故発生からできる限り早い段階で家族に連絡を取り、事故の状況や利用者の状態などを報告しましょう。
なお、家族に事故の説明を行う際、施設にとって知られたくない部分を隠したり、虚偽の報告をしたりすると、法律で罰せられる可能性があります。そのため、家族へ報告する際は事実だけを伝えて、家族が状況把握できるように努めることが何よりも重要です。
事故の調査を行う
事故が起きた場合は、その原因を追求するためにも詳しい状況を調査しましょう。事故発生直前まで遡り「利用者に何が起きたのか」「どうして事故は発生したのか」などを調査します。利用者だけではなく、事故の関係者すべての行動を見直して詳しく調査するのがポイントです。
なお、調査を行う目的は、あくまで事故の再発防止です。個人に事故の責任を押し付けるといった意味はないため、その点を配慮しながら調査しましょう。
関係機関へ連絡する
事故の状況によっては、保健所や警察などへの報告も必要です。たとえば食中毒が起きた場合は保健所へ、事故によって利用者が死亡した場合は警察へ届けなければいけません。
また、事故の調査内容も警察へ報告しなくてはならない場合があるため、関係機関からの指示を仰ぐようにしましょう。
介護現場における災害時のリスクマネジメント
介護現場においては事故のリスクマネジメントに加えて、災害時に備えたリスクマネジメントも必要です。介護現場は高齢者の方が多く集まることから、災害時の安全を確保することは緊急性の高い課題と言えます。たとえば、災害発生時に利用者や従業員がスムーズに避難できるような安全対策や通路の確保は必須です。
さらに、災害に少しでも早くサービスを提供できるように、事業の早期復旧も課題と言えます。災害時の被害を最小限に抑えつつ、事業継続と早期復旧ができるような体制を整えておくことが重要です。
災害時の安否確認にはトヨクモの『安否確認サービス2』がおすすめ
介護におけるリスクマネジメントは、利用者や従業員を守るうえで欠かせません。利用者が安心してサービスを利用でき、従業員が安心して働けるように、あらかじめできる対策を講じておきましょう。
とはいえ、地震をはじめとする自然災害が起きたときは、介護現場も混乱状況にあります。従業員の安否確認がなかなかできなかったり、そのあとの現場の運営に支障が出たりする場合もあるでしょう。そのような場合に備えて、トヨクモが提供する『安否確認サービス2』の活用がおすすめです。
安否確認サービス2とは気象庁の災害情報と連動して、従業員への安否確認メールを自動で一斉送信できるシステムです。従業員は添付されたURLにアクセスすると安否確認を行えるため、スムーズに現在の状況を報告できます。さらに、従業員から得られた回答結果は自動で分析され、管理者が迅速に被害状況を把握できるため、災害発生時の連携をスムーズに行えるのも魅力です。
安否確認サービス2は、直感的に操作できるのもポイントです。誰でもスムーズに操作できるため、どの年代の従業員でも利用しやすいでしょう。災害時の混乱状態であっても、簡単に安否確認ができます。
介護におけるリスクマネジメントを考えよう!
介護におけるリスクマネジメントは、重大な過失やトラブルを避けるうえで欠かせない重要な要素です。あらかじめリスクを想定して予防策を講じていると、利用者の安全を守りやすくなり、従業員にとっても働きやすい環境となります。とはいえ、すべての事故を未然に防ぐのも難しいため、事故が起きたときの対処法も周知しておきましょう。
トヨクモの『安否確認サービス2』を導入すると、迅速に従業員全員の安否確認を把握でき、出社できる従業員数などもすぐに把握できます。誰でも直感的に使いやすい作りになっていることから、すべての従業員が簡単に操作できるでしょう。