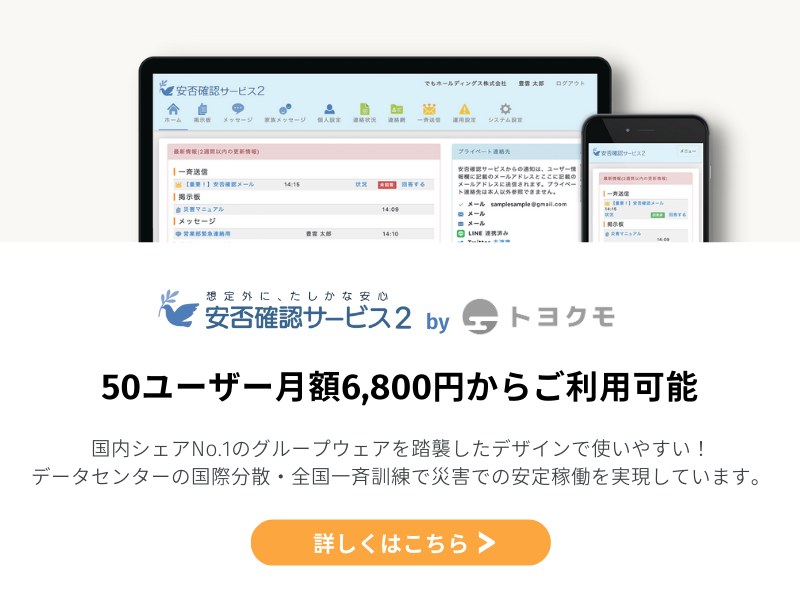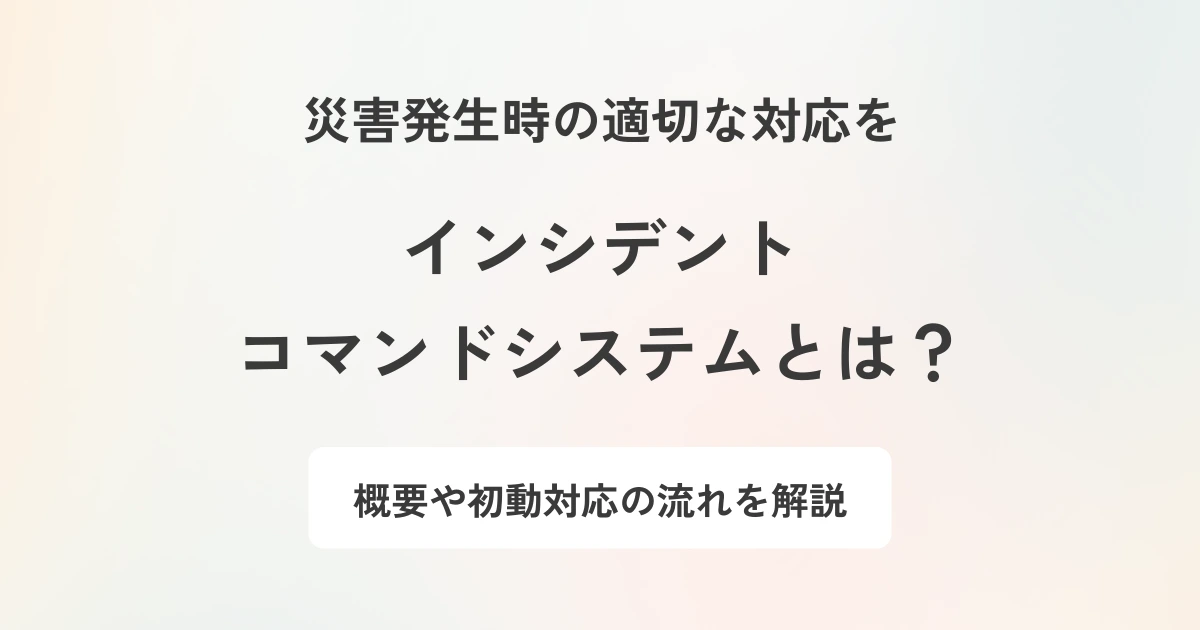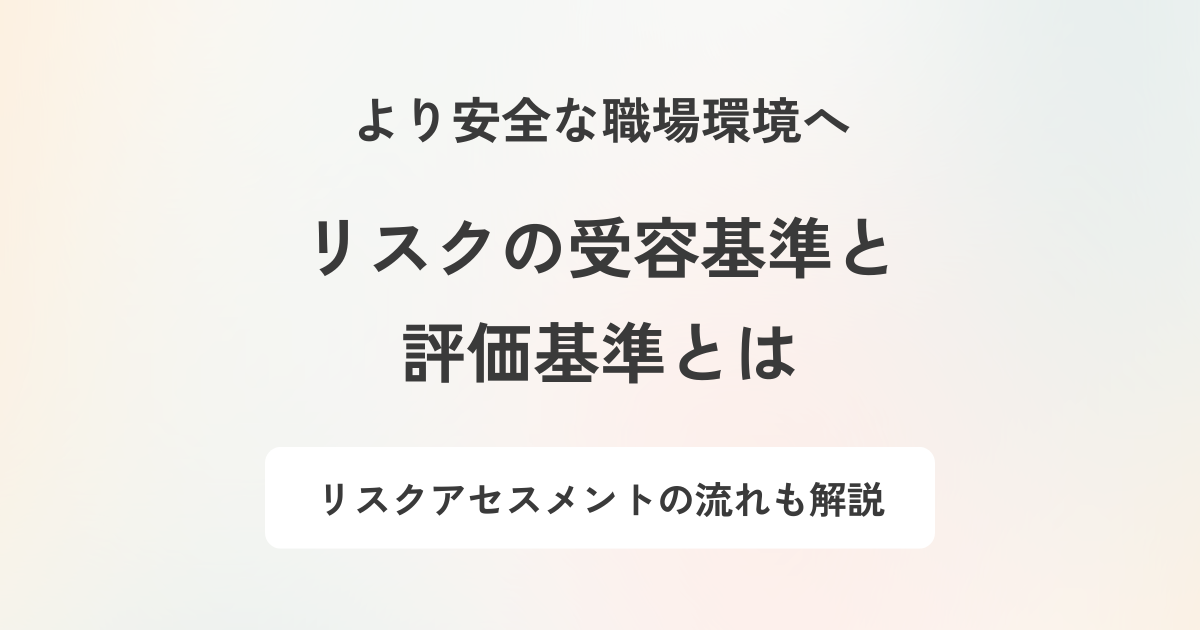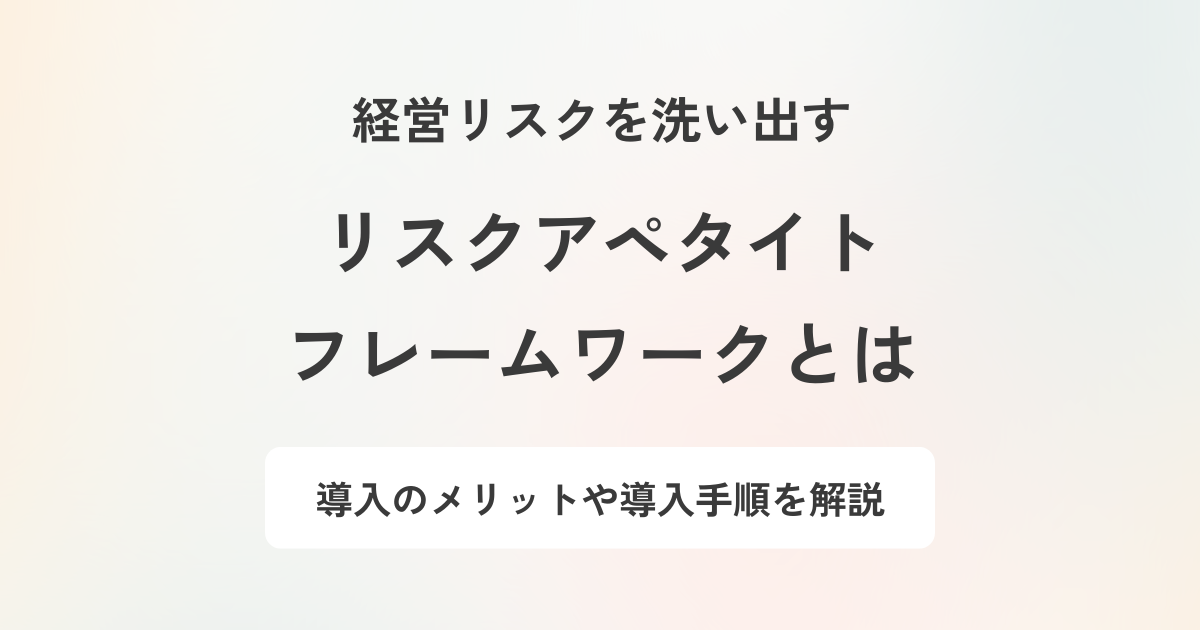自助・共助・公助とは?防災対策で知っておきたい企業の自助や共助の例も紹介

遠藤 香大(えんどう こうだい)
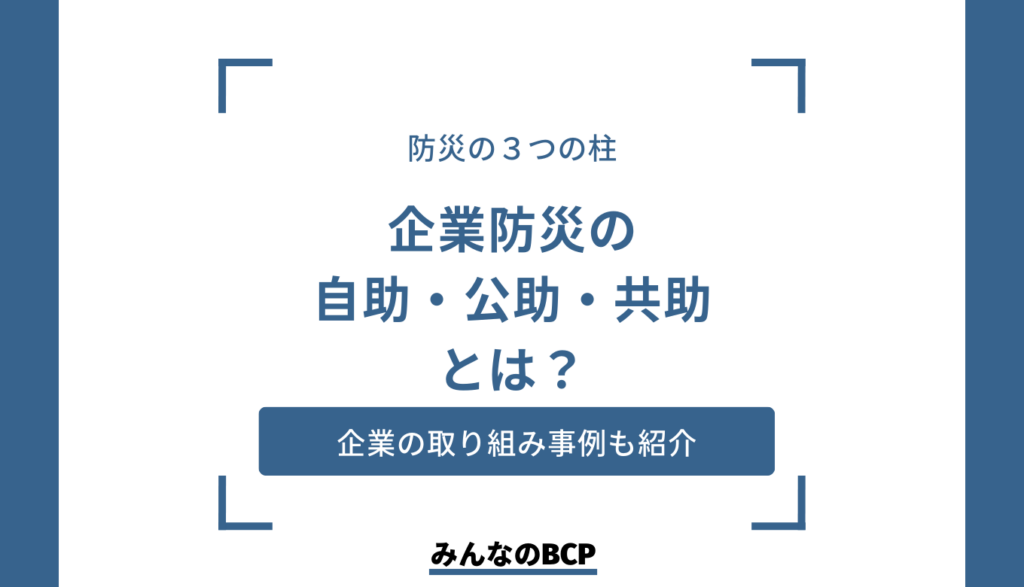
日本は世界でも有数の地震大国であり、大災害と呼ばれる事象がたびたび起こっています。自然災害に直面した際、被害を最小限に留めるためには防災の知識が不可欠です。
この記事では、自然災害発生時や自然災害が起こる前に取り組むべき自助と共助、公助について詳しく解説します。

目次
自助・共助・公助とは
減災を含めた防災について考える際、自助と共助、そして公助が重要です。
それぞれの意味や役割については漠然と捉えている方が多いかもしれません。この機会に、正しく理解しておきましょう。
自助とは
自助とは、自分自身や家族の命、そして財産を守るため、自ら防災に取り組むことをいいます。個人であれば自分と家族の安全がメインであり、企業であれば従業員とその家族の安全がメインになるでしょう。
命を守る行動はさまざまありますが、危険から身を守ったり安全な場所へ避難したりするなど、緊急を要する行動が最も重要と考えられます。緊急を要する危険が去ったあとはこれまで通り、人としての生活を営まなければなりません。
そのためには、平常時から食料品の備蓄や、ハザードマップの確認などの対策が不可欠でしょう。
関連記事:ハザードマップの見方とは|種類や企業における活用方法も紹介
そのほか、事前に安否確認システムを導入して緊急時の行動を決めておいたり、定期的な避難訓練を行ったり、平常時でもできることは多いのです。
関連記事:安否確認システムの必要性とは?導入メリット・失敗しないための選定のポイントを紹介!
共助とは
共助とは、生活を営む地域や職場などにおいて、みんなで協力して防災に取り組むことをいいます。
共助の概念が生まれたきっかけは、1995年に兵庫県で発生した阪神大震災といわれています。阪神大震災を含め、そのあとに発生した自然災害で共助が果たした役割は大きく、その重要性が再認識されています。
また、平常時における防災についての啓蒙や啓発活動、防災訓練なども共助に含まれています。
公助とは
自助や共助と比べ、公助はあまり聞き慣れない言葉かもしれません。
公助とは、都道府県や市町村の自治体や消防、警察、自衛隊などが行う公的な支援のことをいいます。
自然災害時の緊急事態や防災に対して、被災者が必要とする食料や水などの生活物資を備蓄したり、資材や機材を整備したりして万が一に備えます。また、地域によっては民間の事業者や他の市区町村との間で、相互に応援協定を結んでいることもあります。
そして、いざ自然災害が発生した際には、公的な機関として人命救助や復旧に携わり、その後の復興を担います。
公助の限界とは
地方自治体が主導して行う公助は、さまざまな組織が連携して防災できることが特徴です。その規模は、個人や企業では賄えない範囲に及ぶので、公的な機関の強みが活かせるといえるでしょう。
しかし、1995年の阪神大震災や2011年の東日本大震災など、国家を揺るがすほどの大規模な災害が発生した場合は、その機能にも限界が生じます。
2014年版防災白書に記載
2011年に東北の沖合を震源として発生した東日本大震災は、過去に例を見ないほどの津波を引き起こし、東北沿岸部の街を次々と飲み込み、東北地方の広範囲に被害をもたらしました。
2014年版の防災白書には、公助が多くの被災者へ迅速に届けられない事態が発生したことが記載されています。その要因のひとつとして、公的な施設そのものが被災したため、自然災害発生時に行われるはずだった重要な支援が麻痺した点が挙げられます。
公助ばかりに頼るのではなく、地域で事業を行う事業者と、地域で生活を送る住民との連携や共生の促進が、地域コミュニティ全体の防災力向上につながる可能性が指摘されています。
自然災害に備え、自分や家族ができること、近所で力を合わせてできることなどを考え、いざ自然災害が起こった際には相互に助け合うことが重要です。
自助・共助による「ソフトパワー」の重要性
公的な施設が被災して公助が滞った場合、その地域に住んでいたり避難してきた人々が、自発的に救助活動や避難の誘導、そして避難所の運営を行わなくてはなりません。地域のコミュニティにおける自助や共助による『ソフトパワー』を、効果的に活用することが必要不可欠なのです。
また、自然災害発生後の復興段階においても、地域住民やコミュニティが主体となって復興に関わることが重要です。
自助・共助における企業の在り方とは
企業であっても、第一に自助に専念します。個人と同じく、会社の社員やその家族の安全確保が最優先です。例えば、必要となる物資の備蓄や建物の耐震対策は自助に相当します。
一方で、企業による事業活動は人々の暮らしに深く関わるため、安全を確保した上での災害時の事業継続は、共助に寄与するケースが多いといえるでしょう。
現代社会では近所間のつながりが薄くなりつつあるため、地域での共助が難しい場合もあるでしょう。そのため、今後は企業による地域社会への能動的な共助が求められているのです。
関連記事:災害対策は企業の義務? ガイドラインやマニュアル例を紹介
企業が求められる自助への取り組み
ここからは、企業にスポットを当てた防災について考えます。
企業の事業活動がその地域に果たす役割は大きいでしょう。それは防災に関する役割も同様です。
水・食糧・常備品の備蓄
災害時は人々の集団心理として、物資の買い占めが起こるおそれがあります。
災害が起きてから必要な物資を調達することは、非常に難しいといえるでしょう。人々の生活に欠かせない水や食料などの常備品は、平常時に備蓄しておかなくてはなりません。
常備品には非常用の電源や電池など、生活に欠かせないエネルギーも含みます。常備品の備蓄があれば、自然災害が発生した際には地域共助にも役立つでしょう。
大災害が発生した場合、長いと数ヶ月間ライフラインが途絶えてしまう恐れがあります。
ライフラインが復旧するまで、地域住民は配給や炊き出しなどの支援が受けられる可能性もありますが、被災者が多い場合は衣食住の確保が難しいこともありえます。
ライフラインが復旧するまでの間、多くの被災者の生活を賄えるだけの備蓄を持つことは、二次災害や三次災害を防ぐために不可欠です。
非常連絡、安否確認方法の策定
自然災害が起こった際には、従業員の安否確認をして、対応できる人手を把握しなければなりません。
しかし、災害時には電話やメールなどの一般的な連絡手段が使えないことも多いでしょう。企業は多数の従業員を雇用しており、多ければその数は数千人にのぼります。そのため、非常時の連絡方法や安否確認方法を事前に策定しておくことは不可欠です。安否確認が完了してはじめて、緊急時における初動対応が定まります。
関連記事:企業が安否確認訓練を実施する目的は?具体的な手順とシナリオを紹介
ハザードマップ・避難経路の確認
市区町村が発行しているハザードマップは、インターネットでも閲覧が可能なので、いつでも入手できます。平常時からハザードマップに目を通しておき、近隣地域における災害リスクを把握しましょう。従業員には、被災時における避難経路や避難場所などの情報を、平常時から共有します。
自然災害が発生した場合、まずは自分自身で身の安全を確保しなければなりません。そのための情報提供や設備投資、システムの導入などは企業による責任といえるでしょう。
企業が求められる共助への取り組み
前述した通り、企業はその地域における事業活動に、責任を持つ立場にあります。電気やガスなどのインフラを提供する企業は、事業の継続が人々の社会活動に直結します。
一方で、事業自体が人々の生活に直結しない場合でも、さまざまな面で地域の人々を間接的に助けられるでしょう。
ここでは、企業に求められる共助への取り組みについて解説します。
地域貢献を意識した防災備蓄の準備
企業は個人と比べ、大きな規模で自然災害に備えられます。例えば、生活必需品や食料、水などを備蓄することもそのひとつです。災害時には保管していた物資を地域住民に提供することで、支援ができます。
また、被災時に電源を提供し、地域住民のスマートフォンが充電できるだけでも、被災者にとっては大きな支援になります。
地域住民のために備蓄品を提供することも大切ですが、企業の従業員に対しても物資を提供しなければなりません。とくに食料や水は、人間が生きる上で欠かせないため、多めに備蓄しておくことをおすすめします。
自然災害発生時の地域連携
いざ自然災害が起こり、緊急を要する危険が迫っているケースでは人々はパニック状態に陥る危険性があります。
あらかじめ自然災害時の行動計画を策定しておけば、初動の時点で率先して避難指示や避難場所への誘導が可能です。災害が起こったその直後から地域への支援を開始できるよう、事前に行動計画を策定し、従業員が把握できるよう努めましょう。
また、敷地の広い事業所を運営する企業の場合は、自治体から企業側へ避難所の開設を求められるケースもあります。平常時から自治体と連携し、官民一体の防災対策を行いましょう。
BCPと地域共助
BCPとは、企業や組織が自然災害やテロなどの緊急事態を想定して策定する事業継続計画のことをいいます。
BCPの目的は、緊急事態における被害を最小限に抑え、業務を継続し早期復旧を図ることです。BCPを策定することは、取引先の企業を含め、地域におけるコミュニティへの支援につながるメリットがあります。
自然災害発生時には、事前に策定したBCPをもとに従業員の安全確保が最優先となります。非常時の連絡手段や安否確認システムなどを活用して、従業員の安全が確保でき次第、地域との連携に向けて対応します。
個人間では共助の規模に限界がありますが、企業だからこそできる共助は、地域住民にとって非常に有益といえるでしょう。
関連記事:BCP(事業継続計画)とは?専門家がわかりやすく解説
企業の共助参加の取り組み例
自然災害発生時には、どのような企業共助が行われているのでしょうか。
ここでは、企業による取り組みの例を紹介します。
カゴメ
食品や調味料などを製造販売するカゴメは、被災地における自立支援や『やさい財団』と呼ばれる活動などを行っています。
また『みちのく未来基金』を創設し、震災遺児の進学支援にも取り組んでいます。
震災後は家族を失った悲しみやPTSDに対する支援を必要とする人も多いため、カゴメは心のケアについても重視しています。また奨学生同士の親睦を図るイベントを開催したり、進学後であっても面談の機会を設けたり、フォローを続けているのです。
ダイキン工業
エアコンの製造販売で知られるダイキン工業は、同社の草加事業所を対象として草加市及び周辺の5つの町会と『地域防災協定』を結んでいます。
自然災害発生時においては、同社は避難場所や重機の提供、ヘリコプターが離着陸可能な場所の提供などが行われる予定です。
また、平常時においては、防災訓練の協力や防災備蓄倉庫を設置する場所の提供など、さまざまな防災に取り組んでいます。
非常時は企業の力で従業員や地域住民を守ろう
自然災害は避けられないからこそ、被害を最小限に抑えるための準備が重要です。
企業は個人と比べ、大規模な共助が可能であり、地域住民を守れます。そのためにも、まずは自社の従業員を守らなければなりません。
非常時の連絡方法や安否確認システムの導入などは喫緊の課題といえるでしょう。トヨクモが提供する『安否確認サービス2』は、非常時のスムーズな安否確認におすすめです。