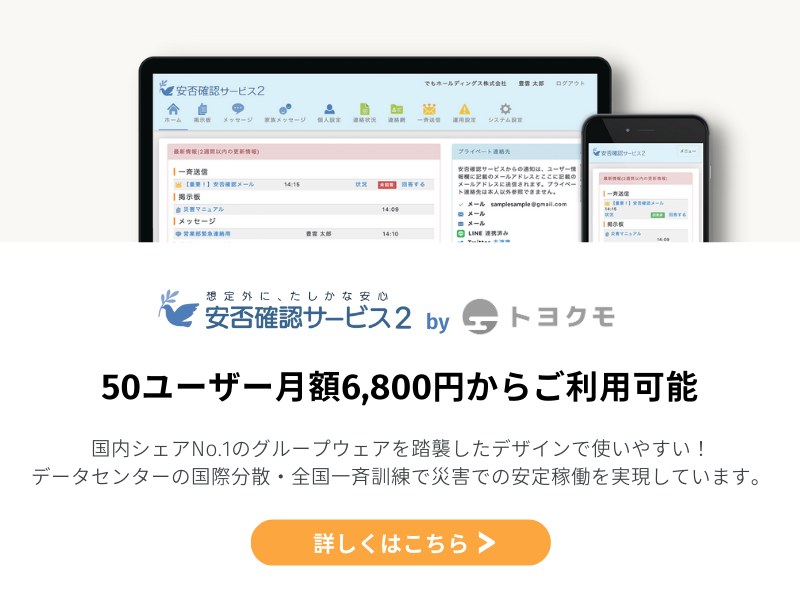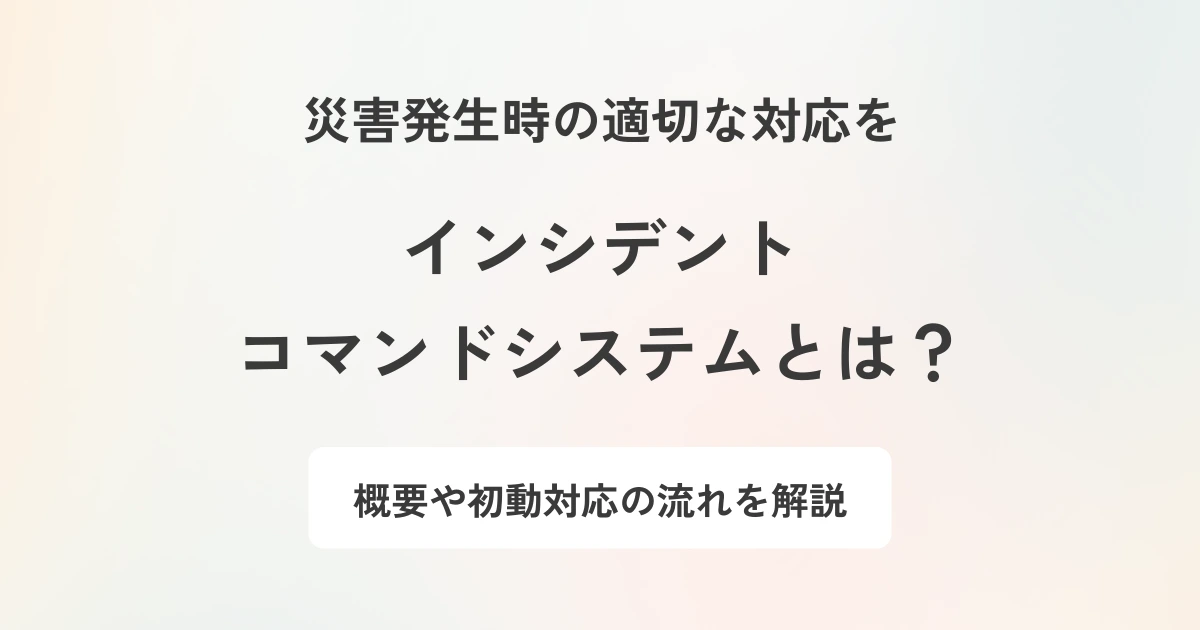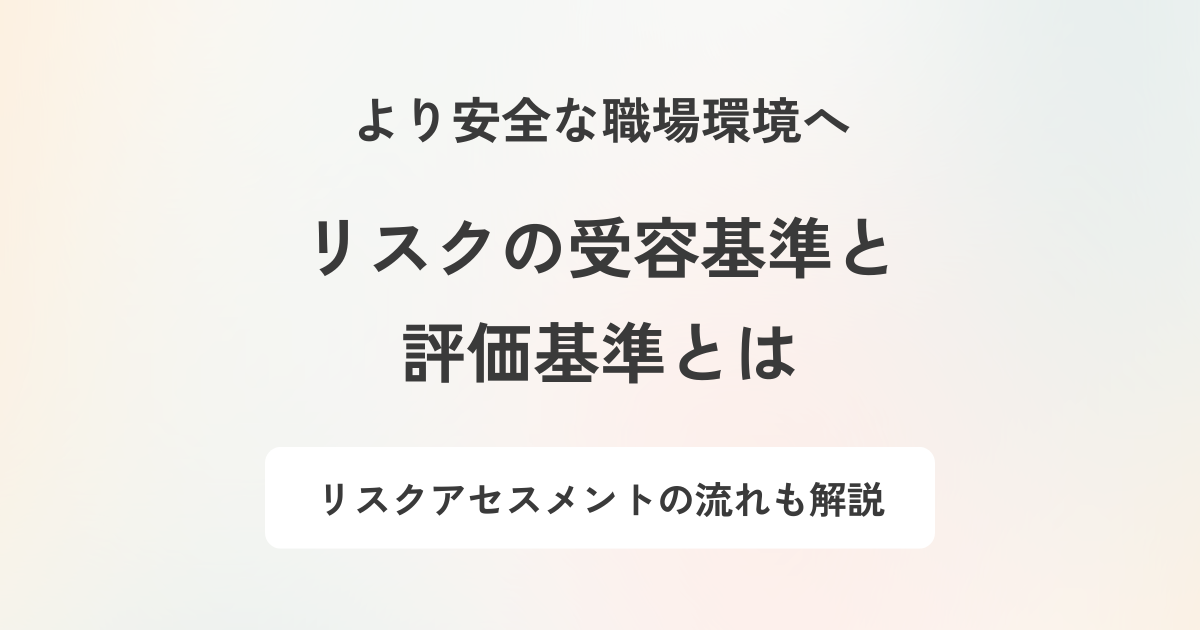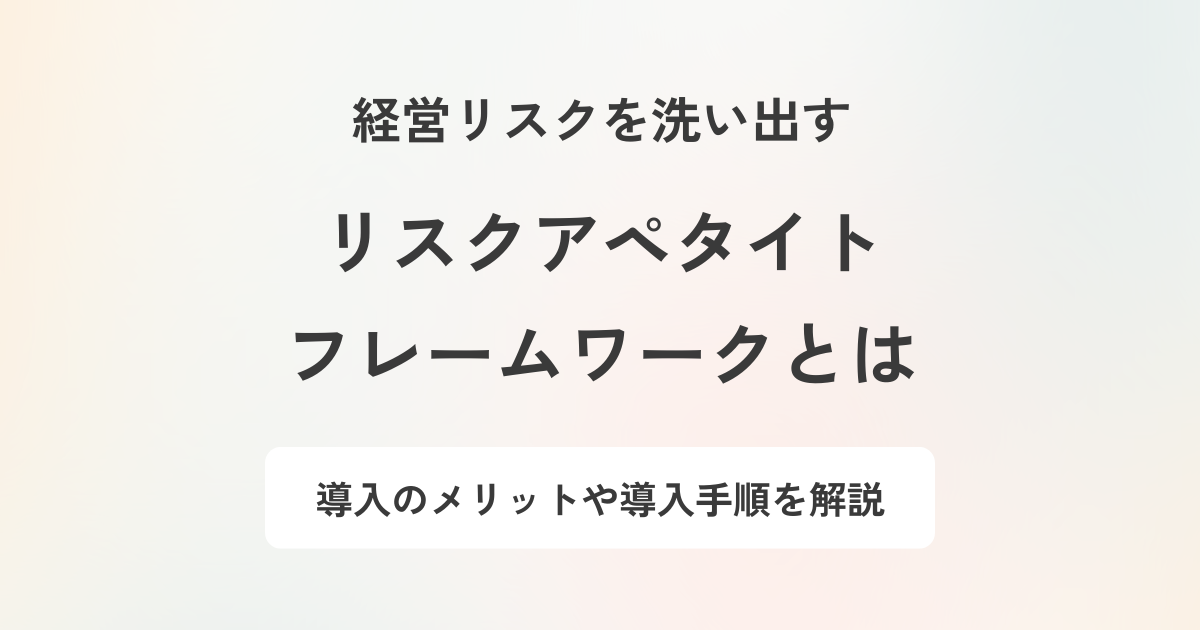安全衛生とは何か?関連法律や取り決めをご紹介

木村 玲欧(きむら れお)
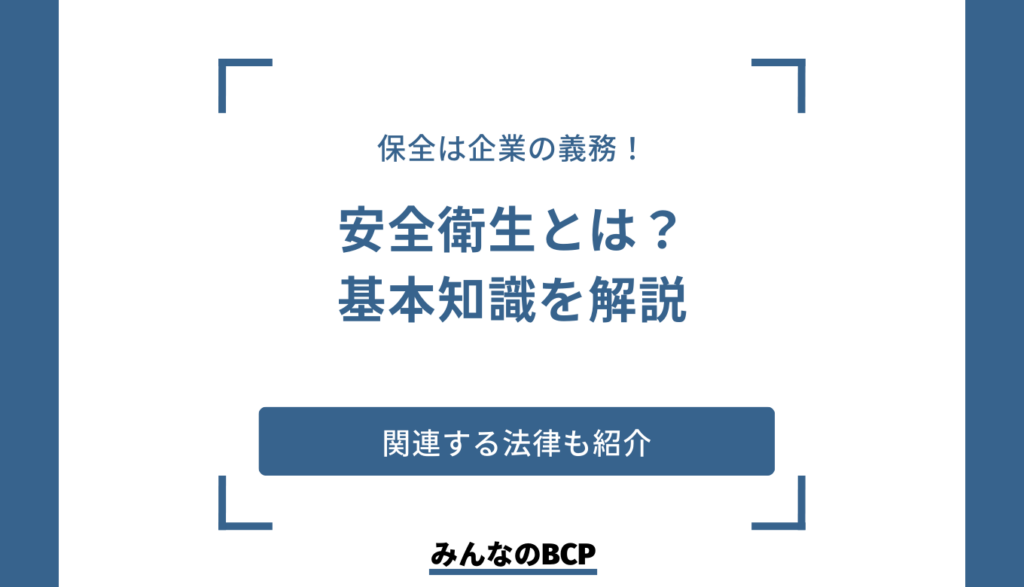
職場において従業員の安全(労働安全)と健康(労働衛生)を守ることは重要です。そのため労働安全衛生法によって、会社にはさまざまな義務が定められています。今回は会社に求められる安全衛生について、関連する法令や取り決めなども含めて紹介します。

兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。
目次
安全衛生とは
安全衛生は従業員の安全と健康を守るためにも、会社を持続的に発展させるためにも必要です。
ここからは、安全衛生の概念について説明するとともに、安全衛生の重要性を解説します。
安全衛生の基礎知識
安全衛生において最も大切なことは、従業員の安全と健康を確保することです。従業員は安全と健康が保証されてこそ、最大限の力を発揮できます。
従業員の安全衛生を考えるにあたり、快適な職場環境作りは欠かせません。職場環境を改善することで、労働災害の発生を防止し、従業員のメンタルヘルスを安定させられるでしょう。
従業員の安全衛生を守ることは、事業者の義務でもあります。
安全衛生が重要な理由
そもそも会社にとって、従業員はかけがえのない資産です。
従業員が安心して働ける環境を整備することは会社の義務です。労働災害を防止して安全を守り、従業員の心を健康に保つことで、会社の利益にもつながります。
安全衛生管理の不足によるリスク
安全衛生に関する設備投資や教育訓練をしなければ、会社にとって大きなリスクとなります。業務の生産性が低下したり、事故が発生したりする可能性があるからです。
安全衛生環境の悪化は過労死や事故死につながり、会社のイメージダウンを招きます。また、メンタルヘルスの不調は、従業員の休職や退職にも発展するのです。
安全衛生を支える法律
国は会社の安全衛生を促進するため、法律を定めて指導しています。違反した場合は行政指導の対象になります。会社はこれらの法律を遵守し、従業員の安全衛生を守らなければいけません。ここからは、安全衛生に関連する法律を2つ紹介します。
労働基準法|労働者の権利を保証
1947年に成立した労働基準法は、労働条件における最低基準を定めた法律です。正社員だけでなく、あらゆる雇用形態の従業員が人間らしく生活を営むために、労働者の持つ「生存権」を保障します。
労働基準法の内容は労働契約、賃金、就業規則などさまざまな項目に及びます。
たとえ雇用主と従業員の双方が合意をしても、労働基準法で定められた内容を下回る労働条件は無効です。
(参考:労働基準法)
労働安全衛生法|労働者の安全と健康を確保
労働安全衛生法は「安衛法」とも呼ばれ、労働者の安全と健康を確保したり、快適な職場環境を作ったりすることを目的とした法律です。従業員を労働災害から守ります。
従来は、労働災害の起こりやすい業種に限定して制定されていた法律でした。しかし高度経済成長時代に労働災害が急増し、従業員の安全衛生を確保する緊急性が高まったため、現在は多くの職種に対応しています。
労働安全衛生法の制定以降、労働災害による死傷者数は減少しています。
(参考:労働安全衛生法)
関連記事:弁護士が教える労働安全衛生法(安衛法)!重要ポイントと対応策、違反した場合の罰則を解説
労働安全衛生法での取り決め
労働安全衛生法では、従業員の心身を安全かつ健康に保つため、さまざまな取り決めがなされているのです。取り決めについて詳しく解説しましょう。
安全衛生管理者・推進者・責任者の設置
労働安全衛生法はさまざまな人員の選任を義務付けています。
たとえば、総括安全衛生管理者は衛生管理者と安全管理者の指揮をとり、職場の安全衛生の総括および管理をします。すべての業種において選任が必要です。
安全管理者は安全に関する技術的な管理をします。林業、鉱業、建設業などの危険を伴う業種で選任が求められます。
衛生管理者は従業員の作業環境や健康などを管理する立場です。すべての業種において選任が必要です。
安全衛生推進者は従業員の安全や衛生を守るため、さまざまな措置や教育を施します。林業、鉱業、建設業などの業種では選任が必要です。
衛生推進者も安全衛生推進者と同様の業務にあたります。安全衛生推進者の選任が不要な業種では、こちらの選任が必要です。
産業医は労働者の健康管理に関する指導や助言をします。すべての業種において選任が求められます。
統括安全衛生責任者は、元方事業者と請負事業者が同一の場合に、作業場で生じる労働災害の防止を目的に選任される責任者です。元方事業者が選任します。建設業や造船業では選任が必要です。
店社安全衛生管理者は統括安全衛生責任者の選任が義務づけられていない作業現場にて、統括安全衛生管理担当者を指導または援助する立場です。
元方安全衛生管理者は統括安全衛生責任者の業務のうち、技術的な事項を管理します。建設業や造船業での選任が必要です。
安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者のいる事業場において、懸念される労働災害を防止するための責任者です。請負責任者が選任します。
関連記事:企業必見!弁護士が10種の安全衛生管理者を徹底解説!役割、業務内容、選任方法まで
産業医の選任と職場巡視の実施
産業医とは、従業員の健康管理について指導や助言をする医師です。健康診断を実施したり、診断結果から指導や勧告をしたりします。
常時50人以上の従業員を使用する事業場では、産業医の選任が必要です。
産業医による月1回の職場巡視が、労働安全衛生規則により義務づけられています。
各委員会の開催
衛生委員会では、従業員の健康増進や健康障害防止について、労使一体となって調査や審議をします。
安全委員会は、従業員の危険防止や安全について、労使一体となって調査や審議をする委員会です。
一部の業種では、衛生委員会と安全委員会、あるいは二つの委員会を統合した『安全衛生委員会』を設置する必要があります。委員会は毎月1回以上開催しなければなりません。
快適な作業環境の保全
従業員が快適に業務できるように、会社は職場環境を整える必要があります。そのために必要な措置や改善は、会社の努力義務です。
たとえば、作業内容に応じて明るさを設定したり、騒音や振動を防止したりするなどが挙げられます。また、休憩設備の設置や室内の換気なども該当します。
カウンセリングルームの設置やメンタルヘルス研修の実施など、メンタルヘルスの不調に対する対策も求められるでしょう。
従業員への安全衛生教育
安全衛生教育は、労働災害を防止し、従業員が安全かつ衛生的に業務遂行するための教育です。
安全衛生教育は、従業員を新たに雇い入れた際や、作業内容が変更された際に実施します。また、新しく任命された監督者、職長、指導者に対しても実施しなければなりません。
医師による健康診断
会社が従業員を雇う際、医師による健康診断の実施が義務づけられています。
さらに、採用後1年以内に1回、指定された職場では半年に1回、医師による健康診断の実施が定められています。
ストレスチェックの実施
ストレスチェックは、従業員自身がストレスに気づくことを目的としたチェックです。メンタルヘルスの不調に関して、リスクを低減できます。
常時50人以上の従業員がいる事業所では、毎年1回の実施が義務づけられています。労働者数50人未満の事業所では、ストレスチェックは努力義務です。
中高年層への配慮
50歳以上の従業員を中心に、転倒による怪我や骨折などの労働災害が増加しています。労働災害による休業が4日以上となった死傷者のうち、60歳以上だった割合は26%(2018年)と高い割合になっています。
今後は中高年層の雇用がさらに進むと予測されます。高齢従業員の業務内容にも配慮し、リスクを軽減しなければなりません。
機械設備の自主的な点検
機械設備は自主的に点検しましょう。安全装置や排気装置の対策をしたり、点検規定を作成したりするのが効果的です。
設備を設置または変更した際、リスクアセスメントを実施することも重要です。危険性や有害性を調査し、保護方策を講じましょう。
残留リスクは、誰でも分かるように警告表示を取りつけたり、事前周知をしたりするなどの対策が必要です。
危険や害を伴う作業の届出
以下の危険や害を伴う作業は、所轄の労働局に届け出る必要があります。
- 危険な機械を取り扱う
- 危険な場所での作業をする
- 有害物質に汚染されている場所で作業をする
有資格者の確保
危険な作業は有資格者でなければできません。届出には、作業内容や有資格者の氏名を記載します。
資格を取得しやすい環境作りや支援制度の設置など、さまざまな配慮が必要でしょう。
労働安全衛生法に違反するとどうなる?
労働安全衛生法に違反した場合、その責任者や会社に対して懲役または罰金が科されます。
労働安全衛生法で定められている罰則は両罰規定であり、違反をした行為者だけでなく、事業主である法人も罰せられるのです。
たとえば、次のようなケースは罰則の対象です。
- 従業員を雇う際、必要な安全衛生教育をしない:安全衛生教育実施違反(50万円以下の罰金)
- クレーンやその他作業機械などの運転を無資格者にさせる:無資格運転(6ヵ月以上の懲役または50万円以下の罰金)
安全衛生の保全は企業の義務!
従業員は会社の貴重な資源です。会社は、従業員が快適に働ける職場を作る必要があります。
労働安全衛生法をはじめとする各種法令の遵守はもちろん、従業員の安全衛生を保全することも大切です。安全衛生への取り組みを怠ると、従業員だけでなく、会社にも悪影響が出ます。
会社の成長のためにも、従業員が快適に働ける職場環境作りを心がけましょう。
兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。