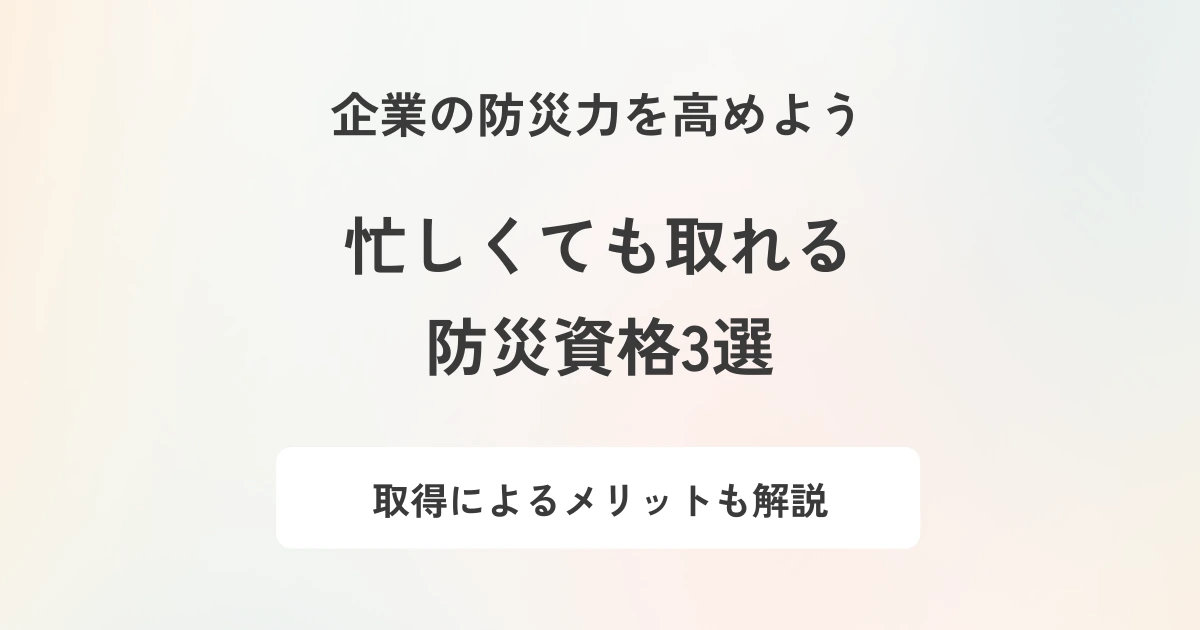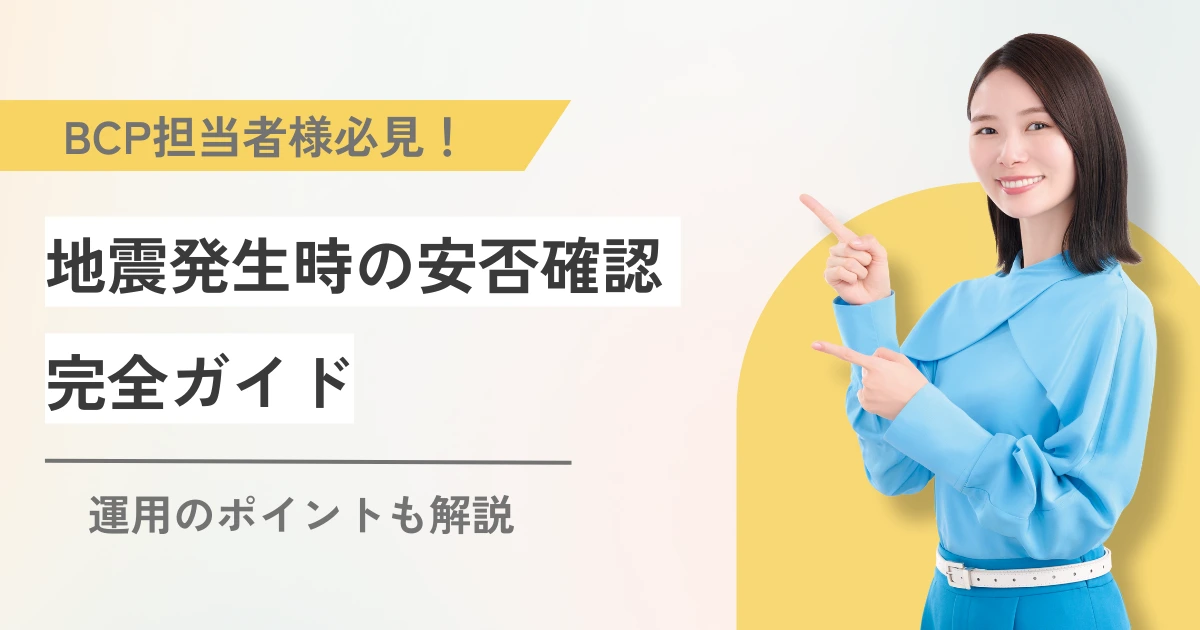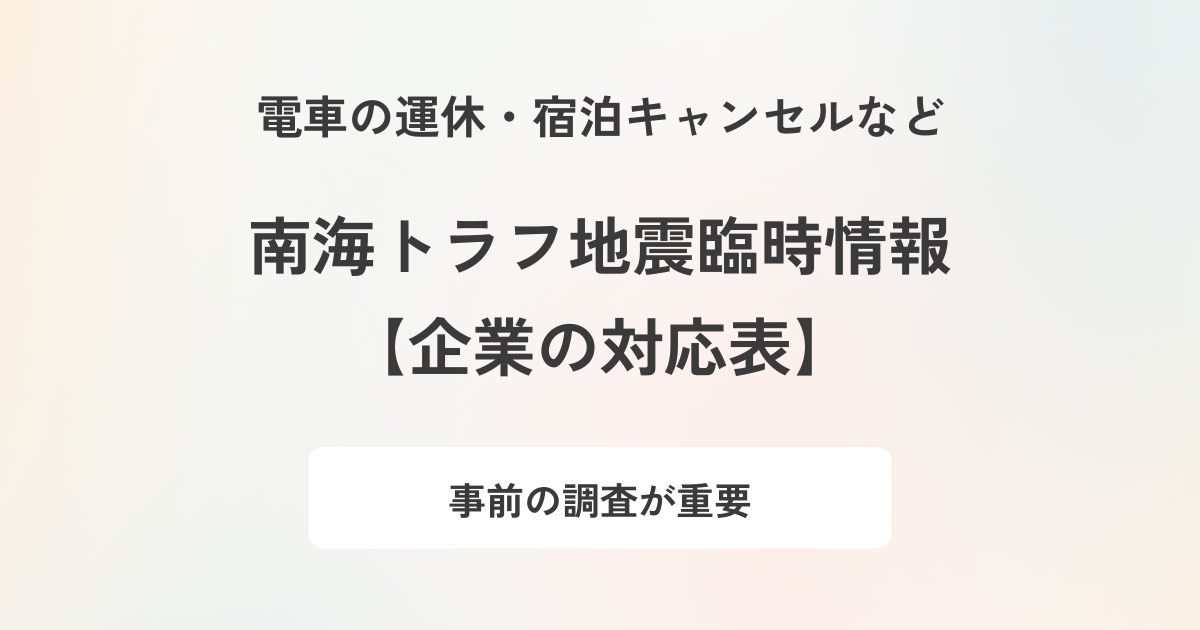防災DXとは?企業が推進するメリットや事例・役立つサービス3選を紹介

トヨクモ防災タイムズ編集部
近年、自然災害の頻発化や激甚化に伴い、企業の防災DX推進の重要性が高まっています。とくに2025年1月には南海トラフ地震の発生確率が引き上げられたこともあり、企業にとって防災DXの推進は急務といえるでしょう。
この記事では、防災DXの概要や推進するメリット、推進事例について解説します。防災DXに役立つサービスも紹介するため、自社の防災力を向上させて事業継続性を高める際の参考にしてください。
目次
防災DXとは
DXは「Digital Transformation」の略称で、デジタル技術を用いて業務プロセスやビジネスモデルを根本から変革するという意味です。防災の分野におけるDX、つまり防災DXは、デジタル技術を活用して、防災を強化する取り組みを指します。
従来、災害発生時の情報収集・共有は、電話や紙など人の手による手法が中心でした。一方、防災DXでは、AIやIoTなどを活用して、災害情報の収集・伝達・分析を効率化します。たとえば、避難所の混雑状況をシステムで把握する、被災地の映像をドローンで確認することも可能です。
防災DXが注目されている理由
日本は地震や台風、豪雨などの自然災害が頻繁に発生する災害大国です。2024年1月には能登半島地震が発生し、甚大な被害を被ったことは記憶に新しいでしょう。
2025年1月、政府の地震調査委員会は、南海トラフ巨大地震が今後30年以内に発生する確率を「70〜80%」から「80%程度」に引き上げました。そう遠くない未来に、甚大な被害をもたらす災害が高い確率で発生すると予測されており、防災への備えの重要性がこれまで以上に高まっています。
また、防災業務を担う自治体の人手不足も、防災DXが注目される理由の1つです。少子高齢化により自治体職員が減少する中、限られた人員で防災対策を進めるために、デジタル技術の導入による業務効率化が求められています。
(参考:南海トラフ地震、30年以内発生確率「80%程度」に引き上げ|日本経済新聞)
企業が防災DXを推進するメリット
企業が防災DXを推進する主なメリットは、以下の2つです。
- 従業員の人命を守れる
- 事業を早期に復旧できる
災害発生時における迅速な情報共有や避難誘導は、従業員の命を守るために不可欠です。防災DXを推進することにより、リアルタイムでの災害情報の収集や、オンラインでの安否確認の実施などを実現できます。これにより、状況把握と指示伝達が迅速化され、従業員の安全確保につながります。
また、災害後の事業停止は企業の存続を脅かすため、できるだけ早く事業を復旧させることが重要です。防災DXで平時から災害に備えておけば、災害発生時に事業が停止する期間を最小限に抑えられます。たとえば、オフィス以外で業務を継続できる体制を構築しておくと、オフィスが被災した場合にも自宅などで従業員が業務に従事でき、事業を継続することが可能です。
防災DXを推進した事例
ここでは、デジタル庁や自治体による実際の事例を紹介します。
デジタル庁の推進事例
国としても防災DXを推進するために、デジタル庁が中心となってさまざまなプロジェクトを展開しています。そのなかでも、防災アプリ・サービスの調達の迅速化と円滑化と、災害対応高度化に関する実証事業について紹介します。
防災アプリ・サービスの調達の迅速化と円滑化
デジタル庁では、自治体が防災アプリ・サービスをスムーズに導入できるよう、「防災DXサービスマップ」と「防災DXサービスカタログ」というサービスを公開しています。
「防災DXサービスマップ」は、災害対応の各段階(平時、切迫時、応急時、復旧・復興時)に役立つサービスを掲載しているWebサイトです。マップ上でサービス分類をクリックすると、より詳細な情報が掲載された「防災DXサービスカタログ」へアクセスできます。
「防災DXサービスカタログ」は、事業者から応募のあったアプリ・サービスをまとめたデータベースです。自治体担当者は各サービスの概要や導入手続き、実績などを確認できます。2025年3月24日時点の登録サービス件数は、212件です。
災害対応高度化に関する実証事業
デジタル庁では、スマートフォンの位置情報を利用して、災害時の捜索救助活動をより効果的にできないか検証を行っています。また、マイナンバーカードと連携した医療情報などをもとに、個人の状況に適した早期避難の促しや避難誘導が効果的に実施できるかどうかといった検証も進めています。
さらに、災害発生後の避難所運営などの業務を効率化するための実証実験も実施しています。2023年度には神奈川県の協力を得て、広域災害を想定した避難者支援業務のデジタル化による効率化実験と、マイナンバーカードの有効性についての実証実験を行いました。
自治体の推進事例
防災DXは、自治体でも積極的に取り入れられています。企業の防災担当者にとっても、自治体が実施する先進的な取り組みは、自社に応用できるヒントになるかもしれません。
ここでは、宮城県仙台市と愛知県豊橋市の推進事例を紹介します。
宮城県仙台市:VR技術で災害を擬似体験する
宮城県仙台市では、VR技術を活用した「せんだい災害VR」というサービスを提供しています。自然災害の予兆や発災の様子などを、臨場感あふれる360度の立体映像と音響で擬似体験できるという防災学習です。
せんだい災害VRでは、地震災害編、津波災害編、洪水・土砂災害編、内水氾濫編の4種類の災害を体験可能です。それぞれ約4分間のVR体験を通じて、日頃の備えや避難時の心構えなどを学びます。利用できるのは、仙台市内の各種団体(学校、町内会、任意団体、事業所など)です。
(参考:防災訓練や防災研修会に「せんだい災害VR」をご利用ください。|仙台市)
愛知県豊橋市:災害被害をリアルタイムで把握するツールを導入
愛知県豊橋市では、災害時に被害状況を即時に把握できる防災・危機管理サービスを導入しています。このサービスでは、SNSや気象データなどの情報を自動で収集・可視化・予測し、リアルタイムで災害関連情報を地図上に表示することが可能です。
従来は職員の巡回や市民からの電話など限られた手段で情報を収集していましたが、防災・危機管理サービスを導入したことにより、迅速かつ正確に状況を把握できるようになりました。実際に、2023年の線状降水帯による豊川周辺の冠水や市内各所の浸水被害が発生した際には、200件以上の動画や写真から冠水・内水氾濫などの状況をリアルタイムで把握できたという実績があります。
(参考:愛知県豊橋市におけるAIリアルタイム防災・危機管理サービス「Spectee Pro」導入事例を公開)
企業の防災DXにおすすめのサービス
企業が防災DXを推進する際に、どのようなサービスを導入すべきか判断に迷うことが多いでしょう。企業の防災DXでとくに重要なのは、事業継続性の確保です。緊急時に迅速に情報共有と意思決定ができて、リモート環境でも業務を続けられる体制を整えておくことにより、事業継続性が高まります。
ここでは、緊急時の情報共有と意思決定、事業継続に役立つ、企業の防災DXにおすすめのサービスを3つ紹介します。
Web会議ツール
Web会議ツールとは、インターネットを通じて、リアルタイムで映像・音声のやり取りを行えるシステムです。映像・音声のやり取りだけでなく、チャットや画面共有などの機能も備えています。
Web会議ツールがあれば、オフィスが被災した際にも、自宅などから打ち合わせを行うことが可能です。また、複数の拠点を持つ企業においては、被災地域と本部との間で即時に情報共有ができ、現場の状況把握や意思決定のスピードが大幅に向上します。
代表的なサービスとして、Zoomが挙げられます。Zoom Video Communications社が提供するツールで、ビデオ会議の参加可能人数は最大1,000人です。ブレイクアウトルーム機能を使えば、参加者を複数のグループに分けて議論できます。主催者から送られるURLをクリックするだけで参加できるため、緊急時にもスムーズに会議に参加できる点も魅力です。
安否確認システム
安否確認システムは、災害や緊急事態発生時に、従業員の安否を迅速に確認するためのシステムです。主な機能としては、災害発生時の安否確認メールの一斉送信、回答の自動集計、未回答者への再送信などがあります。
緊急事態が発生した際に、安否確認のメール配信や回答結果の集計をシステムに任せられるため、連絡忘れや集計漏れの心配はありません。また、手動で安否確認を実施する場合よりも短期間で安否確認が完了するため、次のアクションに移りやすく、最短での事業復旧を実現できます。
なお、トヨクモでは『安否確認サービス2』という安否確認システムを提供しています。気象庁の災害情報と連動して、事前に登録した従業員の連絡先に安否確認メールを自動で一斉送信します。BCPに必要となる機能も備えており、災害時の指示や情報共有を迅速に行えるため、防災DXの推進におすすめです。
スケジューラー
スケジューラーは、会議やタスク、シフトなどを管理するツールです。防災DXにおいて、災害時にも対応チームの活動予定を即座に把握・調整できるという点で重要な役割を担っています。
従来の紙によるスケジュール管理では、緊急事態が発生した際、リアルタイムでのスケジュール共有は困難です。初動対応が遅れて、事業復旧までに多くの時間を要する事態になりかねません。
一方、クラウドやオンプレミス型のスケジューラーを導入することにより、場所を問わずリアルタイムでのスケジュール共有が可能になります。災害発生時に「誰が」「いつまでに」「何をすべきか」が明確になり、対応の混乱を防止できます。さらに、進捗状況がリアルタイムで可視化されるため、対応漏れも防げます。
防災DXを実現する上で役に立つスケジューラーとしておすすめなのが「トヨクモスケジューラー」です。どのような機能があるのか、以下で詳細を紹介します。
トヨクモ スケジューラー
トヨクモ スケジューラーは、トヨクモが提供するクラウド型のスケジュール管理サービスです。kintoneと連携できるのが大きな特徴で、スケジューラーに予定を追加してkintoneで同期することにより、個人・組織がどの業務にどの程度の時間を使っているのかが明らかになります。
また、グループメンバーのスケジュールを一覧で確認することも可能です。災害が発生した際には、迅速な会議設定や対応チームの編成を行うツールとして活用できます。
【トヨクモ スケジューラーの機能例】
| 主な機能 | 概要 |
| 個人ビュー | 個人のスケジュールを週表示と月表示で切り替えて確認できる |
| グループビュー | 週表示のカレンダーでメンバーと施設のスケジュールを縦に並べて確認できる |
| タスク | 個人タスクを管理する。期限を設定すれば、カレンダー上に表示することが可能 |
| 日報 | 予定とタスクから、その日の活動を時系列順にしたテキストを自動で生成する |
| 空き時間ビュー | メンバーと施設の空き時間をまとめて確認できる |
| 日程調整ページ | 社外の人に空き時間をシェアして、予定を追加してもらえる |
スマートフォン用のアプリも提供されており、外出先から予定の確認や変更ができるのも大きなメリットです。災害が発生した際にオフィスに戻ることなく、どこにいても対応チームの編成や調整を行えるため、初動対応のスピードが格段に向上します。
料金プランは企業規模に応じて3つ用意されています。10ユーザー以下の小規模利用なら基本機能が使える無料のフリープランがおすすめです。より本格的な利用には、1ユーザーあたり月額220円(税込)で利用できるkintone同期機能付きのスタンダードプランか、月額5,500円(税込)で30ユーザーまで利用できる大規模組織向けのビジネスプランを選ぶとよいでしょう。
30日間の無料お試しが用意されており、自動課金されない仕組みであるため、安心して試せます。少しでも興味がある場合は、まずは無料お試しで操作性を確認してみてはいかがでしょうか。
防災DX推進に関する課題
防災DXの推進には、多くの企業が共通して抱える課題が存在します。まず挙げられるのが、導入にかかる初期コストの高さです。システムの導入には一定の費用がかかるため、導入コストの高さがネックとなる場合も少なくありません。ただし、この課題はIT導入補助金の活用で負担を軽減できます。
また、DXを推進するための専門知識や経験を持つ人材の不足も大きな課題です。とくに中小企業では、社内に十分なIT人材がいないケースも多く見られます。外部の専門家と連携しながら進めていくとよいでしょう。
防災DXの推進にIT導入補助金を活用しよう
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に、その費用の一部を国が補助する制度です。労働生産性の向上を目的としており、業務効率化やDXなどに向けたITツールの導入時に利用できます。
補助対象には、ITツールの導入費用だけでなく、相談対応などのサポート費用やクラウドサービス利用料も含まれます。ただし、補助の対象となるITツールは、事前に事務局の審査を受けて補助金のホームページに登録されているものに限定されています。
IT導入補助金を活用することにより、初期投資の負担を軽減できるため、自社が利用できる対象に含まれるのか一度確認してみるとよいでしょう。業種によって、中小企業や小規模事業者に該当する資本金や従業員の基準は異なります。申請対象者の詳細については、以下をご確認ください。
まとめ:自社に適したITツールを導入して防災DXを推進しよう
防災DXとは、デジタル技術を活用して、防災を強化する取り組みです。東日本大震災や能登半島地震などの経験から、その重要性はますます高まっています。30年以内に南海トラフの発生する可能性が高いことから、まだ防災DXを推進していない場合には、できるだけ早く着手しましょう。
企業の防災DXを支えるツールとして、Web会議ツールや安否確認システム、スケジューラーなどが挙げられます。初期導入コストの高さがネックとなりがちですが、IT導入補助金の活用によって負担を軽減できるかもしれません。自社が利用できるかどうか公式サイトで確認してみてください。
トヨクモでは、営業業務や採用業務を効率化できる『トヨクモスケジューラー』を提供しています。ユーザー数無制限で利用できる無料お試しが用意されているため、スケジューラーの利用を検討している場合には、試してみてはいかがでしょうか。