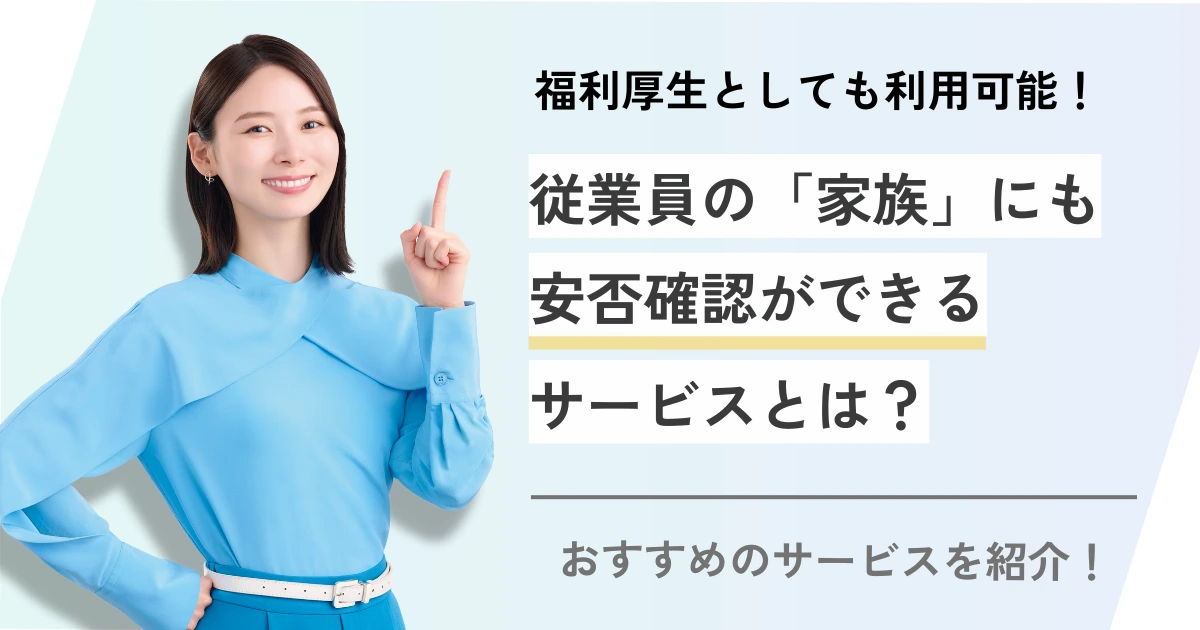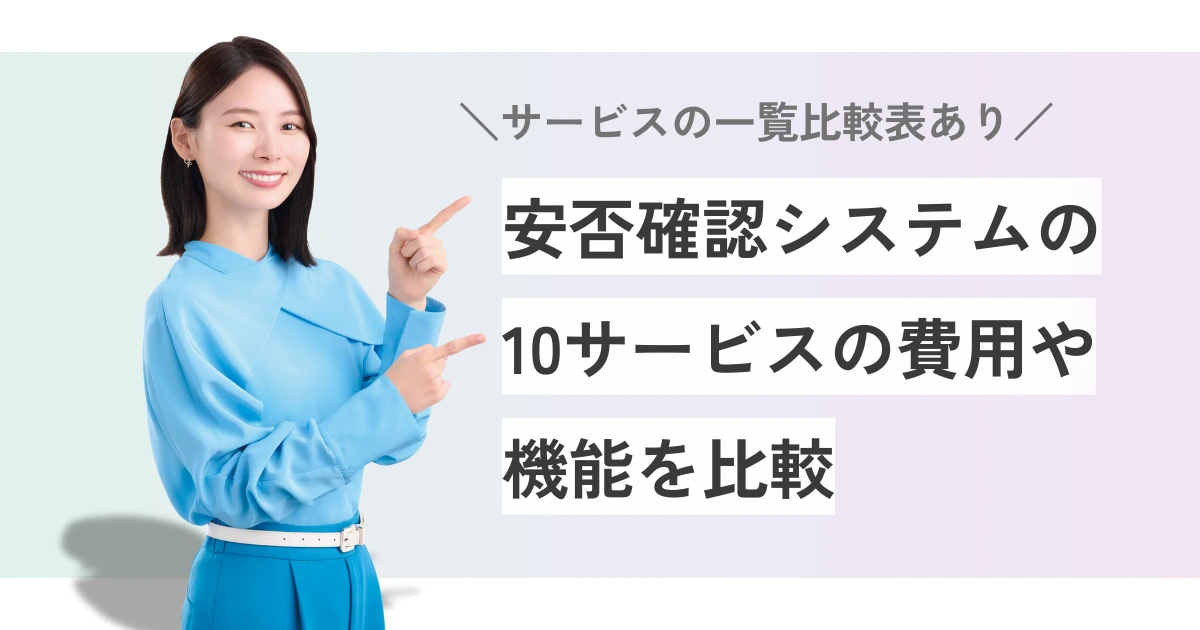金融機関のBCP策定ポイントは?具体的な対策事例も解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
近年、大規模な自然災害の頻発やサイバー攻撃の高度化・巧妙化などが多くの企業で課題となっています。とくに、金融機関におけるBCP(事業継続計画)の策定・強化は、顧客の大切な資産と社会からの信頼を守る上で不可欠な経営課題です。金融システムは社会の基盤であり、その機能停止は経済活動全体に深刻な影響を及ぼしかねません。
しかしながら、金融機関のBCP策定には、金融システム特有の複雑性や規制要件への対応など、専門的な知識が求められるほか、策定・維持には相応のリソースとコストを要します。
そこで本記事では、金融機関におけるBCPの重要性を改めて解説するとともに、具体的な策定ポイントや想定されるリスク別の対策事例、そして大手金融機関の取り組み事例まで、網羅的に紹介します。
BCP策定・運用における課題と、それらに対する解決策も提示するので、ぜひ最後までご覧いただき、貴社のBCP高度化に役立ててください。

目次
金融機関がBCPを策定するべき理由
金融機関において、BCP策定は非常に重要なものとなります。まずは、金融機関がBCPを策定するべき理由を詳しく見ていきましょう。
自然災害やサイバー攻撃が増加している
近年、地震や台風などの自然災害が頻発化しています。たとえば、令和6年1月には石川県能登地方で最大震度7を観測する地震が発生しています。ここ数年だけでも、数回の大地震が起きていることから、自然災害への対策は非常に重要なものだと分かるはずです。
また、サイバー攻撃も高度化・巧妙化しており、金融機関を取り巻くリスクは増大の一途を辿っています。これらのリスクは、金融機関のシステムや業務に深刻な影響を与え、顧客の資産や取引に多大な損害をもたらす可能性があります。
BCPを策定していない場合は、顧客の資産や取引状況に大きな被害を与えることとなり、信頼も大きく低下してしまうでしょう。従業員や顧客を守るためにも、金融機関ではBCPの策定が必要です。
金融機関の業務停止は社会に与える影響が大きい
金融機関は、社会インフラとして重要な役割を担っています。預金や決済などの金融サービスが停止すれば、企業活動や個人消費が滞り、社会全体に混乱を招きます。とくに、地域経済を支える地方金融機関においては、その影響はかなり大きいでしょう。
これらの理由から、金融機関はBCPを策定し、万が一の事態に備えることが不可欠です。
BCP策定による経営上のメリットがある
BCPを策定することにより、金融機関は以下のようなメリットを得られます。
- 顧客の信頼を維持できる
- 社会的責任を果たすことができる
- 事業継続性を高めて競争優位性を確立できる
- 法令遵守とリスク管理体制を強化できる
- 取引先との信頼関係を強化できる
このように、金融機関にとってBCPは、リスク管理の根幹であり、持続的な成長と信頼確保のための重要な経営基盤なのです。
金融機関におけるBCP策定のポイント
続いて、金融機関におけるBCP策定のポイントを見ていきましょう。主なポイントは、以下のとおりです。
- リスクアセスメントの実施
- 優先業務の特定と目標復旧時間の設定
- 代替拠点やシステムの確保
- 従業員の安否確認
- 顧客への情報提供とコミュニケーション
- 定期的な訓練と見直し
それぞれの内容を詳しく解説します。
リスクアセスメントの実施
金融機関におけるBCP策定の第一歩は、リスクアセスメントとなります。リスクアセスメントとは、金融機関を取り巻くさまざまなリスクを洗い出し、その発生頻度や影響度を評価するプロセスです。
リスクの洗い出しでは、地震・台風・洪水などの自然災害、サイバー攻撃や停電によるシステム障害、感染症の流行やテロなど、あらゆるリスクを想定する必要があります。
また、リスクの評価では各リスクが発生した場合に、金融機関の業務や顧客にどのような影響を与えるかを具体的に分析しましょう。リスクアセスメントの結果はBCP策定の基礎となる情報で、優先的に対策すべきリスクや目標復旧時間を設定する上で重要な判断材料となります。
優先業務の特定と目標復旧時間の設定
リスクアセスメントの結果を踏まえ、優先的に継続・復旧すべき業務を特定することも大切です。優先業務とは、顧客への影響が大きい業務や金融機関の経営上重要な業務を指します。
たとえば、預金払い出しや決済、融資などが優先業務として挙げられます。優先業務を特定したら、目標復旧時間を設定しましょう。業務の重要度や顧客への影響度を考慮して設定しておき、万が一の際は顧客に普及までの目安を迅速に伝えられるようにしてください。目標復旧時間を設定することによって、必要な対策を逆算して準備ができます。
代替拠点やシステムの確保
災害発生時には、本店や主要なシステムが利用できなくなることを想定し、代替拠点やシステムを確保しましょう。代替拠点としては、地理的に分散した場所にバックアップオフィスを設置すると効果的です。
また、システムについては、クラウドサービスやデータセンターの利用などの対策が必要になります。代替拠点やシステムの確保はコストがかかるため、優先業務や目標復旧時間を考慮して、適切なレベルで実施しましょう。
システムのバックアップに関しては、定期的にデータが本当に復旧できるかテストし、確実に復旧できることを確認しておくのがおすすめです。代替拠点については、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。
(内部リンク 「bcp 代替拠点」)
従業員の安否確認
災害発生時における従業員の安否確認は、金融機関の事業継続において重要な要素です。従業員の安否確認が迅速に行われれば、従業員の安全確保や業務の早期再開につながります。
安否確認の方法としては、安否確認システムやSNSなどを活用することが考えられます。また、交通機関が麻痺した場合も想定して、どのように従業員に集まってもらうのかも検討しておくとよいでしょう。
顧客への情報提供とコミュニケーション
災害発生時、顧客は金融機関からの情報提供を強く求める傾向です。金融機関は、顧客に対して、正確かつ迅速な情報提供を行う必要があります。情報提供の方法としては、Webサイト・SNS・電話などが考えられます。
また、顧客からの問い合わせに対応するための体制も整備しておくことも必要です。顧客への情報提供は顧客の不安を解消できるだけでなく、金融機関への信頼を維持することにもつながります。情報提供だけでなく、顧客とのコミュニケーションも重視し、適切な対応によって顧客との信頼関係を強化しましょう。
リスクコミュニケーションについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。
(内部リンク「リスクコミュニケーション」)
定期的な訓練と見直し
BCPは、策定したら終わりではなく、定期的な訓練と見直しが必要です。訓練では、実際の災害を想定したシミュレーションを行い、BCPの有効性を検証します。訓練の結果を踏まえてBCPの課題を洗い出し、改善策を検討しましょう。
また、社会情勢や技術の変化に合わせて、BCPを定期的に見直すことも必要です。BCPは、常に最新の状況に合わせて更新していくことによって、より実効性の高いものとなります。金融機関にとってのリスクも日々、変化していくため時代に合わせたBCPを策定しましょう。
金融機関が直面するリスクとBCP対策例
ここでは、具体的な対策を金融機関が直面するリスクごとに紹介します。システム障害と自然災害とでは、行うべき対策が異なってくるため、以下を参考にBCP策定を進めましょう。
システム障害への対策
金融機関のシステムは顧客情報や取引データなど、極めて重要な情報を扱っています。システム障害が発生すれば顧客の資産が失われたり、取引が停止したりすると、金融機関の信頼を大きく損なうことにもなりかねません。
システム障害への対策としては、同じ機能を持つシステムを複数用意することが挙げられます。複数のシステムが使える状態であれば、1つのシステムが停止してもほかのシステムを稼働させ、業務を停止することなく継続できます。
また、データのバックアップも重要です。定期的にデータをバックアップし、バックアップデータを別の場所に保管することにより、万が一の事態に備えられます。
地震・水害などの自然災害への対策
金融機関は、自然災害が発生した場合でも、業務を継続できるように対策を講じることも必要です。まず第一に、建物の耐震化が挙げられます。建物の耐震性を高めることにより、地震による倒壊を防げます。
また、データセンターの分散化も重要です。データセンターを分散させれば、どこかのデータセンターが被災しても、ほかのデータセンターで業務を継続できます。さらに、非常用電源の確保も必要になります。停電が発生した場合でも、非常用電源でシステムを稼働させられるよう、自家発電設備や蓄電池などの導入を検討しましょう。
新型感染症への対策
近年、新型コロナウイルス感染症の流行により、金融機関においても感染症対策の重要性が認識されました。感染症対策としては、従業員の安全確保が挙げられます。従業員にマスクや消毒液を配布したり、テレワークを導入したりすれば、感染拡大を防ぐことが可能です。
また、業務の継続性確保も重要となります。感染者が発生した場合でも業務を継続できるように、業務の優先順位をつけたり、代替要員を確保したりしましょう。さらに、顧客への情報提供も重要です。感染症に関する正確な情報を顧客に提供することにより顧客の不安を解消し、金融機関への信頼を維持できます。
サイバー攻撃への対策
サイバー攻撃は近年、高度化・巧妙化しており、金融機関にとって大きな脅威となっています。サイバー攻撃の対策としては、さまざまなセキュリティ対策を導入するだけでなく、従業員のセキュリティ意識を高めるための教育も重要です。
また、トラブル発生時の対応体制の構築も必要になります。サイバー攻撃が発生した場合に、迅速に対応できるように対応チームを設置し、対応手順を明確にしておくことが大切です。さらに、ほかの金融機関やセキュリティ機関と情報共有し、最新のサイバー攻撃の動向を把握して対策を講じることも有効な手段といえます。
金融機関特有の対策
金融機関は、顧客の資産を預かるという特有の業務を行っているため、一般的な企業とは異なるBCP対策が必要です。
たとえば、ATMの稼働継続が挙げられます。災害発生時でも、顧客が現金を引き出せるように、ATMの稼働を継続することが求められます。停電などがあった場合に、どのような対処をするべきなのかしっかりと決めておくことが必要です。
また、大切な資産を預けている銀行に対しては、問合せをする顧客も多くいます。迅速な顧客対応をすることにより、信頼関係の維持に務めることも重要です。
金融機関のBCP策定事例
以下のような金融機関では、BCPを策定しています。
- みずほフィナンシャルグループ
- りそなホールディングス
- 三井住友トラスト・ホールディングス
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
みずほフィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループでは、「金融決済機能の維持・継続」や「業務の早期復旧」を優先としたBCPを策定しています。緊急事態に備えた危機管理室なども設置しており、災害時の対策をしっかり行っていることが分かるはずです。
大規模災害やシステム障害といった危機発生時においても、金融システムの中核としての機能を維持し、顧客へのサービス提供を継続することをBCPの主目的としています。
りそなホールディングス
りそなホールディングスでは、社員など関係者の人命の安全確保を最優先とし、可能な限りの業務を継続・早期復旧すると明記しています。とくに、預金の払戻・振込・資金証券等の主要業務については、当日中の復旧を目標に設定しているのが特長です。
また、地域社会のニーズを把握し、災害復旧に必要な資金供給や金融サービスの提供を迅速に行える体制を整備しています。
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングスは、常にさまざまなリスク管理をしている金融機関です。BCPの策定はもちろん、実効性を確保するための定期的な訓練、内容の見直しも実施し、徹底してリスクに備えています。
このように、大手の金融機関の多くがBCPを策定しており、BCP策定・強化は信頼の維持や従業員の安全確保において、非常に重要であることが分かるでしょう。
金融機関がBCPを策定する際の課題
BCP策定には、さまざまな課題があるのが現状です。ここでは、金融機関がBCPを策定する際に直面する課題について解説します。
コストの問題
BCPの策定・運用には、多大なコストがかかります。たとえば、代替拠点の確保や訓練の実施などは、費用がかさむ傾向です。とくに、中小規模の金融機関にとっては、コストが大きな負担となる可能性があります。
また、BCPは一度策定すれば終わりではなく、定期的な見直しや訓練が必要となるため、継続的なコストが発生する点にも注意が必要です。コストを抑えつつ、効果的なBCPを策定・運用するためには、優先順位をつけて段階的に対策を進めることが重要になります。
人材の確保・育成
BCPの策定・運用には、専門的な知識やスキルを持つ人材が必要です。しかし、金融機関においては、BCPに関する専門人材が不足している場合が多くあります。とくに、地方金融機関においては、人材の確保が難しいという点も課題です。
また、BCPは策定するだけでなく、従業員に対する継続的な教育・訓練が不可欠となります。人材の確保・育成のためには、外部の専門家やコンサルタントの活用が必要だが、それぞれに大きなコストがかかる点も課題のひとつです。
ITシステムの複雑化
金融機関のITシステムは近年、高度化・複雑化しており、BCP策定を困難にしています。システムの複雑化により、障害発生時の影響範囲の特定や復旧手順の策定も難易度が増している傾向です。
また、クラウドサービスや外部システムとの連携など、システムの外部依存度が高まっていることも、新たなリスク要因となっています。ITシステムの複雑化に対応するためには、システムの可視化やセキュリティ対策の強化などが重要です。
また、システム障害発生時の対応手順を明確化し、定期的な訓練を実施することによりシステムの復旧時間を短縮することができます。
課題解決には『BCP策定支援サービス(ライト版)』がおすすめ
金融機関が抱えるBCP策定の課題解決には、『BCP策定支援サービス(ライト版)』がおすすめです。こちらのサービスは、金融機関がBCPを策定する際の課題を解決するために、専門家が支援するものとなります。
専門家による効率的な支援により、BCP策定にかかるコストを削減できる上に、1ヶ月程度と短期間で策定が完了するのがメリットです。コストやリソースの不足により、BCP策定が遠のいていた企業も、サービスを活用すれば簡単に策定できます。
金融庁のガイドラインなど、BCPに関する最新情報を提供してくれるほか、利用料も1ヶ月15万円(税抜)と安価なのが魅力です。ぜひ、この機会に導入をご検討ください。
BCP策定で顧客の資産や従業員を守ろう
金融機関におけるBCPの策定は、顧客の資産を守るだけでなく、金融機関自身の事業継続を可能にする上で不可欠です。自然災害やサイバー攻撃など、予測不能な事態が発生した場合でも、金融機関は安定したサービスを提供し、顧客の信頼を維持する必要があります。
BCP策定に不安を感じている場合は、『BCP策定支援サービス(ライト版)』の利用がおすすめです。1ヶ月、15万円の短期間・低コストで自社のBCPマニュアルを策定することができる。定期的なマニュアルの見直し時にも活用できます。
本格的なBCPコンサルを探す手間と費用を省き、社内でBCPを策定できるのが大きな魅力です。策定リソースが限られる中で自社の抱える課題を解決し、BCPを策定したいと考えている担当者は、ぜひ導入を検討してください。
また、緊急時の従業員の安否確認には、トヨクモの『安否確認サービス2』が役立ちます。災害発生時に登録した連絡先に一斉に安否確認のメッセージが送信され、通知を受け取った従業員はURLをクリックして回答する仕組みです。回答結果はリアルタイムで自動集計されるため、発災直後の混乱の中でもすぐに従業員の状況が確認できます。就業可能な従業員を把握することは、業務の早期再開にもつながるでしょう。
各サービスについて気になる方は、お気軽にお問合せください。