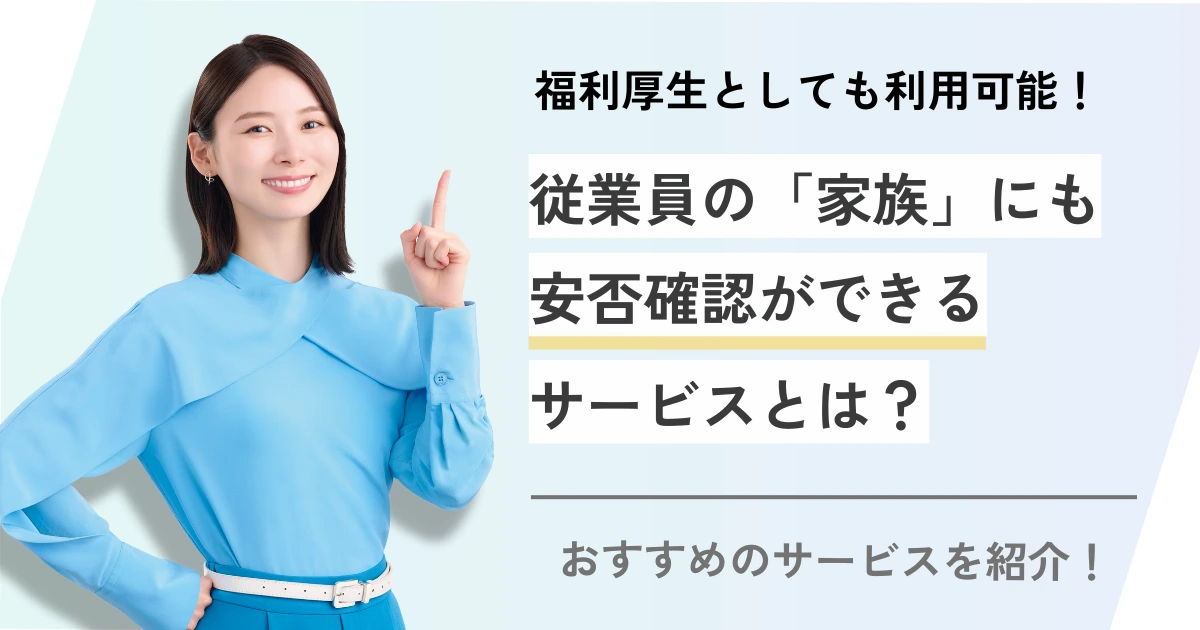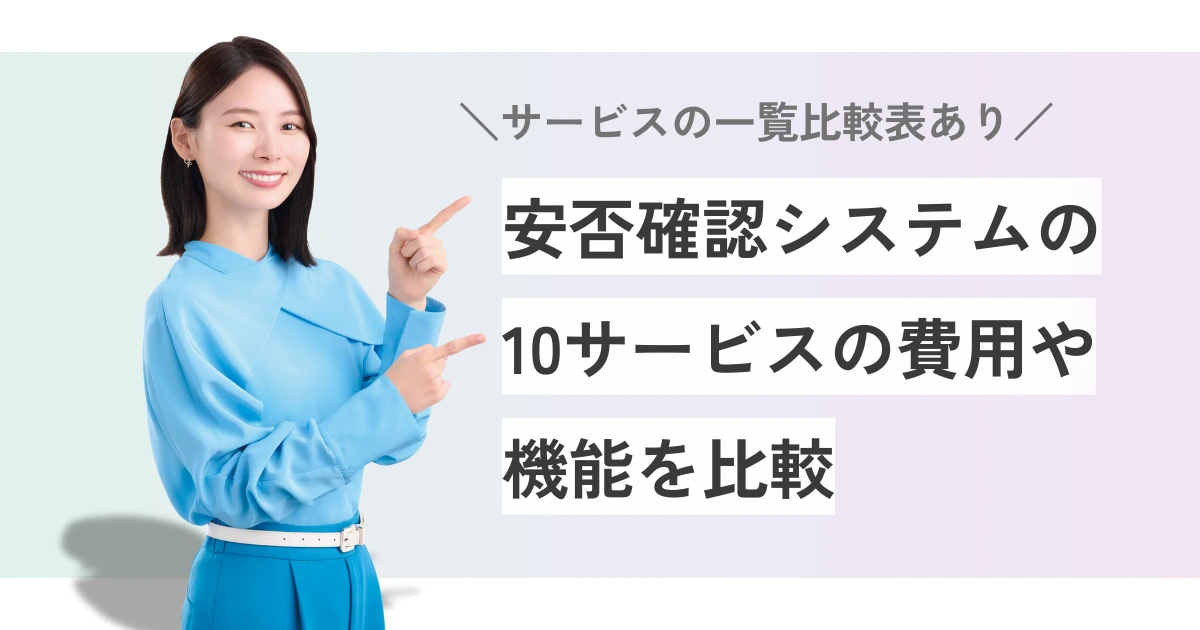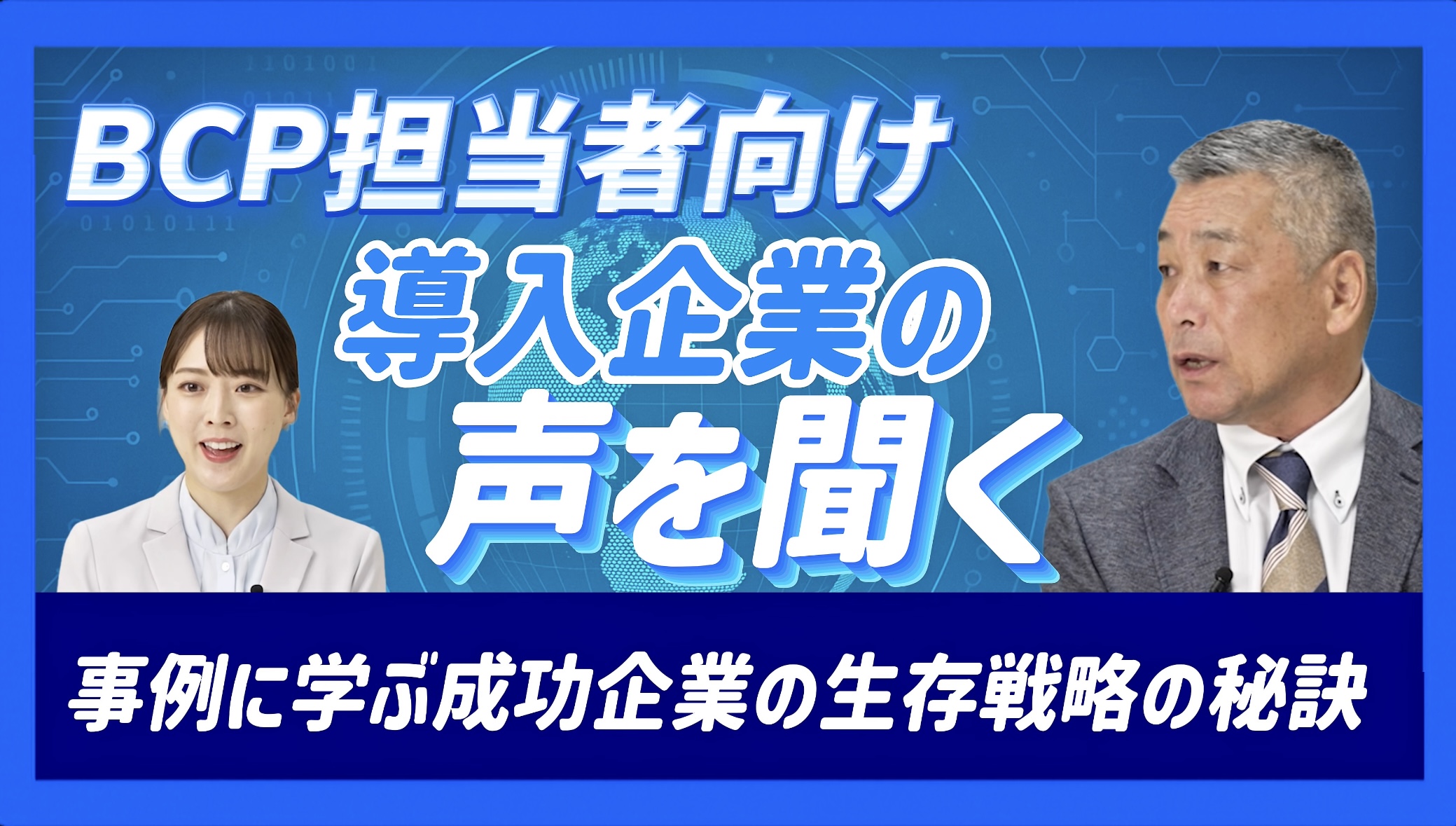中核事業とは?特定方法や中核事業を止めないための危機対応策を解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
企業経営においてもっとも重要なことのひとつは、どのような危機的状況下であっても、企業の“心臓部”といえる「中核事業」を継続させることです。中核事業が停止すれば、売上・収益が途絶えるだけでなく、従業員の雇用や取引先との関係、さらには企業の存続そのものが危うくなります。
地震や台風、パンデミックなどの危機が発生した際に企業が中核事業を継続できるかどうかは、事前の準備と対応策の有無にかかっているといえるでしょう。
この記事では、中核事業の概要や特定方法を解説し、その事業を緊急時でも継続できる仕組みを構築するための実践的な戦略を紹介します。中核事業を止めるリスクを把握した上で、最適な対策を講じていきましょう。

目次
企業存続の鍵となる中核事業とは?
中核事業とは、企業の売上・収益の大部分を占める、経営の根幹を支える事業領域のことです。企業が持続的に成長し、市場での競争力を維持するためには、中核事業の安定した運営が不可欠です。
たとえば、製造業であれば主要製品の生産ライン、小売業ならば物流と在庫管理、IT企業ならば基幹システムの運用などが該当します。中核事業の領域が一時的にでも停止すると、企業の信用が揺らぎ、取引先や顧客の信頼が失われる可能性があります。中核事業の継続は企業が生き残り続ける上で必須の要素です。
とくに近年、予測不能な危機が頻発する状況を鑑みると、「企業が存続できるか否かは、中核事業を継続できるかにかかっている」と言っても過言ではありません。したがって、緊急時に中核事業を止めない仕組み作りは何よりも重要だと言えるでしょう。
自社の中核事業を特定する方法
「中核事業と呼べる事業のおおよその検討はついているものの、客観的にそれが中核事業といえるのか自信がない」などと感じている方もいるでしょう。
そこでここからは、自社の中核事業を特定する手順を整理して紹介します。
財務分析を通じて事業の経済的基盤を評価する
財務分析を通じて事業の経済的基盤を評価しましょう。まず、企業の収益源を把握するために、事業ごとの売上割合を分析します。とくに売上高の50%以上を占める事業は、企業の中核的役割を果たしている可能性が高いです。
ただし、売上だけで判断せず、その事業の市場変動リスクや成長可能性も考慮する必要があります。また、売上だけでなく、利益率も重要な指標となります。たとえば、ある事業の売上が企業全体の40%を占めていたとしても利益率が低ければ、その事業が企業の財務的な安定性に貢献しているとは言えません。売上に加えて粗利・営業利益・純利益の視点から検討することも重要です。
さらに、中核事業は企業のキャッシュフローを支える存在でもあります。運転資金の流れや安定した資金調達のしやすさを考慮し、事業が企業の資本にどう貢献しているかを評価しましょう。
競争優位性の視点から見極める
企業が長期的に生き残るためには、競争力のある事業を持つことが不可欠です。たとえば、企業独自の技術やブランド価値、特許、ノウハウなど、競合他社が簡単にマネできない強みがあるかを確認します。自社の競争優位性を判断したうえで中核事業を見極めれば、他社にはない商品やサービスを提供でき、消費者に必要とされ続けるでしょう。
また、業界内での市場占有率をチェックし、競争相手と比較してどれほどの影響力を持っているかを評価するのもポイントです。市場シェアが高い事業は、企業の中核事業としての可能性が高いですが、一方で成長率や将来的なリスクも考慮する必要があります。
代替案の有無から必要性を判断する
中核事業は代替案の有無から必要性を判断することも重要です。企業の中核事業は、災害や不測の事態が起こった際にも継続しなければいけません。たとえば、製造業であれば生産ラインの維持、IT企業であればクラウドサービスの運用など、緊急時でも業務が止まらない仕組みが求められます。
つまり、中核事業を判断する際は、その事業が企業にとって不可欠なのか、もし停止した場合、代替手段があるかを考えることが重要です。仮に代替が難しい場合、その事業は企業の存続にとって極めて重要だと判断できます。
また、経済状況や技術革新、法律の変更など、外部環境の変化が事業にどのような影響を与えるかを検討します。長期的な視点で成長可能な事業が、中核事業として選定されるべきだといえるでしょう。
顧客関係面から判断する
中核事業を特定する際は、顧客との契約内容についても考慮しましょう。企業は顧客と契約を結んだ上で事業を展開していることから、どのような状況下であっても商品を納品し続けなければいけません。とくに商品の納品時期やサービスの提供時間など、期限が決まっている事業は、延滞における損害が大きなものになるでしょう。
そのため、中核事業を特定するときは、災害などの緊急時に事業が止まってしまった場合の損害状況を考慮し選定することが重要です。
中核事業が停止した際に発生する被害
中核事業が停止すると、以下のような悪影響が発生する恐れがあります。
- 売上減少
- 企業ブランドの低下
- 企業成長の遅れ
それぞれについて解説します。
売上減少
中核事業は企業の売上・収益の大部分を占めることから、停止すると売上減少につながります。たとえば、自然災害の発生により商品を製造できないと、継続した納品が困難となります。中核事業の停止期間が伸びれば市場占有率にも影響を及ぼし、その後の経営戦略にも不利益が起こるでしょう。
また、顧客との契約内容によっては、安定的な納品ができなければ違約金が発生する恐れもあります。すると、売上や利益の減少につながり、企業の存続にも大きな影響をもたらします。
企業ブランドの低下
中核事業が停止すると企業のイメージが悪くなり、ブランド価値が低下する可能性があります。たとえば、自然災害に対する備えを万全にしている企業が緊急時でも事業を継続し、社会経済によい影響をもたらしていると社会的なイメージは向上するでしょう。
反対に、自然災害時に迅速な行動が行えず、社会経済に悪影響をもたらせば、リスクに備えられない企業として評価される恐れもあります。その結果、企業ブランドの価値が低下すると、企業の成長や売上向上は一層困難となるでしょう。
企業成長の遅れ
中核事業が停止すると、長期的な経営目標や事業計画などが思うように進まず、企業成長に遅れが生じる可能性があります。たとえば、中核事業が停止していればビジネスチャンスが訪れても手にすることは難しく、企業成長につなげることはできません。結果的に、競合他社との優位性にも悪影響を及ぼし、企業の存続方法を見直す事態を招く恐れもあります。
中核事業を止めないための危機対策
前述のとおり、中核事業が止まるとさまざまなリスクが起こり得ることから、事前に対応策を講じておく必要があります。具体的には、以下の2つが必須策です。
- BCP(事業継続計画)の策定
- 安否確認システムの導入
それぞれについて解説します。
BCP(事業継続計画)の策定
企業が緊急時でも中核事業を継続するためには、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の策定が不可欠です。BCPとは、災害や事故などの緊急時に、企業活動をできる限り止めずに継続するための計画のことです。
まず、企業が直面する可能性のあるリスクを洗い出し、それが中核事業に与える影響を分析します。たとえば、地震や火災、サイバー攻撃などのリスクがある場合、それぞれの危機に対する対応策を具体的に検討します。その対応策をもとに、企業内で統一された緊急対応マニュアルを作成しましょう。緊急時であっても従業員が混乱せずに適切な行動を取れるように、事前に訓練を実施して避難ルートや代替業務の準備を進めておくことが重要です。
なお、緊急時には社内外の関係者と迅速に情報を共有することが求められます。取引先や顧客、従業員との情報伝達手段を確立しておくことによって、企業の信頼を損なうことなく事業を継続できます。
BCPの策定手順に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はあわせて参考にしてください。
BCPの策定にはトヨクモ『BCP策定支援サービス(ライト版)』
BCPは従業員の安全と社会的信用を確保するために策定すべきですが、策定には多くの手間と費用がかかる点がデメリットです。できるだけ費用を抑えてBCPを策定したいなら、トヨクモが提供する『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用がおすすめです。
通常、BCPコンサルティングは数十〜数百万円ほどかかりますが、BCP策定支援サービス(ライト版)であれば1ヵ月15万円(税抜)で策定できます。また、最短1ヵ月で策定できることから、迅速に対策したい方も活用しやすいでしょう。金銭的な負担や手間を減らしながらBCPを策定したい場合は、ぜひトヨクモのBCP策定支援サービス(ライト版)の導入をご検討ください。
安否確認システムの導入
BCPの中でとくに重要なのが、従業員の安全を確保し、迅速な情報共有を行うことです。これを実現するためには、安否確認システムの導入がおすすめです。安否確認システムとは、災害や緊急事態が発生した際に、従業員やその家族の安否を確認するシステムのことを指します。
自然災害などが発生すると、担当者が個別に連絡するのが一般的ですが、この方法では担当者の負担が大きくなります。担当者が被災したときなどの対応方法も検討しなければいけません。
しかし、安否確認システムを導入すれば、登録している従業員に自動で安否確認通知を送信できます。回答結果を自動で集計・分析できるシステムであれば、安否確認にかかる手間を大幅に削減できるでしょう。企業の規模や業種を問わず活用できるため、中核事業の継続および早期復旧に役立つ重要なシステムといえます。
中核事業を継続するためにはトヨクモの『安否確認サービス2』の導入を!
安否確認システムのひとつに、トヨクモが提供する『安否確認サービス2』があります。気象庁の情報と連動して自動で安否確認通知を送信できるシステムで、従業員からの回答結果も自動で集計できます。
また、情報共有をスムーズに行える「掲示板機能」と特定の従業員とやり取りできる「メッセージ機能」が備わっているため、緊急時の事業継続に向けて迅速な行動が可能となるのも魅力です。
さらに、毎年9月1日に全国一斉訓練を実施しており、システムの安定稼働を確認しているのもポイントです。全国一斉訓練は実施日と時間帯のみを公開しているため、企業の定期訓練としても活用できます。
まとめ:緊急時も中核事業を継続して企業の存続を目指そう
企業はあらゆるリスクを抱えているため、どのような状況下であっても中核事業を継続できる仕組みは必須です。企業に起こり得るリスクを明らかにし、必要な対策を講じましょう。
なお、中核事業を継続的に展開するためには、トヨクモの『安否確認サービス2』の活用がおすすめです。緊急時の初動対応を迅速に行えるほか、今後の指示を出したり情報共有を行ったりできます。
また、初期費用不要で30日間のトライアル期間を設けているため、導入へのハードルも低いのも魅力です。使い心地を試した上で導入できるため、満足度の高いシステム選定を行えるはずです。中核事業を守り続けたいとお考えの方は、ぜひ無料体験から試してください。