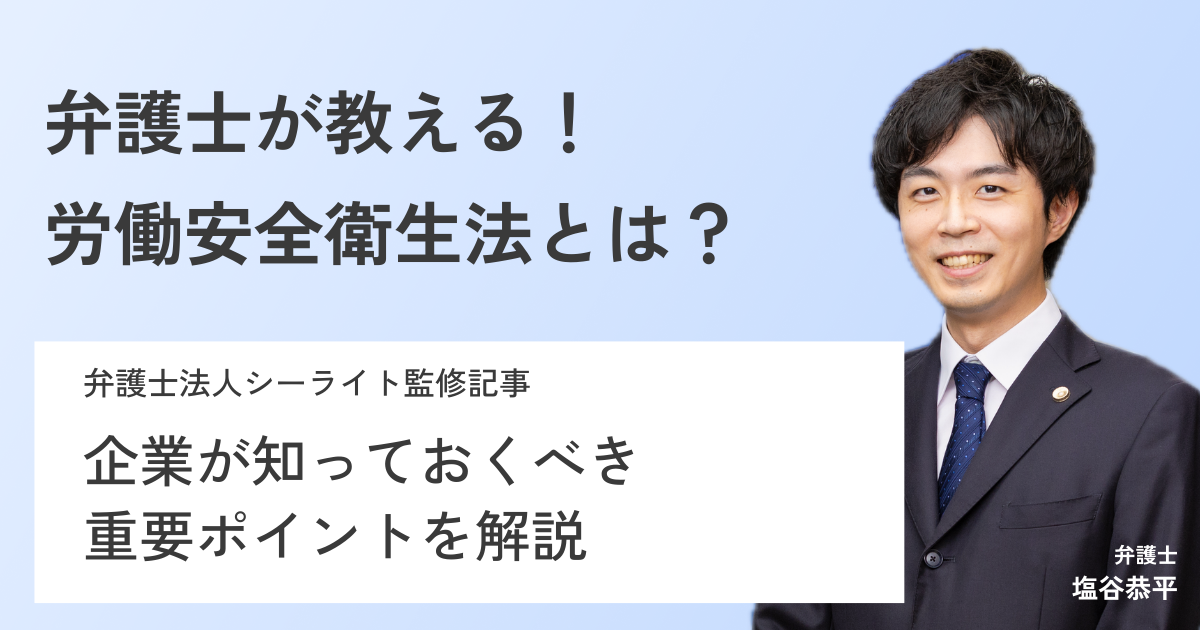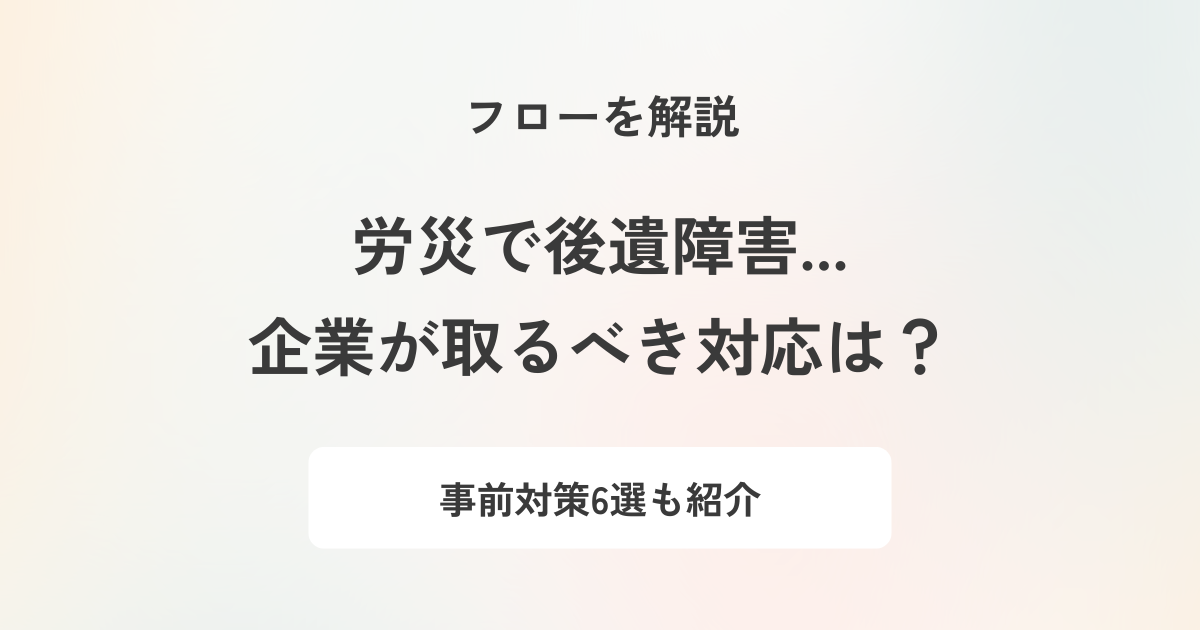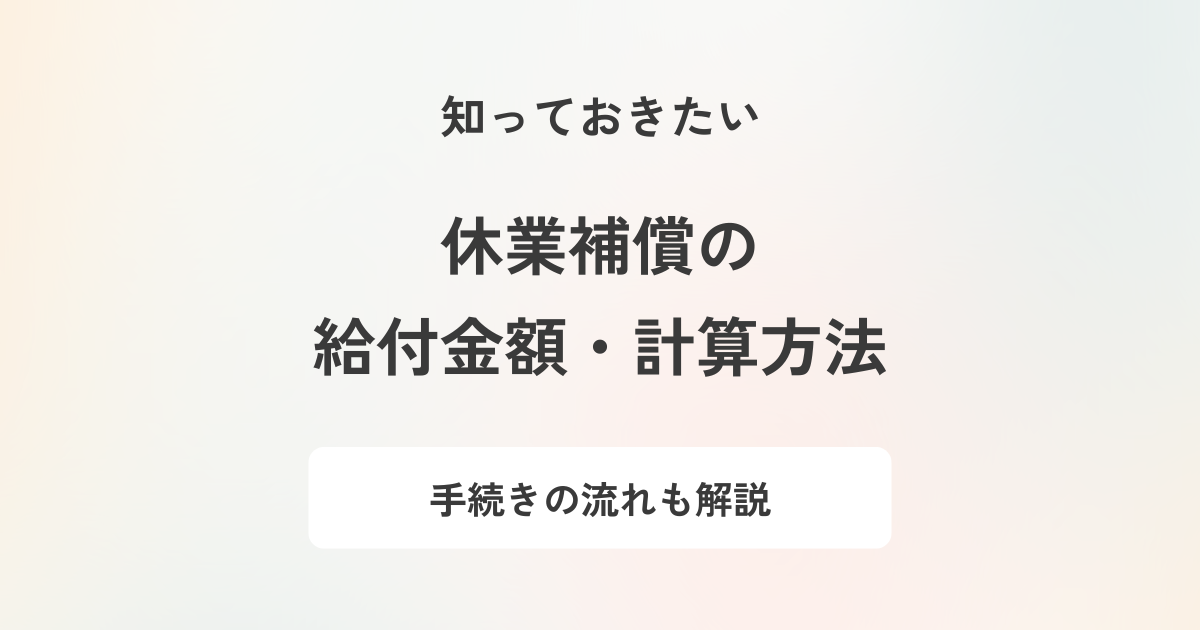【弁護士が教える】2025年施行 労働安全衛生法・規則の改正ポイント|危険箇所の保護・電子申請を解説

塩谷 恭平(しおや きょうへい)
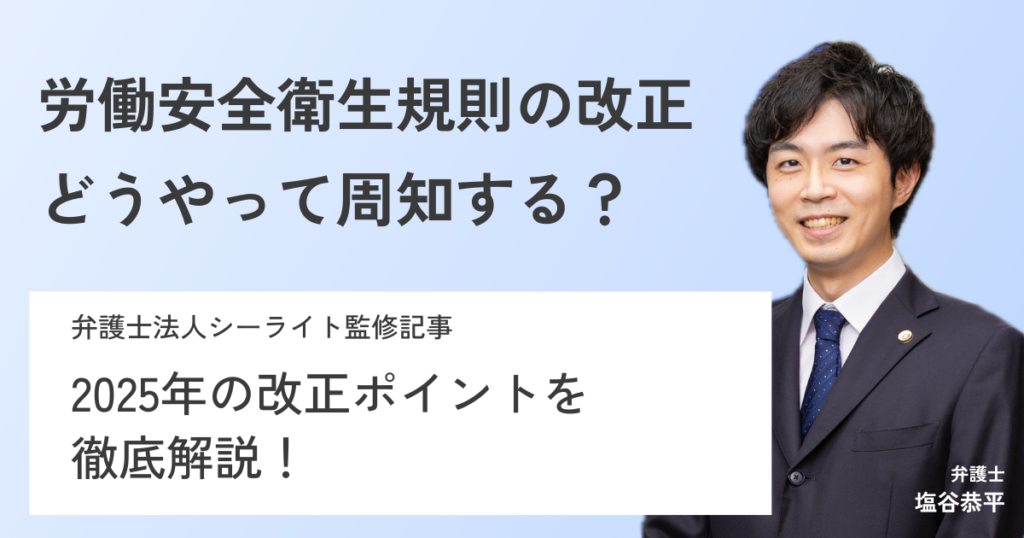
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るための法律です。2025年4月に施行される労働安全衛生規則の改正では、危険箇所での保護対象範囲拡大、一人親方や外部委託者に対する新たな義務など、いくつかの変更が予定されています。
この記事では、弁護士法人シーライト 弁護士の塩谷恭平が、2025年の労働安全衛生法改正の背景やポイント、そして企業が取るべき対応策について詳しく解説します。
職場環境を安全で快適に保つための参考にしていただければ幸いです。

目次
労働安全衛生法・衛生規則とは?改正の背景と目的
労働安全衛生法とは、労働基準法と相まって、事業者が遵守すべき義務等を定めた法律です。快適な職場環境の形成を通じて、従業員の安全かつ健康を確保することを目的としています。詳細は以下の記事をご覧ください。
労働安全衛生規則は、この法律に基づく安全対策や危険防止措置等を定めた規則です。事業者が守るべき詳細かつ具体的な基準が示されています。こちらも以下の記事で解説しています。
2025年施行の労働安全衛生規則等の改正は、令和3年5月17日の「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を受けたものです。この判決で、労働者以外の個人事業主や外部委託者に対する保護措置が不十分であると指摘され、厚生労働省はその見直しを進めました。議論を経て、以下の内容が取り入れられました。
- 保護対象の拡大:危険箇所等で作業を行う場合の保護措置について、労働者のみな らず、雇用関係や契約形態を問わず危険箇所等で働く全ての人を対象とすることが義務化されました。
- 一人親方等への周知の義務化:一人親方や下請業者にも、保護具等を使用する必要 がある旨を周知することが義務化されました。
この改正により、事業者は多様な働き方に対応した安全対策を求められるようになりました。ています。
2025年4月から施行される労働安全衛生規則等改正の主な内容
危険箇所での保護対象範囲の拡大
労働安全衛生法に基づく4つの省令(労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則)の改正により、作業を請け負わせる一人親方や下請業者等の「当該作業場で何らかの作業に従事する全ての者」に対して、以下の保護措置を実施することが義務付けられました。
- 労働者に対する危険箇所等への立入禁止・搭乗禁止、立入等が可能な箇所の限定、悪天候時の作業禁止の措置を行う場合には、当該場所で作業を行う労働者以外の者もその対象とすること
- 喫煙等の火気使用が禁止されている場所においては、当該場所にいる労働者以外の者についても火気使用を禁止すること
- 事故発生時等に労働者を退避させる必要があるときは、当該作業場所にいる労働者以外の者も退避させること
なお、「当該作業場で何らかの作業に従事する全ての者」には、当該作業場で何らかの作業を行っていれば、事業者と契約関係のない一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員なども含まれます。
一人親方や外部委託者への周知義務化
危険箇所等で行う作業の一部を請負人(一人親方や下請業者)に行わせる場合には、以下の措置を実施することが義務付けられました。
- 立入禁止とする必要があるような危険箇所等において、例外的に作業を行わせるために労働者に保護具等を使用させる義務がある場合には、請負人に対しても保護具等を使用する必要がある旨を周知すること
なお、危険箇所等で作業を行う場合以外であっても、
- 作業に応じた適切な保護具等を労働者に使用させることが義務付けられている場合
- 特定の作業手順や作業方法によって作業を行わせることが義務付けられている場合
については、請負人に対して、保護具等の使用が必要である旨や、特定の作業手順、作業方法によらなければならない旨を周知することが推奨されています。
追記:労働安全衛生法改正による電子申請の義務化
義務化の対象となる手続き
2025年1月1日から、以下の労働安全衛生関係の一部の手続きの電子申請が義務化されることになります。なお、2024年12月31日以前に発生した労働災害についても、2025年1月1日以降に報告される場合は電子申請による報告が適用されます。
電子申請義務化の対象となる手続き
- 労働者死傷病報告
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告
- 定期健康診断結果報告
- 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)結果等報告
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告
- じん肺健康管理実施状況報告
- 事業の附属寄宿舎内での災害報告
電子申請の方法
電子申請は、e-Gov電子申請のサイト(e-Gov電子申請)、または、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスのサイト(労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス)から手続きを行うことができます。
なお、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(帳票入力支援サービス)」とは、インターネット上で、届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請をすることができるサービスです。このサービスはe-Govに連携して電子申請を行うため、事前にe-GovアカウントまたはGビズIDを取得してログインするか、他認証サービス(MicrosoftやGoogle)のアカウントでログインをする必要があります。
電子申請の詳細については、上記のリンクからご確認ください。
FAQ:改正対応でよくある疑問を解決
上記の2025年改正における事業者の対応について、よくある疑問点をQ&A形式で以下にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
Q1:事業者が保護措置を行う必要がある「当該作業場で何らかの作業に従事する全ての者」には、当該作業場にいる人は全て含まれますか?
A1:「当該作業場で何らかの作業に従事する全ての者」には、契約関係を問わず、当該作業場で何らかの作業を行っている一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員などの者も含まれます。ただし、一般の見学者や単なる通行人等は含まれません。
Q2:危険箇所等における作業を複数の事業者が共同で行っているのですが、この場合には、それぞれの事業者が個別に保護措置を行う必要がありますか?
A2:危険箇所等における作業について、同一の場所で保護措置を行う義務が複数の事業者に課されているようなときは、個々の事業者ごとに保護措置を複数行う必要はなく、元方事業者がまとめて実施するなど、事業者が共同で保護措置を行っても差し支えないとされています。
Q3:一人親方や下請業者への周知は、どのような方法で行ったらよいですか?
A3:周知方法については、
- 常時、作業場所の見やすい場所に掲示または備え付ける
- 書面を交付する(請負契約時に書面で示すことも含む)
- 磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、各作業場所に記録内容を常時確認できる機器を設置する
- 口頭で伝える
のいずれかの方法で行うようにしてください。
周知する内容が複雑な場合には、上記①~③のいずれかの方法で伝えた方が良いと考えられます。
Q4:2025年1月1日から労働者死傷病報告等の手続きの電子申請が義務化されたとのことですが、まだ電子申請ができる環境がありません。どうしたらいいですか?
A4:経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合には書面による報告が可能となっています。
2025年改正を踏まえた安全な職場づくりを進めよう
今回の改正では、事業者が行う保護措置の対象が労働者以外の者に拡大されたり、周知義務が新たに課されています。事業者にとっては、今一度、安全管理体制の見直しや請負人との契約内容の確認や指導・教育を徹底する等、労働災害を未然に防ぐためにしっかりと改正に対応していく必要があります。
今後も改正されていく労働安全衛生法関係法令に対して、改正の内容や対応策を的確に把握して、労働者が安全で快適に働ける職場環境を目指していきましょう。
もしご不安な方は、労働安全衛生法に関する問題が発生する前に、現状の職場環境や安全衛生管理体制について問題がないかどうかを、弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。

執筆者:塩谷 恭平(しおや きょうへい)
弁護士法人シーライトで、労働災害や企業からの労務相談を多数受任。弁護士として事件解決するだけでなく、労働災害や労務問題を起こさないリスクマネジメントの重要性を訴えることで、予防法務にも尽力している。法律的な説明であっても、できるだけ専門用語を使わずにわかりやすく説明を行う姿勢は、多くの企業の方から「わかりやすい」と好評。神奈川県弁護士会所属。 プロフィール:http://cright.jp/lawyer/shioya.php