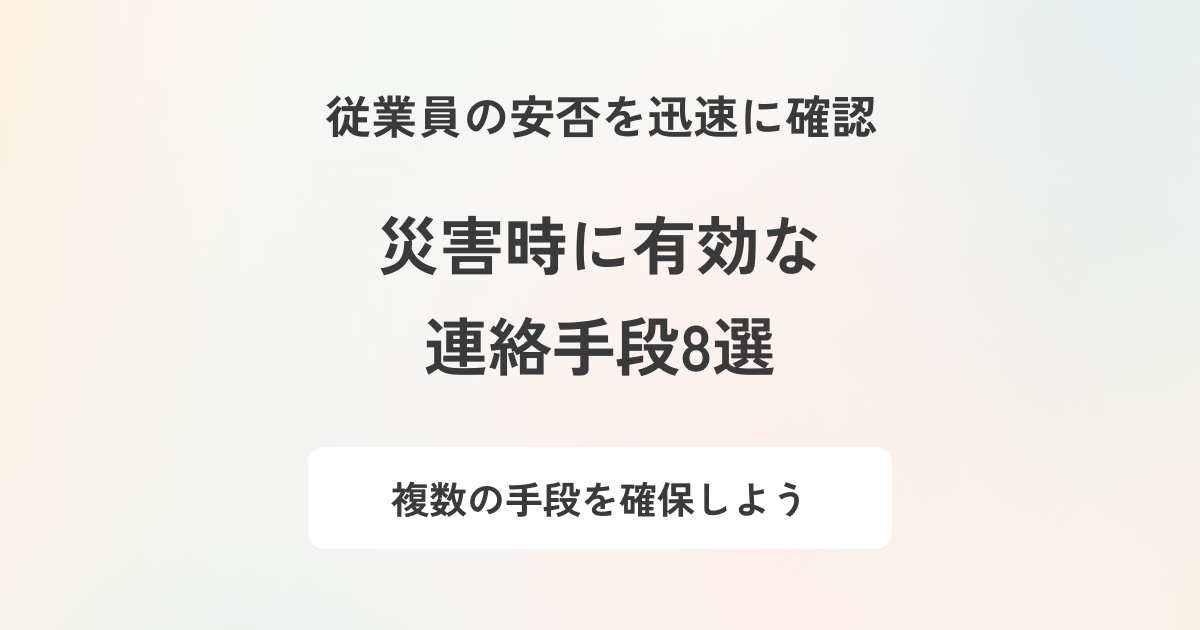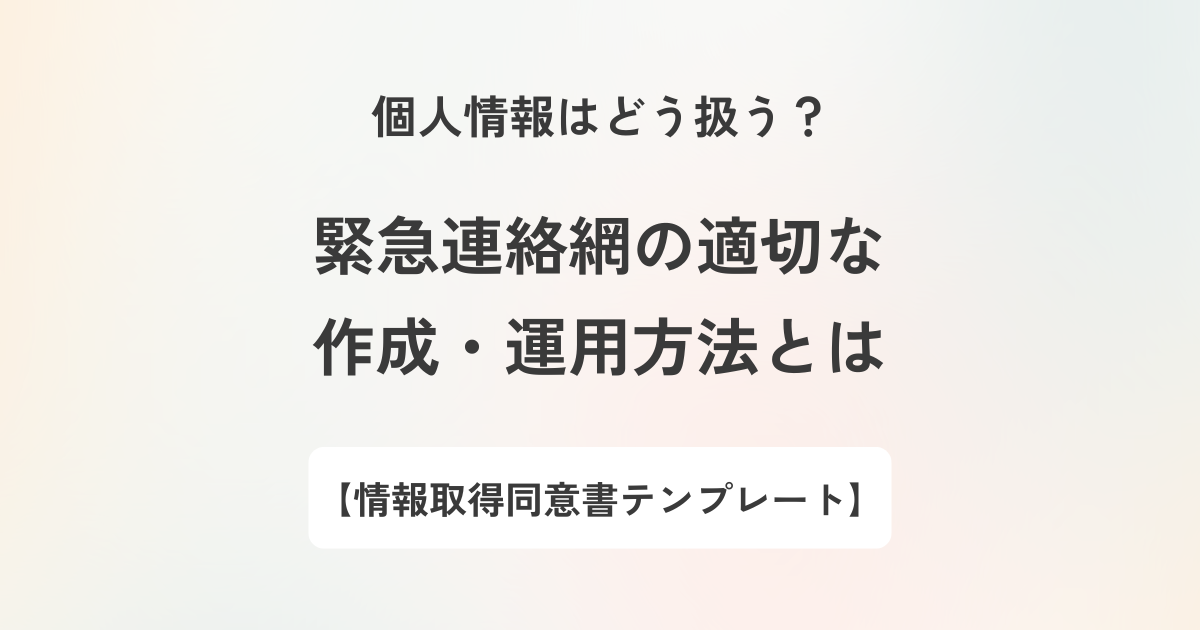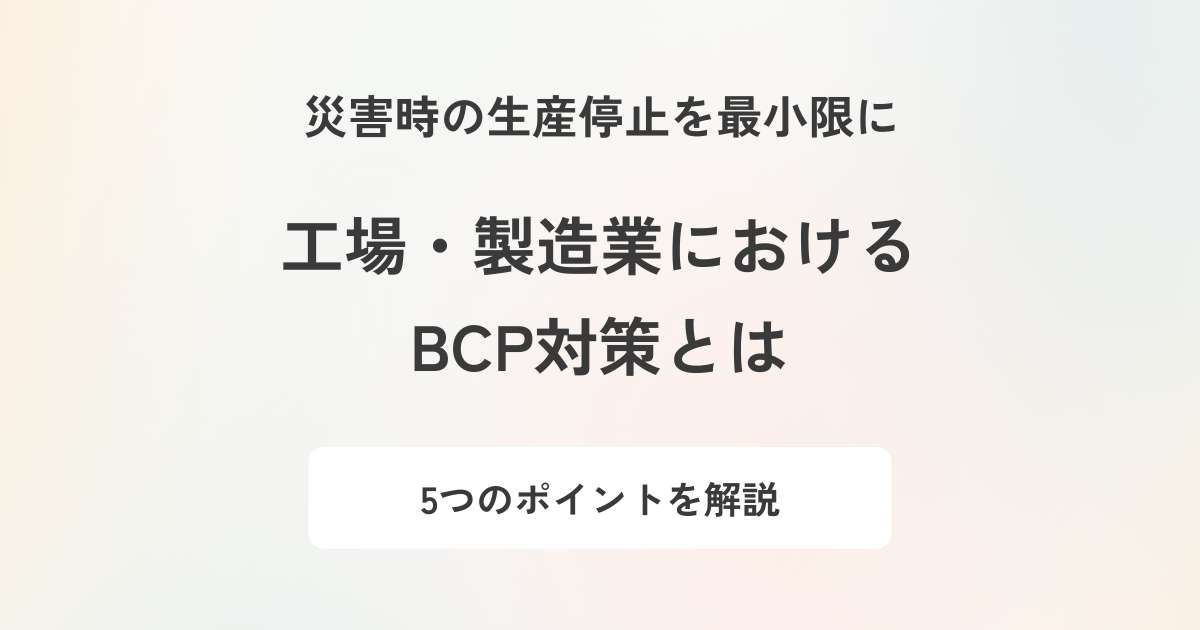訪問看護事業所向けにBCP策定の手順を紹介!未整備のリスクも解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
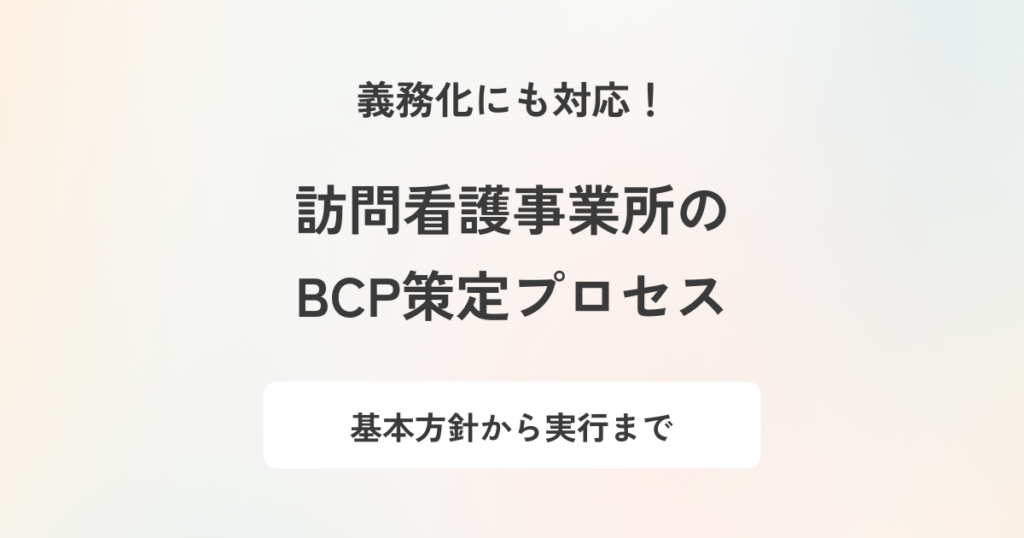
訪問看護事業所には、2024年からBCPの策定が義務付けられています。従業員や利用者の安全確保、訪問看護サービスの継続的な提供には、BCPの策定が欠かせません。
しかし、どのようにBCPを策定するべきなのかわからず、困っているのではないでしょうか?
そこでこの記事では、訪問看護事業所向けにBCPの策定手順や目的を紹介します。BCPの策定に取り組めていない方は、最後までご覧ください。

目次
2024年から訪問看護事業所ではBCP策定が義務化
BCPとは緊急事態が起きた際の被害を軽減し、最短での事業復旧を目指すための業務継続計画です。訪問看護事業所では、大規模自然災害の発生や感染症拡大の影響にともない、2024年4月からBCP策定が義務化されています。
訪問看護事業所は他の業種と比べて、地域の利用者や家族と密接に関わる点が特徴です。利用者は体調や体の機能に不安を抱えており、訪問看護サービスを常に必要としています。
利用者の不安を減らすには予測不可能な事態が発生しても、継続的に訪問看護サービスが利用できる体制を整えなければなりません。
訪問看護事業所を継続的に運営していくためにも、BCPを策定しましょう。
BCPを策定しなかった場合の罰則
2024年度の介護報酬改定にともない、BCPを未策定の事業所に対しては介護報酬が減算されます。
ナーシングホームやケアハウスなど、居住型の看護サービスを提供する事業所の場合、すでに2024年から報酬の減算が適用されています。減算額は所定単位数の3%になります。
ただし、訪問看護や在宅介護サービスなどを提供する事業所に対しては、1年の経過措置が設けられていました。
そのため、BCPが未策定の事業所に対して介護報酬の減算が適用されるのは、2025年の4月からです。BCPが策定できていない訪問看護事業所は、すぐに対応しましょう。
訪問看護事業所がBCPを策定する目的
訪問看護事業所がBCPを策定する理由は、以下3つの目的を達成するためです。
- 事業の継続
- 従業員の安全確保
- 事業所のイメージアップ
BCPを策定しておくと、緊急事態が発生しても従業員の安全を確保でき、最短での事業復旧につなげられるでしょう。
事業の継続
訪問看護事業所に限らず、BCPを策定する最大の目的は事業の継続です。事業を継続するには、自然災害や火事、感染症拡大など、あらゆるリスクに備えておかなければなりません。
加えて訪問看護サービスの利用者は、多くの方が体調面に不安を抱えており、継続的なケアが必要です。
BCPを策定しておくと、緊急事態が発生しても落ち着いて対応できるため、被害の軽減を図れるでしょう。
また、事業再開に必要な作業や手順も記載されており、事業復旧までの期間を短縮できる点もメリットです。
従業員の安全確保
BCPに避難経路や避難場所などを記載しておけば、災害が発生しても従業員の安全を素早く確保できます。
たとえば、新型コロナウイルスやインフルエンザなど、感染症に関する対応策を記載しておくと、感染拡大の抑制も期待できるでしょう。
また、被災後に事業を再開する場合、出勤可能な従業員は、過酷な環境で長時間労働を強いられ、通常よりも大きな負担が生じる可能性が高まります。
訪問看護サービスを継続して提供するには、看護に関する知識や経験が豊富な人材が必要不可欠です。従業員が心身の不調を起こさないよう、メンタルケアや過重労働を防ぐ内容もBCPに盛り込みましょう。
事業所のイメージアップ
BCPの策定はリスクマネジメントの一種として、業種や業界を問わず多くの企業で採用されています。
訪問看護事業所がBCPを策定すると、「あらゆるリスクへ備えている組織」との印象を与えられ、取引先や利用者の家族からの信頼が高まる可能性があります。
緊急事態が発生しても最短での事業復旧が期待できるため、リピート率向上や収益拡大が期待できるでしょう。
訪問看護事業所がBCPを策定する際の手順
以下では、訪問看護事業所がBCPを策定する手順を、9つのステップで解説します。
具体的なステップは、下記のとおりです。
- BCP策定の基本方針と運用体制を整備する
- 事業所を取り巻くリスクを整理する
- 組織の現状把握に努める
- リスク別のシナリオを作成する
- リスク値を算出する
- アクションカードを作成する
- 業務への影響を分析する
- ひな形を使ってBCPを文書化する
- BCPの実行と評価をおこなう
訪問看護事業所がおこなう作業内容を、プロセスごとに確認しましょう。
BCP策定の基本方針と運用体制を整備する
BCPの策定によって、自事業所が達成したい目的を明確にする作業から始めていきます。
たとえば「従業員の安全確保」や「訪問看護サービスの継続」など、具体的な目的を掲げます。
自事業所が重視する価値観や地域の特性を考慮すると、あらゆるリスクを想定したBCPを策定できるでしょう。
目的が明確化されたBCPを策定すると、地域全体の防災意識向上や被害者の減少が期待できます。
BCP策定の目的が固まり次第、BCPの策定や内容の見直し、更新など、計画の内容や進捗状況を管理するチームの整備に移行します。
BCPの運用チームには、訪問看護事業の経営に関する知識やノウハウが豊富な人材を数人入れるのが望ましいです。
また、BCPは基本的にトップダウン方式で運用されるため、BCPを管理するチームには、経営陣の意図を正確に理解し、従業員へ適切に伝えられる人材が必要です。
訪問看護事業の経営に精通した人材がいない場合は所長や主任など、経営層とコミュニケーションが取れる人材を据えましょう。
事業所を取り巻くリスクを整理する
自然災害と感染症、大きく2つに分けてリスクを整理します。主に想定されるリスクを以下の表にまとめました。
| 自然災害 | 感染症 |
| ・地震 ・津波 ・土砂崩れ ・大雨 ・大雪 ・暴風 | ・新型コロナウイルス ・インフルエンザ ・ノロウイルス ・食中毒 |
リスクの整理が終わったら、個々の発生頻度や影響度の大きさを評価します。発生頻度が高く、事業所へのダメージが大きいリスクから優先的に対応策を考えます。
また、対応策を考える際はハザードマップを活用し、避難経路や避難場所を確認しておきましょう。
組織の現状把握に努める
訪問看護事業のリスクを洗い出したら、事業所内の危険な箇所や備蓄品の充実度など、自事業所の防災対策に関して把握しましょう。
厚生労働省が作成した「組織の状況把握チェックリスト」を活用すると、効率的に現状把握が進められます。
チェックリストに記載のある主な確認事項は、下記のとおり。
- 想定されるリスクを把握している
- 災害情報を収集する手段が確立されている
- 従業員や利用者を助ける道具が準備されている
- 最低3日分の食料が事業所内に保管されている
- 簡易トイレを用意している
- マスクや毛布などを用意している
上記に加えて、感染症患者が発生した際の連携医療機関をBCPに記載しておくと、感染拡大を抑えられる確率が高まります。
また、事業所で働く従業員と家族の安全を確保するため、以下の内容も把握しておくことが重要です。
- 従業員一人ひとりの職種
- 従業員の自宅から事業所までの距離
- 徒歩通勤時の所要時間
- 配偶者や子どもの有無
- 緊急時の連絡先および連絡手段
個人情報の開示に抵抗を覚える従業員に配慮し、アンケートや個別面談で上記の内容を確認しましょう。
収集した情報は、被害発生後に出勤可能な人数の算出や事業再開のスケジュール策定などに役立てられます。
リスク別のシナリオを作成する
地震やインフルエンザなどのリスクが発生した場合、自事業所にどのような悪影響を及ぼすか、事前に想定しておくプロセスです。リスク別のシナリオは、以下5つの経営資源ごとに作成します。
- 人
- モノ
- カネ
- ライフライン
- 情報
リスク別のシナリオを作成した例が以下になります。
| 経営資源 | 地震 | 水害 | 火災 | 感染症 |
| 人 | ・訪問看護先で被災する ・交通機関がマヒし、看護先まで移動できない ・従業員の安否が確認できない ・従業員が帰宅できない | ・訪問看護先で被災する ・交通機関がマヒし、看護先まで移動できない ・従業員が帰宅できない | ・訪問看護先で被災する ・事業所が火災した場合、従業員に死傷者が発生する | ・訪問看護先で被災する ・感染症による体調不良で、出勤できない ・複数人が同時に感染した場合、人手不足に陥る ・従業員が帰宅できない |
| モノ | ・事業所が使えない ・車両が壊れ、移動手段を確保できない ・オフィス備品が使えなくなる ・衛生用品が不足する | ・事業所が水浸しになる ・車両が水没し、移動できない ・オフィス備品や看護器具が水没する ・衛生用品が不足する | ・事業所が焼失する ・車両が焼失する ・オフィス備品や看護器具が焼失する ・衛生用品が不足する | ・衛生用品が不足する ・感染症拡大を防ぐ資材が不足する |
| カネ | ・事業停止が長引くほど、収入が減る ・利用者の数やサービスの利用頻度が減る ・従業員の給与が保障できない ・多額の復旧費が必要になる | ・人手不足による減収を招く ・利用者の数やサービスの提供回数が減る ・給料の減額も検討が必要になる ・衛生強化の費用が必要になる | ||
| ライフライン | ・電気が使えない ・水が使えない ・ガスが使えない ・道路が使えない | ・水が使えない ・トイレを自由に使えない ・電気が使えない ・ガスが使えない | ・電気が使えない ・水が使えない ・ガスが使えない | – |
| 情報 | ・電話やメールが使えない ・紙カルテが埋もれる ・電子カルテが閲覧できない ・災害情報を取得できない | ・電話やメールが使えない ・紙カルテが水没する ・電子カルテが閲覧できない ・災害情報を取得できない | ・電話やメールが使えない ・紙カルテが焼失する ・電子カルテが閲覧できない ・災害情報を取得できない | – |
リスク値を算出する
リスク別のシナリオを作成したあとは、影響度と脆弱性の指標を使って、シナリオ別のリスク値を算出してください。リスク値は影響度×脆弱性で算出し、全12段階で評価します。
影響度はシナリオが実際に起きた場合、訪問看護事業所にどの程度ダメージを及ぼすか、評価する指標です。3段階で評価し、評価基準は以下になります。
- ほとんど影響がない
- 事業への影響は発生するが、事業中断には至らない
- 極めて深刻な被害をもたらす
一方、脆弱性とは想定されるシナリオに対して、事業所の防災対策が十分講じられているか、評価する指標です。以下の4段階で評価を下します。
- 十分な対策を講じた上で、定期的に点検もしている
- 十分な対策を講じているが、たまにしか点検していない
- 十分な対策を講じているが、ほとんど点検をしていない
- 対策がほとんど取られていない
仮に地震が発生した場合、経営資源別のリスク値は以下のように算出します。
| 経営資源別 | シナリオ | 影響度 | 脆弱性 | リスク値 |
| 人 | ・従業員が訪問看護先で被災 | 3 | 3 | 9 |
| モノ | ・事業所が使えない | 3 | 4 | 12 |
| カネ | ・多大な復旧費が必要になる | 3 | 2 | 6 |
| ライフライン | ・電力が停止する | 3 | 4 | 12 |
| 情報 | ・電話やメールがつながらない | 3 | 3 | 9 |
リスク値が9点以上だった場合、予防策と災害発生後の対策を検討します。以下に自然災害と感染症発生に備えた対策例を記載しました。
| 経営資源 | 情報 |
| 想定リスク | 地震・水害・火災 |
| リスクシナリオ | 電話やメールがつながらない |
| 現状の課題と対応 | ・緊急連絡網を作成済み ・連絡手段が電話とメールだけとなっており、訪問先で被災した場合、連絡が取れない可能性が高い |
| リスク値 | 9 |
| 予防策や災害発生後の対策 | ・LINEやSNSでの連絡 ・災害伝言板の活用 |
| 期限 | 3月末 |
| 担当者 | 〇〇 |
| 経営資源 | 人 |
| 想定リスク | 感染症 |
| リスクシナリオ | 複数人の従業員が感染症を発症したため、人手不足に陥る |
| 現状の課題と対応 | ・看護経験のある人材を募集中 ・緊急時に連携している看護ステーションから応援を要請済み ・自事業所に近い看護ステーションが少なく、人手不足を解消できるかわからない |
| リスク値 | 9 |
| 予防策や災害発生後の対策 | ・看護学校との連携 ・採用手法の見直し ・営業時間の短縮 |
| 期限 | 4月末 |
| 担当者 | 〇〇、〇〇、〇〇 |
通常業務の運営が優先ですが、対策を後回しにすると決まらない恐れがあるため、担当者と期限を決めておきましょう。
アクションカードを作成する
BCPの内容をもとに、災害発生後に取るべき行動と手順をA4サイズ1枚に簡潔にまとめておきます。
地震など自然災害や感染症はいつ発生するか予測ができず、発生後は素早く安全を確保しなければなりません。
緊急時は一瞬の判断が求められるため、BCPや災害対策マニュアルを時間をかけて確認する時間は取れないでしょう。
また、訪問看護は事業所内と移動中、訪問看護先の3つで被災する可能性があります。自身やスタッフ、利用者さまの安全確保を最優先に行動することを前提に、状況別に応じた行動をアクションカードに記載します。
災害時の不安や被害を軽減するため、アクションカードは自然災害用と新興感染症用など、用途に分けて用意するのがおすすめです。
作成したアクションカードは常にカバンに入れておくよう、従業員に徹底することが重要です。アクションカードを常に携帯しておくと、訪問看護先で被災しても冷静な判断・行動が取れます。
業務への影響を分析する
災害発生がどの程度事業に影響するかを分析するには、まず事業所の平常業務を把握する必要があります。
訪問看護をおこなう上で生じる事務作業や付帯業務を、以下のようにすべてあげます。
- 訪問看護の記録
- 看護器具や設備の管理
- 備品管理
- 注文書や請求書の作成
- 従業員の教育や研修
- 新規人材の採用
- 他事業所との連携
上記に加えて地域の防災活動や看護学生の受け入れをしている場合は、通常業務に含めてください。
通常業務の整理が終わったら、業務を以下の3段階に分けていきます。
- 優先業務:災害後も継続が必要な業務
- 縮小業務:災害後に業務範囲の縮小や内容変更が可能な業務
- 一時休止業務:災害後に業務の一時停止が可能な業務
優先業務はBCPで「中核業務」に位置づけられるため、正確な見極めが必要です。
優先業務に分類する基準は、利用者の命に直結するか、事業所の継続運営に必要かの2点です。上記2つの基準に照らし合わせた場合、体調の悪い利用者宅への訪問看護や看護内容の記録、請求業務など、優先業務は限られるでしょう。
また、縮小業務と一時休止業務の判断基準に関しては、優先業務との関連性の高さがあげられます。たとえば、従業員の育成や地域住民との交流は、緊急時に実施すべき内容ではありません。
一方、ケアプランの確認や訪問看護計画の作成などは、通常時と比べて実施頻度は低くなるものの、訪問看護の継続に必要な作業です。
このような手順で優先業務の整理が完了したら、優先順位にあわせてリソースを分配し、業務上の課題や代替手段の検討を行いましょう。
ひな形を使ってBCPを文書化する
これまでに決めた内容をフォーマットに記載し、BCPとして仕上げる作業です。
BCPの策定には、ひな形(テンプレート)を活用するのがおすすめです。ひな形にはBCPの運用に必要な内容が記載されており、一からフォーマットを作成する必要がありません。
ひな形の入手先には、全国訪問看護事業協会のサイトを活用します。自然災害と新型コロナウイルス用のひな形が用意されており、用途に応じたBCPの策定を効率的に進められます。
BCPの実行と評価をおこなう
BCPは策定して終わりではありません。緊急事態の際に機能するよう、内容の見直しと更新を定期的におこなう必要があります。
BCPに記載した内容がすべて機能するとは限りません。
策定したBCPの有効性を確認するには、自然災害や感染者の発生を想定して実際に訓練を積むことが重要です。
実践を想定した訓練を通して、機能した内容・しなかった内容を評価し、改善に努めます。
評価と改善を繰り返し、BCPの完成度や従業員の防災意識を高めていきましょう。
策定したBCPの強化には安否確認システムの導入が有効
訪問看護所に限らず、策定したBCPの有効性を高めるには、安否確認システムの導入が有効です。
安否確認システムとは、災害発生時に従業員と素早く連絡が取れるシステムです。多くのシステムが、メールやLINE、専用アプリなど、複数の連絡手段に対応しています。
ネットワーク環境の冗長化やデータセンターの分散化など、強固な災害対策も講じられています。そのため、大規模な自然災害が発生しても、訪問看護先や移動中に被災した従業員の安否を素早く確認できるでしょう。
また、掲示板機能が利用可能な安否確認システムを選ぶと、訪問看護事業の再開に向けた準備を進めやすくなります。掲示板は画像や動画での投稿に対応しているケースも多く、短時間で避難場所の被災状況を正確に確認できます。
策定したBCPや感染症対応マニュアルなども掲載できるため、従業員とスムーズな情報共有が期待できるでしょう。
BCP未策定の訪問看護事業所は早めに準備しよう!
すでに2024年から訪問看護事業所にはBCP策定が義務付けられており、未整備の場合はすぐに取り組む必要があります。2025年3月末までにBCPを策定できていない場合、介護報酬の減算が適用されるため、注意しましょう。
また、策定したBCPを機能させるには、安否確認システムの導入がおすすめです。複数の連絡手段に対応しているだけでなく、大規模災害が発生しても従業員の安否確認が期待できるためです。
ただし、はじめて安否確認システムを導入する場合、どのシステムを選ぶべきか、迷う方もいるでしょう。トヨクモの「安否確認サービス2」は、リピート率99.8%を誇る安否確認システムです。
安否確認サービス2は、甲府城南病院や広島共立病院など、医療福祉業界での導入実績も豊富です。
また、安否確認サービス2は気象庁の「地震/津波/特別警報」と連動しています。一定規模の自然災害が発生した際、登録した連絡先に安否確認通知を自動で配信する仕組みです。
通知に記載されたURLをクリックするだけで設問が表示されるため、従業員は訪問看護先で被災しても、自身の無事を素早く伝えられます。
また、安否確認サービス2を導入する際、初期費用や最低利用期間は発生しません。30日間の無料トライアルも用意されており、費用をかけずに機能性を確認できます。
BCPの策定や強化に取り組む訪問看護事業所は、安否確認サービス2の導入をご検討ください。

編集者:遠藤 香大(えんどう こうだい)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部に所属。RMCA認定BCPアドバイザー。2024年、トヨクモ株式会社に入社。『kintone連携サービス』のサポート業務を経て、現在はトヨクモが運営するメディア『トヨクモ防災タイムズ』運営メンバーとして編集・校正業務に携わる。海外での資源開発による災害・健康リスクや、企業のレピュテーションリスクに関する研究経験がある。本メディアでは労働安全衛生法の記事を中心に、BCPに関するさまざまな分野を担当。