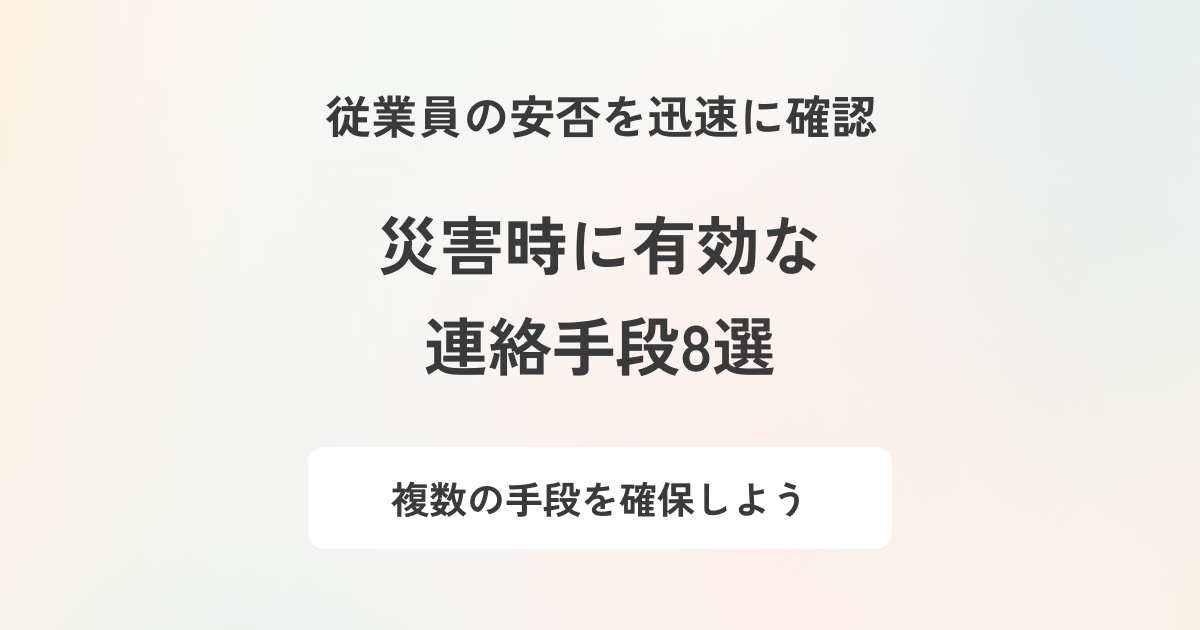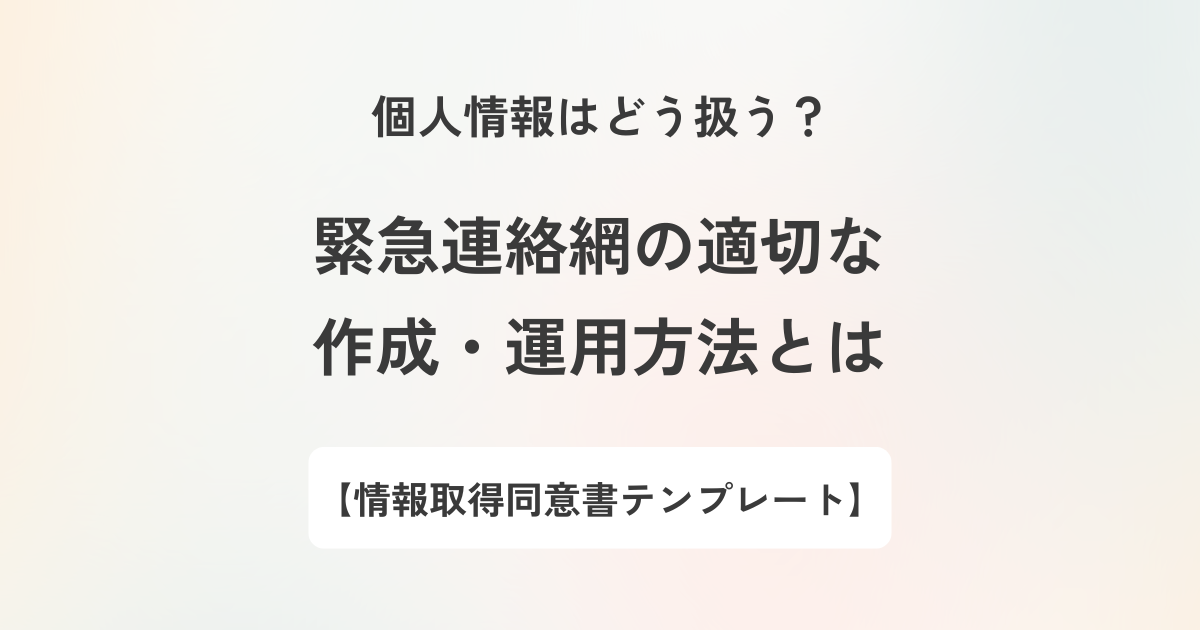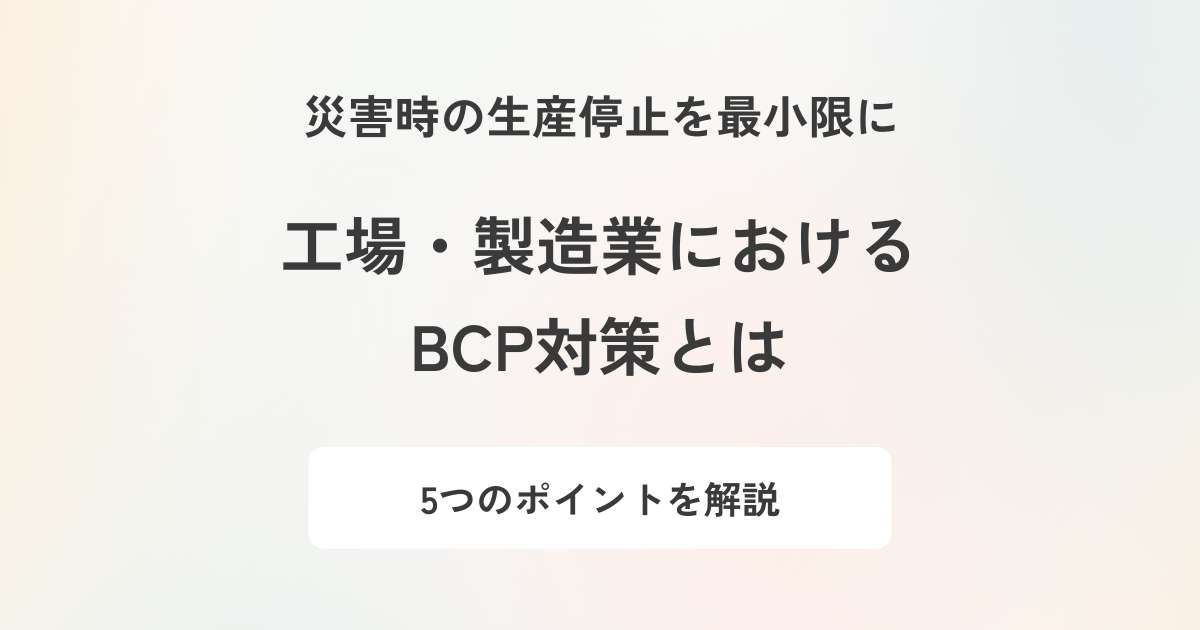「住宅手当」か「借り上げ社宅」住居の福利厚生を選ぶポイント

トヨクモ防災タイムズ編集部

厚生労働省が公表している「平成27年就労条件総合調査」によると、全企業のうち45.8%の企業が、住宅に関する手当を社員へ支給しています。従業員1000人以上の大手企業では59.1%、従業員数30~99人の中小企業でも41.4%が住宅手当を支給しているのが現状です。
現在は住宅手当を支給していなくても、将来的に導入を検討している担当の方も多くいるのではないでしょうか。
この記事では、「住宅手当を支給するメリット」や「社宅との違い」など、住宅手当の導入時に気になるポイントについて詳しく解説します。
参考:平成27年就労条件総合調査結果の概況 住宅手当とは、企業が社員に提供する福利厚生のひとつです。家賃や住宅ローンなど、社員の住宅にかかわる金銭的な負担の軽減を目的としています。
住宅にかかわる福利厚生は、そのほかに「社宅」が挙げられます。「社宅」は企業が所有、もしくは借りている物件を社員に安価で貸し出す福利厚生ですが、「住宅手当」では社員個人の住宅に対して一定額の補助金を出します。
「平成27年就労条件総合調査」によると、全企業の住宅手当平均額は、17,000円/月とされています。企業規模や方針によって支給金額や条件は異なりますが、以下の要素にもとづいて金額を決定することが多いようです。
住宅手当とは、企業が社員に提供する福利厚生のひとつです。家賃や住宅ローンなど、社員の住宅にかかわる金銭的な負担の軽減を目的としています。
住宅にかかわる福利厚生は、そのほかに「社宅」が挙げられます。「社宅」は企業が所有、もしくは借りている物件を社員に安価で貸し出す福利厚生ですが、「住宅手当」では社員個人の住宅に対して一定額の補助金を出します。
「平成27年就労条件総合調査」によると、全企業の住宅手当平均額は、17,000円/月とされています。企業規模や方針によって支給金額や条件は異なりますが、以下の要素にもとづいて金額を決定することが多いようです。 住宅手当を支給するときは、全社員に無条件で支給するのではなく、一定の条件を課すことが多いようです。条件を設定する際にポイントとなるのが、「社員の働きやすさ向上」です。社員をしばるための条件ではなく、会社で働きやすくするための条件を設定しましょう。
住宅手当を導入している企業では、「会社から近い距離での居住」と「会社近距離への引っ越し」に補助金を支給するケースが多いです。住宅手当だけでなく引っ越し費用も負担することで、住宅手当の支給率と福利厚生への満足度向上が見込めます。
大手レシピサイトを運営しているクックパッド株式会社では、月額3万円を上限とする住宅手当を支給しています。住宅手当は、通勤のストレス緩和を目的とする「近距離奨励」の理念にもとづいた福利厚生のため、支給条件は「会社から2キロ圏内に居住していること」です。また、会社から2キロ圏内にはじめて引っ越した場合、20万円が支給される「近距離奨励金」制度もあわせて導入されています。
インターネットメディア運営事業を行う株式会社リブセンスは、住宅手当の支給率を公表しています。リブセンスは、「目黒にあるオフィスから2.5キロ以内の場所に住む正社員」に毎月3万円を支給。公表されているデータによると、この手当を受給している社員の割合は全体の3割程度です。
住宅手当を導入する際は、社員が福利厚生を利用しやすくする仕組みも重要です。「引っ越し補助金」などの制度もあわせて検討してみるとよいでしょう。
住宅手当を支給するときは、全社員に無条件で支給するのではなく、一定の条件を課すことが多いようです。条件を設定する際にポイントとなるのが、「社員の働きやすさ向上」です。社員をしばるための条件ではなく、会社で働きやすくするための条件を設定しましょう。
住宅手当を導入している企業では、「会社から近い距離での居住」と「会社近距離への引っ越し」に補助金を支給するケースが多いです。住宅手当だけでなく引っ越し費用も負担することで、住宅手当の支給率と福利厚生への満足度向上が見込めます。
大手レシピサイトを運営しているクックパッド株式会社では、月額3万円を上限とする住宅手当を支給しています。住宅手当は、通勤のストレス緩和を目的とする「近距離奨励」の理念にもとづいた福利厚生のため、支給条件は「会社から2キロ圏内に居住していること」です。また、会社から2キロ圏内にはじめて引っ越した場合、20万円が支給される「近距離奨励金」制度もあわせて導入されています。
インターネットメディア運営事業を行う株式会社リブセンスは、住宅手当の支給率を公表しています。リブセンスは、「目黒にあるオフィスから2.5キロ以内の場所に住む正社員」に毎月3万円を支給。公表されているデータによると、この手当を受給している社員の割合は全体の3割程度です。
住宅手当を導入する際は、社員が福利厚生を利用しやすくする仕組みも重要です。「引っ越し補助金」などの制度もあわせて検討してみるとよいでしょう。 住宅にかかわる福利構成の代表例が「社宅」です。福利厚生を選ぶ際に、「住宅手当」と「社宅」のどちらを導入すればよいか迷う方もいるかもしれません。それぞれの制度にどんな違いがあるのか解説します。
住宅にかかわる福利構成の代表例が「社宅」です。福利厚生を選ぶ際に、「住宅手当」と「社宅」のどちらを導入すればよいか迷う方もいるかもしれません。それぞれの制度にどんな違いがあるのか解説します。
目次
社員の住宅費用を補助する「住宅手当」
 住宅手当とは、企業が社員に提供する福利厚生のひとつです。家賃や住宅ローンなど、社員の住宅にかかわる金銭的な負担の軽減を目的としています。
住宅にかかわる福利厚生は、そのほかに「社宅」が挙げられます。「社宅」は企業が所有、もしくは借りている物件を社員に安価で貸し出す福利厚生ですが、「住宅手当」では社員個人の住宅に対して一定額の補助金を出します。
「平成27年就労条件総合調査」によると、全企業の住宅手当平均額は、17,000円/月とされています。企業規模や方針によって支給金額や条件は異なりますが、以下の要素にもとづいて金額を決定することが多いようです。
住宅手当とは、企業が社員に提供する福利厚生のひとつです。家賃や住宅ローンなど、社員の住宅にかかわる金銭的な負担の軽減を目的としています。
住宅にかかわる福利厚生は、そのほかに「社宅」が挙げられます。「社宅」は企業が所有、もしくは借りている物件を社員に安価で貸し出す福利厚生ですが、「住宅手当」では社員個人の住宅に対して一定額の補助金を出します。
「平成27年就労条件総合調査」によると、全企業の住宅手当平均額は、17,000円/月とされています。企業規模や方針によって支給金額や条件は異なりますが、以下の要素にもとづいて金額を決定することが多いようです。- 扶養人数や家族構成
- 雇用形態
- 勤務地
- 賃貸か持ち家か
住宅手当導入にあたって知っておきたいポイント
 住宅手当を支給するときは、全社員に無条件で支給するのではなく、一定の条件を課すことが多いようです。条件を設定する際にポイントとなるのが、「社員の働きやすさ向上」です。社員をしばるための条件ではなく、会社で働きやすくするための条件を設定しましょう。
住宅手当を導入している企業では、「会社から近い距離での居住」と「会社近距離への引っ越し」に補助金を支給するケースが多いです。住宅手当だけでなく引っ越し費用も負担することで、住宅手当の支給率と福利厚生への満足度向上が見込めます。
大手レシピサイトを運営しているクックパッド株式会社では、月額3万円を上限とする住宅手当を支給しています。住宅手当は、通勤のストレス緩和を目的とする「近距離奨励」の理念にもとづいた福利厚生のため、支給条件は「会社から2キロ圏内に居住していること」です。また、会社から2キロ圏内にはじめて引っ越した場合、20万円が支給される「近距離奨励金」制度もあわせて導入されています。
インターネットメディア運営事業を行う株式会社リブセンスは、住宅手当の支給率を公表しています。リブセンスは、「目黒にあるオフィスから2.5キロ以内の場所に住む正社員」に毎月3万円を支給。公表されているデータによると、この手当を受給している社員の割合は全体の3割程度です。
住宅手当を導入する際は、社員が福利厚生を利用しやすくする仕組みも重要です。「引っ越し補助金」などの制度もあわせて検討してみるとよいでしょう。
住宅手当を支給するときは、全社員に無条件で支給するのではなく、一定の条件を課すことが多いようです。条件を設定する際にポイントとなるのが、「社員の働きやすさ向上」です。社員をしばるための条件ではなく、会社で働きやすくするための条件を設定しましょう。
住宅手当を導入している企業では、「会社から近い距離での居住」と「会社近距離への引っ越し」に補助金を支給するケースが多いです。住宅手当だけでなく引っ越し費用も負担することで、住宅手当の支給率と福利厚生への満足度向上が見込めます。
大手レシピサイトを運営しているクックパッド株式会社では、月額3万円を上限とする住宅手当を支給しています。住宅手当は、通勤のストレス緩和を目的とする「近距離奨励」の理念にもとづいた福利厚生のため、支給条件は「会社から2キロ圏内に居住していること」です。また、会社から2キロ圏内にはじめて引っ越した場合、20万円が支給される「近距離奨励金」制度もあわせて導入されています。
インターネットメディア運営事業を行う株式会社リブセンスは、住宅手当の支給率を公表しています。リブセンスは、「目黒にあるオフィスから2.5キロ以内の場所に住む正社員」に毎月3万円を支給。公表されているデータによると、この手当を受給している社員の割合は全体の3割程度です。
住宅手当を導入する際は、社員が福利厚生を利用しやすくする仕組みも重要です。「引っ越し補助金」などの制度もあわせて検討してみるとよいでしょう。住宅手当と社宅の比較
 住宅にかかわる福利構成の代表例が「社宅」です。福利厚生を選ぶ際に、「住宅手当」と「社宅」のどちらを導入すればよいか迷う方もいるかもしれません。それぞれの制度にどんな違いがあるのか解説します。
住宅にかかわる福利構成の代表例が「社宅」です。福利厚生を選ぶ際に、「住宅手当」と「社宅」のどちらを導入すればよいか迷う方もいるかもしれません。それぞれの制度にどんな違いがあるのか解説します。