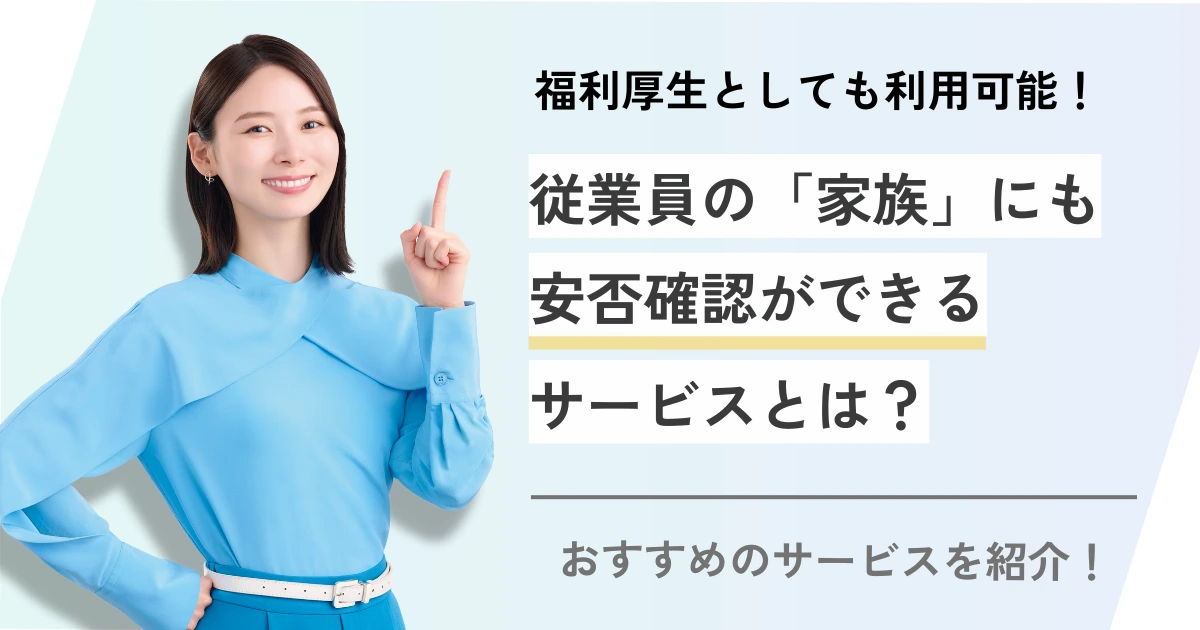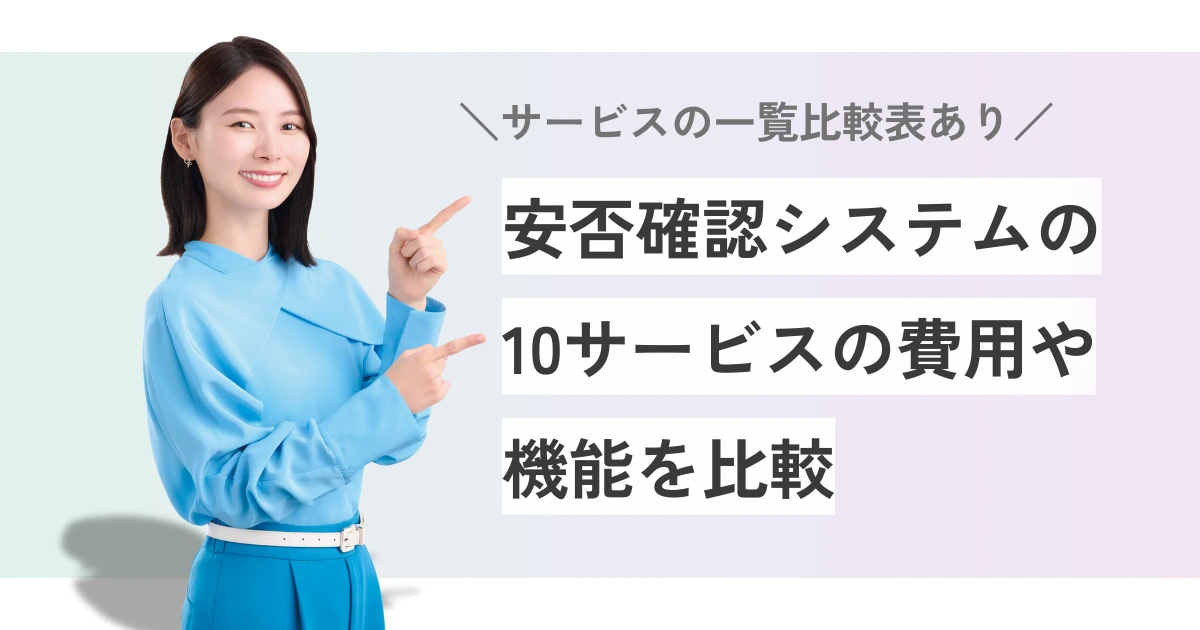BCP対策とは?目的やメリット、策定手順をわかりやすく解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
自然災害や大規模なサイバー攻撃など、企業が備えるべきリスクは近年ますます増加しています。突発的なトラブルが発生した場合でも事業を継続するためには、どのような対応が求められるのでしょうか。
緊急時の対策のひとつとして挙げられるのが、BCP対策です。
この記事では、BCP対策の概要やその目的、メリット、具体的な策定手順などをわかりやすく解説します。BCP対策を通じて、緊急事態に備えられる強固な企業を作りましょう。

目次
BCP対策とは?
BCP対策(Business Continuity Plan)とは、企業が自然災害や感染症などの緊急事態に備え、事業の継続と早期復旧を図るための計画のことです。
リスクマネジメントの一環として、事業資産の損害を最小限に抑えながら、できるだけ早く通常業務を再開することが目的です。
BCP対策には、緊急時の対応だけでなく、事前に行うべき準備やBCP訓練も含まれます。平常時から従業員に対して研修を実施し、適切な対応が取れるよう備えておくことが、効果的なBCPの実現につながります。
業種別のBCP策定ポイントや事例を確認したい方は、下記の記事も参考にしてください。
BCPと災害対策マニュアルの違い
BCP(事業継続計画)と災害対策マニュアルは、それぞれ異なる役割を持ちます。
BCPは、災害発生後も可能な限り事業を継続し、早期復旧を目指すための計画です。一方、災害対策マニュアルは、災害時の具体的な対応手順をまとめたものです。
たとえば地震が発生した場合、BCPは重要業務の継続方法や復旧スケジュールの策定を目的とします。一方、災害対策マニュアルは、従業員の避難経路や初期対応など、安全確保と初動対応に重点を置いています。
両者を適切に整備し、連携させることで、災害発生時の企業の対応力を高められるでしょう。
BCM(事業継続マネジメント)との違い
BCM(事業継続マネジメント)は、組織の事業継続能力を管理・向上させるための体系的な仕組みのことです。主に「計画・実行・確認・改善」のプロセスを踏んで運用されます。
BCPは、BCMの「計画」の一種で、非常時にどのように対応するかを具体的に策定したものです。
BCMは、BCPを含む事業継続の運用管理プロセスであり、いずれも「緊急時に事業を停止させない」という目的は共通しています。適切なBCMの運用により、企業のリスク対応力を強化することが可能です。
BCMについてより理解を深めたい方は、下記記事もあわせてご参照ください。
【対談記事】BCMとは?取り組むメリットや各プロセスを解説|福岡氏と防災士・坂田との対談から学ぶ
BCP対策の必要性と目的
インターネットの普及により、企業は自然災害だけでなく、サイバー攻撃やシステム障害、情報漏洩といったリスクにも直面しています。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大や大規模地震の頻発など、世界的な影響によって事業継続が困難になるケースも増えています。
こうした時代背景を踏まえ、企業が利益を守り、従業員の安全を確保するためには、リスクマネジメントが重要です。
その一環として、2012年5月にISO-22301「事業継続マネジメントシステム・要求事項」が発行され、BCPの考え方や対策が国際的に標準化されました。企業はこれらの指針を活用した、適切な対策が求められています。
BCP対策を導入するメリット
BCP対策の概要や必要性が見えてきたところで、具体的にどのようなメリットがあるのかを確認しましょう。ここでは、BCP対策のメリットについて、下記の3つを解説します。
- 緊急時でも事業継続が可能な体制を整えられる
- 優先すべき業務を明確化できる
- 企業のイメージアップにつながる
メリットを知ることで、BCP対策を導入するきっかけにしましょう。
メリット1. 緊急時でも事業継続が可能な体制を整えられる
BCP対策を適切に実施することで、緊急事態が発生しても事業を継続できる体制が整うことが大きなメリットです。事業の維持や早期復旧が可能となり、取引先や顧客の信頼を損なうリスクを最小限に抑えられます。
また、経営へのダメージを軽減できるため、従業員の解雇や事業の縮小、さらには廃業といった最悪の事態を回避しやすくなります。
BCP対策は企業の安定経営を支える重要な要素です。緊急時にも迅速かつ適切に対応できるよう、日頃から計画を見直し、実効性を高めることが求められます。
メリット2. 優先すべき業務を明確化できる
BCP対策は、緊急時に優先すべき業務を明確にできる点がメリットです。
緊急事態が発生した場合、すべての業務を通常どおり進めるのは困難なことが予想されます。そのため、事前に重要度を整理し、優先順位を決めておくことが重要です。
BCP対策を実施することで、組織体制や業務フローの中でリスクとなる要因を把握しやすくなります。これまで見落とされていた業務の重要性が再認識されることもあり、企業全体の業務改善にもつながるでしょう。
メリット3. 企業のイメージアップにつながる
緊急時に迅速な業務復旧が可能であれば、企業のイメージアップにもつながります。BCP対策を適切に実施していることは、企業の安定性や責任感を示す重要な要素です。
これにより取引先や株主、従業員、地域社会など、さまざまなステークホルダーからの信頼を得られるようになるでしょう。
さらにBCPを策定することで、災害時の環境汚染など二次被害の防止や、地域の雇用維持、経済の安定にも貢献できます。社会的責任を果たすうえでも、BCP対策は欠かせません。
BCP対策のデメリット・注意点
メリットがある一方で、BCP対策により発生するデメリットもいくつか存在します。あらかじめBCP対策のデメリットを把握しておくことで、どのような点に注意すればいいのかがわかります。
BCP対策において注意すべき点は、下記の3点です。
- 机上の空論になる可能性がある
- コストがかかる
- 社内に浸透するまでに時間がかかる
とくに、BCP対策のための費用や時間などを確保する必要がある点には注意しましょう。
デメリット1. 机上の空論になる可能性がある
BCP対策を策定しても、実現可能性が低ければ形だけの計画になりかねません。緊急時に活用できなければ、BCP対策にかけた費用や時間が無駄になってしまいます。
BCP対策では、実際の業務に即した現実的な計画を立てることが必要です。企業の経営状況や外部環境の変化に応じて、定期的に見直し、適宜更新するとよいでしょう。
またBCPの有効性を高めるためには、定期的な訓練の実施が欠かせません。できるだけ実際の緊急事態に近い条件で訓練し、BCPの実効性を検証しながら改善を続けることでデメリットを軽減できます。
デメリット2. コストがかかる
BCP対策には、費用や人材確保、時間など多くのコストが発生します。そのため、リスクの重要度と対策にかかるコストのバランスを考慮し、必要な対策を見極めることが重要です。
まずは、従業員向けの教育やマニュアルの整備など、低コストで始められる対策から進めるのが効果的です。すべてを一度に実施するのではなく、優先順位をつけ、段階的に取り組むことで、効率的かつ実現可能なBCP対策を進められます。
デメリット3. 社内に浸透するまでに時間がかかる
BCP対策は、従業員に正確に伝わらなければ、緊急時にスムーズな対応ができません。そのため、会社の組織文化にBCPの重要性を定着させる工夫が求められます。
単なるトップダウン型の指示ではなく、従業員と協力しながら取り組み、組織全体の理解を深めるとよいでしょう。BCPを日常の業務に組み込み、従業員が自然と事業継続性を意識できるような仕組みを取ることが効果的です。
従業員の理解と主体的な協力が、BCP対策の成功に不可欠な要素となります。
BCP対策の策定手順を具体例付きで解説
具体的にBCP対策を策定するためには、どのような段階を踏めばよいのでしょうか。ここからは、下記の4ステップに分けてBCP対策の策定手順を解説します。
- 方針や目的を決める
- 想定されるリスクの洗い出し
- 分析したリスクをもとに対策を立てる
- BCP対策を文章に落とし込む
BCP訓練を実際に進める際に、どのような点に注意したらよいのか気になる方も多いでしょう。BCP訓練の進め方や成功のポイントを知りたい方は、下記記事もあわせてご確認ください。
【専門家が解説】BCP訓練とは?実際の進め方や成功させるポイント、事例を解説
1. 方針や目的を決める
まずは経営者が中心となり、BCPを策定する方針や目的を決めましょう。方針を決定する際には、自社の事業環境や社会的な責任をしっかり理解し、それにもとづいた目標を設定することが重要です。
業界ごとに方針や目的の具体例は、下記のとおりです。
- 製造業…供給網の途絶を最小限に抑え、生産を早期に復旧させる
- 医療・介護業界…緊急時でも患者・利用者の安全を最優先する
- 小売業…災害時に地域のライフラインとしての機能を維持する
BCP策定やBCM推進の目的を明確にしつつ、組織全体で共有することが成功の鍵となります。
方針や目的が決まった後は、BCPを実行するための組織体制を整えましょう。マネジメント能力やBCMに精通したメンバーを集め、部門横断的なプロジェクトチームを構築することが効果的です。
2. 想定されるリスクの洗い出し
BCPの方針が明確になった後は、想定されるリスクを洗い出しましょう。リスクを洗い出す際には「事業影響度分析(BIA)」と「リスク分析(アセスメント)」を活用するのがおすすめです。
事業影響度分析では、事業が停止した場合の影響を時系列で評価します。これにより、事業継続において優先すべき業務が明確になるのが特徴です。
一方でリスク分析では、リスクの影響度や発生頻度などを詳細に分析します。経営資源へのダメージを予想することで、リスクの優先順位をつける「リスクマッピング」が可能になります。リスクマッピングにより、どの事業や対策に注力すべきかを判断するための工程です。
たとえば、小売業の場合、災害によりクレジットカードや電子マネーなどのオンライン決済システムが使えなくなるリスクが想定されます。
3. 分析したリスクをもとに対策を立てる
続いて、想定したリスクをもとに、目標復旧時間や復旧レベルを設定し、それを達成するための具体的な対策を立てます。
たとえば「地震により〇〇設備が使用できない」といった具体的なダメージを想定することで、効果的な対策が見つかるでしょう。企業の中枢機能を維持しながら、サービスを継続するため、早期復旧を実施することが重要です。
物流業の場合、主な配送センターが災害で使用できなくなるおそれがあります。対策として、いくつか代替ルートを確保したり、提携先倉庫との協力体制を整えたりするのがおすすめです。
また、情報システムの維持も事業継続に不可欠な要素となります。適切な対策を講じることで、緊急時においても安定した業務運営が可能になるでしょう。
4. BCP対策を文章に落とし込む
最後に、これまでの分析結果を整理し、BCP対策の計画を文書化します。記載する内容は、緊急時の連絡手段や対応手順、事前対策、教育・訓練のスケジュール、見直し・改善計画などが一般的です。
このとき、緊急時の「初動対応」と、その後の「事業継続(復旧)」を分けて考えるとスムーズに文章に落とし込めます。たとえば、医療機関では停電時に生命維持装置を安定稼働させるため、非常用電源の使用手順をマニュアル化しておくと良いでしょう。
文書化することで、社内の各部署に容易に周知でき、社員全員が対応方法を理解しやすくなります。
BCP対策ならトヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』がおすすめ
BCP対策には一定のコストがかかるため、必要に応じて外部サービスの活用を検討することも有効です。
BCP策定に必要な時間や人材、費用を確保できない企業におすすめなのが、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』です。BCP策定支援サービスを活用すれば、最短1ヶ月程度でBCPの策定が完了します。
とくに、BCP策定の実績がある専門家に任せたい場合や、知見をもつ人が社内にいない場合には、外部サービスを取り入れることで、スムーズに計画を進められます。
自社で効果的なBCP対策ができるかどうか不安なときは、ぜひ上手に取り入れてみてください。
BCP対策は企業のリスク管理において重要!
BCP対策は、さまざまな問題から企業を守るうえで大切なものです。自然災害や感染症などの緊急時に、事業資産の損害を最小限に抑えつつ、事業の継続と早期復旧を目指せるように、平常時から備えましょう。
企業のリスクマネジメントの一環として、想定されるリスクを洗い出し、適切な対応策を文章としてまとめておくことも重要です。文書化することで、社内全体に対策を周知しやすくなり、緊急時にも迅速で効果的な対応が可能になります。
BCP対策を自社で実施するのが不安な方は、外部のサービスもご活用ください。