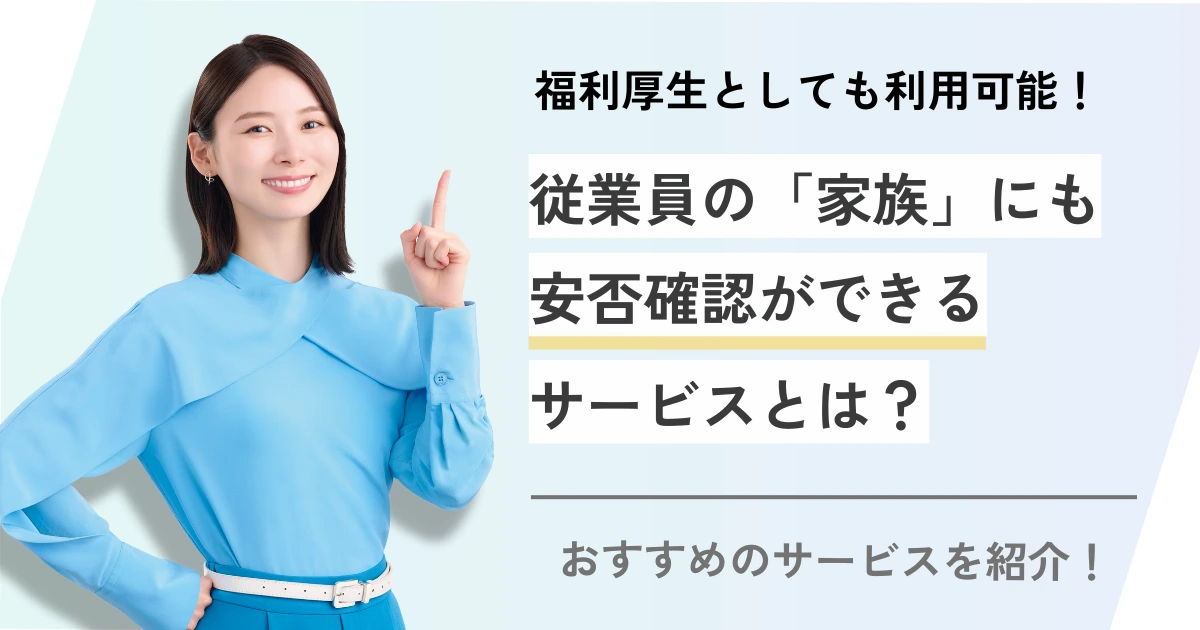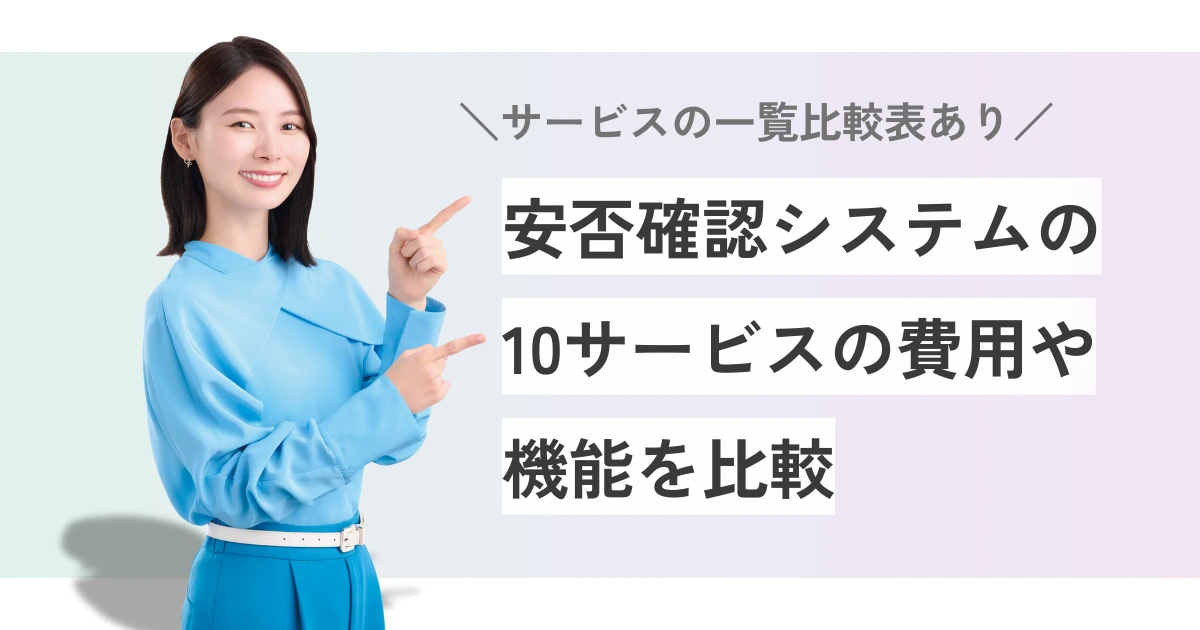BCP担当者がまずやるべきこととは?BCP策定ステップと必要スキルを解説

トヨクモ防災タイムズ編集部
企業のBCP(事業継続計画)とは、自然災害や感染症パンデミックなど、予期せぬ危機が発生した際に、事業の中断を最小限に抑え迅速な復旧を可能にするための生命線です。このBCPの策定および運用において、中心的な役割を担うのが「BCP担当者」となります。
本記事では、新たにBCP担当者となった方や、既存のBCPを見直したいと考えている方に向けて、BCP担当者の具体的な役割と責任、着任後にまず取り組むべきこと、BCP策定の基本的な6つのステップなどをまとめました。また、担当者に求められる重要なスキルについて、網羅的かつ分かりやすく解説します。
BCP担当者として企業のレジリエンス(強靭性)を高め、持続的な事業運営に貢献するための知識と実践的なノウハウを身につけましょう。

目次
BCP(事業継続計画)とは
BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害や感染症、テロなどの緊急事態に遭遇した際、事業を継続または早期復旧するための計画です。BCPの目的には、従業員の安全確保や顧客への製品・サービス提供の維持だけでなく、企業の社会的責任の遂行なども含まれています。
近年では、自然災害の増加や感染症の流行により、BCPの重要性は高まっています。BCPは、企業の持続的な成長と社会への貢献を支える重要な経営戦略の1つです。担当者は、BCPの目的と重要性を深く理解し、実効性のある計画策定と運用を推進していく必要があります。
BCP担当者が最初にやるべきこと
BCP担当者が最初にやるべきことは、主に以下の3つです。
- 自社の体制を確認する
- 平常時の活動を把握する
- 準備を整える
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自社の体制を確認する
新たにBCP担当者に専任されたのであれば、まずは自社の体制を確認しましょう。具体的には、組織図や役員、従業員の連絡先、事業拠点や情報システム、顧客情報などを把握することが挙げられます。これらの情報はBCP策定の基礎となるため、必ず確認してください。
とくに、緊急時の連絡体制や意思決定プロセスは、迅速な対応を可能にするために重要です。自社の事業内容や特性を理解し、どのようなリスクが事業に影響を与える可能性があるかを把握する必要もあります。得た情報は共有し、BCP策定につなげましょう。
平常時の活動を把握する
BCP担当者が最初にやるべきことの1つに、平常時の活動把握があります。具体的には、各部門の業務内容や業務フロー、使用している設備・システム、依存している外部リソースなどを詳細に把握しましょう。普段の業務の流れを把握することによって、緊急時にどの業務を優先的に継続・復旧させるべきか、どのような資源が必要になるかどうかを判断できます。
また、業務の優先順位や代替手段を検討する上でも、平常時の活動把握は重要なポイントとなります。
準備を整える
情報収集においては、過去の災害事例や業界のBCP事例、政府や自治体のガイドラインなどを参考にしましょう。情報を集め、BCP策定・運用の準備を整えることも大切です。これまでの内容を元に、BCP策定に必要な情報収集や関係者との連携、スケジュール管理やリソースの確保などを行います。
関係者との連携では、経営層や各部門の責任者、従業員などとコミュニケーションを取り、BCP策定への理解と協力を得ることが求められます。スケジュール管理では、BCP策定の期限や各ステップの目標を設定し、進捗状況を把握しましょう。予算確保では、BCP策定・運用に必要な費用を見積もり、経営層に説明します。
BCP策定の基本ステップ
BCP策定の基本ステップは、以下のとおりです。
- 基本方針の策定
- 中核事業の特定
- リスクアセスメント
- リスクごとの影響を整理
- 具体的な対策の策定
- 訓練・改定
各ステップの内容をしっかり把握し、効率よくBCPを策定しましょう。
基本方針の策定
BCP策定の出発点となる基本方針を決める際は、まず目的を明確にします。何のためにBCPを策定するのか、具体的な目標を立てましょう。従業員の命を守る、クライアントからの信頼を得るなどの目的が挙げられます。
基本方針は、BCP策定プロジェクトの指針となり、関係者全員が共通認識を持つための基盤となります。定期的な見直しを行い、社会情勢や経営環境の変化に対応できるようにしておく必要があるでしょう。
中核事業の特定
中核事業の特定とは、緊急時において優先的に継続・復旧すべき事業を明確にすることです。顧客や利害関係者への影響を最小限に抑えるために、不可欠なプロセスとなります。
中核事業の特定では、売上高・利益率・顧客への影響度、事業の継続が社会的に果たす役割など、複数の観点から事業を評価しましょう。また、緊急時における事業継続の可否や、代替手段の有無なども考慮に入れる必要があります。
中核事業にも優先順位を付け、取り巻くリスクを評価しながら対策を立ててください。
リスクアセスメント
リスクアセスメントは、企業が直面する可能性があるリスクを特定し、発生確率や影響度を評価することを指します。自然災害や感染症だけでなく、システム障害、情報漏えいなど、あらゆるリスクを洗い出して分析しましょう。
リスクの重要度を客観的に評価するためには、過去の事例や統計データ、専門家の意見などを活用するのがおすすめです。リスクアセスメントの結果は、BCPにおける各対策の優先順位付けや資源配分に役立てられます。ただし、起こり得るリスクは常に変化するため、定期的な見直しも必要です。
リスクごとの影響を整理
リスクごとの影響を整理する目的は、各リスクが事業に与える具体的な影響を明確にすることです。事業停止による損失、復旧に必要な資源、目標復旧時間などを詳細に分析します。リスクごとに影響を整理することによって、優先的に対応すべきリスクや事業を特定できます。
また、リスクごとの影響を定量的に評価すれば、BCP対策の費用対効果を判断しやすくなります。リスクごとの影響を整理する際には、事業影響度分析(BIA)などの手法を活用し、客観的なデータに基づいて分析することが重要です。
具体的な対策の策定
具体的な対策の策定では、リスクごとに事業継続のための対策をできるだけ具体的に検討しましょう。安否確認システムの導入や代替オフィスの確保、データのバックアップと復旧、従業員の訓練などが具体的な対策の例として挙げられます。対策は、企業の事業内容やリスク特性に合わせて、適切に組み合わせることが重要です。
また、対策の実行可能性や費用対効果を考慮し、現実的な計画を策定する必要があります。具体的な対策は文書などに分かりやすくまとめ、関係者全員が理解して実行できるようにしておくことも重要なポイントです。
訓練・改定
BCPは、策定して終わりではありません。定期的な訓練と改定を通じて、その実効性を維持・向上させることが必要です。訓練では、BCP発動時の行動手順や関係者間の連携を確認し、課題や改善点を見つけます。訓練の結果を踏まえて対策の内容を改定し、より実効性の高い計画へと更新しましょう。
また、社会情勢や企業の事業内容の変化に合わせてBCPを定期的に見直し、最新の情報に更新することも重要です。BCPの訓練・改定は、継続的なプロセスであり、企業の事業継続能力を高めるために不可欠となります。
優秀なBCP担当者が持つスキル
優秀なBCP担当者が持つスキルとしては、以下のようなものが挙げられます。
- リスクに対する高い感度と分析力
- 関係者との円滑なコミュニケーション能力
- 多様な知識と柔軟な思考力
- リーダーシップと実行力
- 継続的な学習意欲と改善意識
リスクに対して高い感度を持ち、正確に分析し、適切な対策を講じる能力が求められます。また、BCPの策定後は各所とコミュニケーションを取り、連携性を高めていく必要があります。コミュニケーション能力に加え、多彩な知識や柔軟な思考力も求められます。
そのほかにも、リーダーシップと実行力も必要です。BCPは定期的な見直しなども必要になるため、常に新たな情報を仕入れ、継続的な改善をしていける能力も求められます。これらの能力があるBCP担当者は、企業にとって大きな成果をもたらすはずです。
ただし、最初からすべて完璧に備わっている必要はありません。担当者としての経験を積みながら、意識的に学習・向上させていくことが大切です。
BCP担当者として企業を守ろう
BCP担当者は、リスク分析から計画策定、訓練実施、継続的な改善まで、多岐にわたる業務を通じて、文字どおり企業の存続と成長を支える重要な役割を担っています。その責任は大きいが、同時に大きなやりがいのある仕事です。
BCP策定・運用には、専門知識や多くの関係者の協力が必要であり、時間と労力がかかる取り組みです。もし、「限られたリソースで効率的に進めたい」「何から始めていいか分からない」と悩んでいるなら、専門的な支援サービスの活用も有効な手段となります。
たとえば、トヨクモが提供する『BCP策定支援サービス(ライト版)』は、BCP策定の各ステップを専門家がサポートし、企業の状況に合わせた実効性のある計画策定を支援するサービスです。1ヶ月15万円(税別)からと費用もリーズナブルで、コストを抑えながら専門家の知見を活用したい企業にとって、有力な選択肢のひとつになります。
この記事を参考に、BCP担当者としての第一歩を踏み出し、ぜひ企業の危機対応能力強化に貢献してください。