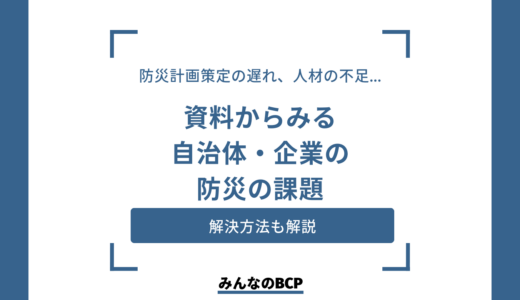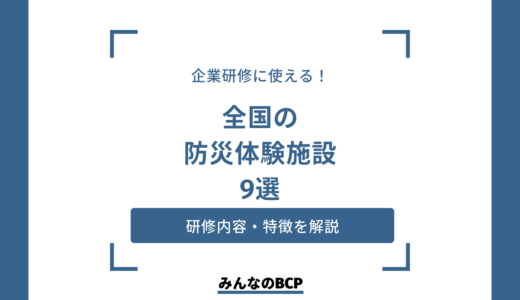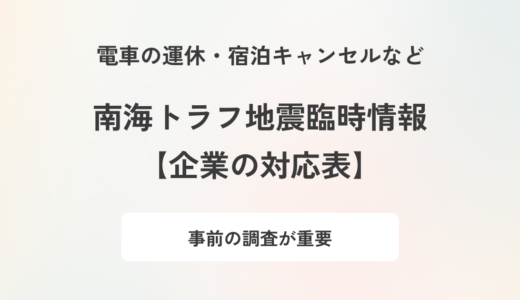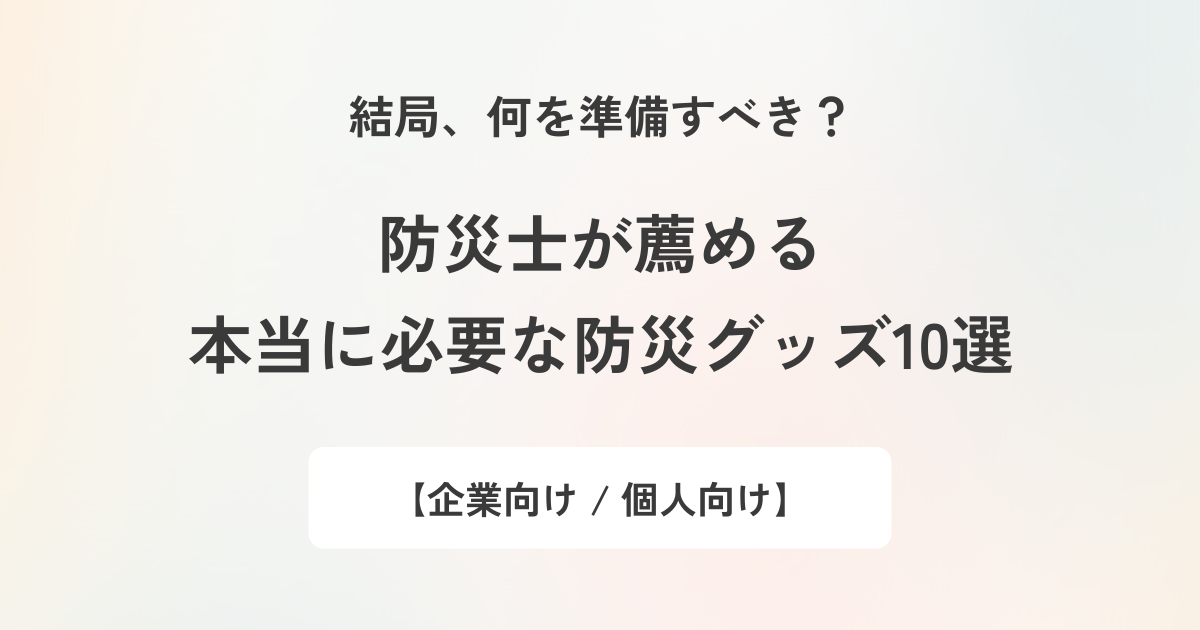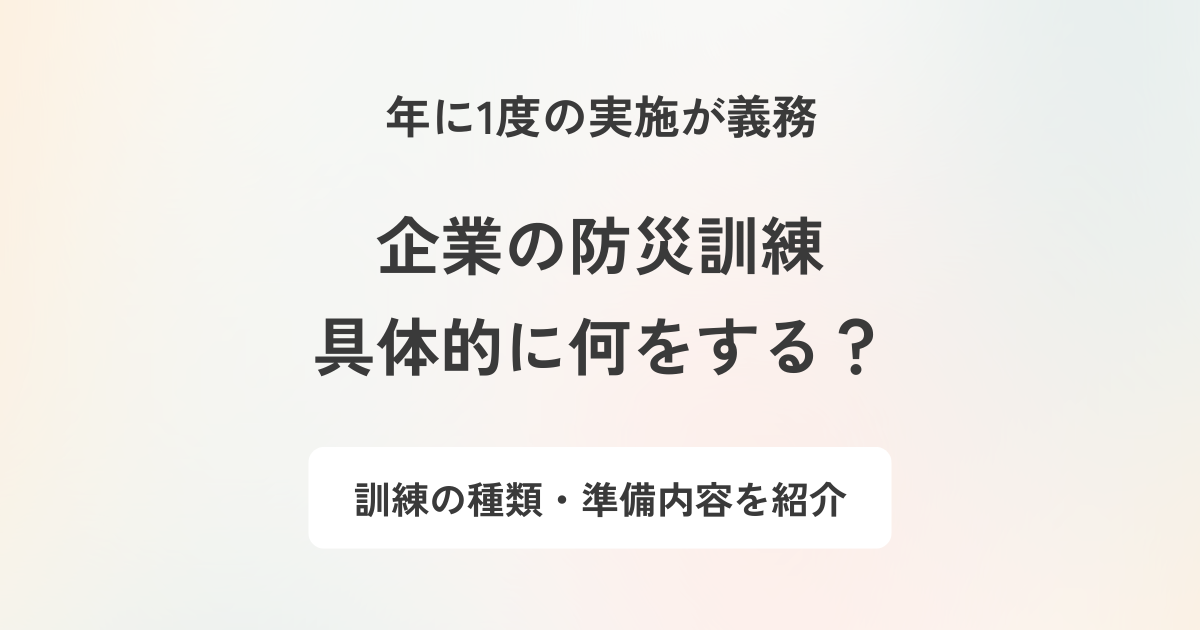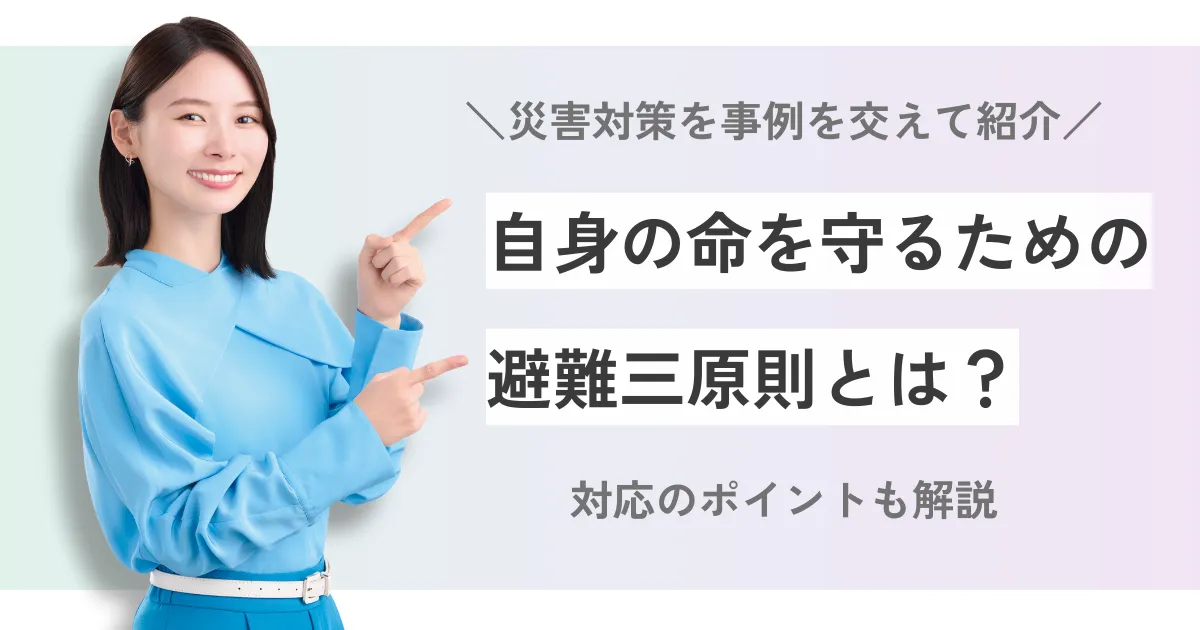地震の備えで大切なことは?企業が取り組むべき10の対策|備品や体制作りについて防災士が解説

坂田 健太(さかた けんた)
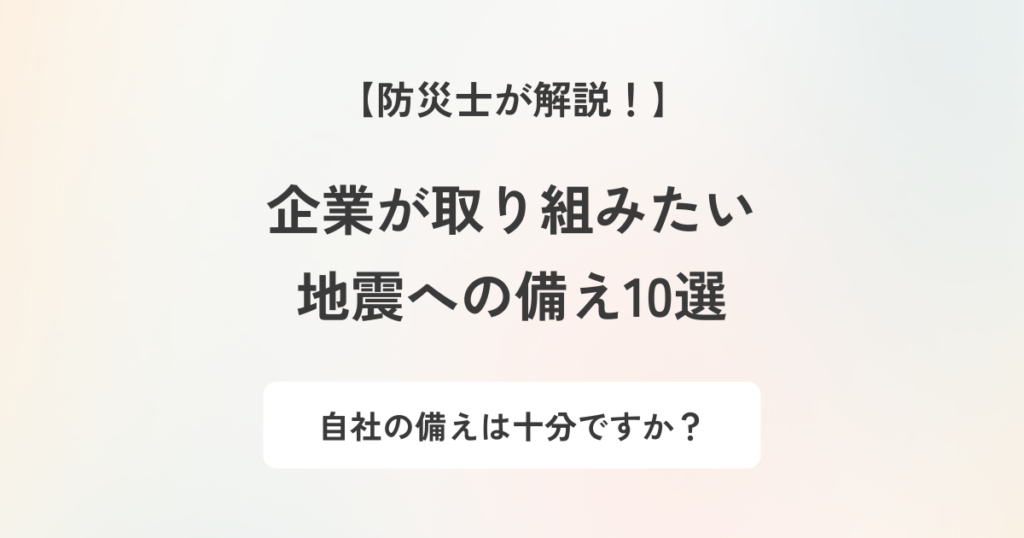
能登半島地震などの大きな地震のニュースをきっかけに、自社の防災対策が十分にできているか気になったという方もいるのではないでしょうか。
政府の地震調査委員会によると、南海トラフでは今後30年以内に震度6弱以上の大地震が70〜80%の確率で発生するともいわれています。大規模な地震が発生したときに従業員の安全を守り、経営への影響を最小限に抑えるためには、事前の準備が大切です。
この記事では、地震に対する防災対策に取り組みたい方に向けて、企業における地震の備えで大切なことを紹介します。BPC関連のセミナーに多く登壇し、BCPの啓蒙や策定のサポートを行うトヨクモ株式会社 防災士の坂田が監修しているため、理解しやすい内容となっています。
ぜひ、自社の状況と照らし合わせながら読み進め、企業の安全確保にお役立てください。
目次
地震の備えで大切なことは?
災害時には、状況の変化に応じて素早く対応する必要があるため、事前の備えがあるかどうかで行動の質や安全性が大きく左右されます。
とくに地震対策は、一度準備したら終わりではありません。家族構成や住まいの変化、周囲の環境に応じて定期的に見直し、更新することが大切です。
たとえば以下の対応が効果的です。
- 地震保険の加入や見直し
- 建物の耐震性の確認
- 防災訓練への参加
- 近隣の危険箇所のチェック など
非常用持ち出し袋の用意や家具・家電の転倒防止、避難場所や避難経路の把握など、日頃からできる対策も欠かせません。具体的な備えについては、次の見出しで詳しく解説していきます。
防災対策の課題と解決策について知りたい方は、下記記事もあわせてご覧ください。
地震の防災対策 1.オフィス家具や什器の固定
東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」によると、近年発生した地震でのけがの原因を調べると、実に約30〜50%もの人が、家具類の転倒・落下・移動によるものという結果が出ています。
とくに複合機や社員用のロッカーなどのオフィスならではの什器は、大規模な地震の発生時には恐ろしい凶器になり得ます。壁面への固定やキャスターの調整など、オフィス環境に合わせた対応が必要です。
(参考:東京消防庁|家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック)
具体的な家具の固定方法
二段重ねの家具は、上下を平型金具でしっかり固定しましょう。家具を柱や壁に固定する際は、L型金具と木ねじを使って上部を留めるのが効果的です。ガラス部分には飛散防止フィルムを貼り、安全性を高めます。
吊り戸棚の扉は、掛金で開かないようにします。食器棚のガラス製品の滑り出しを防ぐために、防止枠を設置すると安心です。
けがの防止策も検討する
地震時のけがを防ぐための対策は大切です。食器棚や窓ガラスには飛散防止フィルムを貼り、ガラスの破片の飛び散りから身を守りましょう。
停電のリスクもあるため、懐中電灯はすぐ手に取れる場所に置きます。散乱したもので足を傷つけないように、スリッパやスニーカーを身近に準備しておくと安心です。
地震の防災対策 2.避難経路の確認
避難経路の確認では実際に通るルートを歩いて確認することが大切です。建物の中では廊下や階段の踊り場など、避難経路として活用すべき通路が荷物でふさがれてしまっていて、緊急時に使用できないといった例がよく見られます。
建物の外では危険なブロック塀がないか、地震の揺れによって大きな看板が倒れて来ないか、などといった点を中心に確認しておく必要があります。
近くの避難場所を把握する
避難場所は、多くの場合、建物周辺の地区ごとに指定されています。
避難場所としては、以下の場所が指定されます。
- 公園
- グラウンド
- 河川敷
- 高層ビル
- 高台
- 高速道路上 など
避難場所は、災害時に安全が確保される場所として、市町村や自主防災組織が決めています。避難場所がわからない場合は、オフィスのある市区町村の窓口に問い合わせ、確認しておくと安心です。
避難経路を実際に歩いて確認する
避難経路は、国土交通省のハザードマップポータルや自治体の防災マップで確認できます。平常時に実際に歩いてみて、危険箇所を把握することも重要です。地震時に注意すべき場所や避難に便利な施設を調べ、自分用のマップにまとめておくとよいでしょう。
地震の防災対策 3.役割分担の明確化
中規模から大規模の組織では、災害時における各人の役割分担が重要になります。大規模な地震が発生した際に必要となる役割は以下のとおりです。
ここで重要なのは、「誰が何をするか」を明確にすることです。つまり、具体的な指示を出す「リーダー(責任者)」の選出とその権限の設定、そして情報伝達のためのルートと方法を明確にすることが不可欠です。
地震の防災対策 4.重要なデータのバックアップ
情報資産の損失は企業に多大な損害を与えます。定期的かつ頻繁なバックアップはもちろん、異なる拠点間によるシステムの二重化や企業によってはデータセンターの利用なども有効な手段です。
事業内容や規模、予算も踏まえ、バックアップすべきデータの優先度や使用するツール、サービスの使い分けを検討しましょう。
地震の防災対策 5.防災教育・訓練の実施
災害時には誰もが普段とは異なる心理状況に立たされます。そのため、防災に関する知識の取得や行動基準の理解など、“頭”で理解する防災教育はもちろんのこと、消火器の使い方やけが人の発生を想定した応急手当など、“体”で覚える防災訓練も重要になります。
防災訓練は日頃から定期的に開催するとともに、可能な限り具体的な被害状況を想定し、それに基づいた人員の配置、物資の準備を行うことで、緊張感の欠如を防ぎます。
防災教育を実施する際は、避難場所や避難ルートなどの情報を周知徹底しましょう。オフィスがある地域の避難場所や避難ルートは、自治体のWebサイトやハザードマップポータルサイトで調べることが可能です。
地震の防災対策 6.緊急時の連絡手段の確保・安否確認
大規模な災害の直後は各種インフラ網が打撃を受け、情報の収集、通信が困難になる可能性があります。その際に重要なのは、社員が慣れ親しんだ共通の通信手段を確保すること、そして複数の連絡手段を準備しておくことです。
いざ活用すべきときに手間取らないよう、普段から日常的に活用しておくことも大切です。
また、安否情報の際に大切なのは、単に無事か否かといった生存の確認に終始するのではなく、被災した社員の被害の大きさを把握し、場合によっては救援の要請など次のステップへ繋げることが大切です。
安否確認方法や集合場所は決めておく
地震発生時の安否確認や集合場所は、事前に話し合って決めておくことが大切です。携帯電話がつながりにくい場合は、災害用伝言ダイヤル「171」や伝言板、安否確認システムを活用する方法を理解しておきましょう。
企業で安否確認システムを導入する際には、従業員への使い方の周知が欠かせません。事前に操作講習を実施し、新入社員にも確実に伝えるなど準備が必要です。
安否確認システム
複数の連絡先登録ができたり、災害情報と連動して自動で一斉送信を行なったり、そのあとの対策指示まで一貫して行える次世代型システムも登場しています。
安否確認システムの導入をご検討の方には、トヨクモの『安否確認サービス2』がおすすめです。簡単な操作で、だれでも直感的に使うことができます。また、災害時を想定した契約全社一斉訓練や、データセンターの国際分散などにより、確実に機能する信頼性の高さも特長です。
また、専門システムの他にも、さまざまな対策方法があります。
- 各種SNS[LINE、Facebook、X(旧Twitter)]
- 災害用伝言ダイヤル「171」
- 災害用伝言板
- J-anpi
- スマートフォンアプリ(ネットラジオアプリ、地震情報アプリなど)
- 公衆電話
このような対策方法の中から自社に合った方法で、確実に連絡手段を確保することが必要です。
地震の防災対策 7.非常用品(非常食)の準備
地震発生後はすぐに必要な物資の確保ができるとも限りません。そういった事態に備え、企業としても個人としても、非常用品の準備が必要になります。
以下に準備すべき非常用品の一例を記載します。
水・飲料水
飲料水は、家族の人数に合わせて準備することが大切です。基本的には、「1日3リットル×人数×3日分」を目安に用意しましょう。3人家族の場合は、27リットル分の飲料水を用意します。
大地震に備える場合は、一週間分の備蓄が理想的です。
飲料水とは別に、トイレや生活用水も確保しておきましょう。お風呂に水をためたり、ポリタンクに水道水を用意しておくなど、普段からの備えが重要となります。
非常食
避難所の生活では、お湯や電子レンジが使えないことが多いでしょう。缶詰や乾パン、チョコレート、ビスケットなど、そのまま食べられる非常食を用意しましょう。非常食の量は、家族人数×3日分が基本です。大規模地震への備えであれば、一週間分用意します。
避難所では炭水化物中心の配給が多いため、タンパク質が豊富な食べ物も準備するのがおすすめです。高齢者や赤ちゃんがいる場合は、専用の流動食も用意しておきましょう。
女性がいる場合の非常用品
女性が避難時に用意すべきものには、生理用品やサニタリーショーツがあります。生理痛がひどい場合は、鎮痛剤も準備しておくと安心です。
また防犯面を考慮し、防犯ブザーやホイッスルなどのグッズも用意しましょう。中身が見えないごみ袋も、生理用品を処理する際に役立ちます。ほかにも、下記のような美容関連のアイテムも可能な範囲で持参すると快適に過ごせます。
- メイク落とし
- 洗顔料
- 化粧品
- ハンドクリーム
- リップクリーム
- ヘアゴム
- 手鏡
非常用の持ち出し袋に余裕がある場合は、あわせて用意しておきましょう。
高齢者がいる場合の非常用品
高齢者がいる場合は、おかゆやとろみのある柔らかい食事が必要です。また大人用おむつや補聴器の電池、入れ歯洗浄剤、老眼鏡、折りたたみ杖も準備しましょう。
また、高齢者は低体温や熱中症のリスクが高いため、避難所での温度管理にはとくに注意が必要です。使い捨てカイロや冷却剤、断熱シートなど、季節に合わせて体温調節に役立つアイテムを用意します。
子どもがいる場合の非常用品
子どもがいる場合は、おむつやおしりふき、粉ミルクや液体ミルク、離乳食などを準備しましょう。普段から食べ慣れたお菓子があれば、お子さんも喜びます。
子どもにアレルギーがある場合は、配給品が合わない可能性があるため、専用の非常食を用意することが大切です。
味付けが強いものや、知らない食べ物は嫌がることもあるため、子どもの好みに合ったものを選びましょう。非常食は最低3日分、可能なら1週間分の備蓄がおすすめです。
地震の防災対策 8.周辺地域との協力体制の構築
災害時の対策は以下の3つに分類されます。
- 公助 行政機関における支援
- 共助 地域住民・企業による相互支援
- 自助 個々人・企業単位での努力
このなかでも大地震などの大規模な災害時には、「自分たちの地域は自分たちで守る」という「共助」の活動が大きな役割を担います。また、企業としても周辺地域の安全性を確保し、事業をいち早く正常な状態に戻す点でも重要です。
そのため、緊急時に連携することはもちろん、日ごろから「自助」にあたる社内の防災対策に加え、「共助」にあたる地域支援としての活動に対しても積極的に関わりを持つことが大切です。
地震の防災対策 9.防災マニュアルの作成
防災マニュアルは、従業員の行動基準として緊急時に大きな効果を発揮します。マニュアルの作成にあたっては、自社の状況に適した内容になるよう心がけましょう。
あくまでも、防災マニュアルは従業員が必要な場面で正しく活用されることが目的であるため、コンパクトなカード形式で配布するなどの工夫も大切です。
また、記載の内容については、誰が読んでもわかりやすいように記載することが前提で、具体的には以下の点が必要になります。
- いつ、何を行うべきかが明確である
- 責任者、行動者の氏名が明確である
- 想定され得るケースが網羅されている
- 二次災害の防止を促す
地震の防災対策10.BCPの策定
BCP(Business Continuity Plan)とは事業継続計画と呼ばれ、大規模な地震の発生時など企業が緊急事態に陥った際に、いかにして被害を最小限にとどめ中核となる事業の継続を図るか、またはそのための手段を決めておく計画のことを指します。
とくに中小企業の場合、地震の発生により事業の一時停止や縮小、最悪の場合には廃業にまで追い込まれてしまう可能性があります。
災害対策としてはもちろんのこと、企業としての責任を果たす上でもBCPの策定、適切な運用が欠かせません。
企業で地震による被害を最小限に食い止めるには、普段から従業員一人ひとりが防災に対する意識を強く持ち、対策を講じることが重要です。
今回ご紹介した内容を踏まえ、いま一度社内における地震の対策状況について目を向けて、具体的なアクションを取られることをおすすめします。
BCPの策定ならBCPコンサルタントへご相談を!
BCPを策定する際は、基本方針や運用体制を決定した上で、中核事業や復旧目標の設定、財務診断、事前対策の実施といった手順を踏むことが一般的です。そのため、BCPの策定には膨大な時間がかかります。
そこで役立つのがBCPコンサルタントによるBCP策定支援サービスです。貴社の状況に合わせた適切なBCPマニュアルの作成を実績豊富なコンサルタントが支援します。
BCPを策定できていないなら、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用をご検討ください!
早ければ1ヵ月でBCP策定ができるため「仕事が忙しくて時間がない」や「策定方法がわからない」といった危機管理担当者にもおすすめです。下記のページから資料をダウンロードして、ぜひご検討ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
火災の発生を想定した対策
大規模な地震の場合、発生直後に火災が発生するリスクもあります。火災発生に備えた対策は、迅速で安全な対応のために欠かせません。ここでは、火災時の具体的な準備や注意点についてわかりやすく解説します。
具体的には、以下がポイントです。
- 消火器を用意する
- 火災警報器の動作を確認する
- 機械からの出火を防ぐ
それぞれ解説していきますので、参考にしてください。
消火器を用意する
地震による火災被害を減らすためには、消火器などの消火用品を必ず準備しておくことが大切です。正しい使い方も、事前にしっかり覚えておく必要があります。
消火器には有効期限があるため、定期的にチェックすることを忘れないようにしましょう。火元に投げるだけで使える、消火剤も手軽でおすすめです。
火災警報器の動作を確認する
火災警報器は、正しく作動するかどうか、定期的に動作確認をすることが大切です。多くの製品には点検ボタンがあり、押すと警報音や音声で正常かどうかチェックできます。
音が出ない場合は、電池切れや本体の劣化が考えられるため、速やかに対策しましょう。
住宅用の火災警報器の寿命は、約10年といわれています。使用開始から10年を目安に、新しい火災警報器に交換するのがおすすめです。
機械からの出火を防ぐ
地震発生後、倒れた家電製品が通電時に作動し、発火するおそれがあるため注意が必要です。また、花瓶や水槽の水がコンセントにかかることで発火するリスクも考えられます。
普段から使わない家電はコンセントを抜き、水の入ったものは近くに置かないようにします。石油ストーブもカーテンや洗濯物のそばに置かず、転倒時に灯油が漏れないよう給油口をしっかり閉めておくとよいでしょう。
【子ども向け】地震の備えで大切なこと
万が一地震が発生した場合、子どもが安全に行動できるよう、日ごろから地震への備えや心構えを身につけておくことが大切です。ここでは、子どもがいるご家庭に向けてわかりやすく対策ポイントを紹介します。
具体的なポイントは以下のとおりです。
- 子どもの心理的なケアが必要になる
- 子どもの避難リュックを用意する
- おもちゃなどの遊び道具を用意する
それぞれのポイントについて解説していきます。
子どもの心理的なケアが必要になる
災害時は、子どもが普段とは違う不安や恐怖を感じやすくなります。
とくに混乱の中では、身体的・性的虐待やネグレクトといった被害のリスクも高まるため、大人の見守りが欠かせません。
子どもは「また災害が起こるのでは」と怯えたり、寝つきが悪くなったり、悪夢を見みたりすることもあるでしょう。ほかにも、食欲が変化したり、急に泣き出したりするなどの反応を示すこともあります。
大人は普段以上に子どもの様子を気にかけ、安心できる環境を整え、話をしっかり聞くことが重要です。
子どもの避難リュックを用意する
非常用持ち出し袋は大人目線だけでなく、子どもの立場に立って用意することが求められます。乳児や幼児がいる場合は、下記のようなものを入れておきましょう。
- おむつ
- おしりふき
- 着替え
- ブランケット
- 遊べるおもちゃ
- 子ども用の歯ブラシ
- ビニール袋
- 常備薬
- 母子手帳のコピー
荷物が多くなるため、キャリーバッグにまとめると持ち運びやすく便利です。ある程度大きい子どもなら、自分用のリュックを一緒に準備するのもおすすめです。
おもちゃなどの遊び道具を用意する
避難生活中、子どもが少しでも安心して過ごせるように、お気に入りのぬいぐるみやブランケットなどを非常用持ち出し袋に入れておくとよいでしょう。
遊びは心身の発達やストレス軽減に役立つため、避難所内に遊び場を設けることも重要です。
たとえば、乳幼児向けのソフトトイや絵本、想像遊びができるブロックやおままごとなどがよいでしょう。ほかにも工作や手芸などのひとり遊び、グループで楽しめるトランプやボードゲーム、体を動かせるスペースなどがあるとストレス解消がしやすくなります。
地震の備えで大切なことに関するよくある質問
地震への備えは大切ですが、何をどこまで準備すればよいのか悩む方も多いでしょう。ここでは、地震対策に関してよく寄せられる疑問や不安について、わかりやすく解説します。
具体的なよくある質問は以下のとおりです。
- 地震発生時は1階と2階のどちらが安全ですか?
- 室内で安全性の高い場所はありますか?
- 地震発生時に最初にすべきことは何ですか?
- 地震の備えでいらなかった防災グッズはありますか?
- 南海トラフ地震で一番危ない県はどこですか?
ぜひ地震対策の参考にしてください。
地震発生時は1階と2階のどちらが安全ですか?
地震発生時に1階と2階のどちらが安全かは、建物や災害の状況によって異なります。
耐震性の高い家なら2階が安心です。一方で、耐震性の低い家は2階の方が倒壊による危険を避けやすいです。
1階はすぐ外に逃げやすく、火災の影響も受けにくい反面、倒壊時に下敷きになるリスクがあります。また、2階は倒壊被害が少ないものの、避難の際に脱出しにくいというデメリットがあります。
住まいの状況に応じた判断が大切です。
室内で安全性の高い場所はありますか?
地震の際に、室内で比較的安全とされるのは、以下のような柱や壁に囲まれた場所です。
- 玄関
- 廊下
- トイレ
- ユニットバス など
とくに玄関や廊下は、避難経路としても使えるため安心でしょう。
揺れを感じた際は無理に外へ出ず、テーブルの下などに身を隠して頭を守ります。近くに座布団やまくらがあれば、頭部を覆うとより安全です。
外に出る場合は、瓦やガラスの落下、ブロック塀の倒壊への注意が必要です。
地震発生時に最初にすべきことは何ですか?
突然大きな揺れを感じたときは、何よりも自分の身を守ることが最優先です。
丈夫な机やテーブルの下にもぐり、脚をしっかり持って体を安定させましょう。近くに座布団やクッションがあれば、頭を守るのに役立ちます。
出入り口の確保も大切ですが、揺れている最中に外へ飛び出すのは非常に危険です。揺れが完全に収まってから、落ち着いて避難行動を開始しましょう。
地震の備えでいらなかった防災グッズはありますか?
地震対策として用意したものの、実際にはあまり使う場面がない防災グッズもあります。
たとえば、ロープは救助や瓦礫撤去に便利ですが、救助や瓦礫の撤去が不要な場合が多い上、使い慣れていないと危険を伴う場合もあるでしょう。
カップ麺も、災害時にお湯を確保できないことが多く、役立たないケースがあります。
ただし、状況に応じて必要かどうかは変わるため、多めに備えておいて損はないでしょう。
南海トラフ地震で一番危ない県はどこですか?
南海トラフ地震が起きた場合、もっとも危険なのは静岡県と言われています。
震源に近く、一部では最大31mの津波が予測されているほか、過去にも大きな被害が発生しています。
関東地方から九州地方の太平洋沿岸では、10mを超える大津波の可能性もあり、日頃からの備えが欠かせません。
実際に、気象庁の令和7年3月の被害想定では、静岡から宮崎の一部地域で震度7の揺れが予測されています。
企業における南海トラフへの対策をチェックリスト形式で確認したい方は、下記の記事もあわせて参考にしてください。
地震の備えで大切なことを把握しておこう
災害時は状況が急変するため、事前の準備や心構えが安全に大きく影響します。企業では、重要データのバックアップや役割分担の明確化、避難経路の確認、オフィス家具の固定などが地震対策の基本です。
防災マニュアルやBCP(事業継続計画)を整備しておくことで、地震による被害を最小限に抑えられます。平常時から防災意識を高めて、適切な対策を実施しましょう。
BCPを策定できていないなら、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用をご検討ください!
早ければ1ヵ月でBCP策定ができるため「仕事が忙しくて時間がない」や「策定方法がわからない」といった危機管理担当者にもおすすめです。下記のページから資料をダウンロードして、ぜひご検討ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。