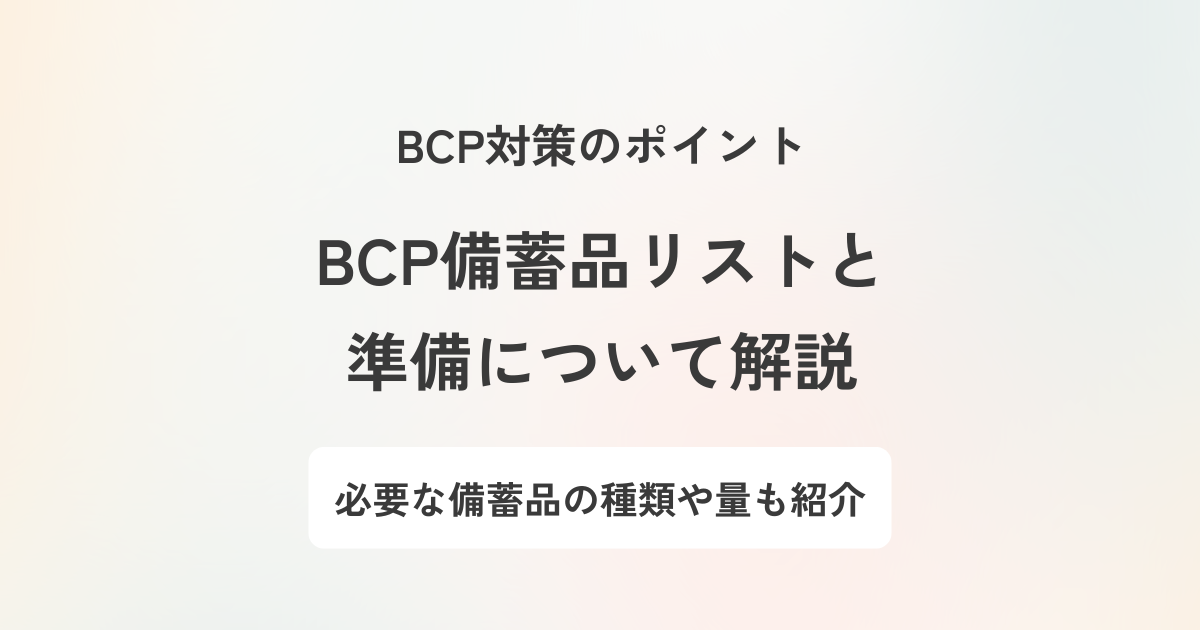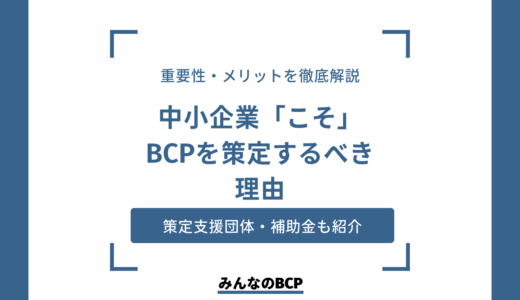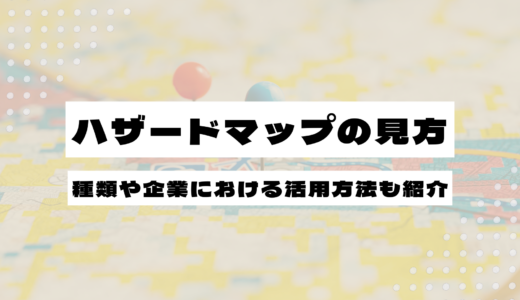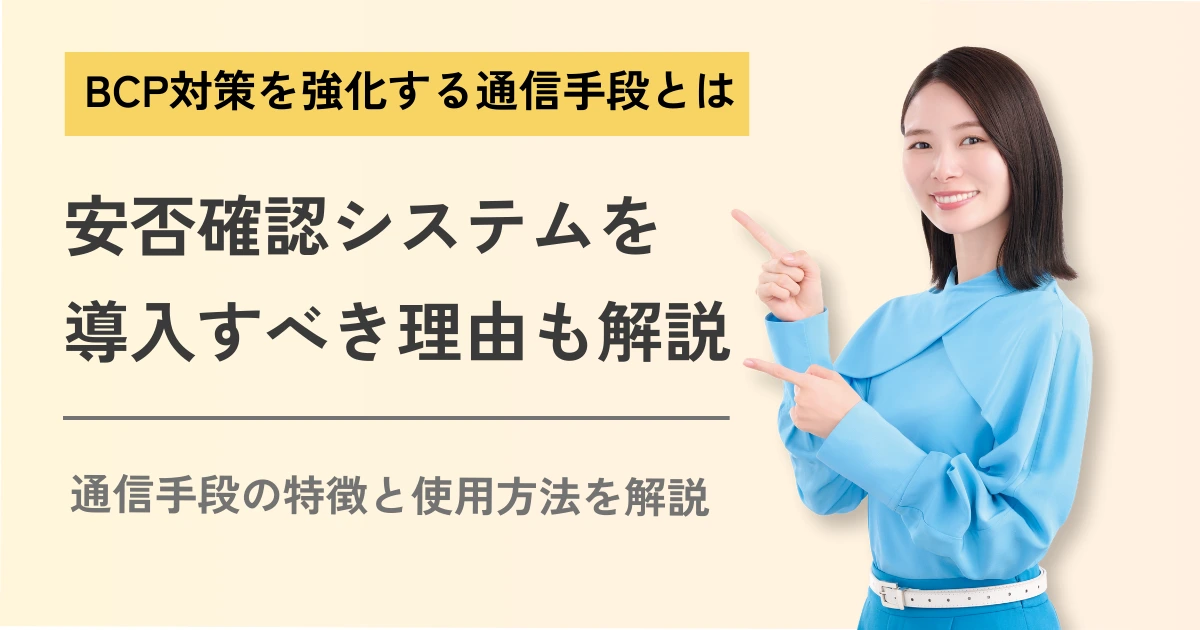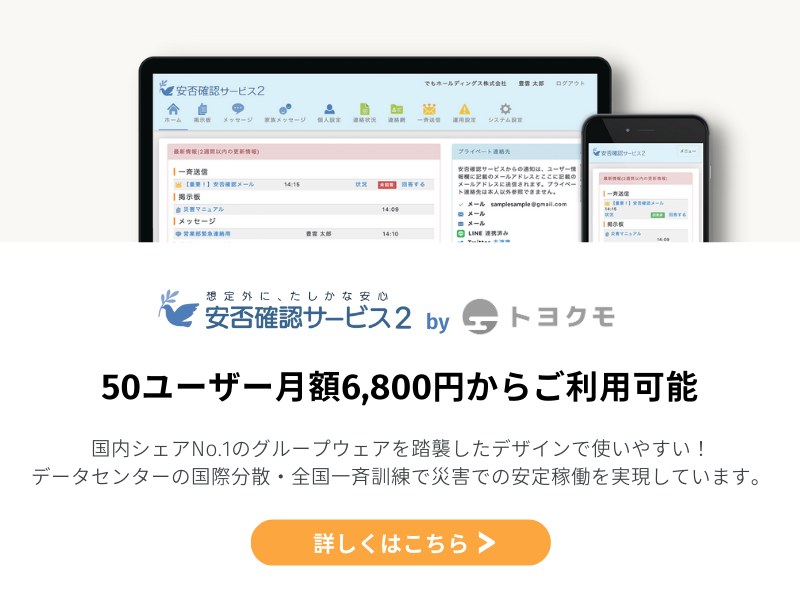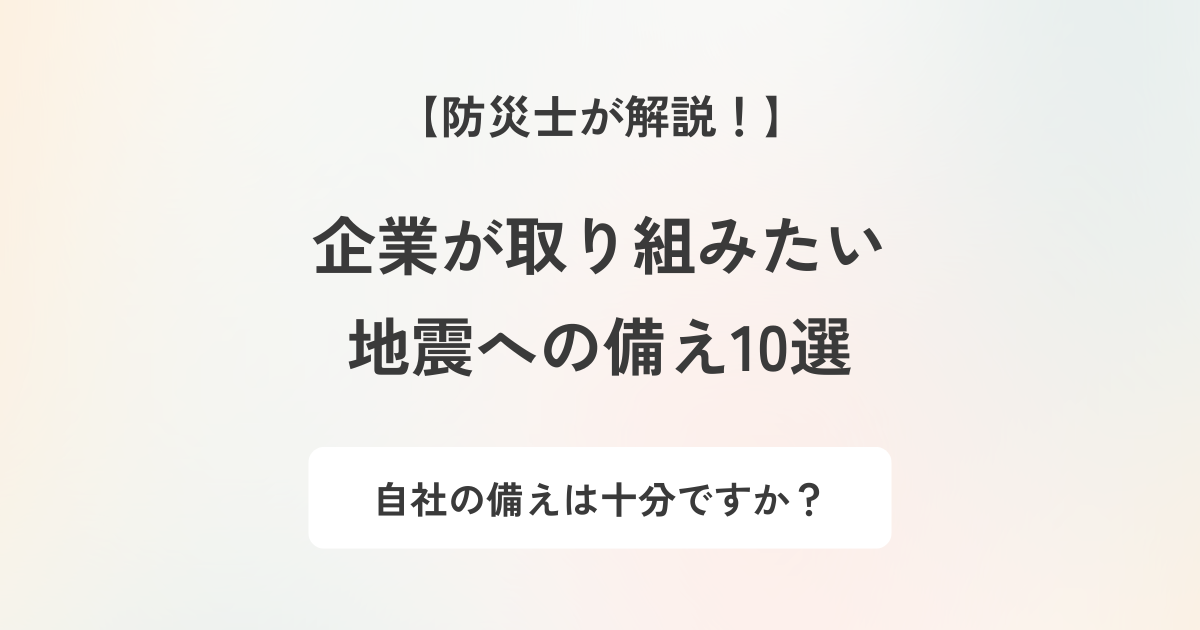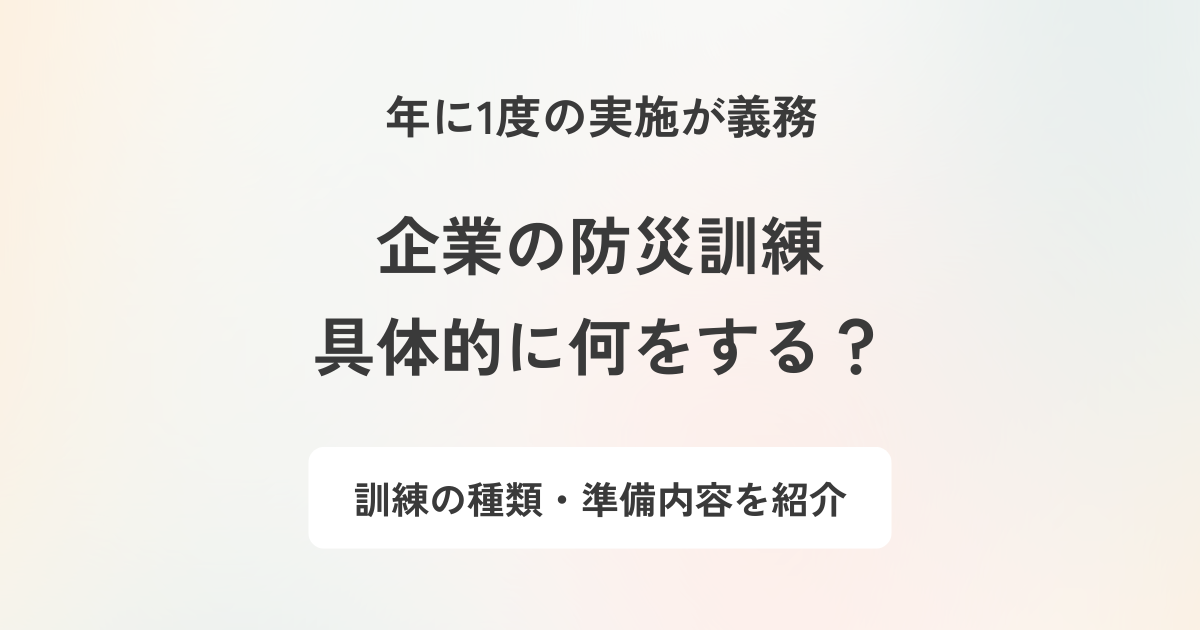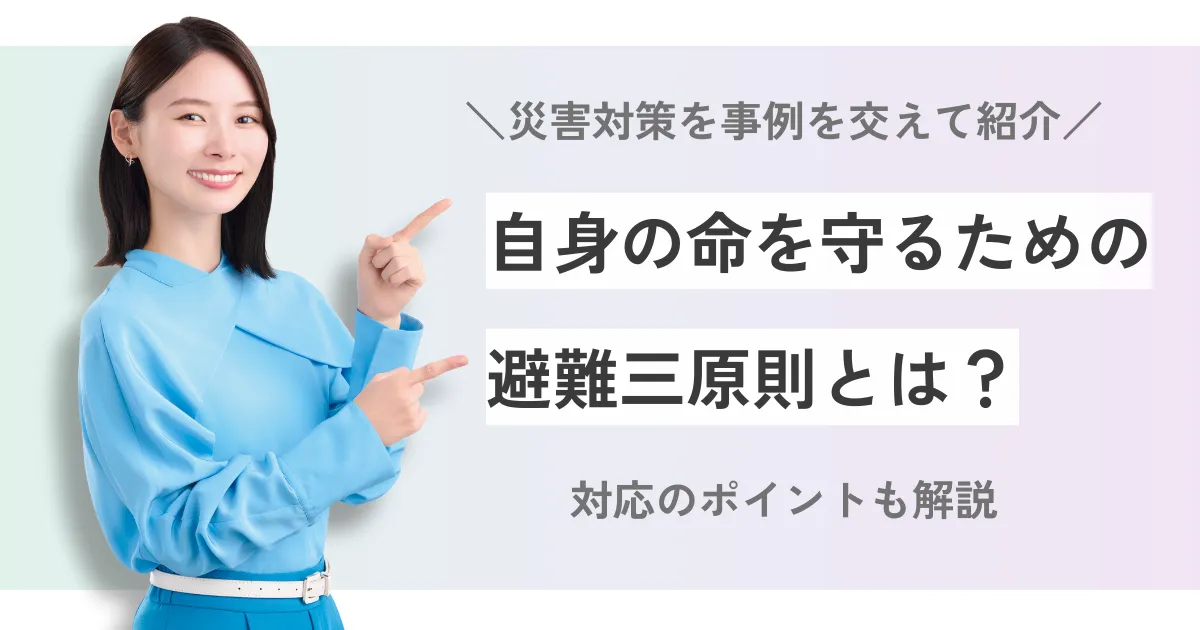【防災士推薦】防災グッズで本当に必要なもの10選!個人向けアイテムも紹介

遠藤 香大(えんどう こうだい)
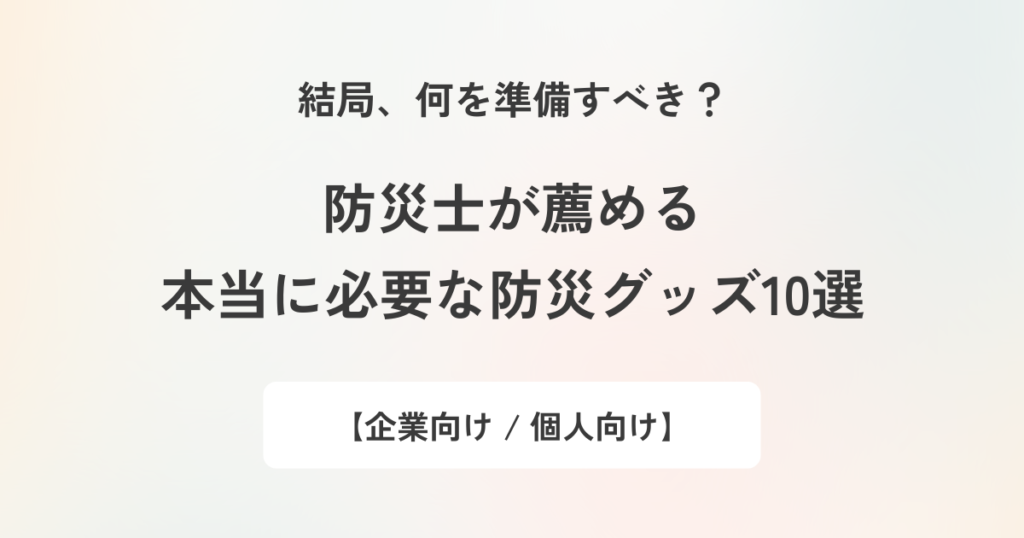
自然災害が起きた際の被害や従業員の不安を軽減するには、防災グッズの準備が必要です。ただし、保管スペースや予算には限りがあるため、本当に必要なものを見極めなければなりません。
この記事では、防災士が選ぶ防災グッズで本当に必要なものを企業向けと個人向けに紹介します。災害対策の強化や安全確保に取り組んでいる方は、最後までご覧ください。
目次
防災グッズで本当に必要なもの10選【企業向け】
労働安全衛生法や労働契約法にもとづき、企業は従業員の安全に配慮しなければなりません。災害規模やライフラインの被害状況によっては、事業所内で一定期間過ごすケースも考えられます。
災害に備えて、以下10個の防災グッズを用意しておきましょう。
- 飲料水と生活用水
- 非常食
- 衛生用品
- 現金
- 防寒具
- 救護用品
- 感染症対策用品
- ラジオやバッテリー
- 懐中電灯とポータブル電源
- 安全対策用品
必要な量や具体的なグッズなどを紹介します。
飲料水と生活用水
飲料水と生活用水は用途が異なるため、別々に確保が必要です。飲料水は水分補給と調理用に使用し、農林水産省は1人あたり1日3Lの飲料水を確保するよう、推奨しています。
ライフラインが復旧するまでの期間を考えると、3日分に相当する1人9Lの飲料水確保が最低限必要です。保管スペースに余裕がある場合、1週間分の飲料水を確保しておきましょう。
また、生活用水は手洗いや食器洗い、トイレなどに使用します。飲料水よりも使用用途が広く、1人あたり1日10〜20Lの生活用水が必要です。生活用水も最低3日分、できれば1週間分を確保しておきましょう。
短期間で多くの水を調達するのは手間がかかるため、定期的に買い足しておくのがおすすめです。
非常食
非常食も飲料水と同様に1人あたり3日分、9食分の確保が1つの目安です。備蓄しておくべき非常食は以下のとおりです。
- 防災用ゼリー
- チョコレート
- 缶詰
- 防災用パン
- 固形用の栄養補助食品
- おにぎりタイプのパックご飯
- 水不要のレトルトパスタ
チョコレートや缶詰など、水を使わずに食べられるものを多めに確保しておくのがおすすめです。場所によっては、水の安定確保が難しい場合もあります。パックご飯やレトルト食品を用意する場合は、水なしで調理できるタイプを選択しましょう。
また、防災用ゼリーは調理不要で手軽に栄養補給ができる食品です。賞味期限が3年や5年などに設定されており、長期保存もしやすいです。食感も軟らかく、アレルギー物質も入っていないため、多くの方が安心して食べられるでしょう。
衛生用品
事業所内の衛生環境が悪化すると、新型コロナウイルスやノロウイルス、黄色ブドウ球菌など、感染症や食中毒を発症する確率が高まります。清潔な衛生環境を維持するには、以下の衛生用品の確保が必要です。
- 簡易トイレ
- トイレットペーパー
- マスク
- 除菌シート
- ウェットティッシュ
- タオル
従業員がトイレを我慢しなくて済むよう、簡易トイレとトイレットペーパーは多めに確保しておきましょう。トイレを我慢すると、膀胱炎や尿路感染症など、さまざまな健康被害をもたらします。
簡易トイレの必要数は1人あたり35回分、1週間分の確保が1つの目安です。経済産業省によると、35回は成人が1人あたり1日平均5回トイレを利用するとの想定です。
また、トイレットペーパーは1人あたり4ロール分の備蓄を推奨しています。個人差はあるものの、1週間に1ロールを消費するとの想定です。
トイレットペーパーは、汚れの拭き取りや止血の際などにも利用できるため、多めに確保しても使い道に困る心配はいらないでしょう。
現金
災害時はATMやクレジットカードが使えない可能性があるため、ある程度の現金を用意しておきましょう。災害時に食料を購入する際、現金のみに対応している店しか営業していない可能性があります。
現金は防水加工の施されている袋や金庫などに保管しておくと、災害時でも安心して利用できます。
防寒具
災害時はいつ発生するか予測できないため、寒さに備えた対策も必須です。毛布やカイロがあれば冷え込む朝晩を乗り越えやすくなるでしょう。毛布は災害によって帰宅できない場合の仮眠時にも利用できます。
救護用品
災害時に負傷や体調不良に見舞われたとしても、被害状況によってはすぐに医療機関で受診できる保証はありません。
消毒液や絆創膏、医薬品などを備蓄しておき、応急処置ができる体制を整えておきます。救護用品は普段から使用できるため、多めに用意しておきましょう。
感染症対策用品
衛生用品に加えて以下のグッズを用意しておくと、感染症の発生リスクを軽減できます。
- 使い捨てゴム手袋
- アルコール消毒液
- パーテーション
- 非接触式の体温計
- フェイスシールド
- 空気清浄機
従業員数が多いほど事業所内の衛生環境が悪化し、感染症や食中毒が起きるリスクが高まります。仮に事業所内でクラスターが発生した場合、早期の事業再開は困難です。
感染症対策用品も事前に確保し、清潔な衛生環境の維持とクラスターの発生防止に努めましょう。
ラジオやバッテリー
災害時にはラジオやスマートフォンを利用して、情報収集を実施します。ラジオは手回し式ではなく、乾電池式を使用するのがおすすめです。手回しタイプの場合、常に回し続けなければならないため、手間がかかります。
また、災害規模やライフラインの被害状況によっては、電気が利用できません。停電対策として、モバイルバッテリーを用意しておきます。
懐中電灯とポータブル電源
懐中電灯やランタンを用意しておくと、停電時に行動する際の転倒リスクを軽減できます。また、停電に備えて非常用のポータブル電源も確保しておきましょう。
ポータブル電源は軽量で持ち運びができる点が特徴です。調理やPCの充電、照明器具の利用など、さまざまな用途に利用できます。エアコンやヒーターなどの大型家電に利用する場合は、700Wh以上の電源を搭載したタイプを選択しましょう。
安全対策用品
従業員の安全確保に必要な安全対策グッズは、以下のとおりです。
- ヘルメット
- 軍手
- 工具セット
- 拡声器
- 投光器
- スコップ
- 消火器
- バケツ
バールやハンマーなどの工具セットを用意しておく目的は、事業所内で火事や建物の崩壊が起きた際、すぐに外へ脱出できるようにするためです。
また、火事の際に消火器をスムーズに利用できるよう、防災訓練の際に使い方や設置場所を覚えておきましょう。
防災グッズで本当に必要なものをそろえる準備
防災グッズの必要性を認識していても、「保管スペースがない」や「予算確保が難しい」などの理由で、十分な確保ができていない企業もあるでしょう。
限られた予算と保管スペースで災害対策を強化するには、以下2点を意識することが重要です。
- 必要量を把握する
- 保管場所を確保する
ポイントを紹介します。
必要量を把握する
防災グッズを用意するときは、必要量を把握しましょう。企業によって従業員や来訪者の数が異なるため、防災グッズの必要量にも差が生まれます。そのため、防災グッズを備えるときは、自社の状況を把握したうえで適切なアイテムと量を準備する必要があるでしょう。
なお、防災グッズの量は最低でも「従業員の数×3日分以上」を備えるのが望ましいと言われています。目安量を参考にしながら、自社にとって必要な量を計算しましょう。
保管場所を確保する
防災グッズの保管場所を確保しましょう。必要最低限の防災グッズを準備する場合であっても、保管場所は必要です。
普段あまり使っていない部屋や倉庫を活用したり、オフィスの隅に場所を確保したりするのもいいでしょう。災害が起きたとき、迅速に取りに行ける場所に保管しておくのが重要です。
企業が防災グッズを備える際の注意点
防災グッズを備える際の注意点は、以下のとおりです。
- 各個人が必要とするものを準備してもらう
- 定期的な見直しを行う
- 防災グッズについて従業員全員に周知する
それぞれの注意点を解説します。
各個人が必要とするものを準備してもらう
防災グッズは、従業員によって必要となるものが異なります。
たとえば、持病のある人は薬が必要でしょう。お薬手帳などを携帯していることも大切です。また、身分証明やホイッスル、軍手などは、個人の準備に任せてもいいでしょう。
企業は従業員の安全を確保するために必要な防災グッズを準備し、従業員にはそれにプラスして備えておきたいものを携帯しておいてもらうと、より効果的な対策ができます。
定期的な見直しを行う
防災グッズの中には賞味期限や使用期限が設定されているため、定期的な見直しが必須です。とくに、備蓄用ではない水や食料は賞味期限がすぐに切れるおそれもあるため、定期的なチェックが欠かせません。
賞味期限をわかりやすいように明記するなどして、見直しの手間を省くようにしましょう。
なお、防災グッズは古いものから消費して、その都度新しいものを買い足していくローリングストックがおすすめです。
消費期限や使用期限が切れる前に消費でき、一定の備蓄量を確保し続けられます。
防災グッズについて従業員全員に周知する
防災グッズの種類や使用方法、保管場所などは従業員全員に周知しましょう。
災害時のために防災グッズを備えていても、従業員が種類や保管場所などを知らないと緊急事態に活用できません。予測不能な災害に備えられるように、すべての従業員が防災グッズを活用できる環境を整えておく必要があります。
防災グッズで本当に必要なもの10選【個人向け】
自然災害はいつ発生するか、予測が不可能です。災害時の不安を減らすには普段から防災グッズを購入し、備えを強化しておきましょう。
ご自宅で用意すべき防災グッズには、以下の10個があげられます。
- 飲料水と生活用水
- 非常食
- 衛生用品
- 衣類
- 現金と身分証明書
- 救護用品
- 季節用品
- ラジオやバッテリー
- 安全対策用品
- 非常用袋またはリュック
家族構成に応じて確保すべき量は異なるため、自身にとって必要な量を把握しておきましょう。
飲料水と生活用水
企業の災害対策と同様、家庭でも飲料水と生活用水は別々に用意しておくのが望ましいです。飲料水は持ち運びがしやすいよう、500mlペットボトルで5~6本用意しておきましょう。
災害規模や被害状況によっては、自宅から避難所へ移動する可能性があるためです。一方、生活用水はライフラインが復旧するまで、自宅での生活時に必要になります。
生活用水は1人あたり1日10~20L使用し、最低3日分の備蓄が推奨されています。定期的に水を箱買いし、少しずつ数を増やしておきましょう。
非常食
企業向けと同様、缶詰やチョコレート、防災用ゼリーなど、調理不要で食べられるものを多く用意しておくのがおすすめです。家族の好みにもよりますが、野菜ジュースを用意しておくのも1つの手段です。
手軽に栄養を補給できるだけでなく、ゴミも少なくて済みます。防災用のパックご飯やパンも選択肢に入りますが、飽きる可能性があるため、備蓄量には注意を払いましょう。
仮に自宅から避難所に移る場合、避難所ではおにぎりやパンが支給されるケースが多いためです。
また、非常食を確保する量は、家族の人数分×3食×3日分です。4人家族の場合は、36食分の確保が1つの目安になります。
衛生用品
災害時にも健康を保つには、衛生用品を十分に準備しておきましょう。
事前に用意しておくべき衛生用品は、以下のとおりです。
- 簡易トイレ
- トイレットペーパー
- マスク
- 歯ブラシ
- 歯磨き粉
- ビニール袋
- タオル
- ハンカチ
- ウェットティッシュ
- 除菌シート
- 生理用品
避難所では自由にトイレが使えないおそれもあるため、家族の人数分×1週間分の簡易トイレを最低限用意しておきましょう。
経済産業省では、1人あたり1週間で最低35回トイレを利用すると想定しています。4人家族の場合、35×4=140回分の簡易トイレの用意が必要です。
トイレットペーパーは、1人あたり1週間に1ロールを消費すると想定します。1ヶ月分の備蓄が推奨されているため、4人家族の場合は16ロール準備が必要です。
また、女性の場合は3日前後の生理用品も事前に準備が必要になります。小さいこどもがいる家庭の場合は、おむつやおしりふき、消臭袋なども用意しておきましょう。
衣類
津波や大雨などの水害に遭い、濡れたままの衣服で過ごすと、低体温症になるリスクが高まります。避難所に素早く避難できたとしても、すぐにシャワーを利用できるとは限りません。
濡れた場合にすぐ着替えられるよう、衣類や下着、靴下を3日分用意しておきます。衣類はジャージやスウェットなど、動きやすい服装を用意しておくのがおすすめです。
避難所生活では支援物資の運搬や手続き、救助活動など、身体を動かす機会が多いためです。圧縮袋を活用すると、非常用袋やリュック内でかさばらずに済みます。
また、洗濯できない場合に備えて、女性はサニタリーショーツを用意しておくのがおすすめです。避難所での盗難を避けるため、下着は地味な色やスポーティーなものを選びましょう。
現金と身分証明書
現金を含め以下の貴重品はすぐに取り出せる場所に、保管しておきましょう。
- 現金
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 健康保険証
- キャッシュカード
- 預金通帳
- クレジットカード
- 印鑑
災害時にはキャッシュカードや預金通帳よりも、身分証明書を携帯しておくことが重要です。大規模災害が発生した際、身分証明書で本人確認ができれば、キャッシュカードや通帳、印鑑がなくても自身の口座から預金を引き出せます。
1日に引き出せる金額は、多くの金融機関で10万円が上限です。被災先で自身が利用する金融機関の支店がなかったとしても、他の金融機関で引き出せる可能性があります。金融機関によって対応は異なるため、被災した際は問い合わせで対応可否を確認しましょう。
また、ネット銀行を利用している方は、まずコールセンターへの連絡が必要です。本人確認ができると、他の金融機関の口座に1回10万円を上限に振り込んでもらえます。
救護用品
災害で負傷した際に応急処置が施せるよう、以下のものを準備しておきます。
- 消毒液
- ガーゼ
- 包帯
- ばんそうこう
- ピンセット
- はさみ
- 風邪薬
避難所に移動する際、持病を抱えている方は常備薬、生理痛に悩まされている方は鎮痛剤を持っていきましょう。
季節用品
夏と冬で準備すべきグッズは異なります。夏は熱中症対策として、塩分タブレットや冷感タオル、うちわを確保しておきましょう。必要に応じて、日焼け止めや虫除けスプレーも用意しておきます。
一方、防寒対策にはアルミシートを用意しておきます。アルミシートの方が毛布よりも持ち運びしやすいため、避難所に移動した際にも便利です。また、使い捨てカイロを多めに用意しておくと、手軽に体を温められます。
ラジオやバッテリー
避難所や自宅で情報収集ができるよう、電池式のラジオと乾電池、モバイルバッテリーを用意しておきます。イヤホンを用意しておくと、周囲を気にせずに音声が聞けます。
安全対策用品
停電が起きた際に足元を照らせるよう、懐中電灯やランタンを用意しておきます。ろうそくは周囲のものに引火する可能性があります。避難所生活になった場合は火事のリスクがさらに高まるため、ろうそくを用意するのは避けましょう。
また、地震による落下物で頭部を負傷しないよう、ヘルメットや防災ずきんも必要です。小さいこどもを持つ方は外出先で周囲に助けを求められるよう、防犯ブザーを持たせておくのも有効です。
非常用袋またはリュック
避難所への移動に備えて、非常用袋またはリュックを用意しておきます。非常用袋は家電量販店やホームセンター、ECサイトなど、さまざまな場所で購入可能です。
また、リュックの場合は移動しやすいよう、軽量で耐久性に優れたものを選びましょう。事前に防災グッズが入るかどうか、背負って運べる重さかどうか、確認をしておくのがおすすめです。
事前に防災グッズのリストを作成しておくと、確認作業をスムーズに進められます。
防災グッズの準備以外に必要な災害対策【企業向け】
防災グッズの準備だけでは、災害対策は不十分です。以下4つの対策を講じ、従業員の安全確保に努めましょう。
- BCPを策定する
- ハザードマップを確認する
- 定期的に防災訓練を実施する
- 複数の連絡手段を確保する
複数の対策を講じると、大規模災害が起きた際の影響を軽減できます。
BCPを策定する
BCP(Business Continuity Plan)とは、自然災害や感染症の発生など、緊急事態の際に最短で事業復旧を目指すための事業継続計画です。2024年から介護事業所を対象にBCPの策定が義務付けられたものの、一般企業はまだ義務化の対象外です。
BCPには初動対応の流れや事業所の安全対策、他施設への連絡先など、さまざまな内容を記載しておき、従業員の不安を軽減します。
緊急時に実施すべき対策が異なるため、自然災害と感染症のBCPを別々に用意しておきましょう。双方のBCPを用意しておくと、大規模災害が起きたとしても、従業員が落ち着いて対応できる確率が高まります。
また、BCPの策定によって「あらゆるリスクに備えている企業」との印象を与えられ、取引先や顧客からの信頼も高まるでしょう
ハザードマップを確認する
ハザードマップとは、自社が拠点を置く地域での自然災害の発生リスクを把握できる地図です。自然災害の発生リスクは、過去の災害事例や地形の特徴、気象傾向などをもとに算出されています。
ハザードマップは地震や津波、土砂災害など、災害の種類別に作られているため、発生頻度の高い災害や危険が及ぶ地域を事前に把握できる点が特徴です。
また、ハザードマップには避難経路や避難場所も記載されています。防災訓練で記載された避難経路や避難場所を確認しておくと、緊急時も素早く避難できるでしょう。
定期的に防災訓練を実施する
最低でも年に1~2回は防災訓練を実施しましょう。消防法にもとづき、消防計画の作成と防災訓練の実施が各企業に義務付けられています。
消防計画にもとづく防災訓練を実施しなかった場合は消防法違反に該当し、100万円以下の罰金または1年以上の懲役が科される可能性もあります。
また、従業員の防災意識を高めるには、定期的な防災訓練の実施が必要です。仮に情報量が充実したBCPを策定したとしても、従業員の防災意識が高まらない限り、記載内容を忠実に実行できる可能性は低いです。
防災訓練では、安否確認の流れや避難経路、消火器の使用方法などを学習し、被災の軽減に努めましょう。
複数の連絡手段を確保する
自然災害が発生した際、すぐに従業員の安否を確認できるよう、複数の連絡手段を確保しておく必要があります。複数の連絡手段を確保すべき理由は、大規模災害の際に電話とメールは利用できない可能性が高いためです。
回線上のデータ通信量が電話回線の容量を超えた場合、音声通話は規制される可能性が高まります。音声通話の規制は、重要通信の受信やネットワーク環境を維持するためです。
東日本大震災の際、データ通信の量は通常の50〜60倍に増加しました。ドコモ・au・ソフトバンクの3大キャリアは、いずれも音声通話を最低でも70%以上規制しています。
また、メールのパケット通信は規制が少なく、音声通信よりつながりやすい状況でした。ただし、データ処理の量がサーバーのスペックを大幅に超えたため、速度遅延や位置情報の動作不良などが発生していました。
上記の内容からIP無線機やSNSなど、電話とメール以外の連絡手段を確保しておく必要があるといえます。複数の連絡手段を確保する手段には、安否確認システムの導入を選ぶのがおすすめです。
LINEや専用アプリなど、複数の連絡手段に対応したシステムが多く、災害時に従業員の安否を素早く確認できます。
さらに、サーバーやデータセンターの分散運用など、強固な災害対策を講じているベンダーが多く、災害時も安定稼働が期待できます。
連絡手段の確保にはトヨクモの『安否確認サービス2』がおすすめ
災害時の連絡手段に安否システムの導入を検討している方は、トヨクモの『安否確認サービス2』を選ぶのがおすすめです。『安否確認サービス2』は、導入実績4,000社以上を誇る安否確認システムです。
メールや専用アプリでの安否確認メール送信に対応しています。有料オプションを利用すると、LINEでの安否確認も可能です。
気象庁と連携しており、一定規模以上の地震や津波などが発生すると、自動で安否確認メールと災害情報を送信するため、従業員に素早く安全確保を促せます。
また、『安否確認サービス2』は、災害時でも安定稼働が望める点が魅力です。シンガポールでメインサーバーを運用しており、国内で大規模災害が生じても影響を受けるリスクを抑えられます。
シンガポールは過去100年間で、地震や津波などによる大規模な被害が確認されていない地域です。電力供給も安定しており、停電でシステムが利用できなくなる可能性も低いでしょう。
災害時の連絡手段をお探しの方は、『安否確認サービス2』の導入をご検討ください。
本当に必要な防災グッズを見極めよう
企業は従業員の安全を守るよう、法的に義務付けられています。自然災害の規模やライフラインの被害状況によっては、事業所内で一定期間過ごす可能性も考えられます。従業員が安心して事業所内で生活を送れるよう、防災グッズの確保が必要です。
ただし、保管スペースや予算には限りがあるため、本当に必要なものを把握することが重要です。また、災害対策の強化には、定期的な防災訓練の実施や複数の連絡手段確保など、防災グッズの確保以外も複数の対策を講じなければなりません。
緊急時の連絡手段確保には、トヨクモの『安否確認サービス2』を選ぶのがおすすめです。『安否確認サービス2』は、多くの顧客からシステムの安定性に関して評価されています。
トヨクモではすべての契約企業を対象に、毎年全国一斉訓練を実施しています。全国一斉訓練とは、『安否確認サービス2』に災害発生時と同等の負荷をかけ、安定稼働するか確認するための訓練です。
訓練結果が、トヨクモの設定するサービス品質保証制度(SLA)の基準を下回ったことはありません。訓練の開始時刻は管理者にも公開されないため、従業員の防災意識を高める場としても活用できるでしょう。
災害対策の強化に取り組んでいる方は、『安否確認サービス2』の導入をご検討ください。