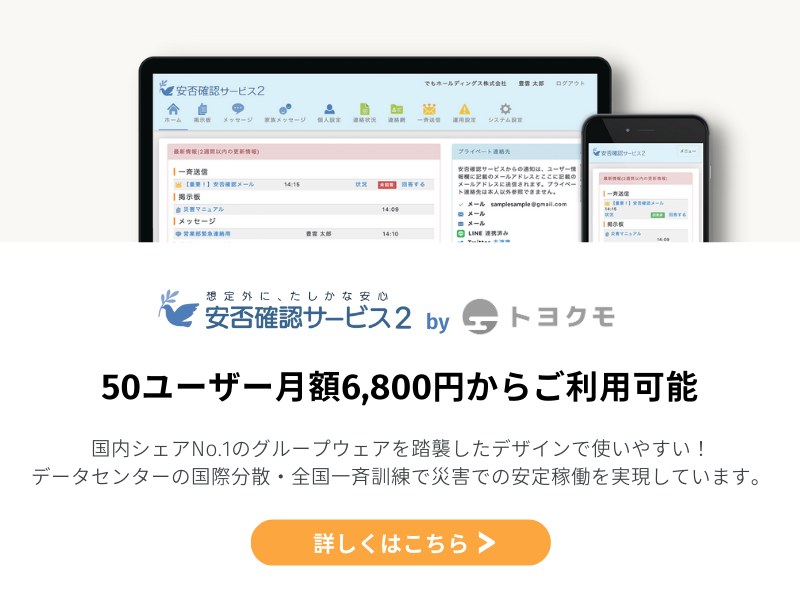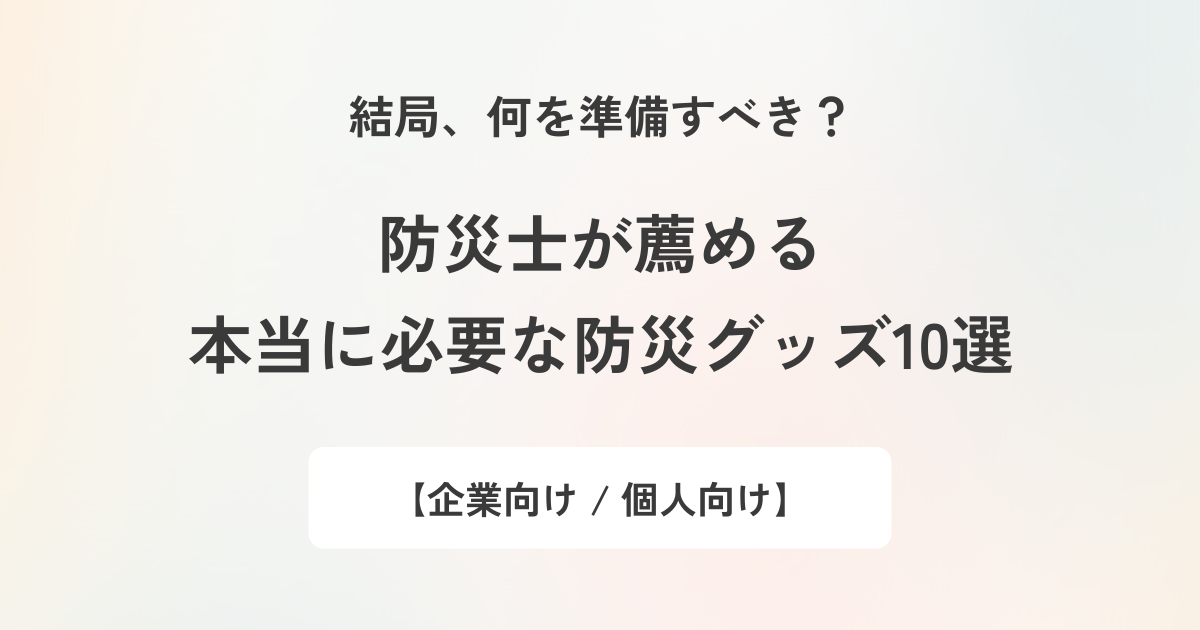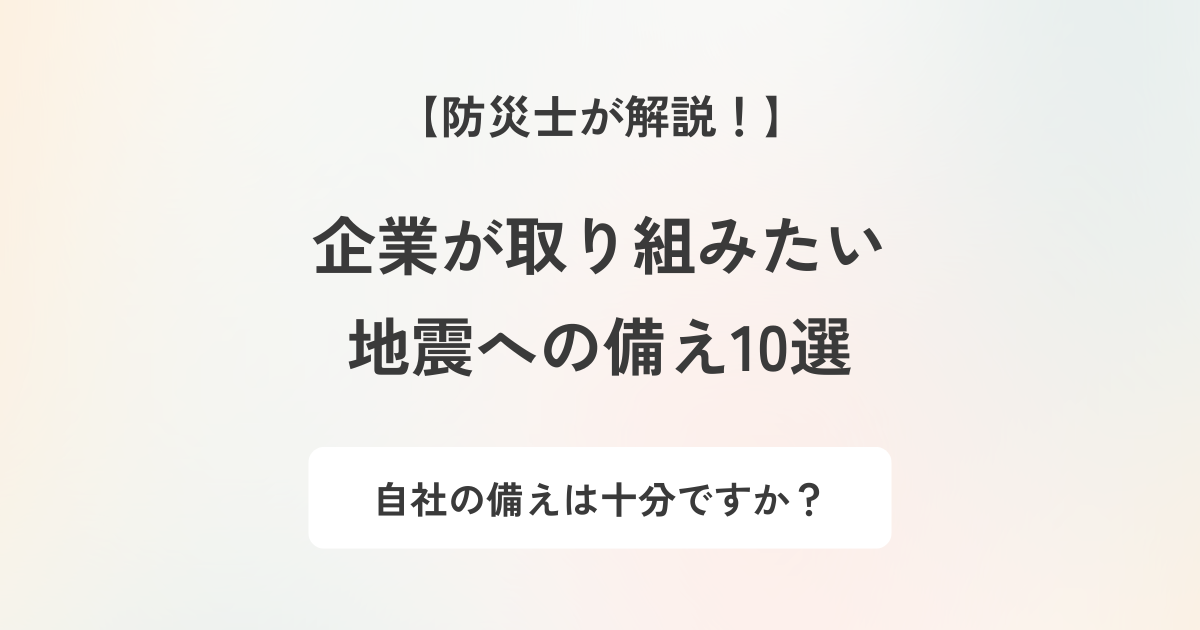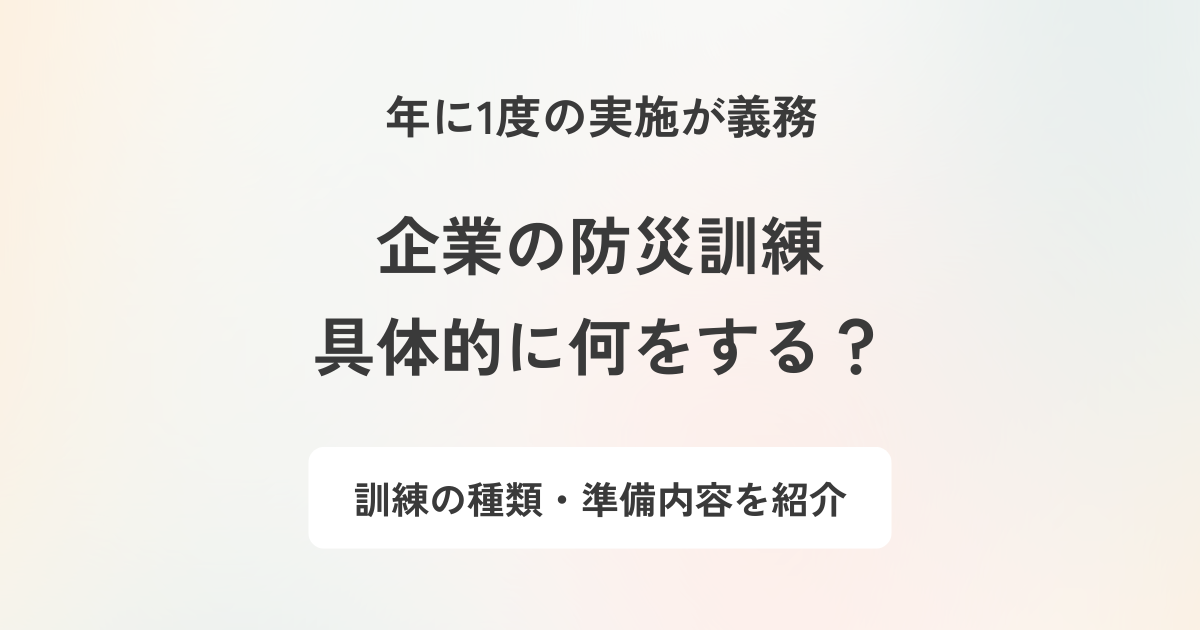災害時の所得税・法人税の減免とは?基本知識を分かりやすく解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
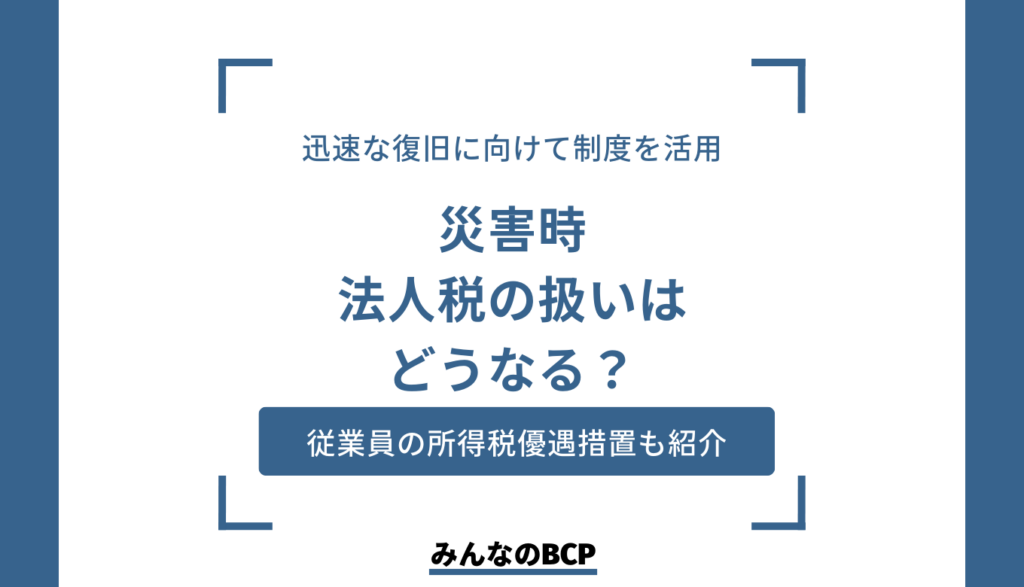
被災すると、一定の条件を満たせば税金の減免措置を受けられます。一方で税金の仕組みは複雑で、減免措置について十分に把握できていない方が多いのではないでしょうか。
この記事では、以下の2点について基本的な知識を分かりやすく解説します。
- 従業員向けの雑損控除や災害減免
- 事業者向けの法人税の優遇措置
これを読んで、自社の災害時の税金対策について考えるきっかけにしてください。



編集者:遠藤香大(えんどう こうだい)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部に所属。RMCA認定BCPアドバイザー。2024年、トヨクモ株式会社に入社。『kintone連携サービス』のサポート業務を経て、現在はメディア『トヨクモ防災タイムズ』運営メンバーとして企画・編集・校正業務に携わる。海外での資源開発による災害・健康リスクや、企業のレピュテーションリスクに関する研究経験がある。本メディアでは労働安全衛生法の記事を中心に、BCPに関するさまざまな分野を担当。
安否確認システムを選ぶなら、トヨクモの安否確認サービス2!
アプリ・メール・LINEで安否確認ができるほか、
ガラケーにも対応で世代を問わず使いやすいのが特徴です。
また初期費用0・リーズナブルな料金で導入できます。
下記のリンクから30日間無料お試し(自動課金一切ナシ、何度でもご利用可能)をお申し込みいただけます。
⇨安否確認サービス2を30日間無料でお試し
目次
従業員向け:雑損控除と災害減免
災害が発生したとき、雑損控除と災害減免の制度を活用すると所得税の優遇措置を受けられます。これらの措置は、災害で損害を受けた納税者が利用できる制度です。
雑損控除では、災害の影響で損害を受けた資産について、一定額の所得控除が受けられます。災害減免法では、損害額と所得額が条件を満たすと所得税の軽減や免除が可能です。
ここでは、制度の詳細について解説します。両者の比較表とあわせて、従業員に利用してもらう際の手順を確認しましょう。
雑損控除とは
雑損控除は、災害が発生したときに生活に必要な資産が受けた損害に応じて一定金額を所得から控除できる制度です。控除額の算出には、2種類の計算式を利用します。
- (損害額+災害関連支出−保険金額)−(総所得額)×10%
- (災害関連支出−保険金額)−5万円
2つの計算結果で、金額が高いほうを選択できます。
(参考:国税庁|災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除))
災害減免とは
災害減免法に基づき、所得税額を減免か免除できる制度があります。制度の要件は、住宅や家財の損害額が時価の1/2以上で、災害が発生した年の所得が1,000万円以下であることです。全額免除から1/4への軽減まで、受けられる措置には幅があります。
災害減免は、雑損控除との併用が不可能です。
(参考:国税庁|災害減免法による所得税の軽減免除)
災害減免と雑損控除の比較
災害発生年の所得が1,000万円以下であれば、災害減免と雑損控除のうち有利なほうを選択できます。
以下は、各制度の概要を比較した表の解説です。災害で資産が損害を受けたときは、控除できる金額と減免・免除される税額を比較し、どちらの制度を利用するか選びましょう。
| 災害減免 | 雑損控除 | |
|---|---|---|
| 災害の種類 | 自然災害のみ | 災害・盗難・横領 |
| 対象の資産 | 住宅または家財(損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上) | 資産(住宅、家財、現金、自家用車など) |
| 申し込み方 | 確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出 | 確定申告書に適用を受ける旨を記載し、「災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類」を添付し、所轄の税務署に確定申告書を提出 |
災害減免よりも、雑損控除のほうが広い対象範囲を持っています。災害減免はあくまでも住宅か家財が災害で損害を受けたときにのみ適用可能です。一方で、雑損控除は災害に限らず盗難や横領の被害でも適用できます。金銭や自家用車など、生活に欠かせない資産であれば対象に含まれます。
| 申告する年の前年の年収 | 災害減免 | 雑損控除 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | ⚪︎(適用できる) | ⚪︎(適用できる) |
| 1000万円以上 | ×(適用できない) | ⚪︎(適用できる) |
年収が1,000万円を超える従業員は、災害減免の適用ができません。従業員に告知する際は、年収を考慮したうえで適用可能な制度を伝えるとよいでしょう。
事業者向け:法人税の扱い
事業者が受けられる措置として、法人税の優遇措置が存在します。災害の発生に伴い、法人として利用している資産が損害を受けたときに受けられる措置です。
ここでは、法人税の納税額を軽減できる4つの仕組みを紹介します。
法人税は、益金(法人の利益)から損金(法人の費用)を引いた所得金額に、税率をかけて算出する税金です。損金に計上できる範囲の拡大や納税期間の猶予を受けることで、納める法人税の負担を軽減できます。
経営者の方は、災害に備えて法人税の優遇措置制度を把握しましょう。
災害による資産の損金算入
商品や店舗、事務所などが法人の所有する資産です。災害の影響で滅失、損壊などの被害を受けた資産は、その損失額や費用を損金に算入できます。
損金に算入できる損失や費用には、具体的な要件が定められています。詳しくは以下を参考にしてください。
- 商品や原材料などの棚卸資産、店舗や事務所などの固定資産が損害を受けた場合の損失
- 損壊した資産の取り壊しや除去の費用
- 土砂やその他の障害物の除去の費用
棚卸資産や固定資産は企業の運営に欠かせず、災害で被害を受けた際は損失額を損金に算入できます。取壊し・廃棄・引き取りにかかる費用も算入が可能です。
また、災害で発生した障害物を除去する費用も、あわせて損金算入が認められています。
(参考:国税庁|災害を受けたときの法人税の取扱い)
評価損
棚卸資産・固定資産・一定の繰延資産が災害の影響で損傷を受けたときは、評価損を計上することで損金を増額できます。評価損とは年度中に資産の価値が下がった際に、元々の帳簿価格との差額を費用として損金に計上する仕組みです。
たとえば、災害の影響で販売できないほどの損傷を受けた在庫商品や、機能や品質が著しく低下した業務用の機械装置などが評価損を計上する適用対象にあたります。
その期における最初の帳簿価額と被害を受けたあとの時価、その差額分について損金算入が可能です。
滅失や損壊に至るまでの被害は受けていないものの、損傷がみられる資産に利用できる制度といえます。前述した損失の計上に代わり、評価損を適用できる可能性があります。
(参考:国税庁|災害を受けたときの法人税の取扱い)
復旧費用
災害の被害を受けた固定資産の復旧に要した費用も、損金に算入できるケースがあります。ここで復旧の対象とする固定資産は、評価損の処理をしたものを除いて「被災資産」の名称で取り扱います。
被災資産の復旧費用を損金算入する基準は、以下のとおりです。
- 被災資産を原状回復させるための費用は、修繕費として計上可能
- 補強工事や排水工事などで、被災する前の効用を維持する目的の工事費用は修繕費として計上可能
- 前述2つ以外の工事で、資本的支出か修繕費のどちらにあたるか明らかでないときは金額の30%を修繕費で計上可能
一般に資本的支出とは資産の改良につながる工事費用で、修繕費は原状回復や修理を目的とした工事費用を指します。資本的支出の費用は資産価額の増加として扱い、損金算入が不可能です。そのため、資本的支出と修繕費の区別が重要です。
(参考:国税庁|災害を受けたときの法人税の取扱い)
災害を受けた際の納税の猶予
法人税は、災害を受けたときに納税期限の猶予を受けられる制度があります。
全資産のうち20%以上にわたる損失が発生した事業者は、損失の発生日から1年以内に期限を迎える国税の納付で猶予を受けられます。
法人税では、以下2つのケースで猶予が可能です。
- 災害がやんだ日以前に課税期間が満了して納付期限が損失発生日以降であり、猶予申請日前に納税額が確定しているとき
- 中間申告をした法人税で、損失発生日以降が納付期限であるとき
前者は、納付期限から1年以内が猶予期間です。後者は、最長で確定申告書の提出期限(通常は翌年の3月15日)まで猶予されます。
猶予を受けるときは、「納税の猶予申請書」に必要事項を記載し、災害がやんだ日から2ヶ月以内に管轄の税務署へ提出しましょう。
(参考:国税庁|災害を受けたときの納税の猶予)
税金の優遇措置について理解し、BCPに組み込もう
今回の記事では、災害が発生したときに従業員や事業者が受けられる税金の優遇措置について説明しました。従業員向けでは所得税の減免措置が受けられ、事業者向けでは法人税の節約や納付猶予を受けられます。
優遇措置を受けるには、制度の仕組みを把握したうえで素早く手続きを実施する体制が重要です。素早い事務手続きは、BCP(事業継続計画)と関わります。
BCPとは、災害が発生したときに事業活動の停止を避けるべく、会社の継続を目指して策定する行動指針のことです。BCPで定める行動に、税金優遇の措置を含めることでスムーズに措置を受けられます。
税金優遇措置の受け方は、BCPマニュアルに含めておきましょう
BCPの詳細については、以下の関連記事をご参照ください。
関連記事:BCP(事業継続計画)とは?専門家がわかりやすく解説
関連記事:BCP対策のマニュアルの作り方【BCPコンサルタント監修のテンプレート付き】
今回紹介した制度の概要や要件を調べていただくとともに、BCPを策定して従業員に周知することをおすすめします。法人の資産だけでなく、従業員の資産を守る結果にもつながるでしょう。
事業の一刻も早い復旧には安否確認サービス2がおすすめ
被災した企業が経営へのダメージを最小限に抑えるには、税金の控除や減免措置を受けることが大切です。しかし、最も優先すべきことは、一刻も早く事業を再開して被災前のレベルに戻すことです。
そのためには従業員の安否を確認し、事業再開への目途を付けることです。
トヨクモが提供する『安否確認サービス2』は、安否確認を自動で送信し、回答をリアルタイムで集計できるツールです。従業員の安否を素早く確認し、いち早く事業を再開させることで、災害からのダメージを最小限に抑えられます。
『安否確認サービス2』の機能は、以下の動画でご確認ください。
安否確認システムを選ぶなら、トヨクモの安否確認サービス2!
アプリ・メール・LINEで安否確認ができるほか、
ガラケーにも対応で世代を問わず使いやすいのが特徴です。
また初期費用0・リーズナブルな料金で導入できます。
下記のリンクから30日間無料お試し(自動課金一切ナシ、何度でもご利用可能)をお申し込みいただけます。
⇨安否確認サービス2を30日間無料でお試し


編集者:遠藤香大(えんどう こうだい)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部に所属。RMCA認定BCPアドバイザー。2024年、トヨクモ株式会社に入社。『kintone連携サービス』のサポート業務を経て、現在はメディア『トヨクモ防災タイムズ』運営メンバーとして企画・編集・校正業務に携わる。海外での資源開発による災害・健康リスクや、企業のレピュテーションリスクに関する研究経験がある。本メディアでは労働安全衛生法の記事を中心に、BCPに関するさまざまな分野を担当。