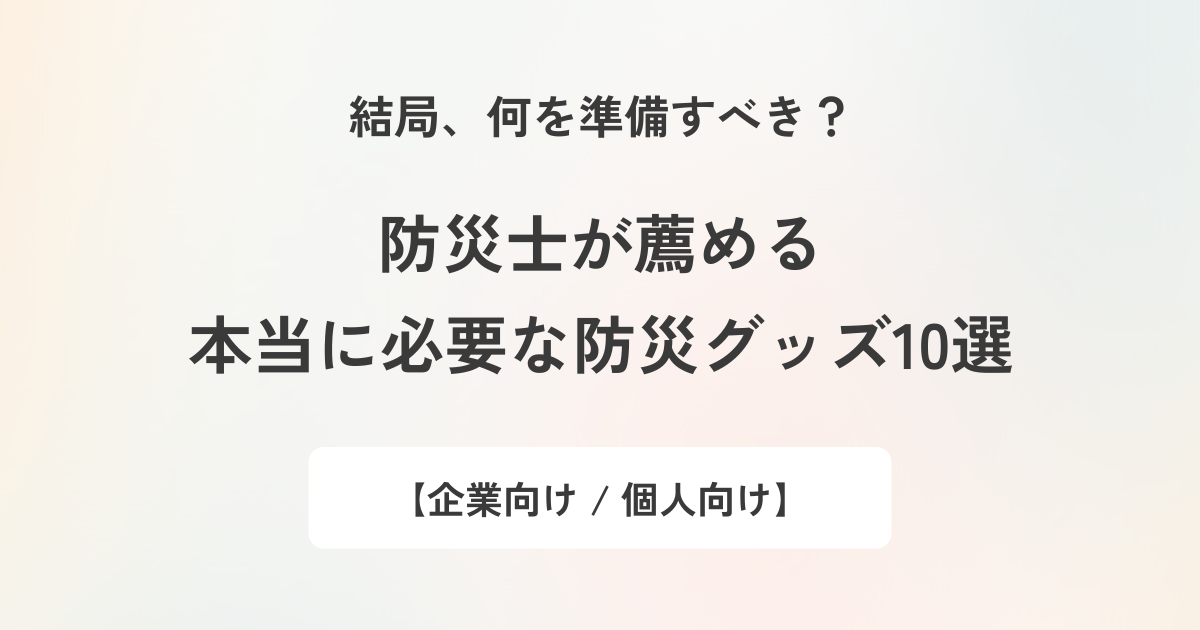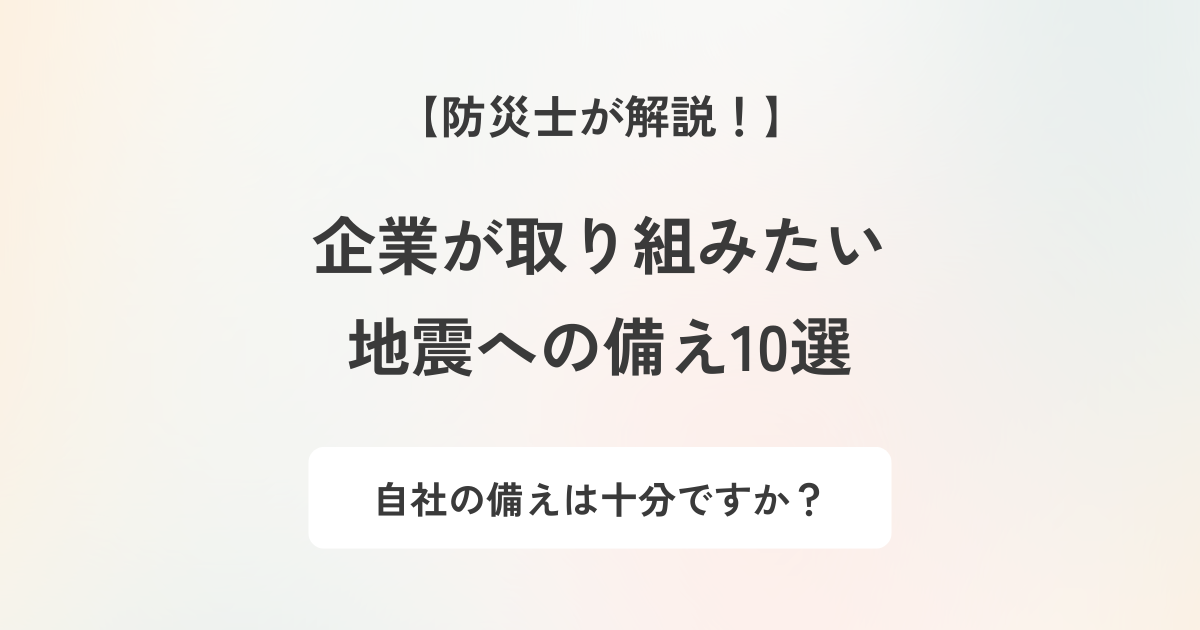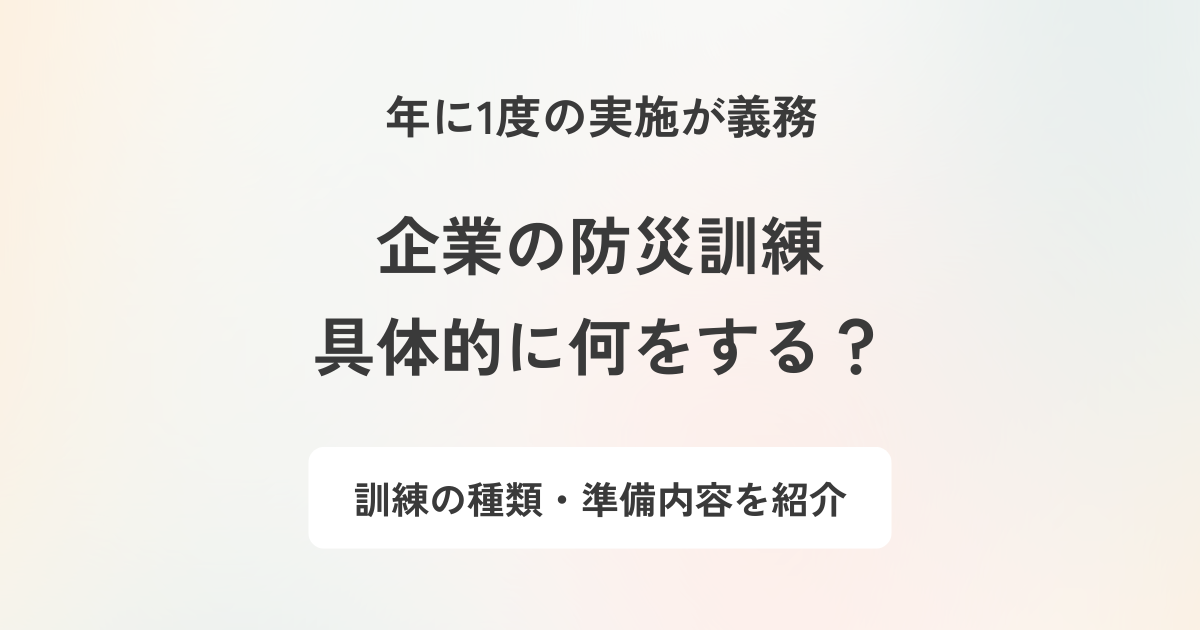【物流・運送業界の防災対策】災害時のドライバーがとるべき行動も紹介

坂田 健太(さかた けんた)

ネットショッピングの利用者が増加の一途をたどり、運輸・物流業界は私たちの生活に欠かせない存在となりましたが、災害発生時はその需要がさらに高まります。
しかし、その分ドライバーが被災する確率も同時に高くなるため、物流業界には防災対策が必要不可欠です。
そこで本記事では、物流・運送業界が抱える災害リスクや被災した際の適切な対応、災害発生後の安否確認方法などについて分かりやすく解説します。

目次
物流・運送業界における防災対策
物流・運送業界は、災害時こそ事業を継続することが求められますが、自社の業務の他に、緊急支援物資を供給するという非常に重要な役割を担うことになります。
つまり、自社を守るための防災対策が、被災地全体のライフラインを繋ぐことになるのです。
そうしたことを視野に入れた上で、防災時の対応を考えることが大切です。
物流・配送エリアのハザードマップの確認
自社の物流や配送エリアについて、あらかじめ国や自治体が発表しているハザードマップを確認しておくことで、災害発生時には従業員の避難や車両の移動などをスムーズに行うことが可能です。
また、自社の事業所や施設があるエリアの危険度について把握しておけば、台風や特別警報の可能性がある場合にも、ある程度早めに判断し、的確な指示を出すことができるでしょう。
社内で防災訓練や避難訓練を実施する際も、ハザードマップを参照しながら行うことで、有事の際は慌てることなく、必要があれば地域の方の誘導も円滑に行えるはずです。
BCP発動時の体制の確立と人的応援・支援体制の整備
そもそもBCPとは「事業継続計画」のことで、災害が発生して被災した状況下において、自社の損害を最小限に抑えつつ事業の継続もしくは復旧を実現するために、事前に計画しておくものです。
物流業界のBCPでは、以下のようなポイントを意識して策定します。
【事前の防災対策】
・ハザードマップによるリスク把握
・情報管理体制の確立
・避難、救難機材
・備蓄品
・通信手段の確立
・データのバックアップ など
【災害発生直後の対応】
・避難
・従業員の安否確認
・被害状況の把握
・顧客などの関係先への連絡
・社内での情報共有 など
【復旧のための施策】
・燃料の確保
・資金対策 など
災害発生時は、パニックに陥った状況下で多くの作業を同時にこなさなければなりません。
とくに会社の営業時間外や休日は、動ける従業員の人数を把握して召集するまでに、かなりの時間を要するでしょう。
そうなると初動に遅れが生じ、円滑な事業継続あるいは復旧が難しくなる可能性もあります。
そうした状況を避けるための第一段階として、安否確認システムは非常に有効な手段といえます。
BCPを策定する際は、併せてシステムの導入も検討してみましょう。
災害対策と備えるべきポイント
例えば地震や異常気象などで大規模な災害が起きた際、物流・運送業界ではさまざまな災害リスクが考えられます。
その中でも、とくに事業継続に大きな影響を与えると考えられるのが、これからご紹介する2つのポイントです。
ドライバーや車両が被災
常に広範囲を走り回っているドライバーは、いつどこで、どのような状況下で被災するか予測できません。
例えば長距離トラック運転手の場合、遠方で被災してしまい、そのまま連絡が取れなくなるといった労働災害のリスクも十分に考えられるでしょう。
また、特別警報級の大雨や津波などで、運転している車両そのものに故障などのトラブルが起こる事例も多くあります。
いずれのケースも運送事業の継続に大きな支障をきたすため、あらゆるケースを想定した対策を考えておく必要があるでしょう。
道路の寸断や通行止めによる配送のストップ
ドライバーが無事で、普段通りに動かせる車両が用意できたとしても、土砂崩れや倒木などにより道路が寸断されたり、冠水で通行止めになっていたりすれば、荷物の配送はできません。
それも物流センターまでの道路が寸断されているのか、幹線道路が通行止めで顧客の元へ届けられないのかなど、状況によって事情が変わってくるため、できるだけ早く状況を把握する必要があります。
発災後の措置
次に、物流会社としての災害時の対応方法について見ていきましょう。
避難
その場にいて危険が及ぶ可能性がある場合は、従業員を安全な場所まで避難させることが基本です。
日頃から、避難所や避難経路などについて社内で共通認識を持っておくと、いざという時焦らず安全な場所まで移動できます。
従業員一人ひとりの防災意識を高めるためにも、定期的に防災訓練や避難訓練を行いましょう。
従業員の安否確認
災害時、会社が事業を継続するためには、一人でも多く動ける人員を確保することが重要ですが、そのためには迅速な安否確認と状況把握が必要不可欠です。
とはいえ、災害発生直後はサーバーのパンクや基地局の被災などが原因で、電話やインターネットがつながらないという状況になることも多く、全従業員の安否確認をするのに何時間もかかってしまうケースが少なくありません。
そこで、近年安否確認システムを導入する企業が急増しています。
安否確認システムとは、災害が発生した際に従業員やその家族に対し、自動で安否確認メールを発信するシステムで、回答者はボタン1つで地震の状況を伝えることが可能です。
トヨクモの「安否確認サービス2」は、地震や津波が発生した時、あるいは特別警報が発令された時には、気象庁の災害情報に連動して自動で一斉に安否確認メールを送信します。
もともと大規模災害が発生することを想定してシステムが構築されているため、万が一の際にもサーバーがパンクすることはなく、安定して運用が可能です。
同時に従業員からの回答は自動集計され、未回答者には自動で再送信するリマインド機能も装備。防災担当者からの連絡だけでなく、掲示板機能を使うことで相互に情報共有をし合うこともできます。
本来であれば数時間かけて行うはずの安否確認作業を丸ごと委託できて初期費用は無料、ランニングコストも安価で操作も簡単ということで、運送業界でも注目を浴びる存在です。
事業所や車両の被害把握
運送業者にとって、破損や横転などで車両自体が使用できなくなってしまうことは、事業を継続するにあたって致命的ともいえます。
災害発生後は、事務所や車両において、どこでどのような被害が発生しているのかという現状を、迅速かつ正確に把握する必要があります。
また、車両の被害状況を確認する際、併せて燃料の残量も把握しておくことがポイントです。
災害が発生すると、決まってガソリンスタンドには長蛇の列ができ、やっと給油できたとしても給油量に制限がかけられてしまいます。
いくら車両が無事でも燃料がなければ事業が継続できないため、日頃から半分以上は燃料が入った状態を維持する、物流事業者間で情報交換を行うなど防災対策をしておくと安心です。
社内への情報共有
災害時にそれぞれが適切な行動を取るためには、被害状況や安否情報などを社内で共有できる環境が求められます。
そのためには、勤務中・勤務外どちらであっても確実に互いの状況が確認できる仕組みが構築されていることが理想です。
そうすることで、会社としても迅速に全体を把握でき、的確な行動指示を出すことが可能となるでしょう。
日頃からコミュニケーションが盛んな会社ほど、いざという時にも意思疎通がしやすく被害を抑えられると言われていますが、日中ほとんどの従業員が外に出ている運送業では、積極的にコミュニケーションを取るのは難しいところです。
それをカバーするためにも、安否確認システムなどを導入し、災害時にツールを統一することを選択肢の一つとして考えましょう。
関係先への連絡
災害の影響で荷物の配送に遅延などが発生する場合、速やかに顧客や配送先に連絡をしましょう。
ドライバーの安全確保のため、一時的に業務を停止せざるを得ない状況になる可能性もあり、一方的に伝えづらいという課題はあります。
とはいえ「緊急時だし大丈夫だろう」などと軽い気持ちで放っておくと、のちに賠償問題に発展するリスクも否定できません。
必ず遅延が発覚した時点で連絡し、代替案を話し合うなど関係先に向けて協力を仰ぐことで良好な関係を維持できます。
荷主と物流会社の連絡機能の確保
災害時も円滑に事業を継続させるためには、荷主と物流会社間の連携体制が必要不可欠です。
日頃から、有事の際の連絡ツールや対応についての認識をとにしておき、情報共有や協力ができる環境を構築しておくことで、スムーズに初動対応を行えます。
復旧作業開始
従業員の安否確認ができ、事業を継続できる人員や車両が確保できることが分かったら、事業再開のために復旧作業を開始しましょう。
抱えている業務をリスト化し、優先順位の高い順に実行します。
被災下では、いくら気丈に振る舞っていても、従業員は少なからずストレスを感じているものです。
心理面のケアも考慮に入れ、過労などの二次災害の防止に努めることが大切です。
ドライバーが運転中に被災したときの適切な防災対応
荷物の配送中に地震や台風などが発生し、被災する可能性は大いにあります。
ドライバーはもちろん、企業の防災担当者は、そんな時どのように対応すべきなのかしっかりと理解し、いざという時の防災対応について周知させておかなければなりません。
ここでは、災害発生時の適切なドライバーの対応について解説します。
ハザードをつけ少しずつ減速する
運転中に揺れや危険を感じたら、すぐにハザードランプをつけて車を減速させる必要がありますが、絶対に急ブレーキをかけてはいけません。
運転手を含め周囲がパニック状態に陥り注意散漫になっている可能性が高いため、必ず周りの様子を見ながら徐々に減速します。
高速道路を運転中は、さらに注意が必要です。
急に停止すると大規模な追突事故を引き起こす可能性があるため、慎重に減速して車を停車させましょう。
まずは落ち着いて車内に留まる
揺れが収まったからと言って、すぐに車外に出るのは非常に危険です。
地震発生時、揺れを感じるタイミングは人や車によって異なるため、慌てて飛び出して後続車に轢かれてしまうというケースが実際にあるのです。
自分だけでなく、周りの状況が落ち着くまでは車内で待機するのが基本です。
車内でラジオを使い情報収集
車内で状況が落ち着くのを待っている間に、ラジオを利用して情報収集を行いましょう。
インターネットが利用できる状態であれば、スマートフォンやタブレットなどを使った情報収集も可能ですが、大規模地震などの場合は通信機器が使えなくなる可能性があるため注意が必要です。
身を守るためにも、地震の震度や規模、周辺道路の状況などについて情報を得た上で、適切な行動を取るよう心がけましょう。
代替ルートの有無を探す
ドライバーの無事が確認された上で、周囲の道路が寸断されたり、通行止めになったりして進めなくなった場合は、業務を継続するために代わりのルートを探します。
リアルタイムの情報を反映する地図アプリや、GPSアプリを活用すると現在の位置情報から効率的に代替ルートの有無を把握できます。
運転する車両の安全管理
運転中に被災した場合、運転していた車両に影響が出ることがあります。
明らかな故障から、ちょっとした違和感までさまざまな症状が考えられますが、少しでも異常を感じた場合は、すぐにその場で確認しましょう。
車両にトラブルが起こった際、どのように対応するかを事前に社内で決めておくと混乱を防げるでしょう。
また、災害時の異常に気付くためにも、日頃から定期的に点検やメンテナンスを実施することで、車の正常な状態と異常な状態を見分けられるようにしてください。
災害時の需要に応えるには従業員の安否確認が第一
今回は、物流・運送業界における災害リスクや防災対策、災害発生後の安否確認方法などについて詳しく解説しました。
物流・運送業界は、災害発生時にはいつも以上に需要が高まる一方で、被災地で緊急支援物資を運ぶという大きな役割も担う存在です。
被害を乗り越え、できる限り速やかに事業復旧をするために、何より重視すべきは従業員の安否確認といえるでしょう。
被災下で電話やインターネットの使用に支障が出る中、確実に安否確認を実行し、迅速な初動対応に移行するためには、ITシステムを駆使した防災対策、安否確認システムを使った従業員の状況把握などが有効です。
この機会に一度導入を検討してみてはいかがでしょうか。