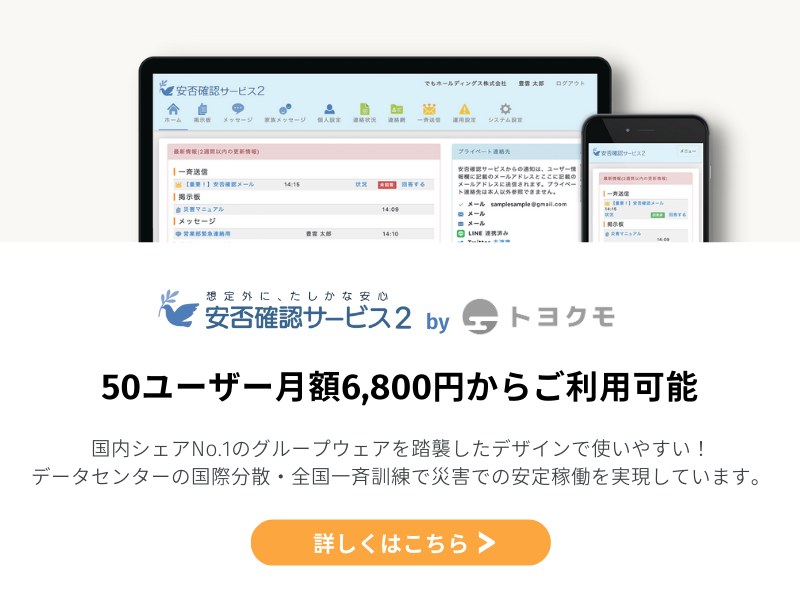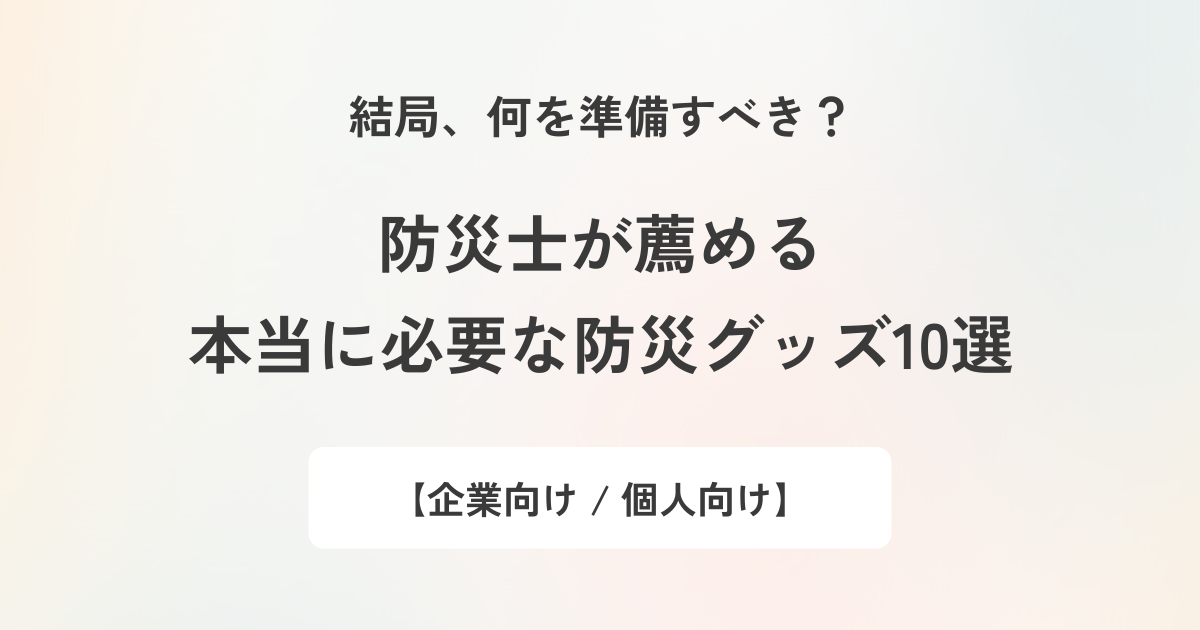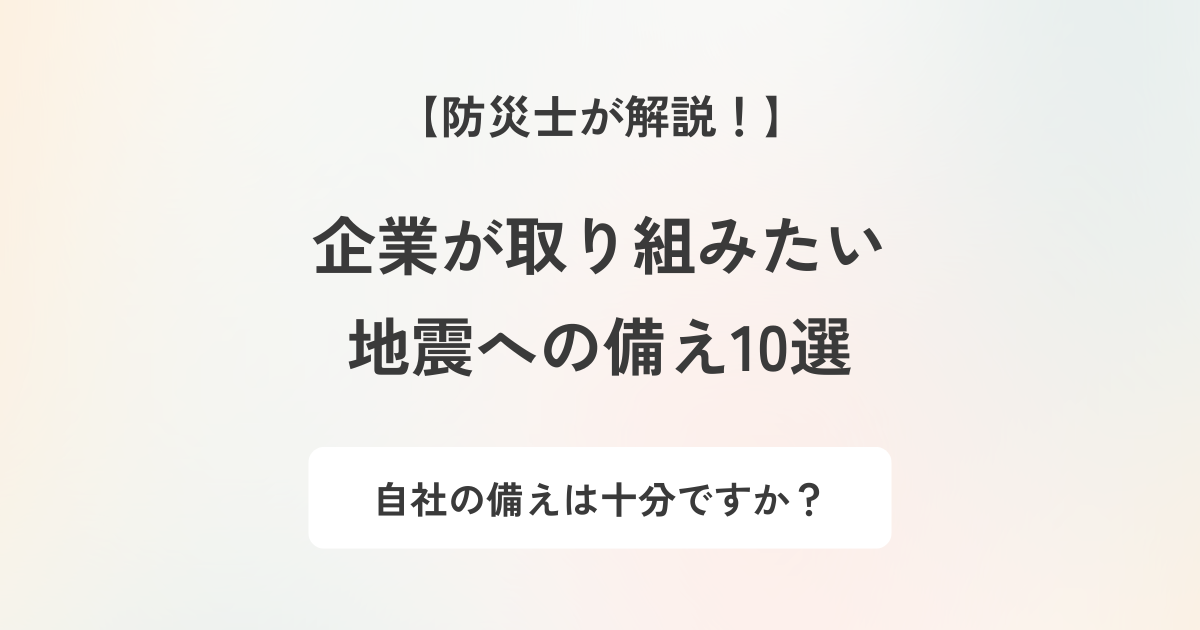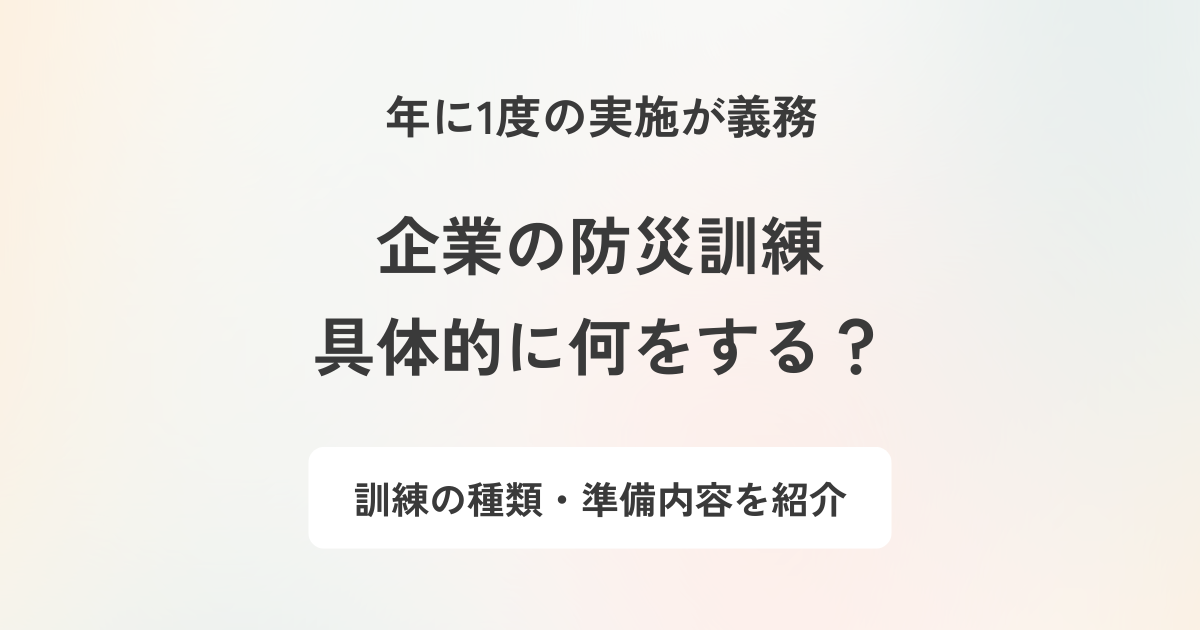地震で起きる液状化現象とは? 被害を受けやすい土地の特徴や対策も紹介

遠藤 香大(えんどう こうだい)
地震が起こると揺れによって地盤が緩み、液状化現象を引き起こしやすくなります。液状化現象は建物の倒壊や傾き、交通傷害などを招く要因ともなり、日々の生活に大きな影響をもたらします。そのため、いつ大規模な地震が発生しても身の安全を守れるように、事前に対策を講じておかなければいけません。
そこでこの記事では、地震による液状化現象の概要やその影響を紹介します。被害を受けやすい土地の特徴や対策も紹介しているので、あわせて参考にしてください。



編集者:坂田健太(さかた けんた)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部 プロモーショングループに所属。防災士。
企業の防災対策・BCP策定を支援するメディア「トヨクモ防災タイムズ」を運営。防災・BCPの専門家として、セミナー講師や専門メディアでの記事執筆も行う。
主な執筆記事に「BCPって何? ~中小企業の経営者が知っておくべき基礎知識~」「他人事では済まされない! BCP未策定が招く経営危機と、”備える”ことの真の価値とは?」(ともにニッキン ONLINE PREMIUM)などがある。
BCPを策定できていないなら、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用をご検討ください!
早ければ1ヵ月でBCP策定ができるため「仕事が忙しくて時間がない」や「策定方法がわからない」といった危機管理担当者にもおすすめです。下記のページから資料をダウンロードして、ぜひご検討ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
目次
地震で起きる液状化現象とは
地震で起きる液状化現象とは、地震の強い揺れによって地盤が液状になる現象です。地盤がドロドロの液体になると建物や道路などを支えられず、地震の被害がより甚大になります。
地震による液状化現象の原因は、強い揺れによって地盤の中にある砂粒の安定性が崩れることです。通常、地盤の中には地下水があり、その中は砂粒同士がかみ合って安定性を保っています。
しかし、ここに地震の揺れが加わると一時的に砂粒同士が外れ、安定性が低下して地盤が緩みやすくなります。地下水の表面に近い部分でこの現象が起こると、よりる液状化しやすく、大きな被害につながる仕組みです。
▲出典:地震・大雨と地盤災害
なお、液状化などの自然災害による被害を軽減するには、事前の準備が非常に重要です。とくに企業は自然災害後に事業の早期復旧を目指さなければ、企業そのものの存続にも悪影響をもたらします。迅速に行動をするためにも、万全な備えは必須と言えるでしょう。
自然災害への備えにはトヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』がおすすめ
自然災害発生後に事業の早期復旧を目指すには、BCP(事業継続計画)の策定がおすすめです。BCPとは自然災害をはじめとする非常時に、事業資産の損害を抑えながら事業の早期復旧を目指す計画です。非常時を想定した計画をあらかじめ立てておくことにより、自然災害発生時の行動を迅速にします。
BCPには会社の重要施設が災害で使用できなくなった場合の代替案なども含まれており、液状化によって大きな被害が生じたときにも役立ちます。液状化による影響が長期化する場合を想定したBCPを策定していれば、事業への影響も最小限に抑えられるでしょう。
(参考:3.2.1 事業継続のための代替策の特定と選択をする)
BCPの策定がまだの方には、トヨクモが提供するBCP策定支援サービス(ライト版)の活用がおすすめです。BCPコンサルティングは数十〜数百万円ほどするのが一般的ですが、トヨクモの「BCP策定支援サービス(ライト版)」であれば1ヵ月15万円(税抜)で提供できます。また、最短1ヵ月で策定できることから、すぐにでも取り入れたい方にもおすすめです。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
液状化現象の被害を受けやすい土地の特徴
液状化現象の被害を受けやすい土地には、以下のような特徴があります。
- 埋立地にような新しい土地
- かつて池や沼があった場所
- 大河川の沿岸部
- 砂丘間低地
土地の特徴や状態によって液状化の発生傾向に強弱はあるものの、上記に当てはまる場合は注意しなければいけません。
▲出典:地形区分に基づく液状化の発生傾向
それぞれについて解説します。
埋立地のような新しい土地
造成後あまり年月が経っていない埋立地のような新しい土地では、液状化現象が発生する危険性があります。東日本大震災にて発生した液状化現象では、造成後50年〜60年以内の土地での被害が目立ちました。
かつて池や沼があった場所
かつて池や沼があった場所も、液状化現象が起こりやすい土地と言えるでしょう。池や沼を埋め立てた土地は地下水位が高く、土や地盤の状態によっては、内陸部であっても液状化現象の発生条件に当てはまる場合があります。
大河川の沿岸部
大河川の沿岸部や下流域は地下水位が高く、地盤の締まりが緩い傾向にあります。とくに砂質地盤の層では、液状化現象が起こる危険性は高いでしょう。よく氾濫する河川の合流部や屈曲部は注意が必要です。
砂丘間低地
主に日本海沿岸や鹿島灘などに分布する砂丘は、長年にわたって砂が蓄積されてできたものです。砂丘の砂は一様に同じ大きさで、かつ砂丘間の低地は地下水位が高いため、液状化は起こりやすいと言えます。
液状化現象によって起こる影響
液状化現象は、1964年に発生した新潟地震で広く知られるようになりました。その後も大規模な地震が発生した際には、以下のような被害をもたらしています。
- 砂や水の噴出
- 地中構造物への影響
- 給排水の障害
- 建物の傾き・倒壊
- 交通障害・事故の誘発
それぞれについて解説します。
砂や水の噴出
▲出典:(4) 2016年熊本地震の事例 (液状化被害の事例)
液状化現象によって地中の水圧が高くなると、砂や水が地面から噴出しやすくなります。すると地面が砂や水だらけになり、道路が使えなくなったり、車や自転車が土砂に埋もれてしまったりします。交通障害を引き起こすと避難の妨げになるだけではなく、物流が停止して生活に必要な物資が手に入りにくくなるかもしれません。
また、緊急車両が通れないと負傷者を搬送できず、救助活動にも影響を及ぼします。さらに、道路が塞がれることによって事故を誘発してしまう可能性も高まるでしょう。
他ほかにも、田畑が水没したり砂で埋もれたりすることによるで、農作物への被害も考えられます。水分が乾いたあとに土砂が舞い散る粉塵被害も予想されるなど、日常生活に大きな影響を与えます。
地中構造物への影響
▲出典:下水道の地震対策を進めています|船橋市公式ホームページ
液状化現象が発生すると、水よりも軽いマンホールのような地中構造物が浮き上がってくることがあります。液状化した土砂がマンホール内に流れ込むと、下水道としての機能が果たせなくなり、人々のライフラインにも重大な影響を与えるでしょう。
これらの被害は応急復旧までに1ヶ月程度を時間を要するため、生活への影響が長引くと予想されます。
給排水の障害
▲出典:(3) 2011年東北地方太平洋沖地震の事例 (液状化被害の事例)
地中に埋設された上下水道の管路が、切断されてしまったり引き裂かれたりすることがあります。
切断部分から土砂が入ると、給排水の機能が停止し、ライフラインに多大な被害をもたらすでしょう。また、破損した周辺だけではなく、液状化現象が発生していない地域にまで被害は広がります。
たとえば、飲料水だけでなく、トイレやお風呂などの生活用水も使用できません。ほか他にもガス管が破損してしまうと、お湯が使えない、調理ができないなど不便な状態に陥ります。
この場合も、復旧までには1ヶ月程度の時間を要するため、日々の生活に大きな影響をもたらすでしょう。
建物の傾き・倒壊
▲出典:(4) 2016年熊本地震の事例 (液状化被害の事例)
液状化によって地盤沈下が引き起こされると、水よりも比重の重い構造物は傾きます。とくに、木造住宅は基礎が浅いため、影響を受けやすいでしょう。
建物が傾くと倒壊の危険性が高まるほか、扉や窓の開閉ができなくなったり、すき間やひび割れが発生したりなど、生活が困難となる場合があります。また、傾いた家で生活していると、体調に支障をきたす恐れもあるでしょう。
なお、主要な橋には液状化への対策が施されているため、橋が傾いたり落ちたりする危険性は以前より少ないと言えます。
地震による液状化現象を防ぐ対策
これまでご紹介してきたように、液状化現象が引き起こす被害は甚大です。
被害を少しでも回避するには、液状化現象の要因となるリスクを低くする必要があります。ここからは、液状化現象による被害を抑えるため、私たちにできる対策をご紹介します。
地震対策については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:地震の防災対策で企業が取り組むべき10の対策|備品や体制作りについて防災士が解説
事業所や建物周辺の地盤を調べる
建物を購入するときは、土地の事前調査がおすすめです。建物周辺の土地が、液状化現象の発生しやすい地盤であるかを確認しておくと、事前に必要な対策を講じることができます。
前述したように、新しい土地や大河川の沿岸部などは、とくにリスクの高い土地です。ほかにも洪水が発生しやすい土地は、地盤に水が溜まりやすく、液状化現象や地盤沈下のリスクが高まります。こうしたリスクのある土地を避けるために、ハザードマップを確認し、周辺の地盤を調べておきましょう。
ハザードマップの詳しい見方については以下をご覧ください。
関連記事:ハザードマップの見方とは|種類や企業における活用方法も紹介
工事や調査を検討する
ハザードマップよりさらに具体的で正確な調査を行うには、地盤調査がおすすめです。地盤にボーリングロッドを打ち込み、筒の入り具合や採取した土を参考に地質を調査します。
費用はかかりますが、地層の状態を正確に把握できるため、液状化現象が起こる可能性についてより詳しく把握できるでしょう。とくに液状化リスクの高い土地であれば、調査しておくことをおすすめします。
調査によってリスクが高いとわかっても、地盤改良や対策工事を行えば、液状化リスクを下げられます。もし液状化現象が発生しても被害を最小限に抑えられるよう、地盤、建物、基礎などの改良を検討してください。
保険へ加入する
液状化現象への対策として、保険を活用するのも有効策です。
自然災害を完全に防ぐことは不可能です。そのため、どれほど万全の対策を行っていても、
大規模地震が発生すれば液状化現象を避けられない場合もあるでしょう。とくに液状化現象はライフラインへの影響が大きく、復旧にも相当の時間を要します。
保険に加入していると、地震による液状化現象で被害が出たとしても、保険金で補償してもらえます。万が一、液状化による被害が発生した際は、保険会社に連絡して補償内容を確認しましょう。
地震への備えにはトヨクモの『安否確認サービス2』も活用しよう
地震はいつ発生するか予測できないため、液状化現象への対策だけではなく、あらゆる備えをしておかなければいけません。備えをより強化するには、トヨクモが提供する『安否確認サービス2』の活用がおすすめです。安否確認サービス2とは、気象庁の情報と連動して、従業員に安否確認メールを自動で送信するシステムです。従業員からの回答結果も自動で集計・分析できるため、安否確認にかかる手間を大幅に削減できます。
また、安否確認とともに従業員やその家族の被害状況も把握できるため、事業の早期復旧に向けての行動も起こしやすいでしょう。メッセージ機能や掲示板機能を活用すると今後の議論もでき、BCPにも役立てられます。従業員の命を守りながら、事業の損害を最小限に抑えたい方はぜひ利用を検討してください。
地震による影響化現象への対策を万全に
液状化現象は、地盤の緩い土地で起こりうる災害です。
液状化現象が発生すると建物が沈下・倒壊したり、交通障害が起きたりと生活に甚大な影響をもたらします。
被害を最小限に抑えるためには、地盤の特徴を事前に調べておき、必要に応じた対策を講じておきましょう。
地震への備えには、トヨクモの『安否確認サービス2』の活用もおすすめです。初期費用不要かつ30日間のトライアル期間を設けているため、自社に合ったシステムかどうかを確かめたうえで導入できます。地震をはじめとする自然災害への備えを強化したい方は、ぜひ無料体験からお試しください。


編集者:坂田健太(さかた けんた)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部 プロモーショングループに所属。防災士。
企業の防災対策・BCP策定を支援するメディア「トヨクモ防災タイムズ」を運営。防災・BCPの専門家として、セミナー講師や専門メディアでの記事執筆も行う。
主な執筆記事に「BCPって何? ~中小企業の経営者が知っておくべき基礎知識~」「他人事では済まされない! BCP未策定が招く経営危機と、”備える”ことの真の価値とは?」(ともにニッキン ONLINE PREMIUM)などがある。