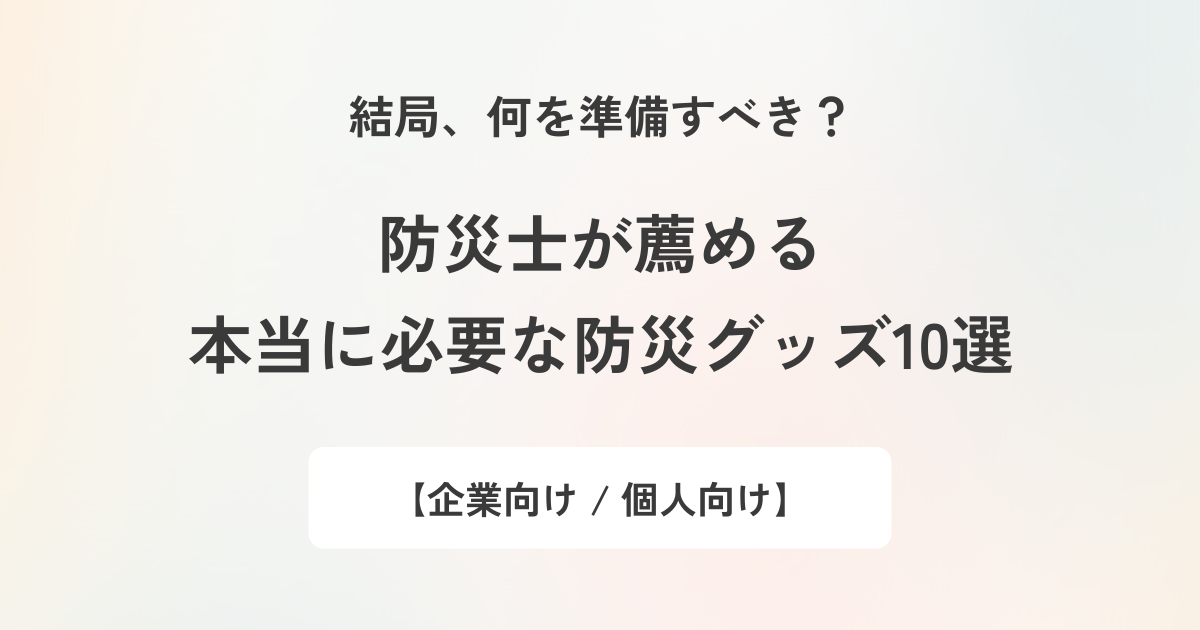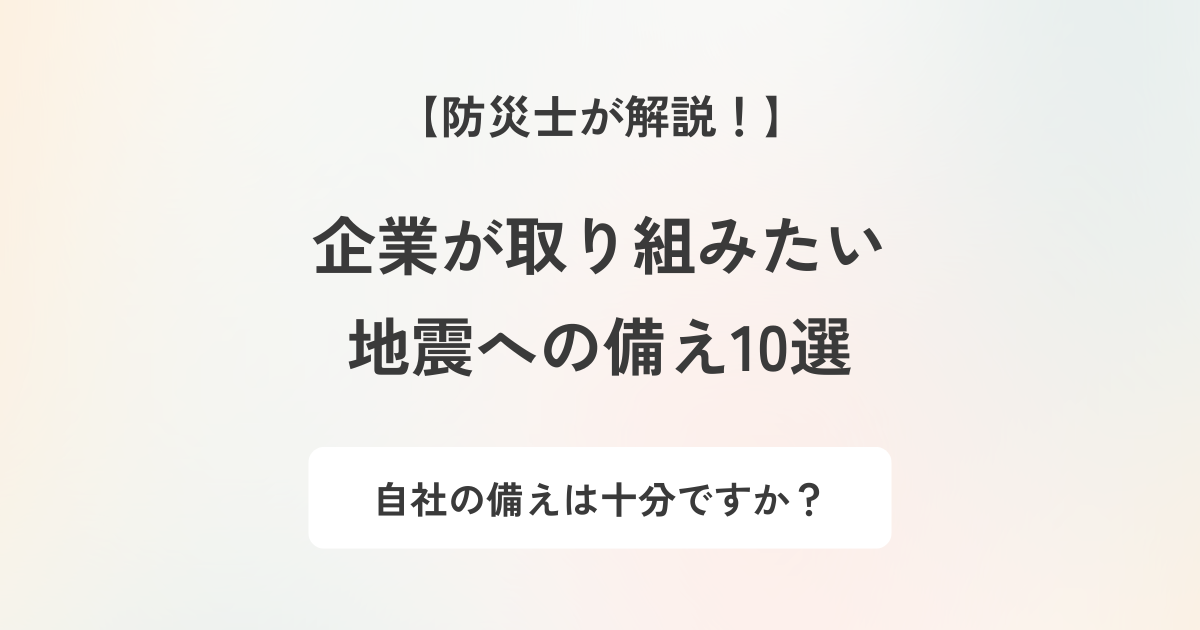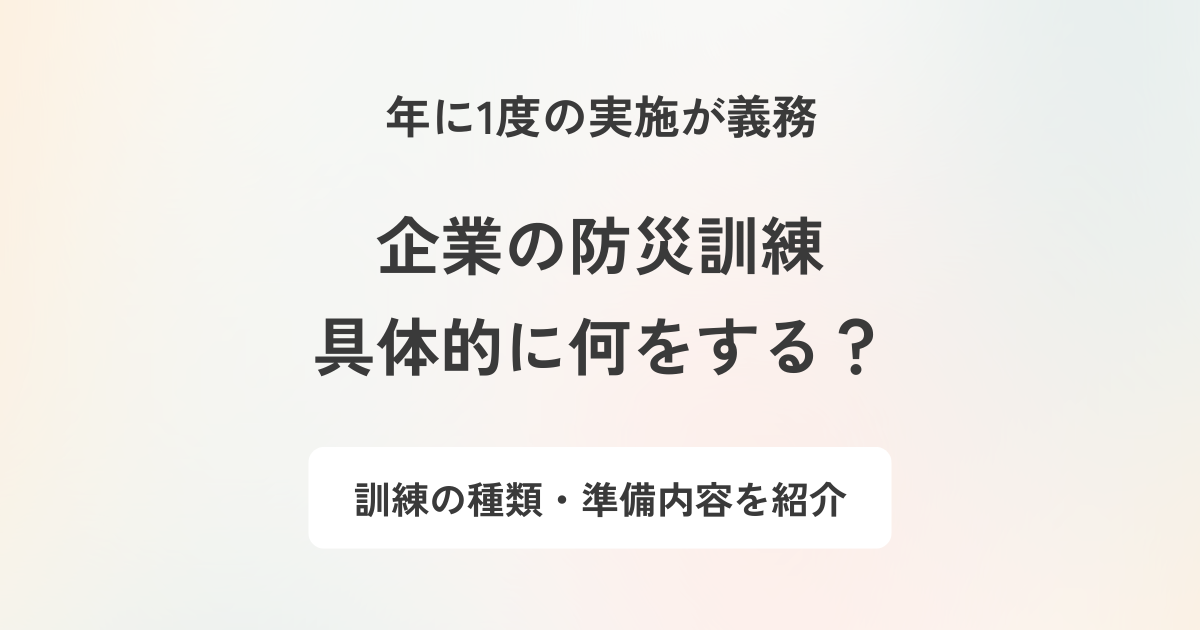避難勧告とは?警戒レベルや求められる行動について紹介

遠藤 香大(えんどう こうだい)
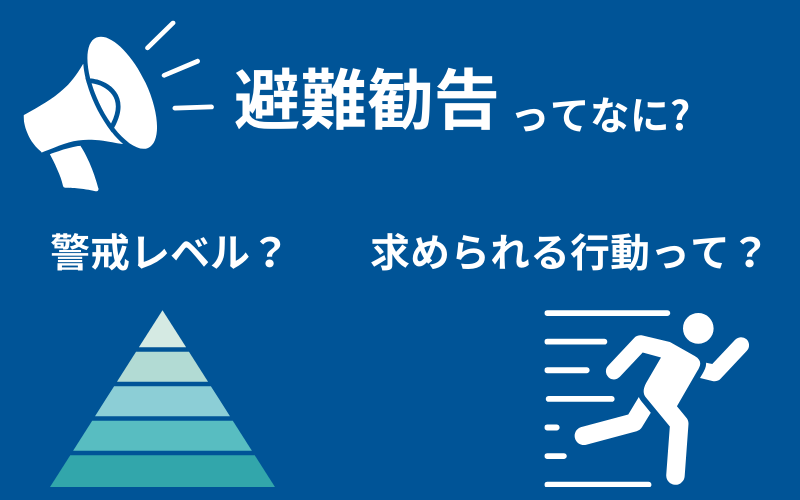
避難勧告は、テレビのニュースで耳にする言葉です。しかし「どのような警戒レベルなのか」「具体的に何をすればよいのか分からない」といった疑問を持つ人も少なくありません。
そこで今回は、避難勧告や避難に関する情報について詳しく紹介します。現在の避難に関する情報についての知識を深め、いざというときに自分や周りの人の命を守れるようにしておきましょう。

兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。
目次
避難勧告とは
そもそも避難勧告とは、どのようなものなのでしょうか。
ここでは、避難勧告の概要や避難指示との違いについて紹介します。
避難を促す情報
避難勧告は、自然災害から住民を守るために避難を呼びかける公的な指示として、過去に用いられていました。呼びかけは法律に基づいて実施され、特定の地域を対象に行われていました。避難勧告を出す人は自治体の長で、発令の際の基準は自治体によって異なっていました。
ただし、この勧告には法的な拘束力はなく、避難の呼びかけがあった際に逃げなかったとしても法的に罰せられる心配は不要でした。ただし、自身の安全確保のため、避難勧告があった際は速やかに安全な場所に移動することが推奨されていました。
2021年5月に廃止
避難勧告という用語は、法律が変わり廃止されました。2021年5月20日以降は、避難勧告という言葉は日本の制度上は存在しない言葉になっています。
変更の理由は、より緊急性の高い「避難指示(緊急)」という用語と似ているからです。以前は、どちらの指示を優先するとよいのかと混乱する声が多く聞かれました。
そのため現在は、避難勧告は自然災害時には利用されません。
もし、組織や地域の計画に「避難勧告」が行動の発動基準になっているものがあれば、すでに存在しない情報をきっかけに何かをしようとしているために、すぐに修正をしてください。
避難指示との違い
前述したように、避難勧告という言葉は、災害対策基本法の改正により2021年5月20日以降は廃止されています。それ以前は、避難勧告は避難指示より危険度が低い位置づけでした。
2021年5月20日までの自然災害に関する情報を危険度の高い順に並べると、次のとおりです。
- 1.災害発生情報
- 2.避難指示(緊急)
- 3.避難勧告
- 4.避難準備・高齢者等避難開始
- 5.各種注意報
- 6.各種早期注意情報
避難指示(緊急)は 危険が迫っている状態で、直ちに命を守る行動が求められました。一方、避難勧告は危険が迫る可能性があるものの、まだ余裕のある状態をいいました。
法律の改正後は2つの言葉は避難指示に統一され、警戒レベル4の段階で発令されます。警戒レベルについては詳しくは後述します。
避難指示との違いがなくなり、どちらが上位の指示なのか混同することはなくなりました。
警戒レベルについて
避難勧告と避難指示(緊急)が一本化されたことで、自然災害の警戒レベルにおける避難に関する情報も新しくなりました。
警戒レベルは、1段階から5段階で設定されています。数字が大きくなるにしたがって、危険度があがります。それぞれについて確認しましょう。
警戒レベル1は自然災害に備える
警戒レベル1は、最も危険レベルの低い状態です。直ちに求められる行動はなく、普段と変わらない状態です。
このレベルでは、気象庁から早期注意情報が出されます。警戒レベル1のときは大雨、高潮が警報級になる可能性を視野に入れておくとよいでしょう。
具体的には、次のような行動をおすすめします。
- 避難場所の確認をする
- 災害情報をこまめに確認する
- 防災用品を準備したり見直したりする
ただし、警戒レベル1が、あっという間に大災害になるケースも存在します。天気予報などで、今後の気象条件が悪化していく可能性がある場合には、情報収集や準備をしておくことが大切です。
警戒レベル2では避難行動を確認する
警戒レベル2は、気象庁から大雨や洪水などの注意報が発令されるような段階です。すでに雨が降っていたり、波が高くなっていたりする地域もあるでしょう。
注意報が発令された初期段階では、多くの人があまり注意を払いません。しかし、災害リスクが高まっていることを理解して準備することをおすすめします。
とくに高齢者や障がいのある人、妊婦など配慮の必要な人がいる家庭は、避難などの安全確保行動の準備を始めたり、必要に応じて早い段階から安全な場所に移動したりすることを検討してください。
上記に該当しない人たちも、最新の気象情報をこまめに確認して、必要な物資が足りていないようであれば準備をしましょう。
天気予報などで、今後。気象条件が悪化していくことが考えられる場合には、ハザードマップの確認などをして、家族で避難について打ち合わせをしておくといざというときに慌てないですみます。自然災害は急激に悪化する恐れがあるため、状況を見極めるようにしましょう。
警戒レベル3で高齢者の避難などの安全確保行動がはじまる
警戒レベル3は、すぐに安全確保できない人について、避難などの安全確保行動がはじまる段階です。高齢者や障害者、小さい子どもや妊産婦がいる家庭などは、避難などの安全確保行動を開始してください。
自分がいる場所が安全ならば、しっかりその場に留まり、いたずらに外出をしない、自分がいない場所が危険ならば、避難所などの安全な場所への移動を行ってください。
また、それ以外の人たちも、ハザードマップなどで、今いる場所が危険な場合には、避難行動を開始しましょう。自治体のホームページ・SNSなどの正しい情報を元にした行動が大切です。
避難をする場合には、近隣住民と協力して、安全を確保しながらの避難が求められます。このレベルでは安全確保行動が必要ないという人たちも迅速な行動を取れるように、こまめに情報をチェックして過ごします。
警戒レベル4は全員が避難などの安全確保行動をする
警戒レベル4は、避難指示に相当するレベルです。発令するのは市町村で、気象庁が発表する危険度の分布「キキクル」では紫色で表示されます。その段階では大きな被害が出ていなくとも、今後の状況を勘案して発令されるケースもあります。
このレベルの段階では、自然災害の危機が差し迫っていると認識し、対象地域の人たちは全員、速やかに避難などの安全確保行動をしましょう。警戒レベル4は、速やかに安全確保をする段階です。安全な場所への避難が必要な場合には家族や近隣住民の命を守るために、お互いに声がけをしながら避難するなど、安全を確認しましょう。
警戒レベル5になると緊急に安全を確保する
警戒レベル5は、リスクが最も高い状態です。どこかですでに災害が発生しているような段階で、もはや移動をともなった避難が困難になる可能性があります。避難する場合には、可能な限り警戒レベル4で避難を完了させておくことが望ましいです。命を守る行動を優先しましょう。
たとえば、浸水がはじまり逃げ遅れてしまったときは、2階以上に避難したり、崖とは反対の部屋に移動したりするような行動を取ります。
既に避難を完了している人は、自治体の指示に従いその場に留まってむやみに外出しないなど、冷静な判断と行動が求められます。
警戒レベル4で求められる行動
ここからは、避難指示に相当する警戒レベル4での行動について詳しく紹介します。先ほども言ったように、このレベルでは発令地域のすべての人々が対象になります。
万が一のときに備えて、きちんと覚えておく方がよいでしょう。
危険な場所から離れる
このような危険度の高い状態になったら、危険な場所から逃げる・離れるという行動が大切です。避難所や避難場所の情報を確認し、事前に調べておいた避難経路で逃げましょう。
とくに住まいや勤務先が次のような場所に近い人は、ハザードマップで危険性を確認した上で、早めの避難行動が求められます。
- 低地
- 河川や海岸の近く
- 地すべりやがけ崩れが発生しやすい場所やその周辺
- 過去に台風や強風の影響を受けたことがある土地
日頃から避難訓練をしたり、地域の自然災害の事例を確認したりして、迅速に安全確保する方法を考えておきましょう。
全員避難の意味を理解する
警戒レベル4は対象地域における全員避難の呼びかけですが、発令された市町村のすべての人々が外に出て、安全な場所まで避難行動をするという意味ではありません。ハザードマップで下記のような地域に住んでいることをまず確認しましょう。
- 浸水リスクの高い地域に住んでいる
- 過去に土砂災害が起きていたり、発生したりする恐れが高い地区に住んでいる
これらの地域に該当せず自宅が安全であればその場にとどまっても問題ありません。
大切なのは、自分や家族の安全を守ることです。そのために日頃から防災に関心を持ち、正しい判断ができるようにしておきましょう。
避難指示で慌てないために企業が事前にできること
避難指示は、従業員がいる時間帯に発令される可能性があります。そのような非常時に慌てないように、企業ができることを考えましょう。
避難場所を確認する
企業は、従業員が速やかに安全確保ができるように、ハザードマップなどで会社などの危険性を調べておきましょう。そして会社にいることが危険な場合には、周辺の避難場所を周知しておきます。
また、遠方から通勤している人や最近引っ越してきたばかりの人など、会社のある場所に土地勘のない従業員も少なくありません。そのような従業員が一目で避難場所が分かるように防災マップやハザードマップの活用をおすすめします。
社内の目立つ場所に掲示したり、防災マップにアクセスしやすい環境を整えたりするとよいでしょう。
内部リンク
会社周辺の地域と関係を築いておく
会社周辺の地域住民や自治体との関係作りをすることは、非常時に役に立ちます。いざというときの対応力が高められるほか、企業市民としての役割を果たすこともできます。
地域社会と関係を築いておけば、避難所などにも積極的に受け入れてもらえたり、自治体からの物資をスムーズに分配してもらえるなどの可能性があるでしょう。
一方で、自然災害発生時に会社の施設を避難場所として提供したり、災害備蓄品を地域住民に提供したりすると地域復興の手助けができ、企業のイメージアップにつながります。
普段から地域住民と一緒に避難訓練をしたり、自治体と協力したりして、いざというときに備えておくことが大切です。
防災用品を揃えておく
避難指示が出ることを想定し、従業員用の防災用品を蓄えておきましょう。自然災害の状況によっては、従業員が帰宅できずに社内にとどまる事態も想定されます。
具体的には、次の防災用品を用意することが望ましいです。
- 水
- 毛布
- 食料
- 携帯トイレ・非常用トイレ
- 医薬品
- 予備の電池
- 会中電と・携帯ラジオ
- 予備の電池・電源・バッテリー
- 防災用ヘルメット
避難期間が長期にわたることもあるため、多めに用意しておくことが求められます。
また、防災用品は定期的に見直すようにしてください。具体的には、備品に故障や不足がないか、賞味・消費期限のあるものは期限が切れていないか定期的に確認するようにしましょう。
防災用品を適切に管理して、いざというときにすぐ使えるようにしておきましょう。
安全確保方法を社内で共有する
安全確保方法を社内で共有しておくことで、従業員の命や安全を守れます。安全確保の方法を知らないと、緊急事態が発生した際に大きく動揺して動けない状態になりかねません。
とくに安全な場所への避難が必要な場合には、次のような避難方法に関連する情報はマニュアルにして、いつでも閲覧できるようにしておくことが求められます。
- 避難場所
- 避難方法
- 責任者・担当者
- 安否確認方法
これらのマニュアルは、従業員がいつでもみられるような場所に保存しておくことが大切です。変更があれば、速やかに全従業員に通達します。
全従業員が避難方法を正しく理解し、実行できるように努めましょう。
避難訓練を実施する
定期的に避難訓練を実施することは、企業が事前にできる防災対策です。避難方法を従業員が正しく理解できているかを確認したり、避難方法に問題がないかを見直したりできます。
避難訓練は、避難計画に基づいて実施します。緊急事態が発生したときの責任者が避難訓練でもリーダーを務めると本番に近い状態の訓練ができるでしょう。
避難訓練後は、反省点や参加した従業員からのフィードバックを集め、避難方法の改善や次回の避難訓練に役立てます。
内部リンク
迅速な安否確認の確保ができるようにする
避難指示が出た際、迅速に安否確認ができるように準備しておくとよいでしょう。
被災によって出勤の困難な従業員が多ければ、その後の災害対応や復旧における人員配置計画を見直すことが求められます。そのため、自然災害発生時の初動対応として安否確認を行う必要がありますが、通信障害などによって電話やメールでの確認が難しい事態も想定されるでしょう。
いざというときにスムーズに従業員の確認ができるように安否確認サービスの利用がおすすめです。たとえば、「安否確認サービス2」は、自然災害が起こったときに自動で安否確認メールが一斉送信されます。回答結果が自動で集計されるため、社員の状況がすぐに把握でき、今後の復旧計画に役立てられます。
避難に関する情報を理解し、日頃から防災意識を高めよう
避難勧告は、現在では避難指示に統一され、存在しない制度になりました。
自然災害の多い日本では、いつどこで避難指示が出ても不思議ではありません。万が一に備えて、企業は避難場所を共有したり、防災訓練を実施するなど防災対策を日頃から行う必要があります。
また、社員の安否確認をスムーズに行うために、安否確認システムの導入がおすすめです。簡単に従業員の状況が把握でき、事業の迅速な復旧に役立つでしょう。安否確認システムをご検討の方はぜひお問合せください。
兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。