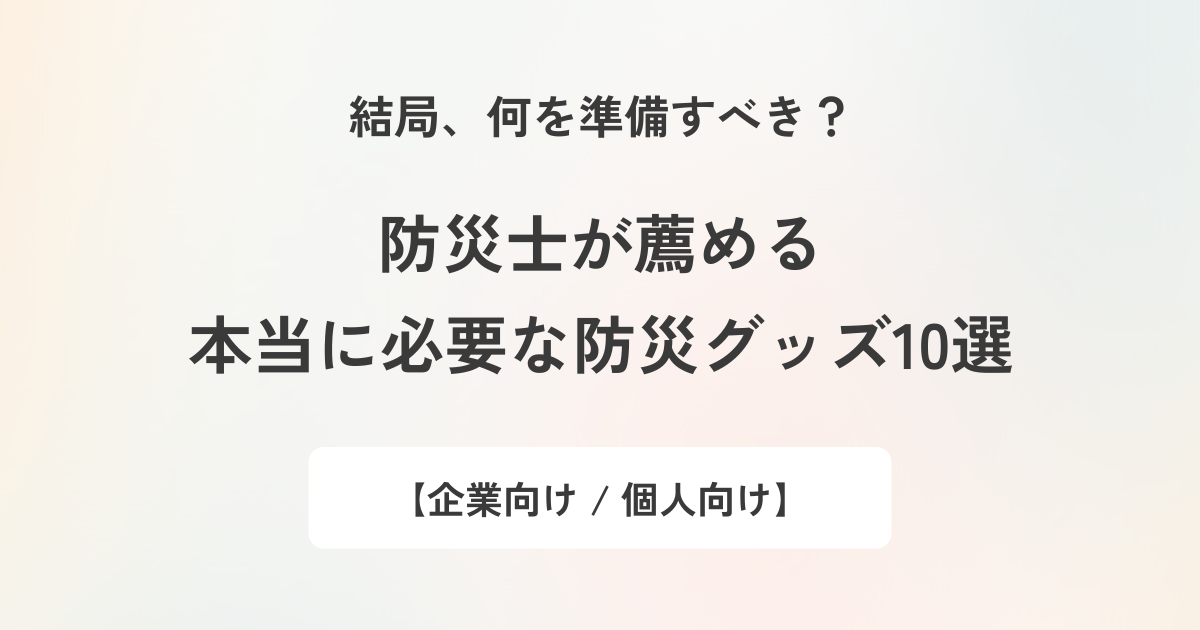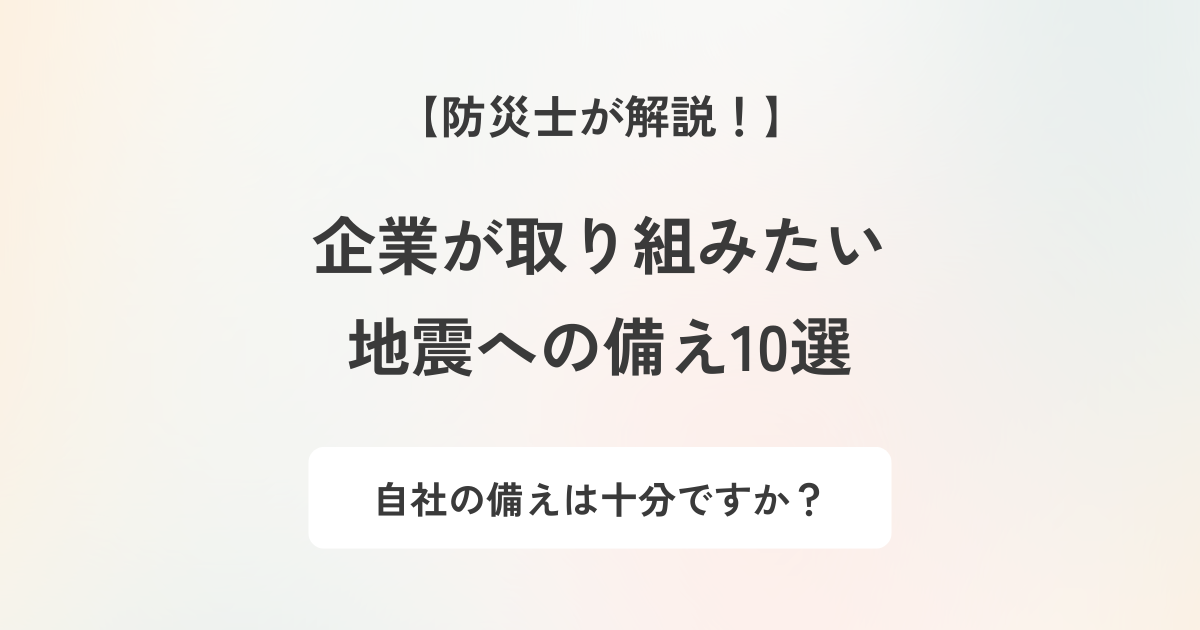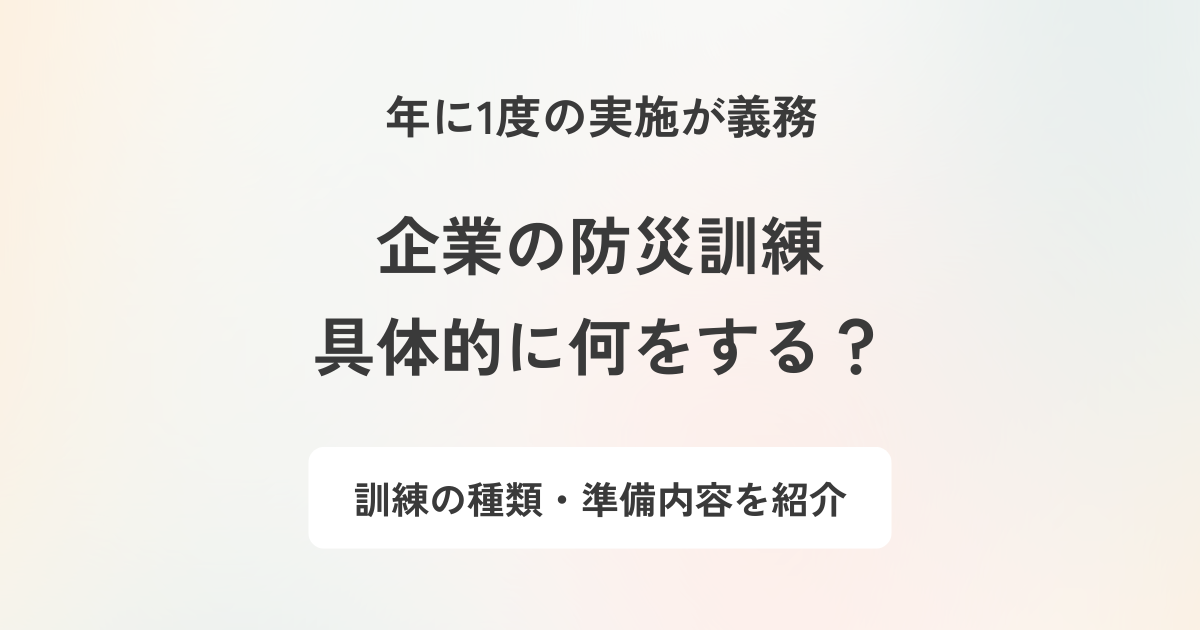自然災害時に避難指示が出たときの企業の対応は?

遠藤 香大(えんどう こうだい)

避難指示が出た際、企業は従業員を守るための行動をとる必要があります。今回の記事では、避難指示と避難勧告の違い、警戒レベルごとに行うべき行動や事前に行っておく対策について解説します。

兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。
目次
避難指示について
避難指示が出ると、迅速かつ適切な行動をとる必要があります。とは言うものの、避難指示とは何なのか、避難勧告とはどう違うのかを正しく認識していない人も多いでしょう。
そこでまず、避難指示について解説したいと思います。
避難指示とは
避難指示とは、自然災害発生時において人的被害の危険が予想される際に発令されるものです。
避難指示が出る状況は、災害発生のおそれが高く、いつ被害が出てもおかしくないときなどに出されます。たとえば津波のように一刻も早い避難が必要な場合、避難指示が発令されます。避難の遅れが生死に関わるため、発令時に必要な安全確保行動をとっていない場合、直ちに行動を起こす必要があります。
避難勧告との違い
避難指示とは別に避難勧告という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
避難勧告とは、被害が懸念されている地域の住民に対し避難を促す目的でかつて発令されていたものです。
避難指示との違いが理解されていなかったことを理由に、2021年5月に廃止されました。
かつて、避難勧告や避難指示で示していた指示は、現在では避難指示に統一されています。
もし、組織の事業継続計画や、地域の地区防災計画などで「避難勧告」という言葉が書かれているときには、すぐに「避難指示」に書き換えて、避難指示での行動を徹底するようにしてください。自然災害発生時には避難指示が出ているかどうかを確認することが大切です。
避難指示が出た際に企業がとるべき対応とは?
企業が従業員を守るためには、避難指示が出た際にとるべき行動を把握しておく必要があります。
避難指示発令時に企業がとるべき行動は以下の通り、3つあります。
- 安全配慮義務に留意する
- 出社の可否を判断して連絡する
- 安全な場所への避難を誘導する
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
安全配慮義務に留意する
企業は従業員に対して安全配慮義務を負います。これに違反した場合、訴訟につながり、企業は信用を失いかねません。
たとえば、自然災害による避難指示が出ている状況で、従業員を無理に出社させることは安全配慮義務違反にあたる可能性があります。通行止めや怪我などで出社できなかった従業員に対して不利益を被らせることも違反にあたると判断されるでしょう。
避難指示発令時は従業員を無理に出社させず、身の安全を守る行動をとれるようにすることが重要です。
出社の可否を判断して連絡する
自然災害により出社するのが危険な場合、出社をさせず、自宅待機(自宅が危険な場合には安全な場所への避難)の指示を出しましょう。災害対応マニュアルを作成し、出勤停止とする警戒レベルを事前に決めておくことで、連絡がスムーズになるでしょう。
出社の可否を連絡するときは、電子メールの一斉送信機能を使うと便利です。
また、在宅勤務やテレワークが可能なシステムを導入しておけば、自然災害の発生が予測される状況でも通常通りに業務を行えます。
安全確保行動を取り、会社が危険な場合には避難誘導する
会社に従業員が出勤している際に避難指示が出た場合は、出社している従業員を安全が確保できる状態にしましょう。ハザードマップなどで会社が危険な場所にあり、避難場所などへの移動が必要な場合には、迅速に誘導しましょう。
そのためにも避難場所を事前に調べ、適切な避難ルートを通れるように備えておくことが重要です。避難時は交通状況や気象情報なども確認し、避難中に被害を受けないよう細心の注意を払います。避難が完了するまで気を抜いてはいけません。
現在の警戒レベル
現在、5段階の警戒レベルが設定されています。
自然災害発生時は、状況に合わせて適切に行動することが大切です。警戒レベルによってとるべき行動が異なるため、事前にどのような行動が必要なのかを把握しておきましょう。
警戒レベル1
警戒レベル1の段階においては、気象庁が「早期注意情報」を発表します。大規模災害のリスクはまだ低いものの、気象情報などに警戒しておきましょう。具体的にはテレビやラジオのニュースや気象庁のホームページなどを確認し、状況の把握に務めることをおすすめします。
警戒レベル2
警戒レベル2では、気象庁によって「大雨注意報」や「波浪注意報」などの注意報が発表されます。危険性が少しずつ高まってきている段階であるため、その場所からの避難が必要な場合には、避難の方法を確認しておくなど心づもりをしておきましょう。
この段階でハザードマップを活用し、会社の立地条件、避難時に通るルートなどを確認しておきましょう。避難するタイミングについてもこの段階で確認するといいでしょう。
警戒レベル3
警戒レベル3は「高齢者等避難開始」が発令される段階です。高齢者や障がいのある方、乳幼児などの避難に時間のかかる人たちが、避難などの安全確保行動を開始します。その支援者も同様です。
また、これらに該当しない人々についても水位が上がりやすい河川の近くや、土砂災害のリスクが高い土地に住んでいる方に関しては、その場所から避難所などに移動する必要があるといえます。すぐ避難を開始できるよう準備を始めておいたほうがいい警戒レベルだと言えます。
警戒レベル4
警戒レベル4では、市町村によって「避難指示」が発令されます。この段階が発令されるとき、自然災害の発生リスクは極めて高い状況です。被害にあう前に避難などの安全確保行動を開始しなくてはいけません。
自分のいる場所が安全な場合には、しっかり留まっていたずらに外に出ないことが重要です。
また、自分のいる場所が危険な場合には、避難場所などへの避難が必要になります。
可能な限り安全なルートを通って、指定された公共の避難場所へ移動します。ただし、移動することでかえって命に危険を及ぼしうる場合は、近くのより安全な場所や建物内に避難しましょう。
警戒レベル5
警戒レベル5においては「緊急安全確保」が発令されます。この段階になると命の危機が迫り、直ちに安全確保行動をとる必要があります。既に自然災害が発生し、避難場所への避難などが困難な場合もありますが、可能な限り命を守る行動をとりましょう。
また、自力での避難が困難であっても、周囲の人たちと協力や連携をしましょう。
可能であれば警戒レベル5に達する前の、レベル3や4までの段階で、確実に安全を確保することが望ましいです。
出典:「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難!5段階の「警戒レベル」を確認しましょう
企業が災害前に行える対策
自然災害による被害を少しでも抑えるためには、事前に対策を行っておくことが重要です。
ここからは、企業が事前に行える災害対策について紹介します。日頃から自然災害について考え、被害を減らすように心がけましょう。
従業員や顧客等の安全確保
自然災害発生時に、企業は従業員や顧客の安全を確保する必要があります。自然災害が起こる前から、避難方法や安否確認のための連絡方法などを確認し、訓練しましょう。
会社がハザードマップなどで安全な場所にあるなど、会社に留まることが安全確保行動になる場合には、従業員が会社に留まるための備蓄も必要です。
水や食料、救急用品などの防災グッズを準備し、置き場所を周知しておきましょう。消火器やスプリンクラーなど防災設備の定期点検も重要です。
防災・省エネまちづくり緊急促進事業の活用
防災・省エネまちづくり緊急促進事業とは、防災対策や省エネ対策などの緊急的な政策課題に対応した質の高い施工者を、国がサポートする事業です。指定区域内で要件を充足していれば、その充足数に応じて国が工事費を補助します。必要用件は高齢者等配慮対策・子育て対策・防災対策・省エネルギー対策・環境対策です。
事業の適用期限は2025年3月31日です。利用を検討される場合、自社が要件を満たしているのかを確認しておきましょう。
事業継続計画(BCP)の策定
自然災害発生後も事業が継続できるように、事業継続計画(BCP)の策定をしておきましょう。
BCPとは、Business Continuity Planの略で、日本では事業継続計画などと訳されます。自然災害やテロ、感染症などの緊急事態に対して、被害を最小限にし、被害が出た場合でも迅速に復旧することで事業を継続するための計画のことです。
BCPを策定しておくことで、継続すべき中核的事業や、被害が出たときに優先的に復旧すべき事業が明確になり、緊急事態に対してどのような行動をとるべきなのかを整理できます。事業継続のため、さまざまな事態を想定しながら計画を立て、緊急事態発生時の指標となるBCPマニュアルを作成しておきましょう。
避難指示が出ても慌てない行動計画を作成しよう!
警戒レベルや避難に関する情報をしっかりと理解し、企業は従業員や顧客を守るための行動をとらなくてはいけません。避難に関する情報が出た際に適切な行動をとるためには、災害対応マニュアルの作成や、それをもとにした避難訓練など、平時からの備えが大切です。
また、自然災害発生時の連絡をスムーズにする安否確認サービスの導入も有効です。
自然災害に備えて適切な行動計画を立てて、万一のときに慌てず、命と事業を守るための行動がとれるようにしましょう。
兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。