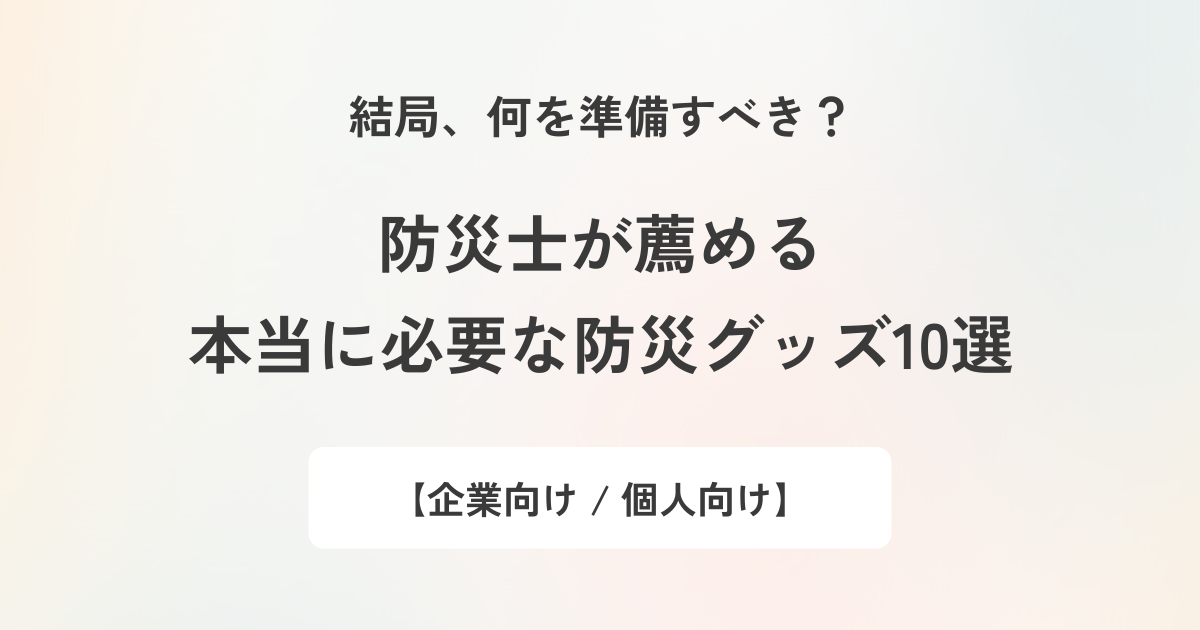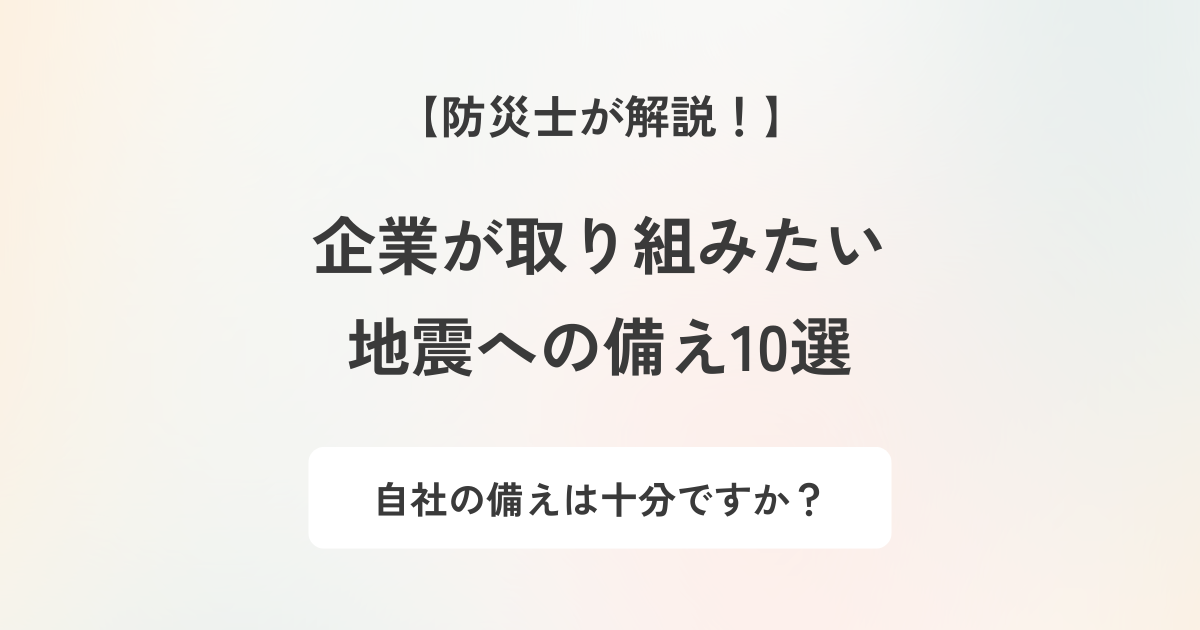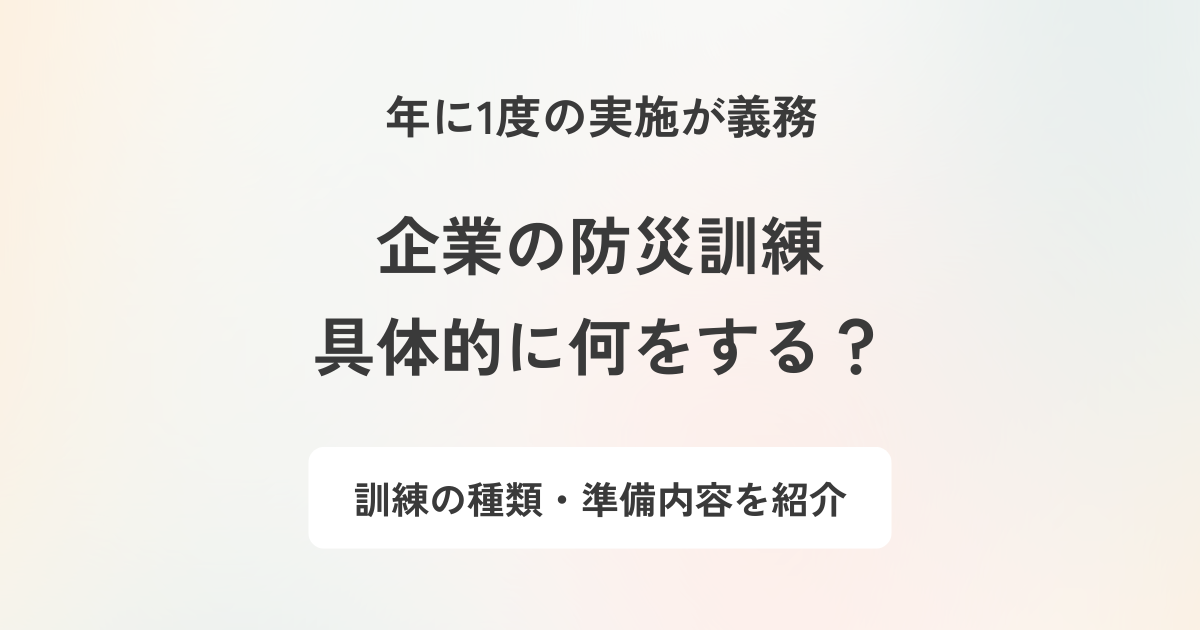水平避難とは?垂直避難との違いやケース別の行動を解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
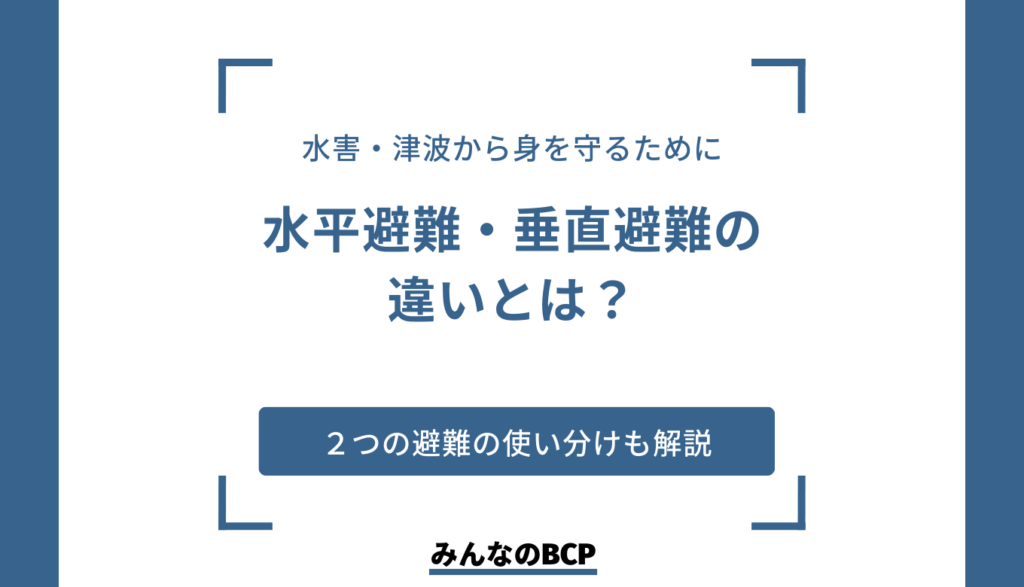
避難行動には、自宅の外にある安全な場所へ移動する「水平避難」と、自宅の2階など屋内で安全な場所へ移動する「垂直避難」があり、地域や状況に応じて避難の方法は異なります。
二種類の避難方法について知り、災害が発生したとき適切な避難を行えるようにしましょう。

目次
水平避難とは
水平避難とは、可能な限り災害の発生場所から遠くへと移動することを指し、立ち退き避難とも呼ばれます。
また、水平避難は災害の発生する前に行うことが原則です。そのため、被災までに猶予がある場合は、水平避難が適しているでしょう。
地域で指定されている避難所への避難も水平避難にあたります。
垂直避難との違い
垂直避難とは、建物屋内において2階以上の高さへ移動することを指し、屋内安全確保とも呼ばれます。
水平避難と垂直避難の違いは、「いまいる場所から遠くへの移動が水平避難」「いまいる場所から高くへの移動が垂直避難」と覚えましょう。
夜間で見通しが悪いときや、すでに被災しているときは、垂直避難が適しています。災害が発生したときは、状況に応じて適切な避難方法を選ぶことが大切なのです。
水平避難を行うべき状況
以下は、水平避難が推奨される状況です。
- 安全な空間を確保する必要がある場合
- 被災までに時間があり、安全な場所へ向かうための余裕がある場合
- 遠くへ逃げる必要がある場合
- 建物が倒壊する可能性のある場合
- いまいる場所で垂直避難を選ぶと、命の危険を脅かす状況に陥ってしまう場合
- 海抜ゼロメートル地帯で浸水が長期化してしまう場合
- 浸水深がいまいる建物よりも高い場合
- 土砂災害特別区域にいる場合
垂直避難を行うべき状況
すでに災害が発生していたり、避難所への移動がむしろ危険だったりする場合、垂直避難が適しているでしょう。ただし、建物の倒壊に関して、リスクがない場合に限ります。
他にも以下のような状況では、垂直避難を推奨しています。
- 夜間の見通しが悪い状況で、急激に事態が悪化した場合
- 浸水の高さが高層階よりも低い場合
ただし、垂直避難については避難行動をしたあとも注意が必要です。垂直避難をしても、浸水の改善やライフライン復旧に時間を要する可能性があります。垂直避難をしたあとも安全に避難生活できるよう、食料や防災用品の備蓄を普段からしておきましょう。
水害時の避難方法
水害リスクが高い場所にいる場合、危険な状態となる前に避難所へ避難しましょう。ただし、ハザードの種別や規模によっては、垂直避難が適切である場合もあるため、注意が必要です。つまり、その時々の状況によって避難方法が変わります。
ここからは、水害時の適切な避難判断について、基準をご紹介します。ぜひご参考にしてください。
水平避難が必要なケース
水害が発生した際、水平避難が必要なケースは以下のような場合です。
- 河川の氾濫が迫る場合
- 浸水が長時間継続する場合
- 浸水深が深い場合
- 地下や半地下に、氾濫した水が流入する場合
- ゼロメートル地帯といった、浸水が長期間継続する場所にいる場合
垂直避難が必要なケース
水害が発生した際、垂直避難が必要なケースは以下のような場合です。
- 短時間で局地的に大雨が降っている場合
- 浸水深が浅い場合
- 局所的に浸水している箇所さえ近づかなければ、命に関わる危険性はないと判断できる場合
火災時の避難方法
火災が発生した際には、垂直避難よりも水平避難が適しています。
避難する際は、煙を吸わないようにハンカチやタオルなどで口と鼻を覆い、姿勢を低くして逃げましょう。このとき、持ち物にはこだわらず、すぐさま避難することが重要です。
また、避難の途中で止まってしまう可能性を考慮し、エレベーターの使用は控えてください。とくに、マンションでの火災であれば階段や避難はしごなどを使って避難しましょう。できるだけ外気に面した場所を目指すことが大切です。
地震時の避難方法
地震が発生した際は水平避難か垂直避難、どちらが適しているのでしょうか。答えはそのときの状況によって左右されるため、正しい判断ができるための知識を事前に得ておきましょう。
水平避難が必要なケース
地震が発生したとき、建物に倒壊の危険性がある場合は、水平避難が適しています。とりわけ1981年以前に建てられた家屋は大きな地震への対策が施されておらず、大型の地震が発生すると倒壊してしまう可能性があると考えられています。したがって、耐震基準を満たしていない古い建造物に関しては、すぐに耐震リフォームをすることが必要です。
避難する際は、必ず揺れが収まってから避難しましょう。渋滞に巻き込まれたり、故障や災害状況などによって動けなくなったりする可能性もあるため、車は使ってはいけません。
垂直避難が必要なケース
地震が発生したとき、建物に倒壊の危険性がない場合は、垂直避難が適しています。耐震性が十分にある家屋の場合、すぐさま外に逃げられるよう1階へと避難しましょう。一方、耐震性に不安がある建物の場合は、2階に避難してください。耐震性のない家屋は、地震で1階のみ潰れる可能性が高いためです。
水平避難を行う際に押さえておきたいチェックポイント
ここからは、水平避難の際に押さえておきたいポイントをご紹介します。
突然発生する災害に備え、事前に確認しておきましょう。
避難場所・避難所
災害が多く発生する日本においては、被害拡大を防ぐためにも、日頃から避難場所や避難所の場所を確認しておくことが大切です。
一方で、避難所には種類があることをご存じでしょうか。東日本大震災以前、我が国の法律では避難場所と避難所を区別できていませんでした。これが被害拡大の一因になったため、2013年には災害対策基本法が改正され、避難場所と避難所が明確に区別されました。
避難場所と避難所の明確な違いについて、以下で確認しておきましょう。
- 避難場所(指定緊急避難場所)
避難場所とは、危機的な状況下で命を守るために避難する場所のことです。
主として広いスペースを持った公園や河川敷が避難場所に該当しますが、災害の種類によって指定場所は変わります。
たとえば地震が発生したときはグラウンド、津波が発生したときは高台などが避難場所となります。
| 指定緊急避難場所 | 自治体で決められた一時的に避難する場所 |
| 一時避難場所 | 一時待機用の小さい避難場所 |
| 広域避難場所 | 多くの人を収容できる大きな避難場所 |
- 避難所(指定避難所)
避難所とは、帰宅困難者が一時的に暮らす場所を指した言葉です。避難所は人が生活できるだけの設備を要するため、学校や公民館などが主に指定されます。
避難所は、以下の3つに分かれています。
| 一次避難所 | 最初に開設される小規模な避難場所 |
| 二次避難所 | 高齢者、障がい者、乳児、乳児の保護者などが避難する場所 |
| 福祉避難所 | 要援護者に配慮した避難施設 |
服装
避難するときの服装として最も重要なのは、怪我をしないかどうかという観点です。
長袖と長ズボンを着用し、肌の露出による怪我を防ぎます。靴は必ず運動靴を履くようにしましょう。可能であれば底の厚い靴を履くことで、ガラス片による怪我を防げます。長靴は安全に思えますが、中に水が入るとかえって動きにくくなるため、使用はおすすめしません。
また、頭を守るためのヘルメットや、粉塵や煙を避けるためのマスクを着用しましょう。
持ち物
いつ起こるか分からない災害に備えて、非常用持ち出し袋を準備しておくといいでしょう。準備ができたら、避難する際にすぐ持ち出せるよう、玄関先に置いておきましょう。
非常用持ち出し袋に入れるものは、以下を参考にしてください。
- 飲料水、食料水
各家庭や事業所で、最低三日分の食料や水の備蓄を行っておきましょう。1日1人あたり3リットルの水が目安とされています。 - 懐中電灯
災害が発生した際は、停電になるおそれがあります。 - ラジオ
懐中電灯と同様、災害が発生した際は停電になりうるため、インターネットやテレビからの情報収集が行えないと考えられるためです。
これらの他にも貴重品、救急用品、その他の生活用品などを入れておくといいでしょう。
重くなるとかえって邪魔になるため、避難時の荷物は必要最低限にしてください。
そのほかの注意点
単独行動ではいざというときに助け合えません。そのため、避難の際には単独行動を控え、できるだけ家族や近所の人たちと一緒に動いてください。
お年寄り、子ども、怪我や病気の患者などは早めの避難が必要です。警戒レベル3が出た場合、避難準備をしなければなりません。また、避難する際は近所への呼びかけを行い、協力しましょう。
避難する際は警察、消防、地域の防災責任者などの指示に則って行動してください。また、ハザードマップで避難経路を事前に確認しておきましょう。
被災状況に合わせて避難方法を選択しよう
避難方法を絞らず、そのときの被災状況にあわせて適切な避難方法を見極める必要があります。今回の記事で紹介した避難方法の判断基準や、避難をするときの注意点を事前に知っておけば、安全な避難が可能となるでしょう。