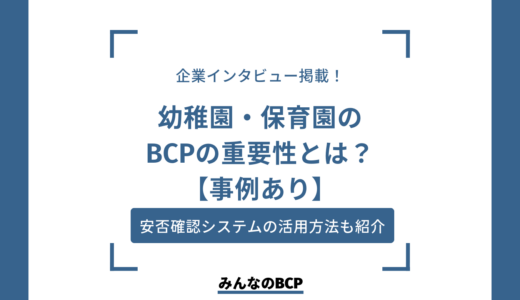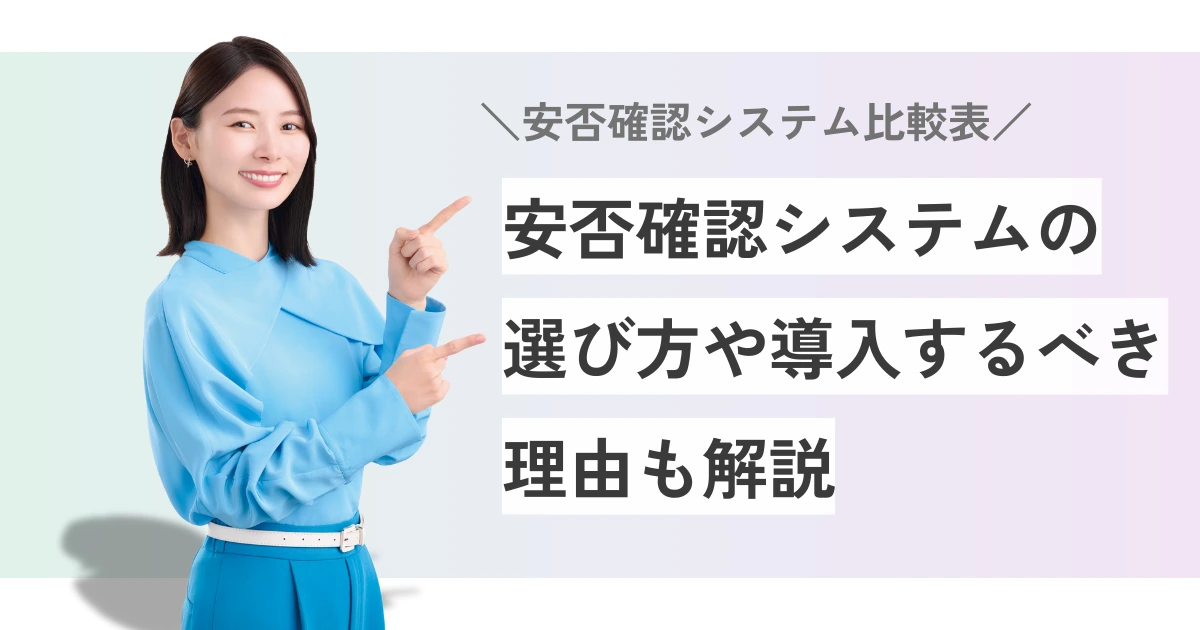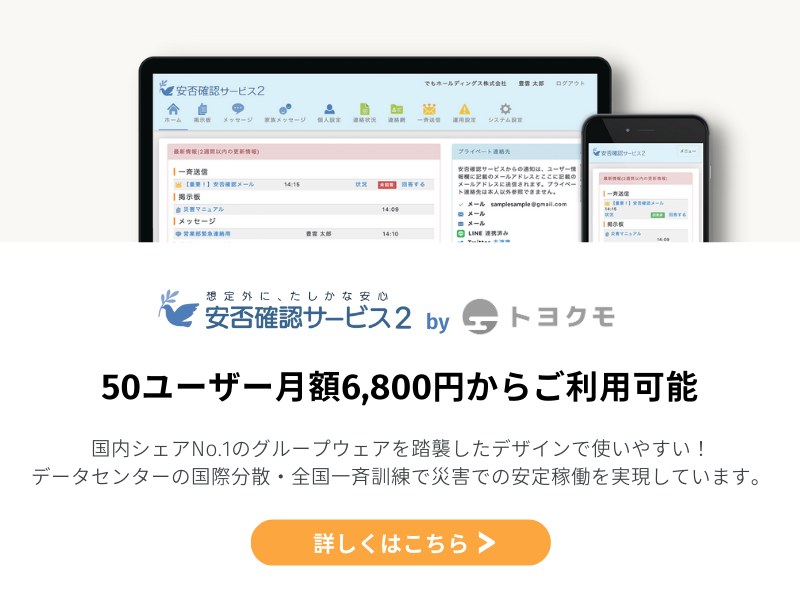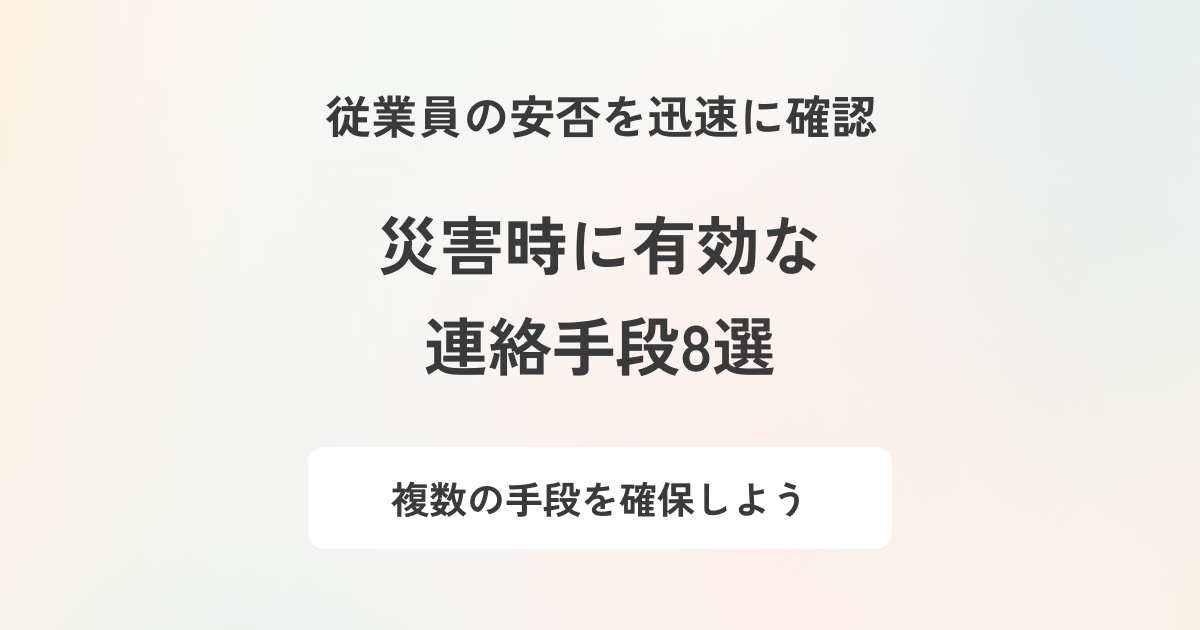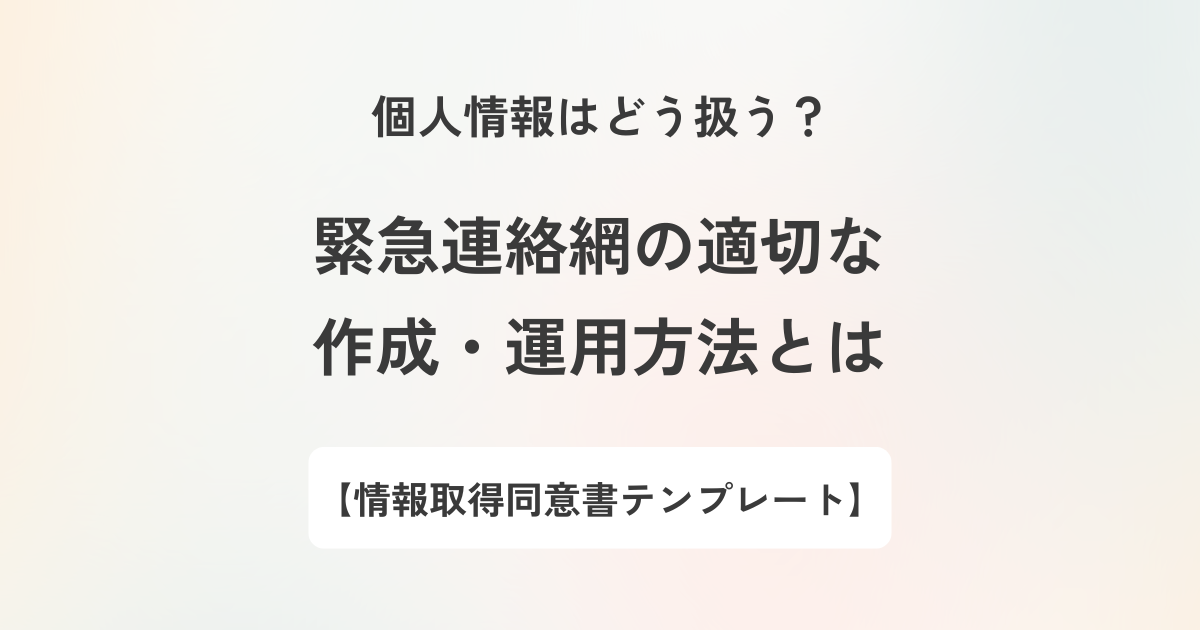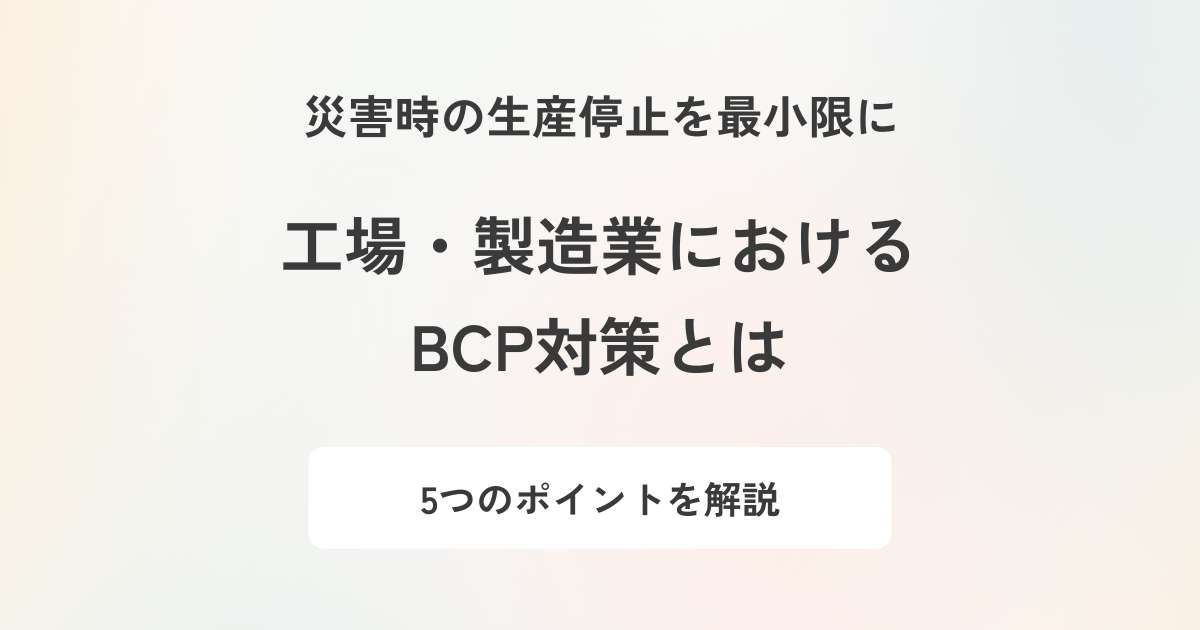病院における安否確認システムの役割は?実際に導入されているサービス5選も

遠藤 香大(えんどう こうだい)
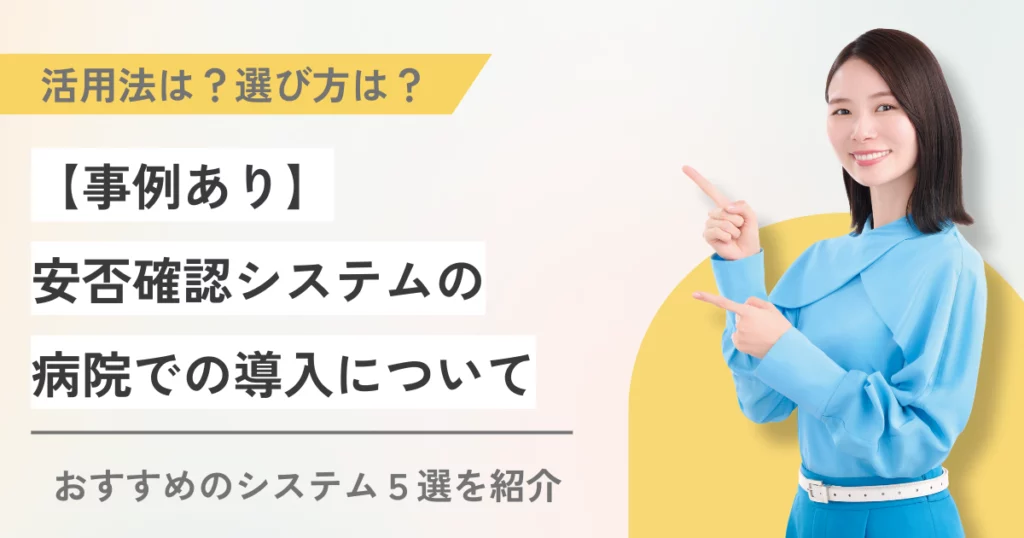
日本は世界有数の災害大国です。災害発生時には災害拠点病院をはじめとする医療施設が、医療施設としての機能を維持しながら、迅速に負傷者等の対応にあたることが求められます。
このような背景から、近年、病院における安否確認システムの重要性が高まっており、BCP(事業継続計画)の策定・運用とともに安否確認システムを導入する病院も増えています。
この記事では、病院における安否確認システムの役割や災害時の活用法、おすすめのサービスについて解説するので、参考にしてください。

兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。
目次
安否確認システムとは
安否確認システムとは、災害時や緊急時に職員の安否状況を収集・集計し、関係者間で共有するためのシステムです。
このシステムを活用することにより、災害時に患者や職員の安否・被害状況の確認と、速やかな機能復旧・機能維持に向けた対応ができます。
とくに、災害時の混乱した状況下において、職員の参集可能状況を即座に把握できることは、限られた人的資源を最適に配置する上で重要な役割を果たします。
病院における安否確認システムの役割
安否確認システムの役割は、大きく分けると2つです。
- 職員の安否状況の確認
- 設備の安全確認と職員への具体的な指示伝達
これらの役割によって、災害時でも迅速に医療活動を開始できます。
職員の安否確認
災害時において、職員の安否確認は非常に大切です。職員に安否確認システムに登録してもらうと、災害時に迅速に職員の安否を把握できます。これにより、災害時における医療サービスの提供について、判断しやすくなります。
医療サービスの提供
災害時は、多数の負傷者が発生します。医療機能の機能維持・機能回復は急務であり、そのためには職員の確保が重要です。
安否確認システムを利用すると、職員が出勤できるか、被害はないかなどの情報共有のツールとして機能します。
メールで安否確認をすると、大規模災害時に通信障害やサーバーダウンなどで遅配が起こる危険性がありますが、安否確認システムであれば世界中のクラウドサーバーとつながっているものもあり、そうした状況でも連絡が可能です。
また、出勤可能人数や出勤までにかかる時間を、非常時に一人ひとり回答をもらって集計していては、手間と時間がかかります。安否確認システムの集計機能を使うと、その手間を減らせるでしょう。
職員への指示
災害時には混乱が起きやすく、職員への指示もうまく出せないケースも考えられます。また、事業の復旧・継続の対応について優先事項の判断や対処も困難です。こうしたなかでも安否確認システムを利用して指示や連絡を行うと、より迅速に対処できます。
なによりも担当者に直接伝えに行く手間を省き、情報の共有や指示ができることは、大きな利点です。
設備や機器の安全確認
大きな災害においては、多くの設備や機器が故障したり、電気・水道などのライフラインが停止したりするなどの事態も考えられます。
安否確認システムは、設備や機器の故障についての写真を共有することも可能です。このような迅速な確認と情報共有によって、より迅速に医療システムの復旧にあたれます。
BCPの実施
医療機関は、災害や感染症などの非常時においても事業の継続が求められます。BCP(業務継続計画)を作成し、訓練などで確認する必要があります。
BCPとは、Business Continuity Planの略で、日本語では「事業継続計画」などと訳されます。自然災害やテロ、感染症などに対して、被害を最小に抑えるとともに、たとえ被害・影響が出てしまったとしても、適切な対応で速やかに事業活動を復旧・継続させることを目的とした計画です。
安否確認システムも、BCPにおける重要な対応である安否確認を促進させるシステムとして位置づけられます。
病院におけるシステムの活用法
ここまで、安否確認システムの重要性を解説しました。ここからは、安否確認システムの具体的な機能や活用法について解説します。
地震自動配信機能
地震自動配信機能は、気象庁の地震速報と連携することにより、地震発生時に職員に安否確認メッセージを送る機能です。地震の震度や地域などを事前に設定しておくことにより、条件に当てはまる地震が発生した際にメッセージが送信されます。
メッセージの送付は自動で行われるため、管理者が被災をした場合でも従業員全体への安否確認が可能です。災害時に起こる回線の混雑に影響を受けずにメッセージの受信が可能なクラウド型もあり、安定してメッセージの送受信が行えます。
気象自動配信機能
気象自動配信機能は、気象庁から出される注意報・警報・特別警報(地震を除く)と連携して、自動安否確認メッセージを送るものです。
警報が出される地域、基準になる警報や注意報の種類を設定しておくと、緊急時に安否確認メッセージが送られます。
また、電話回線の混雑があっても受信可能であり、緊急時に有用な機能です。
手動配信機能
手動配信機能は、安否確認用のメッセージを手動で配信する機能です。前述の自動配信機能とは違い、管理者が手動でメッセージを作成して職員と連絡をとることによって情報を共有します。
手動配信機能はメッセージ内容を自由に作成できるため、緊急時以外にも職員同士の情報共有のツールとして利用できます。
また、アンケート機能などもあり、宛先も絞って配信できるため、幅広い用途で利用できる機能です。
掲示板機能
安否確認システムには、情報共有のための機能に掲示板機能もあります。職員間で、災害時の被害や情報を投稿できる機能です。
文字だけでなく写真を投稿できる場合が多く、設備の故障報告などを写真付きで投稿することができます。
手動配信機能は管理者を挟む必要があるのに対し、掲示板機能は職員間で情報共有ができるため、状況によってはより素早い対応ができるでしょう。
体調管理アンケートの送信機能
規模が大きい施設の場合、職員一人ひとりに確認をとることは手間がかかる上に、聞き取り内容に間違いや誤認が起こりやすくなります。そのため、体調管理アンケートの送信機能の活用がおすすめです。
多くの病院や施設では、安否確認システムの機能を使って、体調管理を行っています。たとえば、毎朝職員に体調確認のメッセージを一斉配信し、回答してもらうという方法があります。体調不良の場合はその旨を回答してもらうことにより、個別で確認する作業はいりません。
事前にメッセージ内容や配信日時を決めて配信すれば、配信や集計の手間がかからないため、効率的に職員の体調管理を行えます。
以下の記事で、具体的な活用方法を事例とともに紹介しています。
病院に導入できる安否確認システムの選び方
市販されている安否確認システムには、さまざまな種類と機能があります。では、安否確認システムを選ぶポイントはどこなのでしょう。
ここからは、システムの選び方について詳しく解説します。
災害が起こった時の稼働実績
安否確認システムは、災害時や緊急事態発生時に稼働します。これまでの災害時や新型コロナ感染症流行期に稼働したか、その際システムに大きな異常がなかったかなどの稼働実績は、安否確認システムを選ぶときの大きなポイントになります。
ほかの病院や施設で導入されたか、稼働状況がどのようなものかを調べることも大切です。
病院業務で活用できる機能、操作性のシンプルさ
安否確認システムは非常時だけでなく、平常時から活用できます。メッセージ機能やアンケート機能を定常業務に利用することにより、作業効率を大きく上げられます。
また、操作性も重要なポイントです。導入しやすいか、ITが苦手な人も手軽に利用できるかという部分もチェックしましょう。
無料お試しがあるか
システムを選ぶ際には、無料お試しがあるかもポイントになります。
職員の多くが安否確認システムを利用したことがなかったり、あいまいな知識しかなかったりすると、いきなりの導入には不安があるでしょう。無料お試しで使ってみれば、「使いやすいか、自分たちの職場に適しているか」を判断できます。
合わないと判断できれば、費用がかかる前に導入を中止できる点も無料お試しのメリットです。
実際に病院で導入されている安否確認システム5選
ここからは実際に病院で導入されている安否確認システム5つを紹介します。
| 初期費用(税抜) | 月額費用(税抜) | 無料お試し | |
|---|---|---|---|
| 安否確認サービス2 | 0円 | 6,800円〜 | 30日間 |
| オクレンジャー | 12,000円~ | 要問い合わせ(※1) | 2週間 |
| ANPIC | 25,000円〜 | 5,130円〜 | 30日間 |
| エマージェンシーコール | 0円〜 | 10,000円〜(税不明) | 30日間 |
| 災害安否確認システム安否コール | 80,000円〜 | 5,000円〜 | 1ヶ月 |
※1.50ユーザーで利用する場合、年間費用は60,000円〜(税不明)
ここで紹介する以外にも多くの安否確認システムがあります。ほかの安否確認システムについても知りたい場合には、ぜひ以下のページも参考にしてください。
安否確認サービス2
トヨクモが提供する『安否確認サービス2』の特長は、便利な機能が揃っているにもかかわらず、安価で利用できる点です。
ハードウェアの整備など初期費用は一切かかりません。月額料金ももっとも人気のプランで月額8800円(税抜)〜です。機能はメッセージ機能や掲示板、LINEをはじめとした各種連携機能がひと通り備わっています。最低契約期間が設定されていないことから、導入ハードルは比較的低いと言えるでしょう。
また、ガラケーでも利用できるシステムであり、スマホをもっていない高齢の方が多い病院や施設ではありがたい特長と言えるでしょう。
さらに、災害時にも安定した稼働を実現しているのも、おすすめのポイントです。世界各地にデータセンターを分散しており、大規模災害が発生したとしても安定して稼働します。奥能登豪雨や能登半島地震の際にも活躍した実績があります。
従業員数、地域を問わず、多くの医療・福祉の現場で採用されているのも特徴です。
30日間の無料お試しでは、機能の制限なく、操作性を確認できます。無料お試しの期間が過ぎても自動で課金されないため、興味がある方は実際に操作してみることがおすすめです。
病院での活用事例
ここでは、病院の活用事例として、福岡県済生会福岡総合病院の事例を紹介します。
福岡県済生会福岡総合病院では従来、連絡手段がメールのみの安否確認システムを導入していました。しかし、訓練での回答率は60%前後と低く、さらに手動で連絡していたことにより、担当者の負担が大きいという課題を抱えていました。
これらの課題を解決するために、安否確認サービス2の導入を決意。その結果、自動送信機能と予約送信機能によって、手動でメッセージを送信する必要がなくなり、担当者の負担は大幅に軽減されています。さらに、さまざまな連絡手動に対応していることから、回答率は95%にまで上昇しました。
また、運用の手軽さ以外にも、導入コストの低さも高く評価されています。職員が多いこともあり、「導入時の登録作業が大変ではないか?」と心配していたものの、簡単に登録作業が完了したとのことです。システムを導入して1ヶ月以内には、1,000名ほどの全職員が自らシステムに連絡先を登録しました。
以下の記事では、福岡県済生会福岡総合病の事例を詳しく紹介しています。
災害拠点病院として、緊急事態に対応するために「安否確認サービス2」を導入!機能性/コストパフォーマンスの高さを実感し他病院にも推薦
▲出典:社会福祉法人 恩賜財団済生会 福岡県済生会福岡総合病院
オクレンジャー
パスカルの提供する「オクレンジャー」の強みは、災害時に強いことです。
サーバーを国内だけでなく、海外のセンターにも2ヶ所設置しており、大規模災害時でも安定したサービスの提供が行えます。
また、災害時のメール遅延の影響を受けないアプリもあるため、緊急時のメッセージ受信も確実にできます。緊急時には通常とは別の通知音で知らせるため、冷静になってから反応できるでしょう。
オクレンジャーでは、安否確認や従業員への日常的なコミュニケーションに加えて、厚生労働省が推奨している職業性ストレス調査票を用いたストレスチェックも行えます。さらに、アルコール検知機の結果をオクレンジャーに自動送信する機能も備えており、平時からさまざまな場面で活用できる点も魅力です。
ANPIC
「ANPIC」のセールスポイントは、低価格です。最安値月額5130円という価格で利用でき、災害時でもLINE連携やアプリなど複数の方法でメッセージを受信できます。初期導入費用は別にかかりますが、登録代行や説明などの導入時のサポート体制は万全で、不安なく導入できます。
また、サポート体制が充実している点も特徴です。無料で初回のユーザー登録を代行してもらえるため、繁忙期にも少ない負担で導入できます。不明点がある場合には、サポートセンターに電話をすると迅速に対応してもらえるため、スムーズに運用できるでしょう。
エマージェンシーコール
インフォコムの提供する「エマージェンシーコール」は、各ユーザー10個まで連絡先情報を登録できて、回答のないユーザーに対して最大99回まで繰り返し連絡できます。職員の家族の安否確認を少ない手間で行える点が特徴です。
また、連絡の送付先媒体がメールや電話、FAX、スマホアプリなど豊富に用意されているのもポイントです。スマホをもっていない高齢の方が多い病院や施設でも、電話やFAXなどで返答できるため、高い回答率を期待できます。
災害安否確認システム安否コール
アドテクニカの「災害安否確認システム安否コール」は、IDとパスワード、メールアドレス不要で登録できる安否確認システムです。最初の登録時に端末認証を行うことにより、以降はログインする必要がありません。災害時の混乱している状況下でも、パスワードを忘れて回答できない事態を防止できます。
また、世界トップレベルの堅牢なセキュリティを誇るプラットフォームで管理・運用されている点も特徴です。海外のメインリージョンをはじめとして、国内の3ヶ所でも運用されており、災害時にも安定した稼働を実現します。
小規模企業向けに「ミニマム」「ミニマム+」、中規模企業向けに「ビジネス」「ノーマル」「スタート」、大規模企業向けに「エキスパート」「プロ」のプランが用意されています。初期費用は8,000円から(税抜)で、月額費用は5,000円から(税抜)です。
病院や医療現場における安否確認システムを導入し、迅速な医療体制の復旧計画を立てよう!
病院や医療現場での安否確認システムは、その重要性が徐々に認識されはじめてきました。
災害時・緊急事態発生時の安否確認をシステムに割り振ることにより、職員はそれ以外の対応に集中することができ、医療体制の迅速な復旧・維持につながります。
トヨクモの『安否確認サービス2』は、多くの医療現場で採用されており、その操作性と信頼性から高い評価を得ています。特に災害時の迅速な稼働実績と、多様な連絡手段を活用した高い回答率が特徴です。ガラケーにも対応しているため、幅広い年代の職員が安心して利用できます。
無料お試し期間中には、すべての機能を制限なく利用できるので、実際の運用に合わせて操作性や機能性をしっかり確認してから導入を決定できます。この機会にぜひ、『安否確認サービス2』をお試しください。
兵庫県立大学 環境人間学部・大学院環境人間学研究科 教授
早稲田大学卒業、京都大学大学院修了 博士(情報学)(京都大学)。名古屋大学大学院環境学研究科助手・助教等を経て現職。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法など「安全・安心な社会環境を実現するための心理・行動、社会システム研究」を行っている。
著書に『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)、『戦争に隠された「震度7」-1944東南海地震・1945三河地震』(吉川弘文館)などがある。


編集者:遠藤香大(えんどう こうだい)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部に所属。RMCA認定BCPアドバイザー。2024年、トヨクモ株式会社に入社。『kintone連携サービス』のサポート業務を経て、現在はメディア『トヨクモ防災タイムズ』運営メンバーとして企画・編集・校正業務に携わる。海外での資源開発による災害・健康リスクや、企業のレピュテーションリスクに関する研究経験がある。本メディアでは労働安全衛生法の記事を中心に、BCPに関するさまざまな分野を担当。