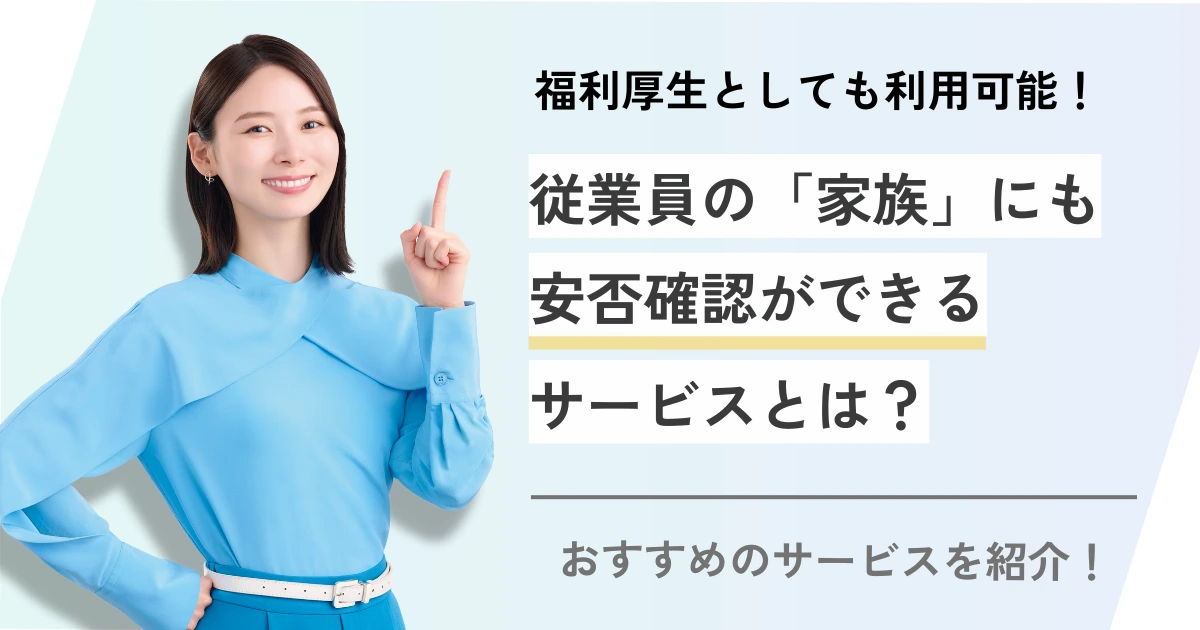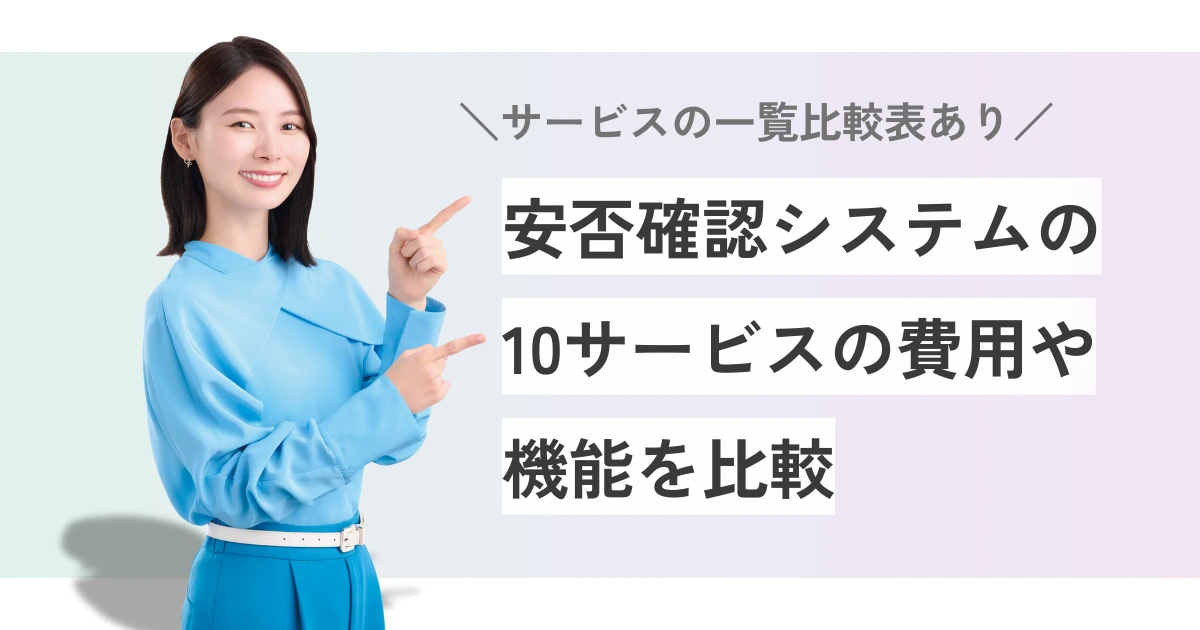【弁護士が教える】労災発生時、労基署長への報告義務とは?必要な書類・期限をわかりやすく

トヨクモ防災タイムズ編集部
労働災害(労災)が発生した際は、労働基準監督署長に報告が必要な場合があります。報告の期限や手続きについて、正しく理解できていますか?
この記事では、弁護士法人シーライト 弁護士の塩谷恭平が、労災報告が必要となる具体的な状況や手続きの流れ、報告をしなかった場合のリスクについてわかりやすく解説します。
事業者として、法律を遵守しながら迅速な対応を行うための参考にしていただければ幸いです。

目次
労災報告の基礎知識

労働災害(労災)とは、労働者が業務や通勤によって死亡したりケガ・病気等になることをいいます。例えば、作業中の転倒事故、工具の取り扱いによる負傷、さらには屋外作業中の熱中症などが労災に該当します。詳細は以下の記事をご覧ください。
▶︎弁護士が教える労働安全衛生法(安衛法)!重要ポイントと対応策、違反した場合の罰則を解説
重大な事故が発生した場合や労災により労働者が死亡した場合等には、事業者は所轄の労働基準監督署長に対して労災を報告する法的義務があります。
労災報告が必要なケースと期限
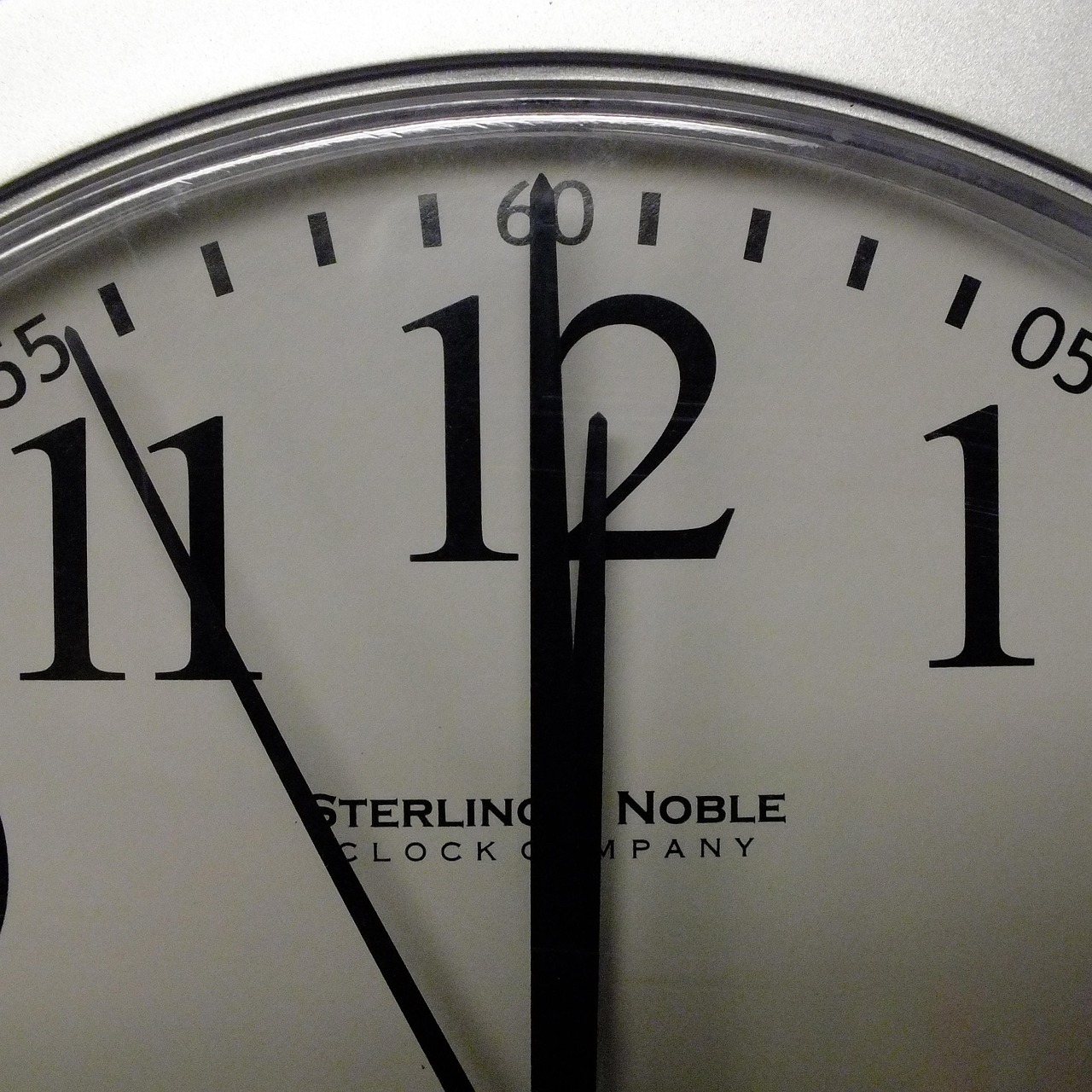
労働基準監督署へ提出する書類や期限は、事故の種類や労働者の死亡の有無、休業日数によって異なります。
| 要件 | 報告期限 | 提出書類 |
| 労働安全衛生規則第96条に規定されている爆発等の事故が発生した場合 | 遅滞なく | 負傷者の有無に関わらず、事故報告書(様式第22 号)を提出 |
| 労働者が死亡、または休業4日以上の場合 | 遅滞なく | 労働者死傷病報告(様式第23号)を提出 |
| 休業3日以内の場合 | 四半期ごとにまとめて | 労働者死傷病報告(様式第24号)を提出 |
| 死亡・休業していない場合 | 不要 | なし |
・原則として、労災事故にあった労働者を直接雇用する事業主が報告義務を負っています。
・この表における「遅滞なく」とは、通常7日~14日以内を目安としています。
・通勤災害の場合には、労働基準監督署長への報告義務はありません。
労働基準監督署長への報告の流れ

労働基準監督署長への報告手順は、以下のようになっています。
- 初動対応
- 報告書の作成
- 労働基準監督署への提出
- 労働災害再発防止対策書の作成
1.初動対応
万が一、労働災害が発生してしまった場合には、まずは落ち着いて以下の点を実施しましょう。
・被災者の救護及び病院への搬送
・(重大な事故の場合)警察署及び労働基準監督署への連絡
・被災者の家族への連絡
2.報告書の作成
上記表のとおり、労働基準監督署長への報告が必要な場合には、対応する報告書を作成することになります。
報告義務があるにもかかわらず報告をしなかったり、虚偽の内容を報告すると「労災隠し」として厳しく罰せられますので、適正な報告を行うようにしましょう。
3.労働基準監督署への提出
作成した報告書は、期限内に所轄の労働基準監督署(原則として、被災者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署)へ提出します。
提出の方法については、令和7年1月1日から、原則として電子申請(e-Gov)による方法が義務化されていますが、当分の間は書面による報告も可能となっています。
4.労働災害再発防止対策書の作成
労働災害発生後は、発生してしまった災害の原因を分析した上で、再発防止策の検討・実施を行うことが重要です。
これらの一連の流れを労働災害再発防止対策書として文書化しておくことが、労働災害を二度と起こさない労働環境の形成に繋がります。労働災害再発防止対策書の様式例については、厚生労働省が公開している労働災害再発防止書様式例を参照してください。
【労働者死傷病報告書】記載時の注意

労働者死傷病報告書を作成する際には、必要事項を漏れなく記載することが重要ですが、その中でも事故状況について記載する「災害発生状況及び原因」欄や「略図」欄は特に重要な事項になります。なぜなら、これらの欄に記載された内容をふまえて、労災認定の可否や事業主等の刑事責任・民事責任の有無が判断されることになるからです。
なお、令和7年1月1日から労働者死傷病報告書の電子申請が義務化されたことにより、「災害発生状況及び原因」欄については、
①どのような場所で、
②どのような作業をしているときに、
③どのような物又は環境によって、
④どのような不安全な又は有害な状態があって、(重要)
⑤どのような災害が発生したか、
の5段構成による記入方法となっています。報告を行う事業主としては、必ず事故現場の確認や関係者への聴き取り等を実施して事故状況を正確に把握した上で、特に④の部分で間違いがないように記載するように注意してください。
また、「略図」欄については、イラストや写真等に補足説明などを追記した画像データ等も添付できるようになっていますので、事故状況をより分かりやすく説明するために活用してください。
労災報告に関するよくある質問

Q.病院に労災保険の書類を提出したら、労働基準監督署長への報告はしなくて良い?
A.労働者死傷病報告は、労災保険の給付手続の有無にかかわらず行う必要があります。病院に労災保険の書類を提出していたとしても、別途、労働基準監督署へ労働者死傷病報告書を提出しなければなりません。
Q.派遣社員の労災報告は誰が行うの?
A.派遣先事業主と派遣元事業主の両方とも報告義務を負っているため、それぞれが労働者死傷病報告書を作成して所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。なお、派遣先事業主は、労働者死傷病報告書を提出したときは、その写しを派遣元事業主に送付しなければならないとされています(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則42条)。
Q.報告書を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合はどうなるの?
A.労働者死傷病報告を故意に提出しなかったり、虚偽の報告をした場合には、いわゆる「労災隠し」に該当します。この場合には、労働安全衛生法で50万円以下の罰金に処する旨規定されています(労働安全衛生法120条5号)。
労災発生時は迅速・正確な報告を
労災が発生した際、企業には正しい手順での報告が求められます。
特に、「労働者死傷病報告書」の 「災害発生状況及び原因」欄や「略図」欄 の記載は、事故の詳細を正確に伝えるために重要です。
もし対応に悩む場合は、弁護士に相談することも一つの選択肢です。
また、安定した経営には、通常時の労災防止だけでなく、非常時に強い体制を作ることも欠かせません。
特に、地震などの自然災害時には、従業員の安否や被害状況を素早く把握できなければ、適切な初動対応ができず、混乱を招くリスクがあります。
- 指示が遅れ、現場が混乱
- 業務再開の判断が遅れ、経営に影響
- 適切な対応ができず、労災リスクが拡大
トヨクモの 『安否確認サービス2』 なら、災害時に安否確認通知を一斉送信し、回答を自動集計できます。
「誰が出社できるか」「支援が必要な従業員は?」を即時に把握し、最適な判断が可能になります。
すでに製造業・建設業をはじめ、多くの企業で導入され、初動対応の迅速化につながっています。導入企業の事例をこちらのページで紹介しているので、ぜひご覧ください。
▶︎安否確認サービス2の導入事例を見る