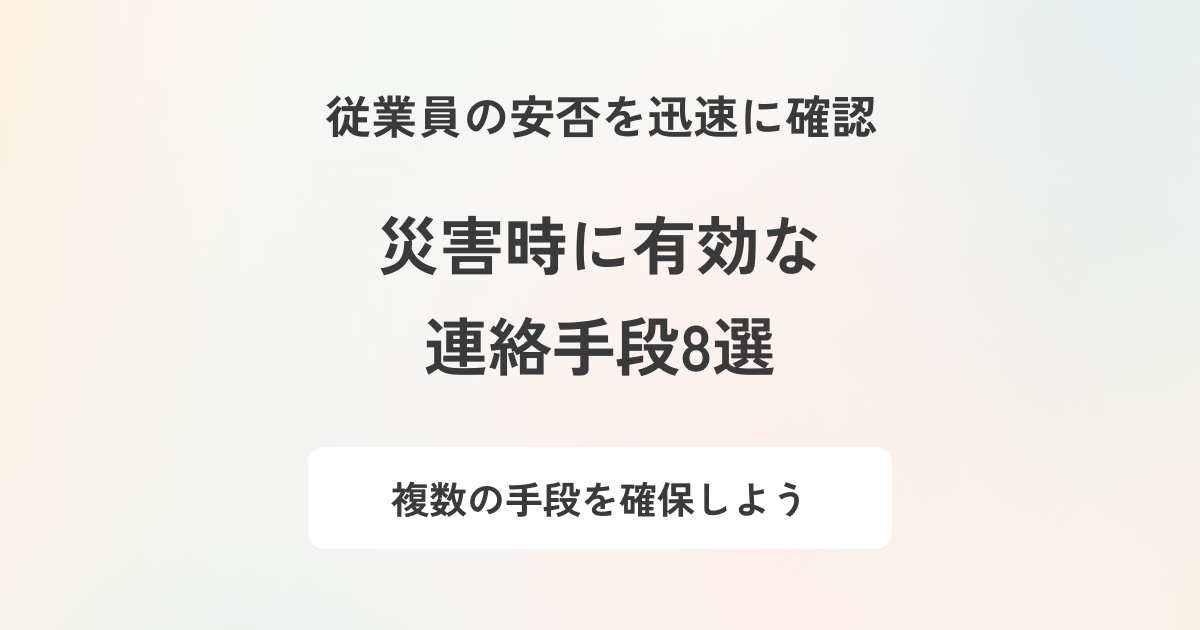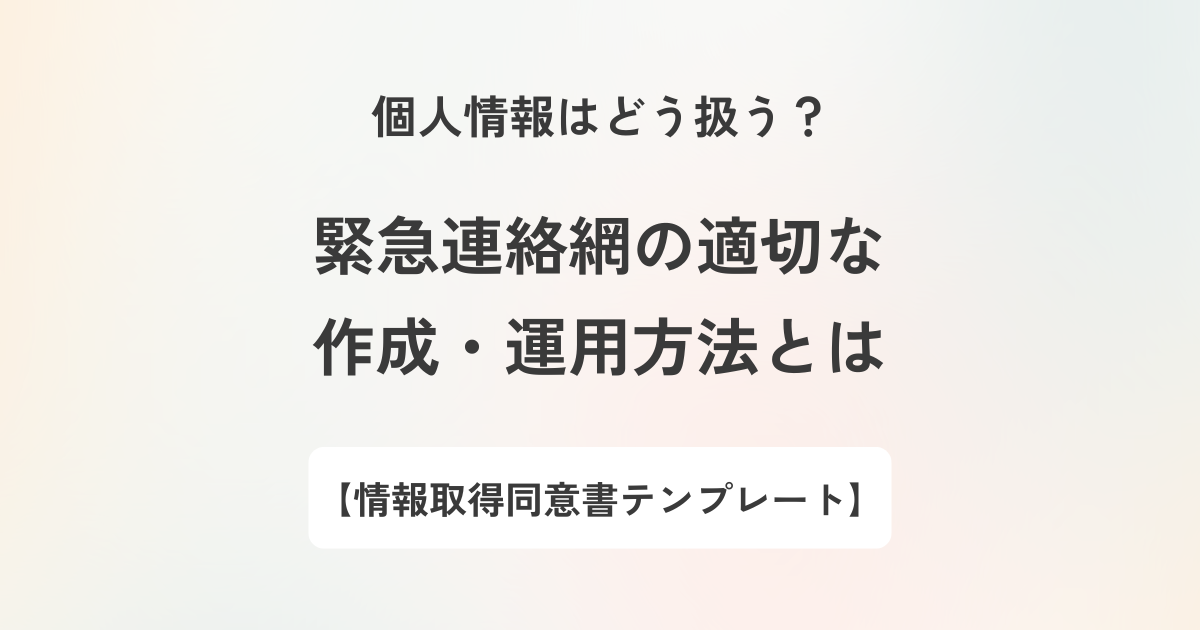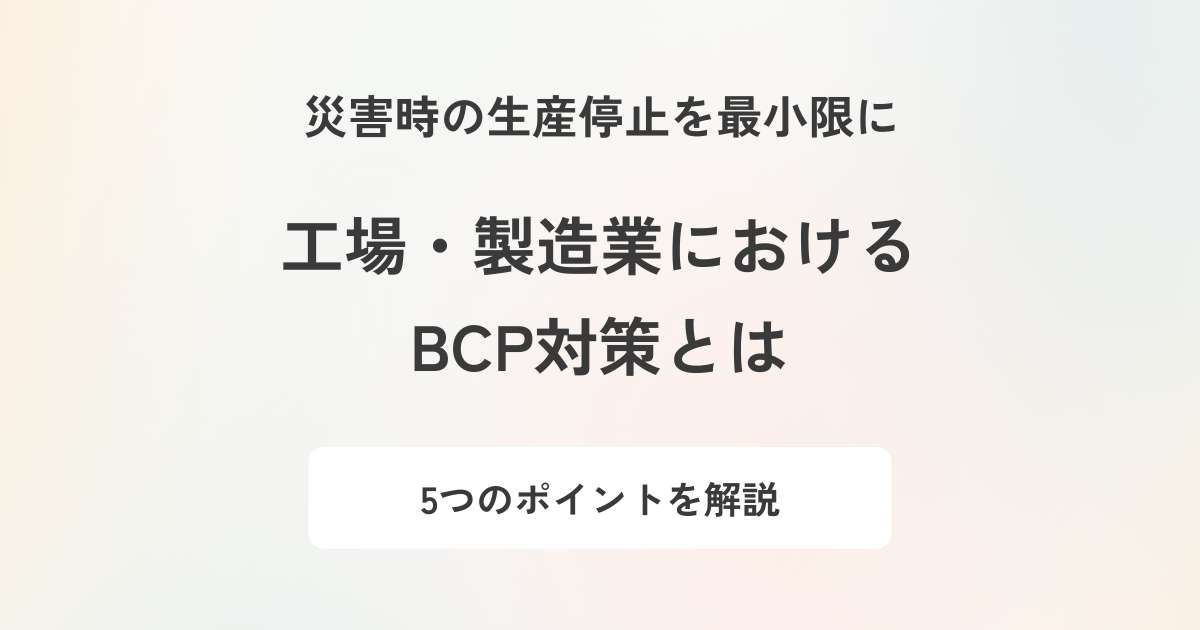【大学BCPの専門家が解説】大学のBCPとは?必要性や策定のポイントを解説

福岡 幸二(ふくおか こうじ)
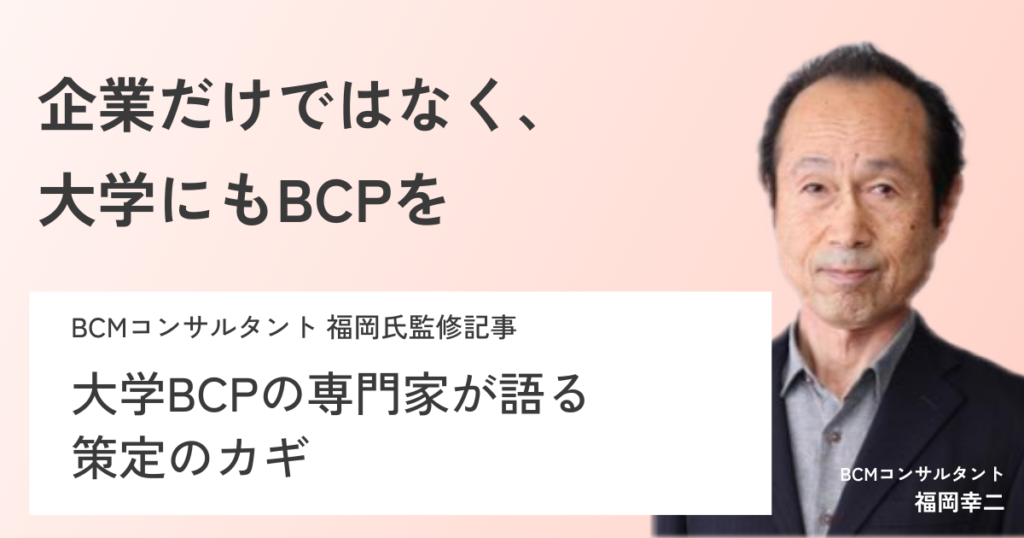
大学のBCP(事業継続計画)は、緊急時に学生や教職員の安全を確保し、業務の継続を図るために欠かせないものです。また、企業のBCPとは異なり、大学特有の状況や課題に対応する内容が求められます。
この記事では、BCP&BCMコンサルティングの代表を務め、実際に沖縄科学技術大学院大学や九州大学などでBCM(事業継続マネジメント)の策定や研修に携わってきた福岡 幸二氏が、大学のBCP策定におけるポイントを解説します。専門家の知見をもとに、実践的なBCP策定・改善の参考としていただければ幸いです。

目次
なぜ大学のBCPが必要か

大学とは教育や研究を行う機関です。また、地域社会での知的・文化的拠点として中心的な役割を担っており、これからも地域や社会、経済、文化などに貢献していくことが期待されています。大学は地域活性化の重要な要素のひとつであり、実現には大学生という若い人的資源の確保も大切です。大学におけるBCPは、こういった大切な役割を担っている機関を守るために必要となります。
大学が抱えるリスク
大学におけるBCPは以下2つの側面からの策定が重要です。
ひとつは、自然災害リスクです。近年の気候変動による災害の激甚化を受け、大学もこれまで以上に自然災害への備えを強化する必要があります。
- パンデミック
- 地震・津波
- 気候変動による災害の激甚化(台風・大洪水など)
そしてもうひとつは、人為的な災害です。大学は多くの人が集まる場であり、学術研究に伴うリスクも抱えています。
- 河川・海洋・山岳での教育研究活動中に発生する死傷事故
- 化学物質などの実験中に発生する火災・爆発や健康阻害などによる死傷事故
- 爆破予告・テロ
- 軍用機の墜落や原子力発電所からの放射性物質放出など、大学の立地特性による重大事象
大学のBCPは、安心できる教育機関として、在籍する学生の安全を確保し公設避難所を設けたり、研究データの保存、破損した備品や研究のための危険物などを管理したりするなどの対応が必要となってきます。
また近年、地域や社会に貢献する施設であることが大学には求められるようになってきています。このような背景を受けて、災害発生時に近隣住民の避難所となることができるような対応も求められています。
学生が安心して教育を受けられる・研究ができる施設であることや、地域や社会にどの程度貢献できるかといったことは、大学の評価にもつながってきます。学生や地域から支持される大学としてあり続け、大学経営をしっかりと行っていくためにも、大学のBCPは企業に劣らないくらいに必要だといえるでしょう。
(参考:月刊総務オンライン 事業継続計画(BCP)の必要性とそのメリット)
(参考:リスク対策.com 第15回 大学の事業継続(1))
(参考:文部科学省 公立大学の役割)
【何が必要?】大学のBCPに必要な基本事項リスト

大学のBCPに必要な基本的な項目は次の通りです。
1. BCP策定前の分析
BCPの内容を決定する前に BIA(事業影響度分析) を実施し、自然災害が大学に与える影響を可視化します。
その分析結果をもとに、BCPを策定しましょう。
2. 組織体制の記述
- 災害対策本部と各対策班の組織構成を明確化
→ 特にキャンパスが分散している大学では、災害対策本部と各キャンパス・部局との関係や指揮命令系統を明確にする必要があります。組織構成が適切でなければ、BCPは機能しません。 - 災害対策本部と各対策班責任者の代行順位を明記
3. BCPの基準を設定
- BCPの発動基準と災害対策本部の解散基準を明記
- 教職員・学生の災害時行動基準を明確化
4. 対策班の役割と業務
- 各対策班の班員と役割を明確化
- 各対策班で、非常時優先業務表の作成
→ 各対策班で優先すべき災害対応業務を明示しておきましょう。
5. 災害復旧工程表の作成
災害時は 安否確認・被害状況の確認 を行い、その後、復旧を進めるための指針として災害復旧工程表 を活用します。
- この工程表は 大学のRTO(目標復旧時間)/ RLO(目標復旧水準) に基づいて作成します。
- 復旧状況の全体把握や担当者間の情報共有に役立つ ため、あらかじめ準備しておきましょう。
6. 人事異動に伴うメンバー表の更新
- 大学では 毎年複数回の定期的な人事異動 が行われるため、それに合わせて 災害対策本部および各対策班のメンバー表を更新 します。
- メンバー表はBCP本文とは別に作成し、氏名を掲載
- 更新時には、各対策班の慣熟訓練を実施しましょう。
7. 備蓄・物資管理
- 備蓄食料・資機材の基準表をBCPに掲載
掲載することで、BCP担当部署が全学の備蓄状況を把握できるようにしましょう。
8. BCPの教育・周知
- 全教員に対するBCPの説明を実施
→ 災害発生時に 迅速な安否確認・被害軽減対応 を行うために行います。 - 災害対応チェックリストを作成し、教員と共有
9. 災害シナリオの考慮
- ライフラインの有無を想定したBCPを策定
→電気・ガス・水道が使える場合・使えない場合を想定しましょう。
10. 特別な配慮が必要な対象者
- 日本語を理解できない外国人留学生や障害を持つ教職員・学生への対応を考慮
11. 学生ボランティア活動
- 活動範囲を明記し、安全に活動できるよう配慮
12. 施設・避難場所の明示
- 各種施設の所在地を図示
- 災害対策本部(代替場所含む)
- 避難場所
- 帰宅困難者待機場所
- 備蓄倉庫
- 被災住民避難場所
13. BCPの継続的改善
- 訓練の実施
- BCP職場巡視の実施
- BCP内部監査の実施
→ 各実施時期や内容を明記
具体的にBCPに何を盛り込むか
では、具体的に大学のBCPとはどのようなものなのでしょうか。
大学の場合は、「学生の安全確保、教育研究の再開、地域との連携や協力」が何よりも重要な業務ですから、これらをできるだけ短期間で遂行できるようにすることがBCPとなります。災害が発生する前に、消防や警察、自治体及び町内会などと連絡を取り合って防災活動を行ったり、非常時に学生がすぐ対応できるよう、避難訓練や消火活動を行ったりしておくこともBCPのひとつです。
さらに、災害時には災害対策本部を立ち上げて、指示を各部局に伝達できるようにしたり、建物の倒壊や人の流れなどを勘案して避難所や集合場所を作ったりすることなどが挙げられます。また、学生や教職員の安否確認・安全確保も重要なBCPとなるでしょう。負傷者を救出したり、帰宅困難の学生の食事や飲料水を配給したりといった対応を行います。食料については、大学事務局が大学生協と災害時協力協定を結ぶことで災害発生時に大量の食料を迅速に確保できるメリットがあります。
そして、研究施設の中には、危険物や高圧ガス、放射性物質、化学物質、実験動物、細菌類などを取り扱っているところもあります。これらの化学薬品やガスによる二次災害、放射性物質の流出、実験動物の逃げ出し、ウイルス・細菌類などの実験室外への流出、遺伝子を取り扱う実験では組み換え体の環境への拡散などを防ぐために、大学内の各専門委員会と災害対策本部が協力して、迅速な広報活動、安全な取り扱いや処理を行う必要があります。
加えて、学生や教職員だけでなく、地域住民を受け入れる避難所として機能したり、他大学との連携を図ったりすることも大学ならではのBCPです。仮に他大学が被災していれば、その大学の学生を受け入れ、学生が研究できる環境を確保するなどの必要も出てきます。
教育機関として、いつから授業が開始できるのか、卒業や入学はどうなるのか、といったことを明確に提示するのも大学のBCPです。教育機関としての使命を果たし、近隣住民に貢献していく業務が大学のBCPなのだといえるでしょう。
大学のBCPの取り組み例
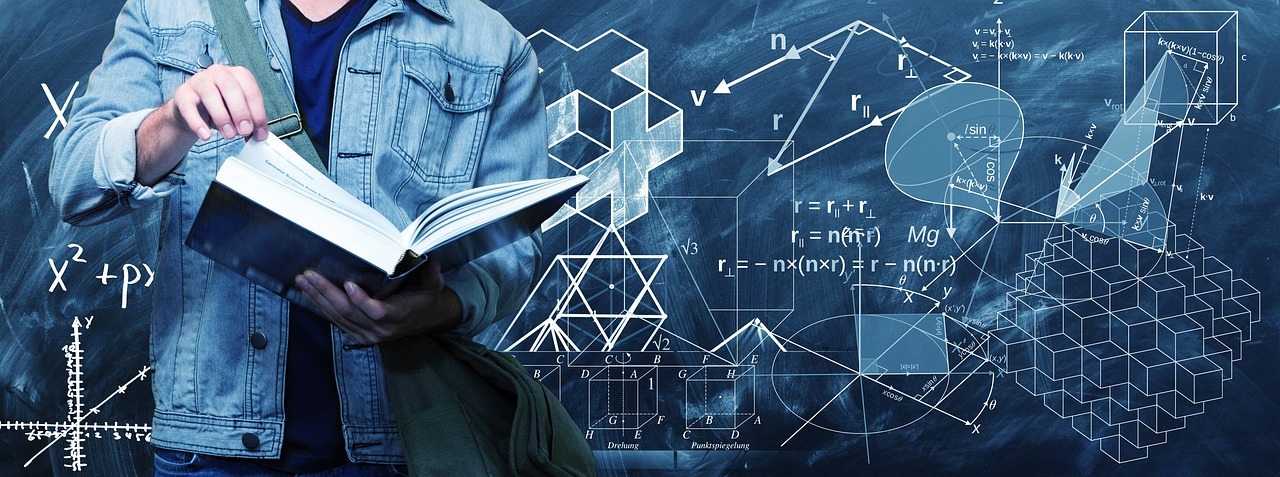
では、実際の大学におけるBCPの実例とはどのようなものがあるのでしょうか。実は、BCPを導入できている大学はそれほど多くはありません。日本大学危機管理学部の福田充教授らの調査によると、BCPを策定済みの大学は全体の9.4%しかないそうです。
BCPを策定済みの大学で行われている実例を見ていくと、大きく以下の4点を目標にしてBCPが行われているのがわかります。
- 学生や教職員の安全を確保し、近隣住民への支援なども行う
- 学生への教育を継続して行えるようにする
- 入学や卒業式といった行事を行えるようにする
- 研究や学業環境の復旧
これらの目標を達成するために、各大学では様々な取り組みを行っています。
その事例をひとつひとつ具体的に見ていきましょう。
1. 学生や教職員の安全を確保し、近隣住民への支援なども行う
まず、学生や教職員の安否を確認するためのメーリングリストやWebアプリの作成が挙げられます。さらに、日本語が不自由な留学生への対処や非常時の各種連絡先の取り決めなどを行っています。災害発生時に取るべき行動を示した多言語対応のポケットガイドを配布している大学もあります。
多くの学生はSNSで通信しています。そのため安否確認システムはメールのみならずSNSからも送受信できるシステムを選択条件にする必要があります。また、教職員学生数が数万人規模の大学では、安否確認システムの登録人数制限がなく、研究室、部署や部局ごとに集計できる機能を備えたシステムであることが条件になります。
多くの大学教員と学生は、キャンパス外や国外で教育研究活動を行っています。この状況を考慮し、本学キャンパスでの大災害発生を想定した安否確認体制と訓練が必要です。
近隣住民への支援については、自治体(市町村)と災害時協力協定を締結することを勧めます。備蓄食糧と避難所の運営は基本的には自治体が準備、担当することになります。
2. 学生への教育を継続して行えるようにする
災害時にも学生たちの教育を継続して行えるようなBCPとして、授業時間の確保や単位認定、推薦書や各種証明書を発行するといったことを行っています。大学のホームページなどを活用していつから授業が開始できるのかを明確に示したり、大学のキャンパスが被災して使用できなくなることを想定して、協定を結んでいる他大学の施設を使えるように事前に協議したりしている大学なども存在します。
大災害で教室が使えなくなった際、代替教室の設置場所や設置方法を事前に準備しBCPで明記する必要があります。キャンパスが分散している場合には被害の小さいキャンパスの教室を利用するなどの選択肢があります。リモートを活用する手法もありますが、それらを併用することも考慮すべきでしょう。
3. 入学や卒業式といった行事を行えるようにする
入学試験などを災害時でも行うための対策や、被災した受験生への対応を事前に練っておくことが挙げられます。また、災害が卒業時期と重なった場合は、卒業生に学位記を授与する式をどのように行うかといったことや、就職活動の支援体制を維持していくための業務維持の対策などを行っている大学があります。
入学試験中、入学式の最中など重要な行事中に大地震が発生した時の現場の教職員の対応は重要です。BCP担当部署と学務部が事前に協議して対策を講じます。
4. 研究や学業環境の復旧
研究は大学で重要な位置を占め、研究活動の復旧は重要項目です。そのため、被災した研究室の停電時の対策、研究室や研究機器が被害を受けた時の対応、研究データのバックアップ、火災発生時や地震発生時の研究室としての対応、被災研究室の代替の研究室の準備、提携大学での研究の再開などについて事前に大学事務局と各部局・研究室が協議して対策を講じます。
沿岸地域、低地に研究施設を設置している大学が多数存在することから津波対策は必要になります。インフラ破壊時の研究室と災害対策本部又は部局との通信手段、安否確認方法、現地までの移動手段、現地対策基地の設置などについて検討する必要があります。
これらの例からもわかるように、BCPを策定している大学においては、学生や地域住民のケアのための活動や、教育研究施設としての役割を維持できるようなBCPが行われている、といえるでしょう。
(参考:西日本新聞 BCP策定は大学の1割だけ 災害時の業務継続計画 熊本地震2年、日大教授調査)
(参考:内閣府政策統括官 TEAM防災ジャパン 【防災施策】BCP策定は大学の1割だけ 災害時の業務継続計画 熊本地震2年、日大教授調査)
(参考:日本大学 平成29年度日本大学理事長特別研究 シンポジウム「大学における危機対応とレジリエンス」のご案内)
(参考:神戸大学 大地震による被災を想定した事業継続計画(BCP))
(参考:リスク対策.com 第15回 大学の事業継続(1))
企業だけでなく、大学にもBCPの策定が求められる
これまで、BCPは企業向けのものという認識が一般的でした。しかし、大学が教育・研究機関としての役割を維持し、学生や教職員の安全を確保するためにも、BCPは不可欠です。 特に大学は、組織構造や目的の点で、BCPの内容と実装に至るまでのプロセスが異なります。
よって、大学教職員のみでBCPを策定するには限界があり、長期間試みても実効性のある計画を完成できないケースもあります。 そのため、大学の組織構造や研究環境を理解した、実績のあるBCP専門家の支援を受けることが、現実的かつ効果的なBCP策定につながります。
加えて、緊急時に学生・教職員の安否を迅速に把握することは、大学BCPにおいて重要な要素のひとつです。 そのため、安否確認システムの導入を検討し、災害発生時の情報共有・対応のスピードを向上させることが求められます。
大学が災害に強い教育・研究機関として存続し続けるために、今こそBCPの整備を進めることが重要です。

編集者:遠藤 香大(えんどう こうだい)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部に所属。RMCA認定BCPアドバイザー。2024年、トヨクモ株式会社に入社。『kintone連携サービス』のサポート業務を経て、現在はトヨクモが運営するメディア『トヨクモ防災タイムズ』運営メンバーとして編集・校正業務に携わる。海外での資源開発による災害・健康リスクや、企業のレピュテーションリスクに関する研究経験がある。本メディアでは労働安全衛生法の記事を中心に、BCPに関するさまざまな分野を担当。

執筆者:福岡 幸二(ふくおか こうじ)
BCP&BCMコンサルティング代表/元九州大学危機管理室 特任教授(博士) 神戸大学大学院海事科学研究科で博士号(海事科学)を取得。マンダリンオリエンタル東京、沖縄科学技術大学院大学、九州大学などで、地震・津波など自然災害や重大事故を含むBCM(事業継続マネジメント)を実装してきた実績を持つ。 2024年に起業しBCP&BCMコンサルティング代表として、大学や企業にカスタマイズされたBCM(事業継続マネジメント)およびSMS(安全管理システム)の構築を提供している。 国際海事機関(IMO)の分析官や事故調査官として国際的な活動も経験。著書に『Accident Prevention and Investigation: A Systematic Guide for Professionals, Educators, Researchers, and Students』(2025)、『Safer Seas: Systematic Accident Prevention』(2019年)があり、大学の実験室での事故防止策に関する論文をScientific Reports誌に発表するなど、現在国内外で活動し危機管理と安全管理を専門とする科学者兼実務家である。 プロフィール:https://bcp-bcmconsulting.com/about/