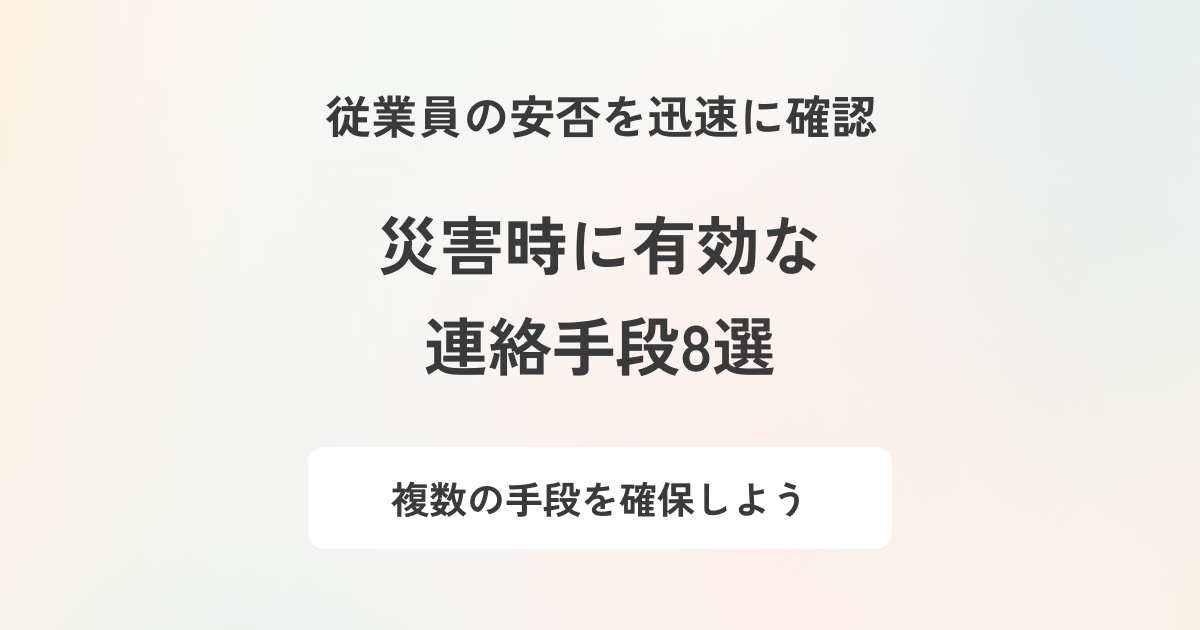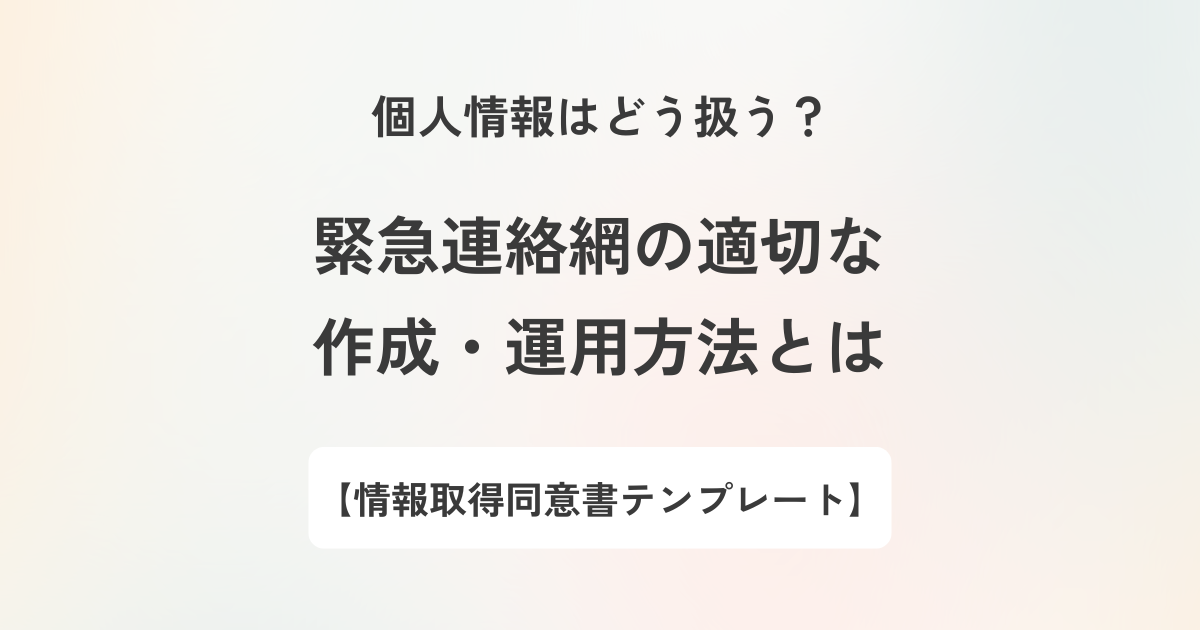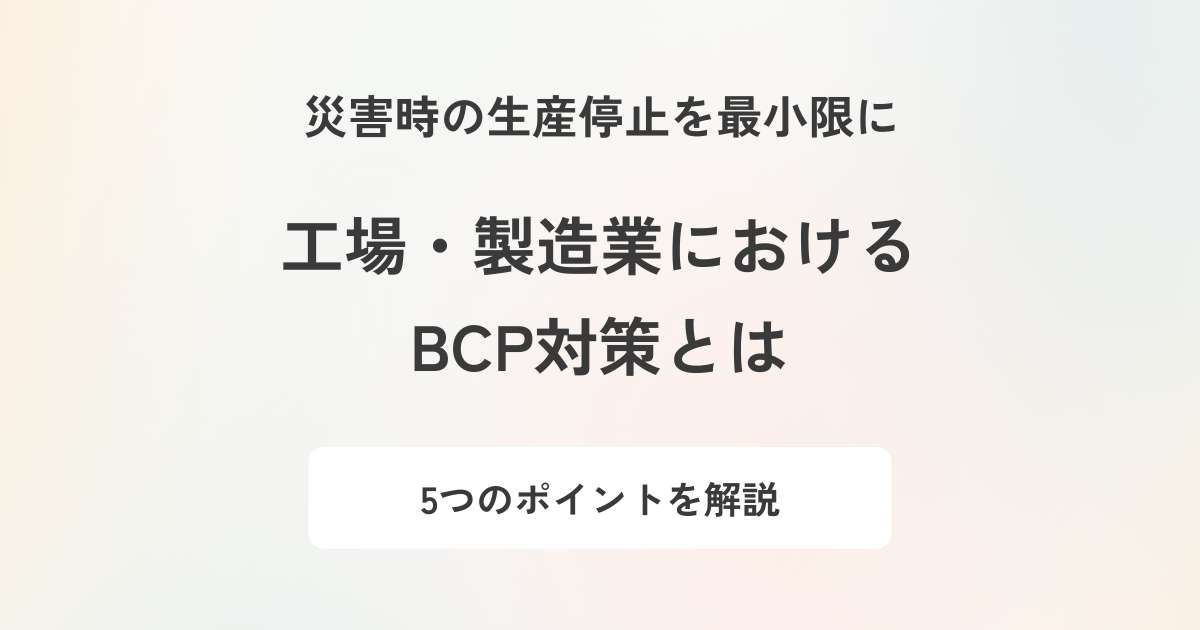安否確認とは?意味や方法、実施時の注意点をわかりやすく解説

坂田 健太(さかた けんた)
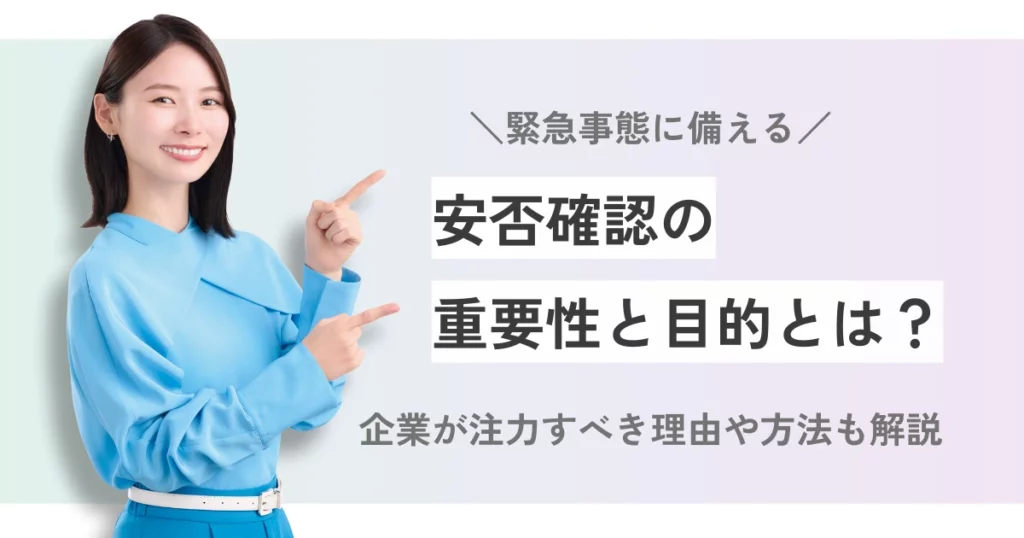
安否確認とは自然災害や感染症拡大など、緊急事態が発生した際に従業員の安否や被災状況を確認する作業です。被災の影響を軽減して事業運営を最短で再開するには、安否確認が欠かせません。
この記事では、安否確認の方法やおこなう意味、実施時の注意点などを紹介します。防災対策やBCP対策強化を検討中の企業は、最後までご覧ください。

目次
安否確認とは?意味や目的を解説
安否確認とは自然災害や火事などが起きた際、従業員の家族を含めて無事かどうか、確認する作業です。実務を担う従業員を一定数確保できない限り、事業運営の継続はできません。
また、事業再開までの期間が遅くなるほど、損失の額も増えます。
そのため、安否確認の目的は従業員全員の無事を素早く確認し、損失の軽減や最短での事業復旧を実現させることが重要です。
従業員の被災状況や避難場所、出社可否を確認した上で、事業復旧に向けた作業へ移行します。
企業が安否確認をおこなう目的
安否確認を実施する目的には以下4つの内容があげられます。
- 従業員と家族の安全を確認するため
- 法律違反を避けるため
- 最短での事業復旧を実現するため
- 取引先への情報発信をおこなう必要があるため
内容を一つひとつ確認しましょう。
従業員と家族の安全を確認するため
自然災害や火災、感染症拡大など、緊急事態が起きた際は、従業員と家族の安否確認を最優先で実施しなければなりません。緊急時の初動対応が遅れた場合、従業員や事業所など、経営資源での損害が大きくなる可能性が高まります。
特に地震や津波、土砂崩れなどの自然災害は、いつ発生するか予測できません。災害発生のタイミングや従業員の職種によっては、移動中や外出先に被災するケースも考えられます。
従業員の家族を含めて無事や避難場所、出社可否を確認できれば、事業再開に向けての指示が出しやすくなります。
また、自身の安全を確保できたとしても、同じ事業場で働く従業員が無事かどうか、気になることもあるでしょう。従業員の不安を軽減するためにも、安否確認を素早く実行することが重要です。
法律違反を避けるため
企業には従業員が安全に働ける環境を整える法的義務があります。
労働契約法第5条にて、企業はいかなる場合においても従業員の安全を担保する義務があると明記されています。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
各従業員の勤務場所に関係なく、全ての従業員の所在地・怪我の有無・それぞれの出勤・対応可否を迅速に確認・把握しなければなりません。
企業の方針にもよりますが、安否確認の対象は従業員本人だけでなく、その家族にも及ぶこともあります。
また、従業員の安全配慮義務については、労働契約法だけでなく、労働安全衛生法にも記載がされています。
(事業者等の責務)
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
最短での事業復旧を実現するため
大規模災害に被災しても従業員の安否確認を素早く終えられれば、最短で事業を再開できる確率が高まります。従業員の無事や出社可否の人数を把握できると、事業復旧に向けての対応や流れを指示しやすくなるためです。
被災後に従業員の安否確認や被災状況の把握が遅れた場合、事業停止期間が長引く可能性が高まります。事業再開の目途が立たないと、顧客離れによって損失の額も増えるでしょう。
被災前と同様に商品・サービスを継続して提供するには、実務を担う従業員を確保しなければなりません。安否確認の際は避難場所や出社可否、家族の無事など、事業再開に向けて必要な情報を集めていきます。
取引先への情報発信をおこなう必要があるため
自社の被災状況を問わず、取引先や各種関係者への影響を最小限に留める義務があります。顧客や取引先は今後も継続して自社が提供するサービスや商品を利用できるかが、気になっている状況です。
仮に事業が再開できない場合、顧客や取引先は類似商品またはサービスを提供している企業を探さなければなりません。顧客や取引先を安心させるためにも、以下に関する情報を可能な限り早い時期に発信しましょう。
- 自社の被災状況
- 事業継続の可否
- 復旧作業の有無
- 事業再開予定時期
事業継続の可否や再開予定時期がわかると、顧客や取引先が復旧までの代替措置を講じやすくなります。
安否確認の方法
安否確認の方法には以下6つの選択肢があげられます。
- 電話
- メール
- SNS
- ビジネスチャット
- 災害用伝言板
- 安否確認システム
それぞれのツールがどのように活用できるか、詳しく見ていきましょう。
電話
電話での安否確認は、最もオーソドックスな方法の一つです。
個人が個人に対して電話で安否確認をおこなう場合、相手が電話に出られる状態であればすぐに安否を確認できます。お互いに相手の声を聞くことで、安心感も高まるでしょう。
しかし、企業が電話を用いて安否確認をおこなうことはあまり推奨されません。まず、災害時は回線が混雑し電話がつながりにくいことが考えられます。
また、電話は相手の時間を半ば強制的に拘束します。被災状況によっては、すぐに応対できない場合もあるでしょう。
そもそも、従業員数が多い企業であれば安否確認の担当者が全員に電話をかけること自体、非現実的と言えるでしょう。
メール
メールも電話同様、最もオーソドックスな安否確認手段の一つです。
電話と違い、送られた側は好きなタイミングで回答できるため、まずは自身の安全を確保してから落ち着いた状況で安否状況を伝える、といった対応が可能となります。
しかし、誰かに安否確認の連絡を入れるたびに新規で文章を作成していてはキリがありません。特に企業が従業員に対し、メールを用いて安否確認をする場合は、事前に文面のテンプレートを作成しておきましょう。
メールの場合はやり取りの記録が可視化されるため、誰が誰に対して安否確認をおこない、どのような回答が得られたかを追いやすいというメリットもあります。
一方で、企業が従業員に対してメールで安否確認をおこなうことにはデメリットもあります。
まず、社用メールアドレスに対して安否確認メールを送る場合、勤務時間外は社用メールアドレスに届くメールを一切確認していない、といったことも考えられます。
あらかじめ聞いていた私用のメールアドレスにメールを送る場合でも、メールアドレスを変更するなど、登録したメールアドレスをもう使っていないという理由で、同じくメールが読まれない事態も想定されます。
また、メールも電話同様、回線の混雑によりメールの送受信に時間がかかったり、そもそも届かなかったりといったリスクも考慮しなければなりません。
相手の時間を不必要に拘束しない、やり取りが可視化されるなど電話にはないメリットはあるものの、災害時において完璧なツールではないことを認識しておきましょう。
SNS
SNSも安否確認ツールの一つとして近年活用されています。特にLINEのグループを使って部署ごとに安否確認をしたり、X(旧Twitter)を使って自社の投稿を従業員が拡散することで別の従業員や従業員の家族に必要な情報を届けたりすることも期待できます。
一方で、いくら拡散性が高いからといって、すべての従業員に情報が届くとは限らない、会社に自分のSNSアカウントを知られたくないといった理由で、SNSもまた完璧なツールではありません。
ビジネスチャット
日常的に社内でビジネスチャットを利用している場合、ログインや操作に手間をかけることがなく、円滑に安否確認のやり取りを行えます。
社用の携帯電話を常に携帯させたり、私用の携帯電話にも社用ビジネスチャットを入れておくよう事前に指示したりすれば、災害時にも連絡がつく可能性は高まるでしょう。
災害用伝言板(web171)
災害用伝言板とは震度6弱の地震や豪雨などが発生した際、家族や友人に自身の無事を伝言として残せる掲示板です。NTT東日本・西日本が提供しており、ドコモのスマートフォンや携帯電話を利用している方向けのサービスです。
災害用伝言板では、1つの携帯電話やスマートフォンから最大10件の伝言を残すことが可能で、1回のメッセージの上限数は、全角100文字以内に制限されています。
大規模な災害が発生すると、電話がつながりにくくなり、安否確認が難しくなることがあります。そんなとき、災害用伝言板を活用すれば、指定した家族や友人に対して無事を伝えられるでしょう。
安否確認を効率化する機能は利用できないため、個人向けの連絡手段と言えます。
安否確認システム
安否確認システムとは自然災害をはじめ、緊急事態が起きた際に従業員と素早く連絡を取るためのシステムです。一定水準以上の地震や津波などが発生した際、システムに登録している従業員の連絡先に安否確認メールが自動で配信されます。
従業員はいくつかの設問に答えるだけで、自身の無事を管理者へ伝えられます。回答結果は自動で集計されるため、管理者が作業をおこなう必要はありません。
また、メールや電話、専用アプリなど、複数の連絡手段に対応可能なシステムが多く、従業員との連絡手段を高い確率で確保できます。
さらに、データセンターの分散化や海外でのサーバー設置など、強固なネットワーク対策を講じているシステムもあります。大規模災害が起きたとしても、安定稼働が望めるでしょう。
安否確認システムの料金相場は?無料で使えるシステムの注意点も紹介
安否確認をおこなう際の注意点
緊急事態が起きる前に以下3点を理解し、対策を講じる必要があります。
- 緊急時は電話やメールが使えない可能性がある
- すべての従業員の安否確認が必要になる
- 回答結果の集計や分析が必要になる
災害の種類を問わず、緊急時にはすべての従業員の安否確認が必要です。連絡手段が限られていると、従業員の無事を確認するまでに多くの時間がかかります。
緊急時は電話やメールが使えない可能性がある
緊急時の連絡手段が電話とメールだけの場合、従業員の安否確認に時間がかかる可能性が高まります。自然災害が発生した際は、多くの方が家族や友人の無事を確認するために連絡を取るからです。
自然災害発生時の電話回線は通常と比べて、トラフィック量が50〜60倍に増えるため、相手との連絡が非常に取りにくい状況です。実際、東日本大震災の時はドコモ・au・ソフトバンクで、音声通信が最大95%制限されていました。
一方、メールはキャリアを問わず通信規制がなかったため、電話よりもつながりやすい傾向にあります。ただし、東日本大震災では、サーバーの処理能力以上にアクセスが集中した影響で滞留が発生し、メールの受信速度が低下しました。
電話やメールに比べると、インターネットサービスは比較的利用しやすい状況です。東日本大震災の際も、XやLINEは利用できたため、双方を利用しての情報発信が活発におこなわれていました。
基地局の予備電源の長時間対応化や大ゾーン基地局の建設など、インターネット通信の停電対策も進んでいます。緊急時に従業員の安否確認を素早くおこなうには、電話やメール以外の連絡手段を用意しておくことが重要です。
また、安否確認システムは専用アプリやLINEなど、連絡手段が豊富です。データセンターの分散化をはじめ、大規模災害対策も整備されており、従業員とのスムーズなやり取りが望めるでしょう。
すべての従業員の安否確認が必要になる
複数の地域に営業所や工場、店舗を展開している企業ほど、緊急時の連絡手段を豊富に用意しておかなければなりません。従業員との連絡手段が電話とメールのみの場合、従業員全員の安否確認が終わるまで、多くの時間が必要です。
電話は同じ避難場所に複数の従業員がいない限り、1対1で安否確認を進めなければなりません。メールの場合は従業員が見落とした場合、長期間回答が得られなくなります。
すべての従業員の安否確認をスムーズに進めるには、安否確認システムの導入がおすすめです。安否確認システムは専用アプリやLINE、SMSなど、複数の連絡手段に対応したシステムが多いです。
安否確認メールに未回答の従業員には自動で再送信するため、手間をかけずに回答率を高められます。
また、安否確認メールを配信する連絡先を管理者に公開することなく登録可能なシステムもあります。個人情報の開示に抵抗を抱える従業員の不安も軽減できるでしょう。
回答結果の集計や分析が必要になる
メールや電話を活用して安否確認をおこなう場合、回答結果の集計と分析を管理者が手作業で進めなければなりません。ただし、災害の規模や被災状況によっては、管理者が集計作業に対応できない可能性もあります。
安否確認システムを導入すると、管理者の被災状況を問わず従業員の無事や避難場所の確認などを進められます。多くの安否確認システムは、安否確認メールの送信〜回答結果の集計まで、一連の作業を自動化しているためです。
安否確認システムの導入によって、管理者の被災状況を問わず、回答結果を集計できる体制を整えましょう。
安否確認に関するよくある質問
安否確認に関してユーザーから多く寄せられた質問を以下に記載しました。
安否確認システムの機能とは?
安否確認システムの主な機能は、以下のとおりです。
- 安否確認メールの自動送信
- 未回答者に対し自動で再通知
- 従業員の家族の安否確認
- 回答結果の自動集計
- 災害情報の取得
- 連絡先の登録
- グループ設定
気象庁と連携可能な安否確認システムを選ぶと、地震や津波などの災害情報を取得できるため、従業員に避難や安全確保を素早く呼びかけられます。
また、上記に加えて掲示板やチャット機能を利用できると、出社可否や今後の対応などに関して、従業員と情報を共有しやすくなります。安否確認システムを選ぶ際は、自社の求める機能が実装されているか、必ず確認しましょう。
安否確認と生存確認の違いとは?
安否確認と生存確認は、対象者や目的が異なります。
安否確認は緊急事態が起きた際、企業が従業員の怪我の有無や被災状況、避難場所を確認する作業です。従業員の家族を含めて素早く安否を確認し、事業復旧に向けた作業へ移行します。
一方、生存確認は自然災害や事故などが起きた際、友人や家族が対象人物の無事を確認する作業です。
BCP対策におすすめの安否確認の方法は?企業が行う目的も解説
安否確認システムを選ぶなら「安否確認サービス2」がおすすめ!
災害が起きた際は、すべての従業員の無事を確認しなければなりません。ただし、連絡手段が限られていると、従業員の安否確認に多くの時間が必要になります。
従業員の安否確認を素早く行うには、安否確認システムの導入がおすすめです。トヨクモの提供する「安否確認サービス2」はリピート率99.8%、導入企業数4,000社を超える安否確認システムです。
安否確認サービス2では、災害を検知した段階で安否確認メールを事前に登録した従業員の連絡先に送信します。一定規模以上の災害が発生したら自動的に送信されるため、人為的ミスは発生しません。
また、すべての契約企業を対象に年1回防災訓練を実施しています。防災訓練は実際の状況と同等の負荷を安否確認サービス2に与え、安定して稼働するかを確認する訓練です。
訓練結果は、トヨクモの定めるSLA(サービス品質保証)の基準を一度も下回ったことがありません。大規模災害の際も高いレベルでの安定稼働が望めます。
また、安否確認サービス2は初期費用や最低利用期間が発生しません。月額料金も中小企業が利用しやすいよう、リーズナブルな価格設定です。30日間の無料トライアルも設定されており、自社との相性を時間をかけて確認できます。
安否確認システムをお探しの方は、安否確認サービス2の利用をご検討ください。
企業における安否確認の意味を理解してシステムを活用しよう
企業における安否確認は、従業員の安否を速やかに確認し、安全確保を図ることはもちろん、その後の事業継続・再開の可否にも影響し、最終的には企業の存続にも関わる取り組みです。
安否確認の精度を可能な限り高め、BCPを機能させるには、従業員一人ひとりが安否確認の意味を理解し、当事者意識を持って取り組むことが重要であることはご理解いただけたと思います。
また、安否確認システムの導入が効率的且つ迅速な安否確認の実施に貢献することも説明しました。
トヨクモの安否確認サービス2は、無料のお試し期間を設定しています。
まずは使い勝手を試してから導入を検討したいと考えている企業様は、ぜひ一度無料お試し期間を活用してみてください。

編集者:遠藤 香大(えんどう こうだい)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部に所属。RMCA認定BCPアドバイザー。2024年、トヨクモ株式会社に入社。『kintone連携サービス』のサポート業務を経て、現在はトヨクモが運営するメディア『トヨクモ防災タイムズ』運営メンバーとして編集・校正業務に携わる。海外での資源開発による災害・健康リスクや、企業のレピュテーションリスクに関する研究経験がある。本メディアでは労働安全衛生法の記事を中心に、BCPに関するさまざまな分野を担当。