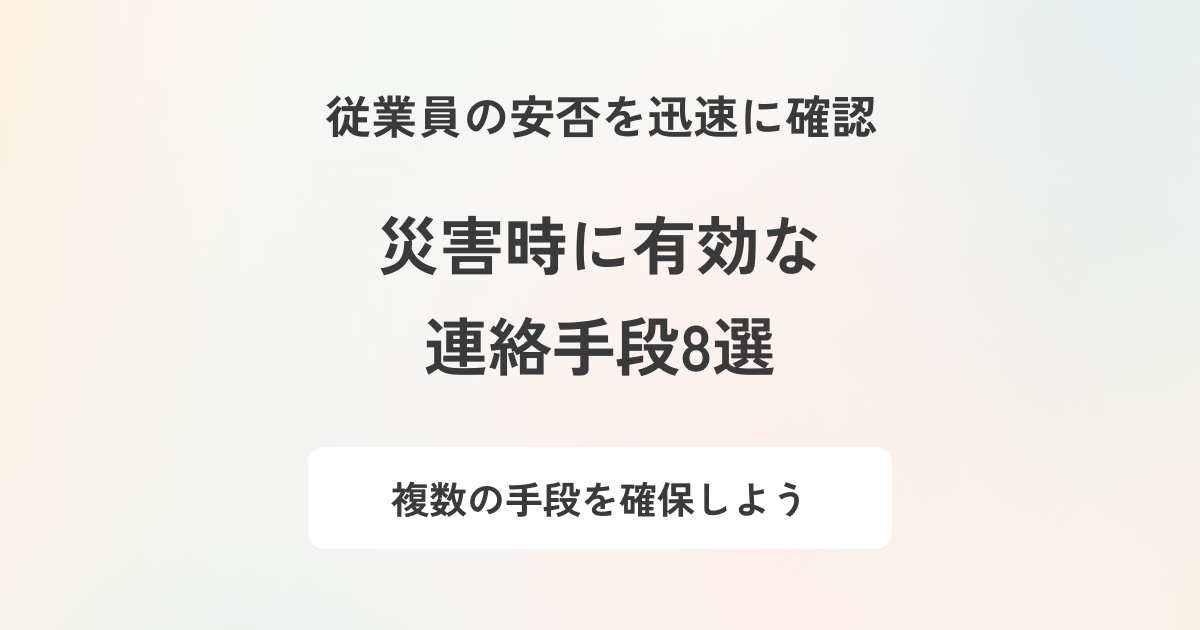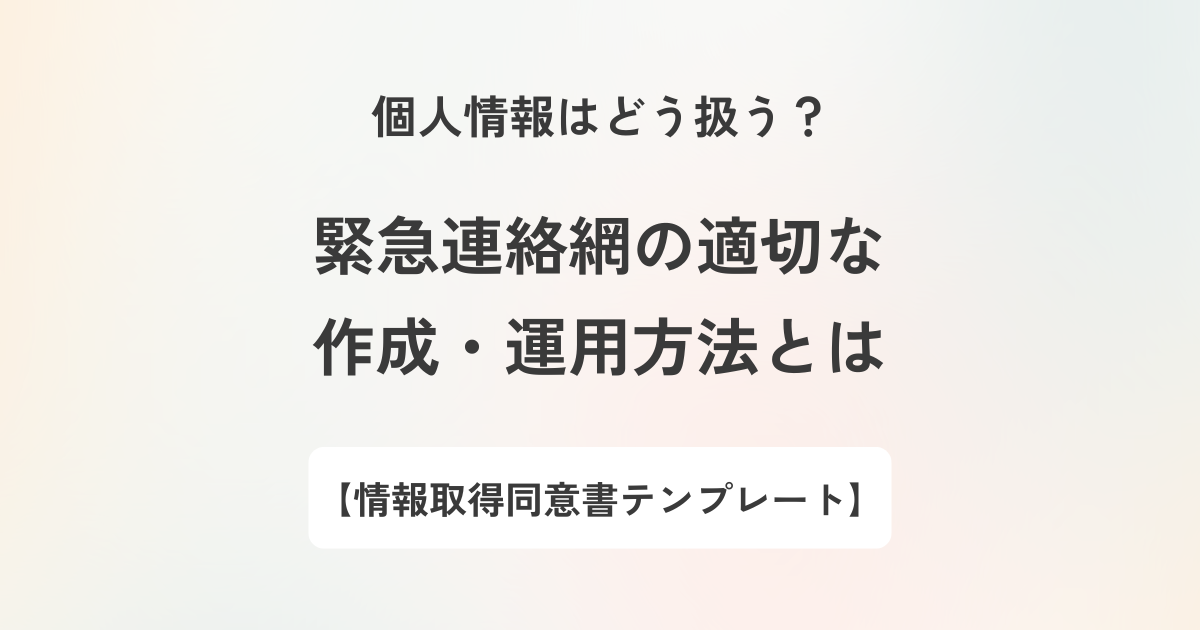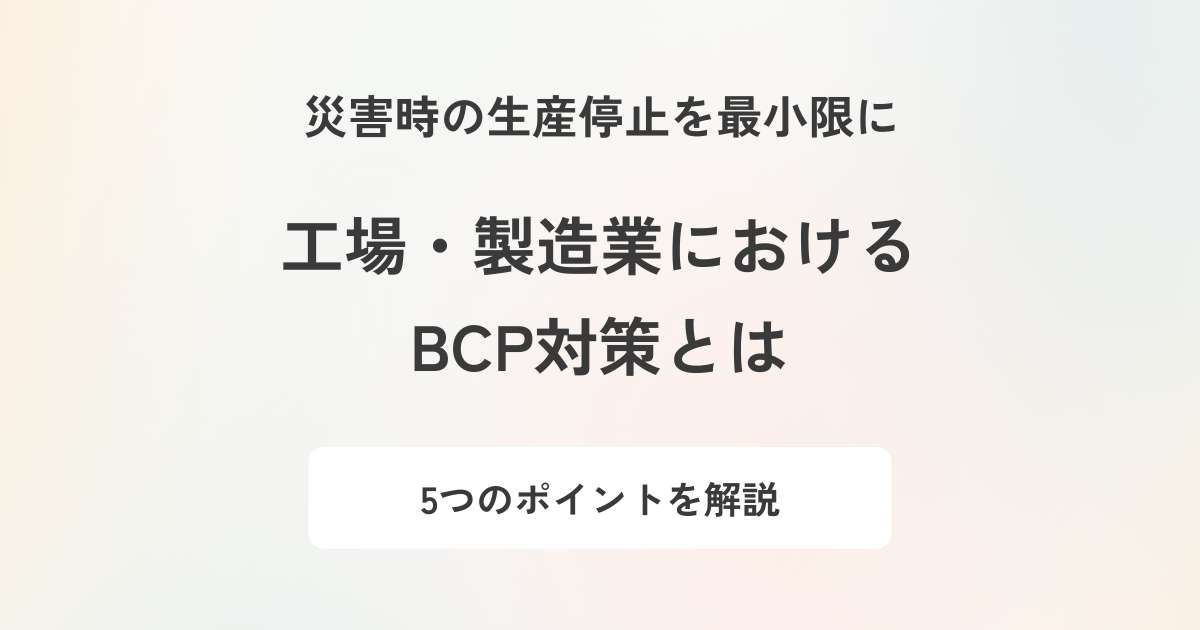策定で終わらない!本番を意識したBCP策定のポイント

遠藤 香大(えんどう こうだい)
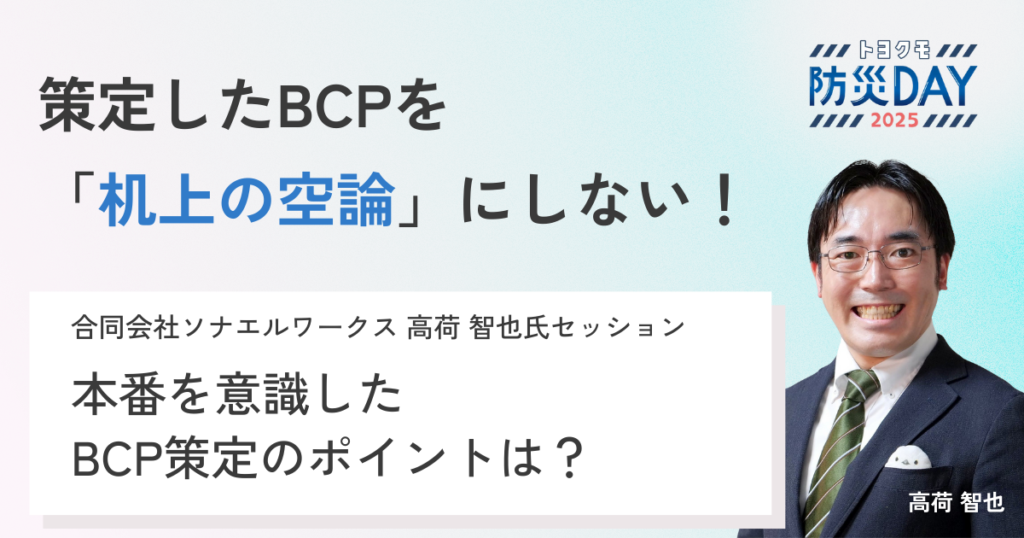
「BCPを策定したのに、机上の空論になってしまった」と感じる企業は少なくないでしょう。せっかく時間をかけてBCPを策定したにもかかわらず、いざ緊急事態が発生した際に使えないと意味がありません。
そこで今回は、「トヨクモ防災DAY2025」として、合同会社ソナエルワークスの備え・防災アドバイザーである高荷智也さんを講師にお招きし、本番を意識したBCP策定のポイントを解説していただきました。この記事では、高荷さんによる講演の内容をわかりやすくまとめてお届けします。

目次
ソナエルワークス プロフィール
「ソナエルワークス」は、備え・防災・BCP策定アドバイザー である高荷智也さんのフリーランス屋号。講師業や執筆業を中心に、防災に関する講演会・セミナーの実施、専門記事の執筆・監修、BCP(事業継続計画)策定のコンサルティング、災害時のコメント取材・メディア出演などの専門サービスを提供する。さらに、「備える.jp」や防災ECサイト「そなえるすとあ」の運営も行う。防災系YouTuberとしても活動する。
BCPが機能しない理由
まず、本番にBCPが機能しない理由は、主に以下の4つが挙げられます。
- 防災しかない・事業継続しかない
- 優先順位が定まっていない
- 経営層・事業部門が関与していない
- 本番時の初動対応計画がない
それぞれについて見ていきましょう。
1.防災しかない・事業継続しかない
1つ目の理由は、防災しかない・事業継続しかないことです。BCP対策が偏っていたり、必要な項目が抜けていたりすると本番で使えない可能性があります。有効なBCPを策定するためには「命を守るための対策」と「事業継続計画」の2つを兼ね備えておかなければいけません。
会社のなかには「BCPは難しいけど防災なら分かる」と思う方もいるはずです。たとえば、備蓄品の購入やハザードマップの確認など防災対策に力を入れている方もいるでしょう。ただし、このような防災対策だけで満足してしまうと、防災しかないBCPに仕上がります。
同様に、避難訓練や火災の消火訓練を実施したり、地震の揺れを体験したりするなど、防災に関する訓練や演習などに力を入れていると、事業継続に関する項目が抜けがちです。人命を守る対策は極めて重要ですが、BCPを考えるうえでは事業継続計画とあわせることがポイントです。
一方、事業継続計画は災害が起きても業務を止めないために作成します。つまり、言い換えると従業員が死傷しても業務を止めないためには、どのような準備が必要なのかを考えることです。事業継続の本質は事業を止めないことであり、決して従業員全員の命を守ることではありません。
もちろん、人命を軽視するわけではありません。事業継続は文字どおり「事業の継続」を指すことから、事業を優先的に守り、集中した対策が必須とされています。
反対に事業継続だけのBCPであれば、災害時にやらなくていい業務に従事する従業員の命を守れなかったといった事態を招きかねません。従って人命を守る計画は、事業継続とは別に取り組むべきと言えるでしょう。
2.優先順位が定まっていない
2つ目の理由は、優先順位が定まっておらず、守るべき対象が不明瞭なことです。非常時に使えるリソースはかなり限られているため、何を誰に対していつまでに提供するのかを具体的に定めておかなければいけません。
そもそも、BCPが必要な非常時は自然災害だけではなく、テロや戦争などさまざまな事態が考えられます。どのような非常時であってもBCPは重要ですが、すべての事態に同時に対応することはできません。
たとえば、大規模な地震が発生すると停電や断水、通信障害、交通網の停止といった被害が生じ、日常生活が止まることがあります。このような状況を想定した場合、「はたして自社の事業は必要なのか」を考えることが大切です。
金融業や小売業などは、インフラが止まっている状態であっても業務を継続的に行う必要があるため、復旧や代替案の計画が必要です。反対にサービス業や娯楽業、教育産業など、平時においては重要な仕事であっても、街が崩壊しているような状況下では無理に事業を再開しなくてもいい場合があります。
このような業界では、営業を止めている期間中の固定費を賄うための資金繰り計画のほうを重要視すべきとも言えるでしょう。災害時の優先順位を考えるうえで、あえて事業を継続しないという選択肢も考えてみてください。
また、単に休業するだけではなく、普段できなかった仕事を別の場所で行ったり、従業員を地方に集めて研修を行ったりすることも検討できます。BCPは「どのような状況であっても事業を継続しなければいけない」という計画ではありません。自社に応じた優先順位を考えておき、必要に応じて事業を止める判断を下すことも大切です。
3.経営層・事業部門が関与していない
3つ目の理由は、BCP策定を総務部門の防災担当者だけで作成し、経営層や事業部門が関与していないことです。防災対策は総務部主導で進めるものの、事業継続計画は経営や事業部門の知見を取り入れなければ作成することができません。事業継続には多くの経営資源が必要であり、何が必要でどうやって守るかを適宜判断しなければいけないからです。
また、BCP策定を行う際に重要な防災対策は、会社のなかにある経営資源を災害から守ることであり、これは防災の役割を担う総務部門でもある程度対応することが可能です。
しかし、想定不能な事態から守る、もしくは会社外にあるものから守るには代替・再調達という考えが必要となり、経営判断が必須とされます。
たとえば、想定外の災害で多数の死傷者が発生した、あるいはみんな無傷だったものの、出社ができなくなった場合の配置転換案などは、現場を知る経営層や事業部門でなければ対応できません。
さらに、仕入れ先や外注先の多重化は防災対策において不可欠です。非常時を想定したシステムの導入や仕組みの構築などは、総務部だけで整えることはできないため、会社全体を巻き込んだBCP策定を行う必要があります。
4.本番時の初動対応計画がない
4つ目の理由は事前計画のみを作成して、本番時の対応計画がないことです。どれほど事前準備を行っても初動対応計画がなければ、実際に動かすことはできません。
なぜなら、大規模な災害が発生した際、すぐさまBCPを発動することはないからです。具体的には、以下のような流れでBCPを発動させます。
| 対応方法 | 具体的な例 | |
| 1.命を守る行動を行う | ・事前に防災対策を施す ・災害時に実施できる計画を立てる | ・避難誘導の準備 ・備蓄品の配布計画 |
| 2.被害・安否状況の確認を行う | ・確認リストに沿って状況を把握する | ・優先順位に基づいた確認リストの作成 |
| 3.被害が甚大であればBCPを発動する | ・状況に応じて適切な判断を下す | ・意思決定者との連絡手段の確保 |
上記のような本番に向けての事前準備がなければ、非常時に使えないBCPに仕上がってしまいます。BCP作成者や担当者以外が防災活動を支えるためには、実行計画とマニュアルの作成が不可欠です。
平常時に必要なBCP基本計画は、緊急事態である災害時には一切見ません。非常時に必要な緊急時マニュアルは社内や受付に設置し、災害時に見なくてもいい情報と分けておくことがポイントです。
優先順位を決める際のポイント
BCP策定時における優先順位を決める際のポイントは、以下の3つです。
- 非常時にも継続すべき中核事業はなにか
- 非常時に優先すべき供給先はどこか
- 供給はいつまでに再開させたいか
まず、災害が起こっている状況下で、非常時でも継続すべき事業もしくは非常時にのみ発生する事業は何かを考えます。たとえば、災害時は食品会社が避難所に飲料水を届けたり、建築会社が道路の開通工事を担ったりすることもあるでしょう。
自社において「非常時にどういったことをやりたいか」「何を優先しなければいけないのか」を考えることが必要です。
そして、その定めた中核事業を「どの程度の基準」で「いつまでに開始したいのか」を検討しましょう。災害時は、平時と同程度のレベルで事業を継続する必要はありません。災害時の事業レベルの基準と再開目標に合わせた行動を行います。
たとえば、小売業の場合、平時であれば以下のような作業が生じます。
- 商品の仕入れ・検品
- 陳列・販売
- 清掃
- 棚卸
しかし、災害時は必要なものだけを仕入れて、販売するだけでも問題ない場合もあるでしょう。すると「倉庫から物を運んでくる」「お客さまに販売する」の2つの作業で済みます。そして、その作業を行うために必要なことをリストアップすれば、BCPで守るべき対象が明確になるはずです。
さらに、中核事業を行うために不可欠な、社内外の経営資源や情報を特定します。大きな災害が起こったとき、必要な経営資源がどのような被害を受けるのかを考え、その被害を軽減できる方法や代替策を検討しましょう。
災害発生時に必要な初動対応とは
災害発生時に必要な初動対応には、どのようなものがあるのでしょうか。最後に、初動対応について深堀りしていきましょう。
情報収集と一時判断
災害発生時の初動対応として重要なのは、以下の2つです。
- 災害情報を収集する
- 被害状況を把握する
とくに重要なのは、会社の中がいまどうなっているのかを調べることです。これは、被災した状態の業務に必要な経営資源などを素早く把握するための初動対応とも言えます。事前に調査項目をリスト化しておき、紙とデータの両方で保管しておきましょう。すると、いつ災害が発生しても必要な事柄を手際よく調査することができます。
また、社内確認で重要なのが従業員の安否確認です。「人」という経営資源を素早く確認して状況を把握するためには、安否確認システムの導入が有効です。
これらの確認の結果、被害が軽微であればBCPを使う必要はなく、普段の業務内で復旧させることができます。反対に、被害が甚大だった場合や状況を把握できない場合は、対策本部を招集して非常時の体制を整えていくことになります。
なお、以上の事柄をスムーズに進めるためには、電話・メールアドレス以外のスマホアプリを活用して各関係者と連絡を取り合える準備を整えておくことが重要です。さまざまなアプリがありますが、通常の業務でも使用できるアプリを選んでおくと災害時も活用しやすいでしょう。
また、安否確認システムを活用する場合はスマートフォンで受信・回答でき、集計まで行えるものを選んでください。メールアドレスのみ有効な場合だと災害時に利用できない可能性があるため、緊急時も活用できるものを選ぶのがポイントです。
専用アプリがある安否確認システムのおすすめ9選!選び方も解説
企業の福利厚生の活用
災害時に必要な初動対応に、企業の福利厚生を活用するのも一つです。防災備蓄品の一部を普段使いできるものに置き換えることで、社内の防災意識向上につながります。具体的な例は、以下のとおりです。
- 来客用の飲料やウォーターサーバー、自動販売機などを非常時にも活用できるようにする
- 社内にミニショップや置き総菜販売、置き菓子販売といったサービスを「見せる防災」として取り入れる
災害時専用の倉庫に片付けてしまうと、備蓄を準備した人しかその存在を知らないという状況に陥る可能性が高いです。防災用品や備蓄品を見える場所に設置して、事前に使い勝手を確かめておくのも有効です。
非常時に役立つBCPを策定しよう
今回は、本番に役立つBCPを策定するポイントについてお話をいたしました。
BCPを策定する際は多くの方を巻き込み、可視化していくことで従業員の意識向上や関心度合いを高めることができます。今回紹介した4つのポイントを見直して、ぜひBCPの改善もしくは策定に取り組んでいただければ幸いです。

執筆者:遠藤 香大(えんどう こうだい)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部に所属。RMCA認定BCPアドバイザー。2024年、トヨクモ株式会社に入社。『kintone連携サービス』のサポート業務を経て、現在はトヨクモが運営するメディア『トヨクモ防災タイムズ』運営メンバーとして編集・校正業務に携わる。海外での資源開発による災害・健康リスクや、企業のレピュテーションリスクに関する研究経験がある。本メディアでは労働安全衛生法の記事を中心に、BCPに関するさまざまな分野を担当。

執筆者:坂田 健太(さかた けんた)
トヨクモ株式会社 マーケティング本部 プロモーショングループに所属。防災士。 2021年、トヨクモ株式会社に入社し、災害時の安否確認を自動化する『安否確認サービス2』の導入提案やサポートに従事。現在は、BCP関連のセミナー講師やトヨクモが運営するメディア『トヨクモ防災タイムズ』運営を通して、BCPの重要性や災害対策、企業防災を啓蒙する。