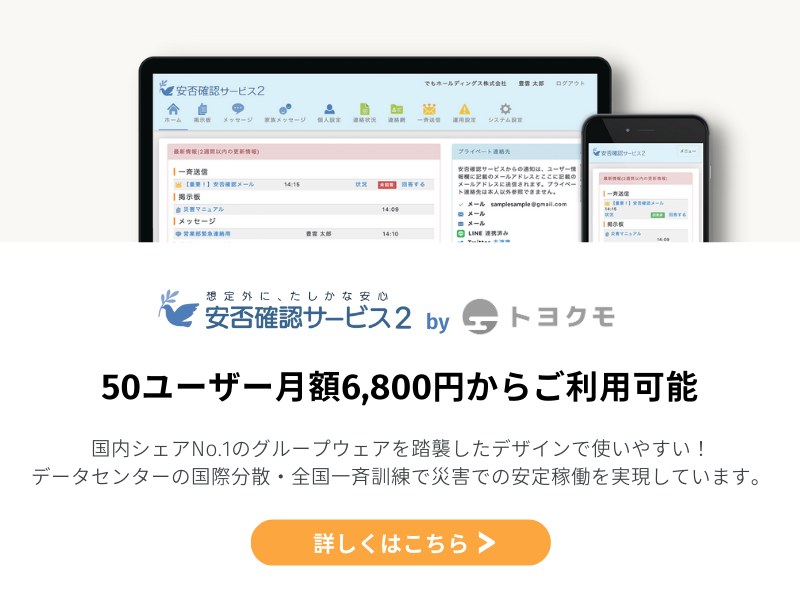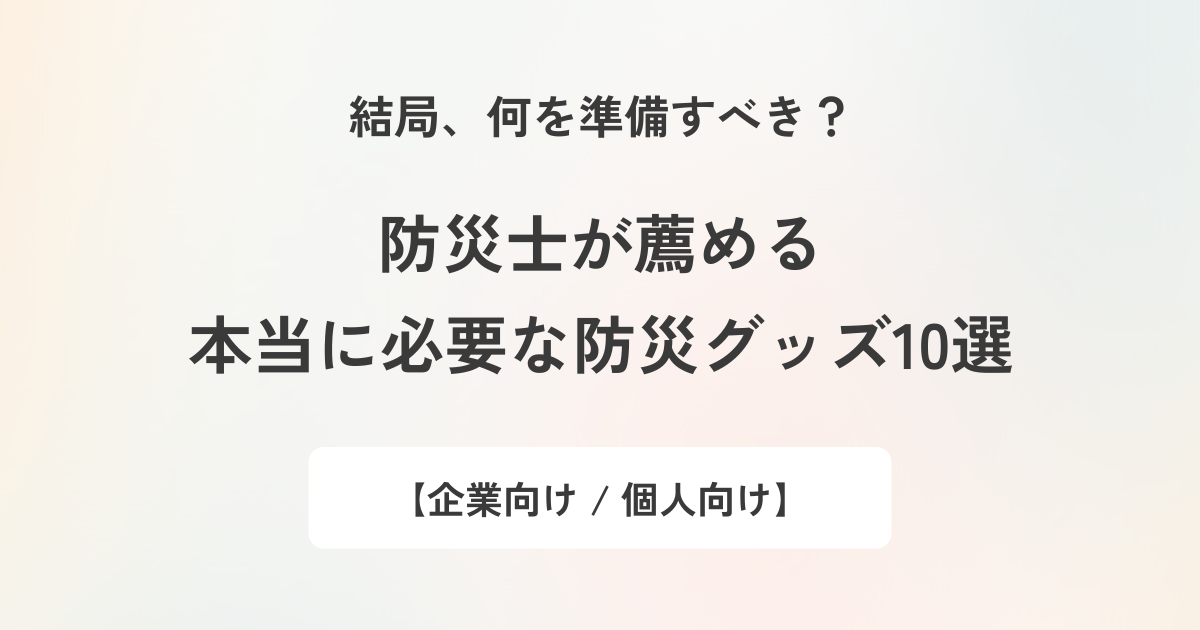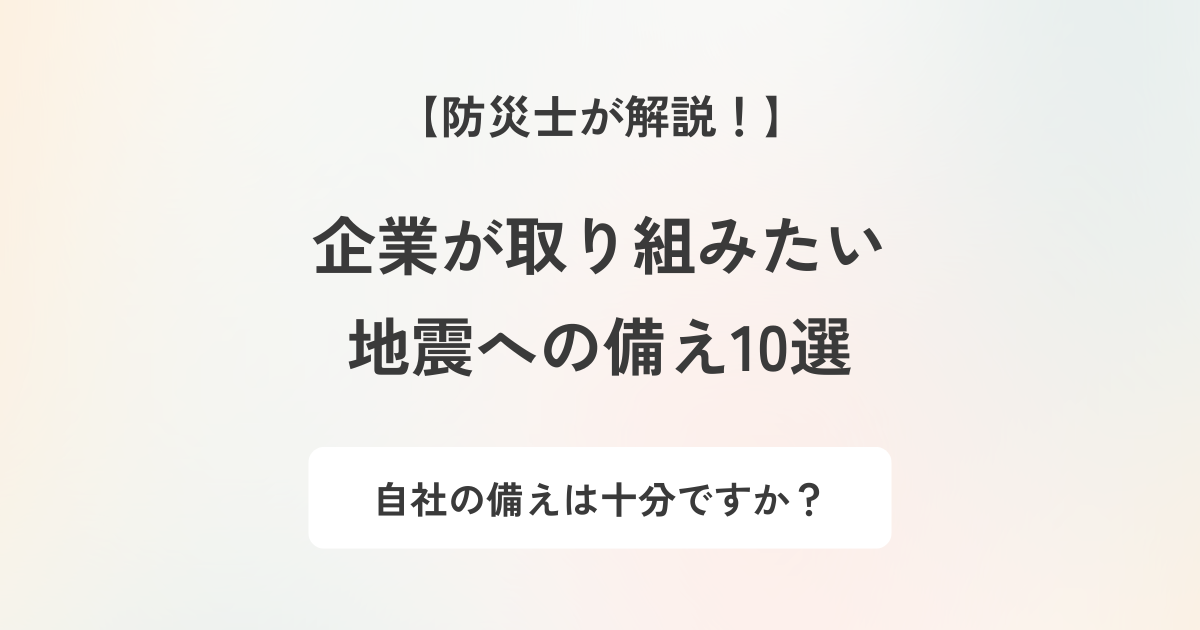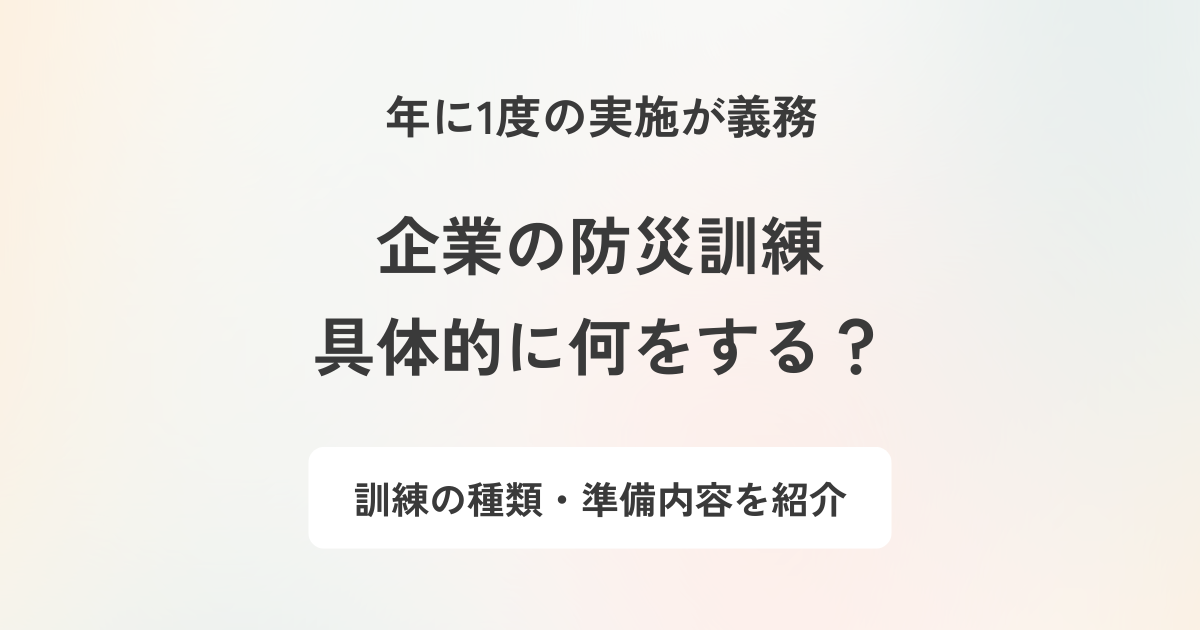【消防訓練は企業義務】行うべき訓練の種類や手順を理解して定期的に実施しよう

遠藤 香大(えんどう こうだい)
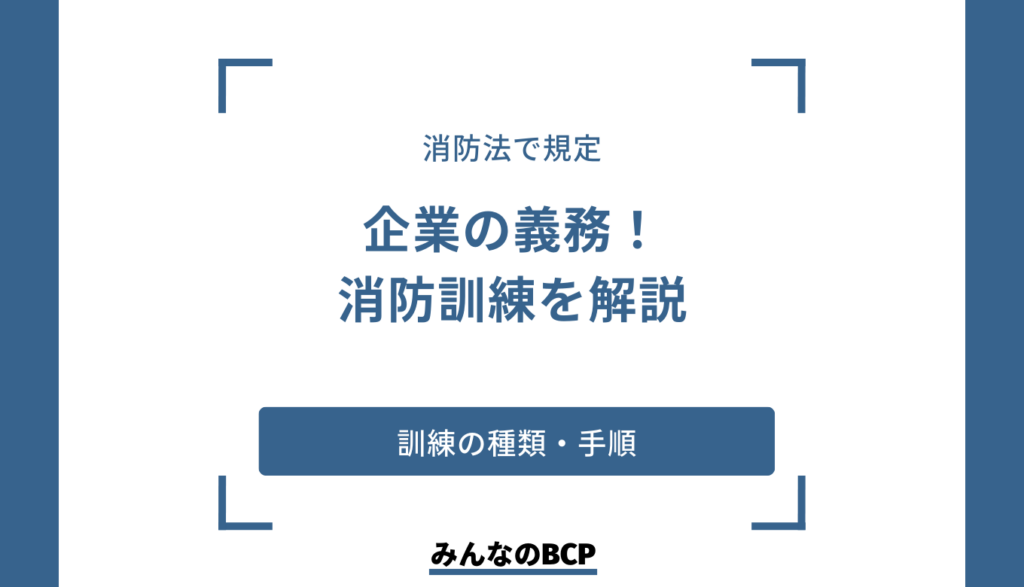
経営者として、従業員や企業の財産を守ることは大切な責務です。火災や地震などの災害は、企業の活動に大きな影響を与えるだけでなく、人的被害や事業の継続困難を招くことも恐れもあります。こうしたリスクへの備えが十分でないと緊急時の対応が遅れ、致命的な損害を受けることも考えられるでしょう。
そのような事態を避けるためにも、企業には消防訓練の義務が課せられています。定期的な消防訓練を通して従業員を守る準備をしていると、非常時も迅速な行動を起こせるでしょう。
この記事では、消防訓練の義務について解説します。訓練の具体的な種類や実施手順も紹介しているので、あわせて参考にしてください。

安否確認システムを選ぶなら、トヨクモの安否確認サービス2!
アプリ・メール・LINEで安否確認ができるほか、
ガラケーにも対応で世代を問わず使いやすいのが特徴です。
また初期費用0・リーズナブルな料金で導入できます。
下記のリンクから30日間無料お試し(自動課金一切ナシ、何度でもご利用可能)をお申し込みいただけます。
⇨安否確認サービス2を30日間無料でお試し
目次
企業における消防訓練の義務
企業には防火管理者を選任し、消防訓練を実施したり、消防に関する設備の点検をしたりする義務があります。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
(引用:消防法 | e-Gov 法令検索)
具体的には以下の4つです。
- 防災管理者の選任・届出
- 消防計画の作成・届出
- 自衛消防組織の設置・届出
- 防災管理点検の報告
防災管理者とは、地震などの被害を軽減するために消防計画を作成し、必要な業務を担う責任者のことです。防災管理点検資格者の中から適任者を選んで、防災管理に関する業務全般を請け負ってもらいます。
消防計画においては防火だけではなく、地震などを想定した計画を立てる必要があります。自衛消防組織とは火災や地震などの災害時の初動を円滑に進め、従業員の身の安全を確保するために設置される組織です。1つの建物に複数の事業所が入っている場合は、共同で設置することもできます。また、防災管理者による点検を実施したら、所轄の消防機関に報告する義務も課せられています。
なかでも消防訓練の実施回数は施設や企業の特徴などによって「特定防火対象物」と「非特定用途対象物」に分けられ、以下のような違いがある点に注意しましょう。
| 概要 | 対象施設 | 訓練の回数 | |
|---|---|---|---|
| 特定防火対象物 | 不特定多数の方が集まる場所(収容人数30人以上) | 百貨店・カラオケボックス・飲食店など | 年2回以上 |
| 非特定用途対象物 | 収容人数が多いものの、限られた方が利用する場所(収容人数50人以上) | 工場・倉庫・学校など | 年1回以上 |
(参考:防火管理制度等の概要)
特定防火対象物は災害が発生するタイミングによって被災する対象者が異なるため、年2回以上の消防訓練を実施して万が一に備えるように定められています。一方、非特定用途対象物は特定の方が利用する場所であり、消防訓練が実施しやすいことから年1回以上と義務付けられています。
消防訓練の必要性
企業における消防訓練の必要性は、以下のとおりです。
- 従業員の命を守りやすい
- 事業の早期復旧を目指せる
それぞれについて解説します。
従業員の命を守りやすい
消防訓練は、従業員の命を守る行動につながります。そもそも企業には従業員を守る義務が課せられており、労働契約法には以下のように記されています。
(労働者の安全への配慮)第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
(引用:労働契約法 | e-Gov 法令検索)
上記は災害時も例外ではなく、どのような非常事態でも有効です。いつ発生するかわからない火災から身を守るためにも、消防訓練は必須と言えるでしょう。
事業の早期復旧を目指せる
消防訓練を実施していると次の行動が読みやすくなり、事業の早期復旧を目指しやすくなります。たとえば火災によって避難しなければいけないとき、消防訓練を実施しているスムーズに避難できるため、身の安全を守りやすいです。その結果、迅速な初動が可能となり、事業の早期復旧に向けての行動も起こしやすくなるでしょう。
事業の早期復旧が可能となれば、企業や取引先の損害を最小限に抑えることもできます。万が一に備えておけば、混乱状況下であっても冷静な判断を下しやすくなるでしょう。
消防訓練の主な種類
消防訓練には、以下のような種類があります。
- 消火訓練
- 避難訓練
- 通報訓練
- 総合訓練
それぞれについて解説します。
消火訓練
消火訓練とは、消火器や屋内消火栓を使用した初期消火を行うための訓練です。消火器の使用方法や消火栓の操作方法などを実際に体験し、従業員が緊急時に適切な消火活動を行えるように訓練します。消火栓などは日常的に使用する機会はないため、訓練を通して使い方を学んでおきましょう。
避難訓練
火災や地震の際に、従業員や来客者が安全に避難できるようにするための訓練です。避難経路や避難場所の確認、避難時の注意点(エレベーターの使用禁止など)を全員で確認します。また、その際「避難経路に邪魔となる障害物はないか」などを併せてチェックすると、より有効な防災訓練を実施できます。
避難器具を使用する場合は、その使い方を覚えましょう。消防機関や消防設備士に立ち会ってもらい、万全な備えをしていると非常時も安心です。
通報訓練
通報訓練とは火災を発見した際に、速やかに消防署や警察に通報するための訓練です。実際の通報手順や通報時に伝えるべき内容(火災の発生場所・状況・被害状況など)を確認します。
火災の発見は従業員が直接発見する以外にも、自動火災報知設備での感知なども考えられます。状況に合わせた通報訓練を実施して、どのような場合でも対応できるように備えておきましょう。
総合訓練
総合訓練とは、上記3つの訓練を組み合わせたものです。一連の流れを訓練することで、火災発生時の混乱を最小限に抑えながら身の安全を守れるでしょう。
関連記事:防災訓練とは?企業における必要性や主な種類・準備事項について解説
消防訓練の実施手順
効果的な消防訓練を行うためには、計画的に手順を踏むことが重要です。具体的な手順は、以下のとおりです。
- 消防訓練計画の策定
- 事前準備と周知
- 消防訓練の実施
- 評価とフィードバック
それぞれについて解説します。
1.消防訓練計画の策定
まず、消防訓練の計画を策定しましょう。訓練の目的や実施日、参加者、訓練内容などを決定し、消防訓練計画書を作成します。とくに新しい従業員が参加する場合や建物のレイアウトが変更された場合には、その点を考慮した訓練計画を立てることが重要です。あらかじめ目的を明確にしていれば、見直しの際にも役立てられます。
火災時は応急救護や情報収集など、やるべき事柄が多くあります。そのため、各従業員に役割を決めておき、適した行動を取れるかどうかもチェックすべきポイントです。さまざまな事態を想定し、代行者を複数人選定すると柔軟な対応が可能となるでしょう。
2.事前準備と通知
消防訓練を実施する前に、従業員や関係者に対して実施日時と内容を通知し、訓練の目的を周知しましょう。また、消化器や放送設備といった必要な機材の準備も行います。
特定用途防火対象物は消防訓練を行う際は、事前に地域を管轄する消防署に通報しなければいけません。また地域住民が実際の火災と勘違いしないように、あらかじめ連絡しておくといいでしょう。
3.消防訓練の実施
消防訓練計画に基づき、訓練を実施します。実際の火災を想定し、従業員が役割分担を理解しながら迅速かつ冷静な対応を行えるように進行します。
4.評価とフィードバック
消防訓練終了後、従業員からフィードバックを収集し、訓練の効果や改善点を評価しましょう。また、次回の訓練に向けて改善すべき点を整理し、報告書を作成・消防署長に提出します。
消防訓練を実施する際の注意点
消防訓練を実施する際の注意点は、以下のとおりです。
- 消防署と連携する
- すべてのシナリオを作成しない
それぞれについて解説します。
消防署と連携する
特定用途防火対象物は消防訓練を行う際は、事前に地域を管轄する消防署に通報する義務があります。非特定用途防火対象物であっても事前に最寄りの消防署と連携し、訓練の計画を伝えることが望ましいです。
消防署の職員が立ち会えれば訓練内容の指導や評価を受けることができ、より効果的な備えができるからです。必要に応じて訓練教材用DVDや訓練用消化器などを貸し出してもらえるため、訓練の実施前に相談するのもいいでしょう。
また、訓練実施後は、特定用途防火対象物・非特定用途防火対象物問わず、訓練の内容を防火管理維持台帳に記録して3年間保存する義務があります。
すべてのシナリオを作成しない
消防訓練の際は、すべてのシナリオを作成しないことも重要です。計画段階ですべてのシナリオを決めてしまうと、臨機応変に対応するのが難しくなるからです。
シナリオに沿った訓練の実施を避けるためにも毎年シナリオを変更したり、一部を非公表にしたりするのも有効でしょう。どのような状況であっても身の安全を守れるように、役立つ消防訓練を実施してください。
消防訓練にはトヨクモの『安否確認サービス2』の活用がおすすめ!
火災が発生した際、いち早く従業員の安否確認を行わなければいけません。すべての従業員の安全を確認することも、企業における義務の一つだからです。また、早い段階で従業員の安否確認をできれば、必要に応じた支援も行いやすくなるでしょう。
そのような場合に活用してほしいのが、トヨクモの『安否確認サービス2』です。気象庁の情報と連動して従業員の安否確認を自動で行えるシステムです。たとえば火災の原因が地震による場合、地震の情報と連動して安否確認通知が自動で送付されます。通知は専用アプリなどの複数の手段で従業員に送られるため、届かなかったといったトラブルも未然に防げます。また、従業員から得られた回答結果も自動で集計・分析してくれることから、安否確認にかかる手間を大幅に削減できるでしょう。
安否確認サービス2は、防災の日である9月1日に全国一斉訓練を実施しています。一斉訓練は実施日と時間帯のみを公開しており、実際の災害時のような危機感を持って訓練を行えます。訓練終了後は各組織に結果レポートを送付しているため、自社の防災意識を貯めるきっかけにも役立てられるでしょう。
消防訓練の義務を果たそう!
企業は消防訓練の義務が課せられており、年に1回以上もしくは2回以上実施しなければいけません。消防訓練を実施していれば、従業員の命を守る行動を起こしやすくなり、事業の早期復旧も目指せるでしょう。今回紹介した消防訓練の種類や手順を参考に、有益な訓練を実施してください。
消防訓練には、トヨクモの『安否確認サービス2』の活用がおすすめです。従業員の安否確認や状況把握を迅速に行えるため、安否確認にかかる手間を大幅に削減できます。また、安否確認サービス2は初期費用不要で、30日間のトライアル期間を設けているのも特徴です。無料体験を活用すれば、自社に合ったシステムかどうかを見極めてから導入できます。災害時への備えとして、ぜひ安否確認サービス2の無料体験を試してください。