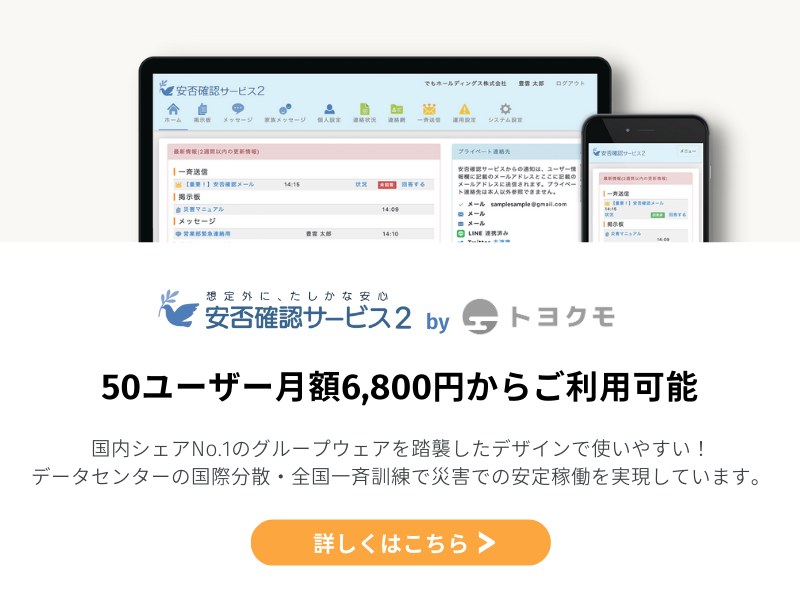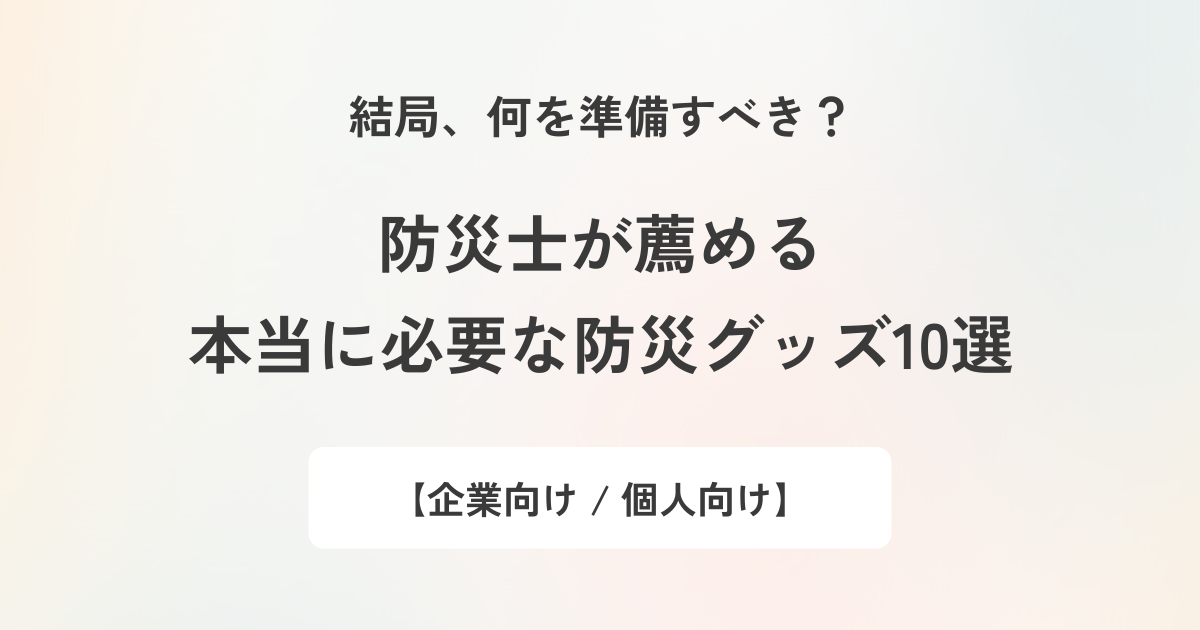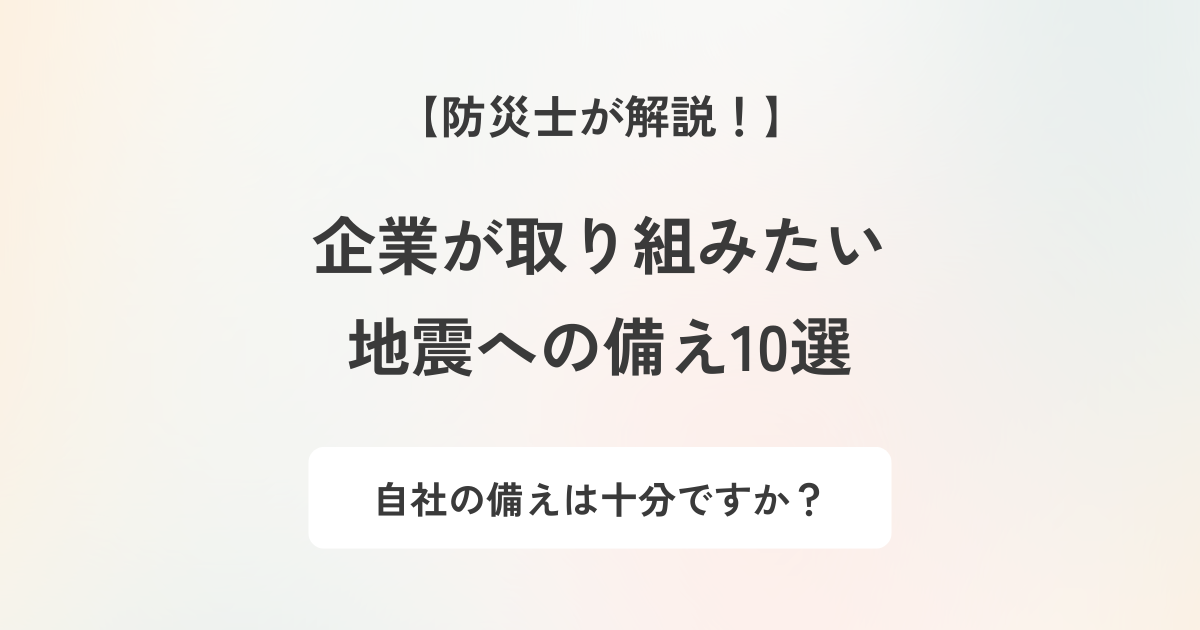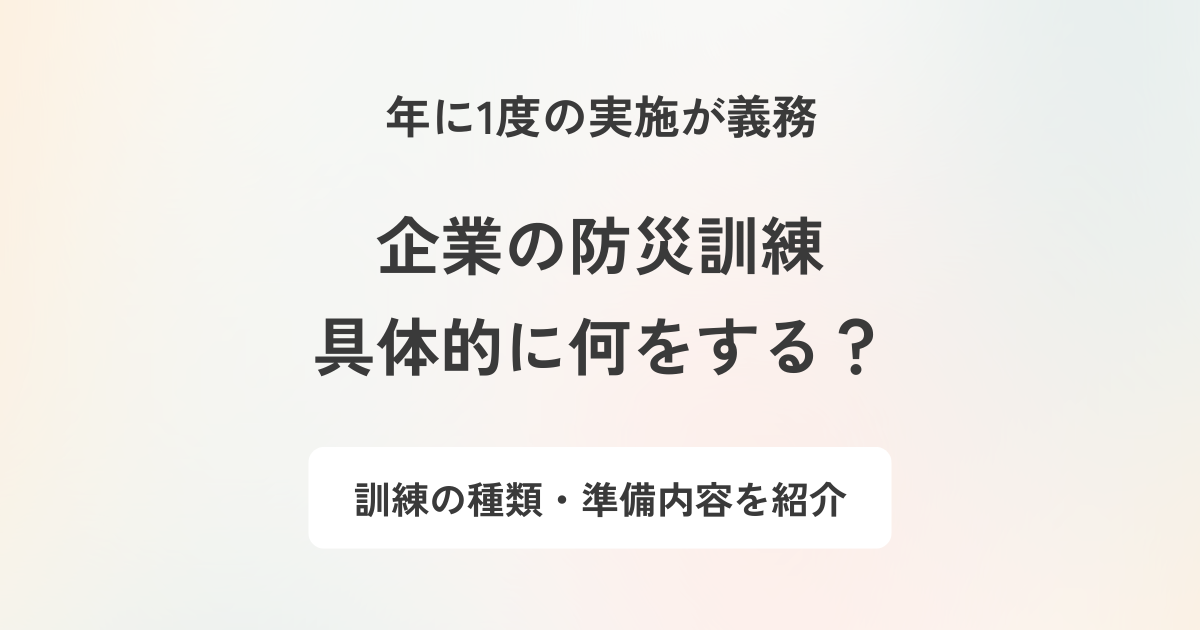避難確保計画とは?基本的な構成やチェックリスト・BCPとの違いを紹介

遠藤 香大(えんどう こうだい)
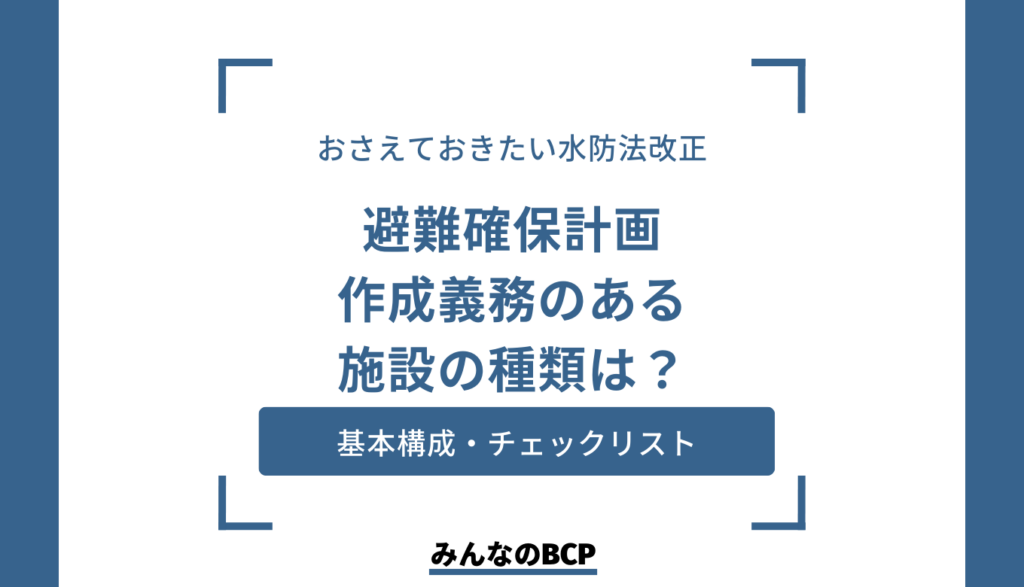
近年、豪雨や土砂災害などの自然災害が頻発しています。2024年9月に発生した能登豪雨でも、死者と行方不明者が出たことにより、防災対策により一層の注目が集まっているのです。
こうした災害から施設利用者の安全を確保するために、施設には避難確保計画の策定が義務付けられています。
そこで、この記事では、避難確保計画の概要や作成方法、作成状況について説明します。BCPとの違いについても紹介するため、避難確保計画について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

BCPを策定できていないなら、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用をご検討ください!
早ければ1ヵ月でBCP策定ができるため「仕事が忙しくて時間がない」や「策定方法がわからない」といった危機管理担当者にもおすすめです。下記のページから資料をダウンロードして、ぜひご検討ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
目次
避難確保計画とは
避難確保計画とは、施設利用者の安全を確保するために作成する計画のことです。水害や土砂災害が発生する恐れがある際、利用者が円滑かつ迅速に避難できるように、以下の事項を定めます。
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の設備
- 防災教育および訓練の実施
- 自衛水防組織の業務(自衛水防組織を配置する場合)
- 利用者が円滑かつ迅速に避難するために必要な措置
避難確保計画が実効性のあるものとするために、基本的に施設管理者が作成します。作成した避難確保計画は、施設所在地の市町村長に報告しなければなりません。
対象施設について
すべての施設が避難確保計画の作成・提出を求められているわけではありません。避難確保計画の作成対象となる施設は、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設です。具体的には、以下のような施設が対象です。
- 老人福祉施設
- 有料老人ホーム
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 病院
- 診療所 など
対象となる施設は、市町村地域防災計画に名称と所在地が記載されています。作成対象かわからない場合には、市町村地域防災計画を確認しましょう。
作成の義務について
2017年に水防法が改正されたことにより、施設管理者に避難確保計画の作成が義務付けられました。避難計画を作成しない場合、設定された期限までに作成するように指示されます。それでも指示に従わなかった場合には、作成しなかった旨が公表されます。
避難確保計画の基本的な構成
避難確保計画で定める項目は、以下のとおりです。
- 基本的な事項
- 防災体制に関する事項
- 避難誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項
国土交通省の「要配慮利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」では、具体的例として、以下の構成が紹介されています。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 基本的な事項 | 計画の目的施設の概要施設が有する災害リスク |
| 防災体制に関する事項 | 防災体制の種類とその確立基準事前休業の有無と実施基準防災体制確立時の組織構成と役割分担防災体制確立時の要員配置情報収集と情報伝達 |
| 避難誘導に関する事項 | 避難先の考え方避難先避難経路避難方法避難に要する時間と避難開始基準緊急安全確保の方法 |
| 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 | 距離に必要な設備とその確保距離に必要な装備品や備蓄品とその確保 |
| 防災教育及び訓練の実施に関する事項 | 避難確保計画の周知防災教育の実施避難訓練の実施避難訓練結果の振り返りと避難確保計画の見直し市町村への避難訓練結果の報告 |
| 自衛水防組織の業務に関する事項(任意) | 水防管理者その他関係者との連絡調整、自衛水防組織が行う業務に係る活動要領自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練その他必要な事項 |
(参考:国土交通省|要配慮利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き)
避難確保計画の作成方法
各市町村の公式サイトで、避難確保計画のひな形と手続きが交付されています。施設所在地の市町村の公式サイトを確認し、ひな形をダウンロードして使用しましょう。
また、国土交通省の公式サイトでも、ひな型をダウンロードすることが可能です。社会福祉施設、学校、医療施設に分けて掲載されているため、該当する施設のひな型を選んで活用しましょう。
ひな型を見てもどのように作成するのかわからない場合には、記載例を確認することをおすすめします。国土交通省の公式サイトに記載例があるため、参考にしながら進めてみるとよいでしょう。
避難確保計画の作成後に確認するチェックリスト
作成した避難確保計画を市町村に提出する際、あわせてチェックリストも提出する必要があります。チェックリストは国土交通省の公式サイトに掲載されており、作成時に確認することにより、実効性の高い避難確保計画を作成できます。
国土交通省の公式サイトでは、社会福祉施設と医療施設の2種類のチェックリストが用意されているため、該当する施設のチェックリストを活用しましょう。たとえば、「社会福祉施設の避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト」では、以下の項目が確認項目として挙げられています。
- 気象情報や河川情報、土砂災害に関する情報、避難情報の収集・伝達方法等を適切に定めているか
- 避難を開始するタイミングを適切に定めているか
- 利用者の避難支援のための体制確立は適切であるか
避難訓練の実施も対象施設の義務
避難確保計画を作成しても、実際の災害時に行動に移せなければ意味がありません。災害時に施設利用者が円滑かつ迅速に避難できるように、施設には避難訓練の実施も義務付けられています。
避難訓練を実施するタイミングは定められていませんが、原則として年に1回以上の頻度で実施しなければなりません。さらに、避難訓練の結果は、実施後1ヶ月以内を目安として、市町村に報告する必要があります。
避難訓練を実施して課題が明らかになったら、課題の解決に努めるとともに、避難確保計画の内容も見直しましょう。また、避難確保計画や避難訓練について、自治体から助言をもらえるため、助言の内容を反映させることも重要です。
関連記事:防災訓練とは?企業における必要性や主な種類・準備事項について解説
避難確保計画の作成状況
2024年3月31日現在、避難確保計画の提出が求められている施設は、全国で124,998施設です。そのうち、約88%にあたる110,076施設がすでに計画を作成済みとなっています。
多くの施設で避難確保計画が作成されていることから、災害発生に向けて万全に備えているように思えるかもしれません。しかし、避難訓練を実施している施設は全国で48,569施設であり、避難確保計画の提出が求められている施設全体の約39%程度にとどまっています。
避難確保計画を作成しているからといって、施設の防災対策が十分とは言えません。各施設は災害時に備えて常時から防災意識を高めておく必要があります。
(参考:国土交通省|都道府県別の作成状況)
避難確保計画とBCPの違い
BCPは、Business Continuity Planの頭文字を取ったもので、自然災害などの緊急事態が発生した際、企業が事業を継続するための行動について記載した計画のことです。日本語では、事業継続計画と訳されます。
避難確保計画とBCPは、いずれも災害に備えたものである点では共通しています。しかし、避難確保計画は主に施設利用者の安全確保に重点を置いているのに対し、BCPは企業の事業継続や復旧を主眼としている点が異なります。
大規模な災害が発生した際には、従業員の安全確保に加えて、重要業務の継続や早期復旧を測ることが企業に求められます。災害に強い企業になるためにも、BCPの策定は重要で欠かせません。
関連記事:BCP(事業継続計画)とは?専門家がわかりやすく解説
費用を抑えて災害に備えたい場合には『BCP策定支援サービス(ライト版)』がおすすめ
BCP策定には多くの手間と時間がかかります。BCPを作成するノウハウがない状態でやみくもに作ろうとすると、さらに時間がかかってしまい、担当者の負担が大きくなるでしょう。効率的にBCPを策定するには、専門ノウハウを持った外部に依頼することが有効です。
しかし、一般的にBCP策定を外部に依頼すると、数十万〜数百万円程度のコストが発生します。できるだけ費用を抑えてBCPを策定したい場合は、トヨクモの『BCP策定支援サービス(ライト版)』がおすすめです。
BCP策定支援サービス(ライト版)は、専門家がBCPの策定を支援するサービスです。安価でBCPを策定できるうえに、最短1ヶ月程度と策定期間が短いという魅力もあります。興味のある方は、ぜひ以下のリンクから資料をダウンロードしてください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
避難確保計画を策定して避難訓練を実施しよう
避難確保計画は、水害や土砂災害が発生した際、施設利用者の安全を確保するための重要な計画です。対象施設の管理者は、避難確保計画を作成し、市町村長に報告することが義務付けられています。また、作成した計画に基づいて定期的に避難訓練を実施し、実効性を高めていくことも求められています。
災害はいつ発生するかわかりません。施設利用者の安全を守るためにも、避難確保計画の策定と避難訓練の実施に取り組んでいきましょう。あわせて、企業は事業継続のためにBCPの策定も検討することをおすすめします。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。