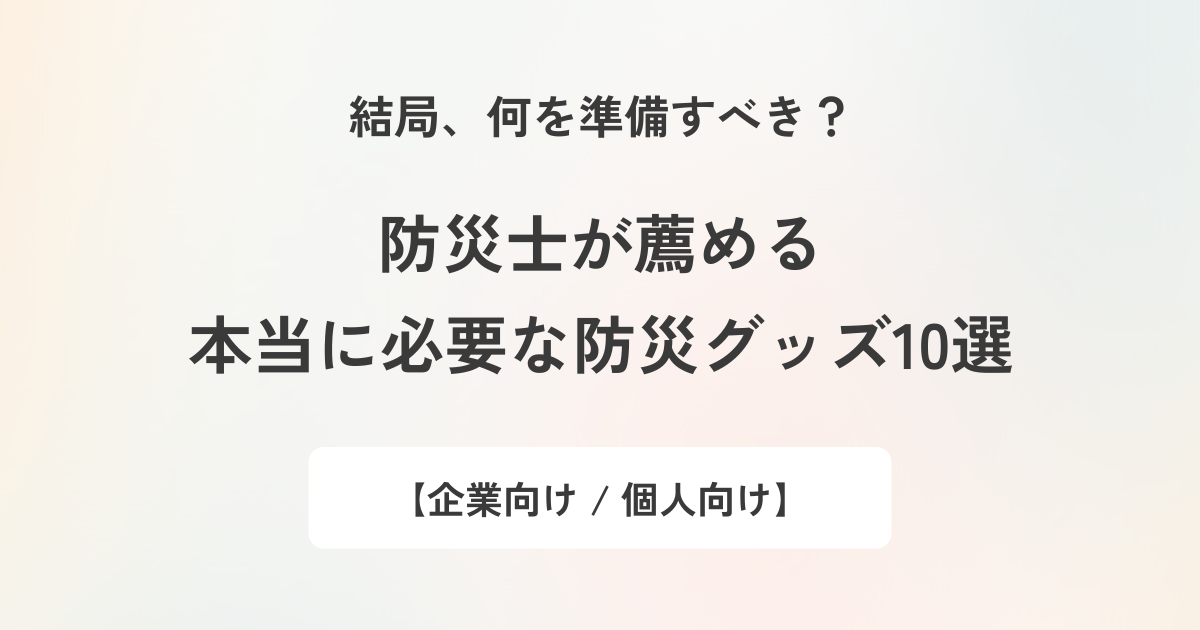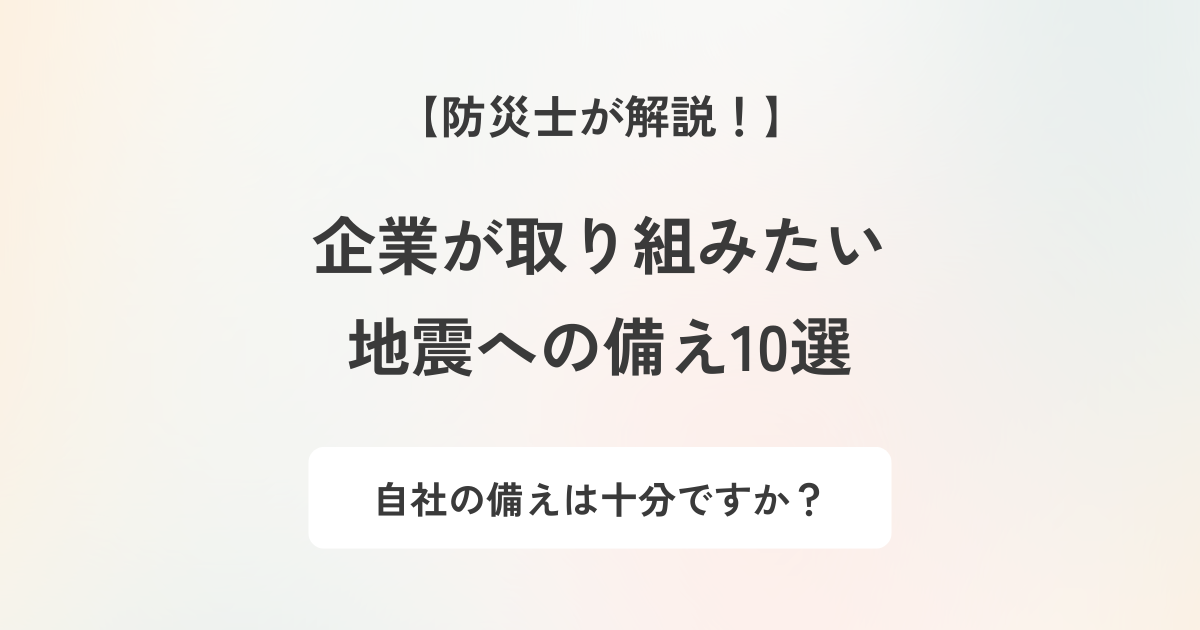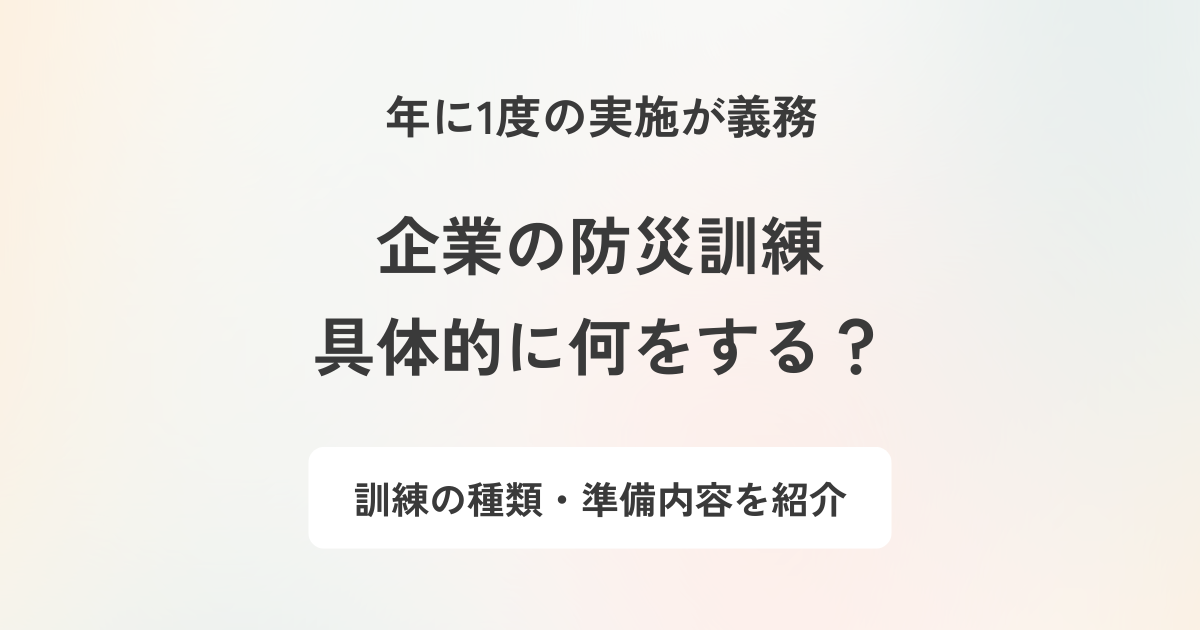忙しくても取れる防災資格3選|企業の防災力を高めよう

トヨクモ防災タイムズ編集部
日本は地震や台風、大雨など、さまざまな自然災害に見舞われる国です。とくに近年は異常気象が増え、防災の重要性はますます高まっています。
しかし、日々の仕事や生活に追われており「防災対策をしたいけれど、何をすればいいのか分からない」または「時間がなくて、防災について学ぶ余裕がない」と感じる方も多いでしょう。
そこで今回は、忙しくても取れる防災資格3選を紹介します。これらの資格を取得し、防災の知識を深め、職場や家庭での安全対策を強化しましょう。

目次
忙しくても防災の知識を身につけるべき理由
日本は地震をはじめ、さまざまな災害が頻発するため、いつどこで災害に遭遇するか分かりません。しかし、毎日の業務に手一杯で、防災対策が後回しになっている企業も多いでしょう。
しかし、防災の知識を身につけておくと自分や周りの従業員をはじめ、大切な人の命を守ることにつながります。災害はいつ起こるか分からないため、事前に備えておけば、被害を最小限に抑えることが可能です。
基本的な防災知識を身につけておけば、状況に応じた判断がしやすくなります。たとえば、地震の際に安全な場所へ避難する方法や、火災発生時に避難経路を確保するポイントなどを事前に知っておけば、パニックを防ぎながら落ち着いた行動が取れます。災害時は混乱しやすく、適切な行動が取れない可能性があるので、平時から高い防災意識を持ち、事前の準備をしておくことが重要です。
とくに、企業では防災資格を持っている人材の配置が求められます。資格の取得によって組織の防災対策を強化し、安全管理のリーダーとして活躍することも可能です。 さらに、防災知識があると企業の事業継続計画(BCP)の策定にも貢献でき、災害発生時の混乱を抑えながら業務を継続するための体制を整えられます。
忙しくても取れる防災資格3選
忙しくても防災の知識を身につけることは、災害時に事業存続や従業員の安全確保ために重要です。ここでは、比較的短期で取得できる以下の防災資格を紹介します。
- 防災士
- 防災管理者
- BCPアドバイザー
1.防災士
防災士は、防災知識を体系的に学び、地域や職場で防災活動を推進できる資格です。「自助」「共助」「協働」を原則として、十分な意識と一定の知識・技能を修得します。
企業や自治体では防災担当者としてのスキルが求められることが多く、この資格を持っていることで専門的な知識を証明できます。
防災士の資格を取得するメリットは、主に以下のとおりです。
- 災害時の適切な対応力が身につく
- 地域や職場で防災リーダーとして活躍できる
- 防災対策の提案ができ、組織の安全性向上に貢献できる
防災士の資格取得を通じて、災害発生時の対応方法を学べます。緊急時に冷静な判断ができるため、自分や周囲の人の命を守る行動が取れるようになるでしょう。また、企業の防災活動でリーダーシップを発揮できます。防災意識の向上に貢献し、組織の安全性を強化する役割を担えます。
さらに、自然災害のリスクを見極め、それに応じた防災対策を提案できるようになるのも魅力です。企業にとって、事前の備えを強化するための重要な知識を提供できるでしょう。
なお、防災士資格は講習受講後に認定試験を受けることで取得可能です。比較的短期間で学習できるため、忙しい方でも取り組みやすいでしょう。
(参考:防災士とは)
2.防災管理者
防災管理者は、企業や施設の防災計画や避難対策を適切に実施するための資格です。一定規模以上の建物では防災管理者の配置が義務付けられているため、企業の防災担当者が取得すると組織の安全性を確保できます。
防災管理者の資格を取得するメリットは、主に以下のとおりです。
- 企業の防災体制を強化できる
- 避難計画の策定や防災訓練の実施が可能になる
- 防災設備の管理方法を学べる
防災管理者の資格を取得すると、災害発生時に従業員の安全を確保するための体制構築が可能になります。とくに、大規模なオフィスや施設では、事前の避難計画が重要であり、防災管理者が適切な指揮を取ることで被害を最小限に抑えられるでしょう。
また、防災管理者がいると定期的な防災訓練を実施できるようになり、適切な避難計画を作成すれば企業全体の防災力を向上させることができます。火災報知器や避難誘導設備の適切な管理方法を学べ、企業の安全環境の向上にもつながります。
防災管理者の資格は、研修受講を経て取得できるため、比較的短期間で資格を得られるのも魅力です。とくに、企業の総務担当者や施設管理者におすすめの資格です。
(参考:防災管理者とは)
3.BCPアドバイザー
BCPアドバイザーは、企業の事業継続計画(BCP)を策定・運用する専門知識を持つ資格です。災害時の混乱を最小限に抑え、業務を継続できる体制を整えるために役立ちます。
BCPアドバイザーを取得するメリットは、主に以下のとおりです。
- 企業の事業継続計画を策定・改善できる
- 災害時に迅速に対応できる知識が身につく
- 組織の防災力向上に貢献できる
BCPアドバイザーの資格を取得すると、BCPの考え方を学べて、災害時でも業務を止めないための計画を策定できます。これにより、企業の経済的損失を減らし、取引先や顧客への影響を最小限に抑えられます。また、予期せぬ災害が発生した際、どのように対応すべきかを学べるのもメリットです。事前の備えを通じて、従業員や関係者の安全を確保しながら業務を継続できるようになります。
さらに、BCPアドバイザーの知識を習得すると、企業のリスク管理能力が向上します。防災対策を経営戦略の一環として組み込み、長期的な企業価値を高めることができるでしょう。
なお、BCPアドバイザーは、Web試験に合格すると取得できます。企業の経営者や管理職が取得すると、組織全体の防災・危機管理体制を強化することが可能です。
(参考:RMCA BCPアドバイザー|日本リスクマネジャー&コンサルタント協会)
資格取得後に活用すべき「安否確認システム」
防災資格を取得したとしても、災害時に迅速な情報共有ができなければ、その知識を十分に活かせません。とくに企業では、従業員の安否確認が事業継続に大きな影響をもたらすでしょう。
そこで導入すべきなのが、安否確認システムです。安否確認システムを活用すると、災害時に従業員や関係者の安全状況を把握し、必要な対応を迅速に行えます。安否確認システムを導入すると、以下のようなメリットを得られます。
- 災害発生時に迅速な安否確認ができる
- スムーズに情報共有できる
- BCP対策としても活かせる
安否確認システムを導入すると、大規模な災害が発生した場合であっても、従業員や関係者の安全を即座に確認できるのが魅力です。安否確認のための個別連絡に時間をかけることなく、一括で情報を集約できるため、企業の危機管理能力を向上させることも可能です。
災害発生時、システムが事前に設定した連絡手段を使い、従業員へ安否確認の通知を自動で送信します。メールやアプリ通知など、複数の連絡方法があるシステムであれば、より迅速かつ確実な対応が可能です。
なお、BCPアドバイザーの視点から見ても、安否確認システムの導入は事業継続計画(BCP)の強化につながります。災害時に従業員や関係者の安全を把握しながら、業務継続の判断を迅速に行えるため、企業のリスク管理に大きく貢献するでしょう。
企業の防災対策にはトヨクモ『安否確認サービス2』の活用がおすすめ
安否確認システムのなかでもとくにおすすめなのが、トヨクモが提供する『安否確認サービス2』です。気象庁の情報と連動して自動で安否確認通知を送信できるため、状況を把握しやすいです。また、安否確認サービス2は、毎年9月1日に全国一斉訓練を実施しており、実際の災害時に近い負荷をシステムに急激にかけることで、安定稼働できるかどうかを確認しています。そのため、大規模な自然災害が発生したときであっても、安心して活用できるでしょう。
さらに、掲示板機能やメッセージ機能がついており、今後についての議論や情報共有にも役立てられます。BCP対策を強化したい企業にもおすすめのシステムです。
まとめ:忙しくても企業の防災力向上は重要
今回紹介した防災資格は、忙しい方でも取得しやすく、企業の防災力を高めたいときにも役立ちます。しかし、資格取得後の知識を実践に活かすためには、適切な防災ツールの導入が欠かせません。
トヨクモの『安否確認サービス2』は、災害時の安全確保において重要な役割を果たします。なお、初期費用不要で30日間のトライアル期間を設けているため、導入へのハードルも低いでしょう。企業の防災力向上を目指す方は、ぜひ無料体験からお試しください。