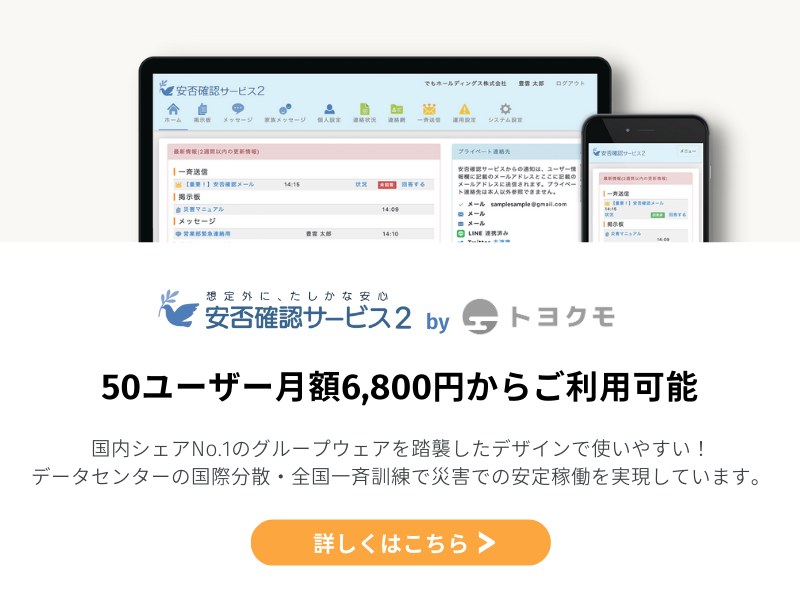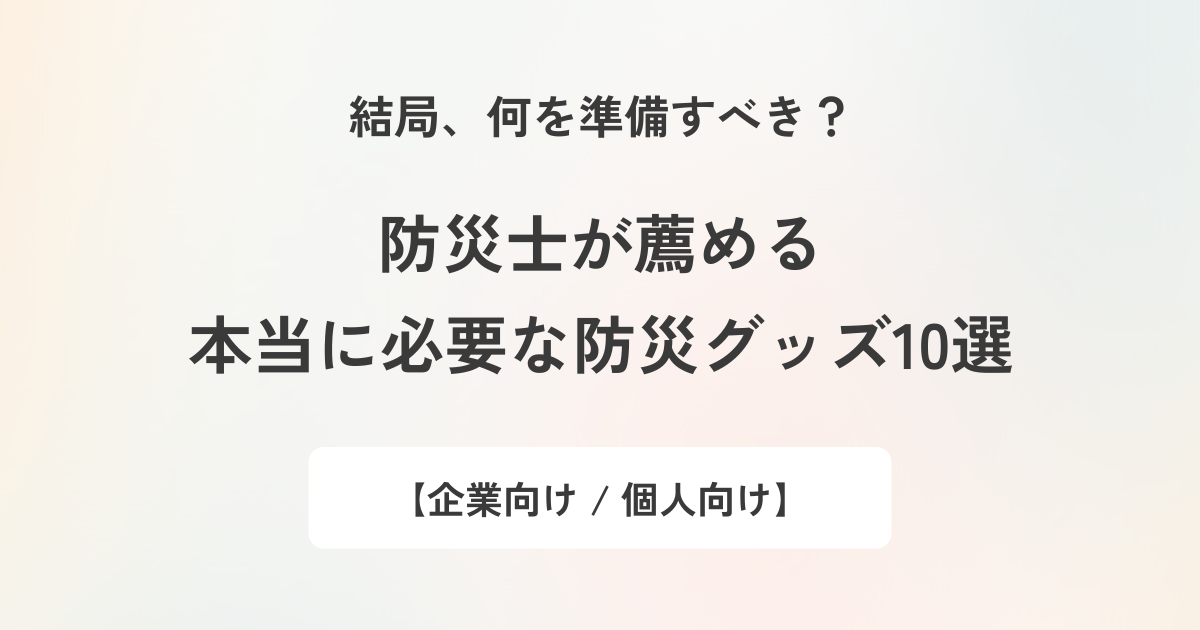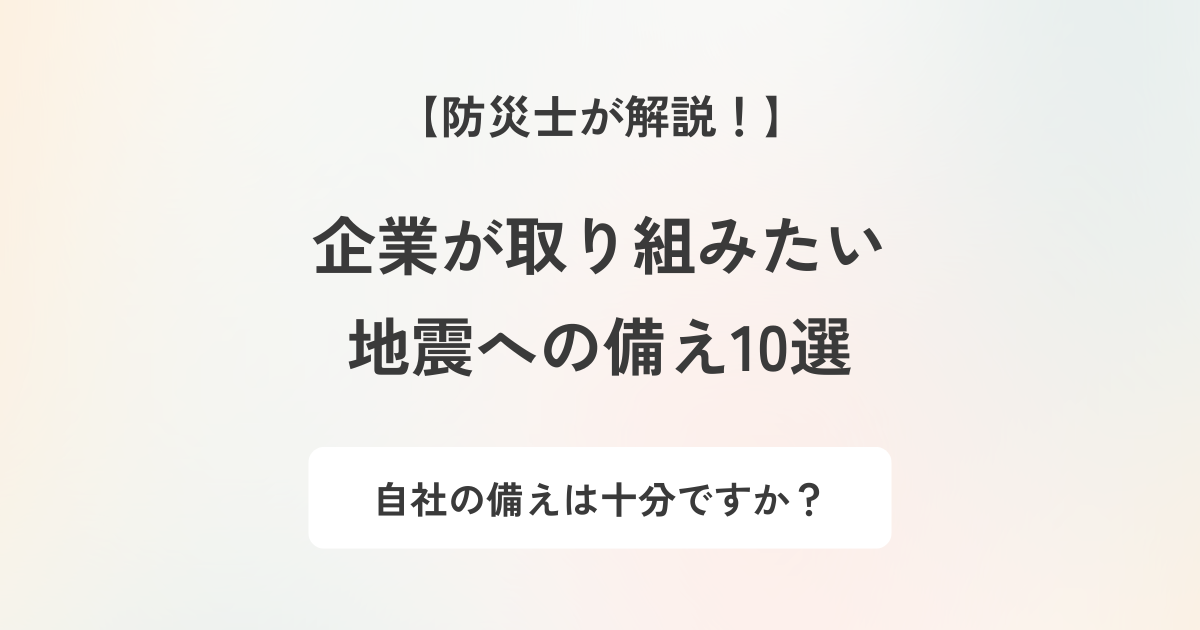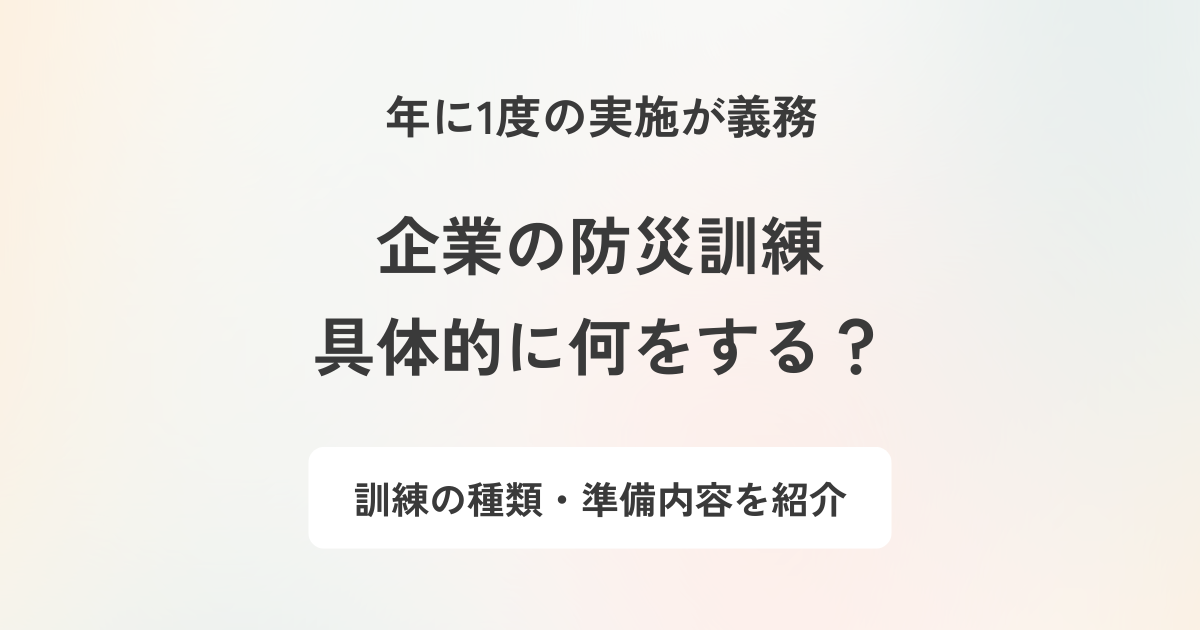津波避難タワーとは?想定される問題点や企業BCPへの組み込み方法を解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)
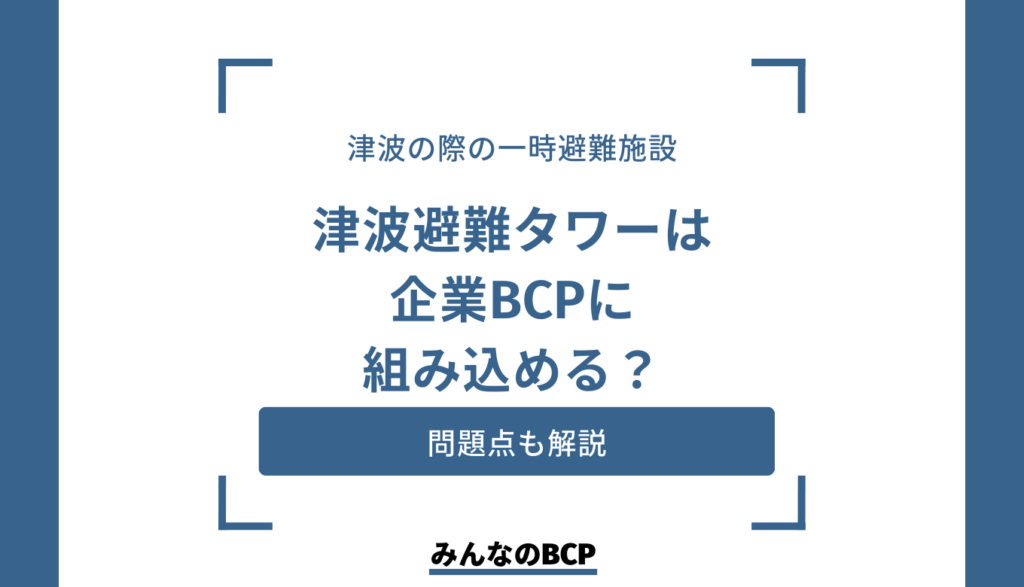
津波避難タワーとは、津波発生時に高台への避難が困難な地域に設置された一時避難のための施設です。近くに津波避難タワーがあれば、地震発生後に身の安全を確保しやすく、津波による被害を軽減できる可能性があります。
とはいえ、津波避難タワーには想定される問題点もあり、それらを事前に把握しておくことが重要です。
そこでこの記事では、津波避難タワーの概要や想定される問題点を紹介します。企業BCPへ津波避難タワーの活用を組み込む方法も紹介しているので、あわせて参考にしてください。

目次
津波避難タワーとは
津波避難タワーとは、津波被害が想定される地域の方が緊急時に一時避難できる施設です。津波による浸水が想定されるすべての地域に設置されているものではなく、以下のような基準があります。
- 地震発生から津波到着まで時間的猶予がある
- 避難が困難な地理的条件である
- 近くの高台へすぐに避難できない
津波避難タワーは、やむを得ず避難する場合に適しています。長時間の滞在を前提としているものではないため、オフィスや従業員の自宅が被災した場合の避難先は、津波避難タワー以外にも確認しておく必要があるでしょう。
とはいえ、緊急時にすぐ津波避難タワーへ避難すれば、津波から命を守れる可能性は高まります。津波の恐れがある地震が発生した場合は早急に避難し、身を守れる体制を構築しておくべきです。
(参考:津波防災地域づくり に関する法律)
(参考:ハザードマップポータルサイト)
津波避難ビルを活用するのも一つの有効策
津波避難タワーと同じく一時的な避難場所として、津波避難ビルがあります。津波避難ビルは津波避難タワー同様に高台へ逃げられない場合に活用でき、身の安全を守るものです。津波避難ビルは既存ビルを活用できるものの、耐震基準といった一定の基準を満たさなければいけません。条件に合う既存ビルがない場合は、津波避難ビルとして活用できる建物を新たに建設もしくは建て替えをする必要があります。
津波避難タワー・避難ビルで想定される問題点
津波避難タワー及び避難ビルで想定される問題点は、主に以下の4つです。
- 建設コストがかかる
- 活用しにくい
- 二度逃げしにくい
- 安全な避難経路の確保が必要
それぞれについて解説します。
建設コストがかかる
津波避難タワーは自治体が設置するものですが、建設には莫大な費用がかかります。設置費用やメンテナンス費用などを含めると数百万円以上の費用がかかるため、どの地域でも設置が可能というわけではありません。津波避難ビルは一般企業が設置することもありますが、新規でビルを建てるとなると大きな負担となります。
また、従業員のみならず、地域住民の避難場所として機能させるために地域との連帯も欠かせないでしょう。
(参考:津波避難タワー)
活用しにくい
津波避難タワーは活用しにくいのも問題点の一つです。津波避難タワーは高台へ逃げられないときに活用できるものの、最上階まで上がる手段が階段しかなければ、怪我人や体の不自由な方、高齢の方などは避難できません。実際、津波避難タワーが建設された宮城県石巻市では、地震発生後も活用された形跡を確認できなかった事案があります。
津波避難タワーが身近にあっても、実際に津波が発生したときに活用されなければ意味がありません。つまり、津波避難タワーの活用を検討するときは「津波発生時、本当に活用できる場所か」を見極める必要があります。
なお、津波避難タワーの管理は、自治体が行っていることが多いです。しかし、津波避難タワーは維持管理が難しく、この点も活用されにくい要因につながっているでしょう。
(参考:「津波避難タワー」費用負担が課題…「高齢者にはきつい」建設しても使われないケースも)
二度逃げしにくい
津波避難タワーは、二度逃げしにくい点も問題点です。二度逃げとは、津波が来た場合にひとまず避難した場所からさらに高い場所に逃げることを指します。
高台へ避難した場合、想定よりも高い津波がきてもさらに安全な場所へ移動しやすいでしょう。しかし、津波避難タワーの場合は他に逃げ場所がなく、命を守る行動ができません。したがって、津波避難タワーを活用する際は、個々の命を守るための最適な判断能力が必須です。
安全な避難経路の確保が必要
津波避難タワーを活用する際は、迅速に行動できる避難経路を確保する必要があります。たとえば、津波避難タワーまでの距離が離れている場合、避難途中で被災する可能性は十分にあります。
津波発生時は時間との勝負であり、どのようなときも迅速に逃げられる体制を整えていないといけません。津波避難タワーまでの安全な避難経路を確認しておき、スムーズに逃げられる体制を構築することが人命を守る上で極めて重要です。
津波避難タワーを企業BCPに組み込む方法
企業における津波の備えとして津波避難タワーを活用する場合は、あらかじめBCPに盛り込んでおくべきです。BCPとは事業継続計画のことで、緊急時に事業資産の損害を最小限に抑えながら事業の早期復旧を目指すことを目的としています。
関連記事:BCP(事業継続計画)とは?専門家がわかりやすく解説
津波をはじめとする緊急時は平常時と異なり、何が起こるか想定できません。混乱した状況の中では冷静な判断ができずに、損害が大きくなることも想定されます。あらかじめBCPを策定しておけば、今すべきことが明確になり次の一手を出しやすくなります。その結果、従業員を守りながら、企業への損害を最小限に抑えられるでしょう。
なお、津波避難タワーの活用を検討している場合は、以下の手順に沿って準備を進めてください。
- 津波発生時の避難計画を策定する
- 定期的な避難訓練を行う
- BCPの改善や見直しを行う
それぞれについて解説します。
1.津波発生時の避難計画を策定する
まず、津波発生時の避難計画を策定しましょう。具体的には、以下の点を考慮しながらBCPを策定します。
- 津波発生時に従業員が安全に避難できる経路はどれか
- 避難開始のタイミングはどのように見極めるか
- 避難時の役割分担をどうするか
BCPでは起こり得る津波の被害予測にもとづいて、適切な行動を示していきます。実際に津波が発生したことを想定しながら、必要な事柄を決めましょう。
2.定期的な避難訓練を行う
BCPを策定したら、定期的に避難訓練を実施しましょう。BCPで策定した避難経路を実際に辿り、津波避難タワーまで逃げてみることも効果的です。そうすることにより、BCPを策定する際に気付けなかった課題や問題点が見えてくるでしょう。
また、定期的に避難訓練を行うことによって緊急時の混乱を防ぎやすくなり、津波発生時にも迅速な行動をしやすくなります。従業員の身の安全を守るためにも、日頃から備えておきましょう。
関連記事:【専門家が解説】BCP訓練とは?種類や事例、効果的に実施するポイントを紹介
3.BCPの改善や見直しを行う
BCPは策定したら終わりにするのではなく、定期的に見直しを行いましょう。避難訓練によって見つかった課題や問題を反映させたり、状況に応じて改善したりすることで、よりよいBCPを策定できるからです。緊急時に従業員の人命を守りつつ、企業の損失を最小限抑えるためにも欠かせない業務と言えるでしょう。
なお、BCPの策定がまだの方には、トヨクモが提供している『BCP策定支援サービス(ライト版)』の活用がおすすめです。BCPの策定には多くの手間と費用が必要となり、策定を後回しにしている企業も珍しくありません。しかし、備えがない場合は緊急時に事業の継続が困難となり会社の経営が傾く恐れがあります。
BCP策定支援サービス(ライト版)であれば最短1ヵ月で策定できます。また、BCPコンサルティングは数十〜数百万円ほどするのが一般的ですが、BCP策定支援サービス(ライト版)は1ヵ月15万円(税抜)で利用できるのも魅力です。費用や手間を抑えつつBCPを策定したい方は、ぜひご活用ください。
津波発生時の安否確認にはトヨクモ『安否確認サービス2』がおすすめ
津波への備えとして避難場所や避難経路の確保をしておくことはもちろん、従業員の安否を把握する手段を確保しておくことも重要です。
BCPの一環として安否確認に活用してほしいのが、トヨクモが提供する『安否確認サービス2』です。気象庁の情報と連動して従業員の安否確認を自動で行えるため、手間を省きながら被害状況を把握できます。地震および津波による従業員やその家族の被害状況を確認できれば、出勤できる従業員の確保も早急に行え、すみやかな事業の復旧につながるでしょう。
また、安否確認サービス2は掲示板機能を利用して一部の従業員と今後の議論をしたり、情報を共有したりすることも可能です。さらに、毎年9月1日には全国一斉訓練を行っており、津波発生時を想定した避難訓練にも役立てられます。
安否確認サービス2の導入によって平時から社内の防災意識の底上げし、従業員の身の安全を守りましょう。
津波避難タワーを活用して従業員の命を守ろう
津波避難タワーは高台への避難が困難な地域において、従業員の命を守る手段として活用できます。近い場所に津波避難タワーや津波避難ビルがあれば比較的短い時間で避難できるため、迅速な行動も可能となるでしょう。
ただし、津波避難タワーは維持管理にコストがかかることや、2度逃げしにくいといった問題点があり、これらを考慮した上での活用が求められます。
津波発生時の安否確認には、トヨクモの『安否確認サービス2』を活用してください。自動で安否確認ができるほか、BCPに必須機能も搭載されているため、今後の事業継続にも活かせます。
初期費用不要で30日間のトライアル期間を設けており、自社に合ったシステムかどうかを確かめられるので、ぜひ無料体験からお試しください。