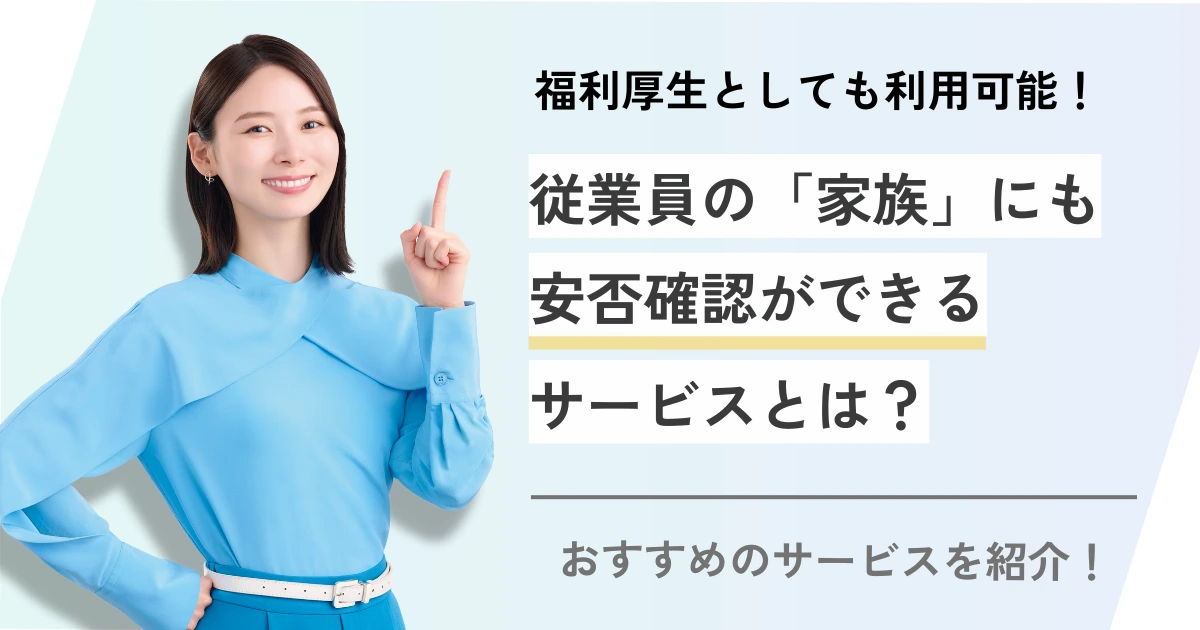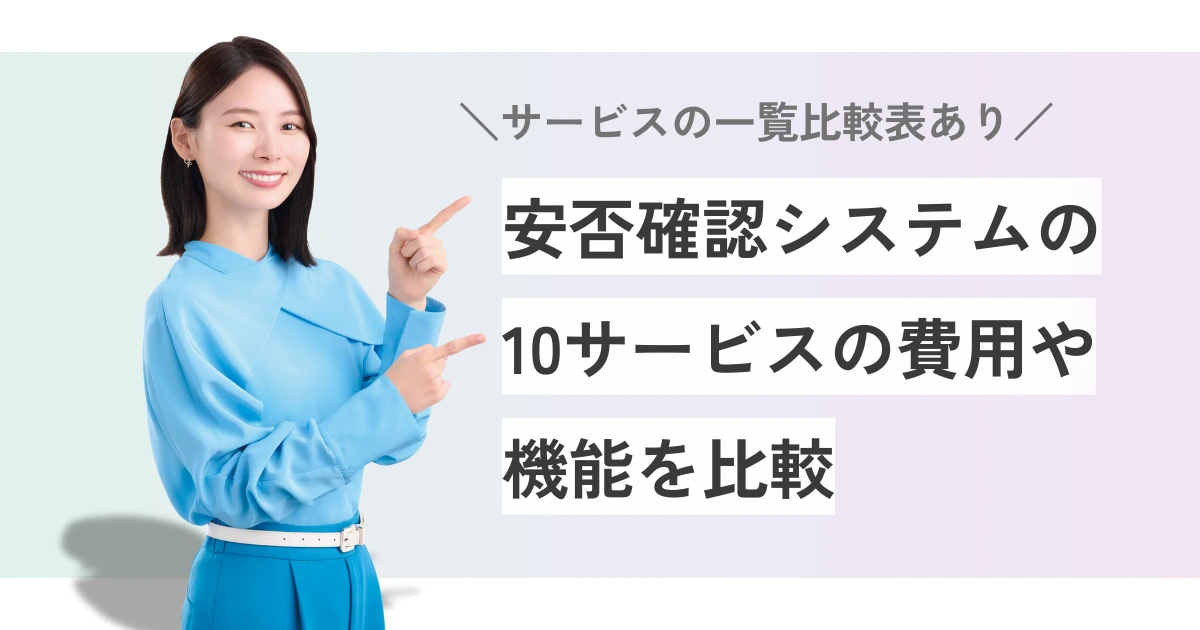BCP対策を強化する通信手段6選!安否確認システムを導入すべき理由も紹介

トヨクモ防災タイムズ編集部
BCP対策の強化には、緊急時の通信手段を複数確保しておくことが重要です。インフラの被害状況によっては、電話やメールが使えないケースも十分考えられます。
この記事では、BCP対策の強化につながるおすすめの通信手段を中心に紹介します。BCPの見直しやリスクマネジメントの強化に取り組んでいる企業は、最後までご覧ください。

目次
BCP対策を強化する緊急時の連絡手段6選
緊急時の連絡手段として有効なツールを6つ紹介します。
- IP電話
- SNS
- IP無線機
- 衛星電話
- 災害用伝言サービス
- 安否確認システム
個々の特徴やメリットに関して紹介します。
IP電話
IP電話とはインターネット回線を利用して音声通話ができるサービスです。スマートフォンやPC、タブレットを利用して相手と通話をします。
専用アプリを提供しているサービスの場合、文章や画像、動画を交えたコミュニケーションが交わせるため、被災状況や避難場所の様子を詳細に伝えられます。
また、IP電話はインターネット回線を利用するため、電話回線と異なり基本的に配線工事は必要ありません。通話料も相手との距離を問わず一定の場合が多く、毎月の通信代も抑えられます。
一方、インターネット環境が整っていない場所では、相手と通話できません。アクセス地点によっては、速度遅延や通信障害が起きる可能性もあります。
SNS
LINEやXなどのSNSは、日常生活で利用している方も多く、緊急時も操作に戸惑う心配が少ない点がメリットです。
とくに、LINEは業務の連絡事項や進捗状況の共有など、従業員との普段の連絡手段に使用している企業も増えています。緊急事態が起きた際もグループトークを活用すると、グループに加入している従業員の安否を素早く確認できます。
一方、Xはリアルタイムの情報を集められる点がメリットです。ただし、すべての投稿が正確な情報とは限りません。災害情報の収集には有効ですが、誤情報やデマも拡散されやすいため、必ず複数の情報源や自治体・政府の公式発信と照らし合わせて確認しましょう。
また、どのSNSを利用する場合でも、従業員数が多いほど従業員の安否確認に手間がかかります。安否確認メールの送信や回答結果の集計、未回答者への再送信などは、管理者が主導で作業を行わなければなりません。
さらに、従業員の個人情報や顧客情報を漏らさないよう、利用する際は細心の注意が必要です。機密性の高い情報(社員証、顧客名簿、医療情報など)は、撮影・送信しないようにしましょう。
IP無線機
IP無線機とはインターネット回線を使って、音声や通信データのやりとりを交わす無線機です。通常の無線機に比べて通信範囲は広く、電波の届くエリアであれば比較的通信状態は安定しています。
IP無線機はIPアドレスに直接音声データを送信しており、電波や障害物の影響を受けにくい点が特徴です。通信品質を高水準に保てるだけでなく、停電時でも相手とやりとりを交わせます。
また、1台のIP無線機で複数人と通信できるため、従業員の安否確認や被災状況を素早く確認できます。ボタンを押すだけで操作ができるため、使い方に戸惑う心配も少ないでしょう。
災害時にも強く広範囲に通信が届くため、緊急時の通信手段としておすすめのツールです。
衛星電話
衛星電話は、地球上の基地局を経由せず、通信衛星を介して直接通話やデータ通信を行う仕組みです。
衛星が無線電波を通信用の人工衛星に向けて発し、地上局を経由してスマートフォンや衛星電話専用のデバイスとやり取りを交わします。サービスによっては地上局を経由せず、スマートフォンや衛星電話専用のデバイスと直接通信を交わします。
衛星電話は場所を問わず相手と通話できる点がメリットです。世界のあらゆる地域をカバーしており、山間地や離島、海上など、電波が届きにくい場所でも利用できます。また、衛星が宇宙空間に存在しているため、大規模な自然災害が起きても影響を受けません。
通信には若干の遅延が発生するため、通常の電話と比べるとリアルタイム性は劣る場合があります。他の通信手段と比べて通信料も高いため、導入できる企業は限定されるでしょう。
災害用伝言サービス
災害用伝言サービスとはNTT東日本・西日本が提供する伝言サービスです。災害用伝言サービスは電話を利用する「災害用伝言ダイヤル(171)」、インターネット上の掲示板を利用する「災害用伝言板(web171)」の2種類に分けられます。
災害用伝言ダイヤルはNTTへの加入電話や公衆電話などを利用し、家族や友人に向けての伝言を残せるサービスです。以下の手順に沿って伝言を残します。
- 171に発信する
- ガイダンスが流れる
- ダイヤル「1」を押して伝言を録音する
- ガイダンスが流れる
- 市外局番から電話番号を入力する
伝言を聞く際は発信者と同様に171に発信し、ダイヤル「2」を押したあと、電話番号を入力すると、伝言が再生されます。
一方、災害用伝言板はスマートフォンやノートPCなどを利用して、インターネット上に設置された掲示板に伝言を残すサービスです。サイトにアクセスしたあと、市外局番から電話番号を入力し、操作画面の表示にしたがって伝言を残します。
内容を閲覧する際も伝言を残す際と同様、サイトにアクセスしたあとに電話番号を入力します。どちらのサービスも登録できる伝言の数は20件までです。災害用伝言ダイヤルは1つの伝言で30秒以内、災害用伝言板は100文字以内にまとめる必要があります。
また、どちらのサービスも安否確認メールの送信や回答結果の集計など、安否確認を効率化する機能は実装されていません。従業員との相互コミュニケーションが難しいため、他の連絡手段と併用するのが望ましいでしょう。
緊急時の連絡手段や連絡手段を確保すべき理由などに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
災害時の緊急連絡手段5つ|連絡先や利用条件を分かりやすく解説
安否確認システム
安否確認システムとは自然災害や感染症の発生など、緊急時に従業員と素早く連絡が取れるシステムです。専用アプリやメールなど、複数の連絡手段に対応しているシステムが多く、システムによってはLINEとの連携にも対応しています。
多くのシステムが気象庁と連携しており、一定規模以上の災害が起きた際は、災害情報と一緒に安否確認メールが自動で送信されます。従業員からの安否回答はシステムが自動で集計するため、管理者が確認をする必要はありません。
また、ネットワーク環境の冗長化やデータセンターの分散化など、多くのシステムが大規模自然災害への対策を強化しています。一部のシステムは災害対策として、海外にサーバーを設置しています。
海外でサーバーを設置・運用しているシステムを選ぶと、国内で災害が起きても影響を最小限に抑えられるでしょう。
上記の理由から安否確認システムの導入によって、緊急時の通信手段確保やBCP対策の強化につなげられます。
安否確認システムの導入メリットや必要性などに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。以下の記事もあわせてご活用ください。
安否確認システムの必要性とは?導入メリット・失敗しないための選定のポイントを紹介!
BCP対策強化の通信手段に安否確認システムが最適な5つの理由
緊急時の連絡手段に安否確認システムを推奨する理由には、以下5つの内容があげられます。
- 大規模災害時もインターネット回線は機能しやすい
- 緊急時でも従業員とのやり取りが望める
- 災害情報を取得できる
- 事業復旧に向けた動きに素早く移れる
- 管理者の負担を減らせる
インターネット回線は電話回線と比べて、大規模災害の際も比較的機能しやすいです。また、安否確認システムは複数の連絡手段に対応している点、安定稼働が望める点などが、強みになります。
大規模災害時もインターネット回線は機能しやすい
大規模な地震や津波などが発生した際も、インターネット回線は電話回線と比べて機能しやすいです。東日本大震災の際も被害が極端に大きかった地域を除き、インターネット回線は機能していました。
当時はXやLINEを使って災害情報や避難の呼びかけなど、情報発信が活発に行われていました。また、予備電源の配置や大ゾーン基地局の整備など、停電時の対策も進められています。
大ゾーン基地局とは人口が多い地域を対象に、通常よりも広範囲の地域で電波の送受信を行う基地局です。全国的な大ゾーン基地局の整備が進むと、停電時も安定した通信のやりとりが交わせます。
さらに、「00000JAPAN」の提供によって、大規模災害の発生時に契約の有無を問わずインターネット回線にアクセスできます。
00000JAPANとは、大規模災害時に通信事業者が提供する無料の公衆Wi-Fiサービスで、認証不要で誰でもインターネットに接続できるようにする取り組みです。
緊急時でも従業員と連絡が取りやすくなる
安否確認システムの導入によって、緊急事態が起きた際の従業員との連絡手段を確保できます。専用アプリやSNS、SMSなど、複数の連絡手段に対応したシステムが多く、従業員の安否を素早く確認できます。
緊急時の連絡手段が電話やメールのみの場合、従業員の安否確認に多くの時間が必要です。通常よりも多くのトラフィック量が生じるため、相手と連絡が取りにくくなるためです。
実際、東日本大震災の際、通常と比べて50~60倍のトラフィック量が発生していました。
auやドコモ、ソフトバンクの音声通信は、70~95%制限されており、ほとんどつながらない状態です。
また、メールは電話よりはつながりやすかったものの、サーバーの能力を大幅に超えるアクセスが集中し、通信障害や速度遅延が発生していました。
安否確認システムを提供するベンダーの多くは、データセンターやサーバーの分散化など、大規模災害時でもサービスを継続できる体制を構築しています。
災害情報を取得できる
気象庁と連携した安否確認システムを導入すると、以下の災害情報を取得できます。
- 地震情報
- 津波情報
- 気象庁の警報(特別警報)と注意報
- 記録的短時間大雨情報
- 土砂災害警戒情報
- 指定河川洪水予報
災害情報は一定規模以上の災害が起きると、安否確認のメールが従業員の連絡先に自動で送信される仕組みです。管理者が毎回対応する必要はありません。
災害情報の取得によって、従業員へ安全確保と避難を素早く促せます。
事業復旧に向けた動きに素早く移れる
安否確認システムによっては、掲示板機能を利用できます。
掲示板を実装しているシステムを導入すると、策定したBCPマニュアルや今後の流れに関して、掲示板に掲載できます。
掲示板ではコメントの掲載に加え、画像や動画も添付できるため、管理者は従業員の避難場所や被害状況に関して正確に把握できるでしょう。
また、安否確認の際に従業員から出社可否や避難状況に関して回答してもらうと、事業復旧に向けたスケジュールを立てやすくなります。
管理者の負担を減らせる
安否確認システムの導入によって、安否確認で生じる管理者への負担を減らせます。
BCP策定の際に決めた管理者が、必ずしも毎回対応できる保証はありません。災害の規模や被害状況によっては、管理者が対応できないケースもあるでしょう。
安否確認システムを導入すると、安否確認メールの配信や回答結果の集計はシステムに任せられるため、管理者への過度な負担の集中を避けられます。
また、安否確認のメールに出社可否や避難場所に関する設問を加えておくと、現在の被害状況を正確に確認でき、やりとりの手間が省けます。
安否確認システムの料金やおすすめのシステムなどに関しては、以下の記事をご覧ください。
安否確認システムの料金相場は?無料で使えるシステムの注意点も紹介
安否確認サービス2を導入してBCP対策での通信手段を確保
緊急時の通信手段に安否確認システムを検討している場合、『安否確認サービス2』を選ぶのがおすすめです。『安否確認サービス2』は、トヨクモ株式会社が提供する安否確認システムです。緊急時にはメールや専用アプリ、LINEで従業員の安否を確認できます。
「緊急時も安定稼働が望める安否確認システム」としての評価が高く、リピート率は99.8%を誇り、導入実績も4,000社を突破しました。
『安否確認サービス2』はすべての契約企業を対象に、全国一斉訓練を毎年防災の日に実施しています。全国一斉訓練とは、災害時と同等の負荷を『安否確認サービス2』に与え、システムが正常に稼働するか、確認するための訓練です。
訓練結果が、トヨクモの採用しているサービス品質保証制度(SLA)の基準を下回ったことはありません。はじめて安否確認システムを導入する方も、安心して利用できるでしょう。
また、掲示板やメッセージ機能を実装しており、事業復旧に向けての指示や情報共有をスムーズに進められます。
BCP対策の強化や緊急時の通信手段確保に取り組んでいる方は、『安否確認サービス2』の導入をご検討ください。
緊急時の通信手段を確保してBCP対策を強化しよう!
緊急時は通常よりも大幅にアクセスが増えるため、電話やメールで相手と連絡が取れない可能性が高まります。従業員の安否確認を素早くおこなうには、安否確認システムの導入がおすすめです。
安否確認システムは複数の連絡手段に対応可能なシステムが多く、緊急時の連絡手段を高確率で確保できます。トヨクモの提供する『安否確認サービス2』は、大規模災害の際も安定稼働が望める安否確認システムです。
自然災害が少なく、安定した電力供給が望めるシンガポールでサーバーを運用しています。日本で大規模地震や津波が発生しても、ダメージを受けません。また、気象庁が災害を検知した段階でサーバーを拡張するため、急激なアクセス増加にも対応できます。
さらに、『安否確認サービス2』は中小企業が利用しやすいよう、月額料金が比較的リーズナブルな設定です。初期費用や最低利用期間は発生しません。
安否確認システムをお探しの方は、『安否確認サービス2』の導入をご検討ください。
BCP対策の通信手段に関するよくある質問
ユーザーから寄せられた以下に関する質問をQ&A形式でまとめました。
BCP対策とは?
BCP(Business Continuity Plan)とは、日本語で「事業継続計画」と訳されます。事業継続計画とは自然災害や感染症の発生など、緊急事態が起きた際に被害を最小限に抑え、最短での事業復旧を実現するための計画です。
BCP対策には災害発生時の避難経路や安否確認の手段、衛生用品の確保など、さまざまな内容を記載します。あらゆるリスクに備えておく手段として、BCPの策定は欠かせません。
2024年には介護サービスを提供するすべての事業者に対して、BCP対策の策定が義務付けられました。
災害時にスマートフォン以外で連絡が取れる通信手段は?
IP無線機です。携帯電話の電波が届く地域に相手がいれば、怪我の有無や避難場所などを確認できます。IP無線機は相手の無線機に直接音声データを送信するため、電波や障害物の影響を受けにくい点も魅力です。
また、インターネット回線を利用するため、停電した際も相手とやりとりを交わせます。操作性にも優れており、緊急時の通信手段として用意しておく価値はあるでしょう。